【2次試験】あと19日で何をやる?直前期のオススメ勉強法7選 by まよ
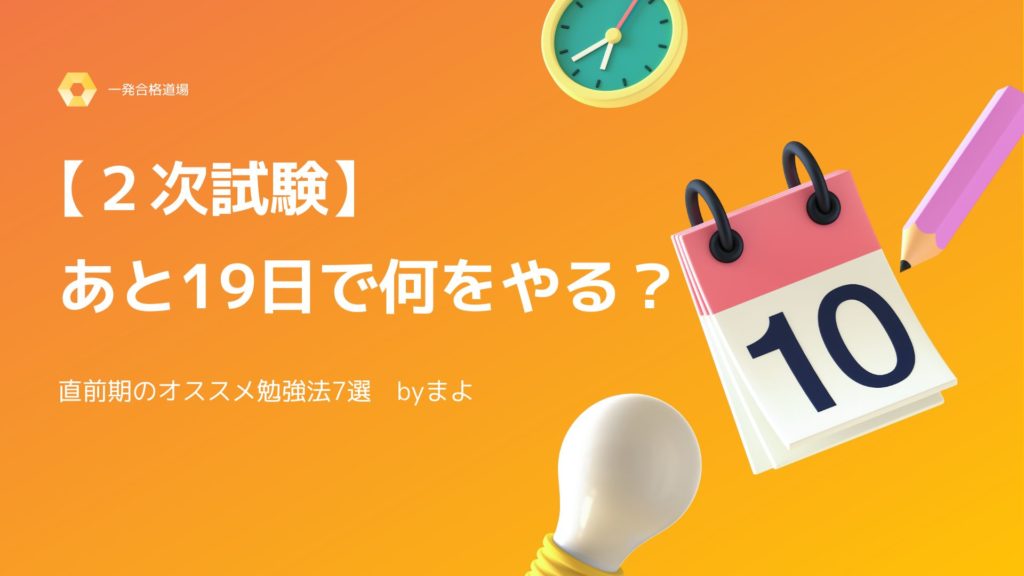
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

こんにちは!まよです☆
いよいよ2次試験まであと3週間を切りました!
本日は、試験本番までの残り時間でやるべきオススメ勉強法をお伝えします。
ご自身の弱点克服に向けて取り入れてみてください!
はじめに
本日は、2次試験が迫るなか「合格なんてできそうになくてヤバいけど、何をやっていいかいいか分からない!」
そんな受験生に向けた記事です。
大丈夫です!あと19日もあります。
試験当日まで実力は伸び続けますので、諦めずに頑張りましょう!
かと言って残り時間のなかで、あれもこれも手を出すのは現実的ではありません。
合格ライン到達するためには自分に『何が欠けているか』今一度見つめ直してみてください。
そして、その欠けている部分に絞って重点的に対策を行いましょう。
本記事では、私がやっていた勉強法のうち、残り19日間のなかで効果が発揮できる〝即効性のあると思われる勉強法〟を「受験生全員にやって欲しいこと」と「必要に応じてやって欲しいこと」に分け、計7つ挙げています。
ご自身に必要だと思われるものを選択し、日々の勉強に取り入れていただければと思います。
★必須★ 受験生全員やるべし!!
まずは、今年度2次試験を受験する全ての受験生にやって欲しいこと3選をお伝えします!
その1:セルフ模試を行う
道場界隈では、本番と同じ時間割(9:40~17:20)で初見問題を事例Ⅰ~Ⅳ通しで解くことを『セルフ模試』と言っています。
私は2次試験を2回受験している多年度生ですが、1回目に受験した時の反省点(過去記事参照)からこの『セルフ模試』の実施を強くオススメします。
セルフ模試を行う目的
- 持久力の強化
これまでの自身で行ってきた事例演習とは異なり、試験本番は朝から事例Ⅰ~Ⅳを通して解くことになります。これが想像以上に疲れます。強く意識をしておかなければお昼を跨いだ事例Ⅲぐらいから、集中力が途切れてきます。
セルフ模試を通して事例Ⅳの最後の最後まで全力でやり切れるよう慣れておく&集中力を保つ対策を考えておきましょう。
- メンタルの強化
散々過去問をやり込んできても、試験当日は緊張のせいで思い通りに解けなかったりします。さらに、これまでと問われ方が少し変わると「あれ?傾向が変わった?!」とパニックに陥ったりもします。
セルフ模試を通して「傾向・問われ方が変わっても、いつも通り解けるメンタル」を鍛えておきましょう。
- タイムスケジュールを体で覚える
集中力が切れてくると試験終了時刻を間違えるという初歩的なミスを起こしがちです。2次試験を始めて受験した時の私がそうでした。
セルフ模試を通して、試験本番のタイムスケジュール(9:40~17:20)と80分間という時間感覚を体に叩き込みましょう。また、休憩時間はトイレに行く・軽食をとる・ファイナルペーパーを見るなど、なるべく試験当日と同じ行動を取るようにし、本番に近い状態を体験しておきましょう。事例Ⅰが終わった後は事例Ⅱ、事例Ⅱが終わった後は事例Ⅲと、頭を切り替える訓練にもなります。
セルフ模試をやって本番に挑むのと、やらないで挑むのでは心構えに雲泥の差が出ると思います。
試験前1カ月の土日は全てセルフ模試をやってたで♪
試験前1か月!本番を想定した過ごし方 by あらきち
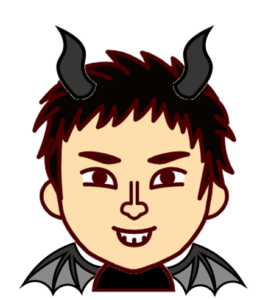
あらきちと同じく、私も試験前1カ月前から休日はほぼ全てセルフ模試に時間を費やしました。
セルフ模試のやり方は人それぞれだと思いますが、以下の2点は守った方が効果的です。
- 本番と同じ時間割(9:40~17:20)で解くこと
- 初見問題(あるいは、1度解いてから時間が経っている事例)を解くこと
(よりストイックにやりたい場合は、本番同様に狭い机で行ったり、わざわざ雑音がある場所で行ったり、マスクを着用してセルフ模試に挑んではいかがでしょうか。私はそこまでやりませんでしたが・・・)
ストレート生の方はなかなか時間を割くことが難しいかもしれませんが、最低1回、出来れば3~4回程度セルフ模試で本番のシミュレーションを行っておきましょう。
その2:毎日事例Ⅳを解く
事例Ⅳは、やればやった分だけ点数が上がりやすいコスパの良い事例と言われています。
一方で詰めが甘いと想定外の足切りにあう怖い事例でもあります。(私![]() もあらきち
もあらきち![]() も、事例Ⅳ足切り経験者です・・・)
も、事例Ⅳ足切り経験者です・・・)
記憶は薄れるものです。
事例Ⅳに苦手意識のある方はもちろんのこと、既に事例Ⅳ対策が完ぺきと思っている方も、試験本番まで毎日1問でも事例Ⅳに取り組むことをオススメします。
特に、3大頻出論点(経営分析・CVP・NPV)は重点的に対策を行いましょう!
その3:ファイナルペーパーの作成
ファイナルペーパーなんて作ってる時間ないしぃ~と思いがちですが、自身の頭の整理のためにも早いうちに作成しておきましょう。
先代のものをベースにパクッてカスタマイズして、時間を節約するのも手です。(13代目メンバーも半数はパクッてカスタマイズ派でした!)
本番に向け、どんどん自分用にアップデートさせていきましょう。
パクるべし。先代のファイナルペーパーはこちらから。(ページ下部のまとめにリンクあり)
ファイナルペーパーの作り方はhotman![]() のこちらを参考に。
のこちらを参考に。
俺のファイナルペーパーも使ってイイゼ☆
【2次試験】私のファイナルペーパー by どらごん

必要に応じてやるべし!!
以下に挙げる4つの勉強法は、ご自身の状況に合わせて、必要に応じて取り入れてください!
その4:解答プロセスの再確認
こんな人はやるべし!!
- 80分で解ききれないことがある
- 解答の再現性が低い( ≒ 解答プロセスが安定していない)
ご自身の解答プロセスは定まりましたか?
いつでも同じ解法で、同じような解答を作成することができますか?
2次試験において、『自分なりの解答プロセスを確立』は最も重要なことの1つだと思います。
不安がある方は、解答プロセスの見直し・定着を集中的に行いましょう。
現時点で80分で解ききれていない方は、今一度「無駄なプロセスはないか」振り返ってみてください。
例えば私の場合、80分内に抑えるため以下のようにプロセスを見直しました。
- 与件文に段落番号を振らない
- 問題用紙は破らない
- 解答骨子の精度を粗くする(解答用紙に書き込む方に時間を割く)
- 解答に使用するキーワードのみにマーカーをひく
遅くとも試験本番の2週間前を目安に、解答プロセスの最終的な見直しを済ませておく方がよいでしょう。
80分の解答プロセスを決めたら、事例問題で定着を図ります。
一度解いたことのある事例は早く解けてしまうことが多いので、解答プロセスの再確認は初見の事例で行うことをオススメします。
必要であれば新規の事例を入手しましょう。
![]() 過去問を使い果たしてしまった方へ
過去問を使い果たしてしまった方へ
過去問は全部手を付けていて初見の事例なんて無い!という方は、予備校で演習問題を販売していますのでご活用ください。
(TACの演習問題の販売ページはこちら)
ただ、予備校の演習問題は本試験と若干クセが異なりますので、あくまで解答プロセスの確認までに留め、過去問と同レベルの答え合わせや復習は省いて良いとか思います。
その5:設問解釈トレーニング
こんな人はやるべし!!
- 与件文を読むのに時間がかかる
- 与件文と設問の紐づけに時間がかかる
- 制約条件を外すミスをよく起こす
- 解答が文章として分かりづらい
設問解釈トレーニングは、80分の全体プロセスのなかで「設問解釈」のみを単体でトレーニングすることを言います。
与件文から効率よくキーワードを拾えず、与件文と設問文を何度も行き来で時間を食ってしまったり、聞かれたことに答えていないといったミスを起こしがちな方は、設問解釈が甘い可能性があります。
対策として、設問解釈トレーニングを行いましょう。
特に、解答がパターン化されている事例ⅠとⅢにおいて有効です。
トレーニングの方法は、さろ![]() のこちらの記事を参考に。
のこちらの記事を参考に。
レイヤーの考え方を取り入れた、まん![]() の記事も参考になります。
の記事も参考になります。
設問解釈はやればやった分だけ身になります。
スキマ時間に立ちながらでも、設問文さえ見ることができる状況であれば10分で1事例分の設問解釈を行うことができます。
なので、毎日少しずつでも是非取り入れて欲しいです。
設問解釈を行う際に「解答の方向性を連想できていない」場合は、次にあげる『1次知識の復習』と併せて取り組みましょう。
「文章が分かりづらい」と感じている方は解答の型を作成するところまでセットでトレーニングを行いましょう。
その6:1次知識の復習
こんな人はやるべし!!
- 多面的な解答を書けない
- 解答に一貫性がない(因果で書けていない)
- フレームワークを使いこなせない
2次試験では、1次試験で学習した知識を使わないと解けない設問が一定数存在しています。
あやふやなままでも1次試験は選択式だからどうにかなってきたものも、2次試験ではそうはいきません。
例えば、設問解釈で「機能別組織」というワードがでてきたら、すぐに機能別組織のメリット・デメリットが思い浮かぶレベルになっておく必要があります。
知識が不足したままだと、解答の要素が不足していたり、因果が成立せずハチャメチャな文章になっていたりします。
1次知識が十分でないと感じている方は、まずはこちらの記事をご確認ください。
2次試験で使う1次知識は大体決まっており、そんな多くはありません。〝最低限〟の知識を網羅できる有難い記事です。
さらに必要に応じて予備校のテキスト等で1次知識の総復習を行い、すぐに引き出せるレベルに知識を定着させておきましょう。
その7:事例のヨコ解き
こんな人はやるべし!!
- 事例Ⅰ~Ⅲのうち、特定の事例に苦手意識がある
- 各事例ごとの違い(セオリーなど)を意識できていない
- これまで事例ごとのヨコ解きをやったことがない
ヨコ解きとは事例別(論点別)に年度をまたいで、事例問題を解くことをいいます。
事例1/事例Ⅱ/事例Ⅲの何れかに苦手意識のある方は、直近の過去問3~5年分を出来るだけ短期間でヨコ解きしてみることをオススメします。
ヨコ解きしてみると、その事例特有の傾向やが浮かんで見えてくるようになります。
どの事例も問われている本質的なところは、毎年大きく変わりません。(なんとも抽象的な表現ですみません)
詳しくは、こちらのりいあ![]() の記事や
の記事や
こちらの私![]() の記事を参考にしてください。
の記事を参考にしてください。
事例ごとのセオリーや特徴を抑えておくと、グッと解きやすく感じるはずです。
さいごに
< 本日のまとめ >
■★必須★ 受験生全員やるべし!!
■必要に応じてやるべし!!
いかがだったでしょうか。
目新しい勉強法はなかったかもしれませんが、どれも直前期において効果を発揮する勉強法かと思います。
泣いても笑ってもあと19日。
自分の弱点を見つめ直し、徹底的に潰しましょう!!
そして、寒暖差の激しい日々が続いていますが、
まずは『会場に試験を受けに行けること』が最重要事項です!!
体調第一で過ごしつつ、ラストスパートをかけていきましょう!!
最後に少しだけ告知させてください。
≪ 開催決定!!≫
事例Ⅴ ーオンラインお疲れ様会ー
2次試験が終わった後は、これまで共に頑張ってきた仲間同士「お疲れ様」を言い合いませんか?
- 日時:11月5日(土)21時〜
- 参加要件:2022年度2次試験の受験生
- 募集期間:未定(後日ブログにてお知らせします)
まずは二次試験に向けて全力投球で頑張りましょう。
終わった後は共に飲み明かしましょう。
みなさんとお酒を飲めること、道場一同楽しみにしております!!

本日はここまで☆

明日はさろです!お楽しみに~
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)



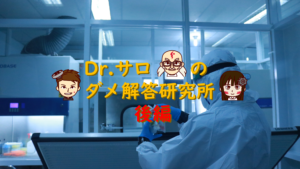
まよさん
毎日スキマ時間などに読ませていただいてます。ありがとうございます。
今回の記事、特に設問解釈がありがたかったです!過去問を解くことに集中していましたがいまいち成果が出ていなかったので、一度設問解釈を、強化して改めてラストスパートしたいと思います。
しのさん
コメントありがとうございます!
設問解釈についてはさろ、まん、あらきちが記事を書いています。
人によって色々とやり方がありますので、是非ご自身に合うと思われるものとパクッてカスタマイズしてみてくださいね!
試験までの残り14日間スキマ時間に取り入れるだけでも、だいぶ効果があると思います。
いよいよラストスパートですね。
今が一番苦しい時がと思いますが、頑張りましょう!!応援しています!!
いつも読ませていただいております。
貴重な情報ありがとうございます。
私は今回が4回目の受験となります。 これまでの1.2.3回目の受験は散々な結果でしたが、ここにきて、合格者の答練と似たポイントを回答に選択できるようになってきて、MMCの模試でも合格点を取れるようになってきました。
まだ合格もしてないのに喜んではいけませんが、ようやくここまでこれたのかとうれしく思っています。これまで、とても恥ずかしくて言えないほど、この4年間で何度も何度も過去問を解いてきました。
なんて書いてよいかわからないし、頭をフル回転させようとしても頭に知識がなかったから何も浮かばないし、設問を読み解けないし、与件文がとても長く感じ、読むのがしんどいし、何書いてあるかわからないし、、、、、過去問を解くことが、とても苦しく感じていましたが、ずいぶんと楽になってきています。
そんな現状ですが、「一発道場の過去の高得点答案から読み解く事例の本質」https://rmc-oden.com/blog/archives/143906 を、一つ一つ丁寧に自分の解答と見比べ、改善点や自分の頭にない知識の補填などの確認作業を、しているところですが、ここに書かれてある合格者数人の高得点答案を見れば見るほど、「合格者の解答も、書かれてあることに開きがあるんだな。」ということを感じています。
と考えれば考えるほど、自分の解答は、合格点に達しているのか!合っているのか!と混乱してきます。
じゃあどうすれば、自分の解答が60点を超えているかを認識できるのか、毎回誰かが採点してくれればいいのにな、、、、とか、模範解答には含まれてないけど、この自分の解答も間違っていないはずなのにな、、、、とかです。
結局のところ、設問に対して、制約のある中で、ある程度のストラークゾーンに入れて、採点者が読めるようにわかりやすく、且つ、多面的にかくことができれば、60点は取れているんだろうな、、、、、、と感じていますが、どうなんでしょうかね。
ぺっぺさん
コメントありがとうございます!
>自分の解答は、合格点に達しているのか!合っているのか!と混乱してきます。
悩むお気持ち、とてもよく分かります。正解がない試験ゆえ、多くの受験生がこの悩みに直面していると思います。私も漏れなく悩む受験生の内の一人でした。
>結局のところ、設問に対して、制約のある中で、ある程度のストラークゾーンに入れて、採点者が読めるようにわかりやすく、且つ、多面的にかくことができれば、60点は取れているんだろうな、、、、、、と感じていますが、どうなんでしょうかね。
私もぺっぺさんと同じような考えです。
ぺっぺさんのおっしゃる通り、模範解答でなくとも点は入ります。予備校の模範解答は『参考程度』に見ておいてよいと思います。
極端なこと言ってしまえば、ストライクゾーンに入れずとも、全ての設問において大事故を起こさず(題意を大きく外さず)、一貫性のある文章が書けていればクリアできるているのではないかと。
・中小企業への助言として大きく逸脱したこと(例えば、多額の投資をするとか、大手と競合して価格競争するとか)を書かない
・筋が通っていていて分かり易い文章である
・制約条件を外さない(≒事故を起こさない)
・ある程度解答用紙を埋める
概ねこのあたりができていれば、合格ライン(上位18%)なのではないかと私は考えます。※あくまで私個人の考えです。
当たり前のことの羅列のようですが、試験当日って独特の緊張感故にこれまでできていたことができなくなってしまうんですよね・・・
(不合格だった年の私もそうでした)
ぺっぺさんは既に手応えを感じてらっしゃるようですので、あとはとにかく本番で100%のパフォーマンスを発揮できるように!事故を起こさないように!意識されてみてはいかがでしょうか。
(なんか、偉そうなアドバイスで申し訳ないです・・・)
今年4回目の受験ということで、これまで辛く大変な思いをされてきたかとお察しします。
それでも前向きに取り組まれている姿勢に感服いたします。
ぺっぺさんが今年合格されるよう心よりお祈りしております!!!