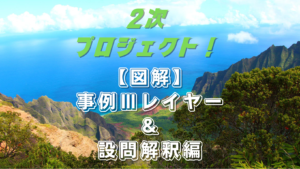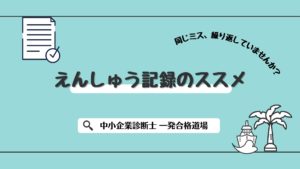【70点超】事例ごとの特徴【後編】事例Ⅲ byりいあ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はじめに

こんにちは。りいあです。
今回は、前回に引き続き、事例の特徴についてお伝えします。
なお、私の体験談からいうと、2次試験で50~60点得点するためには事例Ⅰ~Ⅲに共通する部分を磨けば足りました。
しかし、それ以上の点数をとるためには、事例ごとの傾向の違いを知り各事例の核心をついた解答を書く必要があると感じました。
というわけで、本日の後編では事例Ⅲの特徴についてお伝えします。
あれ事例Ⅳどこいった…?


今日は、事例Ⅲ一筋でいきましょう!
事例Ⅲ
事例Ⅲは、製造業の方以外は比較的とっつきにくく馴染みのない内容だと思います。
しかし、時間をかけて解き方を身につければ、事例Ⅰに次いで安定的な得点源にできます。
私は最初のころ事例Ⅲを最も苦手としていましたが、事例Ⅲに時間をかけて勉強していくうち、最終的には事例Ⅰに次ぐ得意科目となりました。
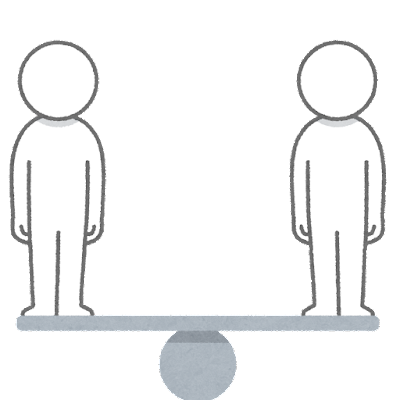
事例Ⅲの心がけ
そんな事例Ⅲを解くときに認識しておくべき怖~いことはこちら、
- 午後の眠気・つかれ
- 作業ボリューム大で時間切れ
- 与件文の問題点整理難航
診断士2次試験当日は、すごく疲れます。
きっと皆さん朝から緊張状態にあり、午前中は事例Ⅰと事例Ⅱを必死で解くことになります。
前日うまく寝付けなかった人もいると思います。
昼食後は疲れと眠気から頭が回らなくなることがあります。
そんな午後、まず試練として現れるのが、事例Ⅲです。
事例Ⅲは、事例Ⅰ・事例Ⅱと比べてボリュームが大きいことが多いです。
単に与件文が長いというわけではありません。
与件文に散らばった問題点が多く、階層や相互の関係性も複雑で、整理するのが難しいのです。
また、場合によっては資料読取が必要な年度もあります。加えて、解答指定文字数が多くなりがちです。
こういったボリュームの大きさから、時間切れになるリスクがとても高いです。
なので、事例Ⅲの心がけとしては
- 時間注意!!できるものからサクサク解いていく!
- 与件文の整理がメイン⇒設問解釈等に時間かけ過ぎない
この二つが重要です。
特に、与件文の整理がメインの科目と心得るべきです。
情報整理のための切り口(QCD、4M、DRINK、計画と統制、など)を複数持っておきましょう。
そして他の事例と比べて相対的に、設問解釈よりも与件文の整理に時間をかけるほうがおススメです。
事例Ⅲの特徴
さて、今回の本題です。ここから、私が気を付けていた事例Ⅲの特徴をあげていきます。
- 事例Ⅲのテーマは『生産性向上』&『損益改善』
事例Ⅲは「生産管理」に関する問題なので、問われることも生産面についてのみかと思いがちです。(私は思っていました。)
しかし、与件文の中には生産面以外にも、営業面や経営面などの多様な問題点も出てきます。
そもそも、「生産管理」は製造業の健全な運営と発展のためにあります。
そして、製造業が成功するために必要となるのは…
まず、限られた人員・設備をうまく使って効率的に生産することです。さらに、作りっぱなしでは利益は出ないので、製造したものを売って売上に変えることが重要です。
こう言った点から、事例Ⅲのテーマは、『生産性向上』と『損益改善』になります。
- 設問のパターン:(設問1)強みの整理、(設問2)(設問3)問題点・課題と対応策、(設問4)今後の戦略
事例Ⅲには、各設問ごとに出題傾向があります。
必ずしも毎回同じではありませんが、この分け方になることが多いです。
- (設問2)(設問3)は『生産現場の改善』がテーマ
『生産性向上』と『損益改善』のために、どこまでの施策を提案して良いでしょうか。
特に(設問2)(設問3)では、オペレーションレベルでの解答を求められることが多いです。
現状の設備等(人・物・情報)の活用をどう実現するか、という内容です。
例として、【作業】面では情報共有、作業の標準化、5S、多能工化、等は頻出です。
【管理】面では平準化、ラインバランシング、一元管理、全体最適などがあります。
- (設問4)は強みを活かし機会を捉える
(設問4)は将来に向けた経営的な視点での戦略を問われることが多いです。
定番の解答は、「①強みを活かし弱みをカバーする+②営業力強化」の構成です。
事例Ⅲでは、いくら製造しても、売らなければ製造業は成功しないという悩みがあります。
なので、一見事例Ⅱのような営業力強化という売るための策も大事になります。
(注意:もちろん与件文ファーストですので、与件文に営業面の問題点が書いてあることが前提です。)
- (設問2)(設問3)“オペレーション”と(設問4)“経営”を混同しない
- 与件文に素直に「できていない」ことを「やってください」と言う!
これは、かの有名なだいまつさんの記事のとおりです。
事例Ⅲではトリッキーな提案は特に不要です。
与件文に散らばった問題点を、正しい切り口で因果関係に沿って整理できたら、あとは「できていない」ことを「やってください」と言えれば、それで正解なのです。
- 与件文・資料読取に時間必要&解答ボリューム大⇒他事例より設問解釈短め
これは個人の好みによりますが、事例Ⅲでは、事例Ⅰ・Ⅱと比べて相対的に与件文の情報整理等のボリュームが大きいため、場合によっては80分間のタイムスケジュールを事例Ⅲ用にアレンジした方がやりやすいかもしれません。
私の場合は、事例Ⅲだけ設問解釈の時間を短くし、与件文の整理や骨子作成に割ける時間を多くとっていました。
- ボトルネックを見極める(優先度の高いものを判断)
事例Ⅲでは与件文に散らばる問題点が多すぎて、全部を盛り込むことは難しい(そしてそんなことしなくていい)時があります。
特に、ふぞろいのキーワード採点を得意としている人は注意が必要です。
問題点どうしの因果関係を整理したうえで、「ボトルネック」=作業能力が一番弱い部分を発見し、優先度の高いものから順に解答要素とする必要があります。
- 中小企業への提案である(費用負担の大きいものは×)
これは他の事例にも言えますが、事例企業は中小企業なので、大きな規模の設備投資など負担の大きいものは適切でない可能性が高いです。
よほどボトルネックになっていない限り、優先度は下げた方が賢明です。
事例Ⅲの世界観を知る
事例Ⅲの世界観に馴染むためには、これしかないです。
コミック版の方が圧倒的にすぐ読み終わるので、試験まであと1か月強の今であれば、コミック版をおススメします。
軽く読めますが、「ザ・ゴール」の理論はきちんと残っているので、大変勉強になります。
おわりに
いかがだったでしょうか。
前回から前編と後編の2回に分けて、事例Ⅰ~事例Ⅲの特徴をそれぞれ特記してみました。
試験直前期に入ろうかという今の時期の皆さんであれば、既に知っていることばかりだったかもしれません。
ただ、昨年度の私はまだ事例ごとの違いを全く把握しておらず、そこが「ボトルネック」になってしまっていました。
「ボトルネック」を抜ければ、ある時急に合格までスーッと伸びる時が来ました。
昨年度の私と同じように困っている受験生の方や、すでに知っているけれど再確認しとこうかな、という受験生の方にとって少しでも役立つと幸いです。
少し肌寒くなってきましたが、体調にはどうか気を付けて、残りの限られた期間を走り抜けてください!
応援しています!

明日はYOSHIHIKOです~
お楽しみに☺
ミスターD☆Bとは俺のことよ☆☆
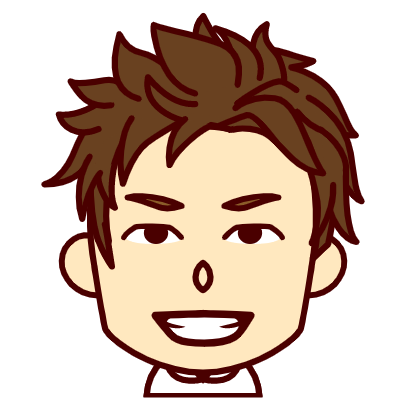
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)