1次試験前からできる2次試験対策【14代目インタビュー】初年度編・多年度編 byみっきー

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
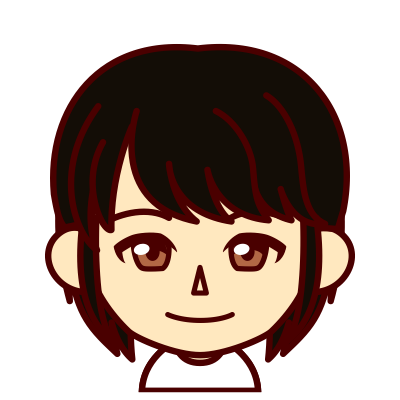
記事を開いて下さり、ありがとうございます!
「やりこみ受験生」を自称している、みっきーです。
(※割り切れないタイプだったので、色んなことをやりこんでいました。)
自己紹介記事はこちら。
新年度がスタートして約2週間となりました。
環境の変化がある方も、特に生活は変わらない方も、
日々試験勉強に励まれている方も、ちょっとお休み中の方も、
皆さま日々お疲れ様です。
私は育休からの復職を控え、息子(1歳)の保育園の「慣らし保育※」期間です。
1歳児クラスは、毎朝、複数人の泣き声の大合唱。これも春の風物詩らしいです🌸
※集団生活をしたことがない子どもたちを保育園に慣らすための期間。1日1~2時間の短時間保育から2週間ぐらいかけて徐々に時間を伸ばし、フルタイム働く時間(1日9~10時間)を保育園で過ごせるようにしてもらいます。

さて、本日はそんな春、1次試験前の2次試験対策についての記事です。
14代目が今月末に開催する春セミナーの申込時、
「今の時期の2次試験対策」ついてのご質問を多数いただきました。
みなさま、2次試験について、下記のようなお悩みはないでしょうか。

1次試験の前から2次試験ってする必要あるのかな?
そんな余裕はないんだけど…
2次試験まではまだ時間があるけど、
何をやっておけばいいんだろう?

今の時期からバリバリ2次試験対策をしている初学者の方も、
今年度の試験に向けての道筋がばっちりみえている多年度の方も居ると思いますが、
上記のような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回はセミナーに先駆けて、
「この時期の2次試験対策」について紹介いたします。
例年のように話題に上がるテーマですが、
今回は2023年度版ということで、
初年度編・多年度編をそれぞれ14代目メンバーにインタビューを行いました。
何かお役に立てる情報があれば嬉しいです。
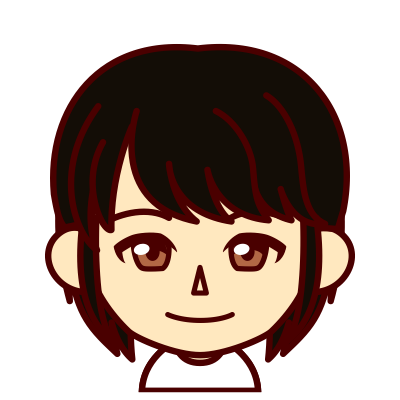
まずは初年度編!
多年度生の方は、こちらをクリックでスキップできます。
初年度の2次試験対策
ストレート生、多年度生、メンバー構成が豊富な14代目。
皆に、勉強開始1年目の春、2次試験対策をしていたかどうか聞いてみました。

初年度の1次試験前から2次対策をしていた14代目は、12人中3人のみ。
大多数のメンバーが、2次試験対策を行っていませんでした。
しかし、

多数のメンバーが、「今の時期からの2次試験対策をおすすめする」という結果になりました。
「今の時期から2次試験対策をしておいた方がいいか」という初年度生の疑問には、
余裕があればぜひ準備しておくのが理想ですというのが答えになります。
とはいえ、実際にどの程度のことを、どのレベルでやればいいのか?
詳しくご紹介していきます。
どんな対策をしていた?
まずは、初年度の1次試験前から2次対策をしていた14代目メンバーに、
どんな取り組みをしていたか聞いてみました。
まずは、ストレート合格組のひろしとはっしー。
2人は、1次試験も高得点で通過しています。
◆ひろし(ストレート合格)
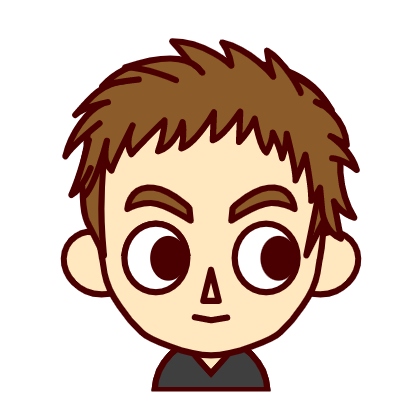
①4月に1年分の過去問を解いた。
②Youtubeで2次試験の情報収集をしてた。
(1度は事例を見てからの情報収集をおすすめ)
2次試験のYoutube活用については、昨日更新のうっかりアッパの記事が参考になります。
◆はっしー(ストレート合格)
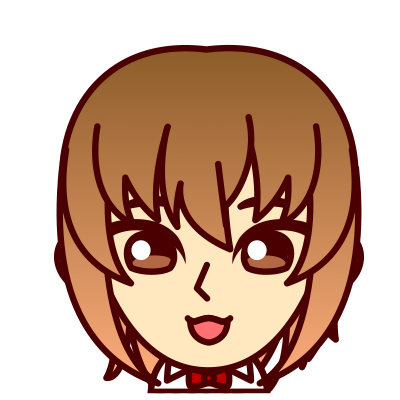
①GWに過去問を1年分解く
②道場で参考書の種類など情報収集
③100字トレーニング
をやっていました。
100字トレーニングとは?
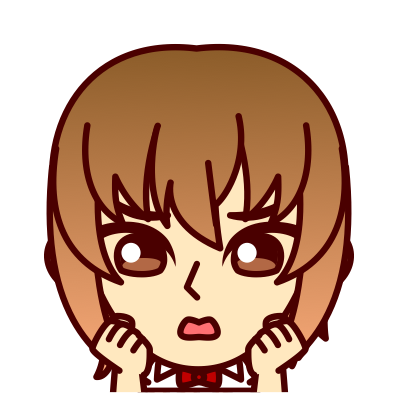
「設問に100文字で答える」という一部予備校等で行われている勉強方法を、
一次対策対策を含めて自己流でアレンジしてやっていました。
具体的には、キーワードを羅列して、
概要とメリット/デメリットを15分以内で100字で方眼ノートに記述していました。
例えば、組織論の場合は「機能別組織」「事業別組織」「マトリクス組織」などのキーワードをピックアップしていました。
1次試験と2次試験、両方の対策ができる勉強法、さすがです。
続いては、計画的1.5年受験のアッパです。
・うっかりアッパ(1次複数回・2次ストレート)
アッパは1年目は2次と関連の薄い科目(経済学、法務、情シス、中小)を受験、
翌年に2次直結科目(企業経営理論、財務会計、運営管理)と2次試験合格を達成しました。
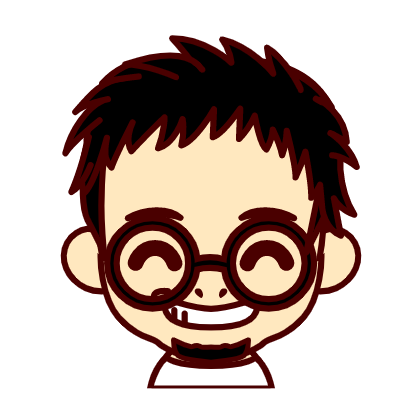
1年目は情報収集だけ。
2年目の1月に合格者が放出するふぞろいを購入。
2月から3週に1度のペースで過去問事例勉強会を開始。
6-8月は基本1次集中で、8月中旬から毎週過去問事例勉強会をしていました。
1次試験前から、2次試験の対策を段階的に進めていたようです。
初年度生に今おすすめする2次試験対策
ここからは、14代目が初学者に「1次試験前にもこれだけはやっておくのがお勧め」な2次試験対策を紹介していきます。
手軽にできるものから、レベル順に並べてみました。
勉強を開始した時期・1次試験対策の進捗によって、
できそうなものがあればぜひ取り入れて下さい。
14代目おすすめの2次試験対策
レベル1:2次試験がどんなものか情報収集する
レベル2:教材だけ揃えておく
レベル3:2次試験でどんな問題がでるか把握しておく
レベル4:2次試験の問題を1度解いてみる
レベル5:事例Ⅳ対策のみはじめておく
レベル1:2次試験がどんなものか情報収集する
もしがっつり時間が取れない方も、
1次試験前から、最低限、2次試験がどんな試験なのかの情報は最低限持っておけると心強いです。
とはいえ、情報収集とはどこまでやっておけばいいのか?何を把握しておく必要があるのか?
判断が難しいですよね。
とりあえずこの記事を読んでおいていただければ大丈夫です!!!
つまり、毎日道場の記事を読んでくださっている読者の方は、既にレベル1クリア済です。
おめでとうございます。
このおのDが書いてくれた記事でのポイントは、1次試験と2次試験の繋がりが分かることです。
2次試験を見据えた1次試験の勉強ができると、ストレート合格にぐっと近づくはずです。
おのDは実際に過去問を解くこともお勧めしてくれていますが、
この記事の内容を把握しておくだけでも十分に力になると思い、
こちらの項目で紹介しました。
インタビューでは、うっかりアッパから、この「2次試験を見据えた1次試験の勉強」についてコメントを貰っています。
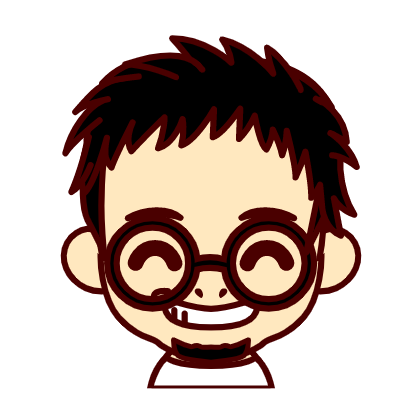
1次試験は、正解不正解を覚えてクリアするのに終始しがち。
2次試験ではそうではなくて、
何を聞かれていて何を答えなければならないのか、
どうして正解して、どうして不正解だったのか、
しっかり認識する勉強のやり方をするのが重要。
PDCAのPDばっかりでも何とか1次はクリアできちゃうけど、
2次、というか勉強には特にCAが超重要。
1次の時からCAを意識できていると、2次の勉強にスムーズに移行できるはず!
レベル2:教材だけ揃えておく
2次試験向けの教材準備はお早めに!!
1次試験後では買えないリスクがあります!

突然さやに叫んでもらいましたが、本当にこれにつきます。
2次試験向けの教材は、1次試験後では買えないリスクがあります。
さや自身が、仕事が多忙で1次試験前に2次の情報収集ができず、教材を買い損ねたとのこと。
私も1年目、同じパターンで教材購入に苦労しました。
2次試験の教材は1次試験が終わると急に品薄になります。
ですが、今年度の道場読者のみなさまは大丈夫です。
さや渾身のこの記事を読んで、紹介されているおすすめ教材を、販売開始次第、手元に用意してください!!!
記事中でお勧めしている、
「ふぞろいな合格答案」「全知識&全ノウハウ」シリーズの2023年度版はこれから発売予定です。
(※「2023年度改訂版 事例IVの全知識&全ノウハウ」は4月に発売済です。)
勧め教材の販売開始については、道場のTwitterでも情報発信する予定ですので、
ぜひ合わせてチェックをしてみてください。
レベル3:2次試験でどんな問題がでるか把握しておく
余裕がある方はぜひ、実際の2次試験の過去問を読んでいただき、
「こんなことが聞かれるんだ」というのを把握してみてください。
中小企業診断協会のHPにも過去問はありますが、
2次試験予備校AASによる「2次試験過去問ダウンロード」が一元化されていてお勧めです。
国語が得意な方は、もしかしたら「意外と簡単」だと感じるかもしれません。
(国語が得意だと有利かもしれませんが、それだけで合格できるものではありません。)
逆に、今の時点では、全く問題を解くビジョンが見えないかもしれません。
色々調べたくなるかもしれませんが、今の時点ではそこまで深入りせずにOKです。
取り急ぎ、一歩踏み込んで実際の問題を読んでみていただけると、
1次試験が2次試験に繋がっているというビジョンがより具体的になると思います。
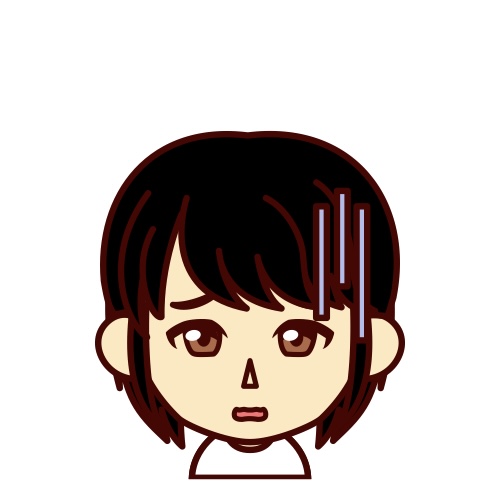
私は国語が得意だったので(センター試験の国語198点でした!)
2次試験問題は初見「意外と大丈夫そう」だと感じました。
もちろん、勘違いでした。
合格するためには、国語力だけではなく、的確な1次知識の活用が必要です。
レベル4:2次試験の問題を1度解いてみる
この辺りから、それなりの時間が必要となり、対策が難しくなってきます。
ですが、可能であれば1度は制限時間80分で2次試験の問題を解いて、
難易度や手応えを実感として持つ、
というのを多くの14代目メンバーがお勧めしています。
GWに連休が取れる方は、ここで1度解いてみると後の勉強が変わってくるはずです。
じっくり復習の時間がとれなくても、とりあえず解いてみるだけで大丈夫!
もしある程度解けた場合は後はぜひ、
その過去問の年度の実際の合格者の答案を見て、
このレベルの回答を書けるようになれば受かるのだというビジョンを持ってみてください。
(予備校の2次試験の模範解答を見てもOKですが、満点を目指している解答なので相当レベルが高いです。
実際の合格者の答案を見ていただく方をお勧めします。)
合格者答案と自分の解答との比較・分析には、参考書の「ふぞろいな合格答案」が便利ですが、
現時点ではネット上で公開されている合格者の再現答案を見る程度で良いと考えます。
道場のリアル再現答案をぜひご活用下さい。
※14代目の令和4年度2次試験の再現答案は、今後、公開する予定です。
また、「ふぞろいな合格答案」の令和4年度版も6~7月頃の販売予定ですので、
GWに取り急ぎ過去問を解いてみる場合は、令和3年度以前の問題が合格者再現答案を見つけやすくお勧めです。
4月29日開催の14代目春セミナーの2次試験編では、
過去問の実際の解き方や、初めて解くのにお勧めの過去問の紹介も行う予定です。
(※ご好評につき、既にセミナーの申込は締め切っています。)
残念ながらセミナーに出られないという方も、
セミナー翌日(4月30日)に報告レポートを上げる予定ですので、
ぜひチェックしてみてください。
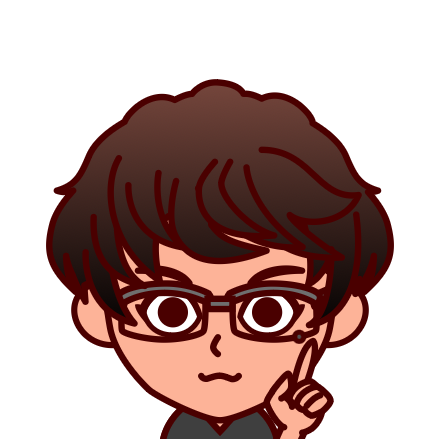
とりあえず、1度は過去問を解いてみるのがおすすめ!
過去問を解いた後の振り返りがしたい方や、
全然解けなくてどうしていいか分からなくなった方には、
おのDのこちらの記事が有用です。
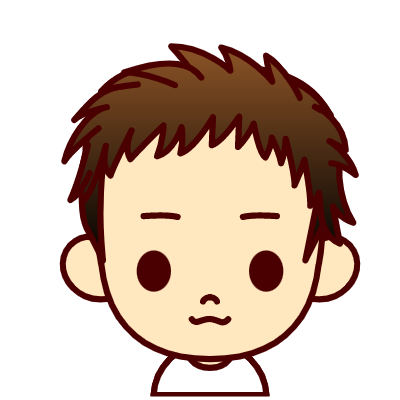
2次の過去問が全然解けず「絶望」した場合の対策も記載しています。
レベル5:事例Ⅳ対策のみはじめておく
レベル5、と書きましたが、番外編のような扱いになるかもしれません。
2次試験全体での対策を始めるのもが難しくても、事例Ⅳ対策のみは行っておくのはお勧めという意見も数名から出ました。
・さや(1次は計画的に2回受験・2次ストレート)
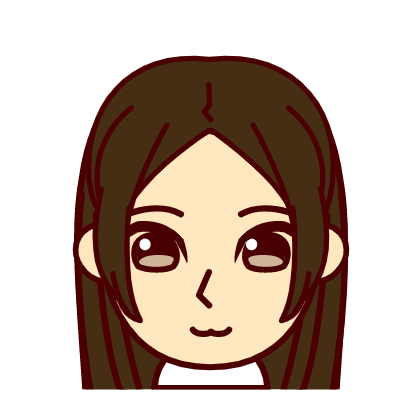
いま当時に戻るのなら、情報収集と事例Ⅳ対策はやると思う。
診断士受験界隈では以前から、「事例Ⅳを制するものが、2次試験を制する」と言われています。
事例Ⅳとは、財務分析を活用して企業の課題・問題点を発見、改善提案を行う科目です。
例年必ず出題される財務分析と、計算問題が主となります。
つまり、模範解答がない2次筆記試験で、唯一「正解」と明確な「解答方法」が存在します。
診断士試験の事例Ⅰ~Ⅲに関しては、
明確な正解がないためどこを目指していけばいいのかゴールが分かりづらいというのが大きなネックです。
対して、事例Ⅳは積み重ねて勉強をすることで、確実に成績を伸ばすことができる科目です。
2次筆記試験は相対評価のため、数点の差が合否を左右します。
1日1問ずつでも、早めに事例Ⅳ対策を始めることができれば、他の受験生に差をつけることができます。
1次試験前から対策を始める場合は、いきなり過去問ではなく、
基本問題が載っているテキストから始めることをお勧めします。
私のお勧めテキストは「30日完成!事例Ⅳ合格点突破計算問題集」。
基本問題から、徐々に難易度を上げた問題に挑戦することができます。
また、さやがブログで紹介していたTAC出版の「 第2次試験 事例Ⅳの解き方」もよさそうです。
早めの事例Ⅳ対策で、ストレート合格へより近づいてください!
そうは言われても、余裕はないという方へ
ここまで、初年度生へ向けの2次試験対策を長々と紹介してきました。
が、まずは1次試験で手一杯。そんな時間は取れない。
…という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんなあなたへ、
14代目メンバーで唯一「1次試験前の2次試験対策は必要ない」派だったTakeshiの意見をお届けします。
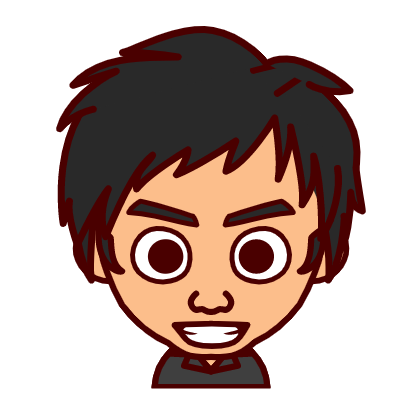
下手に2次試験対策に手をだすことで、
「1次も2次も中途半端になる」リスクもあるよ。
1次で確実に絶対全科目合格点を取れる自信があるならともかく、
落ちるリスク考えたら、
目の前の1次をしっかりやった方が後悔しない。
1次から2次まで3ヶ月あるのは、
その期間で対策が間に合うという協会側のメッセージだという話を読んで、
その通りだなって感心した記憶がある。
Takeshiの意見通り、無理に2次試験対策に手を出して、1次試験に合格できなければ意味がありません。
実際に、多くのストレート合格生が、1次試験合格後の3か月の勉強で2次試験に合格できています。
このブログで紹介した2次試験対策は、
その方が合格が近づき、2次試験対策が楽になるという1つの提案です。
潔く、まずは1次試験対策に専念するというのも正解です。
上記情報を参考に、自分に合った勉強方法、出来る範囲での2次試験対策をぜひ見つけてみてください。
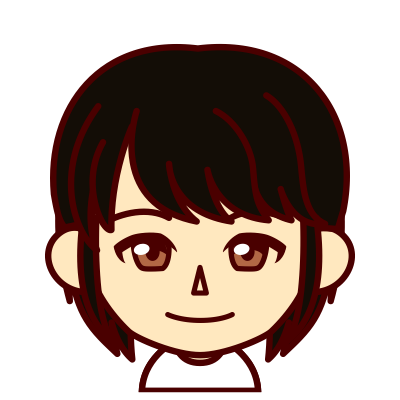
次は、多年度生向けの情報となります。
初年度生の方は、こちらをクリックで最後にスキップが可能です。
多年度の2次試験対策
現在、どの段階に居るかで変わってくる多年度生の2次試験対策。
1次試験を再受験する可能性の有無、
前年の2次試験の手ごたえや自身の強みや弱みによって、
選択肢が無限にあるからこそ悩ましいかと思います。
14代目で、2次試験を複数回受験している4人に合格年度の春の2次試験対策についてインタビューしました。
・アストロ(2次試験2回)
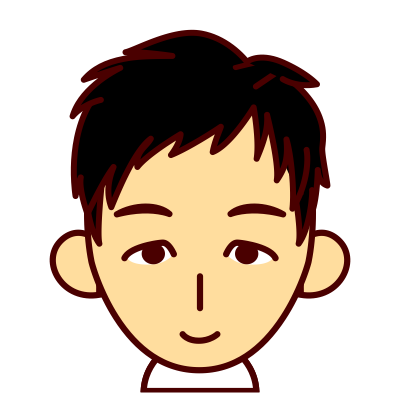
1年目の経験からずっと勉強するのは心身が持たないなと判断し、
この時期はお休み中でした。
これをやっておけばよかった、と思うのは下記の4つです。
1.教材を早く揃える
2.過去問を数多く解く
3.勉強習慣の確立(立て直し)
4.1次試験の知識の思い返し
2次試験本番まではまだまだ時間がありますので、
アストロのように休みを挟んで勉強に緩急をつけるというのも選択肢の1つだと思います。
アストロの提案する春の過ごし方については、詳しくはこちらの記事の「2次専念編」へ。
・トロオドン(2次試験4回)
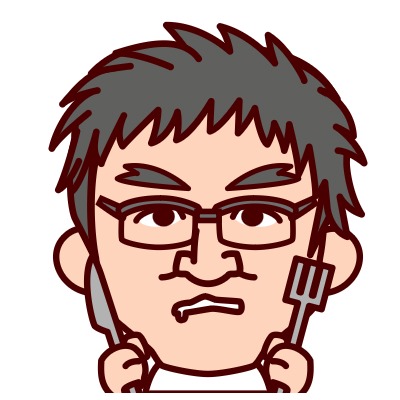
①道場読む
→足切りの反省のため。
②本読む
→「坂の上の雲※」を完読してモチベ向上!
③超たまに、2次試験予備校EBAのYoutube動画を見る。
→2次試験の振り返りのため。
※「坂の上の雲」は、司馬遼太郎の長編歴史小説。
明治維新を成功させて、近代国家として歩みだし、日露戦争勝利に至るまでの勃興期の明治日本が舞台。
文庫版で全8巻、完読にはそれなりに時間を要したと推測します。
トロオドンが、この時期の多年度生にお勧めしてくれているのは、下記の対策です。
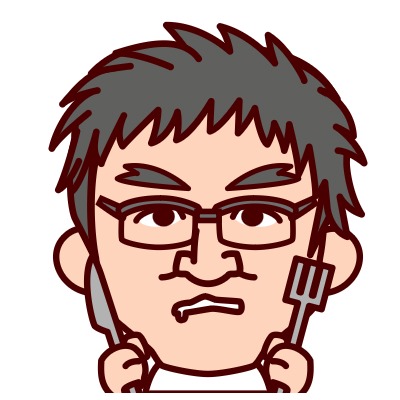
何が原因で点数が伸びなかったのか、徹底的に究明すること。
必ずしも机に向かう必要はないと思います。
詳しくは、今後「トロオドンの失敗シリーズ」という事で深掘りをしてくれる予定のようです。
点数が伸びない原因について悩んでいる方、ぜひお待ちください。
・ベスト(2次試験4回)

1次試験対策のみ(苦笑)
2次試験対策が、時間を取られて苦手(=キライ)だったから、
通学予備校の4年目以外は、3ヶ月前くらいから本格的にやりだした。
アストロに続き、合格年度は、春の時点では2次試験対策なし!
ベストの春の2次試験対策は、下記のようなスケジュールだったようです。
1年目:1次試験対策のみ
2年目:春は手つかず
3年目:春は1次試験対策のみ
4年目:通学(KEC)でひたすら2次試験答練
5年目:1次試験対策のみ
ベストが、この時期の多年度生にお勧めしてくれているのは下記の対策です。

1次試験の知識を、体系立ててしっかり理解すること。
全知全ノウの全知識編に書かれていることは、
理解するのみならず「白紙に説明しながら書ける」レベルで落とし込むこと。
さやの記事でも紹介されている、「全知全ノウ」こと「2次試験合格者の頭の中にあった全知識/全ノウハウ」。
ベストも編集にかかわっている2023年度版は、7月の発売予定です。
・みっきー(2次試験2回)
最後に、私、みっきーのこの時期の2次試験対策について。
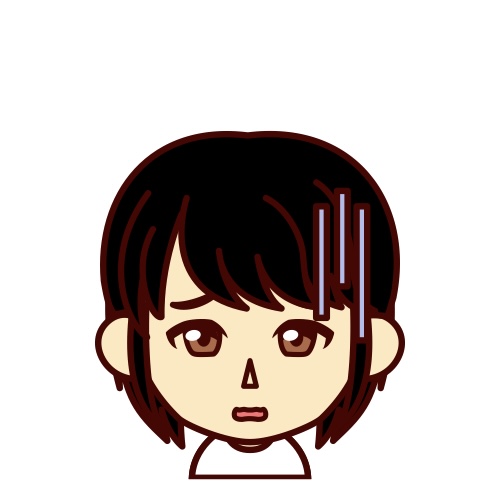
前年に生まれた息子がまだ小さく、なかなか勉強時間がとれませんでした。
唯一やっていたのは「1次試験の知識の復習」です。
また、前年の勉強会の経験が2次試験対策に役立ちました。
・1次試験の知識の見直し
昨年の今頃の私は、
子どもが昼寝している時間、
2次試験に関連する1次知識を見直す作業をひたすらしていました。
結果的にこれが合格につながったと感じているので、
私が多年度の方にお勧めする今の時期の2次試験対策は「1次知識の見直し」となります。
既に十分に知識を持っているという方も多いかもしれませんが、
改めて見直すことで、発見することがあると考えています。
私が特に注力していたのは、「2次試験の設問レイヤーと、1次知識を結び付ける」作業です。
「レイヤー」とは、直訳すると「階層」。
設問が、大きな経営戦略のレベルの話なのか、具体的な施策の話なのか、を分けるものです。
これは「開眼」…と巷で呼ばれている、2次試験への理解を深めることにとても役立ったので、
後日独立してブログ記事にしたいと考えています。
なお、2次試験を解く時に「レイヤー」を意識したかどうかは、14代目メンバーの中でも別れました。
レイヤー使いになるにはそれなりの時間を必要とするため、
この時期から見直しを行うのにお勧めの項目となります。
・2次試験のレイヤー
分かりやすいのは、13代目まんさん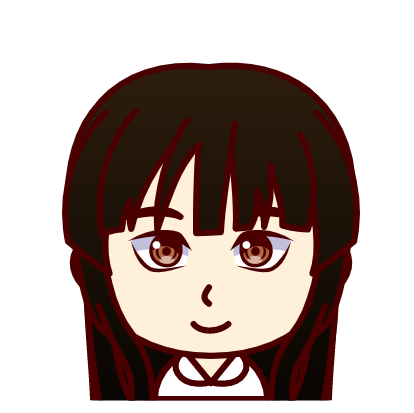 の記事です。下記にリンクを紹介します。
の記事です。下記にリンクを紹介します。
「2次プロジェクト!~【図解】事例 レイヤー&設問解釈編~ byまん」
・勉強会への参加検討
2次試験の再チャレンジには、自分自身の強み・弱みを理解しておくことも大切だと考えます。
これに役立つのは「勉強会」です。
私は、他の受験生と自分を比較することで得るものが多くありました。
「勉強会」への参加もある程度の時間が必要となるため、今の時期からの検討がお勧めです。

勉強会に参加してみたい方は、
オンラインで勉強会を運営するココスタがお勧めです。
勉強会のメリットに関してはこちらが参考になります。
最後に
本日は、「今の時期だからこそ」の2次試験対策について14代目インタビュー結果を紹介しました。
繰り返しになりますが、どこまでできるか、何をやるかはそれぞれの勉強の進捗次第。
大変な時には、休んで体調管理することも大切な試験に向けての取り組みの1つです。
無理はしない範囲で、色々とご検討いただければと思います!
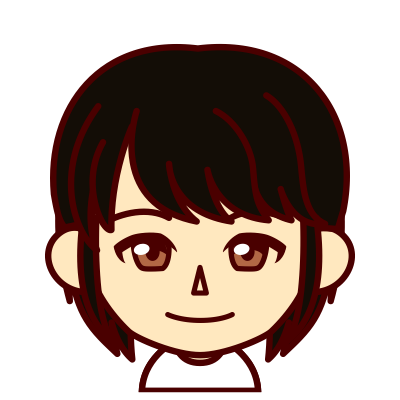
春は気圧差も激しく、疲れが出たり、体調を崩しやすい時期。
周囲のワーママ友の間で、
疲れには「アミノバイタル」がお勧めだと口コミまわっています。
私には効果抜群でした、良かったらお試し下さい。
本日も読んでいただき、ありがとうございました。
明日は、『s.t.o』です!
s.t.oもこの春に大きく環境変化があった1人。
忙しいはずなのに、いつもポジティブです。
明日の記事も、ぜひ楽しみにお待ちください。
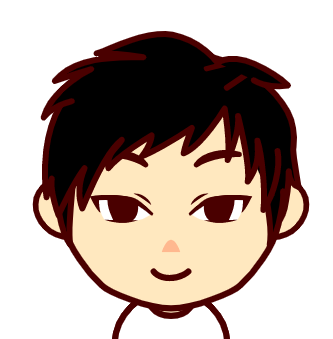
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)
記事へのコメントについて
記事へのご感想やご要望があれば、下部の入力フォームから是非コメントをお寄せください!
執筆メンバーの励みになりますので、よろしくお願いいたします。
※コメント送信後、サイトへ即時反映はされません。反映まで数日要することもあります。
※コメントの内容によっては反映を見送る場合がございますので、予めご了承ください。



