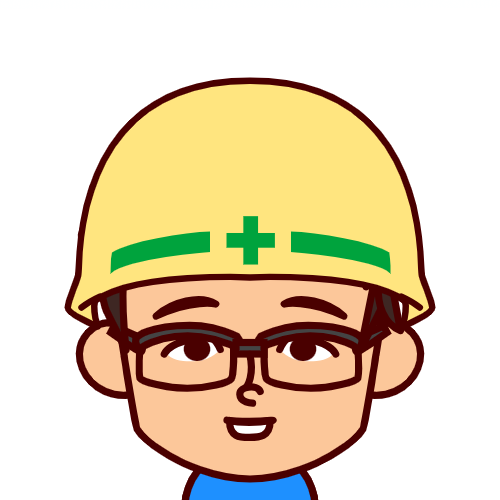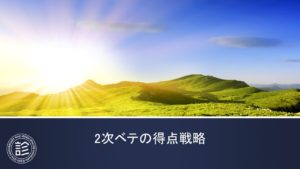読書感想文-『科学的根拠に基づく最高の勉強法』 byごり

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
一発合格道場ブログを
あなたのPC・スマホの
「お気に入り」「ブックマーク」に
ご登録ください!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
まずはTHE DANKAIのお知らせから!6/15、若干名の枠がまだありますよ!

6/15(土)はまだ若干名の空きがありますので、興味がある方は以下のリンクよりポチっとお申込みください!
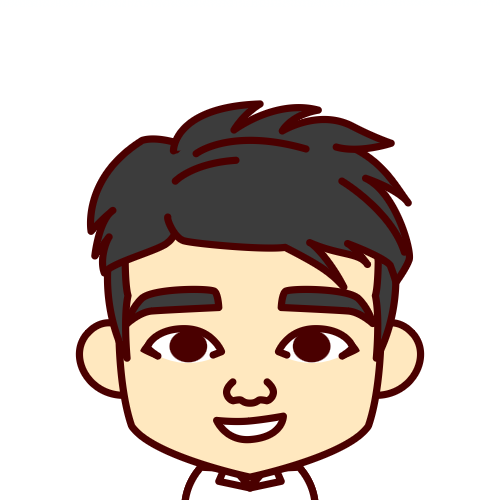
今日もアウトプットしてますか?
仕事、家庭、趣味、睡眠、、、勉強に時間をそこまで割けない方は沢山いらっしゃると思います。
そのような中、誰もが、限りある勉強時間で、可能な限り効率的・効果的に勉強をし成果を得たいという思いを持ちますよね?
自分の中小企業診断士の勉強方法を振り返ってみると、インプットはそこそこに、とにかくアウトプットを重視して取り組んできました。当時はその勉強方法に明確な根拠をもっていたわけではなく、実際に結果が出ていたので特に深く考えずに中小企業診断士試験も最後まで走り抜けました。
そんな2次試験も終わった初冬あたりにYouTubeで出逢ったのが「最高の勉強法・効率的な覚え方【科学的根拠のある効果的な学習方法について医者が解説】」でした。
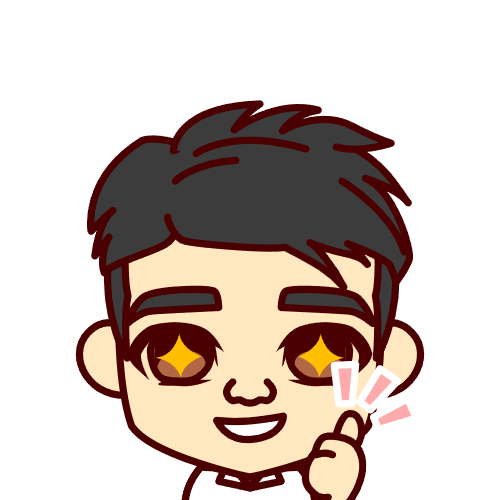
ヘウレーカ!!!
動画では、科学的に効果が低いと考えられる勉強法、効果が高いと考えられる勉強法が端的にまとめられており、まさに目から鱗、(全部とはいいませんが)私の勉強方法も、なかなかどうして科学的に根拠があった(かも)、と嬉しくなった瞬間でした。
この動画は、現在300万回再生以上されている人気動画となっています。より詳細・具体的にまとめた書籍「科学的根拠に基づく最高の勉強法」も販売されており、もちろん個人的に購入しましたので、今日はその書籍の読書感想文的な記事をお届けしようと思います!
内容に入る前にどうしても言っておきたいこと
この本の著者は、米国内科専門医の安川康介さんです。
敢えて書きませんが、肩書や経歴だけを見ると、人類トップレベルの頭の良さが醸し出ているため、
「どうせ頭の良い人が書いた自慢話なんでしょ?」
「勉強が苦手な人間には関係のない話でしょ?」
と思われるかもしれませんが、

ちがーーーーう!!!
これから紹介する本の内容は、
勉強の得意不得意に関係ない!意識の問題、スタンスの問題に過ぎない!

のです。勉強に対するアプローチを変えるだけです。
本書は、受験勉強・資格勉強で必要な知識を効率的・効果的に記憶し、定着させるためにはどういう勉強をすればよいか(あるいはしないほうがよいか)、というテーマを扱っています。
そもそも、ほとんどの人は一度書物を読んだだけではその内容の記憶を保ち続けられません。見た映像記憶を保ち続けられる「カメラアイ」の能力を持っている人間は3万人に1人(約0.003%)です。私も含めた普通の人はそんな簡単に物事を覚えられないのです。
そんな人類の99.997%(適当)を占める「普通の人」が、それでも「どうすれば効果的に記憶が定着するのか」ということを世界中の学者が研究して、現時点での著者が考える「科学的根拠に基づく最高の勉強法」を「普通の人」向けに紹介しているのがこの本になります。
知っているか知らないか、意識するかしないか、それだけでもしかすると中小企業診断士試験はもちろん、今後の人生における「勉強」の質が変わるかもしれません。
勉強の質が変わるということは、人生が変わる可能性を秘めているということです。
今日あなたの人生が変わるかもしれません。
とはいえただの一読者の読書感想文なので気になったら詳しくは本書を購入ください(いつもながらステマではありません。笑)。
本書の概要
私たちが今まで慣れ親しんだ、繰り返し読む(再読)、ノートに書き写す・まとめる、ハイライトや下線を引く、といった学習法は、実は身につきにくいやり方だった。
安川康介『科学的根拠に基づく最高の勉強法』Amazonの概要から引用
覚えたことを思い出す、人に教えられる=アウトプットこそが成長につながる、研究によって検証された効率的な勉強法です。
著者の安川さんは以前からYoutubeで医学的な情報を発信していたところ、「科学的根拠のある勉強法に関する情報が、もっと世の中に知れ渡ってほしい」と考え、2023年に効果の高い勉強法や著者が行ってきた勉強法の一部を紹介する動画を投稿されました。
すると大きな反響があり(私が記事作成時に読んだAmazonページでは338万回再生と記載)、この動画等の内容を詳細にまとめたのが本書となります。
もちろん本は詳しく書いてありますが、この動画も20分程度でわかりやすく勉強法のポイントがまとめられており、お勧めの動画です。
科学的に効果が高くない勉強法
まず第1章では、科学的に効果があまり高くないとされている勉強法について紹介します。なぜなら、勉強の効率を上げたいのならば、比較的効果の低い勉強法について知り、こうした勉強法に使う時間を減らし、その分を効果の高い勉強にあてることが重要だと思うからです。
安川康介,『科学的根拠に基づく最高の勉強法』,KADOKAWA, 2024,p. 10.
多くの人がやっている効果が高くない勉強法の例として、ただ繰り返し読むということや、参考書や教科書の内容をノートに書き写したり、まとめたりすることがあります。
本書で科学的に効果が高くない勉強法として紹介されているもの
繰り返し読む(再読)
ノートに書き写す・まとめる
ハイライトや下線を引く
好みの学習スタイルに合わせる
繰り返し読む(再読)
皆さんは参考書を読むだけで重要論点・単語を覚えられますか?あるいは動画で視聴するだけで受講した内容を覚えられますか?
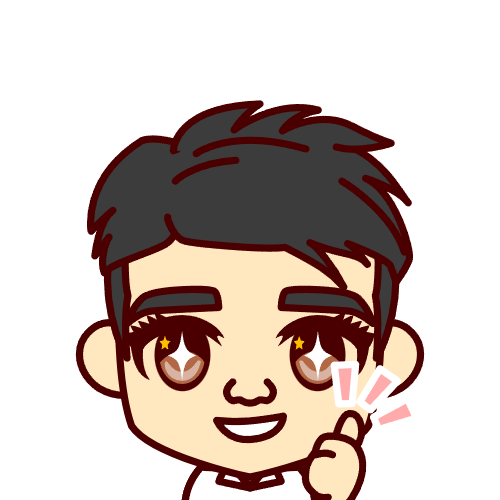
僕は無理です!!!
そしてこの本によると、たとえ、繰り返し読んだとしても(再読)、2回目以降はわかった気になってしまう「流暢性の錯覚」(すぐに思い出せることは、将来も容易に思い出せると誤解すること。)に陥りやすく、実際には記憶の定着効果は、後述する効果的な勉強法よりも低いらしいです。
単純な再読では、理解を深めることや覚えたりする「深い情報処理」が行われにくいことが原因であるようです。
であれば、どんな勉強法がよいのか、それを著者は以下のように書いています。
効果的な勉強にとって大切なのは、ある程度積極的に自分の脳に負担をかけること
安川,『科学的根拠に基づく最高の勉強法』,p. 24.
この積極的に自分の脳に負担をかけることは、「望ましい困難」と呼ばれており、後半で紹介する効果的な勉強法は、この「望ましい困難」を生み出す方法になります。
ノートに書き写す・まとめる
また、教科書や参考書の文章をノートにただ書き写したり、まとめることもあまり効果が高くない、とされています。
自分の言葉で言い直したり要約すると「ただ書き写すよりは」学習効果が高くなるようですが、そもそもの要約能力が必要で万人がすぐにできることではないとのことです。
著者の安川さんは、ノートはとらないが、情報がまとまった参考書に問題を解いた際に得た情報などを書き込み、試験に必要な情報を集約したうえで、後述の効果の高い勉強法を使って記憶に定着させていった、とのことです。
私も、論点をまとめたもの、という意味では、「ノートを取るより、シートに頼ろう」のまとめシートで「キレイにまとまったノート」を作る作業を野網先生に丸投げ(笑)して、問題演習で気になったことや補足をまとめシートに直接書いました。
好みの学習スタイルに合わせる
そして私がこの章で1番「まじか!?」となったのが以下の記述です。
学習者の好みの学習スタイルを判別し、学習方法を変えたほうが効率的なのかについては、今のところ科学的根拠はあまりない
安川,『科学的根拠に基づく最高の勉強法』,p. 44.
あまりに「自分にはこの勉強法が合っている」と囚われてしまい、本当に効果的な勉強ができていない場合は注意が必要です。
安川,『科学的根拠に基づく最高の勉強法』,pp. 45-46.
(中略)効果の高い勉強法というのは必ずしも自分ではその効果が実感できないからです。試してみた時の感覚では「これはあまり良くないなあ」「あまり覚えられていないなあ」と感じる学習法が、実は長期的にみればより効果が高いということもあります。
一応科学的根拠も付されて紹介されていますが、一般的な感覚と違う気もしてしまいます(とはいえ一般的な感覚や信じられていることが客観的事実とは異なることなんて沢山ありますが、、、)。
著者も、
自分の好きな学習スタイルで勉強することがモチベーションにつながり、そうでない場合は勉強の意欲がなくなってしまうのであれば、好きなスタイルで勉強した方が良いこともあると思います。
安川,『科学的根拠に基づく最高の勉強法』,p. 45.
としたうえで、効果が高い勉強法が必ずしも実感を伴うものではないことを考慮して、
「他人と違う自分だけに合った勉強法」に囚われすぎずに、(中略)勉強法を柔軟に試して、取り入れてみることが大切だと思います。
安川,『科学的根拠に基づく最高の勉強法』,p. 46.
と述べています。
もし、自分にはしっくり来ているのに、なかなか成績が上がらない、、、という方がいた場合にはこうした罠にはまってしまっているのかもしれません。
科学的に効果が高い勉強法
本書で「科学的に効果が高い勉強法」として主に紹介されているもの
アクティブリコール
分散学習
アクティブリコール
本書で学ぶために決定的に重要とされているのが「アクティブリコール」です。
そのアクティブリコールは以下のように説明されています。
勉強したことや覚えたいことを、能動的に思い出すこと、記憶から引き出すこと
何かを記憶するためには、それを積極的に思い出す作業や、脳みそから頑張って取り出す作業こそが、決定的に重要
安川,『科学的根拠に基づく最高の勉強法』,pp. 48-49.
遥か昔の学生の頃ですが、大学受験まで私はインプットの鬼でした。鬼というか、ひたすら覚えたい英単語や社会の単語を繰り返し書く(身体に覚えこませるみたいな要素が強いので脳にはあまり負担がいっていない)、という作業をしていました。
その努力のおかげ?で、英語や社会は得意科目だったのですが、その他の科目には全然手が回らず、理系科目は全滅、というか手を付けていませんでした(そうです私立文系です)。
また、そのころはあまり問題演習をしなかった気もします。あくまでも問題演習(アウトプット)は、インプット(参考書を読む、講義を受ける、ひたすら書いて覚える)の成果を確かめるためのものだと考えていました。
それが社会人になってからの勉強は、動機は時間がないからでしたが、アウトプットを中心に回すようになって、アウトプット中心「でも」意外と覚えられるんだ、という認識に変わりました。
そして、現在は、動画や本書を読んで、そして自らの中小企業診断士試験勉強の経験から、
「思い出す作業、空白から答えを絞り出す作業、つまりアウトプットこそ記憶の定着に結びつくんだ!」という考えに至っています。
ちなみに恐ろしいことに、本書で紹介されている研究結果では、勉強でアクティブリコールをした集団とそうでない方法で勉強した集団でテストをした結果、成績はアクティブリコールをした集団が最も高かったにもかかわらず、勉強直後に「一週間後にどのくらい自分が内容を記憶しているか」を被験者に予想してもらったところ、アクティブリコールをした集団が一番自信がない(覚えていないだろう)と回答したそうです。
アクティブリコールをしたグループは勉強直後は、他の勉強方法で勉強をした人たちに比べて一番自信がなかったのです。実際は一番効果がなさそうだと評価されたアクティブリコールが、一番効果があったというわけです。
安川,『科学的根拠に基づく最高の勉強法』,p. 57.
この「勉強の本当の効果は、勉強している本人には実感しにくいことがある」、ということは、重要なポイントです。
自信を持っている勉強方法は(比較的)効果が出ず、自信をもっていない方法で効果が出る、というのはただのトラップですよね。笑
さて、アクティブリコールの具体的な方法については以下のように例示されています。
練習問題や過去問を解く、模試を受ける、暗記カードやフラッシュカードを使う、紙に書き出す、学んだことを誰かに教えるなどです。
安川,『科学的根拠に基づく最高の勉強法』,p. 60.
私の場合だと、過去問を解いたり、Good Notesの学習セット(フラッシュカード)がアクティブリコールに当たると考えています。
また、本書にも記載がありますが、参考書を読むにせよ、動画で受講するにせよ、受動的に情報を得たままだと記憶の定着がよくないため、アウトプットを意識して行うと記憶の定着がよくなるかもしれません。例えば、動画で受講した後に、何も見ない、聞かない状態で、動画の内容を書き出してみる、などです。
分散学習
分散学習とは、一夜漬けのように、間隔をあけずに一気に勉強するのではなく、間隔をあけて勉強することです。
著者によると、
一度にまとめて勉強するよりも、時間を分散して勉強するほうが長期的な記憶の定着が良く、この効果は分散効果と呼ばれています。
これは同じ内容を、同じ時間をかけて勉強するにしても、分散したほうが学習効果が高いことを意味します。
安川,『科学的根拠に基づく最高の勉強法』,p. 73.
とのことです。
分散学習については、試験前から知っていたため、過去問演習については、間隔をあけて復習するなどしていました。前にも紹介しましたが、まずは全部解いてみる、次の日に間違えた問題だけ解く、その3日後にさらに間違えた問題を解く、、、、といったかたちです。
その間にはGoodNotesで作ったフラッシュカードもやっていました。このカード(学習セット)は自動的に分散学習的なことをしてくれます(間隔を開けて問題が出題される)。 私の中小企業診断士の試験勉強は、このアクティブリコールと分散学習の組み合わせが行を奏したと確信しています。
本書でも、この組み合わせが「最強の学習法」と述べられています
最強の学習法:アクティブリコール+分散学習=連続的再学習
安川,『科学的根拠に基づく最高の勉強法』,p. 81.
アクティブリコールと間隔反復、この2つを組み合わせた勉強法が、現代の学習の科学的根拠に基づく、誰でも実践可能で効果の高い方法だと考えます。
留意事項
これまで紹介したことすべてが絶対に正しい、と主張するつもりはありません。
例えば、再読は効果が低い、という点も、再読の仕方やテキストの長さや難易度によって結果が異なってくるかもしれません。
とはいえ、「脳に負担をかけない単純なインプットをしても効果(記憶の定着率)が低く、適切なアウトプット=脳に積極的に負担をかけ、それを反復的に行うことが、特に資格試験や受験勉強の学習においては重要かもしれないな」というのが、私がこの本を読んだ感想であり、自身の試験勉強の経験からある程度確信している考え方です。
その他の内容
本書には、他にも効果的な勉強方法であったり、記憶術、勉強にまつわる心・体・環境の整え方が紹介されています。もちろん上記の根拠となる研究結果も記載がありますよ。
興味がある方は是非書店やAmazonなどで購入してみてくださいね(しつこいですがステマではありません)。
終わりに(彼ら・彼女らもそうだったのかも)
私は、社会人で働きながら勉強するに当たり、「時間がないため効率的に勉強したい」「単語をジャポニカ学習帳に書き写しなんてしてられない」と考え、アウトプット(脳に負担をかける作業)を中心とした勉強法を試した結果、それまで何十回も書き写さないと覚えられないと思っていた単語などが覚えられ、その退屈で長い作業時間から解放されました。
アウトプットをすれば覚えられるという成功体験は、極端にいえば、人生におけるターニングポイントだと考えています。
大学受験勉強をしていた高校生のとき、全教科の点数をしっかりと取っている同級生を見て、「頭の出来が違うんだ」「能力や努力の差なんだ」と思っていましたが(いやもちろんそれもあるのですが。笑)、もしかすると、彼ら・彼女らは自然と、あるいは意識的にこのような勉強法を実践していたのかもしれません。
ちなみに、家族に、特に子供たちには、人生における強力な武器として、この本の内容を早めに知ってほしかったので、僕としては相当珍しいのですがこの本は「紙」の書籍を購入しました(でも自分用にはやっぱkindleがよかったな、、、笑)。
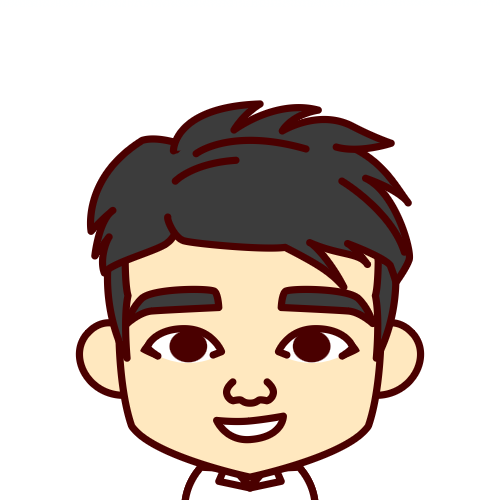
明日は一蔵の登場です!
労働法を深掘りして、一つのストーリーに仕上げてみました。お楽しみにーw
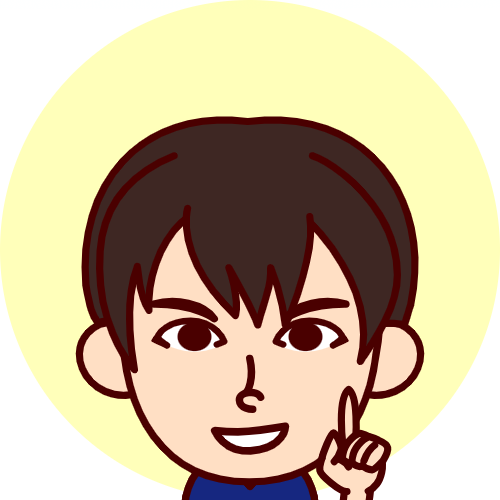
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)