2次試験2週間前! 試験まで何をする? 〜のきの場合〜
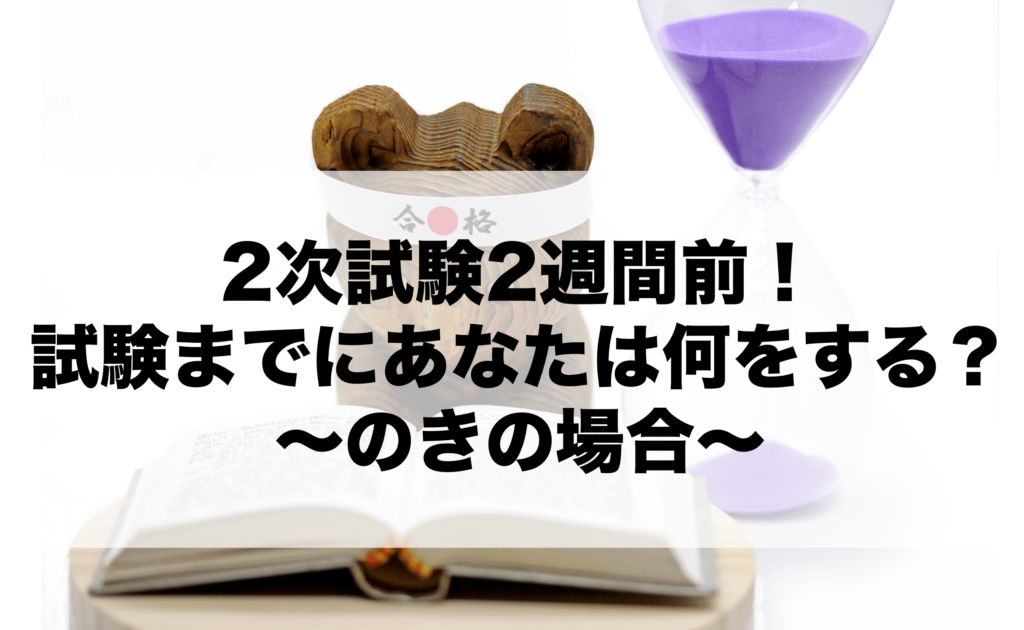

どうも、のきです。
2次試験本番まで14日!
10月頭ではまだ暑く、半袖で過ごしている人も多かったですが、だいぶ涼しくなってきて半袖をきている人が減ってきましたね。
試験当日までにどこまで気温が下がるかわかり読めませんが、必ず体温調整ができる服装を準備しておくようにしてください。
ちなみに私は、昨年の試験当日(10月25日)は薄手の長袖の下に半袖のTシャツを着ていました。
そして昼食後の事例Ⅲ以降は上の長袖を脱ぎ捨てて、Tシャツで過ごしていました。
ちょっと肌寒かったですが、事例Ⅰと事例Ⅱが終わって全力稼働中の脳のクールダウンができて個人的には良かったと思います。
さて、今日のテーマは試験まで残り2週間で何をするか?
あくまで私のパターンではありますが、試験まで残り2週間の間にどんなことをしてきたかということを参考に示したいと思います。
当然、人によって学習の進捗は異なると思いますので、ご自身の状況を踏まえながら試験当日に最高のパフォーマンスを発揮できるように参考にして貰えればと思います。
あ、あと、私のファイナルペーパーも公開するので、よろしければご活用ください。
(ファイナルペーパーに何を書いていたかは以下のファイナルペーパー(FP)を作るという項を参照ください。)
それでは、前置きもそこそこにいきますよ〜。
試験2週間前の状態
まずはじめに、人によって学習の進捗状況が違うので2週間前の私の学習状況を以下に示します。

今回のポイントは赤字のところですが、それは後ほど話をしていきます。
大枠としては、過去問は概ね解いた、問題集も大体解いて身につけていた状態だったということです。
私の2週間前の状態を見てどう感じるかはご自身の勉強の進捗状況によって変わると思いますので、ここで多くを語るつもりはないです。
では、この状況の中で残り2週間をどう過ごしたのかを見ていきましょう。
残り2週間でどれだけの勉強をしたか
まず、最初に断っておきますが、”まだ”2週間あります。
大丈夫。”まだ”合格レベルに達するための努力をする時間的猶予はあります。
次回の私の記事は偶然にも試験前日ですが、その時に同じセリフは吐けません。今だけです笑
さて見出しの通り、ここで2週間前の私の勉強時間を晒します。(Studyplusの記録から持ってきています)

見ていただけるとわかると思いますが、土日以外はあまり勉強できていません。
なんなら1秒も勉強していない日があります笑
ちょうど試験前くらいから会社の仕事が立て込んできてしまい、遅くまで仕事が終わらないなかでなんとか2〜3時間を捻出しています。
試験直前の木・金曜日は開き直って有給を取ったので、勉強できていますが、休みの日にまとめてというが大きな傾向です。
(直前の金曜日が勉強時間少なめ理由はこのあと説明します)
本記事では参考に私が2週間前にどんなことをしていたか、そしてどんなことを考えていて過ごしていたかを紹介したいと思います。
ラストスパート期の一つのケースとして活用できることを採用していただければ幸いです。
残り2週間でやったこと
ここでは、私が残り2週間やったことをなるべく時系列に並べて紹介していきます。
先ほども申し上げましたが、個人の学習状況に合わせて使えそうなものをチョイスするようにしてくださいね。
事例Ⅳの演習
タイミング:ほとんど毎日
これだけは私だけということではなく、全ての人にやってほしいことです。
道場の他の記事でも、他の受験生支援のブログでも広く言われていることですがので耳タコだとは思いますが、事例Ⅳの計算問題だけはやはり毎日しておくことをオススメします。
計算力や数字に対しての感覚というのは使わないとやはり鈍ります。
鈍った感覚では同じ問題を解く上でも30秒〜2分程度差がつきます(当社比)
ある程度期間が空いても少し練習すれば感覚は戻りますが、のこり2週間でその感覚を一度失わせるのは得策ではありません。
15分でも1問でもいいです。必ず事例Ⅳの問題を解くようにしましょう。
この15分や1問の差が当日の80分のうちの1分の差をつけると信じて演習を行なってください。
15分や1問を笑うものは15分や1問に泣くです。
セルフ模試
タイミング:最後の土日どちらか
たまに試験当日まで本番と同じスケジュールで事例を解いたことがないという人はいますが、基本的には一度は同じスケジュールで試験本番を体験しておくことをオススメしておきます。
4つの事例を1日でこなすのは想像以上にハードです。
それこそそのあと焼肉を食べて体力補給をしないといけないくらいには消耗します。
どのタイミングで食事を摂るか?
どのタイミングで間食を食べるか?
どうやって事例間の気分を切り替えるか?
当日いかに快適に、自分のペースで試験本番を過ごすかというのは地味に重要だと私は考えています。
masumiの記事で話をしていたように診断士試験の本番では頭が真っ白になることもあります。
実際、私自身もあまり道場の記事では書けていませんが、苦手な事例ⅡのSWOTや事例Ⅲの第2問の営業と製造部門の解答の切り分け等で軽く冷や汗が出る程度にはめちゃめちゃ焦っています笑
その焦った頭をいかにいつものクリアな脳みそに引き戻すか。
そのためには、試験当日に変に浮き足立たずに、平常心で全ての事例と全力で戦えるかが重要なのです。
ですので、一度は本番当日を想定した動きを一度は経験しておきましょう。
解く事例はなんでもOKです。
私はたまたま3回目の演習が終わっていなかった平成30年の事例を使いましたが、注目すべきは出来ではなく80分×4事例+休憩を想定した練習です。
繰り返しますが、セルフ模試で重要なことは如何に当日を同じスケジュールで、体力と平常心を維持するかの実験をするということです。
問題が解けたか解けないかではありません。
必要なものをそろえる
タイミング:最後の土日
試験日に必要なものを落ち着いて揃えることができるチャンスは最後の土日です。
きっと、私のような、持ち物にズボラな人のために持ち物チェックをしてくれる気立てのいいお母ちゃんであるなゆたが10月29日(金)に記事を書いてくれるので、そちらを使って持ち物チェックをしてください。(リンクは1次試験のものですが一部は流用できるはず!)
ちなみに私は最後の土日に蛍光ペンと電卓を買いに行きました。
というのも、試験勉強中は1式ずつしか持っていなかったのですが、とある考えが頭をよぎったのです。
「試験当日に今あるペンと電卓が使えなくなったらマズくないか……?」
その結果、蛍光ペンと電卓をそれぞれ3セットずつ揃えて盤石の体制としたのです。(愛機の電卓にルートがなかったというのも一因ではありますが笑)
普段は、「まぁ、そんな最悪のケースは起こらないでしょ♪」と考える超楽観的人間がこんなことを考えたのです。
今思い返しても本当に自分がそんなことを考えていたとは信じられないのですが、それくらい直前期はナーバスになっていたのかもしれませんね笑
流石に電卓3台はやりすぎでしたね笑 2台で十分でした。
というわけで、当日ないしは前日に慌てないためにできれば前の週の土日に必要なものは揃えられるだけ揃えておくことをオススメします。
ファイナルペーパー(FP)を作る(のきのFPおまけ付き)
タイミング:残り1週間前〜試験前日まで
こんちゃんやTAKUROは学習を進める過程でファイナルペーパーを作成していました(TAKUROの記事はこちら、こんちゃんの記事はこちら)
基本的に後のことをあまり考えず、壁にぶち当たってから考える猪突猛進タイプの私にはこんなに綿密に学習の途中でファイナルペーパーの完成まで想定して準備することはできませんでした。
ですが、そんな私でも事例Ⅰ〜Ⅲはファイナルペーパーを作成しました。
残り1週間の作成期間でどんなことを意識したかというと、
のきがファイナルペーパーに書いたこと&書いた理由
- これまで解いてきた事例をもとに各事例で意識しないといけない(とのきが考えた)大きな方向性を明確に示す。
私は各事例で考え方を切り替える必要があると考えていました。
その上で私はマクロで全体像を掴んでから詳細を理解していくタイプが得意なので、とにかく大きな方向性を意識することで、当日事例間での頭の切り替えをすることを目的に記載しました。 - 各事例で頻出のフレームワークや視点(例:DRINK, ダナドコ)
各事例で使うフレームワークは異なるので、上の大きな方向性の意識づけと合わせて休み時間に頭にすり込ませるために書いていました。 - 各事例での頻出キーワードをフレームワークや視点と併せて記載しておく。
上記で整理したフレームワークや視点とキーワードをセットで並べておくことで知識と思考のパターンとの紐付けをスムーズに想起できるように記載しました。
ちなみに、最後の知識の整理の作業であったため、手書きで噛み締めるように書いていきました。
「手書きは効率が悪い!」と、誰かの声が聞こえてきそうですが、私なりの知識定着の方法なのでここだけは譲れません笑
これまで、「読み解く事例の本質シリーズ」3記事の最後に「のきの考える事例の本質」という項目をブログに書いてきました。
今回実際に合格者や受験生が書いた各事例の本質について検討しましたが、一部気づいたことや受験後に考えついたことを追記しているものの、ファイナルペーパーに書いていたこととそこまで大きく相違はなかったなと思っています。
というわけで、以下のリンクで私のファイナルペーパーを公開しますので、よければ参考にしていただければと思います。
また、ファイナルペーパーはあくまで自分が理解をするために書いていたものですので、わかりにくい箇所があるかもしれません。
以下の「読み解く事例の本質シリーズ」3記事の最後、「のきの考える事例の本質」に少しだけ説明を加えて記載しているので、そちらも参考にしてもらえればと思います。
なお、事例Ⅳは基本的な計算方法だけ理解できていればいいだろと考えていたので、10代目ぐっちのファイナルペーパーを拝借しました。(リンクはこちら)
ファイナルペーパーは新たに知識を仕入れるために準備するためのものではありません。
あくまでお守りとして試験当日に自分の思考パターンに引き戻すための気付けとして活用することをオススメします。
初見事例を解く
タイミング:試験3日前
※幸い私は試験前の木曜日と金曜日に有給が取れたのでやりましたが、正直この作業はスキップしてもいいと思います。
かつて私はとある記事で「過去問に始まり、過去問に終わる」とのたまうていどには過去問至上原理主義者なわけですが、試験直前期にふと教理に反する思考が頭をよぎりました。
「過去問以外の初見問題をやって自分が本当に実力がついているかわかるのでは?」
今考えると、完全に邪念でしかないのですが、当時ののきさんはそうだ! 思い立ったが吉日と即座にネットの海を探し始めました
その結果、2次試験向けの予備校であるMMCの体験添削の問題を見つけました。
問題や解答用紙、解説までついていたので独学の私にはもってこいでした。
とはいっても解く上で大事にしていたことがあります。
それは自分が決めたプロセス通り問題が解けるかと解答の因果関係は明確かです。
悪くいう意図はないのですが、当時から「予備校の作った問題はあくまで予備校が過去問を真似て作った問題」であり、過去問を作っている偉い先生方の思考は絶対に完コピすることはできないと考えていました。
なので、予備校の事例に書かれているキーワードは重要ではなく、いかに自分の解答プロセスが再現性高く実行できているかを確認することに注力していました。
そもそも、合格する気で勉強していたら試験3日前には一通り知識は身についているはずです。
そして診断士2次試験で重要なことはあくまで1次試験の知識を用いていかに論理的に作問者の問いに答えられるかです。
そのため、試験直前期に解く初見問題から完全に新しく学ぶことはないはずです。(そう開き直りましょう)
合格というステップに登るための踏み台になってもらいましょう!
4事例一気に解く
タイミング:試験前日の午前中
こちらも若干劇薬な気がしますが、私なりに考えて実施したので紹介します。
私は試験前日の午後はゆっくり自分がやってきたことを見返す時間にするつもりだったので、事例を解くならば午前中までと決めていました。
そして1週間前に思いついたのがこの4事例一気に解くという暴挙です。
2次試験の各事例を一気解くと80分×4=320分。
つまり5時間半で解き終わるわけですね。
朝6時から始めると午前中には終わります。
そして4事例一気に解く以上の負荷は試験当日はかからないはず。
そんなことを考えて、令和元年度の問題を使って4事例一気解きを敢行しました。
この時に意識していたことはセルフ模試でも初見事例のところでも書きましたが、疲れている状況の中でも解答プロセスが維持できるか、そして疲れている脳みそで因果関係が通った文章が書けているか、です。
そう、どんな状況下でも再現できる解答プロセス、そして明確な因果関係を提示できる脳が試験会場であなたの助けになってくれるのです。
事例を解くことが目的ではありませんよ!
番外編:体調を整える
タイミング:〜前日まで(主に前日午後)
今現在、あなたの体に調子の悪いところはないでしょうか?
腰でしょうか? 目でしょうか? 手でしょうか?
おそらく、受験勉強を一生懸命やっていく過程で無傷で進められている人はほとんどいないと私は思っています。
実際、私も受験勉強中はひどい眼精疲労と腱鞘炎に悩まされてきました。
しかし、肉体的な痛みや辛さはなんとかできる可能性があります。(精神的なものはなかなか即効性を持って治すことは難しいのですが)
なるべく肉体的な痛みについては早々に専門家、つまりは医者に相談するに限ります。
とはいえ、そんな簡単にお医者さんのところにぷらっといけないのも忙しい社会人の悩ましいところ。
今回私が、試験に臨むにあたって、苦しんでいた眼精疲労と腱鞘炎については経験に基づいて対応策を提示したいと思います。
対 眼精疲労
基本的にはお医者さんにいくのが良いのはわかっています。
ですが、とにかく今目が疲れているのをなんとかしたい……。
そんな人もそれなりの数いるのではないかなと思います。
そんな方にオススメしたいのが、「めぐりズム 蒸気でホットアイマスク」です。
疲れた箇所は、原因にもよりますが、温めて血流を促進して、新陳代謝を促進するにつきます。
そのため、こういった温熱効果系のアイテムはかなり有効です(と、私は思っています。)
また、この製品は匂いが5種類あるので、自分の好きな匂いを感じながら、目のケアをすることで疲れた脳をリラックスさせる効果もあります。(と私は(ry)
これを話すと意外だと100%いわれるのですが、結構匂いで癒されたりしますので、好きなゆずの香りを楽しんでいました。
ちなむと、診断士試験に合格してからも目が疲れているなーと感じた時には時折使うようにしている愛用製品です笑
対 腱鞘炎
腱鞘炎と一口に言っても、体は関節で繋がっている以上、必ずしても手だけが原因ではないそうです。
なので、根源的な解決を行うのであれば、整形外科か信用できる整骨院に行ってください。
これだけは本当にお医者さんや柔道整復師さんの力借りることをオススメします。
試験勉強の過程で、ペンを持つ右の手と手首に慢性的な強い痛みがあり、柔道整復師さんのいる整骨院にいきました。
一通り私の腕や肩周りを触った後に、私の場合は前腕部の筋肉に腫れがあるので、負荷が指や手首といった関節に余計な力がかかってしまっているとのことでした。
なので、整復士さんに診断士の2次試験があるのでなんとかしたいということを相談して、定期的に腕から肩にかけて全体をマッサージをしてもらって少しでも負担を減らしてくれることになりました。
結果としてかなり痛みが引いた状態で試験を受けることができ、320分間の戦いに耐えうる手首で試験に臨むことができたかなと思っています。
自分が成し遂げたいことをするために正直に話をして誰かの力を借りることは決して悪いことではありません。
例えそれにお金がかかったとしても成し遂げたいことの価値とで天秤かけて価値があると自分自身が思えばそこに価値は生まれているです。
自分の体のことばっかりは自分でどうすることもできないと私は判断したので、プロの力を借りました。
餅は餅屋。体のことは体のことをよく知っている人に相談してください。その方が解決も早いですよ!
もちろん今回紹介させていただいた目と関節に関しての悩みを抱えている方もいると思います。
そのような方にはご期待に添えずすみません。ですが、弱っている箇所は多少の投資が必要だとしてもケアしてあげましょう。
試験を万全の状態に臨む準備をする期間。
それが試験2週間前の時期だと私は考えます。
おわりに
さて、今回こそはさらっと終わらせようと思っていたのですが、なんだかんだでそれなりの分量になってしまいました。
泣いても笑っても残り2週間です。
ここまできたら私から多くは語る必要はないと思っています。
自分が納得できるまで頑張るだけです!
明日は、サウナで同じ釜の蒸気を浴びたソウルメイト、にのみです!
では、また試験前日に!
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)

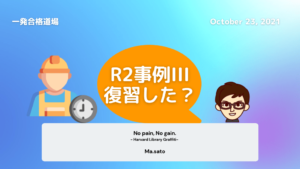

のきさん、二次試験二週間前の記事、ありがとうございます。
この記事を読んでいて、二週間後の今はまだ再現答案を作っているのかもしれませんが、長かった勉強から解放されているのだと思います。
自分は大分過去問の周回をこなしてきたので、あまり焦る気持ちはありません。
これから試験まで、今までこなしてきた平日、休日の勉強ペースを維持しつつ、どうしてもまだやらかしてしまううっかりミスを減らすためにファイナルペーパーに書いてあることを暗記して、あとは体調管理に注力しようかと思います。
ただ、このコメントを書きながらも、まだ寝るまでに時間はあるし事例Ⅳの問題を少しでも解いておこうかなと思います。
この僅かな時間に問題を解くことが決定的な差になると信じて、問題解いてきます!!