3大忘れがちな事実(中小企業診断士) byごり

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
一発合格道場ブログを
あなたのPC・スマホの
「お気に入り」「ブックマーク」に
ご登録ください!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
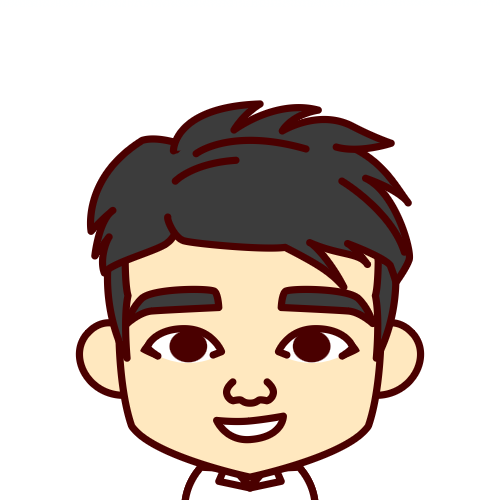
今日は中小企業診断士(試験)で忘れがちな3つの事実についてお話します(独断と偏見)。
これから中小企業診断士試験を受験し資格取得を目指す方、そして、もしかして10月の2次試験を受験した方も忘れがち(忘れがちというか曖昧な認識)になっている中小企業診断士に関する3つの事項について説明します。
その1|2次試験の試験内容
いやいや受験生なら試験内容は把握して当然でしょ?

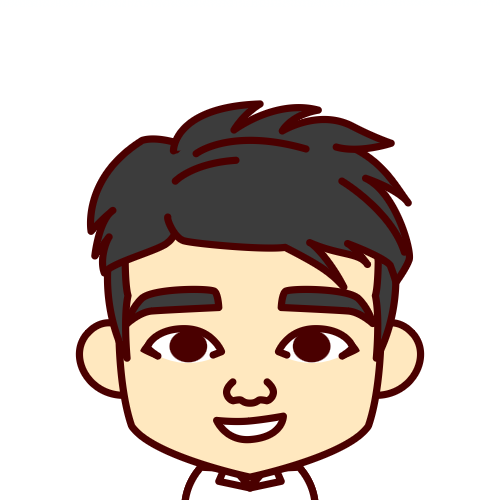
まぁさすがに2次試験があること自体を知らないままの人はいないと思うけど、、、
私自身、中小企業診断士の資格勉強を開始するにあたり、事前に1次試験の各科目の過去問をナナメ読みして試験内容や難易度をなんとなく把握する作業はしました。
でも2次試験は、1次試験に受かったら受けるもの(当たり前)で、1次試験のボリュームが多いこともあり、後回しというか「まずは1次試験の突破」ということで事前に一切過去問を見ていませんでした。
私以外にも同じような挑み方をした道場15代目メンバーがいます。
こんなはずじゃなかったというか、1次試験との趣の違いが際立ってびっくりします。
とはいえ、そんな状態からでも合格を掴み取ることも可能ですのでご安心ください(この記事を読んでいる方が2次試験内容をおざなりにして勉強開始するとは思いませんが、笑)。
勉強開始前に2次試験に向けて意識しておくべきこと
①どのような出題形式か、どのような内容の問題が出るかは過去問をサラッと読んで把握しておく
②2次試験対策の参考書は1次試験直後は品薄になるので、スタートダッシュのために事前に買っておく(予約しておく)
【参考記事】
その2|2次試験に合格しても中小企業診断士になれない
衝撃の事実ですね。
いやいやいや、そりゃなれないよ!みんな知っているでしょ!

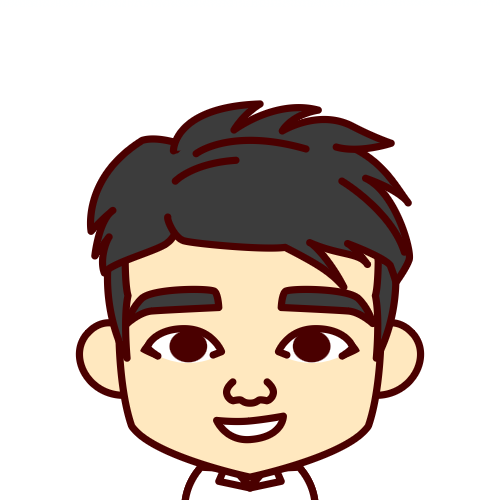
そう、みんな知っている。知っているけど、実際にその事実に直面したときにね、、、
「中小企業診断士」になるためには
中小企業診断士第2次試験に合格された方は、合格後3年以内に、「実務に従事した日数」または「実務補習を受講した日数」の合計が「15日以上」を満たすことにより、中小企業診断士として経済産業大臣に登録の申請を行うことができます。
ここで実務従事?とか実務補習?とかになる方は以下の記事が参考になりますよ。
なお、実務補習については、これまで15日間(5日間×3企業)コースと5日間コース(1企業)がありましたが、令和7年2月以降は15日間コース(8日間+7日間(2企業))と8日間コース(1企業)のみに変更されます(一部地域では令和7年2月までは5日間コースもあるようです)。
詳しくは日本中小企業診断士協会連合会のお知らせ(令和6年度からの中小企業診断士実務補習に関するお知らせ)をご覧ください。
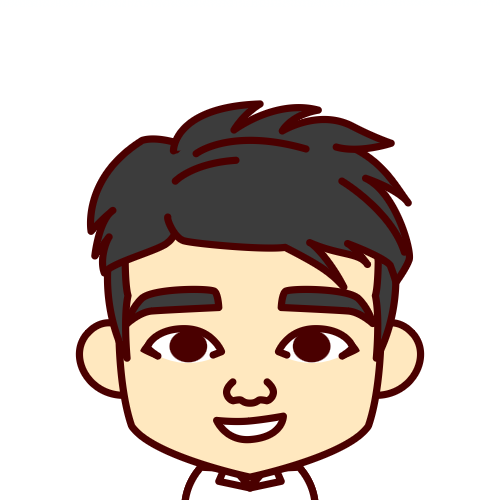
会社員など、平日は本業で仕事をしている方だと複数日の休暇は必須になります!
実務補習は平日と休日にまたがって行われ、8日間コースでも3~4日程度平日に被るので、会社員の方などは職場の調整が必要になります。
また、休日にも行われる観点からは、家族との調整も必要になります。補習は丸1日×4~5日取られますので、小さいお子様がいる方は、パートナーに休日複数日ワンオペになる点を事前に説明し、必死に説得してください。家族の理解が得られないと中小企業診断士にはなれません。
なお、例年2月の実務補習は、2次試験合格発表直後に申込が必要となり、争奪戦となります。
次の2月の申込期間は、「令和7年1月9日(木)~1月21日(火)」となっています。
あと大事な話ですが、実務補習にはお金がかかります!!!
実務補習費用(2024年11月記事執筆時点)
・15 日間コース:210,000 円(税込み)
・8日間コース:105,000 円(税込み)
これを高いと思うか、安いと思うかはその個人によると思います。
いかにお金をかけないで中小企業診断士試験を合格するか考えてきた人間には厳しい金額です、、、。
一方、「実務従事」は以下のとおり、普段からコンサルティングを生業にされている方や、中小企業診断士人脈があると有力なポイント獲得手段になりますし、費用面も柔軟性が出てきます。
診断協会の実務補習と違い、自分自身で診断先企業を探し、そこに対して診断業務を行います。すでにコンサルティング業務を生業とされている方は比較的簡単に要件を満たせる一方、経営者の知り合いがいない普通の会社員だったりするとハードルが高くなります。
しかし、民間企業や団体が独自に実務従事の募集を行っていることがあります。この場合、無料のもの、費用を支払うもの(受講する側がお金を支払う)、報酬をもらうもの(受講する側がお金をもらう)、という風に様々な形態があります。
出典|14代目ひろしさん 診断士登録のポイントの集め方 https://rmc-oden.com/blog/archives/187629
その3|診断士登録後も資格更新のためにポイントが必要
衝撃の事実ですね!!!(2回目)
いやいやいやいや、これも診断士を目指す者として当然のこと!


これは結構知らない人もいそうな、、、、
診断士の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年間です。このため引き続き登録(更新登録)を希望される者は、お手元の中小企業診断士登録証に記載された登録の有効期間の満了日までに、更新登録申請が必要です。
更新登録にあたっては、登録の有効期間の開始日から、今回の申請日までの間に、以下の(1)専門知識補充要件と、(2)実務要件の両方を満たす必要があります。
出典|中小企業庁 申請・届出の手引き(更新登録申請) https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/shindanshitetuduki02_03.html
- 専門知識補充要件
以下のいずれかを合計して5回以上の実績を有すること。
1)理論政策更新(理論政策)研修を修了したこと。
2)論文審査に合格したこと。
3)理論政策更新(理論政策)研修講師を務め指導したこと。- 実務要件
以下のいずれかを合計して30日以上行ったこと。
1)診断助言業務等に従事したこと。
2)実務補習を受講したこと。
3)実習、実務補習を指導したこと。
ご存じでしたか?これは「まずは2次試験に合格しよう!」と考えている受験生の中には詳しく知らない方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。
実際、私が実務補習で出会ったメンバーの中に、この事実をその時に初めて認識し驚愕していた方もいます。
出典|ソロでもいける!中小企業診断士 中小企業診断士の更新方法とは?登録更新要件について https://solodemo-blog.com/shindanshi-update-summary
資格更新については、上記画像の引用元であるAzさんのブログに詳細にまとめられていますので、是非ご覧ください。
https://solodemo-blog.com/shindanshi-update-summary
中小企業診断士を生業にしようとしている方にとっては何でもないことですし、普段からコンサルなど、企業診断をしている方にとってもポイント獲得は造作もないことだと思います。
一方、私を含め、企業内診断士、というか本業がある中で診断士資格を取った人間からすると、特に実務要件について、平日は仕事をしているなかで、実務補習も大変だったのに5年で30ポイントなんてどうするんだ、、、と絶望される方もいらっしゃると思います。
ここは、私も手探りではありますが、例えば東京都中小企業診断士協会では、実務従事事業ということで、診断士向けに土日を中心とした診断業務の機会を提供しているようです(有償)。
また、各協会のマスターコースや研究会、と呼ばれる集まりの中で診断業務の機会が提供されることもあるようです。
いずれにせよ、積極的に情報を取りに行ったり、協会やコミュニティに所属しないとなかなかポイントの獲得=資格の更新は難しいと思いますので、予め知っておくとよいですね。
最悪、ポイントが獲得できず更新できない、となった場合、診断士の業務休止申請が可能です。
業務休止をする者は、5年間の登録有効期間の満了日までに、申請する必要があります。
業務休止ができる期間は申請を行った日から最長15年間です。
出典|中小企業庁 申請・届出の手引き(業務休止申請)https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/shindanshitetuduki04_06.html
また、残りの登録の有効期間とは業務休止申請を行った翌月1日から、この時点の登録の有効期間が満了する日までの期間のことで、これが業務再開後の登録の有効期間となります。
ただし休止後の業務再開にあたっては、再開要件がありますのでご留意ください。
業務休止申請で交付を受けた、中小企業の経営診断の業務再開の申請可能証書に記載のある業務再開申請可能期限まで業務再開申請をすることができます。
業務再開要件は、申請日の前3年以内において以下の専門知識補充及び、実務の両方の要件を満たすことが必要となります。
出典|中小企業庁 申請・届出の手引き(業務休止申請)https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/shindanshitetuduki04_06.html
- 専門知識補充要件として、理論政策更新(理論政策)研修等を5回以上修了したこと。
- 実務要件として、実務または、実務補習等に15日以上従事または、受講したこと。
締め
みなさんはいくつ知っていましたか?笑
すべてを把握されてから勉強をされている方もいれば、まずは2次試験合格を!ということで勉強を開始されている方やされる方もいらっしゃると思います。
特に後半の2つは、2次試験合格はゴールではなくスタートである、ということが否応なしにわかるものですので、まだよく把握されていない方は、しっかりと認識されてから試験勉強をはじめるのもよいかもしれませんね。
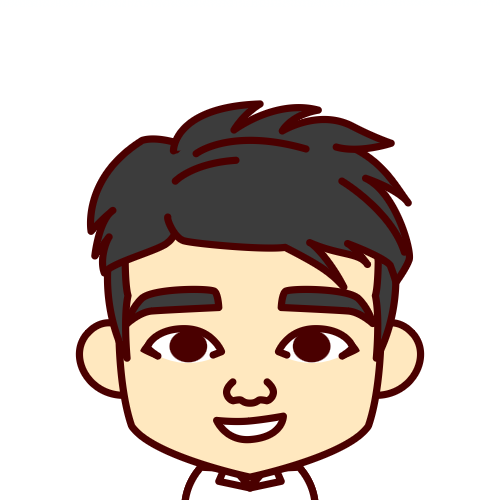
明日は一蔵です!
zzz…
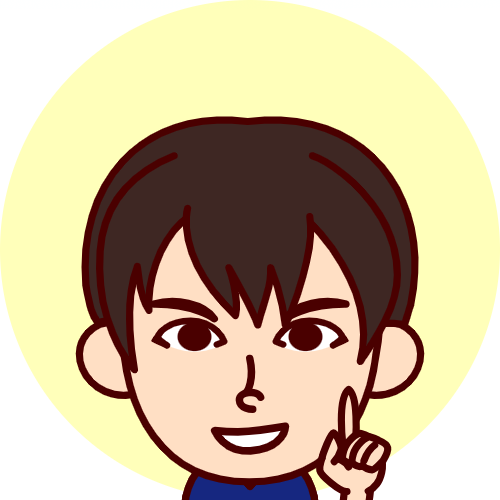
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)




こんばんは!
にっくです。
診断士として忘れがちな、忘れてはいけないことの記事、ありがとうございます!
僕もざっくりとは知っていたつもりですが、改めて正確に理解することができ、感謝しています。
「診断士でいること」のハードルが高いと言うことは、逆にそれだけ診断士の価値が上がることだとも思うので、甘んじて受けたいと思います!(合否発表まだですが)
診断士目指して、がんばるぞー!おー!
ありがとうございました!
にっく
にっくさん コメントありがとうございます。
おっしゃるとおり、厳しくはありますが、中小企業診断士という質を保つために必要な施策だと思っております。
1月の筆記試験合格発表で良い知らせがにっくさんに訪れることを祈っています!
ごり
ごりさん
ありがとうございます!
元気出てきました!
にっく