これでカンペキ!実務補習の準備・完全マニュアル by masumi
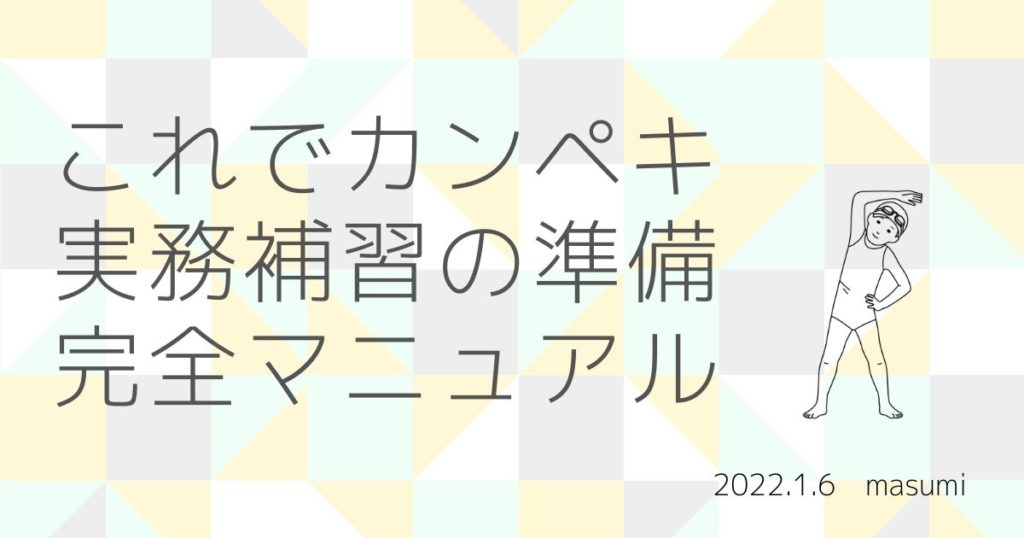

あけましておめでとうございます。年末年始はゆっくりできましたか?
2年ぶりにmasumiと会った。いつの間にか診断士になってたね。

そうなんです。りんは実家で飼っているマルチーズですがコロナ禍で実家に帰れずにいたのでしばらく会っていませんでした。
久々に会いましたが、、か、かわいい( ´艸`)
実物のりんはツッコミをすることもなく私になついています。
***
さて今回は2月の実務補習の準備を早めにしておきたい人向けに、事前にやっておくとスムーズだよ、ということをお伝えします!
事前準備はやらなくてもなんとでもなりますが、私は計画的に事前準備をして後でラクをしたいので、同じタイプの人は必読です!
ちなみにタイトル通り、実務補習の完全マニュアルではなく、「準備」の完全マニュアルです。
ここまで準備しておくと他のメンバーから一目おかれること間違いなし!
ついでに変人扱いされるでしょう。
![]() ちょっとまじめな話(たまにはちゃんとしたこと言います(笑))
ちょっとまじめな話(たまにはちゃんとしたこと言います(笑))
実務補習に限ったことではなく、私は何事も事前準備が大事だと思っています。
いかに効率よく進められるかとアウトプットの質は準備段階ですでに決まっていると思うのです。
メンバーが揃っている時は揃っていないとできないことをすべきで、ひとりでもできることは事前にやっておく、というのが私の基本スタンスです。
その方がディスカッションなどの全員での作業に時間を使え、アウトプットの質も向上します。
masumiは事前準備と計画性のオニなんだよ。相当だよね。


そうです。私はオニなのです。
忙しくなることが分かっていれば数か月前からリスクヘッジしていますし、目標から落とし込んでスケジュールを立て、スケジュール通りに進められるという変人です。
ギリギリでバタバタが苦手なのです。
*今日の名言*
準備にかけた時間は裏切らない by masumi
ちょっといいことを言ったので早速進めようと思いますが、その前に、、
まさかこんな人はいないですよね?↓
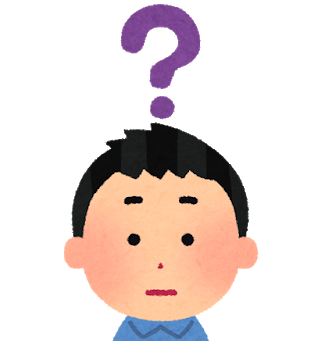
実務補習ってなに?合格したから診断士登録できるんでしょ。
いいえ、合格しただけでは登録はできません。
そんな人はこれらの記事でさらっと事前知識をインプットしてから読んでくださいね!
(けっこう長いからさらっとでOK)

では早速いってみよう!
この記事でわかること
- 実務補習の持ち物
- 実務補習前にやっておくと良いこと
- 企業訪問前にやっておくと良いこと
- 実務補習で役立つサイト
contents
実務補習の持ち物
実務補習で必要な持ち物は以下の通りです。
※外出するのに当たり前のもの(スマホやマスクなど)は除きます。
1日目 ガイダンス・顔合わせ・ヒアリング(リアル開催)
現在の実務補習は、開催時期や地区、指導員によって、リアル開催とオンライン開催、ハイブリッドとやり方はまちまちです。
ただし1日目は必ず企業にヒアリングをするのでリアルの場合が多いと思います。
実務補習では5~6人で役割分担をします。経営戦略、販売・マーケティング、生産管理、人事組織、情報システム等です。

自分がどの担当をするかは事前に決めている場合もあるけど1日目に集合してから決める場合もあるよ。 池やんも言うように1度はリーダー(経営戦略担当)をやってみると勉強になるよ。
*ないと困るもの*
- メモするためのもの(筆記用具やノート、PCやタブレットなどにメモする人はそれでも◎)
- 事前に送られている実務補習テキスト
- 事前にメールなどで送られた企業情報(データか紙)
- 事前に送られている業種別のチェックポイント(データか紙)
- その他指導員から指定されているもの
- 印鑑
指導員から事前に会社に関する情報と業種別のチェックポイントが送られているので、それを元にヒアリング内容を検討することになります。
そのため、それらのデータは見られるようにPCを持っていくか印刷して持っていきましょう。
印鑑は持参するよう指示されています。秘密保持契約書に捺印します。
*持っていくのが一般的なもの*
- ノートPC
- 名刺
- スーツ(事前に要確認)※持っていくというより着ていく
スケジュールによって1日目はPC無しでも頑張ればなんとかなりますが持っていくのが無難ですね。
ヒアリング内容を直接PCに打ち込みながら聞くことも可能です。
13インチくらいのPCの人が多いですが、15インチの人もまあまあいます。重そう。
私はもともと持ち歩かない前提で15インチのPCを使っていたのでこれを機に買い換えました。
3か月近く検討した結果、hpのENVYを購入しています。どんな点で迷って、何を基準に選んだのかについての記事はこちらからどうぞ。
名刺は現在の仕事の名刺です。メンバー間で名刺交換をします。基本的に訪問企業では名刺交換はしません。
服装はスーツが一般的ですが、私が訪問した会社は小売り業で店舗訪問だったのであまり堅い服装でなくてよいと指示がありました。
事前に指示が無ければ確認した方が良いですね。
*あると安心なもの*
- USB
- (PCによって)映像出力端子の変換アダプター
- インターネット接続できるようにするもの
USBは各自調べてきたことを共有する時に使うことが多いです。
Googleドライブ等で共有できますが、USBならインターネット環境がなくても使えるので、誰かひとり持っていると便利です。
変換アダプターについてですが、ディスカッションする時は誰かのPCをプロジェクターに映して書き出していくことが多いので、プロジェクターに接続する必要があります。
PCによっては端子がないのでUSB端子をHDMI等に変換するアダプターがあると良いです。
え、どういうこと?という人はこのサイトを参照ください。
私のhpも映像出力端子がなく、アダプターも持っていなかったので、必要な時はUSBでデータを移して他のメンバーに映してもらっていました。ちなみにUSBも借りています(^▽^;)
ネット接続について。
1日目はインターネットはちょっと調べたい時に使う程度なのでスマホでもなんとかなりますが、ネット接続はされていた方が安心です。
打合せを行う会議室はWi-Fiが使えるようになっているのが一般的なのですが、私が1日目に使った会議室はWi-Fiが無い、と言われて、それぞれでデザリングで対応していました。
デザリングって何?って人はこちらの記事を参照ください。
(↑実際はWi-Fiが使える会議室でした。指導員が知らなかっただけでした。)
この「あると安心なもの」は全部持っていかなくて人任せだったね。

そうです。メンバーに大変お世話になりました。本当に感謝です。

リーダーの時もありましたが、実際なくてもなんとかなります。ただ、もし次があるなら準備していこうと思ったものを書きました。
2日目~4日目(ディスカッション・個人作業・提案書まとめ)
2~4日目はメンバー間のディスカッションや個人作業になります。リアルの場合もオンラインの場合もありますね。
リアルの場合の持ち物を紹介します。
*ないと困るもの*
- ノートPC
- メモしたノートやデータなど
- メモできるもの(1日目と同じ)
- 財務担当なら預かっている財務資料
- その他事前にもらっている企業情報など(1日目と同じ)
さすがに2日目以降はPCが必須です。2日目は前日のヒアリングを元に方向性をまとめていく作業がメインになります。
その際にいろいろ調べることが多いのでネット環境は必要ですが、基本的に2日目は会場のWi-Fiが使えます。
※1日目と2日目の会場が違う場合があり、2日目はWi-Fi完備されています。
服装は、企業訪問しない日はカジュアルな服装で大丈夫です。
*あると安心なもの*
- USB
- (PCによって)映像出力端子の変換アダプター
- インターネット接続できるようにするもの
- kinko’sの会員証
あると安心なものは1日目とほぼ同じです。
USBはそれぞれの提案書をまとめる時に必要ですが、最終日は協会に完成版を提出するのにも使うので指導員が持っていることがほとんどです。
4日目に全ての作業を終了する必要がありますが、終わらないと会場の外で作業することになり、インターネット接続ができないと困ります。
デザリングやポケットWi-Fiで対応できるようにしておくと安心です。
終了時間の17時までに終われば必要ないよ。

kinko’sの会員証は、最後にkinko‘sで印刷をする時にあると良いです。ポイントによって割引価格で利用できます。会員登録は無料です。
他の印刷サービスや手段を使って印刷する場合は不要ですし、特になくても利用できないというわけではありません。
ちなみに協会から印刷代が支給されますが、全員手元に印刷して持っておきたい場合はその金額では足りないです。

結論、あると安心なものはなくてもなんとでもなる。
念のためリーダーなら用意できるものはしておいた方がいいかもね。
1か月前くらいからやっておくと良いこと
さて、ここからは今からできることをお伝えしていきます。
実務補習とは何か、どんなことをするのかは私も事前に知っていましたが、実際に経験して、”事前準備と計画性オニ”のmasumiとしては
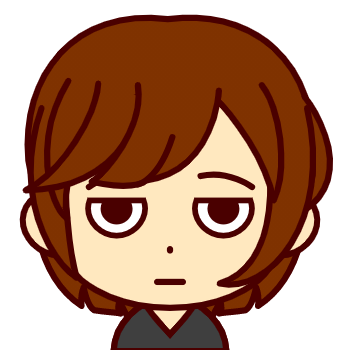
事前にやっておけることいっぱいあるじゃん
と思いました。
ですので、2回目の実務補習ではこれらを実行しています。
2次試験の復習をしておこう
当たり前ですが、2次試験の知識や考え方を元に訪問企業の課題解決提案をします。
基本スタンスは『診断士脳』です。忘れてしまった人もいると思うので、この記事を読んでおさらいしておきましょう。
さらに、経営戦略、マーケティングについてはこちらの記事を読んでおいてください。
実はこの記事、私が実務補習で必要だなと感じた内容を中心にまとめているので、かなり実務補習に則していると思います。
実際に経営戦略を担当した時に作成した資料も含まれています。
社長へのプレゼンでは、戦略の立て方、考え方から伝えることが必要になる場合もあります。
財務・会計の復習もしておいた方が良いです。具体的には以下の点です。
①損益分岐点の計算
PLを見て固定費と変動費を分けられるようにしておきましょう。材料費や外注費以外は固定費として考える、くらいで問題ないです。
損益分岐点を計算してグラフにして報告することが多いのかなと思うので、これがどんなものなのか説明できるようにしておきましょう。
②設備投資の評価方法
計算が複雑なNPVは実際に中小企業で使うことはあまり多くないと思われます。回収期間法を使って計算し、説明ができれば良いかと思います。
また、私は「投資余力」という言葉も実務補習で初めて聞きました。
これから設備投資をするにあたって、どれくらいの額が投資に充てられるかということです。当期純利益+減価償却費でいいよ、と指導員から言われ、そういうものなのかと思った記憶があります。
③その他
キャッシュフローは試験勉強の時のように、純利益から±して細かく計算することもなく、営業利益に減価償却費を足し、税金を引いた数値を用いたり、上記のように純利益+減価償却費だったりと、ざっくりと省略した数値を使うことが多いです。
このざっくり計算の考え方と投資評価の仕方はこの記事が分かりやすいかと思います。
また、実際の財務諸表の数値をMCSSという分析ツールに入力するのですが、1,000円未満の扱いは切り捨てが一般的だったり、法定福利費は人件費に入れる、など実際に担当して知ったことも多いですね。
当たり前のことなのかもしれませんが、私は普段財務会計に全く関わらない業務なので初めて知りました。

ちなみに私は2回の実務補習で、1回目は一番自信のない財務、2回目はリーダーの経営戦略を希望したよ。
実務補習は1回5万円払っている勉強なので、普段やっていないことの方が得られるものが多く、得な気がします。
なんか変な貧乏根性でちゃってる。

本を読んでおこう
初めての実務補習では、事前に本で勉強しておくとスムーズです。
どんな流れで課題抽出や提案を行うかのイメージを持つため、使えるフレームワークを知るために私はこの2冊を読んでおきました。
事前に送られてくる実務補習テキストを熟読することも有効です。
wordを勉強しておこう
提案書はwordで作成します。
誰か詳しい人がいれば問題ないのですが、意外とwordに苦戦します。使う機能としては以下の点を押さえておけばよいかと思います。
- 見出しの書式設定
- 目次の自動設定
- 表紙をつける
- 目次の後からページ番号をつける
- バラバラのファイルをひとつにする(これをマージという。いわゆるがっちゃんこ)
- 画像を挿入する
- コメントを入れる
ここでは詳しく書きませんが、検索してやり方を調べておきましょう。
私の1回目の実務補習では、4日目に見出しの後からページ番号をつけるのに苦戦してなかなか印刷ができず、kinko’sが閉まるギリギリになりました。
2回目では目次を付けた時に段落がおかしくなり、どうやって直すか必死で検索してだいぶ時間を使いました。
普段ExcelやPowerPointばかり使っているのでwordは苦手です。。。
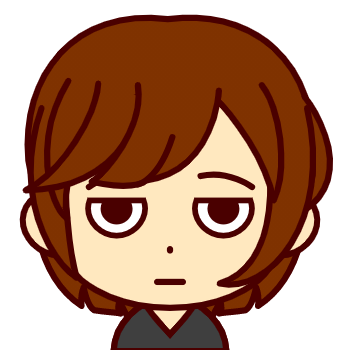
wordじゃなかったら絶対もっと早く終わる
と、誰もが思っていますが、協会の決まりなので仕方ないです。
補助金や助成金を調べておこう
設備投資や新しい事業を提案することもあります。その際に補助金や助成金を合わせて提案すると喜ばれます。
診断する企業が分かってからでも良いですが、どういった業種の企業がどんな用途の場合に使えるかを事前に確認しておくと時間短縮になります。
補助金であれば以下を押さえておくと良いです。
- 小規模事業者持続化補助金
- IT導入補助金
- ものづくり補助金
- 事業再構築補助金
その他は自分の「住んでいる県や市+助成金・補助金」と検索すると、一覧になっているサイトなどがあります。
この記事の最後に紹介しています。

資金調達では「クラウドファンディング」も使えるよ
そう、補助金・助成金ではありませんが、クラウドファンディングもお忘れなく。よく分からない人は調べておきましょう。
SDGS・カーボンニュートラルについて理解を深めておこう
必ずしも関係するとは限りませんが、時流として知っておいた方が良いです。
国策がいろいろありますので、それらを活用したり、提案の根拠にしたりできます。
webマーケティングについて理解を深めておこう
こちらも業種によりますが、webマーケティングは中小企業の施策として大きな資金を必要とせずに行えるというメリットがあり、提案の幅が広がります。
ホームページの役割やWEB広告の種類についての理解、YouTubeやSNSの活用方法、かかる費用などを勉強しておくと良いです。
意外といろいろあるね。


そうだね、実際全部使わないかもしれないけど、実務補習後に補助金申請の支援などでは使うから勉強しておいて損はないね。
いつでもいいけど事前にやっておくと良いこと
いつでもいいですが、やっておいた方がいいことを紹介します。
実務補習の申し込みシミュレーションをしよう
これは、意外と実務補習を申し込みする手続きに手間取るからです。
申し込みはWEBか郵送ですが、ほとんどの人がWEB申し込みをすると思います。
特に東京は激戦であっという間に募集枠が埋まります。さっと入力できるように事前準備が重要です。
協会HPで必要事項の確認
まずは協会HPで必要事項を確認しましょう。
令和4年2月の実務補習は、令和3年度受験生は1月14日(金)の10:00から申し込み開始です。
申し込みにはMYページ登録が必要でが、このリンクから申し込みできるようになります。
記入情報の確認
郵送用の申し込み用紙がありますので、これをwordでダウンロードして記入しておきましょう。申し込みが開始したらすぐにコピペで入力きるようにするためです。
焦って入力ミスをするのも防げます。
そこまでする?と思うかもしれませんが、卒業年度や2次試験の受験番号なども必要ですので突然言われても分からないものもあります。事前に確認しておきましょう。
 これは1分1秒を争う戦いなのです!
これは1分1秒を争う戦いなのです!
入金をする
登録が完了したらひとまず安心です。
忘れずに入金をしましょう。
WEB申し込みができなかったら・・・
そんな時は最終手段、郵送です。
郵送の募集枠は東京でも5名とものすごく少ないのですが、WEB申し込みができなかったらすぐに郵送に切り替えて申し込みできた、という話を聞きます。
郵送の場合は支払いを済ませてから申し込みになりますので、WEB申し込みができなかったら振込みダッシュです。
その場合にも郵送用の用紙の記入は役に立ちますね。印刷して持っておけばいいですね。
気合がすごい・・・


私はこのコピペ登録戦法で受付開始と同時に申し込みを済ませ、激戦区東京の7月を勝ち取った勇者なのです。ちょっとでも手間取ると7月枠は逃すと思われます。
ちなみに、MYページのログインIDが分からなくなったりしますが、登録時のメールアドレスがIDです。(←重要)
次回の募集は2月開催のみなので問題ないですが、7月、8月、9月は同じ日に募集を開始してそれぞれ個別に申し込みが必要なので注意しましょう。
ドロップボックスが使えるようにしておこう
実務補習の資料共有はドロップボックスで行います。
ドロップボックスて何?と思った方はこちらで確認しておきましょう。フォルダを共有できるツールです。
ブラウザ版でも使えますが、アプリをダウンロードしておくとフォルダに入れたまま編集ができるので便利です。
容量によって無料版と有料版がありますが、ひとまず無料で大丈夫です。
ドロップボックスは実務補習後も何かと使うのでいずれ有料版にする人も多いです。

今のところ私は無料版で生き延びている。
仕事の調整をしておこう
実務補習期間は5日コースの場合は、最初に土日の2日間あり、1週間後の土、日、月の3日間の5日ですが、その間の期間は通常の仕事をして、帰ってから作業をすることになります。
その間はできるだけ作業に充てられるよう、事前にできる通常の仕事はやっておきましょう。
私は7月の実務補習と会社の大き目のプレゼンが重なっていて、さらにその少し前の6月には補助金申請と研究会の発表資料作成などもあったので、5月から会社の資料作成に着手してかなり早めに終わらせていました。
ブログも実務補習後の分まで先に書いておいて、この期間は他のことをしなくていいように調整していました。
結果的に相当バタバタするのですが、事前の調整としては万全です。
道場のセミナーと企業診断の執筆も同じ時期だったね

そうなんですよ、、重ならないようにしていたはずなのにいつの間にか重なっていました(笑)
ヒアリングまでの準備
実務補習の1週間前くらいになると指導員から連絡がきます。
事前に調べておくことなどの指示がありますので、それに従いましょう。
何も言われなくても以下のことをやっておくとスムーズです。
ヒアリング内容を考えておこう
だいたいは考えておくよう指示されますが、私は何もしなくてよいと言われました。
準備がなくて楽だったのですが、その結果1日目に集合してから考えることになり、ロクな質問ができませんでした。
ですので、たとえ担当が決まっていなかったとしても、考えておいた方が良いです。
事前に送られてくる「業種別のチェックポイント」(持ち物参照)というExcelファイルに質問項目がありますので、確認して、課題抽出のために何を聞けばいいだろうか、と決めておきましょう。
業界知識をまとめておこう
業界知識を事前に調べる手段として「業種別審査辞典」が有名です。
ものすごい分厚い辞典なので、購入する必要はなく、図書館で必要箇所をコピーしたりメモしておけば良いです。
ただし、必ずしも必要なわけではないです。ネット検索で分かることも多いです。
興味がある人は図書館で見てみても良いと思います。色んな業種の情報が載っていて辞典自体は面白いです。

ちなみに図書館の本をスマホで撮影するのは禁止されているよ。
会社名を検索して会社の記事や口コミがないか探しておこう
会社のHPを見ておくのはもちろんですが、会社名を検索してGoogleマイビジネスの口コミやネット上の記事の確認も企業情報の収集に有効です。
Googleマイビジネスって何?という人はこちらを参照ください。
会社の理念や社長の思い、沿革や従業員数なども見ておきましょう。
のちのちSWOT分析をしますので、その視点で見ると良いです。
ディスカッションに使えるフォーマットを用意しておこう
ディスカッションをする時には誰かが記録する必要があります。
ヒアリング→ディスカッションしながらSWOT分析 という流れになるので、そのフォーマットを用意しておくとスムーズです。
私の場合は、PowerPointを用意して、実務補習に必要な情報と企業情報、参考にしたリンクをひとまとめにしていました。
かなり適当ですが、当日用意するよりはマシです。こんなかんじのものです。
HPを見て重要そうな部分は切り取って貼り付けておいたり、リンクをつけておくと資料作成の時に楽です。
報告書作成の留意点をまとめておこう
2回目以降の場合は誰かが持っていることが多いですが、報告書を作成する時のフォントやリスト表示、言い回しについての留意点をまとめたものがあるとスムーズです。
例えば、フォントサイズや行間の設定、見出しの装飾などの書式設定から、西暦か和暦か、数字の単位は円か千円か、社長の呼び方、自分たちの班の呼び方、言い切りかですます調か、などの書き方のことです。
書式は実務補習テキストに指示がありますので、それを元にして書き出しておき、細かい点は集まってから決めても良いです。
最初にこの書式でフォーマットを作成して、それをコピーして個人で文章を書いていく作業をするのが後々マージする時に楽です。
できるところはフォーマットに記入しておこう
上記のフォーマットを作ったら、現時点でわかること、入力できるところはやっておきます。
PEST分析はヒアリングをしなくてもできそうですね。
商圏マップを作ってみよう
業種にもよりますが、企業の商圏の人口統計などを事前に調査してマップにしておくと施策の提案に使えます。
jstadmapという地図アプリで作成できます。jstadmapの使い方は中小機構で説明されています。
会場近くのkinko’sの場所を調べておこう
最終的に印刷したものを診断先へ提出するのでkinko’sを利用することが多いと思います。
打合せしていた会議室の近くのkinko’sの場所と営業時間を確認しておくとスムーズです。
4日目に利用しますが、日曜日なので営業していなかったり、営業時間が違っていたりするので注意です。
気合がすごい・・・


オニだからね。
使えるサイト情報
最後は実務補習で役立つサイトです。
財務の業界比較や商圏分析、補助金や助成金の検索などで使えるので参考にどうぞ。
その他統計資料全般
さいごに
いかがでしたでしょうか。
ここまでやらないといけないの?と思いましたか?
いや、ここまでやらなくても全然問題にないよ。

そう、やらなくても全然大丈夫です(笑)
私的にはそんなに変なことだと思っていませんが多分ちょっと変(やりすぎ)なのかもしれませんね(笑)
ただ、たくさん準備したことは決して無駄にはなりません。実務補習自体スムーズに進みますし、その後も生かせる知識が身に付きますよ。

これくらい普通だよ、もしくはもっと準備するよ、という人はぜひお友達になりましょう!![]() このお面、余ってるんで。
このお面、余ってるんで。
なぜこんなに準備をしているかと言うと、冒頭の通り、事前準備がすべてというのが私のモットーだから、というのもありますが、1回目の時、全員が初めてで全く準備をせずに丸腰で挑み、いろいろと手間取ったからです。
みんなで苦労しました(笑)
4日目の朝4時過ぎまで作業をして2時間だけ寝ようと思って3時間くらい寝てしまって、慌てて身支度をして会議室の会場へ走る、という経験をしました。
アラフォー女子のやることではありません。課題の終わらない大学生のやることですw
こんな準備の甲斐もあり、めでたく2回目はだいぶ早く進みました。
ということで、これでカンペキ実務補習の準備でした。
時間がある人はいろいろやってみても良いかもしれません。時間がない人はできる範囲で少しでもやっておくとちょっと楽です。
では次回は2次筆記試験の合格発表後にお会いしましょう!あと8日ですね!

明日は池やんです。お楽しみに!
masumiのその他の記事はこちら
★★★★★
いいね!と思ってもらえたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
にほんブログ村のランキングに参加しています。
クリックしても個人が特定されることはありません

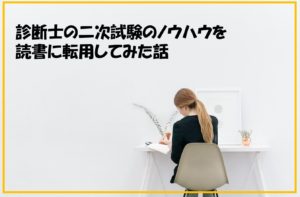

masumiさん、あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します!
実務補習の記事をありがとうございます。
個人的に「待ってました!」という記事の内容でした!
内容も非常に詳細に書かれていて、「実務補習の事前準備をがっちりやっておきたいタイプなんだけど、どうしたらいいのか分からないなぁ」という自分の悩みが一気に解決しました!
自分も、もしかしたらmasumiさんと同じくらいに事前準備をきっちり行って、後ですっごい楽をしたいタイプなので、めちゃくちゃ気持ちが分かります!(ただし、準備の質がいいとは言えない……)
また、ある意味一番重要とされる申込についても説明をして頂いたのがとても助かります!
本日から、過去に試験合格された方の申込が開始されるので、今の内にシミュ―レーションしておこうと思います。
合格発表まであと8日ですが、よい結果になることを前提に今からwordの練習をちょこちょこ進めていこうと思います!
今年一年、12代目の皆さんが担当される時間は短いですが、最後まで応援しております!
ロムさん あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします(^^)
コメントありがとうございます。以前ロムさんにご要望いただいていた実務補習の記事がようやく書けました。
1回目の時に後でブログで伝えよう、と思ってメモしていたんですよね。
ロムさんも準備万端にしておきたいタイプとは!
診断士関連のことって、これまで出会ってきた「これくらいできるでしょ」の範囲をかなり超えてきます(笑)
MAX頑張ってなんとかなる、レベルのことばかりなのでだいぶ鍛えられますね。
ぜひ今からできることをやってみてください。
もうすぐ合格発表ですが、ロムさんの朗報を祈っています!