【今年二次にリベンジするあなたへ】~合格に向けてまずやること~ by だいだい

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
一発合格道場ブログを
あなたのPC・スマホの
「お気に入り」「ブックマーク」に
ご登録ください!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ご案内

リアル桃鉄🍑診断士(登録前)(※)のだいだいです!
まずはご案内!
(※)なんそれ?の方が多いと思うので、ご案内の次もチェックしてくださいねっ!
①令和7年度 中小企業診断士試験実施スケジュール
詳しくは協会ホームページをご確認ください。
スケジュール
| sすkすkう | 試験日程 | 申込受付期間 | 合格発表日 |
| 一次試験 | 令和7年 8月2日(土)・3日(日) | 令和7年 4月24日(木)~5月28日(水) | 令和7年 9月2日(火) |
| 二次筆記試験 | 令和7年 10月26日(日) | 令和7年 9月2日(火)~9月22日(月) | 令和8年 1月14日(水) |
| 二次口述試験 | 令和8年 1月25日(日) | ー | 令和8年 2月4日(水) |
なお、令和7年度から中小企業診断士試験はインターネットによる受験申し込みに変更する予定です。
それに伴い、従来実施していた試験案内・申込書の配布は行いません。 ※協会ホームページより抜粋
②道場春セミナー → 好評につき定員に達しました!

絶賛申込受付中!申し込みはこちらからどうぞ!
※定員になり次第、受付終了となります。
- 日 時:4月26日(土)13:00~15:00
- 形 式:ZOOM
- 定 員:先着30名(集まり次第終了)
- 参加費:無料
- 内 容:道場メンバーとの座談会
一次試験対策、二次試験対策それぞれでブレイクアウトルームに分かれて座談会を行います!診断士試験界隈では知らない人はいない?!あのスペシャルゲストも参加予定!!乞うご期待☆
3月後半のだいだいはいずこへ
わたしはリアル桃鉄🍑診断士(登録前)として、仕事で日々あちこち全国を飛び回っています!
桃鉄🍑とは
ボードゲーム形式に日本全国を旅するゲームです🎮
世界版もありますよね~
わたしは仕事で日々全国を飛び回っているため、
そのリアル版を体験しているという意味で、
この名前を名乗らせていただいています!
サイコロ振って行き先きめとんの?


さすがにそこまでは。。。
3月後半も様々なところに行きました。
福山(広島県)には駅前にかっこよく福山城がそびえたち、加古川では駅前にヤマトヤシキという老舗百貨店があります。八戸はせんべい汁やサバ、いちご煮(お吸い物)などが有名ですね。水戸には日本三大庭園の一つ・偕楽園があります。訪れたのは「水戸の梅まつり」が終了したあとでした。大船には駅近くにお寺があり、電車の窓から大きな大仏が見えます!

ファッファー!!
だいだい社長!
次の目的地は?


4月は出張ひと段落かな。。
余談はこれくらいにして本題へ!
二次筆記試験で悔しい想いをしたあなたへ

わたしも1年目の二次筆記試験はあえなく撃沈しました。。。
あなたと同じ立場だからこそ、伝えたいことがあります!
二次筆記試験の合格発表から約2カ月半が経ちました。
手応えがなかったものの、微かな可能性を信じて、年明けの合格発表を待つ日々。そして発表当日、恐る恐る試験結果のページをチェック。そこに自分の受験番号はなく、悔しい結果に深く気持ちを落とす。
今年の1月15日はそんな日を過ごされたのではないでしょうか。
試験に懸ける想いの強さや、いろいろなものを犠牲にして費やした勉強時間が長い人ほど、落胆は大きかったと思います。。。
一次から再受験する人、今年二次筆記試験に集中する人、養成課程を選択する人、区切りをつけて別の道を進む人、いろんな人がいると思います。
どの道を進むにしても、自分で納得して決めた道なら正解だと思います!
今回は、今年二次筆記試験にリベンジする人へ向けて、
わたしの経験を踏まえて、「合格に向けてまずやること」を記事にしていきます!
この記事の内容
この記事がどんな記事か、事例Ⅱではおなじみ!「だなどこ」風に説明すると
- だ(だれに)
今年二次筆記試験にリベンジするあなたへ - な(なにを)
合格に向けてまずやるべきことをお伝えします - ど(どのように)
わたしが2年目に取り組んだ内容をご紹介することで - こ(効果)
道筋が整理でき、合格可能性を格段に向上させます!

少しでもあなたの力になれたらうれしいです!
では行ってみましょう!
だいだいの1年目を振り返る
わたしは一次試験1回、二次筆記試験を2回受験しました。1年目はTACに通学していて、一次・二次ストレート合格コースを受講していました。8月の一次試験までは一次の勉強に全集中だったため、二次試験の情報は皆無でした。そして一次試験当日、試験後に自己採点をすると幸いにも合格点を満たしていたので、そこから得たいの知れない二次試験の情報収集を始めました。試験概要や勉強方法などを確認し、引き続き、TACの二次対策コースを受講しました。TACでもらった模範解答は過去3年分しかないため、それ以前についてはふぞろいを用意し、事例Ⅳ対策では30日完成を購入しました。事例Ⅳの計算問題は、どうやら1日一問は取り組んだ方がいいとのことなので、毎朝一問やるようにし、夜は事例Ⅰ~Ⅲの過去問を中心に取り組みました。当時も出張ざんまいで全国各地のカフェやホテルで勉強をしていました。

函館の五稜郭公園駅前のスタバ、富士の富士市中央公園近くのコメダ珈琲、福岡天神駅の新天町にあるマック・・・
いろんなところで勉強したなー☕
そんな慌ただしい毎日を過ごしているうちにあっという間に二次筆記試験の日を迎えます。
決戦の場は立正大学。
試験当日は焦らないように、前週に試験当日と同じ電車に乗り、会場を下見(入り口前まで)していました。そこには同じような考えの受験生と思しき人が数名いたような気がします。そして試験当日、事例Ⅰの開始直後に解答メモを作成するため、問題用紙のホチキスを外そうとするも緊張のせいかなかなか外せず、いきなり焦る。。。
しまった。。ここの想定はできてなかった。。
もちろん、みながここまで想定して準備する必要はないと思いますが、緊張しいわたしは細かいところまで準備したいタイプです。15代目 一蔵さん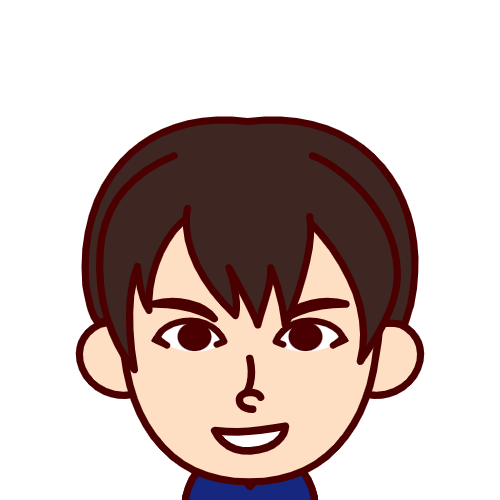 は試験直前に試験官に問題用紙を破っていいか確認したそうです。もちろん、破ったのはこの時が初めてだと思います。
は試験直前に試験官に問題用紙を破っていいか確認したそうです。もちろん、破ったのはこの時が初めてだと思います。
わたしも欲しかったですその対応力・・
15代目一蔵さんの記事を載せておきます!
二次筆記試験当日の細かな描写が描かれており、とても臨場感があります!読んだあとは何かこみ上げてくるものがありました!
その後も会場の雰囲気に飲み込まれて自分のペースを保つことができませんでした。
あまりのできなさ、手応えのなさに、試験中に「来年は二次筆記に集中できるしまた頑張ればいいか」と諦めの考えをしていたことを覚えています。諦めたらそこで試合終了なのに。。
試験後は、一応メモ程度で再現答案(再現答案というほどのものではない)を作り、年明けの試験発表までは道場ブログをたまに確認するくらいで、診断士試験に関することは何もしていませんでした。
そして迎えた2024年1月11日(木)二次筆記試験合格発表当日、淡い期待もむなしく、試験結果ページに自分の受験番号はありませんでした。
関西出張中で発表日の夜に結果を確認しましたが、その後幾時間ぼーっとしていたことを覚えています。
合格した人たちは一様に「手応えなかったし受かるとは思ってなかった!」とおっしゃるので、ひょっとしたらひょっとするかも?と、少しだけ、ほんの少しだけ期待をしてみましたが、やはりそんな甘い試験ではありませんでした。
わたしの1年目をざっと振り返るとこんな感じです。一次が終わってから対策を始めたため、時間がなかったということもありますが、勉強の質について今思えば多分に改善の余地があったと思います。
次の章からはどのように2年目をスタートさせたかをご紹介していきます!
2年目のスタート
いつから勉強再開する? ~勉強スイッチを入れる~
二次筆記試験に集中できる2年目。いつから勉強を再開するか決めていますでしょうか?もうすでに始めている人、まだ先でいいやと考えている人、そろそろはじめなきゃな―と思っている人、理由が明確にあって決めた時期から始めるのであれば、それはいいと思います。ただ、まだ再開時期を決めていない人は、この時期から動き出すことをお薦めします。
わたしはというと、1年目の結果発表後すぐには再開する気力もなく、仕事に、趣味に、友人との遊びに時間を費やしていました。
いつ頃から勉強再開しようかと考えているときに、ふと思い出しました。

TACの先生は確かこんなこと言ってたなあ
僕も2年目で合格したけど、GW明けから勉強再開したよ!
それまでは一切なにもしないと決めていたんだ!


よし、自分は準備をしっかりしたいからその1か月前の4月から勉強を再開しよう!
ということで、4月まではリフレッシュ期間としていました。そしてあっという間に4月に突入。徐々に勉強モードを高めていきました。
なにから始めたかというと。。
1年目の試験で感じたことは? ~失敗から学ぶ~
わたしの1年目の二次筆記試験の結果はこちらです。
| 事例Ⅰ | 事例Ⅱ | 事例Ⅲ | 事例Ⅳ | 計 |
| 58 | 48 | 50 | 47 | 203 |
まずは合格までになにが足りないのかを考えました。どの事例もA評価はなく、圧倒的に知識が不足していたと思うのですが、それ以外にも自身の性格や癖を理解したうえで戦い方が構築できていなかったと感じました。そして”失敗”の粒度は問わず、ひたすら改善が必要なことを書き出しました。
書き出した内容を一部ご紹介します。
- 各事例のお作法の把握が不十分だった
- 与件文に出てきた言葉からキーワードの連想ができていなかった
- 直近3年分の過去問はTACの模範解答しか見ていなかったので、それを唯一の正解と思い込んでいた
- 試験中のルーティン構築が不十分だった
- 解答メモの作成方法が、頭でわかっていたが事前に実践してなかったので本番中に手間取った
- 与件文の重要そうなところにマーカーは引いているが、一色だったので見返した時にそのマーカー箇所がどこで使う内容なのか、再度把握するのに時間がかかった
- そもそも場の雰囲気に飲み込まれて、緊張して与件文を読んでも頭に入ってこなかった
- 与件文を読むことに時間を要し、下書きの時間が取れず何度も消しゴムを使いながら解答を作成した
そのうえでいつまでに何をすべきかを考えました。
試験までに何したらいい? ~改善策を考える~
抽出した”失敗”を克服するための改善策を考えます。各事例のお作法の理解を深めるには該当の道場ブログを確認するも良しです。
わたしは13代目まよさん のブログを見て各事例のお作法を理解していました。
のブログを見て各事例のお作法を理解していました。
とっても勉強になる記事ですので掲載しておきますね。
それ以外にも、
- 与件文に出てきた言葉からキーワードの連想ができていなかった
⇨ふぞろいを使って、設問・与件文からキーワードを連想する訓練をする。 - 直近3年分の過去問はTACの模範解答しか見ていなかったので、それを唯一の正解と思い込んでいた
⇨ふぞろいを購入し、受験生のいろいろな解答を確認する。 - 試験中のルーティン構築が不十分だった
⇨どの工程を何分までにやるのかを決め、それに対して進捗管理、残り時間の配分を考える訓練をする。 - 解答メモの作成方法が頭でわかっていたが、事前に実践してなかったので本番中に手間取った
⇨1年目の実際の問題用紙を使って、実際に破ってみる、肌触りや書き心地を確認する。 - 与件文の重要そうなところにマーカーは引いているが、一色だったので見返した時にそのマーカー箇所がどこで使う内容なのか、再度把握するのに時間がかかった
⇨内容によって色を使い分ける。必要に応じてマーカーを引いた際に補足を書き込む。 - そもそも場の雰囲気に飲み込まれて、緊張して与件文を読んでも頭に入ってこなかった
⇨模試を複数回受けて場の雰囲気に慣れる。 - 与件文を読むことに時間を要し、下書きの時間が取れず何度も消しゴムを使いながら解答を作成した
⇨各工程の時間配分を決める。体で慣れるために過去問を解く際は時間になったら終わってなくても次の工程に進む訓練をする。

知識補充や解答プロセス構築はもちろん、メンタル面強化についても改善策を考えましょう!
試験まであとどのくらい? ~残された時間を把握する~
自分にどのくらいの時間が残されているのかをざっくり知っておく必要があります。試験日までの日数はみな平等です。しかし、試験日までに使える時間はひとそれぞれです。さきほど話した通り、まだ具体的に勉強再開時期を決めていない人がこの時期に動き出した方がいい理由はここにあります。改善策を洗い出し、仕事や家庭環境などを考慮したうえで、試験日までに残された時間はどのくらいあるのか、ここで余裕があるなと感じる人は間に合うようなスケジューリングをすればいいと思います。わたしのようにやること山積み・・という人はこのタイミングであればまだ半年以上あります。巻き返しはいくらでもききます。

ちなみに今日から二次筆記試験まではあと208日です!
陥りやすい失敗は? ~2年目の落とし穴を知る~
2年目は二次筆記試験に集中できる分、陥りやすい落とし穴があります。
- 過去問の与件文・解答を丸暗記してしまう
何度も同じ過去問を解いていると、そのつもりがなくても内容を覚えてしまいます。その部分だけ記憶をリセットできる人はいいですが、普通の人はできません。
覚えてしまうこと自体が悪いわけではなく、解答プロセスや解答がおざなりになることが問題です。
いくら数をこなしても、同じ問題は二度と出ないので時間が無駄になってしまいます。自分の型通りに解答プロセスを構築できたか?与件文の言葉からキーワードを連想できたか?など、目的をもって取り組みましょう。 - オリジナルな解答を追い求めすぎない
合格率約18%の壁を突破するためには、周囲の受験生が思いつかないような鋭い解答を考えるべきではないか、と考える人がたまーにいます。
ただ、それは大きな間違いです。あなたが持っている武器は一次試験の知識と与件文のみです。奇を衒う解答は求められていません。 - 初見問題対策としてオリジナル問題をたくさん解く
ひょっとしたら推奨派もいるかもしれません。
ただ、わたし個人としてはオリジナル問題は診断士試験と関係ない人が作問している文字通りオリジナル問題なので、優先順位は過去問が上だと思います。過去問を何周も繰り返し、解答プロセス構築や知識補充ができてから取り組んでみるのであればよいと思います。(オリジナル問題が悪いというわけではありません!過去問を優先した方がいいという個人的見解です。)
今年合格するあなたへ
2年目は二次筆記試験に集中できるからこそのアドバンテージもありますし、落とし穴もあります。
1年目の”失敗”は合格するために必要な経験です。
着実に改善していけば合格まで必ずたどり着けます。
診断士試験は合格したい気持ちが強い人が合格できる試験なので。

明日は なつ よろしく!
なにやら事業再生についてのブログだそうで。
ぼくも一緒に学ばせてもらいますっ!
任せて♪

☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)



こんにちは!
にっくです。
だいだいさんの真似をして、改善点を書き出してみました。
・道場の知識を活かせてなかった
・設問文の読み込みが甘かった
・焦りすぎて、問題文の全体構造を意識できていなかった
・気取ることで(戒めを込めて)与件文の内容を活用できていなかった
・下書きに時間を使いすぎていた
・1次知識を使いこなせていない(もしくは頭から抜けてる)
まあ~出るわ出るわ
それ以外の問題点については改善案を出せたのですが、最後の「1次知識を使いこなせていない」だけ、「まとめシートを復習する」位しか改善案を思いつきませんでした。何か具体的にいい方法があれば、アドバイスよろしくお願いします!
にっく
にっくさん
いつもコメントありがとうございます!
わたしも出るわ出るわで・・・お気持ちすんごい分かります。
たださっそく改善案を出せているのは素晴らしいです!
やるべきことが見えてくると少しでも整理されていきませんか?
「1次知識を使いこなせていない」に関しまして、
さらに深堀りをしてみるのはいかがでしょうか?
一次知識の〇〇(科目)の〇〇(論点)に関して、
①定着はしているけど本番頭から取り出せなかった?
②取り出せたけど知識が曖昧で書けなかった?
③そもそも定着していなかった? など
文脈から察するに②かと思いました。
3/31 tomiがアクティブリコールについて記事を書いており、
能動的な学習が知識の定着に非常に有効だと感じました。
疑問解消の一助になれば幸いです。
ありがとうございます!
早速やります!
だいだいさん
素敵な記事ありがとうございました。
今年2次再挑戦の者です。
自己紹介の記事を拝見した時に1回目の2次試験の点数が私が受けた昨年のものと近く、記事を楽しみにしておりました。
「あと数点で合格だった方」とは異なる目線(失礼な言い方申し訳ございません)でのノウハウ、非常に参考になりました。今知りたかった情報が詰まっており、ここから何度もこの記事に戻ってくるなと思いました。
ここからの勉強計画を改めて立てようと思います。
これからも記事を参考にさせていただきます。
なごみさん
コメントありがとうございます!
そう言っていただけると非常に励みになり、また身の引き締まる想いです。
わたしは昨年のこの時期、
・二次特化の予備校へ通うべきか、あるいは独学か(結果的に独学)
・参考書はふぞろいと事例Ⅳ30日完成だけでいいか、あるいはいろいろ買いそろえるか(結果的にその他も購入)
・8月一次の保険受験を受けるべきか、あるいはその時間も二次に集中すべきか(結果的に保険受験する)
など、いろいろ迷いながら勉強を再開したことを覚えています。
今後もなごみさんの合格に向けて、有意義な記事が書けるよう努めますので
ぜひご期待ください☆
大変参考になる記事ありがとうございました。私はマーカーの色と使い方・下書きで悩んでいます汗 マーカーだらけで見づらくなったり下書き⇒消しゴム過多で時間を浪費したり・・・。一度まよさんの記事に入ってみます!
しまんと1号さん
コメントありがとうございます!
まよさんの記事は読みやすく、わたしも非常に勉強になりました。
>マーカーだらけで見づらくなったり下書き⇒消しゴム過多で時間を浪費
非常によくわかります。。わたしも同じ経験あります。。
今後記事にしていく予定ですが、
わたしは1年目はマーカー複数で持ち替えたりしていましたが、
2年目は5色ボールペン1本でカチカチ色を変えながら対応していました。
相性がありますので絶対ではありませんが、S/Oは青、W/Tは赤、社長の思いは緑、など
しっくりくるマイルールができると、スピードが格段に上がるかもですね!
道場にはたっくさんの時間の使い方や解答プロセス構築に関する記事がありますので、
読み漁って、ぜひご自身に合うものを試してみてくださいー☆