2次ベテにならないための教訓シリーズ④ by サトシ
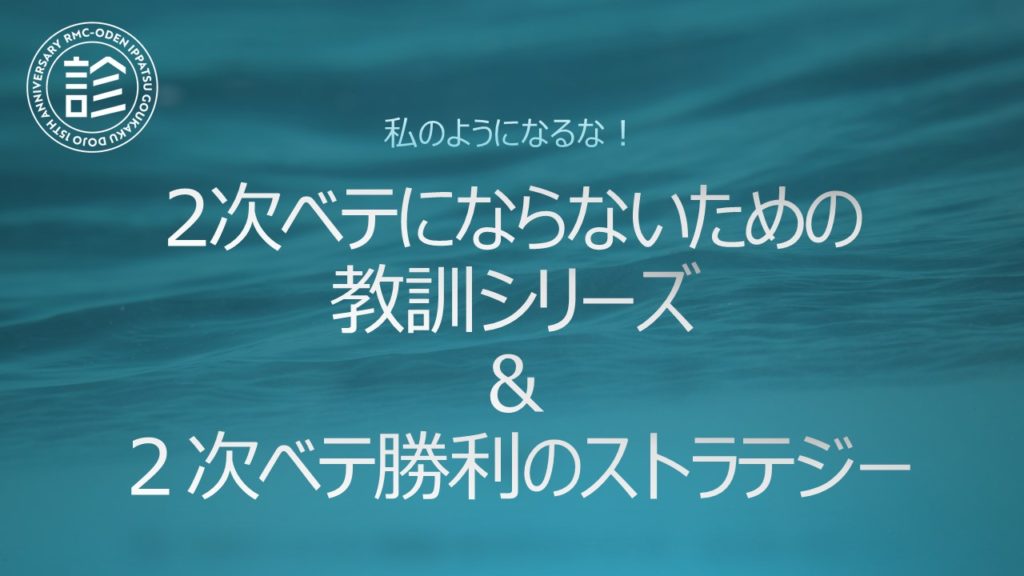
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
一発合格道場ブログを
あなたのPC・スマホの
「お気に入り」「ブックマーク」に
ご登録ください!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
みなさん、こんにちは。
初対面でその人が2次ベテになりそうかわかります、「サトシ」です。

相手が2次ベテになりそうか一発でわかるって、サトシは占い師か!?
勉強会のときの相手の発言内容や性格の癖でおおよそわかるよ
(今回はそんな2次ベテになる人の特徴を紹介します)
.png)
GWも終わり、いよいよ1次の直前期に入りましたね。2次専念の方は、まだ少しだけスケジュール的に余裕があるかもしれません。そこで、今回はそんな方にむけて「2次ベテ(超多年度生)にならないための教訓」シリーズの最終回を、私の受験歴とは違った角度からお送りしてみたいと思います。
- 私の自己紹介はこちら。
- 1回目の記事(教訓・ストラテジーの1~6)についてはこちら。
- 2回目の記事(教訓・ストラテジーの7・8)についてはこちら。
- 3回目の記事(教訓・ストラテジーの9・10)についてはこちら。
私は合格までに8年(途中の充電期間を入れると9年)かかったので、診断士受験に関するほとんどのものに触れてきたと思います。予備校にしても、他の診断士受験生にしても、試験対策のノウハウやスキルにしても、様々なものに触れてきました。無駄なこともたくさんしてきました。
そして、今まで私は多くの受験生と出会ってきました。その中で、「こういう人は2次ベテになる」というのもわかってきました。今回は私と同じく2次ベテになってしまった(なっている)方の特徴を紹介します。上から出会った人数が多い順(=あるある順)になっています。
今回も長いので(いつもすいません)、サクッと短時間で内容を知りたい方は、目次を見てご自身に該当するものや気になるものだけをチェックする形でもOKです。
それでは、今回もよろしくお願いします。
- 1. 細かいところや変なところにこだわる方、完璧主義の方(割り切れない方)
- 1.1. 教訓&ストラテジー 11
- 1.1.1. 解説
- 2. 難しく複雑に考えてしまう方
- 2.1. 教訓&ストラテジー 12
- 2.1.1. 解説
- 3. 早合点する方、飛びついてしまう方
- 3.1. 教訓&ストラテジー 13
- 3.1.1. 解説
- 4. 「習ったら終わり」の方
- 4.1. 教訓&ストラテジー 14
- 4.1.1. 解説
- 5. ネガティブ思考の方、メンタルが弱い方
- 6. 仕事の忙しさを言い訳にする方
- 6.1. 教訓&ストラテジー 15
- 6.1.1. 解説
- 7. 知識(理論)偏重の方、過去問マニアの方
- 7.1. 教訓&ストラテジー 16
- 7.1.1. 解説
- 8. 予備校や講師などの情報マニアの方
- 8.1. 教訓&ストラテジー 17
- 8.1.1. 解説
- 9. 実務のノウハウを出してしまう方、現実の会社への当てはめをしてしまう方
- 9.1. 教訓&ストラテジー 18
- 9.1.1. 解説
- 10. 演習や模試で模範解答を見る、事前に解くなど不正をしてしまう方
- 10.1. 教訓&ストラテジー 19
- 10.1.1. 解説
- 11. 不平不満ばかり言って他の受験生(仲間)のモチベーションを下げる方
- 11.1. 教訓&ストラテジー 20
- 11.1.1. 解説
- 12. 2次ベテは、意識を変えると一気に伸びる
- 13. 次回予告
細かいところや変なところにこだわる方、完璧主義の方(割り切れない方)
2次ベテになってしまう方で最も多く見かけたのが、細かいことや変なところにこだわる人、完璧主義の人です。こういう人は勉強会の際にも発言内容から一発でわかります。
解説講義で「この部分はできなくてもいいですよ」と講師が言ったところや、「そこ、どうでもいいのに」というような変なところにこだわります。完璧主義で妥協することができず、合格のための割り切りができません。
例えば事例Ⅳの本試験問題では、投資の意思決定の問題など、正答率が限りなく0に近いものもあります。そのような難しい問題ができるようにすることにこだわり、難しい問題集ばかりやってしまい、基本問題を軽視してしまうことが2次ベテではよくあります。「基本問題だけ完璧に仕上げよう」と割り切ることができません。
教訓&ストラテジー 11
2次ベテ勝利のストラテジー 11
こだわりは捨て、合格することだけに割り切りましょう!合格することだけに全集中すれば、合格に不必要な部分は気にならなくなります。
解説
2次試験は、多くの受験生が取れている内容(問題)ほど多く加点され、あまり解答できていない内容(問題)は少なく加点される、もしくは全く加点されない特徴があります。
そのため、難しいところにこだわって多くの受験生が取れる基本的な部分を疎かにしてしまうと、点数は伸びません。難しいところは正答率が低いことを考えると確実に正解できる保証はありません。最悪、難しいところも基本的なところも取れなくなり、大惨事となります。
2次試験を受けるたびに合計点が下がっている場合は、この事態に陥っている可能性が高いです。
なお、「2次ベテ勝利のストラテジー4」でも完璧主義のことを扱っていますので、そちらも合わせてご覧ください。また、5月1日公開の一蔵のこちらの記事も参考になりますよ。
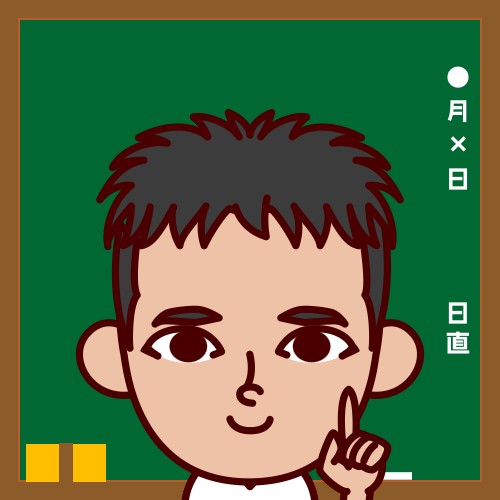
ここは捨てる、ここはできなくてもいい。こう思える勇気を持とう
難しく複雑に考えてしまう方
勉強会で他の受験生の考えたことを聞いてみると、たまにとてつもなく難しく複雑に考えてしまっている方がいらっしゃいます。これも勉強会の際に一発でわかります。
例えば設問文に「組織面の」という制約条件があったとすると、多くの受験生は「人事施策、組織構造、組織文化」くらいをシンプルに想起して終わるのですが、ここで「いや、この場合はバーナードの組織の三要素に照らし合わせて、、いやもしかしたらリーダーシップ理論か?」などと変な方向に考えてしまいます。
教訓&ストラテジー 12
2次ベテ勝利のストラテジー 12
難しく複雑に考える必要はありません。シンプルに行こう!
設問文や与件文の内容を解釈する際には、「自分がした解釈は他の受験生(特にストレート生)が考えに至るものか」を意識してみましょう。
解説
難しく複雑に考えてしまうと、2次ベテ路線を突き進むことになります。2次試験の受験が3~4回目くらいになってくると、難しく複雑に考えてしまうことが癖になってしまい、シンプルに考えることが逆に難しくなってしまいます。
難しく複雑に考えてしまうのは、2次試験そのものや2次試験の他の受験生を過度に神聖視するあまり、自分の実力以上のことを考えないといけないと思ってしまうことが背景にあります。
しかし、そんな難しく複雑な考えをしている受験生は他にほぼいません。道場15期メンバーの13人で言うと、難しく複雑に考えるのは私くらいで(笑)、他の12人はそんな考えは全くしていないイメージです。
そのため、解釈の時点から多くの受験生とズレていることになり、多くの受験生が取れるところが取れない結果につながり、点数が伸びません。
また、意外ですが基本レベルの想起ができていない可能性もあります。求められている王道の内容が出てこないため、自分が思いついたことが出てきたら強引にその内容に都合の良いように解釈してしまうのです。それが結果として難しく複雑に考えていることにつながっているケースもあります。この場合は、要求解釈力が足りないだけなので、要求解釈のトレーニング(設問文を見て必要な想起をするトレーニング)を行えば短期間で解消できます。
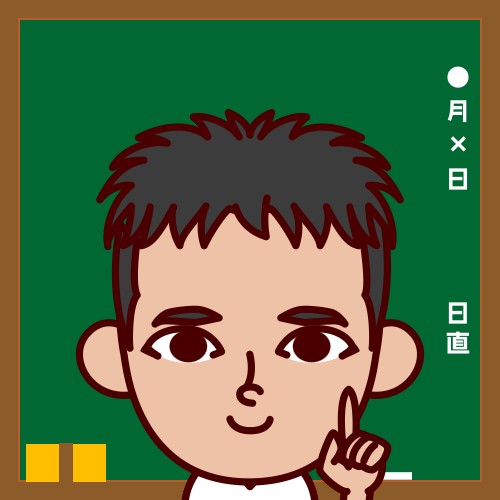
基本レベルや王道の想起、基本ができること。これを徹底しよう!
早合点する方、飛びついてしまう方
これ、完全に私です(笑)
だからでしょうか、勉強会の際に設問内容や与件文の文言から飛びつく方がいると、心境がとてもよくわかります。
問題を見た瞬間に「よっしゃ、これだ」と早合点してしまうのです。本当は違う解釈をするのが正解だとしても、「これだ」と決めつけているので、正しい解釈ができるチャンスはなくなります。
例えば「生産面」という制約条件を見た瞬間に「あぁ、生産管理のことね」と決めつけてしまうのです。実は生産現場のこと(設備やレイアウトなど)が求められていたのに、最初から生産管理のことと決めつけているので、生産現場のことが出てくる可能性はなく、正しい解釈はできません。
また、与件文(事例企業の内容が書かれている文章)の中に解答根拠を見つけた瞬間に、「はい、これね」と飛びついてしまうパターンもあります。他の解答根拠のことは無視して、そこだけでドヤ顔で解答を作ってしまいます。
教訓&ストラテジー 13
2次ベテ勝利のストラテジー 13
「よっしゃ!これだ」と思ったら、「他にはないか?」を考える癖をつけよう!
解説
設問文の解釈の場合、あえて想起する内容を増やすようにしましょう。先ほどの生産管理の例なら、「他にはないか?」を考えることで生産現場や製販会議、発注のことも想起することができます。
要求解釈トレーニングにより想起の経験を積み、王道の内容の想起が安定してできるようになると、自然と多くのことが想起できるようになります。私はこれで飛びつきの癖を解消できました。
与件文中の解答根拠の場合、「よっしゃ!これだ」と思ったとしても、あえて「他にはないか?」を考えてみましょう。「あれ?ここの内容を思い切り解答に書いてもまだ字数が足りないぞ」と思ったら、まず間違いなくこのパターンに陥っています。そうなると、間違った解釈をしたり解答内容が不足したりするわけですから、やはり点数は伸びません。
与件文中の解答根拠については、飛びつきをして解答内容が不足する事故を何回か起こしていくと(経験を積んでいくと)、与件文中の解答根拠を見て飛びつきそうになっても「他にはないか?」と考えられるようになります。
ちなみに、私のいたTAC名古屋校ではこのような飛びつきをすると、津田先生(まどか先生)からこう言われます。私も飛びつくたびに何回も言われました(笑)
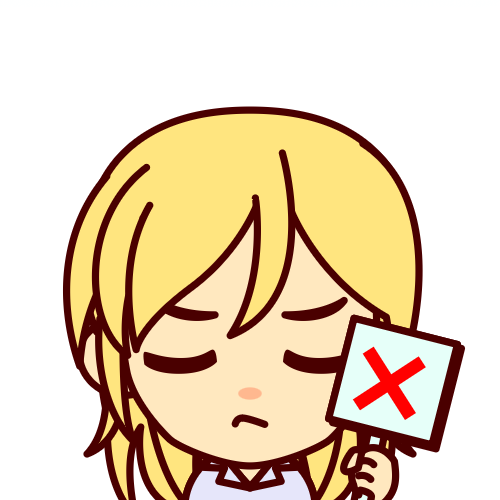
飛びつきNG!「他にはないか?」をしっかり考えよう
「習ったら終わり」の方
これは2次対策に限らず、1次対策でも言えます。
この時期は各予備校の2次本科クラスでは知識のインプットの講義が終わっていると思います。1次対策も7科目の基本講義が終わったと思います(答練に入っていると思います)。
しかし、その講義の内容はきちんと復習していますか?
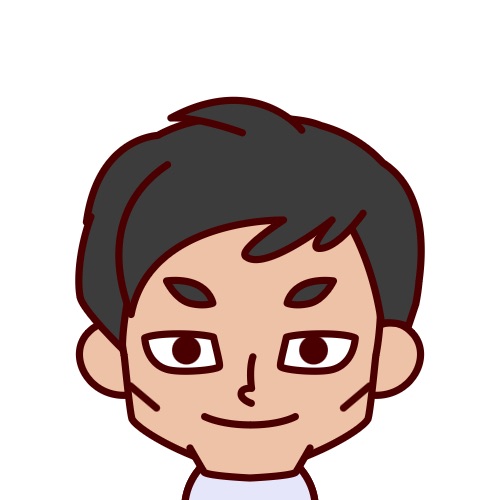
講義の後にやったから大丈夫だよ!
では、その内容についてスラスラ言えますか?例えば生産管理についてスラスラ説明できますか?生産計画と生産統制の種類とそれぞれの内容は言えますか?
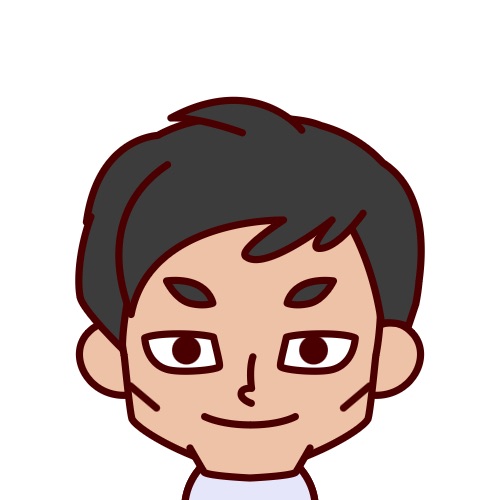
えっと、、、(何だっけ?)
このように、大抵の方は言葉に詰まります。
そう、インプットした内容について定期的に振り返っていないため、忘れてしまっているのです。
テキストを見返したら「あぁ、そうだった」と思い出せても、まっさらな状態だとなかなか知識が出てきません。
教訓&ストラテジー 14
2次ベテ勝利のストラテジー 14
インプットの講義で習った内容は必ず定期的に確認しましょう!
解説
習った知識は「知っている」から「わかる」へ、「わかる」から「使える」へレベルアップさせないと、2次試験には対応できません。
また、有名な「エビングハウスの忘却曲線」にもあるように、知識は定期的に振り返らないとどんどん忘れていきます。そのため、ザーッと見返すくらいでもいいので1ヶ月に1回くらいは振り返るようにしましょう。
上級生や2次専念の方なら時間に余裕があるでしょうから、企業経営理論・財務・運営管理の3科目だけでもいいので、ぜひ知識の定期メンテナンスをやってみてください。
.jpg)
知識の定期メンテナンスは、私の合格体験記にも掲載されています
ネガティブ思考の方、メンタルが弱い方
こちらは私の受験歴のところでたくさん語っておりますので、そちらをご覧いただければと思います。その中にある「教訓&ストラテジー2・6・9・10」がメンタルに関する内容となっています。
やはり、メンタルが弱い方は本試験で力を発揮できず、ミスを連発して不合格になりやすいです。2次試験はそれだけメンタルの要素が強い試験となっています。私も散々、津田先生からメンタルのことを聞かされてきました。

サトシ君はとにかくメンタルね!
また、メンタルが弱い方は合格への「執念」が足りないことも特徴です。合格への執念がないから、強気にいくことができず、本試験前のプレッシャーに潰されてしまい、「あぁ、もういいや」となり、結果として「戦う顔」での受験ができないという流れになっています。仮に本試験の開始時点で戦う顔での受験ができていたとしても、どこかの事例で思うようにいかなかったら途中で諦めてしまい(戦意喪失してしまい)、「戦う顔」ではなくなってしまいます。

戦う顔での受験ができると、周囲の受験生よりも頭が働くので、多少の実力不足ならカバーできます!
仕事の忙しさを言い訳にする方
私が出会った方の中で何人かは、常に仕事が忙しいのか、何かにつけて「仕事が忙しいから」が第一声の方がいました。私はクラスの受講生の声掛け係のようなものになっていたのですが、たまにこのような方に出くわすことがありました。
.jpg)
来週は勉強会に来れますか?
いや、仕事が忙しくてなかなか、、

.jpg)
計算問題集を解く時間って取れていますか?
いや、仕事が忙しくてなかなか、、

.jpg)
勉強時間は確保できていますか?
いや、仕事が忙しくて(以下同文)

こういう方は、勉強時間の確保が苦手な傾向が強いです。
そうなると勉強をしていないので、1次も2次も実力が伸びません。何年もダラダラと受験生活を続けてしまい、結果的に2次ベテになります。合格することよりも、勉強時間を取って勉強することが目的になってしまいます。
また、仕事の忙しさを免罪符にすることで勉強をしていない自分を許してしまおうとする心理も働いています。
「今日は勉強できなかったのは仕方ない。だって仕事が大変だったから(その代わり明日はやろう)」と思うことは誰にでもあります。私もそうです。しかし、こう思うことは癖がつきやすく、いつまでも改善に向かいません(ダイエットや禁煙を明日からやるというのと同じ心理です)。
教訓&ストラテジー 15
2次ベテ勝利のストラテジー 15
仕事の忙しさを言い訳にするのはやめましょう!
勉強時間確保が苦手な場合は、忙しい社会人向けの勉強法や時間術の本を読み、そこに書かれている内容を実践してみましょう。勉強時間の確保の仕方がたくさん書かれています。
解説
実際、夜遅くまで仕事をしている方でも合格した方はいらっしゃいます。15代メンバーなら「かます」がまさにそうです。4月17日公開のかますのこの記事によると、大変な中でもルーティンとして勉強時間を確保していたことがわかります。
こういう方は勉強時間の確保の仕方がうまいのです。かますのようにルーティン化していますし、仕事が忙しくて勉強会に欠席する場合でもきちんと代替案(この日は行けます、など)を提示してくれます。運営管理でやった「工数計画」や「余力管理」ができていると言えます。
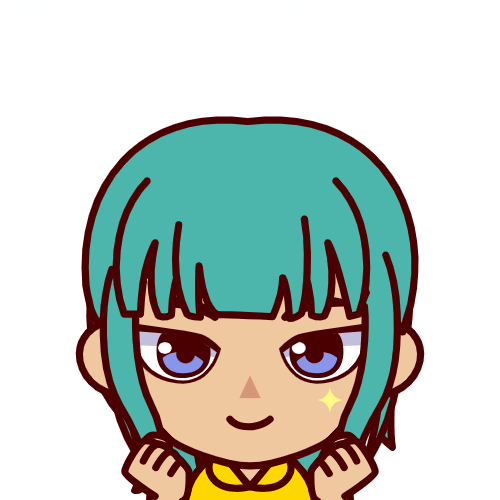
私、仕事の忙しさや通勤時間の長さは言い訳にしません
知識(理論)偏重の方、過去問マニアの方
知識偏重については、解答文に与件文(事例企業の内容が書かれている文章)の内容はあまりなく、代わりに「満足度・愛顧向上、関係性強化」など知識フレーズばかり乱発させている方が該当します。本人としては1点でも多く取れると思ってドヤ顔でいます。
平成の頃はこういう解答を書いても高得点が取れて合格できました。しかし、令和に入ってからは事例企業の中身を踏まえた具体的な解答(その事例企業だから適用できる具体性の高い解答)でないと点数が伸びにくいようになっています。
表面上をすくったような解答や一般論だけでは点数は伸びません。与件文を軽視した理論マニアの解答は良くて50点台となっています。
2次ベテの方が受験勉強を始めた平成末期と令和の時代では、採点に関する環境が変化しています。この変化を受け入れて解答スタイルを変えないと、いつまでも2次試験には合格できません。2次ベテの方で受けるたびに点数が下がっている場合、細かいところへのこだわりや完璧主義が原因の場合もありますが、他にはこの傾向が強いです。
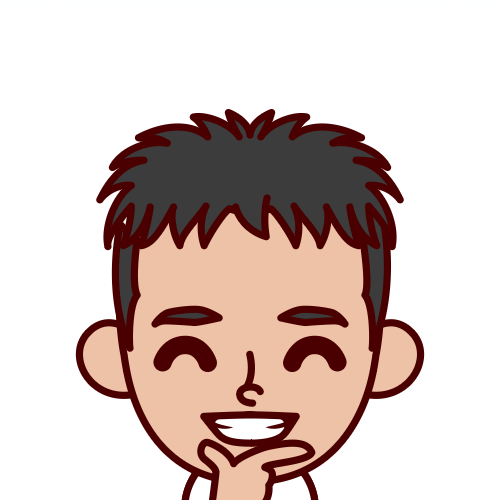
環境変化があったら、、
そう!「柔軟・迅速に対応する」だよね
過去問マニアについては、「今回のこの演習の第1問は、平成18年の事例Ⅰの第1問を参考にして作ったな」などということを他の受講生にドヤ顔で話す人がたまにいらっしゃいます。また、各年度の与件文の内容を暗記している人もいました。
ではそういう方が合格されたかと言うと、していません。大抵はどこかのタイミングで診断士の勉強から撤退しています。
.jpg)
ドヤ顔で言う背景には他人に承認欲求を満たしてほしい思いがあるよ。
診断士は謙虚さが重要だから、承認欲求は自分で満たしていこう!
教訓&ストラテジー 16
2次ベテ勝利のストラテジー 16
事例企業の具体的な内容に沿った解答を心がけましょう!知識や過去問を知ることは大切ですが、マニアになる必要はありませんし、むしろ足かせになり事例企業の中身を踏まえた具体的な解答を書きにくくなります。
解説
知識偏重、過去問マニアの両方に言えることとしては、事例企業に沿った解答をしていかないと合格できないということです。過去に解答した知識フレーズが次の試験にも当てはまる保証はありませんし、過去問と同じ企業は今後の試験には出ません。事例企業の状況は毎回異なります。他の企業の内容をそのまま別の企業にもってきても、点数は伸びません。2次試験はあくまで事例企業に沿った内容が解答として求められています。

マニアとドヤ顔は、診断士では求められていないんだ
予備校や講師などの情報マニアの方
「この予備校のあの先生は無類のワイン好き」とか、「この予備校は令和になってから2次の合格率が低くなった」など、あなたは内部の関係者ですかと言いたくなるような情報通の方がたまにいらっしゃいます。予備校の30人くらいのクラスなら毎年1~2人ほどいます。
また、「この予備校のこの演習がいい」とか「この問題集は何年に発売されて今回この部分が改訂された」など、予備校や出版社の回し者ですかと言いたくなる方もいます。
教訓&ストラテジー 17
2次ベテ勝利のストラテジー 17
現在習っている予備校や講師を信頼し、そこに集中することで余計な情報はシャットアウトしましょう!マニアになっても2次試験合格には1ミリも役に立ちません。知りたければ受かってからにしましょう!
解説
こういう「マニア」は2次ベテにちらほらいます。はい、私もでした(笑)
私はTACに2015年度からお世話になっていたので、講師よりTACの事情に詳しくなっていたようで、飲み会や勉強会の際に「TACに転職しますか?」とか「TACの営業の方でしたっけ?」とよく言われます(笑)
こういう状況になると、講師や予備校、問題集などの情報を集めることが快感になってしまい、合格することに意識が向きにくくなっているため、合格まで何年もかかってしまいます。
また、教訓シリーズの1回目でも出しましたが、「昨年はこの予備校、今年はあの予備校、落ちたら来年はそっちの予備校」というように、予備校を転々としている方が毎年何人かいました。同じ予備校内でも校舎や講師をコロコロ変えている方もいました。こちらも様々な講師のノウハウを得ることが目的になってしまうので、2次ベテまっしぐらとなります。
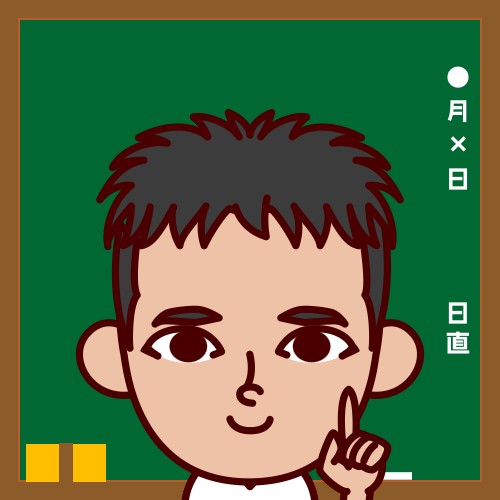
マニアやコレクターに憧れるのはやめましょう!
実務のノウハウを出してしまう方、現実の会社への当てはめをしてしまう方
これは年配の方に多い傾向です。豊富な実務のノウハウや経験があることから、事例問題にもそれを適用してしまい、こう考えてしまいます。
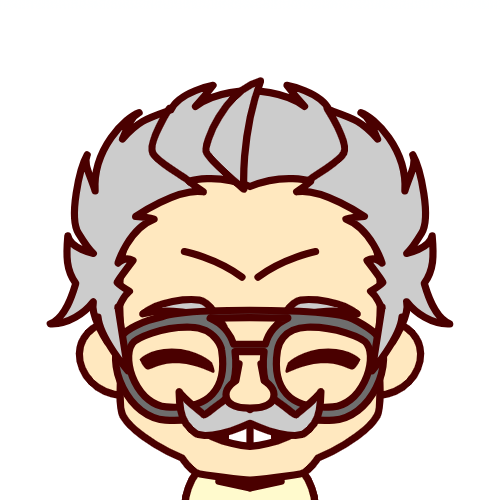
この問題は仕事でよく使うこのノウハウを使えばいいな
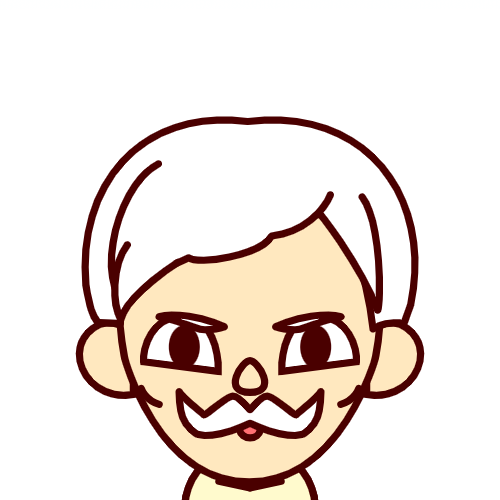
こんな設定、実際の会社じゃありえないよ
教訓&ストラテジー 18
2次ベテ勝利のストラテジー 18
実務のことや実際の企業のことは封印し、事例問題は事例問題と割り切ろう!
解説
当然ですが、実務のノウハウや経験はその方にしかありません。公平さが求められる国家試験でそのような内容が解答に求められているわけはありません。もちろん先ほども出ました「事例企業の中身を踏まえた具体的な解答」にもなりません。
このように、多くの受験生は解答しない内容なので、実務のノウハウをドヤ顔で解答しても点数は伸びません。
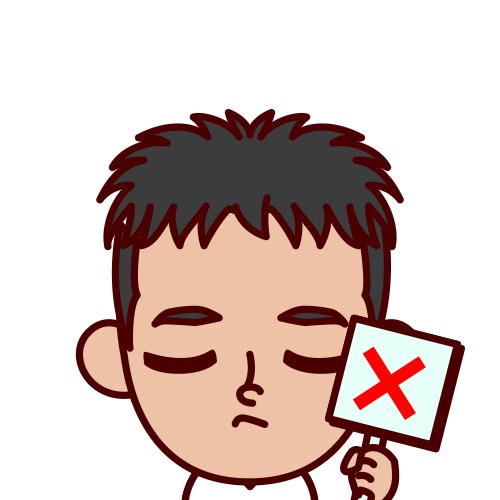
ドヤ顔NG!
演習や模試で模範解答を見る、事前に解くなど不正をしてしまう方
これは通信生に多い傾向ですが、通学生も1クラスに数人は存在します。
演習や模試で明らかに「これは答えられないだろう」という要素を答えていたり、模範解答と全く同じ文言で書いていたりすることが特徴です。
基本的にプライドが高い方、優劣や順位にかなりこだわる方が該当します。他人に負けること、できないこと(演習なら低得点、模試なら悪い判定を取ること)が明るみになるのが怖くて不正をしてしまうそうです。
詳しい内容・やり方は不正誘発防止のため割愛しますが、通学生でもこのような不正が一部では行われています。勉強会で他の方の解答を見る機会があると、すぐに「やっている」とわかります。
教訓&ストラテジー 19
2次ベテ勝利のストラテジー 19
演習や模試は真面目に受けましょう!
真面目に受けたのなら、順位や評価は一切気にする必要はありません。
解説
こういう不正をすると、得点や順位もかなり伸びてしまいます。演習なら簡単にクラストップの成績になります。模試なら自身だけでなく他の受講生の判定にも影響してしまいます。実際、上位のランキングやA判定がほぼ通信生(自宅受験)で独占されている模試もあります。
当たり前ですが、ドーピングをしているようなものなので、自分の本当の実力とは異なります。また、本試験ではそのような不正はできないため、いつもと勝手が違ってしまい落ち着いて問題を解くことができません。ミスを何ヶ所もしてしまい、結果として何年も不合格になり続けてしまいます。
ちなみに、通学生の場合だとこの不正は講師にはバレています。その人の解答と模範解答を照らし合わせたら簡単にわかります(私でもわかります)。証拠がないし、本人に直接言うことで問題になる可能性もあることから、あえて言わないだけです。
しかしこのままだとクラスの他の受講生への影響もあることから、演習や模試の解説の際に、誰がやったかは特定しない形で警告を出している講師も何人かいました。
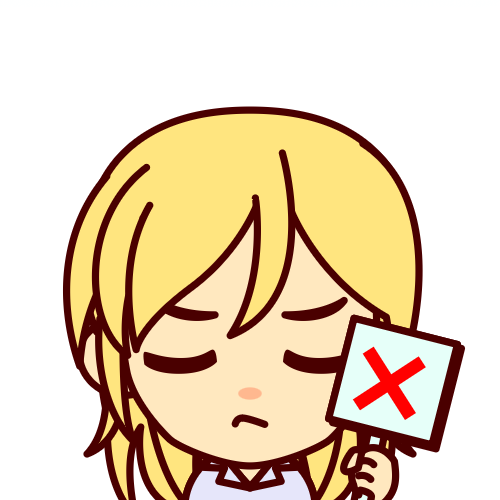
不正はダメ!ゼッタイ。やったらすぐにわかるからね
不平不満ばかり言って他の受験生(仲間)のモチベーションを下げる方
これは8年の受験生活で2〜3人くらいしか出会ったことはありませんが、一応いらっしゃいます。こういう人も2次ベテです。
演習のたびに「あんな問題、できないよ。こんなの本試験で出るわけないよ」と大声で周囲に愚痴や不平不満を言い、他の受験生のモチベーションに悪影響を及ぼしています。「できない」と周囲に言うことで、できない自分を正当化しようとする心理があります。
教訓&ストラテジー 20
2次ベテ勝利のストラテジー 20
「できない」は言わないようにしよう!スモールステップや超基礎まで戻ることによって「できる」ようにしていきましょう!
解説
仕事でも言えることですが、「できない」なら、できるようにするしかないです。本人の能力が低いのではなく努力が足りないだけです。スモールステップで確実に進んでいけば必ずできるようになります。愚痴をこぼすくらいなら、問題集を1問でも多く解きましょう。1つでも多く暗記しましょう。思い切って基本レベルに戻ってもいいです。とにかく前に進みましょう。
ちなみに、当たり前ですが他の受講生に対して直接ネガティブなことを言う人も、ネットの掲示板に他の受講生や講師の悪口を書く人も、2次ベテまっしぐらです。
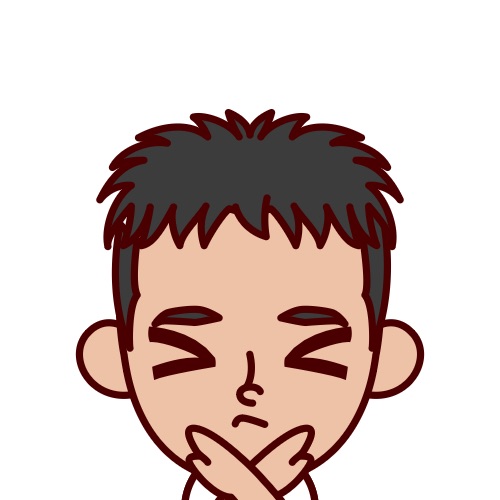
ネガティブなことを言うのは合格後も損をするよ
2次ベテは、意識を変えると一気に伸びる
最後に、2次ベテの方にとっての意識改革の必要性について述べさせていただきます。
2次ベテの場合、知識やスキルを増やす余地はあまりありません。イメージとしては、ミクロ経済学の最初のほうに習った生産関数のような収穫逓減です。「勉強時間」という生産要素を投入しても、「実力の伸び」という生産量が徐々に限界生産物が低下していきます。今のままやり続けても、おそらく実力(点数)の伸びはほとんどありません。もちろん私もそうでした。

生産関数はミクロ経済学の最初のほうにある論点だね。グラフの形、平均生産物と限界生産物の違い、どちらが大きいか、利潤最大化の要件は覚えていますか?
いや、先生。今は実力の伸びのことで例えただけですよ…
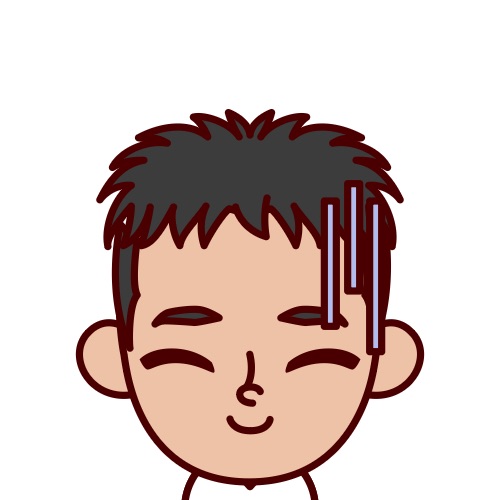
しかし、ここまでの内容にあるものでご自身が該当するものを改善させることで、取り組み方が変わり、一気に次の段階にジャンプアップします。
イメージは、企業経営理論でやった技術革新の非連続性のグラフ(S字グラフが2つ並んでいるもの)です。S字単体だと、生産関数のように収穫逓減になっています。しかし、意識改革をして次のS字にジャンプすることで、慣れるまでは一時的に実力は下がるかもしれませんが、慣れると一気に実力や点数が伸びます(経済で言うJカーブ効果と同じ理屈です)。意識改革をして次のS字にジャンプし、そこでさらに実力をつけていくほうが、合格可能性は高まります。

(内閣府 平成24年度年次経済財政報告 コラム1-4図から引用)
今日の私の記事、おそらくいくつかは耳の痛い話もあったと思います。しかし、逆に言えばそこさえクリアできれば一気に好転します。むしろ絶好のチャンスと捉えていただければ幸いです。
.jpg)
大丈夫です。メンタルが最大最強の壁だった私だって合格できたんです。みなさんも合格できます!
次回予告
ここまで、2次ベテにならないための教訓と、2次ベテが合格するための「勝利のストラテジー」を4回にわたって見ていきました。長々とした私の記事にお付き合いいただき、ありがとうございました。
次回から2回にわたり、これらの教訓と勝利のストラテジーをもとに、2次ベテの得点戦略についてお伝えします。次回もよろしくお願いします。
明日は定休日です。明後日は「ごり」の登場です。ん?なぜかキラキラしているぞ。
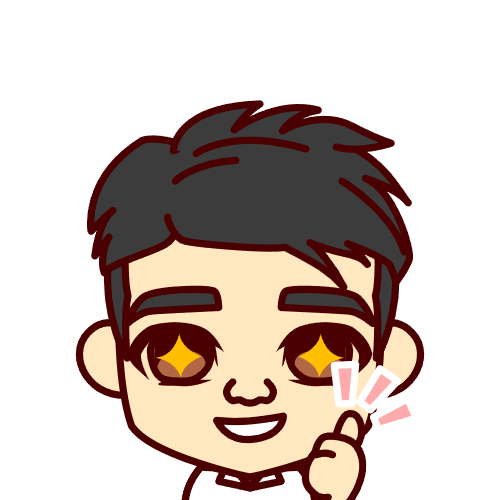
そろそろ1次対策に本腰を入れていこう!
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)



こんにちは!にっくです。
「中小企業診断士に必要なこと」というよりは「良き大人であるために必要なこと」を学んでいる気がして、真摯に読ませていただきました。
今や過去の自分に当てはまるものが何個もあり、「ああ、こんなこともあったな・・・」と走馬灯を見ているようでした・・・笑
サトシさんのお仲間にぜひ私も入れていただきたいです!
4回にわたってありがとうございました!
にっく
にっくさん、コメントありがとうございます。
実はこの記事にある内容って、診断士に受かってからも必要になるものです。
完璧主義や細かいところまで気にする方、難しく複雑に考える方は、私もこれまで実務で何人か出会いました。しかし、こういう方がいると本筋から逸れるので効率や最終的な成果物の品質はかなり落ちます。
また、診断士の仕事の誘いがあったのに「本業が忙しくて、、」と断っていては(もちろん正当な理由や代替案を出せばOK)誘いが来なくなります。
にっくさんも仲間ですよ!
ぜひ合格して一緒に仕事しましょう!
サトシさん、二次ベテシリーズ面白かったです。
私も今年が4回目の2次試験になり、ベテランの域に足を突っ込みつつあります。(もうベテラン?)
教訓、ストラテジーの20個も自分自身であてはまるものや、まわりの方でのあるあるがたくさんですごく共感できました。私自身は知識編重、過去問マニアになっているのが、合格を遠ざけているように感じてます。
最後にかかれてましたが、意識を変えて一気に実力を伸ばして、今年で合格を勝ち取りたいと思います。
今後も記事を楽しみにしています。
tomiさん、コメントありがとうございます。
大丈夫ですよ。ベテランでも昨年は私の知り合いでもたくさん合格されています。むしろ今は追い風が吹いています。
今回の私のシリーズを読んでいただいて、ありがとうございます。
どのパターンに当てはまるかを把握し、ご自身なりに受け容れることができているのは大きいです。
意識改革をしてもう次のS字にジャンプできますからね。
tomiさんならもう合格するためのスキルや知識の土台は完成しています。あとは安定させるだけです。
応援しています。頑張っていきましょう!