事例Ⅱの「だなどこ」基礎講座 by Takeshi

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はじめに
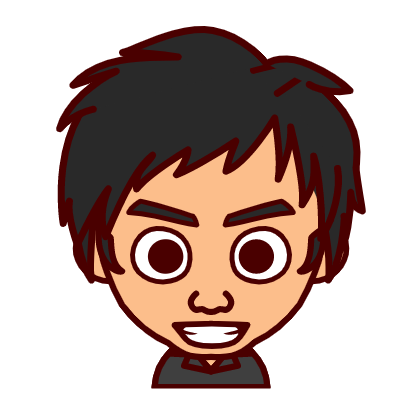
Hello, DOJO!
9月になってもまだまだ暑いです。体調に気を付けて!
今年度の1次試験の合格発表は9月5日(火)です。
例年だと、午前10時すぎに診断士協会のホームページに公開されます。
自己採点してもまだドキドキしている方もいると思いますが、その気持ちは2日後に取っておいて、今は2次試験対策に集中しましょう!
発表直後はホームページが重くなるので注意!
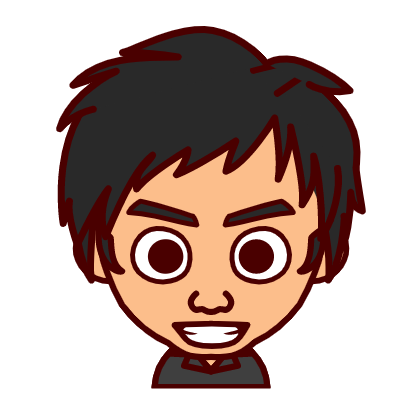
那覇地区の方へ!
経済産業省が、1次試験に合格しなくても2次試験を受験できる特例措置を盛り込んだ法改正に向けて動いております。
法改正が実施された場合、9月6日(水)に2次試験の案内が発送されます。1次試験と2次試験の両方を対策するのは大変ですが、今は2次試験対策を優先することをおすすめします。
さて、今日は事例Ⅱの対策についてです。得意と苦手が分かれやすい科目ですが、僕なりの視点で解説していきます。

でもTakeshiって、事例Ⅱは59点しかなかったよね?
痛いところ突かないで!

事例Ⅱで使う「だなどこ」って何?
事例Ⅱは「マーケティング・流通」を中心とした問題が出題されます。
これらの問題を解きやすくするフレームワークが、事例Ⅰで使えるレイヤーの知識と同様に事例Ⅱにもあります。
それが、「だなどこ」です。
診断士しかそんな変な単語使わねーぞ
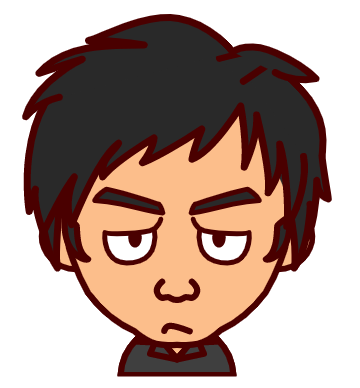
「だなどこ」とは具体的に、
だ(誰に)
な(何を)
ど(どのように)
こ(効果)
の頭文字から取られており、マーケティングの助言問題で強みを発揮します。「ふぞろいな合格答案」の参考書や他の受験セミナーでもよく出てくる単語ですね。
4P戦略(製品、価格、場所、プロモーション)ともかかわりが深いため、きちんと押さえるようにしましょう。
出題の趣旨との関連性
中小企業診断士試験は2次試験の模範解答が公開されません。
その代わりに、2次試験の出題趣旨が毎年公開されています。この出題趣旨を過去2年分のぞいてみましょう。
https://www.j-smeca.jp/contents/010_c_/001_shiken_kakokekka_syusi.html
第2問
令和4年度 「中小企業の診断及び助言に関する実務の事例Ⅱ」の出題の趣旨
(略)ための商品戦略と流通戦略について、助言する能力を問う問題である。
第3問
(略)ためのターゲティング戦略について、助言する能力を問う問題である。
第4問
(略)商品戦略、(中略)コミュニケーション戦略の提案について、助言する能力を問う問題である。
第2問
令和3年度 「中小企業の診断及び助言に関する実務の事例Ⅱ」の出題の趣旨
(略)ための、ターゲティング戦略、商品戦略、流通戦略を提言する能力を問う問題である。
第3問
(略)特定ターゲットへのニーズ対応方法を提言する能力を問う問題である。
第4問
(略)必要となる、製品戦略、コミュニケーション戦略を提言する能力を問う問題である。
それぞれの戦略を「だなどこ」に当てはめるとこうなります。
・誰に … ターゲティング戦略、ニーズ対応方法
・何を … 商品戦略・製品戦略
・どのように … 流通戦略、コミュニケーション戦略
・効果 … 助言、提言で必要
このように、「だなどこ」は単なる受験テクニックではなく、ちゃんと出題者の意図に沿った解答方法であると言えます。
ここからは、「だなどこ」の中身について解説していきます!
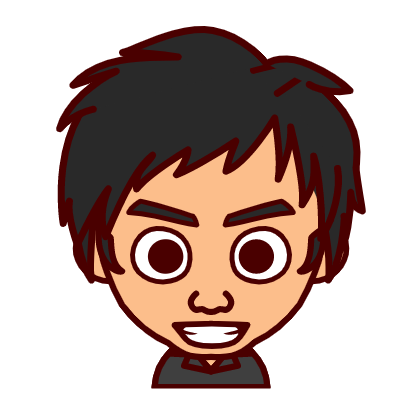
誰に(ターゲティング戦略)
はじめに、「誰に」マーケティングするかを決めます。
ここでは1次試験でも勉強したSTP分析を用いたうえで、ターゲットを絞っていきます。
STP分析は覚えていますか?
「セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング」のことです。
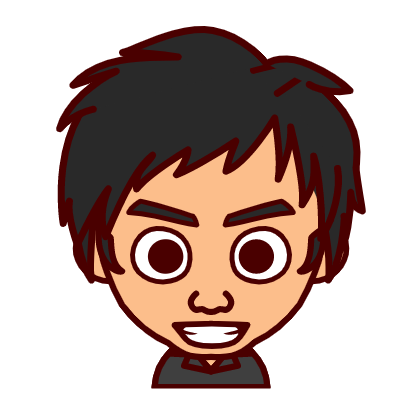
ターゲティングは、「物理的(ジオグラフィック)、人口分布(デモグラフィック)、心理的(サイコグラフィック)」の3つの観点で行います。
「ジオ・デモ・サイコ」と覚えましょう。
これの詳しい使い方は、過去の道場記事を検索してみるとたくさん出てきます。ぜひ参考にしてください!
ヒントとなるキーワード!
・地元の人々、遠方からの観光客
・子どもやその親、高齢者、一人暮らし
・~にこだわりを持つ、安心を求める
さらにターゲティング戦略の隠し要素として、「既存顧客」か「新規顧客」かも重要になってきます。
下の2人を見ても、この後の「何を」「どのように」「効果」は全然違うものになります。
この街に住み続けて十数年。地元のお店にいつもお世話になってるよ~
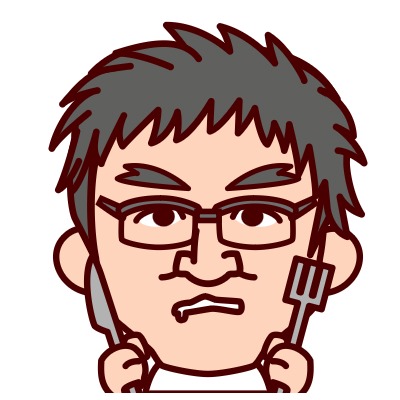
初めて来たけど、雰囲気もよくてサービスも最高!
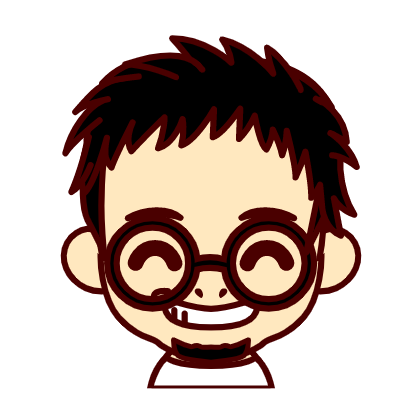
この場合、トロオドンには「これからも末永く利用してもらうための戦略」、うっかりアッパみたいな人には「新しく利用してもらうための戦略」が必要になります。
何を(商品戦略・製品戦略)
次に「何を」マーケティングするかを解答します。
売り込むもののヒントは与件文に書いてあります。その中でも着目すべきなのは以下の通りです。
・事例企業(B社)の強み
・付加価値になりそうなもの
特にB社の強みは分かりやすく書かれていることが多いため、与件文にマーキングして忘れないようにしましょう。
ヒントとなるキーワード!
・こだわりの~、昔からの~
・地元の〇〇を用いた~、目利きの~
・新開発の~、共同開発の~
どのように(流通戦略、コミュニケーション戦略)
この次は、「どのように」マーケティングするかを解答します。
ただ店頭に商品を置くだけで売れるとは限りません。
そこで、いろいろ工夫してマーケティングを行うことが必要になります。
「いいものなら売れるというナイーヴな考え方は捨てろ」
って某漫画でも言ってるしね。

「流通戦略(チャネル戦略)」とは、生産から販売までの各部分をつなげるものです。この戦略では、販売するモノに対するアプローチをとらえましょう。
解答に使えるキーワードとして以下のものがあります。
・他社との協業
・店頭以外での販売網(共同販売、EC販売など)
「コミュニケーション戦略」とは流通戦略と異なり、販売するモノやサービス以外のアプローチ方法を考えます。
解答に使えるキーワードとして以下のものがあります。
・実践販売、個別カスタマイズ
・アフターサービス
・口コミ、SNS活用
さらに、最近取り上げられやすいのがデジタルマーケティングです。
DM発信、個別SMS、オンラインサービスなど、キーワードを蓄積しておくことをおすすめします。

私をいっぱい使ってお客さんを呼び込むのよ~
効果(助言)
最後は効果を解答します。
診断士としていろいろ提案してみても、結局それが有効かどうかが分からなければ経営者も不安です。
「こんないいことがありますよ!」と経営者を後押しするのが、診断士としての助言になります。
効果を書くにあたっては、設問文をしっかり読みましょう。
設問をそのまま書き写すだけでも「問題に素直に答えている」というアピールになり、加点が期待できます。
仕事でも、「それやって意味あるの?」と聞かれますよね。
「意味あります!」と堂々と言えることが非常に重要です!
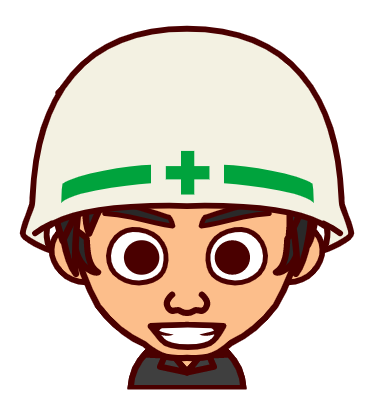
なお、文字数の関係で効果まで書けない場合もあるので、本番では柔軟に対応する必要があります。
最後に
実は、僕自身事例Ⅱが大のニガテでした。
アイデア勝負になりがちなので、営業やマーケティングの業務を行った経験がない方にはとてもつらい科目だと思います。
そのような場合に重要なのは、「だなどこ」の基本を押さえて、採点者に「分かっている」アピールできる解答を作ることです。
高得点でなくても、少なくとも足切り点を回避できるように対策を続けていきましょう!
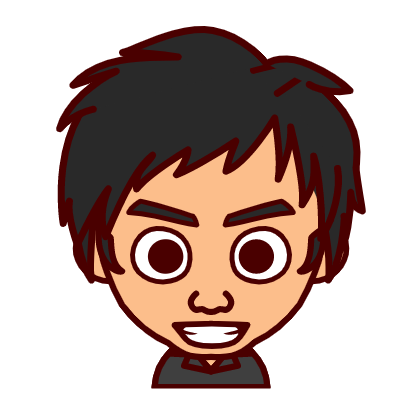
事例Ⅱに限らず、苦手な科目に多めに時間を割けるよう勉強の優先度を調整していきましょう。
See you!
明日はさや姉です!
事例Ⅱの次は事例Ⅲ。お楽しみに!
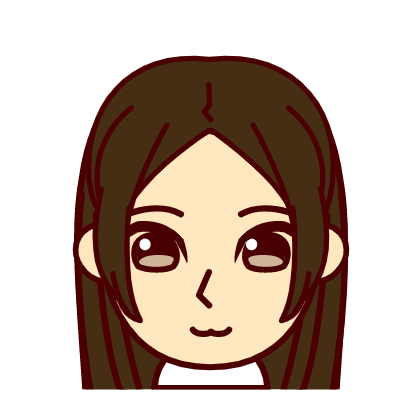
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)



