【合格体験記】量をこなすことで質を引き上げる努力型受験生 by ぱおずさん
-1024x576.jpg)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

受験体験記の投稿ありがとうございました!一つ一つご紹介していきます
ちなみに私、ぱおずさんとは知り合いです。
受験生情報
- ハンドルネーム:ぱおず
- 年代:30代
受験回数
- 1次試験:5回
- 2次試験:3回

私と同じ多年度生ですね。多年度生の雰囲気はまるで感じさせないぱおずさんです
自分の診断士受験スタイルを一言で表すと
受験勉強期間は診断士試験を中心に据えて、量をこなすことで質を引き上げる努力型

量をこなすことで質を引き上げる、素晴らしいスタンスです!
診断士に挑戦した理由・きっかけ
コロナ禍の時、本業の業績不安と仕事面での将来への不安を、変わらない会社のせいにしていました。
そのため2021年早々に本業を退社し、お金持ちの知り合いと一緒に事業を行うことを考えていました。しかしながらその時、自分自身は社会人として15年以上仕事をする中でビジネスマンとして力をつけてきたつもりではありましたが、冷静に自分を俯瞰してみてみればただ歯車として会社に乗っかかっていただけ。あるのは知り合いだけで、結局は人に依存して生きていこうとしていることを信頼できる人から指摘され、このままでは家族を守れないと思い独立は断念しました。 人や会社に依存しないで、自分の足で歩くためには自分自身に力をつけなくてはならない。そう考えた時、以前独学で少しだけ勉強をし、1次試験が通過せずに断念した診断士試験のことを思い出し、一度興味を持った資格試験に改めて取り組み、いつか胸を張って、自分の意思で人生を歩いていくためのパスポートを得るために全力投球をしてみようと考えたことが理由です。

ぱおずさん、そんな事情があったんですね
職務経験・保有資格
【職務経歴】 株式会社中日新聞社
2007年4月 入社
同8月 名古屋本社販売局勤務
2012年4月 東京本社販売局勤務
2019年7月 名古屋本社販売局勤務 現在に至る

中日新聞ということは、阪神が苦手なバンテリンドームをホーム球場にもつあの球団もよく知っているのだな。お~ん
【保有資格】
・小学校教諭一種免許状
・中学校教諭二種免許状(社会科)
・日商簿記2級
・ファイナンシャルプランナー2級
・普通自動車免許

ちなみに、コミュ力検定というのがあれば、ぱおずさんは間違いなく1級です!
それだけコミュ力オバケです
得意科目・不得意科目
- 1次試験 得意科目:なし
不得意科目:情報 - 2次試験 得意科目:なし
不得意科目:なし
再現答案の有無
あり

再現答案を作れと念を押したからね!
合格までの学習法
- 1次試験:独学・TAC通学
- 2次試験:TAC通学
1次対策
※令和6年度試験は、二次試験に二度落ちたため受験資格喪失、一次試験からのやり直しとなりました。そのため、令和6年度に向けた試験対策の学習方法を中心に記載します。
・なお、2021年9月からTAC通学講座にて一次試験対策を開始し、令和4年度は一次試験7科目受験し合格、その後から二次試験対策を開始し10月に受験をしましたが、不合格。翌年は二次試験勉強に集中して取り組むも令和5年度も不合格に終わりました(サトシさんは当時同じクラスで、大変お世話になりました)。

いやいや、こちらこそお世話になりました。
でも本当に1次からやり直しになっても5合目くらいからのスタートでしたでしょ?
(1次からのやり直しになって、ぱおずさんから相談があり、そのとき私は「5合目にいます」と言いました)
・2024年1月末から、改めて一次試験からやり直し、今年中に二次試験まで突破することを決意し、勉強を再開しました。学習スタイルとしては、一次試験7科目は、まずは過去問を中心とした独学。並行して2~4月までは二次試験対策をTAC通学で並行して行いました。
・一次試験対策をすべて独学で行うには当初から不安がありましたが、特に2日目の暗記系3科目については、最新のトレンドや法改正対策も必要だと考え、TAC通学の単価生として演習2回と直前講義を受講しました。
・基本フォーマットとしては上記の通りです。進め方としては各科目一通りの再インプットと問題集によるアウトプット。1科目2週間程度を目安とし、1月末から4月末まで地固めを行いました。その後、4月下旬から過去問を中心のアウトプット→インプット→アウトプットを継続。直近5年間の過去問を通しで、90分科目は2~3周、60分科目は3周を行い、全科目前年度90点以上取れることを目標に取り組み、やり切りました。
・6月末に受けたTACの一次試験模試では7科目合計で461点だったため一定自信はつきましたが、ここで手を抜いたら落ちると気を引き締め、7月は1ヵ月で152時間を勉強に充てました。結果、令和6年度の一次試験は7科目合計501点取ることができました。

1次500点超え!!
2次対策
・2024年前半は一次試験対策をメインに行いましたが、2~4月までは二次試験対策をTAC通学で並行して行いました。理由は、上積みは作れないにしても、昨年積み重ねた二次対策の力の維持と、一次試験終了後の学習をどのように進めるか見定めるためでした。
・5月以降、しっかりとした二次対策は行っていませんが、それでも6月中旬ころまでは事例Ⅳ対策と、Ⅰ~Ⅲの設問分析力向上だけは継続的に図っていきました。
・8月に一次試験終了後、1ヵ月以上をかけてひたすらⅠ~Ⅲの設問分析と事例Ⅳ対策を行いました。理由は、一次試験後最初に受けたTACの演習が、あまりにもできなかったからです。自分としてもう少しできるものかと思い込んでいましたが、いざ解いてみると、設問で聞かれていることがわからない、考えがまとまらない、思い付いたことが答案に書けない…。まさに、運動会で身体がついてこないお父さん状態でした。ではこの状態をどのように解消するかと考えた時、昨年度の二次試験の敗退理由と考えた設問分析力の欠如です。一方で最近まで一次試験に全力投球をしていた強みを生かし、ここは一次試験と同じようにひたすらインプット→アウトプットすることで、これまで学んできた知識を二次試験対策で使える知識に変換しようと考えました。結果、直近5年間分の本試験過去問と、昨年から今年の前半までTAC通学講義で受けた演習の設問と、想起すべき知識ワード等をまとめ、その上で導き出せる模範・目標解答を全て書き出した独自ツールを作成しました。二次試験対策はあまり学習ツールがないと思われますが、なければ自分で作ればいいのです。
・その後はひたすら過去のTAC演習と過去問を解きまくりました。なお毎日事例Ⅰ~Ⅲの内1つと、事例Ⅳを1つ、通しで解くようにしました。その際意識したのは、事例Ⅰ~Ⅲは共通して、解答前プロセスを適切に行うことと、問一の現状分析計の問題を短時間処理すること。事例Ⅳは、通しで解くことで本番での時間感覚と優先順位感覚をつかむことでした。
・二次試験の前日は、事例Ⅰ~Ⅲは問一の現状分析系問題短時間処理と、R5年度の事例Ⅳ過去問を通しで解くことをし、最後の最後まで感覚を研ぎ澄ますことを怠らず当日を迎えることができました。
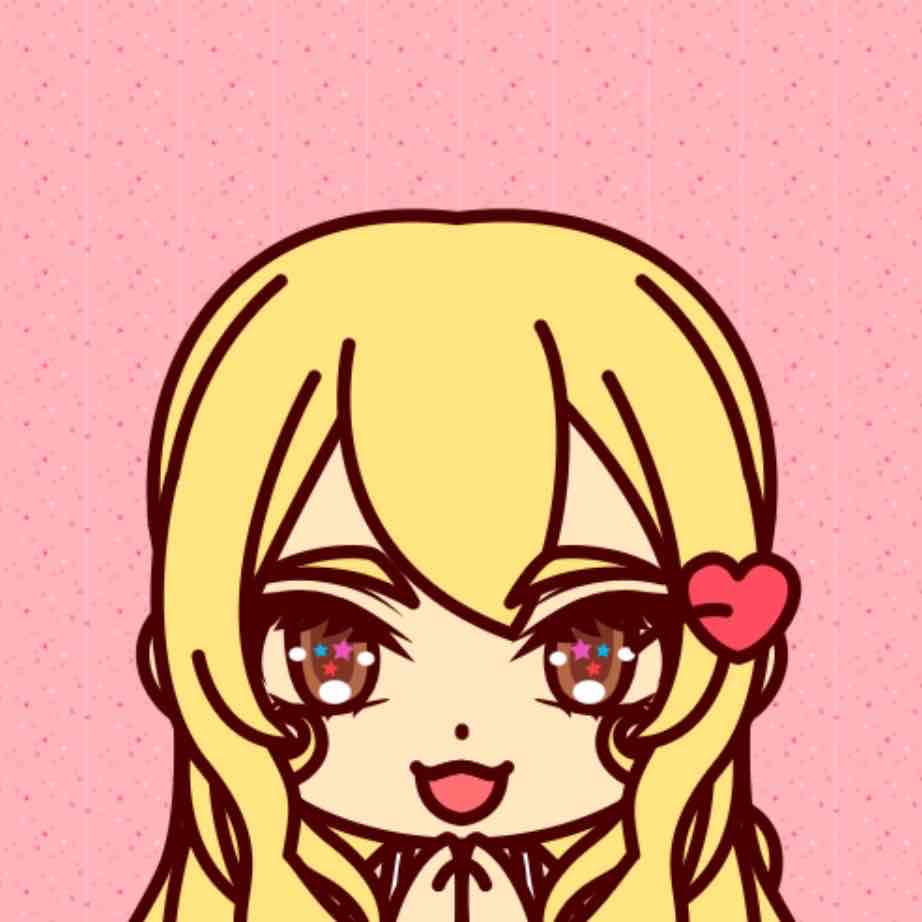
私がビシバシ鍛えました(昨年のサトシ君と同様に)
(ちなみにこの似顔絵アイコンは、私が作った津田先生(まどか先生)の似顔絵アイコンをもとに、ぱおずさんが作成しました。誇張しすぎてません?(笑))
なぜその学習方法を選んだのか?
基本的にはTAC通学を選択しています。理由は①リアルで決まった時間に講義があることで学習ペースを一定にすること、②リアルで講師の話を聞くことにより、テキストを読むだけではわかりにくい、知識の優先順位や最新情報を知ること。また講師との対話を通して自身のモチベーションを向上させること、③二次試験対策では仲間づくりのためです。

2次試験は団体戦。これはTAC名古屋校でよく先生が言っていることです
学習開始時期
2021年9月
学習時間(目安)
- 1次試験:747時間(2024年)、1688時間(2022年、2024年通算)
- 2次試験:418時間(2024年)、1494時間(2022-2024年通算)
学習時・受験時のエピソード
学習を行っていく上で最も大切なことは、学習環境作りだと思います。
学習環境も3つに分類されると思います。①学習スタイル、教材選び、②学習を行うための仕事・生活面作り、③家族の協力。
- 学習スタイル、教材選び
通学にするか、通信にするか、独学にするか。様々な情報がネットその他に溢れており、それぞれでメリットデメリットあります。教材も同様です。それぞれ判断基準があるとは思いますが、私の場合はまず「通学」で学習することを決めました。理由は「なぜその学習方法を選んだのか?」に記載の通りです。その上で、立地や講義のペースを比較した上でTACへの通学を決めました。
- 学習を行うための仕事・生活面作り
合格までに何時間勉強しなくてはならないのか、何をやらなくてはならないのかをまず計画しました。その上で、2024年は1月末からのスタートだったため、平日3.5時間、土日は10~12時間の学習が必要と考えました。では、これだけの学習時間を確保するためにはどうすればいいのかを考え、仕事面と生活面を作ることから始めました。具体的には、極力残業はしない、業務上外せない、または冠婚葬祭絡み以外の飲み会には極力参加しない、毎日6時に起きて勉強をする、といったことを決め、1月末からペースを作り、10月末まで継続させました。
- 家族の協力
家族がいる身としては、実はこれが一番大事だと思います。家庭内の雰囲気がよければ学習もはかどりますし、逆もしかりです。子供もまだ小さく、親がかかわらなければならない時期にたくさんの時間を使って一人部屋にこもって勉強をします。私の場合は妻が大変協力的で、その姿を見て子供も応援してくれました。
一次試験、二次試験、口述試験。それぞれの試験の前日にはカツ、当日には子供が作ったお守りを渡してくれました。勇気が出ました。これからは私が妻たちに恩返しをしていく番です。

いいこと言いますね~
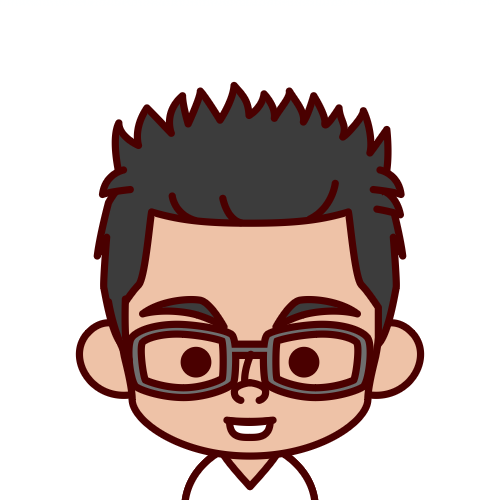
でしょ~サトシさん!
(前に「受験仲間」として似顔絵アイコンを作りましたが、ぴらりんに似ています)
これから合格を目指す方へのアドバイス
やはり、人間最後は本気と気合いです。私はTACに全集中いたしました。本気ならば信頼できる講師・予備校に全集中し、余計な情報に触れないことも重要かと思います。
おわりに
私と同じTAC名古屋校で津田先生(まどか先生)に鍛えられて合格を果たしたぱおずさん、いかがでしたでしょうか。こちらもいさしおさん同様、多年度生には特に参考になるかと思います。
ぱおずさん、個人的にも今後ともよろしくお願いいたします。バンテリンドームの野球観戦の約束、守ってくださいよ~(笑)

ぱおずさん、合格おめでとうございます!
(個人的にもめっちゃ嬉しいです)
コメントについて
記事へのご感想やご要望があれば、下部の入力フォームから是非コメントをお寄せください!
執筆メンバーの励みになりますので、よろしくお願いいたします。
※コメント送信後、サイトへ即時反映はされません。反映まで数日要することもあります。
※コメントの内容によっては反映を見送る場合がございますので、予めご了承ください。
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)

-300x169.jpg)
-300x169.jpg)