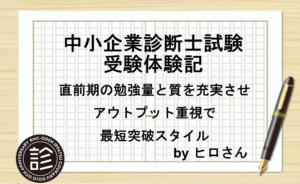【合格体験記】9回裏3点ビハインドからの代打逆転満塁サヨナラホームラン! by ダイキさん

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
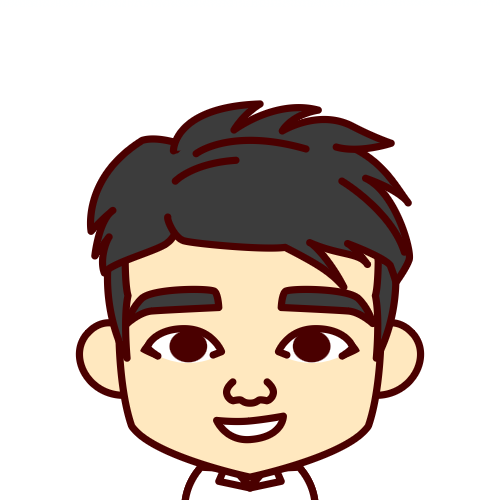
経営者に近いところで仕事がしたい、と診断士試験に挑んだダイキさん。
本業でマーケティング業務をしつつも、事例Ⅱが上手くいかなかったダイキさんの攻略法とは?
受験生情報
- ハンドルネーム:ダイキ
- 年代:30代
受験回数
- 1次試験:3回
- 2次試験:2回
自分の診断士受験スタイルを一言で表すと
9回裏3点ビハインドからの代打逆転満塁サヨナラホームラン!
(追い込まれてから実力を発揮するタイプ。ということです)
診断士に挑戦した理由・きっかけ
「経営者(=社長)」に近いところで仕事がしたい、それが叶えば自分が成長できると思ったからです。
経営者と近いところで仕事をするために“ある一定量の知識・能力があることを外部に証明する必要”があると考え、(そしてちょうどコロナで時間が空いたので)診断士試験への挑戦を始めました。
また、2021年に居住地の商工会議所の創業塾に参加し、お世話になった中小企業診断士の先生(=塾長)の元で修行させていただいた経験も「診断士として経営者に近いところで仕事をしたい」という想いを強くすることにつながっています。
(修行の結果、まだ受験生である2024年に創業塾のWebマーケティング講師として登壇することに。)
更に2025年は、診断士取得とともに所属会社の人事異動で〇〇になることが内定しており、、、
経営者に近いところで仕事をしたいと思っていた人間が、診断士の勉強を通じて自らが〇〇になってしまった・・・
という嘘のような状況になっています。
職務経験・保有資格
- IT企業にてマーケティング系のクラウドシステムの営業、システムに付随するデジタルマーケティング支援業務に約10年間従事しております。
- 並行して、2022~2024年に上記記載の通り商工会議所を通して居住地の中小企業・個人事業主のデジタル周りの支援を副業で実施
- 2024年は更に並行でグループ会社であるスタートアップ向け広報・PR支援会社のセールス・マーケティングに従事し、2025年4月より〇〇に就任予定
得意科目・不得意科目
<一次>
得意:経営情報システム、企業経営理論
苦手:経営法務、経済、財務会計
<ニ次>
得意:なし(事例Ⅲはそれなりに点数取れていた。)(事例Ⅱと言いたかった)
苦手:事例Ⅳ(まなび生産性向上の事例Ⅳ特訓に参加しましたが、それでも苦手です)
合格までの学習法
1次対策
通信(スタディング)
1回目、2回目の一次試験はスタディングを利用
3回目の1次試験は、経済学のみだったため、スタディングは課金せず「はじめよう経済学」で死ぬ気で学ぶ
2次対策
通信(事例Ⅳ特訓)・勉強会
1回目のニ次試験は、一次通過で満足し何もできず(ふぞろいの存在も知らなかった)
2回目の二次試験は、これではまずいと思いタキプロのリアル勉強会に参加(初回勉強会でふぞろいの存在を知る。)
特に事例Ⅳが自力ではどうしようもなかったので、事例Ⅳ特訓でなんとか足切り回避&強制的に事例Ⅳを溶きまくることを選びました。
なぜその学習方法を選んだのか?
一次:スタディング
→コロナ禍で外出することを選べなかったため通信しか選択肢がなかった
→他の通信は金額が高すぎて手が出なかったため、ほぼ消去法でスタディングを選ぶ。
ニ次:勉強会・独学
→1回目の二次試験は、全く何も対策が打てなかった(スタディングでうろ覚えレベル)
その状況で200点が取れた&足切り回避出来たので、過去問こなせばギリギリ240点行けるのでは・・・?
と判断し独学路線で進む。
→2回目の二次試験は、独学で進むことを決めたが、様々情報を集めた結果「1人で勉強しても合格できない!」と判断し、様々な有志団体の勉強会など「独学だけど他の受験生と学び合う」環境に積極的に進出。
勉強をこなしていたが、事例Ⅳがどうしても伸びず(NPVが本当にワケがわからなかった)、
事例Ⅳは追加でなにかしないとまずいと考え、まなび生産性向上の事例Ⅳ特訓に参加することを選びました。(結果的にこの選択が2次試験全般に活きました)
学習開始時期
2020年4月〜
学習時間(目安)
- 1次試験:650時間
- 2次試験:150時間
学習時・受験時のエピソード
一次試験
(初回受験)
経済48点、財務64点、企業経営理論71点、運営管理60点、法務52点、経営情報システム60点、中小企業経営・中小企業政策59点(合計414点)
→初年度は不合格だったが「意外と行けるぞ・・・!」という変な自信が、不合格にも関わらず芽生える。
(2回目受験)
経済48点、財務36点、企業経営理論58点、法務72点、経営情報システム60点、中小企業経営・中小企業政策63点(合計337点)
→経済と法務が苦手意識しかなかったので「すでに科目合格している財務、企業経営理論で70点ぐらい取れたら合格できるだろう」と思い、免除科目をあえて受験する方針を取る。(前年の変な自信がこの選択をさせてしまった・・・)
→結果、科目合格していた「財務、企業経営理論、経営情報システム」を受験していなければ、、、この年に一次試験に合格していた。。。という最悪な結果に。
→奥さんに「私、免除になった科目は受験しないほうが良いと思ってたけど、受験前にそんなこと言われたら「いや!俺のこの受験が正しいんや!」ってどうせ言ってるやろ?」と言われる。(非常に的を得ている)
→結果が出た後に知り合いの弁護士から「弁護士が中小企業診断士を受験するときですら、法務は科目免除しますよ」と教えられ、自分の調子乗り具合にようやく気づく・・・
(3回目受験)
経済:60点
→2回目受験の反省から、苦手科目経済一本の受験に。
→「はじめよう経済学」で死ぬ気で学ぶ。結果超ギリギリで合格
二次試験
(1回目受験)
事例Ⅰ44点、事例Ⅱ46点、事例Ⅲ64点、事例Ⅳ46点(合計200点)
→一次試験合格に満足し、二次試験は全く情報収集出来ず何も対策が打てず、ほぼ記念受験。
→そんな状況で足切りがなく、200点取れたことで変な自信がまた芽生えかける。
→しかし、流石に一次試験と同じ轍は踏まず、、、変な自信は事例Ⅱによってボキボキに折られてしまいました。
★R5事例Ⅱに心を折られた件★
私は、小学校~高校まで12年間野球をやっていました。小学校は西日本大会優勝、中学校は全国大会出場、高校は福井の強豪校に進学、在学中に2度甲子園に出場しました。(私はスタンド応援&荷物運びでテレビに映りました)
また私は、社名に「マーケティング」と付く会社に新卒入社し、受験時まで約8年間、デジタルマーケティングに従事しております。
R5年の事例Ⅱ、題材は「野球用品の専門性に強みを持っているスポーツショップのマーケティング」でした。
「これは俺のための問題だ!来た!来た!来たー!!!」と思いました。ここで変な自信が湧きました。
自信満々に、何も情報収集していない私は好き放題なことを書きました。当時何を書いていたかは全く覚えていません。
結果、46点。私は2024年2月ごろまで「事例Ⅱだけは」ガチでテンションが落ちていました。
この結果から学んだことは「二次試験は業界理解が深い=点数が取れるものではない!」「マーケティング会社で働いてたら事例Ⅱ得意!と軽率に言ってはいけない」「二次試験は自らの考えや想いを書く場ではない」ということです。過去に様々な諸先輩方がブログ等で発信されている内容と同じだと思いますが、それが正しいことを肌で感じました。
(2回目受験)
無事合格!
・まず立地面で勝利
→筆記試験の会場は、自宅から徒歩10分(大和大学)
→口述試験の会場は、自宅から車で10分(大阪経済大学)
→10:24の口述試験で、10:55には自宅に帰宅していました。
・2次の過去問について、R5年過去問を筆記試験2日前まで温存し、リハーサルと昨年からの成長を図るために直前に自宅で解いてみたところ、、、ふぞろい採点でまさかの「239点」・・・
しかし「去年より39点も上がってる!俺、成長したなぁ・・・」と超絶プラス思考でした。
これから合格を目指す方へのアドバイス
一次試験
- 科目合格した教科を、調子に乗って再受験しない!
- 自己採点は自分の受験科目がすべて終了してから行うこと!特に初日の科目は当日自己採点NG!
二次試験
- 一次試験の勉強期間から、二次試験についても情報収集すること。全く情報収集しないのは破滅。
- 二次試験は問題ではなく「社長のお悩みに診断士として回答するコーナー」と心得る。(とにかく効果!)
<勉強面について>
独学が基本でしたが「1人で勉強しない」ことが自分にとっては非常にプラスに働きました。
(プラスに働いた例)
・タキプロを中心とした有志の勉強会に積極的に参加することで、合格された先輩方の知見やテクニックを学び、同じ受験生仲間の回答の良いところ悪いところを学びに変えることが出来た。
・まなび生産性向上の事例Ⅳ特訓に参加し、事例Ⅳの学びを得られたことはもちろん、特訓メンバーで自主的に事例Ⅰ~Ⅲの回答についても意見を出し合うことで想定以上の学びを得ることができた。
・会社の同僚で資格勉強している仲間を集め、週一回ペースでオンライン勉強会を実施。違う資格であってもお互いに「このテクニック使えそう」という学びを得れたり、何より同僚なので得られる刺激が大きく、モチベーション向上につながった。
・社内、社外(取引先など)の診断士合格者や先生に積極的に会いに行き、試験の経験や実務についてお話を聞くことで、受験中や受験後、合格後のイメージを明確に持つことが出来た。
<特に独学の方、ご家庭やお仕事と勉強の両立に悩まれている方向けに伝えたいこと>
私は診断士試験を通じて感じたこと、特に二次試験について強く感じたことは「様々な方にお力添えをいただいたおかげで合格することができた」ということです。
私1人で勉強しているだけでは、中小企業診断士試験には合格出来ていませんでした。
1人で勉強することを勧めないということは、通信や通学などで学べば良いのか?と思われるかもしれませんが、
ご家庭の事情、お仕事の事情などで通信、通学での勉強が難しい方も大勢いらっしゃると思います。
私も家庭を持って、診断士試験を受験した4年間で子どもが二人生まれ、子育て+仕事をしながら診断士試験の勉強に取り組むことは非常に難しいことを痛感した人間です。
そんなみなさんに伝えたいことは「人を巻き込んで学ぶ」ことです。
まず大前提ですが、あなたにとって診断士受験生は敵ではありません。同じ目標に向かって走る仲間です。
診断士試験は基準となる点数(6割)より高い点数を取る試験です。
誰かを蹴落とすことで合格率が高まる試験ではありません。
蹴落とすよりもみんなで頑張ったほうが、様々な人の知見を掛け合わせることができて、関わったみなさんの合格率を高めることも、ご自身の合格率を高めることもできて一石二鳥です。
私と同じように独学を選んだ方、ご家庭やお仕事と勉強の両立で悩まれている方は、少ない時間の中で最大効率を出すために、一発合格道場などを活用し「人を巻き込んで学ぶ」ことを意識していただけると幸いです。
おわりに
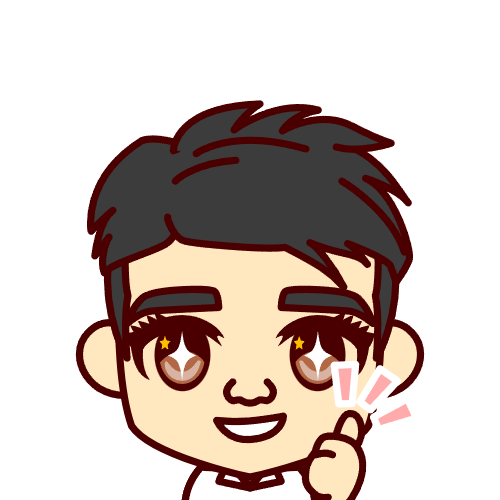
「1人で勉強しない」「人を巻き込んで勉強する」といったスタイルで合格をつかんだダイキさん。これからも周りの方を巻き込んで大きなことを成し遂げていってくださいね。
また、何やら4月からはただならぬ変化が起きそうな予感!楽しんでください!ご寄稿ありがとうございました。
コメントについて
記事へのご感想やご要望があれば、下部の入力フォームから是非コメントをお寄せください!
執筆メンバーの励みになりますので、よろしくお願いいたします。
※コメント送信後、サイトへ即時反映はされません。反映まで数日要することもあります。
※コメントの内容によっては反映を見送る場合がございますので、予めご了承ください。
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)

-300x169.jpg)