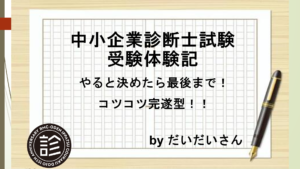【合格体験記】iPad等活用で学習効率最大化! by ぽおやさん

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

受験体験記のご投稿、ありがとうございました!
今回の体験記は、ぽおやさんです!
受験生情報
- ハンドルネーム:ぽおや
- 年代:30代
受験回数
- 1次試験:1回
- 2次試験:2回
自分の診断士受験スタイルを一言で表すと
🍀iPad&Officeソフト活用し学習効率最大化、最後に小手先技であがく🍀
診断士に挑戦した理由・きっかけ
理由は2つ。
- 30代になり、難関資格への挑戦意欲が芽生えた事。
毎年何等かの資格試験には取り組む事を心がけてきたが、20代を振り返ると毎回短期集中型で資格勉強に取り組んでいた。これを反省し、30代は本腰を入れて取り組む難関資格にチャレンジしようと考えた。 - 本業への活用。
現職は銀行の市場部門でデリバティブ商品の営業をしている。金融市場の知識だけでセールスするのではなく、社内体制整備や会計、法務に至る迄、ワンストップで総合的な提案を実現する為、中小企業診断士に挑戦する事にした。
職務経験・保有資格
- 職務経験:銀行_市場部門
- 保有資格:通関士、日商簿記2級、FP2級、TOEIC835、知的財産管理技能士2級、VBAエキスパート他
得意科目・不得意科目
1次:経営法務、中小企業政策
2次:事例Ⅰ
合格までの学習法
1次対策
- 通信(STUDYing)
使用教材:STUDYing、TACスピード問題集(アプリ)、診断士秒トレ(アプリ)
2022年11月~2023年8月頃- 通勤中にSTUDYingの講義視聴
- 普段より1-2時間早く出勤し、社内で問題集を解く
- 2022年10月迄取り組んでいた通関士試験のテキストが重く持ち運びが大変だった事から、中小企業診断士試験は全てiPadに集約。又、Officeソフトを活用。OneNoteにSTUDYingテキスト取込、間違えた問題の解説等もスクリーンショットで貼付けし、いつでも参照できるようにした。
2次対策
- 独学・その他(模試5回)
使用教材:STUDYing、ふぞろい、30日完成!事例Ⅳ、TAC事例Ⅳの解き方、意志決定会計講義ノート、EBAの100字訓練、雑誌『企業診断』に付属する予想問題
2023年8月~2023年10月
- それまで2次試験の問題は見てこなかった為、試験後すぐに2次対策を始める。
- 当初STUDYingの教材を利用したが、多面的な解答ができているか不安になり時を経ずしてふぞろいへ移行。二次試験の与件文・解答用紙をiPadに取込み、繰り返し取り組む(平成24年分まで遡った)。30日完成は3周。
- 試験後は会社から取得指示されていたG検定、データサイエンティスト検定の勉強に移行。
2024年1月~2024年10月
- 不合格を確認し、敗因を分析する。
①書き直しする場合、iPadは消しゴム機能で一瞬だが、紙は時間がかかる。いかに手直しを抑制するか。
②SWOTを色で分けてマークするも、与件文が極彩色になり参考にならず。
③本番では事例Ⅳのページ数が多すぎて混乱。要は場慣れしていない為に要らない混乱・緊張をした。
④1次試験の用語はカタカナが多いが、カタカナは情報量が少ない(為、字数をたくさん使う)。カタカナの言葉ばかり使っていた為に、解答欄は埋められても内容がスカスカで得点に結びつかなった。- 以上の敗因から、以下の対策を実施。
①試験開始後に問題用紙を分解、白紙部分を回答用紙のマスに透かし、下書きを行う。書きたい内容を全て書き終えてから字数をカットする工程とし、清書時の手直しを抑制。
②SWOT別で色分けせず、問毎に色分け。先に問題文を読み、問と色を対応付け。後に与件文を読む際に各問で使いそうな文章を対応する色で下線。マーカーだと極彩色になる為、ボールペンに移行。
③模試を5回受験し場慣れ。
④解答時に漢字や略語を使えるよう、Excelに用語集をまとめた。その他、可能な限り句読点を使わずに韻でリズムを作る(句読点は情報量ゼロ)、解答の型を作って情報漏れを無くす、等を心がける。解答文字数100字であれば少なくとも98字は埋め、その98字も情報量を最大化する。
- 以上の小手先技を過去問演習で身につけた(平成21年まで遡り、各年度3回以上解いた)。
- 以上の敗因から、以下の対策を実施。
何故その学習方法を選んだのか?
iPad・Officeソフト活用については、①中小企業診断士前に受けていた通関士試験を通じた反省、②YouTube等を通じて自分に最適な勉強方法を模索、した末に辿り着いた学習方法。情報を1か所に集中する事で、気になった内容があればすぐに参照でき、いつでも勉強に取り組む事ができたので大変よかった(2024年1月には遅めの新婚旅行でモルディブに滞在したが、朝焼けを見ながらiPadを開いて勉強した思い出がある)。
2回目の2次試験で習得した小手先技は、生産管理の内容を踏まえながら創意工夫したもの。問毎に色分けする事で5Sを与件文上で実現し、「解答を作る」という目的に最適化。消しゴムの使用は解答時間の仕損と捉え、手直しを無くして解答時間の歩留り改善。略語や漢字を使って解答文の情報密度を高めていく作業は、L/T向上を狙って外段取り化をしたり運搬時間を抑制したりして稼働効率最大化を目指す取り組みをイメージしながら行った。小手先技は技術のようではあるが、自分としては生産管理で学習した事の実践として取り組んだ。
学習開始時期
2022年11月
学習時間(目安)
- 1次試験:800時間
- 2次試験:1,000時間
これから合格を目指す方へのアドバイス
ここまで読んでいただきありがとうございました。
私は銀行の市場部門でデリバティブ商品のセールスマンをしています。ここにいますと、日々の株式や為替の値動きがそのまま業務に直結する為、「画面上に映っている数字が全て」の様に思えてしまいます。実際にそういう人もいます。そんなデリバティブは当然、中小企業診断士の出題範囲です。ですが、財務会計の中の、ほんの一隅の分野に過ぎません。
診断士の勉強を通じて、私の今の業務が如何に狭い分野の内容なのかを思い知りました。
一方で、会計や法務、人事等、他分野にデリバティブを接続する事ができれば、
デリバティブ自体の潜在的な可能性がとても大きい事を感じ取る事もできました。
これらを知る事ができただけでも、私は診断士受験に取り組んでよかったと思えています。
この試験に取り組もうという方々は、恐らく何等かの分野におけるプロフェッショナルの方々だと思います。
自らの業務分野から更に視野を拡げたいという方にこそ、是非診断士受験に取り組んでいただきたいです。
「小手先技」とおっしゃっていますが、1点が貴重な試験では、
とても大事なことだと思います。
後へ続く皆様へのメッセージも有難うございました!

コメントについて
記事へのご感想やご要望があれば、下部の入力フォームから是非コメントをお寄せください!
執筆メンバーの励みになりますので、よろしくお願いいたします。
※コメント送信後、サイトへ即時反映はされません。反映まで数日要することもあります。
※コメントの内容によっては反映を見送る場合がございますので、予めご了承ください。
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)