【サトシの書籍シリーズ】⑤あなたのブランド戦略

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
一発合格道場ブログを
あなたのPC・スマホの
「お気に入り」「ブックマーク」に
ご登録ください!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
みなさん、こんにちは。
ここまで、4回にわたって「サトシの書籍シリーズ」をお送りしてきました。診断士試験合格後、すぐに活躍するためのノウハウをお伝えいたしましたので、合格された方や受験生のお役に立っていただけると嬉しいです。
今回は「サトシの書籍シリーズ」延長戦として、私も現時点でプランを練っている最中の診断士のキャリアやブランド戦略についてお伝えしようと思います。今回が本当に最後です(笑)
と言っても、今回も25,000字ほどあります(笑)
ですが、2次筆記試験の合格発表後、合格者からほぼ毎日のように質問や相談をいただいていることもあるので、今回の内容はみなさんも関心が高い内容かと思います。
それでは、今回もよろしくお願いします。

おい、本当にこれが最後だよね?
サトシのことだから、延長戦の延長戦、なんてことになったりして(笑)
大丈夫です!これが本当に最後よ。
もう思い残すことなく書きたいことを書けたよ

- 1. 第1章:正しい積極性
- 1.1. 1年目から差がつく
- 1.1.1. ①受け身になっている、周りに流されている
- 1.1.2. ②何でも手をつけてキャパオーバーになる
- 1.1.3. ③キャリア分析やブランド確立をしていない
- 1.2. 診断士は積極性を見せるのがポイント!
- 1.3. 自分のキャパを把握しておく
- 1.4. キャリア分析とブランド確立を行う
- 2. 第2章:キャリア分析
- 2.1. 診断士界隈の機会(ニーズ)の分析
- 2.2. 強み分析
- 2.2.1. 肩書きはブランドの鉄則
- 2.3. 強みを複数組み合わせる
- 2.3.1. 強みを組み合わせるほど競合の数が少なくなる
- 2.4. クロスSWOT分析をしてみよう
- 2.5. あなたのブルーオーシャンを見つけよう!
- 2.5.1. それってあなたのやりたいことですか?
- 2.6. このブルーオーシャンの中で関連多角化を図る
- 2.7. 経営理念、ビジョン、ミッションなどを作ってみる
- 3. 第3章:ブランド確立・ブランド戦略
- 3.1. ブランド確立
- 3.1.1. 価値
- 3.1.2. 独自性
- 3.2. ブランド戦略も関連多角化でいく
- 3.3. シンプルなフレーズでのブランド名を作る
- 3.4. ロゴや色などでもブランド化できる
- 3.5. ブランドになるフレーズを商標登録する
- 3.6. マーケティング戦略を実行する
- 3.6.1. 積極的に情報発信する
- 3.6.2. 個人名刺を作る
- 3.7. 横断的に取り組んで知名度を上げる
- 3.7.1. お金にならなくても実績を積む
- 3.8. ブランドに統一感をもたせる
- 3.9. 1分・1枚で自己紹介できますか?
- 3.10. 「●●と言えばこの人」を目指す
- 4. 第4章:キャリア分析やブランド戦略の効果を高める方法
- 4.1. 合格すると視野が広がる
- 4.2. 短サイクルでキャリアを見直す
- 4.3. ブランド戦略の留意点
- 4.3.1. メンタルに不備があるとブランドに傷がつく
- 4.3.2. 「暇人」と思われるとブランドに傷がつく
- 5. おわりに
第1章:正しい積極性
積極性については、これまでの記事で多く述べてきました。もちろんキャリア形成やブランド戦略においても積極性は重要になります。しかし、その積極性も間違えてしまうと問題が出てきます。
1年目から差がつく
診断士になってよくあるのが、1年目に何も決めず、のんびりと過ごしてしまうことです。
これは非常にもったいないです。スタートシグナルが点灯しているのにスタートしないのと同じですから、後ろからスタートした人にどんどん抜かれてしまいますし、先頭グループからどんどん離されてしまいます。
私は9年も合格までにかかったので、これまでたくさんの合格者と、その合格者のその後の歩みを見てきました。その経験から言うと、活躍している人は1年目開始の時点で商工会議所や経営者とのつながりがある人か、そうでなくても1年目から活発的に動いている人です。 逆に1年目でのんびり過ごしている人は2年目以降も同様です。診断士合格が自己満足以外ほぼ無意味なものになってしまいます。
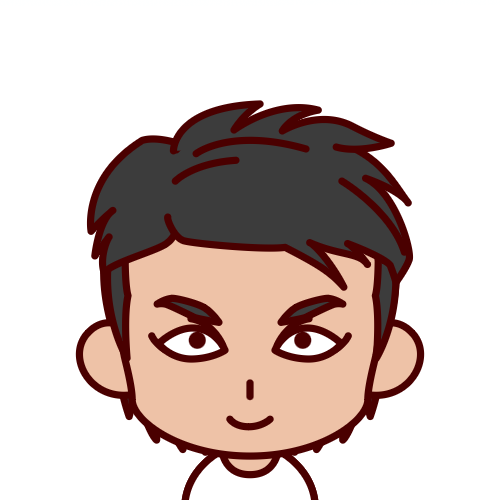
じゃあ1年目から活動的に動きます!
残念!それだけでは甘いです。
1年目から動いたとしても、以下のようだとまずいのです。しかし、そういう人が非常に多いです(私もこの1年で身に染みました)。
①受け身になっている、周りに流されている
目的意識をもって自分から主体的に動くのではなく、先輩や他の診断士の様子を見て周囲の人に言われるがまま動いてしまう人がいます。確かに動いてはいますが、気づけば変な方向に行っていることがよくあります。ご自身に合わない方向性に動いても納得できないですよね。
レースで例えると、コースを間違えていたら戻るための時間も含めて大きなタイムロスとなってしまいます。

診断士も「目的意識をもって能動的にやっている人」と「周囲に流される人、やらされている人」では大きな差がつきます
②何でも手をつけてキャパオーバーになる
何でもかんでも言われたことを引き受けて、キャパオーバーになってしまう人もいます。はい、1年目の私は7月にそうなりかけました(笑)
キャパオーバーになると体調だけでなくメンタルも弱るため、何か不快なことが起きると一気にメンタルを崩してしまいます。私もメンタルが回復するまで3ヶ月くらいかかりました。
こちらもレースで例えると、オーバーランをしたら、戻るための時間も含めて大きなタイムロスとなってしまいます。

何でも手をつける人は後半に出てくる「暇人」と思われるリスクもあります
③キャリア分析やブランド確立をしていない
就活や転職活動の際、最初に自己分析をしますよね。
しかし診断士生活をスタートする際に自己分析をする方は非常に少ないです。だからどの方向性に進んだらいいかわからず、他の診断士の動きを見ながら自分も進むとか、来た案件を手当たり次第受けてしまうことになります。結果として心身を壊したり、活動ができているのかよくわからないことになったりします。

「あなたの強みは何ですか?」「あなたのやりたいことは何ですか?」と聞かれてすぐ言えますか?
さて、これをすぐに言えるようにすることが、今回の記事のテーマです。
診断士は積極性を見せるのがポイント!
これは先ほどの①に関することですね。
診断士は積極性を見せないと何も起きません。待っていても仕事は来ません。活躍するためには自分から動かないといけません。協会などから勝手に「はい、あなたにこの案件をあげます」と仕事が来ることはありません。
私はこれまでいくつか診断士としての仕事をしましたが、すべて「これをやりたい」と周囲に宣言して得た仕事か、募集案件が来て自分から応募して得た仕事です。
ボケーっと待っていて勝手に仕事が舞い込んでくることはありません。ボケーっとしていたら診断士がペーパー資格になってしまいます。
今の居心地が良いと思い現状で満足してしまったら、そこからは衰退していくだけです。「現状維持は衰退と同じ」と思っていただいてもいいです。
自分から前に動いていかなければ成長はありません。自分から主体的・積極的に動いていけば、たとえ失敗しても経験値として蓄積され、成長につながります。どんどん積極性を出していきましょう!
「これがやりたい」と周囲に宣言してみましょう。募集案件が来たら(関連多角化の範囲内で)積極的に応募してみましょう。また、積極的に社外の人と会ってみましょう。ネットワークが広がるし、新たな視点を見つけたり刺激を受けたりしますよ。
副業禁止などで診断士としての活動ができない方も、診断士のコミュニティに入って人脈やネットワークを広げることはできると思います。それだけでもペーパー資格化は回避できます。
予期不安
もしかすると、先が不安だから手を出しにくい方もいらっしゃると思います。
しかし、それは気にしないほうがいいです。
不安や心配事の96%は「予期不安」と言って実際には起こらない取り越し苦労のものになります。 不安や心配事が出てきたら「強気・ポジティブ・楽しい」の解釈で気にしない、受け流す、深追いしないようにしましょう。アリ地獄のように不安や心配事を膨らませてしまい、積極性を出せないのはもったいないです。
自分のキャパを把握しておく
これは先ほどの②に関することですね。
先ほど、「募集案件が来たら積極的に応募してみましょう」と述べましたが、「関連多角化の範囲内で」という制約があったと思います。
ご自身のキャパを把握せず、何でもかんでも手をつけるのは危険です。途中でキャパオーバーになり、時間が足りなくなることや、体調やメンタルを崩すことになります。
「①診断士のコミュニケーション」で見たとおり、診断士の仕事では納期遅延は絶対NGです。また、他のメンバーにも迷惑をかけることになります。
そのため、ご自身なりのキャパを把握しておく必要があります。
例えば平日の夜と土日はすべてできるのか、日曜日しかダメなのか、はたまた平日ならいつでも使えるけど土日はダメなのか、ご自身なりに診断士の業務に使える時間を分析し、ご自身が診断士の業務として抱えられるキャパを把握しましょう。
徐々に加速していこう!
診断士試験に合格されて、診断士のキャリアをスタートさせたみなさん、いきなり全開で走っていませんか?そうなるとキャパオーバーになってしまいます。
マラソン大会でスタートした瞬間に全速力で走り出す、目立ちたがりの素人や芸人っていますよね。必ず途中でバテて他の選手にどんどん抜かれているはずです。
こうならないように、徐々にギアを上げていきましょう。
マニュアル車で言うと、1速からいきなり3速に入れるのではなく、「1速→2速→3速」という順に入れていく感じですね。最初は様子を見ながら1速で走り出し、慣れてきたら2速に入れて加速し、診断士の業務の要領がわかったところで3速に入れて一気に加速していきましょう。
私は診断士のキャリアをスタートした直後は1速で走り出していました。しかし、7月に実務補習が入って体調とメンタルを崩し、一気にペースが落ちてしまいました。慣れてきて2速に入れたみなさんとは異なり、私は1速のまま目一杯引っ張り続けていました。そしてペースが戻るまでに3ヶ月かかりました。ペースが戻ってからは3速で加速できるようになりましたが、ペースが落ちている間のキャリアは非効率なものになりました。

1速で目一杯引っ張って3速に入れると、タコメーターの針は(7000回転から)3000回転くらいまで落ちてしまう。4500回転を超えないと加速がもたつく。2速がないってこういうことなんですね。何でもないところでやすやすと抜かれてしまう。辛いだろうな・・・
それはMFゴーストのセリフだな。わかる人少ないぞ

はい、車のレースのアニメ「MFゴースト」の第24話から拝借しました(笑)
でもスタートから全開でいくような人はこのように「1速で目一杯引っ張って3速に入れる」ようなことをしています。だから途中でキャパオーバーを起こしてバテてしまい加速がもたつき、スムーズに加速している他の人に抜かれてしまうのです。
診断士としてのキャリアは長いです。ご自身のキャパの範囲内で無理なく加速していきましょう!
ちなみに、このMFゴーストの例えはわからない方が多かったと思います。1速とか2速とかも、最近の車はオートマが多いのでマニュアル車にはあまり触れる機会がないですよね。
しかし、車好きの方やアニメ好きの方にはわかる内容となっております。わからない人が大勢いようが、車好きやアニメ好きの人達に刺さればいいのです。刺さらない人は無視していいのです。企業経営理論でやった選択と集中、ターゲットマーケティングの考え方ですね。
この先、「勝てるフィールド」とか「独占市場・ブルーオーシャン」というものが出てきます。
しかし、これは何千人・何万人も顧客がいるフィールド・市場ではありません。
百人もいなくても、刺さる人がいれば「勝てるフィールド、独占市場・ブルーオーシャン」になります。
フィールドや市場の話を見ていく際は、ターゲットを絞るということと、せいぜい百人単位の大きさのものだと思いながら読んでください。
キャリア分析とブランド確立を行う
これは先ほどの③に関することですね。
就活や転職活動のときにやった「自己分析」によってご自身のキャリア分析をし、ご自身に合った方向性と仕事量で診断士1年目を動いていくだけでも、1年目から差別化ができます。
また、診断士のキャリアはブランドがあると有利になります。
自分のブランドが確立されていると、診断士界隈での存在感や知名度(認知度)、信頼が上がります。ブランドがあるだけで顧客や他の診断士などに思い出してもらいやすくなるため、受注獲得がしやすくなりますし、連携相手・協力者も確保しやすくなります。品質や付加価値も高いように思われるので高価格化も行いやすくなります。長期継続顧客になってくれるファンも集めやすくなります。結果として「売れ続ける仕組み」が構築され、安定した売上を獲得できます。

ブランドもののバッグがいい例ですね。高いけど高品質で長期的なファンも多い!
ブランド確立(ブランディング)の目的は「ファンを育成し売れ続ける仕組みを作ること」であり、自分から営業しなくても顧客のほうから自分を選んでくれるようになることです。
詳しくはこの後のブランド戦略のところで見ていきますが、ブランドに価値(特に情緒的価値)と独自性があり、相手に受け入れてもらえるものほど強いブランドになり、「売れ続ける仕組み」が出来上がっていきます。
第2章:キャリア分析
ここでは診断士のキャリア分析の方法を述べていきます。イメージは就活や転職活動のときにした自己分析です。もちろんこの後のブランド確立にもつながるものとなっています。
診断士界隈の機会(ニーズ)の分析
キャリア分析やブランド確立のためには、診断士界隈の機会(ニーズ)を把握しておく必要があります。
基本的には中小企業白書で主張していることが診断士界隈の機会であり、ニーズになっています。例えば伴走支援、事業承継、再生支援、創業支援、従業員の離職防止などですね。
タキプロの記事になりますが、中小企業白書・小規模企業白書をまとめてみました。こちらに国の主張や本音が書かれていますので、よろしければご覧ください。
他にもPEST分析や5フォースの分析などをやってみることで、機会(ニーズ)を見つけることができます。
また、ニーズも真因まで分析することで、潜在ニーズや顧客が本当に求めていることがわかってきます。
参考までに、私が分析した診断士界隈の機会(ニーズ)はこのようになっています。


特に近年は伴走支援について国が熱く推しています
(詳しくは「④伴走支援って?」を参照)
強み分析
診断士のキャリア分析やブランド確立のために最も重要なのが強み分析になります。これをやらないとどうやって診断士の活動をしていくかの指針や方向性が定まらないため、自分から動けません。また、間違った方向性に進んだり、キャパオーバーになったりしてしまいます。
詳しくは「③サトシのコミュニケーション&メンタル」で述べていますので、そちらをご参照いただければと思います。
再度掲載しますが、「強みノート」はかなり使えるツールだと思います。
もちろん、ご自身なりに本やアプリなどで強み分析をされてもOKです。
強み分析のコツは、当たり前すぎること・些細なことでも強みとして認識することです。
また、リフレーミングによって言い方を変えることで強みにすることもできます。「繊細」なら「人の心境の変化にすぐ気づく」などですね。これは実際に企業でも行われています。例えば「建物の内装がボロい」を「昭和レトロ」と置き換えて売りにしている企業もあります。
強みやキャリアの分析についてはセミナーや勉強会が開かれていることが多いです。そういうものに参加し、他の人とグループになってお互いに書いた強みを見せ合いフィードバックをもらうのもいいですね。
それから、伴走支援でも見たように、強みの真因まで分析すると自分の根底にある価値観やさらに大きな強みが見つかってきます。
参考までに、私の強みを公開いたします。強み分析の加減の参考にもなるかと思います。

ご自身の強みを把握し、他人に対してスラスラと言える人は診断士として有利になります。
企業でも小規模企業になるほど強みの把握や戦略が曖昧になっています。当たり前すぎ、些細なことという理由で強みだと気づいていないことが多いです。そのため、そのような企業に向けて伴走支援ができるように、ご自身の強みの把握をしていきましょう。
肩書きはブランドの鉄則
これは日本人の典型的な特徴と言えるものですが、日本人は人を肩書きで判断しがちです。テレビのニュースで大学教授や弁護士の言ったことを疑わずに信じてしまうことって、みなさんにもあったのではないでしょうか。これは本来なら悪いように言われますが、キャリア形成やブランド戦略に関してはこの特徴をうまく「活用」しましょう。
例えば全く同じ知識やスキル、経験をもっている人でも、「中小企業診断士」という肩書きをもっている人と、そうでない人(受験生)がいたとします。企業の経営者が相談をするとしたら前者の人ですよね。また、多少知識やスキルが劣っていても「中小企業診断士」という肩書きがあるとそれだけで有利に働きます。
私なら中小企業診断士以外にもほめ達やコーチング、カウンセラー、受験メンタルトレーナーの資格を取り、名刺に記載しています。実は資格によっては全く難しくなくテキストを見ながら受験できるものもあります。そういう資格は取得にかかる労力がほぼかかりません。
名刺交換をした人は名前や社名の次に、保有資格や役職などの肩書きに目が行きます。日本人は人を肩書きで見るため、簡単に取れるものだろうが何年もかかるものだろうが、このような資格が名刺に書いているだけでかなりのアピールになります。
実際、私も名刺交換をすると「カウンセラーなんですね」とか「ほめ達ってすごいですね。私のことをほめてくださいよ」とよく言われます。
強みを複数組み合わせる
「1本の矢はすぐ折れてしまうけど、3本束ねたら折れにくくなる」というのがありますよね。強みもまさにこれと同じです。1つだけなら差別化は難しくても、強みを複数組み合わせることで差別化が可能になります。
特にIT系、会計系、製造業の診断士は競合が多いため、強み1つだけではなかなか差別化は図れません。ご自身が属している(属していた)企業名では差別化は図りにくい印象です。差別化のためには複数の強みが必要になります。 例えば13代目hotmanさんなら、ITスキルと発声のスキルを組み合わせています。具体的には、「ITと発声のスキルを活かし、講師業やプレゼンを控える社会人に向けてzoomなどで発声の講演をする」という具合に活躍されています。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
強みを組み合わせるほど競合の数が少なくなる
私なら「日本全国に人脈がある」、「フットワークが軽い」、「中小企業や自治体の改善ネタを豊富にもつ」、「ほめ達」、「診断士」というように、特徴をいくつも組み合わせるほど競合が少なくなるので、唯一無二の存在になります。
・中小企業診断士 →競合は数万人いる
↓
・フットワークが軽い中小企業診断士 →競合は1000人くらいになる
↓
・日本全国に人脈のあるフットワークが軽い中小企業診断士 →競合は100人くらいになる
↓
・日本全国に人脈のあるフットワークが軽い中小企業診断士で、中小企業や自治体の改善ネタを豊富にもつ →競合は20人くらいになる
↓
・日本全国に人脈がありフットワークが軽いほめ達の中小企業診断士で、中小企業や自治体の改善ネタを豊富にもつ →競合がいなくなる(唯一無二)
キャリア形成やブランド戦略では、この唯一無二の状態を目指す(確保する)ことが重要です。経済学で言う「独占」、企業経営理論で言う「ブルーオーシャン」ですね。ニッチャー戦略と言うか、ニッチ市場でのナンバーワンのイメージです。
独占なら供給量を少なくでき、価格を上げることができますから、少ない負担で稼げるわけです。また、営業をしなくても勝手に顧客のほうから集まってきます。
もちろん、独占は無理でも最低でも「寡占」の状態にはもっていきたいです。
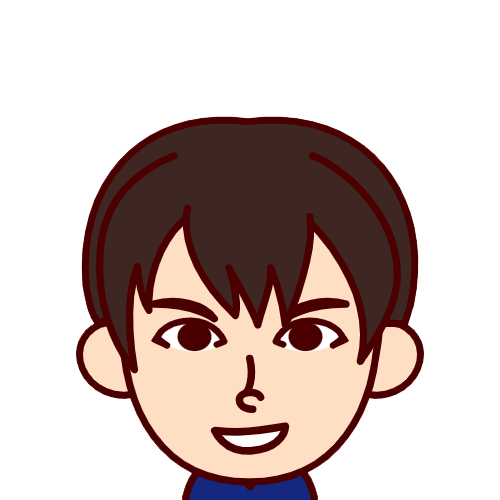
サトシはさらに「多年度で診断士受験の経験とノウハウと知識が豊富」とか「受験生支援が得意」という強みもあるから、もっと競合が少なくなるよね
今回紹介している唯一無二、独占・ブルーオーシャンの内容は説明上シンプルにしています。実際はそんな単純にはいかないですし、強みについての内容も多少盛っています。今回は説明の都合上、私の強みやキャリアプランなどを好き放題書かせていただいていますが、自慢の意図は全くありません。謙虚にいきましょう!
(ちなみにこれは「③サトシのコミュニケーション&メンタル」でも同様です)
クロスSWOT分析をしてみよう
強みを複数組み合わせることで「独占・ブルーオーシャン」のもとができます。あとはそれを実際のニーズにつなぐ必要があります。ニーズがないのに唯一無二では意味がありませんからね(ただの自己満足です)。
そこで使われるのがクロスSWOT分析です。クロスSWOT分析をすることで、強みを複数組み合わせたご自身が実際に仕事としてできるフィールド、勝てるフィールドが見え、キャリアの方向性が見えてきます。
診断士にとっての勝てるフィールドは、「独占市場・ブルーオーシャン」です。そこで仕事をしていくことがあなたのキャリアの方向性になります。
なお、フィールドやキャリアの方向性についても「選択と集中」が必要です。中小企業がターゲットやドメインを絞り込むように、診断士のフィールドやキャリアの方向性も絞り込む必要があります。
「誰でもウエルカムです」や「何でもやります、やれます」では仕事は獲得しにくいです。また、自分から手を上げる場合でも「何でもやります、やれます」であれこれ手をつけているとキャパオーバーになります。
クロスSWOTの各事象のイメージ
クロスSWOTの組み合わせ(各事象)のイメージとしては、以下のようになっています。
・S×O:積極的に競争優位にもっていこう!(積極展開、攻めの経営)
・W×O:弱みを改善していこう!(弱点克服)
・S×T:強みで競争回避しよう!(独自路線)
・W×T:素直に撤退しよう!(防衛戦略、勇気ある撤退)
自身のキャリア形成やその先にあるブランド(後で見ていきます)につながるのは、基本的には「S×O」で、積極的に競争優位にもっていく(積極展開、攻めの経営)路線になります。
例えばメンタルのスキルを活かし、ニーズが高まっているメンタルヘルスの講師や執筆の仕事をしていくことが挙げられます。メンタルヘルスの講師はメンタルのスキルがないとできませんから、それがあれば他の診断士との競争優位・差別化が図れます。
やはり中小企業と同じく、診断士のキャリアやフィールドも「強みを活かせ、ニーズがあるもの」は王道になります。
また、「S×T」は強みで競合との競争を回避する路線(独自路線)です。診断士にとっての競合は税理士や社労士ですね。こういう人達が苦手な分野や手をつけにくい分野に進出し、それに合う強みを活用できれば、「S×T」の路線も見出せます。
例えば「④伴走支援って?」で見たように、コミュニケーション力や傾聴力を活かして伴走支援の路線に行くのも「S×T」の路線ですね。税理士や社労士は一方向のコミュニケーションになりやすく、傾聴が苦手ですので進出してきません。そのため、伴走支援は競争回避になります。

競合(T)の強みと弱みも分析しておきましょう!
逆に診断士の場合、弱み(W)はノータッチか外部に任せます。なので、「W×O」の弱みを改善していく路線(弱点克服)、「W×T」の撤退路線(防衛戦略、勇気ある撤退)は無視するか外部に任せて構いません。
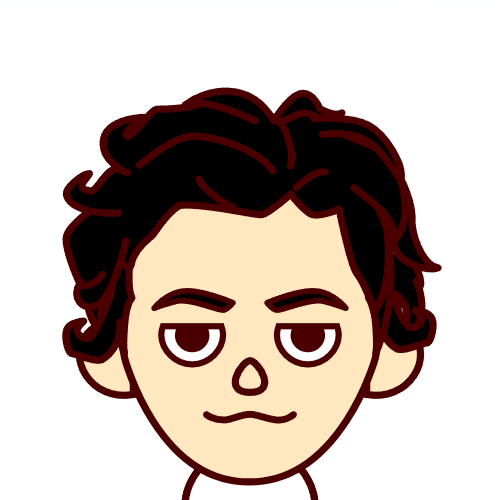
例えばIT苦手代表のサトシがITの路線に行っても結果は見えているよね。それならITが得意な俺に任せなさい!
参考までに、私がクロスSWOT分析をして出したやりたいこと、キャリアの方向性を公開いたします。クロスSWOT分析の参考になるかと思います。

なお、SWOTとクロスSWOTは3C分析で行うこともできます。

これは自分が提供できるサービスメニューになります。
あなたのブルーオーシャンを見つけよう!
クロスSWOT分析をする際に、他に意識することとして「競合」の存在があります。
競合が多いほどレッドオーシャンに、少ないほどブルーオーシャンになります。
ブルーオーシャンは、「自社(自分)が提供できて、顧客のニーズがあり、競合が手を出していない」領域です。これを探していきましょう。
ブルーオーシャンなら差別化も容易で、自分が差別化された唯一無二の存在になれば、そのフィールドが独占市場・ブルーオーシャンになり、営業をしなくても顧客のほうから勝手にやってきます。それがあなたの勝てるフィールド、キャリアの方向性になります。
逆に「自社(自分)が提供できて、顧客のニーズがあるが、競合も手を出している」領域はレッドオーシャンとなります。差別化は難しく、ここで勝負をするのは避けたいところです。

さて、私なら「日本全国に人脈がありフットワークが軽く、中小企業や自治体の改善ネタを豊富にもっているほめ達の中小企業診断士」という唯一無二の強み(組み合わせ)がありますね。
もちろん、これを望んでいる顧客はいます。ダメ出しよりもほめてほしい、対面でほめてほしいと考えている社長や従業員は多いです。若い人ほどほめてほしいニーズが高いため、これからはどんどんそういう社長や従業員が増えていきます。また、伴走支援や地域活性化のニーズも高まっています。コンサルタントに大企業の理屈をドヤ顔で言われて困っている社長も多いです。
伴走支援をしてくれて、必要に応じてこまめにほめてくれて、しかも「日本全国どこでも行きます。中小企業や自治体の改善ネタを豊富にもっています。必要ならどんどん地元の専門家を紹介します」という診断士は唯一無二のレベルだと思います。つまりこの市場は(あくまで説明のためのシンプルな設定ですが)ブルーオーシャンとして私が独占できるわけです。
それってあなたのやりたいことですか?
いくらブルーオーシャンで独占できると言っても、自分がやりたくないことではモチベーションが続かないですよね。
売上2,000万円稼げるけど、毎日パワハラとセクハラとカスハラに悩まされて神経をすり減らしながらやらないといけない仕事だったら、大抵の人はやりたくないと思います。
逆に自分がやりたいことなら、楽しくできますよね。私はよく

診断士はサトシさんの天職ですよね

診断士のことを話しているサトシ君って本当に楽しそうだよね
と言われています。
「楽しいもの、自分がやりたいと思っているもの」を満たすと、努力をする際に「努力をしている」という自覚がなくできます。毎日が充実しているような感覚で仕事ができるため、VRIO分析にあるような価値や希少性、模倣困難性が高まり、差別化できる可能性はかなり高くなります。
「ブルーオーシャン」かつ「やりたいこと」なら、それがあなたの勝てるフィールドであり、キャリアの方向性になります。
このブルーオーシャンの中で関連多角化を図る
このブルーオーシャン内で関連多角化を図ることも可能です。
関連多角化の範囲で事業の柱を3つ立てるといいとされています。それによりシナジー効果を発揮できて模倣困難性が向上し長期的に競争優位を確保でき、安定売上につながる効果があります。
逆に無関連多角化だとリスク分散はできますが経営資源も分散し、方向性がブレるリスクもあります。

関連多角化と無関連多角化、企業経営理論でやりましたね
私なら、「日本全国に人脈がありフットワークが軽く、中小企業や自治体の改善ネタを豊富にもっているほめ達の中小企業診断士」として、講師、執筆、伴走支援の3つの事業の柱を立てています。
伴走支援では上記のようにほめてほしい社長や従業員のニーズに応えています。そのノウハウを執筆案件で書けますし、講師案件で講演ができます。つまりシナジー効果が起きています。逆に講師の経験を伴走支援にも活かせていますし、執筆のネタにもなっています。
これはまだ先のことですが、これらの経験と実績を積むことで商工会議所などの支援機関での案件につなげていく予定です。
経営理念、ビジョン、ミッションなどを作ってみる
さて、ここまで強みを複数組み合わせ、機会に当てるためのクロスSWOT分析をして「独占市場・ブルーオーシャン」を見つけて唯一無二の存在(もしくは寡占市場でそれに近い存在)になり、さらに関連多角化もできてきたと思います。
そこで、経営理念、ビジョン、ミッションなどを作ってみましょう。せっかく診断士になったわけですから、診断士の知識を活用しないともったいないですからね。それに、企業の経営理念などを作る機会ってそうはないと思います。なので、自分自身の経営理念などを作ってみましょう。
経営理念は自分が仕事を通じて社会にどのような貢献をしたいのか、なぜこの仕事をしているのかを入れてみましょう。例えば「様々な人との関わりを大切にする」など診断士に必要なことや、「クライアントや地域や社会を盛り上げていく」など相手に対することを経営理念などに入れてみてもいいと思います。
参考までに、私の経営理念、ビジョン、ミッションはこのようになっています。私はこの経営理念にあるように、「日本全国にいる様々な人に元気と勇気と希望と笑顔と感動を届け、地域や社会を盛り上げる」をモットーに取り組ませていただいております。

第3章:ブランド確立・ブランド戦略
さて、ここまでの内容があなたのブランドになります。これはまさにあなただけのブランドです。「パーソナルブランディング」とか「セルフブランディング」というやつですね。
ブランド確立
まず、「中小企業診断士2次試験 解き方の黄金手順」でお馴染みの寺嶋直史先生は、著書「儲かる中小企業になるブランディングの教科書」の中で、ブランドを以下のように定義しています。
ブランドとは、顧客がこの会社や商品・サービスに対して思い浮かべる「価値イメージ」である。
寺嶋直史 儲かる中小企業になるブランディングの教科書 より
これを個人に応用すると、以下のように定義できます。
ブランドとは、顧客がその人自身やその人が提供するサービスに対して思い浮かべる「価値イメージ」である。
「イメージ」とありますが、明確な表現になっているほど、相手にとっての明確なブランド認知につながります。
価値
「価値」については機能的価値(機能面)と情緒的価値(感情面)があります。
機能的価値は商品やサービスそのもののことで、例えば飲食店なら食事の提供、カウンセラーならカウンセリングです。私なら双方向のコミュニケーションやほめることによる伴走支援、講師、執筆ですね。
情緒的価値は商品やサービス以外の価値のことで、例えば飲食店なら「居心地がいい」、カウンセラーなら「話を共感してもらえてスッキリした」です。
情緒的価値は共感や信頼などを通じて顧客に価値を浸透させていく効果があります。その結果、ロイヤルティの高い長期継続顧客獲得や口コミによる新規顧客獲得ができます。機能的価値と違って人による差異が大きくAIにも代替できないため、差別化のためのカギになります。強いブランドは情緒的価値が優れており、人の心に訴えかける要素があります。
例えば私なら「話を聞いてもらえてスッキリできる、ほめてもらえる」や「講義を聞いてわからなかったところがスッキリした」、「記事を読んで勉強する気になった」などが情緒的価値と言えますね。
なお、当たり前ですが利用シーンとマッチしていないと価値はありません。「野球が上手い診断士」じゃブランドになりません。また、基本的にはポジティブなものでないと価値にはなりません。「ダメ出しされてへこまされる診断士」ではブランドになりません。

「日本一接客態度の悪い店」のようにネガティブなものを価値にすることもできますが、それはかなり難しいです
独自性
ブランドを確立するなら独自性も意識していく必要があるでしょう。
明らかに差別化できるならシンプルでいくこともできますが、そうでないなら組み合わせることがオススメです。強みのところで見ましたね。要はそれをやれば独自性になります。
私なら「日本全国に人脈がある」、「フットワークが軽い」、「中小企業や自治体の改善ネタが豊富」、「ほめ達」、「診断士」というように、特徴をいくつも組み合わせるほど、競合が少なくなるので、唯一無二の存在になり、ブランドになります。つまり、勝てるフィールド、独占市場・ブルーオーシャンのフィールドで見た「日本全国に人脈がありフットワークが軽く、中小企業や自治体の改善ネタを豊富にもっているほめ達の中小企業診断士」が私のブランドになります。
私以外にも、例えばhotmanさんなら「IT×声の講師ができる診断士」ということでブランドにしています。IT系なので先ほども述べたように強み1つでは差別化が図りにくいですが、複数掛け合わせることで唯一無二になり、強いブランドを確立して差別化が図れています。
強みの組み合わせのところでも見ましたが、1つ1つは些細なことでもOKです。それを複数組み合わせ、それが機能的価値と情緒的価値を大きくさせるなら、差別化要素になります。
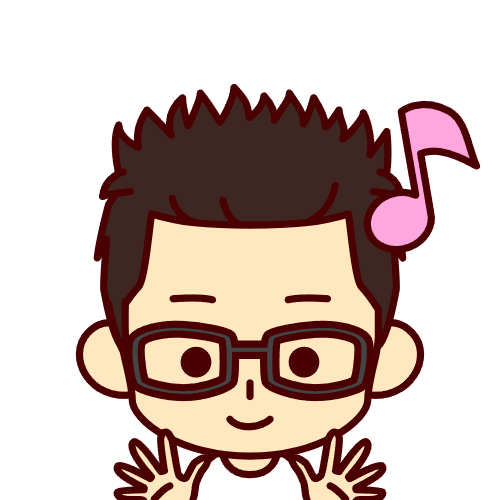
10人に1人の強みを2つ組み合わせたら100人に1人になるよね
企業経営理論のバリューチェーンの論点でも、強みのある機能を複数組み合わせると模倣困難性が高まることや高付加価値化が図れることを習いましたよね。
ポーターの競争戦略論
企業経営理論で習ったポーターの競争戦略論はキャリア分析やブランド確立にも適応できます。
儲かる市場を選ぶために5フォースモデルで業界構造を分析し、競争回避の戦略として参入障壁を築き、差別化集中戦略を実施し、価値連鎖分析で複数の強みを組み合わせて模倣困難性を高めてVRIOを満たし、持続的競争優位を確保して長期継続的に安定利益を確保するものですね。
また、中小企業白書でも「中小企業・小規模企業はきちんと戦略を立ててほしい」と主張しています。
ブランドはキャリア形成のところで見たように、強みを複数組み合わせてニーズに当てる「S×O」でいき、高付加価値化による差別化を図ることで確立できます。差別化の程度が強いほど強いブランドになります。
その一方で、独自のポジションなど唯一無二のフィールドで使えるものも強いブランドになります。「よそがやらないから、うちがやろう」という「S×T」の方向性でも強いブランドは構築できます。
ブランド確立の目安
・なぜそのサービスを受けたいのか
・なぜあなたからサービスを受けたいのか(なぜ他の人ではなくあなたが選ばれるのか)
この2つを明確に答えられるなら、ブランド確立(ブランディング)はできていると言われています。
先ほども見たように、ニッチでブルーオーシャンのフィールドを見つけ、そこで独占・ナンバーワンになりましょう。そうすると上記の2つにも明確に答えられると思います。
強いブランドというのは、唯一無二やナンバーワンにこそ与えられるものです。日本一高い山は富士山だけど二番目に高い山はすぐに出てこないように、唯一無二やナンバーワンは強いブランドになります。
そして、強いブランドを確立し、クライアントが忠誠心(ブランドロイヤルティ)をもてるようにしましょう。もちろん心理的にも行動的にも高い「真のロイヤルティ」ですよ。
ブランド戦略も関連多角化でいく
企業経営理論でブランド戦略ってやりましたよね。ブランド名と製品カテゴリーの組み合わせのやつです。
覚えていますか?
ライン拡張、ブランド拡張、マルチブランド、新ブランド、ですね

「ラブマシーン」と覚えるって?そらそうよ
この製品カテゴリーをご自身の仕事のフィールドと考えれば、ブランド戦略の知識を診断士のキャリア形成に応用できます。
と言っても、先ほどの勝てるフィールド、独占市場・ブルーオーシャンのフィールドで見た内容と同じです。
まずはご自身のブランドを確立し、ご自身の仕事に直結するフィールドで活躍しましょう。例えば私なら税理士事務所で伴走支援をしていますので、「日本全国に人脈がありフットワークが軽く、中小企業や自治体の改善ネタを豊富にもっているほめ達の中小企業診断士」というブランドを伴走支援で活かします。
次に、ブランドはそのままで、関連多角化により新たなフィールドに挑戦しましょう。私なら、「日本全国に人脈のありフットワークが軽く、中小企業や自治体の改善ネタを豊富にもっているほめ達の中小企業診断士」というブランドで執筆や講師業に進んでいます。そして講師、執筆、伴走支援の3つの事業の柱を立てています。
シンプルなフレーズでのブランド名を作る
私の「日本全国に人脈がありフットワークが軽く、中小企業や自治体の改善ネタを豊富にもっているほめ達の中小企業診断士」というブランド、長すぎませんか?(笑)
確かに強みを複数組み合わせていて内容的にはわかりますが、一発でわかるインパクトはありません。
そこで、可能ならシンプルなフレーズでブランド名を考えてみましょう。
やはり、ブランド名は短いほど覚えやすくなります。例えば「Japan Railways」より「JR」のほうが覚えやすいですよね。
また、アイドルが自己紹介のときに「あなたの心のお供」などのキャッチフレーズをつけていますが、あれでもいいです。自分が提供できる価値や専門性を一言で表すフレーズを作り、それをブランドにしてみましょう。

実は私、あの長いブランドの他にシンプルなフレーズもブランド名にしています
ロゴや色などでもブランド化できる
サービス名やキャッチフレーズ以外にも、ロゴ、色、似顔絵アイコン、マークなども自分を表すものならブランドになります。
例えば緑色の帯のコンビニならファミリーマート、青色の帯のコンビニならローソンを思い浮かべますよね。山手線なら黄緑、東海道新幹線なら白と青ってすぐにイメージしますよね。このように、パーソナルカラーをブランドにする手もありますよ。
15代目メンバーでパーソナルカラーと言えば、かますの緑でしょうか。

私なら緑の髪の似顔絵アイコンがブランドを構成しているのね
ブランドになるフレーズを商標登録する
フレーズ、色、ロゴ、マークと聞いて、何か思い当たることはありませんか?
そう、商標です。
実は私、シンプルなフレーズの商標登録をいたしました。2024年の6月に出願をし、ちょうどクリスマスの12月25日に登録をいたしました。
もちろん模倣防止の観点もありますが、やはりご自身のブランドが一発でわかるフレーズを商標登録していると相手に認知もされやすいです。
個人でブランドとなるフレーズの商標登録をしている人なんてまずいないので差別化も圧倒的にしやすくなりますから、ぜひやってみてはいかがでしょうか。せっかく法務で商標のことを習ったのですから、その知識を活用・体験してみてください。法務の知識の復習にもなりますよ。

「ニッポンの社長」って芸人もいるし、「中小企業の社長」なんていかが?
よっ!社長!

中小企業白書・小規模企業白書でも述べている
ブランド化や商標登録の話は中小企業白書や小規模企業白書においても中小企業・小規模企業に向けて国が主張しています。
つまり、中小企業や小規模企業はブランドやノウハウなど、無形資産にこそ価値があるため、もっと自社・商品・サービス・技術についてブランドを構築し、必要なら知財での保護をすることで、需要が高まり、価格を上げられ、利益も増えると主張しています。 中小企業や小規模企業に向けて情報提供をする診断士なら、ブランド化や知財での保護も自分なりに体験しておいたほうがいいですよね。
マーケティング戦略を実行する
いくらキャリアの方向性やブランドを構築しても、顧客や他の診断士などに自分の存在や価値を認知してもらえないと、必要なときに自分を思い出してもらえず、仕事などの獲得にはつながりません。
そのため、自分の存在や価値を認知し、必要なときに自分のことを思い出しやすくするためのマーケティング戦略が必要になります。
マーケティング戦略と言えば、「誰に、何を、どのように、効果」ですよね。
「誰に」はあなたが活躍するフィールドにいる顧客、「何を」はあなたができること(やりたいこと)、「どのように」は強みやブランドを活かすこと、「効果」はLTV系のことになります。
しかし、実はここまでの内容ができていれば、マーケティングの「誰に、何を、どのように、効果」は自動的にできています。
ナンバーワン、オンリーワンになり、営業しなくても顧客のほうから勝手にやってくる独占市場・ブルーオーシャンを見つけていますよね。
この独占市場・ブルーオーシャンに来る客が自動的にあなたの顧客(ターゲット、誰に)になります。
また、強みを複数組み合わせたものが「どのように」になり、それによるサービスが「何を」になり、効果として長期継続顧客獲得や口コミによる新規顧客獲得になります。

「誰に」は、「サイコ、ジオ、デモ」を考えるとさらに具体的になります。また、仮の顧客像(ペルソナ)を設定するとニーズの想定がしやすくなります
他にマーケティング戦略で意識すべきなのが、マーケティングの4Pですよね。
・価格戦略:基本的には「高い」=高付加価値での差別化路線
・チャネル戦略:対面、オンラインの他に、人脈・ネットワークも該当
・製品戦略:あなたができること(やりたいこと)。「何でもやります」はダメ
・プロモーション戦略:特に広告がポイント
プロモーション戦略の広告については、ブログやSNS、YouTubeへの投稿、自分のホームページの作成などがありますね。頻繁に投稿すること、知り合いに対しては定期的連絡をすることが効果的です。
もちろん成果をアピールするのもいいですね。確かな成果はブランドを強化してくれます。
なお、具体的な広告の方法などは士業向けのマーケティングの本を読んでみてもいいかもしれません。かなり詳しく書かれていますよ。

ブランドは相手の不安を解消させる効果もあります
積極的に情報発信する
ブランドを構築したら、ぜひ強みや取り組み、やりたいことと一緒に積極的に情報発信してみてください
FacebookやLINEでの発信のほか、イベントなどでアピールするのもいいですね(但し、目立ちたがりの出しゃばりにはならないようにしてください)。
これは中小企業白書・小規模企業白書でも主張しています。特に小規模企業になるほど強みや売り、取り組みなどを積極的に情報発信してアピールしてほしいというのが国の本音です。
診断士もどんどんアピールして他人に認知してもらい、人脈やネットワーク、仕事につなげていきましょう。
「私はこれが得意、私はこれがやりたい」と周囲の人に知られているほど、自分のことを思い浮かべてもらい、仕事が集まってきます。これにより、営業をしなくても営業しているのと同じ効果をもたらすようになります。これがプロモーション戦略の理想です。
個人名刺を作る
これは「③サトシのコミュニケーション&メンタル」でも扱いましたが、会社の名刺ではなく個人の名刺を作っておくと差別化が図りやすいです。
会社の名刺だと会社の連絡先になってしまうので連絡が取りにくい面もありますが、自由に記載できない面が大きな痛手です。
その点、個人名刺なら個人のメールアドレスやFacebook、LINEの案内があるので連絡が取りやすいです。また、強みや資格、経歴、実績、アピールポイントなども書けるので、効率的に相手に自分自身や自分がもつ「ブランド」を認知してもらうことができます。
ここに先ほどの商標登録されたフレーズがあると、名刺交換した際に目立つのでさらに認知されやすくなります。
横断的に取り組んで知名度を上げる
特に1年目の診断士なら、慣れてきた段階で関連多角化の範囲内+ご自身のキャパの範囲内で多くのことに取り組んでみたほうがいいと思います。
横断的に取り組んでいると、診断士界隈での存在感や知名度(認知度)、信頼が上がります。それだけで他の診断士などに思い出してもらいやすくなるため、ブランドになります。
例えば私は一発合格道場以外にタキプロもやっています。タキプロは、最初は名古屋の勉強会班のみでしたが、慣れてきたあたりで関西・zoomの勉強会班、ブログ班、メディア班(YouTube出演)、事務局(他団体連携プロジェクト、タキプロメンバー交流会)も担当しました。
おかげで、タキプロのメンバーの中での知名度は圧倒的に上がりました。タキプロメンバーどうしの集まりがあるといつも私の名前が出るそうです(悪口じゃないよね?笑)
そのため、「日本全国に人脈がありフットワークが軽く、中小企業や自治体の改善ネタを豊富にもっているほめ達の中小企業診断士」という私のブランドを多くのタキプロメンバーに認知していただいたと思います。少なくとも「サトシ=日本全国どこでも行く」とよく言われていますので(笑)
ここまでのことはしなくても、研究会や勉強会などのコミュニティでは横断的に取り組んでみてもいいと思います。

もちろん、診断士の活動に慣れてきてから徐々にやる形でいいですよ。いきなり全速力でやると必ず途中でバテます
お金にならなくても実績を積む
横断的に取り組む、積極的に取り組むと言うと「お金にならないことはやる気がしない」と思われる方もいらっしゃると思います。また、もらえるお金が多い仕事しか引き受けたくない方もいらっしゃるかもしれません。
別にそれは悪い考えではありません。しかし、長い目で見たらお金にならない取り組みをしたおかげでお金を多く稼げるようになります。
ボランティア、もしくは低報酬でも「あのプロジェクトに関わりました、あの雑誌に記事が載りました」という実績を名刺に書いたりFacebookで投稿したりすることで、周囲の人にアピールすることができます。
実績は強いブランド確立につながります。それにより、将来的には多くの受注を得ることができ、長期的に見たら多くの収入を得ることができます。

短期的なお金より、長期的なブランド確立のほうが大事

迷っているくらいならやる。これが道場の掟です!
ブランドに統一感をもたせる
ブランド品が色やパッケージにもこだわっているように、ご自身の名刺やファッションもブランドに合わせましょう。
ブランドの周辺まで統一感があると相手が覚えやすくなります。例えばブランドもののバッグなら、店内もホームページも包装も高級感があるものになっていますよね。店がズタボロだったら違和感ありありです(笑)
これはコミュニケーションでも同様です。例えばほめ達の私なら、コミュニケーションもポジティブで楽しいものなら統一感があります。Facebookで愚痴をこぼすのはおかしいですし、LINEなどで怒っている印象や冷たい印象のメッセージを書くのはおかしいですよね。 以前の記事で「普段と仕事で態度が変わる人はまずい」と述べたのは、ブランドの統一感がなく強いブランドにならないからです。
1分・1枚で自己紹介できますか?
さて、ここまで見てきた内容で、ご自身の強みや勝てるフィールド(ブルーオーシャン)、ブランド、マーケティング戦略も含め、1分間で話せる、もしくはA4の用紙1枚で書ける自己紹介をしていきましょう。
診断士になると、自己紹介をする場面が増えます。よくあるのが口頭で1分話す、1枚のWordやパワポに書くというものです。
ところが、大抵の人が自慢話やどうでもいい話、相手にわからない話、趣味の話などをしてしまい、効率的な自己紹介ができず、インパクトが残らないため、相手からすると「その他大勢」と同じになっています。
自己紹介をする場合、このようなものを入れるとうまくいきやすいとされています。
・肩書き(中小企業診断士など)
・キャッチフレーズ(経営理念などでもOK)
この2つで相手に興味をもってもらいます(2割ほどの量です)。
・プロフィール
・強み(特徴):ブルーオーシャンになる特徴や組み合わせ
この2つで相手にインパクトを残します(8割ほどの量です)。
自己紹介はインパクトが残ることが重要です。例えば私なら「京都から来た」とか「日本全国どこでも出没する」とか「ほめ達としてほめまくります」と言うとインパクトに残りやすいです。こういうインパクトに残るものを自己紹介の所々に入れていきましょう。
ということで、私の自己紹介はこんな感じになります。太字のところがインパクトを与えるものです。
サトシの1分自己紹介
みなさん、はじめまして。
ほめ達診断士こと、中小企業診断士のサトシです。
千葉県出身、京都府在住で京都市内の税理士事務所で主に中小企業・小規模企業に向けた伴走支援を行っています。
「日本全国にいる様々な人に元気と勇気と希望と笑顔と感動を届け、地域や社会を盛り上げる」をモットーに、伴走支援のほか、講師や執筆の仕事もさせていただいております。
趣味は鉄道で、新幹線に乗れば体力が全回復します!
なので今日も京都から来て、最終の新幹線で帰ります(笑)
おかげでフットワークはかなり軽く、日本全国様々なところを頻繁に訪れています。稚内以外はすべて近場です!
伴走支援は私の得意なコミュニケーション力やほめ達の力を活かし、京都府の中小企業や小規模企業、自治体を相手に◾️件ほどやらせていただいております。
講師は●●の講座や●●のセミナーなど●件登壇したことがあります。
執筆は▲▲の雑誌の記事の執筆など▲件を経験しております。
その他、一発合格道場やタキプロで「サトシ」として受験生支援の活動し、勉強会、ブログ、他団体連携やメンバー交流の幹事、YouTube出演をしました。そのため、日本一、横断的にやっていたと思います(笑)
あと、出身地や出張・旅行先を言っていただければそこの地元トークができます。ぜひみなさんとお話できればと思っていますし、ほめ達としてみなさんのことをほめまくりたいと思っております。
よろしくお願いします。
いかがですか?
みなさんもぜひ、自己紹介文を作ってみてください。
1分間であなたの魅力を効果的に伝えることができれば、他の人の印象に残り、それがブランドになります。

自己紹介をするときは明るく楽しそうな雰囲気を出すといいですね。全く同じ内容でも暗そうに話している人と明るく楽しそうに話している人では相手の印象は全く異なります
「●●と言えばこの人」を目指す
「●●と言えばこの人」のようなイメージを他人から持たれることが「ブランドになる」ということであり、ブランド確立(ブランディング)のあるべき姿となります。
企業経営理論のブランドの論点でブランド連想やブランド再生ってありましたよね。
例えば京都と言えば寺や神社が頭に思い浮かびますよね。名古屋ならお城や味噌カツが思い浮かぶかと思います。これがブランド連想です。
逆に寺や神社の街と言えば京都、お城や味噌カツと言えば名古屋というように、逆のアプローチでも思い浮かぶと思います。これがブランド再生です。
どちらのアプローチでも思い浮かぶと強いブランドになっていると言えます。
例えば私なら「日本全国に人脈がありフットワークが軽く、中小企業や自治体の改善ネタを豊富にもっているほめ達の中小企業診断士」というのがブランドですが、私が会った人にはよく「ほめ達」とか「フットワークが軽い」とか「あちこちに人脈がある」と言われます。つまり私を見てイメージが思い浮かんでいる(ブランド連想ができている)のです。
また、「ほめ達」とか「日本全国どこでも行ける」と聞いて私のことを思い浮かべていただければ、ブランド再生ができていることになります。
「サトシと言えばフットワークの軽いほめ達診断士」、「フットワークの軽いほめ達診断士と言えばサトシ」というように、私についてどちらのアプローチでも思い浮かべていただければ、ブランドになっていることになります(そうなっていれば嬉しいです)。もちろん、ブランド連想・再生がともに素早く(強力に)できるほど強いブランドになります。
強いブランドは、コンセプトやイメージが明確であり、情緒的価値が強く他人の感性に訴求することができるものです。だから簡単にその名前と特徴を頭の中に思い浮かびます。しかもそこからプラスアルファの意味も見出します。だからすぐに顧客に選ばれるのです。しかもリピーターにもなりやすく、口コミも広まりやすいです。
なお、頭の中に思い浮かぶと言っても、それはもちろんポジティブなイメージです。悪評のようなネガティブなイメージが思い浮かんだら顧客からは選ばれません。
第4章:キャリア分析やブランド戦略の効果を高める方法
ここからは、これまで見てきたキャリア形成やブランド戦略の効果を高める方法について見ていきます。
合格すると視野が広がる
さて、ここまで強み(S)、機会(O)、クロスSWOT、ブランド戦略を見てきましたが、診断士生活を進めていくと次々と新たな発見が出てきます。そうすると、キャリアプランも適宜見直していく必要があります。
合格したら受験生の頃より5〜10倍くらい視野が広くなります。受験生の頃には知らなかった「診断士の業界のこと」がどんどんわかってきます。「あんなやり方があったのか」とか「こういう仕事があるのか」というのがわかってきます。
例えば私も実務従事のことは診断士試験合格時点ではあまりよくわかっていませんでしたし、登録や更新に必要なポイントをもらえる「加減」もよくわかっていませんでした。商工会議所の人との関係性の作り方や研究会のこともわかりませんでした。しかし5月くらいになると先輩や道場・タキプロのメンバーから情報が入ってきて、そのようなものもわかるようになりました。
実務補習や実務従事をやると課題もたくさん見えてきます。「こういう人はまずい」という反面教師にすることも見えてきます。
今はまだ「見えていない」だけで、診断士業界のことは徐々に見えてくるようになります。
短サイクルでキャリアを見直す
新しい発見があったらその都度、ご自身のキャリアプランを見直していくといいと思います。つまり、短サイクルでキャリアプランを見直していきましょう。そうすると効率的に診断士生活を送ることができます。
診断士生活をスタートしたらいきなり全速力ではなく徐々に加速したほうがいいと述べましたが、それは途中で診断士業界のことについて徐々に新たな発見があるからです。いきなり全速力でキャパオーバーを起こしていると、新たな発見をしてもそれに対応することができません。徐々に加速してキャパに余裕があれば、発見があるたびに計画を見直して対応することができます。
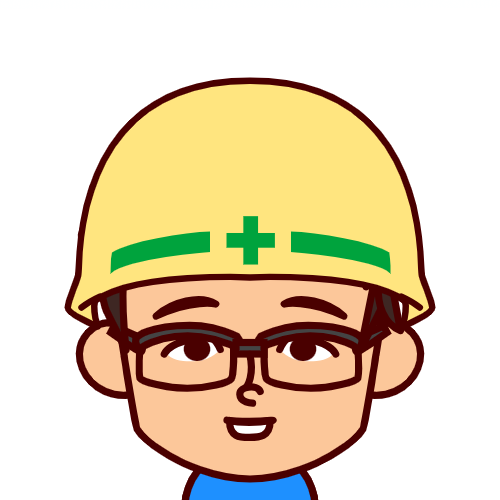
こまめな変更。生産計画と同じですね
ブランド戦略の留意点
ここでは、ブランドやそれを活かした戦略に関する留意点を見ていきます。
メンタルに不備があるとブランドに傷がつく
これはご自身のメンタルが弱くてすぐに落ち込んでしまうという対内的なものではなく、例えば機嫌の波が激しい、上から目線、承認欲求目的の言動、ネガティブなことばかり言うなどの対外的なことが該当します。こういう人は他人から不快に思われるので、ブランドに傷がついてしまいます。
企業経営理論で習ったように、「ブランド知識=ブランド認知×ブランドイメージ」です。いくら認知されていても、悪評などによりイメージがマイナスになるとブランド知識はマイナスになってしまいます。つまりブランドの持つ資産価値(ブランドエクイティ)がマイナスになってしまい、ブランド戦略はうまくいかなくなります。
以前述べました「普段は良くても仕事になると攻撃的になる人はまずい」というのも、イメージがマイナスになるのでブランド知識やブランドエクイティがマイナスになり、他の人が悪い印象をもってしまうからです。
メンタルの不備を避けるための方法について、詳しくは「②診断士のメンタル」をご覧ください。
極限まで絞り込むと、「謙虚さ、ポジティブ、楽しい」のメンタルがないとブランドに傷がつきやすいです。
例えば「自分が成功して良い流れになっていることは、自分ではなく周りの人のおかげ」と思えていると、謙虚さを維持できていることになります。しかしこれが曖昧になってくると謙虚さがなくなってきていることになり、他人からすると不快に思われたりします。
また、普段から「ポジティブ、楽しい」を意識していると、思考・発言・態度も「ポジティブ、楽しい」ものになっていき、仕事の結果や診断士生活の流れも「ポジティブ、楽しい」ものになっていきます。この流れに沿っていないと他人からすると不快に思われる可能性があります。
自慢はブランドに傷がつく
もしかしたら、みなさんの中には報告という名の「自慢」をされてしまう方もいらっしゃると思います。
学歴自慢、職歴自慢、診断士の成果の自慢などが代表例ですが、2次試験の採点サービス結果や実際の得点結果の報告(自慢)もそうですよね。本人としては報告のつもりで自慢の意思はなくても、他人からは自慢に受け取られてしまいます。
点数や偏差値、合否、成果など、相対的な比較ができてしまうものは相手の劣等感につながります。こういうものの報告をすると、相手は「すごいですね」と言ってくれるかもしれませんが、内心は劣等感を抱かせられ不快に思っています。つまり、ブランドイメージがマイナスになるため、ブランド知識やブランドエクイティもマイナスになってしまいます。
自慢をしたらご自身のブランドに傷をつけることになります。いくら技術力がすごくても人間性に問題のある人とは一緒に仕事したくないですよね。
承認欲求は他人ではなく自分自身で満たしましょう。すごい成果を出したら自分で自分をほめるようにして、他人に「報告」という名の「自慢」をしないようにしましょう。
少なくとも相対的な比較を意識させるような報告(「俺のほうが上だ」とか「俺は優秀だ」みたいな報告)はしないようにしたほうがいいです。
どうしてもしたい場合や立場上せざるを得ない場合は、「これもみなさんのおかげです。ありがとうございます」のような感謝のメッセージを入れましょう。そうすると謙虚さが見えて相手は不快に感じにくくなります。
こちらも詳しくは「②診断士のメンタル」をご覧ください。
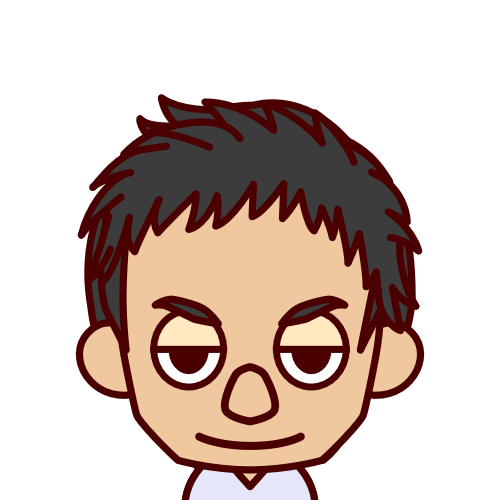
優劣のようなタテの思考よりも、仲間意識のようなヨコの思考のほうが大事やな

あと、ネタだとしても相手を挑発する言い方、相手の劣等感を刺激する言い方はNGです
ちなみに、他人から自慢された場合、こちらは不快になるのではなく、「この人は不安や心配事が溜まっていて承認欲求を満たしたいのだろう」と、背景の事情を考慮して労をねぎらいましょう。それが「②診断士のメンタル」を満たす診断士であり、魅力的な診断士です。
「暇人」と思われるとブランドに傷がつく
これは主に独立開業をしている方向けの内容となります。
独立開業をしている方は、時間が有り余っていることや、少しでも収入を得たいことから、来た案件はすべてすぐに受けてしまうこともあるのではないでしょうか?
これって一見すると良いように思えますが、実は危険です。
と言うのも、暇人と思われてしまうと警戒されるからです。
みなさんも、終始ガラガラのラーメン屋には行きたがらないですよね。ガラガラということは、味や店員の態度など何かしらの原因があって質が悪いと警戒して店には入らないですよね。
暇人は、平日の昼間を含めて時間を自在に使える、時間がたっぷりあるというメリットがあります。これは確かに差別化要素になります。そのため、「あの企画にも応募している、この案件にもこの人がいる」という状況になっていることもあります。
しかし、他人からすると「この人、普段何をしているの?」となります。独立していると知っていてもです。下手をすると「仕事ができないから仕事が来ず、結果的に暇人なのだろう」とか「性格面とかの問題があるのかも」と思われるリスクがあります。先ほどのガラガラのラーメン屋の例のように、何かしらの原因があって質が悪いと警戒されてしまいます。
暇人に対しては、フットワークの軽さや積極性、時間の融通性を買ってくれる人もいるでしょう。しかし、仕事の質や人間性の悪さがイメージ的に先行してしまう人もいます。私の知り合いではハッキリと「暇人と思えるような人には仕事は回さない」と宣言している方もいます。

「暇人」というマイナスのイメージがあると、いくら認知されていてもブランド知識はマイナスになり、悪い印象をもたれてしまうね
独立開業されている方も、おーちゃんのように忙しくされている方はたくさんいます。そういう方は仕事の選び方が上手いのです。つまり、関連多角化の範囲内なら仕事を受ける一方で、その範囲外のことは手をつけていないのです。だから「あの企画にも応募している、この案件にもこの人がいる」という状況にならず、他人に警戒されません。関連多角化の範囲内なら強みを活かせるので結果も伴います。
しかし、関連多角化の範囲外のことまであれもこれも受けていると、ご自身のキャリアの方向性の間違いやキャパオーバーになるだけでなく、「この人はいつ依頼をしてもすぐに受けるけど、暇人なのか?」など、他人から暇人と思われてしまいます。

仮に時間が余っている方でも、たまには依頼を断る、無視する勇気を持ちましょう!
あと、ネタ半分だろうが自己紹介や飲み会の際に「暇してるので」とか「仕事ください」と周囲に言うのもNGです。自分から「私は暇人です、仕事の質が悪いです」とアピールしているようなもので、相手から警戒されます。仕事がほしいなら、自分の強み・やりたいことなどをこまめに情報発信しましょう!

Facebookなどに忙しそうにしている旨の投稿をするのも有効ですよ。
私が毎日Facebookを投稿している理由もそれにつながっています
おわりに
いかがでしたでしょうか。今回は診断士に合格された直後の方が関心のある、診断士のキャリアやブランド戦略について説明してまいりました。
本当は一発合格道場で書いても良かったのですが、タキプロのほうから「サトシさんの1年間の軌跡を書いていただけますか?」との依頼を受けたので、2月28日のタキプロブログで私が1年目にしたことを公開いたします。よろしければそちらをご覧ください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。また、ここまで4回+1回の「サトシの書籍シリーズ」をご覧いただき、ありがとうございました。すべての読者の方々に感謝を申し上げます。また、このような大掛かりな執筆の機会をくださった道場15代目メンバー、先代のメンバーにも感謝を申し上げます。
以上、一発合格道場15代目「サトシ」でした。
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)


