【永久保存版】令和5年度事例Ⅲ 再現答案分析(得点:81/65/49) by たいしん

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
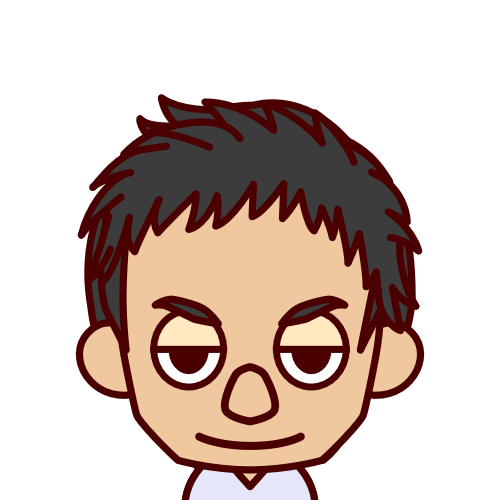
みなさん、まいど!
たいしんです。
まずはお知らせから!一発合格道場では、久方ぶりとなるリアルセミナーを開催します!
さて本編です。
いよいよこのシリーズもラストになります。引き続き令和5年度2次試験の15代目再現答案を分析して参ります!こちらは9代目だいまつさんの「超高得点シリーズ」の流れを汲んでおり、内容をブラッシュアップしつつ、脈々と受け継がれてきた記事になります。今回は令和5年度の事例Ⅲです!
毎度のことながら、超長文です。今回は過去最多15,000文字オーバーです。要注意です。PC閲覧推奨・ブックマークして復習のお供にお使い下さい!
再現答案分析の定義や目的(再掲)
- 完全ネタバレになります。令和5年度の事例を解いてからお読みください。
- 15代目メンバーから3名分(松・竹・梅)の再現答案を使います。
- 「出題の趣旨」と「ふぞろい17」を使って、加点・減点ポイントを分析していきます。
- 加点要素に下線、設問ごとに採点・評価を行います。
- 各設問の評価は、6割以上でA、5割~6割でB、4割~5割でC、4割未満をDとしています。
- 最後にふぞろい採点と実際の得点の乖離も確認します。
- 設問ごとに導き出される「攻略のポイント」を纏めてお伝えします。
令和5年度事例Ⅲの問題用紙・解答用紙、出題の趣旨は、下記からダウンロードできますので、ご活用ください。(*ダウンロード元はAASの過去問ダウンロードサイトになります。)
本日も宜しくお願いします!![]()
- 1. 解答者紹介
- 1.1. たいしん(令和5年度事例Ⅲ_81点)
- 1.2. かます(令和5年度事例Ⅲ_65点)
- 1.3. サトシ(令和5年度事例Ⅲ_49点)
- 2. 第1問
- 2.1. たいしん
- 2.2. かます
- 2.3. サトシ
- 3. 第2問
- 3.1. たいしん
- 3.2. かます
- 3.3. サトシ
- 4. 第3問
- 4.1. たいしん
- 4.2. かます
- 4.3. サトシ
- 5. ちょっと休憩して厨房でもみましょう
- 6. 気を取り直して、ホテルのビュッフェでリラックス!
- 7. 第4問
- 7.1. たいしん
- 7.2. かます
- 7.3. サトシ
- 8. 第5問
- 8.1. たいしん
- 8.2. かます
- 8.3. サトシ
- 9. 実際の点数との比較
- 10. おまけ①
- 11. おまけ②
- 12. 本日の攻略ポイント纏め
解答者紹介
まずは今回の再現答案分析に協力いただいた15代目メンバーを紹介します!今回の切られ役は、サトシです。落ち込まない程度に切っちゃいます(事前に了承はもらってます💦)。
たいしん(令和5年度事例Ⅲ_81点)
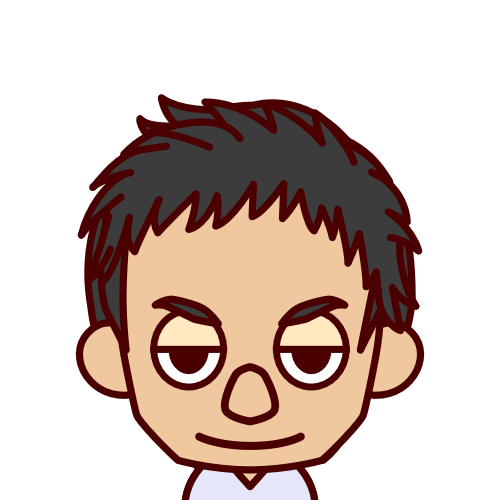
ナリタタイシンの一瞬の切れ味に感動。当時はビワハヤヒデ・ウイニングチケットと3強を形成して・・・
かます(令和5年度事例Ⅲ_65点)
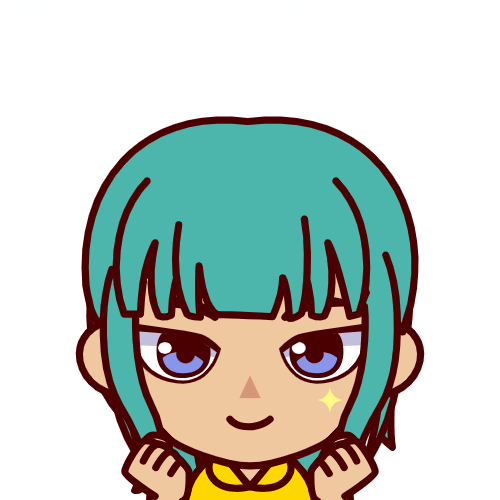
15代目No.1のストイックガール!
かわいい見た目とは裏腹に、初学でオールAを叩き出すグリーンモンスター
サトシ(令和5年度事例Ⅲ_49点)
.jpg)
あなたは一体どこに住んでるの?
未だに双子説が飛び交う、機動力No.1の電車男サトシ!
第1問
(配点10点)
C社の生産面の強みを2つ40字以内で述べよ。
出題の趣旨
C社の生産面の強みについて、分析する能力を問う問題である。
問題文みじかっ!字数すくなっ!配点10点!?
・・こういう時はオートマチックに、最後に解くのをお勧めします。だってあれこれ悩んで選べないですもん、むしろ悩めるかって話で。私は他の事例でも第1問を最後に解くことの方が多かったです(以前の事例Ⅰ分析に詳細記載しております)。かますもその一派なようで、↓こちらの記事を参照して頂ければと思います。
アタリ![]() を付けて読みながら、解きながら、最後にダダっと強みを書いてしまう感じですね。ただ配点が10点といえど、侮るなかれ。
を付けて読みながら、解きながら、最後にダダっと強みを書いてしまう感じですね。ただ配点が10点といえど、侮るなかれ。
間違った強みを書いてしまうと痛い目にあいます。
あと制約条件に「生産面で」とあります。「生産面で」と言われたら「4M」なのでしょうが、4Mを思い浮かべるだけではドンピシャな解答は書けないと思っています。もっと簡単に考えれば、営業面・組織面・収益面、以外のこと、ぐらいでもいいかと思います。
たいしん
たいしん
①料理人の経験者が多くニーズに対応できる。②多品種少量の生産体制を構築できている。
採点:10/10、評価:A
うん、危なげないですね。これも最後に書きました。後述しますが、第4問で使えたので、最終的に第1問の解答として抜擢しました。40字って少ないなって思いましたが、1要素につき20字だと考えるとちょっと長い。端的に強みを挙げてしまうと文字数が足りない。そこでどうするか、どういうことが求められているか。
これは「何故それが強みになるんだ?」ということもわかるように記載しなければならない、と解釈しました。とすると、1つの要素を因果で纏めると綺麗な解答になる気がします。
また制約条件に「2つ」とあるので、解答は①②を使っています。設問要求に確り応えていますよー!というアピールです。わかりやすいですね。この①②の使い方は、「並列で述べる時」など、マイルールを決めておくとよいかと思います😊
かます
かます
生産面は①料理経験のある工場管理者やベテランパートリーダー②顧客からの要望対応力
採点:5/10、評価:B
まず「生産面は」の記載が余計でしたね。ここを削れば②を膨らませることが出来たかもしれません。
そしてかますの解答、私とまぁ似たようなものです。かますもここで挙げた強みを第4問につなげています。というか第1問を最後に解く一派としては、これぐらいの一貫性は朝飯前のもんです。
ですが、とても重要なことが隠されています。よくいう「多面的に書くこと」です。あれあれ?2つ書いてるやん、となりそうですが。。かますの解答をよ~く見て下さい。①と②が実は因果関係になっているんです。「料理経験のある方がいるので、顧客からの要望対応力がある」と読むと、1つの強みしか挙げれていません。(「顧客からの要望対応力」が多品種少量の受託製造体制から導いているものかもしれませんが、それでしたら「因」の方、ここで言う多品種少量の受託製造体制を書くべきかな)
並列で書く時は、それが本当に多面的な解答になっているかどうか、改めて見直してみると良いですね。
サトシ
サトシ
工場管理者のホテルや旅館での料理人の経験、ホテルや旅館と同じ設備機器のレイアウト。
採点:6/10、評価:A
サトシのポイントとなるところです。ふぞろいではレイアウトも加点要素に入っています。そしてサトシは、ここで挙げた強みを第4問と第5問で言及しているんです。
・・何の問題もないんじゃないかと思いますよね。なのですが、第5問でやってしまってるので、結果的には「レイアウト」を強みとして入れるべきではなかったのかなと思います。これは後ほど第5問で分析します。
ここで、この「レイアウト」について考察です。以前の分析記事でも「わざわざ入れている表現は大ヒント」的なことを述べました。その思いは変わりません。今回の事例Ⅲでも、第6段落に、わざわざ「各加工室の設備機器のレイアウトはホテルや旅館の厨房と同様のつくりとなっている。」と記載があります。
ただ私はこれを「弱み(というより改善すべきところ)」と捉えました。何故ならば、受注量が増えてきているからです。ホテルと同じレイアウトで、受注増に対応できますか?って話です。この第6段落でレイアウトについて言及した後に「わざわざ」フローダイアグラムの図を挿入しているのもいやらしいですね。フローダイアグラムは「ものの流れ」です。
第2問にも繋がるところなんですが、生産性をあげるには、そりゃ流れに沿ったレイアウトの方がいいでしょう。工場っぽくね。ホテルや旅館は「厨房」のイメージ。なので今後のことを考えると、現レイアウトは「改善すべきところ」にカテゴライズされると思います。
但し、というか実は、このレイアウトは「両利きの経営」をテーマとするなら、強みとして考えておいても良いキーワードだと感じます。このへんは最後のおまけの部分で述べたいと思います。
一見飛びつきたくなるようなキーワードでも、のちの設問間の繋がりによっては逆の意味にもなる。ここは覚えておきましょう。
攻略のポイント
- 「生産面で」と問われれば、営業面・組織面・収益面、以外のこと、ぐらいでもOK
- SWOTなどで1要素につき20文字であれば、要素内で因果関係を明記する
- 設問要求にわかりやすく応えるために、記号を使うルールを決めておく
- 並列記載は、多面的な内容になっているかどうかチェック
- 一見飛びつきたくなるようなキーワードでも、のちの設問間の繋がりによっては逆の意味にもなる
第2問
(配点20点)
C社の製造部では、コロナ禍で受注量が減少した2020年以降の工場稼働の低下による出勤日数調整の影響で、高齢のパート従業員も退職し、最近の増加する受注量の対応に苦慮している。生産面でどのような対応策が必要なのか、100字以内で述べよ。
出題の趣旨
コロナ禍後の増加する受注量に対応するための C 社生産面の課題を整理し、その対応策について、助言する能力を問う問題である。
まず制約条件をみてみましょう。「生産面」での「対応策」ですね。課題を整理しなきゃ対応策を示せないのは、出題の趣旨に書いてある通り。このように事例Ⅲで対応策なんかが問われる時に、非常に役に立つフレームワークがあります。言わずと知れた「ゲ・モ・タ・コ」です。
ゲ:原因、モ:問題、タ:対応策、コ:効果
これだけだとなんだかわかったようでわからないので、具体例と共にTipsにしてみました。結構使えるので、懐に忍ばせておいて下さい♪具体例は、とある物流企業の想定です。
ここでのポイントは、対応策が原因と対比していることです。こうすることでロジカルに記述することが出来ますね。
たいしん
たいしん
対応策は①SLPを用いて適切なレイアウト構築②汎用調理器に設備を導入し自働化③各課の作業をマニュアル化しOJTによる教育で多能工化④顧客やり取りはデータで行い変更時間の短縮。以上で生産性を向上させる。
採点:16/20、評価:A
「対応策は」から始まり、受注量の対応に苦慮する原因に対比した対応策を①②③④と並列で記載し、最後は効果で締める。まぁ良い型なんじゃないかと思います。それぞれの対応策について、想起した原因は以下の通り。
①レイアウトが悪い(ゾーニングしているので、そもそもレイアウト変更はあり得ない、との声は百も承知です)
②前工程が手作業で進められている(専用設備導入は、中小企業には敷居が高いとの論点もありますが、そこまでの費用感ではないと判断しました)
③レシピや作業手順などが整理されていない(「作業の標準化→マニュアルを作成→OJT→教育→多能工化」この流れはどこかで必ず使うぐらいのイメージでいいと思います)
④販売先料理長が登場しすぎ!(第9段落から第11段落にかけて5回も!登場しており、しかもわざわざ来社している様子も2回ほど表現されています)
これらに対する対応策を記述した感じですね。
かます
かます
対応策は①班毎の人員を流動性をつけ多能工化②機械化できるところは機械化③作業標準化しOJT等の教育④生産の全社的計画と週次化⑤若手の次期パートリーダー育成により生産性向上させる。
採点:12/20、評価:A
かますも型はいいですね。最後も効果で締めれています。かますの解答では3つポイントがあるかと思います。
まず1つ目ですが、②の機械化というところです。加点にはなりましたが、正確に記載するなら「機械化」ではなく専用設備導入による「自動化」でしょう。そして折角フローダイアグラムの図があるんですから、どの工程に導入するかも入れ込んで欲しいところ。文字数にも余裕がありましたしね。とにかく図が出てきたらチャンスです。使って下さいという合図です。
次に2つ目ですが、④の全社的計画と週次化のところです。私は第3問でこの論点を述べましたが、かますの解答を見てなるほどなと。第2問で挙げても違和感ないなと感じました。生産計画の精緻化は、人員のアジャスト(=生産性向上)にも寄与するし、資材の無駄を省くことにも寄与しますよね。
そして3つ目ですが、⑤の若手の時期パートリーダーの育成ってところです。たぶん設問文の設定(高齢のパート従業員の退職)や、第5段落にある「ベテランのパートリーダー」から想起したものだと思われます。言いたいことはわかりますが、これで生産性が向上しますか?これは生産面での対応策ですか?ってところです。どれも将来的には繋がるかもしれませんが、やはり制約条件からは外れていると判断されると思います。
サトシ
サトシ
対応策は製品仕様のレシピの整理と標準化を行い販売先料理長と工場管理者で共有しパート従業員への OJT での育成を図ることで販売先料理長の来社や指示を待たずに試作や生産・加工を行い生産リードタイム短縮を図る。
採点:8/20、評価:C
まず読みにくいです。その原因は、息継ぎがないこと。なので、主語である「対応策は」に対する述語が迷子になってしまっています。この文章を極端に要約すると「対応策は生産リードタイム短縮を図る」になってしまいますね。キーワードを入れ込みたい気持ちはわかりますが、採点する方が疲れないように、句読点や記号を活用して息継ぎしましょう。
そして後半部分が一切加点となっていないのは、因果関係がわかりにくいからです。生産リードタイムの短縮と生産性向上は微妙にニュアンスが違う気もします。
また、私やかますには入っていた論点である「専用設備の導入」に触れられていないのも失点ポイントです。
サトシの解答、少し言い換えて整えてみます。
⇒対応策は①製品仕様のレシピの整理②作業工程の標準化③それらをデータベース化し販売先料理長と工場管理者で共有④標準化されたマニュアルを用いたOJTによる育成。以上で生産性の向上を図る。
あと今回の設問でお伝えしたいことがもう少し。
こちらは第2問を先ほどの「ゲモタコ」で解析した図です。

そして実際に試験本番で記載した私のメモがこちら。

解答の型と効果を書いただけ。これだけなんですが、設問解釈の時点で、ほぼ解答のイメージが出来ている状態です。あとは与件文を読みながら、先のイメージを描き、型にはめれば完了です。右の方に書いてあるのは、事例Ⅲの施策問題で有効な「ヒキタホウダレ」です。これも覚えておいて損はないです😊

攻略のポイント
- 事例Ⅲ重要フレーム「ゲ・モ・タ・コ」を活用すべし
- 対応策は原因と対比すると書きやすい
- 使える解答の型:対応策は、① ② ③ 、効果
- 「作業の標準化→マニュアルを作成→OJT→教育→多能工化」この流れはどこかで必ず使うぐらいのイメージ
- 図が出てきたらチャンス、使って下さいという合図、特に事例Ⅲ
- 冗長的な文章は読みにくい(採点難度が上がる)、記号や句読点を活用すべし
- 事例Ⅲの施策問題では「ヒキタホウダレ」も使える
第3問
(配点20点)
C社では、最近の材料価格高騰の影響が大きく、付加価値が高い製品を販売しているものの、収益性の低下が生じている。どのような対応策が必要なのか、120字以内で述べよ。
出題の趣旨
最近の材料価格高騰に対応するため、C 社の資材調達管理、在庫管理、製造工程管理の課題を整理し、その対応策について、助言する能力を問う問題である。
収益性の低下に対する対応策ですが、出題の趣旨にあるような観点からのコスト低減策が思い浮かびます。そして「収益性」を上げるには、コスト低減も然ることながら売上の拡大にも着目したいところですね(本問はあまり関係ないかもしれませんが)。
イシューツリーで分解すると、↓こうなります。しん![]() からお借りしました!
からお借りしました!

この図が入っているしんのブログは必見です。是非ご一読を!
たいしん
たいしん
対応策は、月次計画から週次へ精緻化し、レシピを整理してDB化することで見積精度を向上させ、資材発注を定量発注方式に変更し、入出庫記録もつけ現品管理を強化し、在庫維持費用と廃棄ロスを削減。納期遅れによる機会損失も防止し売上も向上させる。
採点:17/20、評価:A
まず読みにくいです。さっきサトシの解答でつっこんだとこですが、文中で区切りがないので何を言いたいのかわかりにくいですね。息継ぎ、大事!

冗長的になる状態の時って、わかるんです。サトシの気持ちも。自信がない時にこうなるんです。普段の会話でもそう。聞かれたことだけに答えればいい場面で、自信がない時や不安な時って、聞かれたこと以外も話したりしてません?あれと同じようなものです。
時間もない中、設問文に傾聴も出来ず、焦ってキーワードだけでも詰め込みたくなる、そんな状態。こういう時は、この言葉を思い出して下さい。「忙しい、時ほど整理、整頓を!(5・7・5)」
さて分析ですが、出題の趣旨に沿って、資材調達管理・在庫管理・製造工程管理、それぞれについての対応策、最後に効果もみていきます。
資材調達管理:発注方式を変更しないと!との意欲は感じられますが、果たして定量発注方式が合ってるの?ですね。たぶん加点されていません。週次に計画を変更するのであれば「資材発注もそれに合わせる!」ぐらいシンプルでよかったかも。
在庫管理:ここは順当に言及できています。
製造工程管理:ここもいいですね。問題ないです。DB化の後に「共有」まであれば、なお良しでしょう。DRINKってやつです。
効果:廃棄ロス・保管コストへの言及+機会損失防止(売上面)を入れ込めたのは、我ながらファインプレーです。
キーワード的には17/20なのですが、冗長的な文章のせいで、それほど伸びていないかもしれません。。
ここで少しDRINKの紹介をしておきます。
D:データベース
R:リアルタイム
I:一元管理
N:ネットワーク
K:共有化
だいたい事例Ⅲのオペレーション部分でダメなとこが出てきたら、このフレームで考えればなんとなくの解答ができる、っていう優れものです。事例Ⅲでは超重要フレームワークです。
ただこのDRINK、この順番って何か使いにくいんですよね。これだけ覚えていても、前後装飾したり与件に忠実じゃないと使えないし。Maki![]() もわちゃわちゃと同じように考えていたみたいで。
もわちゃわちゃと同じように考えていたみたいで。
Makiは「D⇒N⇒I⇒R⇒K」の順番で活用していたみたいです!個別で覚えるのではなく、文章化した流れを習得していた様子。さすがです。実は私も同じようにDRINKを変形させていました。私バージョンのDRINKについては↓でTipsにしてみましたのでご参考までに。
Makiにせよ、私にせよ、DRINKを「自分が使える形にした」ところがポイントかと思います。
かます
かます
対応策は①全社的な生産計画で週次化し、調達や在庫管理を見直し歩留まり向上と廃棄を見直す。②資材調達を形式知化し入出庫記録をつけ在庫管理コスト低減。③生産統制に結びつけることで、コスト削減し収益性を向上させる。
採点:20/20、評価:A
かます!120字に対して104字は少ない!でも65点取れてる!なんか詰め込んでたらもっと取れてたかも!
・・でもやはり要求文字数の95%ぐらいは書ききるクセをつけておいた方が良いかと思います(本問なら、120×95%で114字ぐらい)。
そして分析ですが、キーワード的には満点です!満点なのですが、少し具体性に欠ける感じなので、実は点数が意外と伸びていないかもしれません。
資材調達管理:いいですよね。クセつよパートリーダーの属人的な部分を解消する対応策が書けています。おいおい勘で仕事すんなよ!って感じですよね。
在庫管理:OKですね。問題ないかと思います。
製造工程管理:全社的な生産計画作成⇒週次化⇒(少し空きますが)生産統制強化、この流れは非常に重要です。事例Ⅲでは、どこかで使うイメージをもっておいた方がいいでしょう。ただ生産統制の部分をもう少し具体的に書ければ良かったのではないかと思います。現品管理・余力管理・進捗管理ですね。本問だと、現品管理の部分です。
あとかますは、第2問と第3問の解答で、どちらにも「全社的生産計画」「週次化」を入れています。よく事例Ⅲは問題に対しての切り分けが難しいと言われています。通常はMECE(漏れなくダブりなく)で考えるところ、事例Ⅲに対する時だけは「漏れなくダブりあり」でも最悪OKです。たぶんかますは意図的に両方の解答に入れています。高度なリスクヘッジですね。素晴らしい👏
効果:売上部分には言及していませんが、それでもポイント抑えています。
サトシ
サトシ
対応策は食材や調味料の必要量見積りの標準化や生産計画・発注の小ロット・短サイクル化を図り、資材管理課での入出庫記録作成と現品管理・納品管理を行うことで製造日に必要な食材や調味料を早くから準備でき納品遅れ防止や在庫の量・コスト、廃棄減少を図る。
採点:15/20、評価:A
資材調達管理:いいですよね。生産計画と共に発注も小ロットにするという。具体性満点です。
在庫管理:ここもOKです。生産統制の具体性もありますね。OKなんですが解答内赤字の部分、これ不要かと思います。「強化」という言葉に置き換えれば、文章として、解答として成立します。(・・・現品管理を強化し納品遅れ・・・)
詳しく伝えたい気持ちが溢れていますが、ここは文章を簡潔にし、多面的にもう一要素入れたかったところです。
製造工程管理や効果の部分もポイント抑えていますが、収益性の改善は最後に入れたいですね。ここは設問文のオウム返しの方が締まるでしょう。
この第3問は、第11段落に解答要素がこれでもかっていうぐらい詰まってます。こういう時は得点のチャンスですね。ダメなところを抜き出して良い風にしてあげる。「事例Ⅲは「できていないこと、やらなきゃいけないことを、ただやってください」と書くだけ」by 9代目だいまつ兄さん。それだけでいくつか稼げます。ここで着実に取れているかが、攻略のポイント(足切り回避のポイント)でもあったかと思います。
攻略のポイント
- 「忙しい、時ほど整理、整頓を!(5・7・5)」
- 超重要フレーム「DRINK」を使える形で習得せよ
- 要求文字数の95%ぐらいは埋めるクセをつけよう
- 全社的な生産計画作成⇒週次化⇒生産統制強化の流れは、どこかで使うイメージ
- 生産統制(現品管理・余力管理・進捗管理)は具体例を示せば解像度が上がる
- 切り分けに迷ったら「漏れなくダブりあり」でリスクヘッジ
- 効果に迷ったら、設問文のオウム返しで意外といける
- 「できていないこと、やらなきゃいけないことを、ただやってください」と書くだけ
ちょっと休憩して厨房でもみましょう


って、誰が厨房見てリラックスすんねん!
ひぐま出せ!ひぐま!
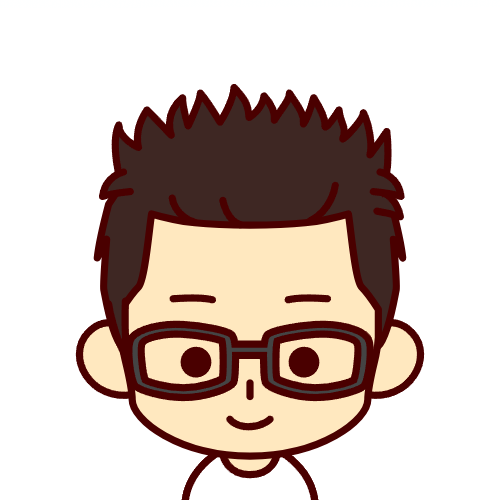
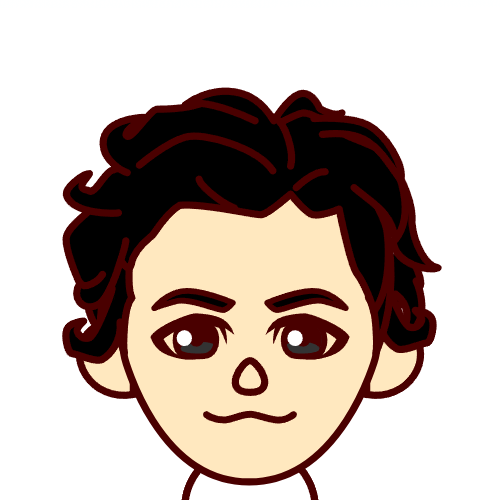
お茶だしとけ!お茶!
めちゃくちゃに切りやがって!
電車の絵だせー!チクショー!


代打は川藤やろー!川藤!
・・・一部を除いて、突っ込みの激しい関西勢からダメ出しをくらいましたので、画像変更します。。納品先のホテルのビュッフェとかがいいですかね。
気を取り直して、ホテルのビュッフェでリラックス!

第4問
(配点20点)
C社社長は受注量が低迷した数年前から、既存の販売先との関係を一層密接にするとともに、他のホテルや旅館への販路拡大を図るため、自社企画製品の製造販売を実現したいと思っていた。また、食品スーパーX社との新規事業でも総菜の商品企画が必要となっている。創業から受託品の製造に特化してきたC社は、どのように製品の企画開発を進めるべきなのか、120字以内で述べよ。
出題の趣旨
自社企画製品の販売を実現するために、創業から受託品の製造に特化してきた C 社の製品企画開発の課題を整理し、そのために必要となる社内対応策について、助言する能力を問う問題である。
設問文、長いですね。こういう時は確りと制約条件を抜き取りましょう!ここでポイントは4つあると考えます。まず1つ目は社長の思いに寄り添うこと。「既存販売先と関係性を密接にしつつ商品を開発し販売したい」という思いですね。2つ目に新規事業でも商品企画が必要であるという外部環境。3つ目に受託製造に特化してきたが故の弱み(社長の思いを妨げる課題)があるということ。そして4つ目に、問われ方が「どのように」という点。「どのように」なので、流れに沿って説明すると良いかと。
ここまで解釈すると、解答の方向性は、「順を追って、社長の思いを妨げる現体制の課題を克服する対応策を示す」でいいかと思います。
たいしん
たいしん
まず営業部から配送業務を切り離し営業に特化させ、次に顧客ニーズを収集し商品開発に生かす。強みである多品種少量生産体制や、採用した外部人材を生かして、季節感があり高級感がある総菜を季節ごとに開発し差別化を図る。採用人材から課員への教育も行う。
採点:13/20、評価:A
いきなり第1段落に「配送業務を兼務する営業部」とあります。こりゃ専任させな!とすぐにピンときてください。営業部の多忙さは事例Ⅲあるあるです。兼務してたら専任させてあげましょう!
流れはいいですね。営業強化→ニーズ収集→商品開発。装飾足りないだけで概ねOKでしょう。ただ社長の思いに寄り添うなら、ニーズの収集先を入れるべきでした。設問解釈、大事!
それから第1問で挙げた多品種少量生産体制も使えています。というよりこの後で第1問は書いてます。ですが、もう1つの強み「料理人の経験」を捻り出せていません。実は3人ともです。なんとな~く、開発部分で活用できそうでしたが、ダイレクトに表現することが出来ませんでした。多分言わずもがなと思ったんでしょうね。3人とも。
私の解答でいえば、「課員への教育」を抜いて、開発の下りに適用すれば良かったです。
かます
かます
①製品開発担当者を営業同行させ顧客から直接ニーズ収集し商品開発し②過去のレシピをDB化し相互に検討③開発部門に人を配置しOJTなどで開発ノウハウを教育し強化④自社ブランド提案。以上より販売先との関係性を強化し販路拡大を図る。
採点:10/20、評価:B
かますも流れに沿って解答出来ていますね。営業強化(もしかしたらこの部分は具体性が足りないかもしれません)→ニーズ収集→商品開発を当たり前のように書けています。ただかますの解答で惜しいと思うのが、第1問で挙げた強みをわかりやすく活かせていないところです。おそらく「要望対応力」をこの問題へ活かした(活かしたかった)と思うのですが、第1問で述べた通り、料理人の経験があってこその要望対応力だと思うので、こう変形させると良かったのかもしれません。
顧客から直接ニーズを収集し商品開発し⇒顧客から直接ニーズを収集し料理人の経験を活かした商品開発を行い
それから開発部門の強化は一切加点要素に入っていません。「製品の企画開発の進め方」というお題なので、根底となる部分は問われていないという理屈でしょうか。ただ私も同じような要素を入れていましたので、ここは検討の余地ありというところだと思います。
サトシ
サトシ
製品開発部に採用された外部人材の中堅食品製造業での製品開発の実務や管理の経験を活かし、製品の企画開発力の育成を行い、販売先からニーズを把握し季節感や高級感のある和食や洋食の総菜、地元食材を使った特色あるメニュー等を開発して差別化を図る。
採点:9/20、評価:C
キーワードは漏れなく入っていますが、点数が伸びていません。その理由は「外部人材の経験」を第1問で強みとして挙げていないからです。一貫性、大事!
それから「受託品の製造に特化してきた」故のC社の課題(=営業力)を解決できていません。設問解釈、大事!
ただ「季節感」を入れ込めているのは素晴らしいところです!何故かというと、このワードが与件文中に繰り返し(といっても2度ほどですが)出現しているからです。繰り返し出てくる言葉は、ピックアップしたいですね。
攻略のポイント
- 営業部の多忙さは事例Ⅲあるある→専任化の方向性
- 繰り返し出てくる言葉は、どこかでピックアップしよう
第5問
(配点30点)
食品スーパーX社と共同で行っている総菜製品の新規事業について、C社社長は現在の生産能力では対応が難しいと考えており、工場敷地内に工場を増築し、専用生産設備を導入し、新規採用者を中心とした生産体制の構築を目指そうとしている。このC社社長の構想について、その妥当性とその理由、またその際の留意点をどのように助言するか、140字以内で述べよ。
出題の趣旨
工場増築などの設備投資によって生産体制を構築し、新規事業の生産に対応しようとするC社社長の構想の妥当性とその理由、またその際の留意点について、助言する能力を問う問題である。
出ましたね。留意点。私は事例Ⅰの分析記事で、留意とは「ある物事を心にとどめておくこと」「解決策やその後の効果までは期待されていない」と述べています。その設問には、文脈から「気をつけなはれや!」程度でOKでした。
ただ今回の「留意点」に関しては、やや施策っぽいことまで求められているような気がします。ん~ガチっと定義しようとすると難しいですね。
「具体的なこと・行動を実行する前に気を付けておくべきこと」という留意点。例えば「もし新人比率が高くなったら、教育関連とか整備しとかなあかんかな」みたいな。
「実際に何かする時に発生するであろう問題に対処する」という留意点。例えば「新人比率が高くなりそうだから、ベテランAさんからのOJTによる教育をせなあかんな」
前者は「気を付ける程度」、後者は「施策っぽい感じ」かな。後者の方がより具体的になるので施策っぽくなる。
すいません、うまく表現できません。。まぁ文脈から素直に感じ取れることが1番です。同じような言葉を書いても、上記の通り留意点とも施策とも取れますしね。
少し話が逸れましたが、設問解釈します。意外とわかりやすいです。
①まず妥当かどうか(社長の思いも汲み取りましょう!)
②その理由(工場増設は?専用設備導入は?新規採用者中心は?)
③その際の留意点(工場増設したらどうなる?専用設備導入したらどうなる?新規採用者中心にしたらどうなる?)
④「助言せよ」なので、とりあえず効果は書いておく
たいしん
たいしん
妥当性はある。理由は専用設備なので新規採用者でも生産性を上げることが出来るから。留意点は①適切なレイアウトの構築②作業の標準化と新規採用者への教育③納品の頻度が増える為、配送の効率化を検討する。以上で高付加価値化と他社との差別化を図り、売上拡大と収益性の改善を図る。
採点:25/30、評価:A
妥当性の判断。その理由。留意点。効果。判を押したように書けています。まず妥当性の部分ですが、設問文で既に「留意点」を問われているので、「妥当性はある」一択だと感じました。そりゃ投資案件ですから、環境考えると安易に手を出せないのもわかります。ただ第15段落に「この新規事業に積極的に取り組む方針」と書いてあるので、そこは意を汲んで、社長の背中を押してあげましょう!
次に理由の部分が少し薄いですね。結局「なんでこんなことすんの?」って、売上拡大したり、両利き経営でリスク分散させたりしたい訳ですよ。そこに言及しても良かった。第14段落にも「10数店舗まで徐々に拡大したい考え」と書いてあります。社長の思い、本当に大事!
留意点も万遍なく書けています。個人的には③の「配送の効率化」はめっちゃポイントやと思ったんですがね。配送に関する記述である第12段落と第14段落を何とか使いたかった。。でもふぞろいでは加点になっていませんでした。
効果は書かなくても良かった問題だったかもしれませんが、最後に羅列しちゃってます。私は「迷ったら効果を書く派」でしたが、どうやら「字数が足りなくて困ったら効果を多発する病」にもなっていたみたいです。最後の方だけとってつけたようになっていますよね。こういうのはやっちゃダメですよ。効果羅列、ダメ!絶対!
かます
かます
工場を増築し、設備導入、新規採用者を中心とした生産体制は妥当である。理由は需要増に現在の生産力では対応出来ないため。留意点は①現工場でベテラン従業員からノウハウの教育研修を行い、②作業の標準化を行っておくことで、新規事業に対応し売上拡大を図る。
採点:23/30、評価:A
だからかます、122文字は少ないって!!でも65点取れてるねんなぁ~。
理由のところは私と同じく社長の思いを反映させればよかったですね。留意点ももっと書ききれば良かったんでしょうが、重要なキーワードが全て入っているので、程よく加点されています。
サトシ
サトシ
妥当である。理由は各加工室の設備機器のレイアウトを活かし、専用生産設備の導入なら操作方法の育成不要で規模の経済によるコスト減少や専門性向上が図れるから。留意点はホテルや旅館での料理人経験のある工場管理者が新規採用者の OJT での育成を行うことで生産能力を上げX社の店舗拡大に対応する。
採点:13/30、評価:C
さて大トリのサトシです。
キーワード採点では一応13点分入っていましたが、もしかするとほとんど点数が入っていないかもしれません。
サトシはすごく丁寧に、そしてかなり訓練された意識をもって、第1問で挙げた強みをこの第5問で使っています。このプロセスをオートマチックに吐き出せる状態であったと思います。私もサトシも多年度です。こういう訓練を嫌というほどしてきたので、肌でわかります。
ではなぜ「ほとんど点数が入っていないかも」と推測したのか?その理由を説明します。
各加工室の設備機器のレイアウトは、ホテルや旅館の厨房と同様の作りです。そしてそれは多品種少量生産向けのレイアウトとなっています。そのレイアウト(多品種少量)を活かして専用生産設備導入(多量)というところが矛盾しているんです。そもそも専用生産設備を導入するのは、工場敷地内に増築する新工場内ですので、現在のレイアウトは関係ありません。確りと設問を読み込めば、この矛盾を回避できたかもしれませんね。
第1問、10点の問題。侮るなかれと申し上げました。ストライクゾーンが狭い分、間違ったポイントに手を出すと大事故を起こすということです。このような配点の時には、後の問題と辻褄が合っているのか確りと見直しましょう。
攻略のポイント
- 社長の思い、本当に大事
- 効果羅列、ダメ!絶対!
- 配点が少ない問題は、後の設問で大事故を起こす危険性をはらむ、要注意!
実際の点数との比較
ここで、今回の採点と実際の点数を比較してみます。

私はドンピシャ、かますは甘め、サトシはちょい甘め。
かますはやはり第3問と第4問のところでしょうか。具体性の部分で減点が入っているかな。サトシは全体的な文章構成のクセでしょうかね。主述関係の破綻が減点対象となっているかもしれません。
おまけ①
事例Ⅲは一連の流れをイメージして解く。他の事例よりも型が作りやすく、設問の流れもほぼ変わらないので、私はとっつきやすかったです。そのイメージが下記の通りです。
第1問
SWOTで強みを抽出、問われてなくても弱みも抑えておく
道中
とにかくダメなところ良い風にする
生産計画→生産統制、標準化→マニュアル化→OJTで教育、DRINK
最終問題
戦略は①強みを活かし②機会を捉え③弱みを克服し④高付加価値化・差別化で、経営課題を克服する
スイマセン💦これだけです。設問文の左の方に矢印使って書いておいて、頭の片隅に置きながら問題演習を繰り返し、定着させました。
おまけ②
第1問で少し触れている「両利きの経営」についてです。どっちかっていうと事例Ⅰよりなんですが、トレンドなので押さえておきましょう。両利きの経営とは「主力事業の絶え間ない改善(知の深化)」と「新規事業に向けた実験と行動(知の探索)」を両立させることの重要性を唱える経営論のことです。成功を収めた大企業が新興企業に敗れ低迷する「イノベーションのジレンマ」の処方箋として、近年注目を集めている理論になります。
今回の事例Ⅲでいうと、ゾーニングされたレイアウトを強みとした既存顧客との関係性強化が知の深化、食品スーパーX社と共同で行っている総菜製品の新規事業が知の探索、となります。(そう考えると既存のレイアウトも弱みではないかもしれません・・)
とにかくこの「深化」と「探索」は覚えていた方がいいです。きっと困った時の何かのヒントになります。
両利きの経営については、14代目のさたっち兄さん![]() が超優良記事をあげてくれています。こちも是非参考に!
が超優良記事をあげてくれています。こちも是非参考に!
本日の攻略ポイント纏め
最後に本日出てきた攻略のポイントを纏めておきます。
令和5年度の再現答案分析もこれにて完了です。皆さまのお共にと、出来るだけ具体的に攻略できるポイントを抽出して参りました!是非今回の事例Ⅲに加えて、事例Ⅰ・Ⅱも合わせてご活用して頂ければ幸いに御座います。
余談ですが、この分析手法を受験生時代にやっておけばよかったなと思います。人に伝えるために文章を起こすことは、本当に勉強になりました。余裕のある方は是非♪
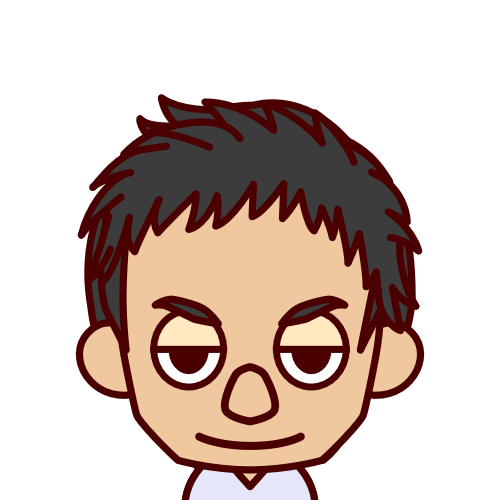
明日はせーでんきです!
朝ドラ「らんまん」のモデルにもなった、
牧野富太郎博士の話らしいっす。
世の中に〝雑草〟という草はない。
どんな草にだって、ちゃんと名前がついている。
フフッ

☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)








-300x169.jpg)

事例Ⅰ~Ⅲとボリューム満点の内容、ありがとうございました。
毎年、道場で取り上げてもらえるため、過去問実施時には大変参考にさせて頂いています。
本当はⅠ・Ⅱでもコメントしたかったのですが、あまり時間に余裕がなく、できていませんでした…。
ちなみに、気のせいかもしれませんが、今回の事例Ⅲが一番力が入っているように感じました(笑)
留意点…私はずっと悩んでいます。
「課題」のように書けばいいのか、「施策」のように書けばいいのか、「効果」まで書いてしまった方が良いのか…などなど。
でも、たいしんさんのおっしゃる通り、「文脈から素直に感じ取れることが1番」がしっくりくるような気がしました。
若干曖昧さが残りますが、最も適切と思える解答を書けるように頑張りたいと思います。
じょにーさん
日々の勉強お疲れ様です!
いつも一発合格道場の記事を参考にして頂き、有難うございます。
コメント頂くことは大変うれしいのですが、皆さまの負担になっては本末転倒ですので、余裕のある時や気晴らしなんかでご利用下さい^^
(じょにーさんの仰るように、事例Ⅲは少し力が入って長くなっていたかもしれません・・)
留意点。悩みますよね。この曖昧さをどこまで許容できるかも二次試験攻略のポイントかもしれませんね。
本番まであと少しとなってきましたが、引き続き頑張って参りましょう!
たいしんさん
シリーズ連載超お疲れ様でした。
大変勉強になりました。
事例3も強みを活かすことは重要そうですね。
本試験時、私は強みが読み取れず、ゾーニングによる安全意識と書きましたが、以降の設問で全くふれなかったので、全体の整合性がとれずでした。一応、ふぞろいでは得点になっていますが。
最終問題は投資費用あるのか等、悩みましたが、二次試験では社長の積極的にやりたいという想いに最大限に応えてあげるのが鉄板ですね。
シリーズ通して、ポイント纏めで、自身の課題に繋がる点はファイルペーパーに追記させて頂きました。
次のブログも楽しみにしております。
(次回からはナリタタイシンの切れ味についての考察が始まる?)
tomiさん
日々の勉強お疲れ様です!いつもコメント下さり、ありがとうございます。
また労いのお言葉も頂き、お心遣い痛み入ります。
強みを活かすことや社長の思いに応えることは、本当に鉄板ですよね。正解がわからない2次試験ですが、そこだけは間違いないと思います。
またポイントの纏め資料をご自身の課題と向き合わせて活用されているご様子、1歩1歩合格へ近づいている感じを受け取りました^^
引き続き頑張って参りましょう~!
そして仰るように、次回からはナリタタイシンの全レースを詳細に分析し、あの脚の再現性について深く掘り下げて・・・