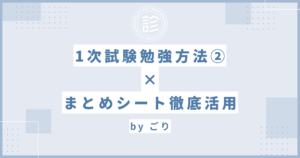2次ベテの1次試験得点戦略 by サトシ
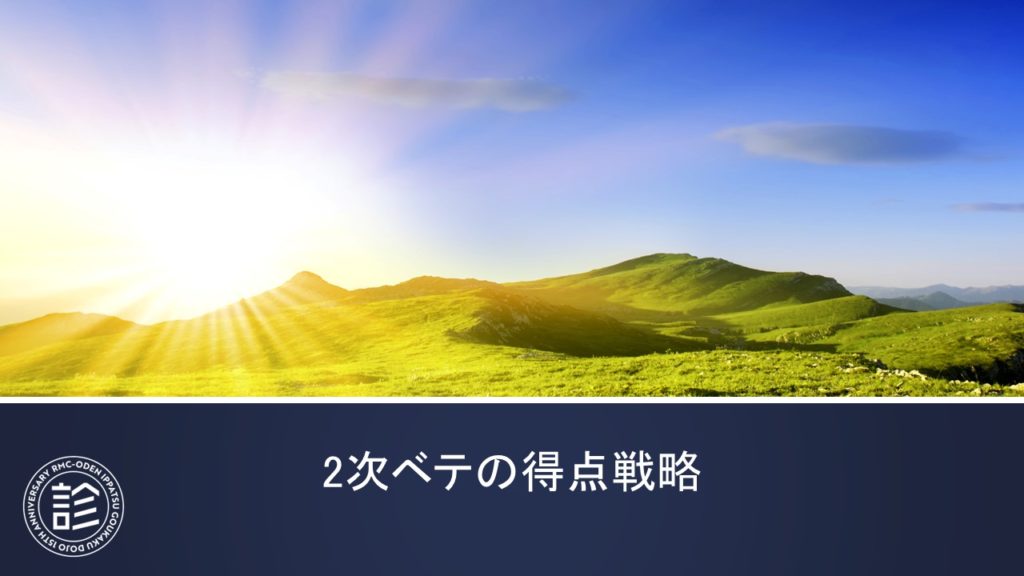
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
一発合格道場ブログを
あなたのPC・スマホの
「お気に入り」「ブックマーク」に
ご登録ください!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
みなさん、こんにちは。
2次試験に2回落ちて1次試験からやり直しになった経験を2回味わっていました、「サトシ」です。
ここまでの私の記事では、2次ベテにならないための教訓や合格するための勝利のストラテジーを紹介してきました。
今回からは2回にわたり、そんな2次ベテの方に向けた得点戦略についてお伝えしようと思います。今日は1次試験の得点戦略になります(2次試験の得点戦略は次回になります)。
もちろん、ストレート生や1次試験の経験がある上級生にも読んでいただけるような内容にしてあります。目標点数は「2次ベテの方・上級生向け」と「ストレート生向け」の両方を提示しています。
.jpg)
その前に、座談会のお知らせです

今年もやります!THE DANKAI 2024! ←某漫才の大会みたいな雰囲気ですね(笑)
1次試験・2次試験のお悩み相談とモチベーションUPが目的です。もちろん私の今日の記事の内容(1次試験の科目ごとの目標点や勉強法など)について私以外の道場メンバーに相談してもOKですので、参加をお待ちしております。
前置きが長くなりましたが、今回もよろしくお願いします。
- 1. 7科目受験のメリット
- 2. やり直しのハードルは思ったより低い
- 2.1. テキストの内容はほとんどが見たことのあるもの
- 2.2. 過去問もほとんどが一度解いているもの
- 2.3. 答練や問題集にある問題も、ほとんどが前と同じもの
- 3. 圧倒的に有利な立場にいます!
- 4. 難易度の変化で目標点数を変動させる
- 5. 得意不得意で目標点数を変動させる
- 6. 経済学:72点(スト生は68点)
- 7. 財務:68点(スト生は64点)
- 8. 企業経営理論:60点(スト生は56点)
- 9. 運営管理:60点(スト生は56点)
- 10. 法務:64点(スト生は60点)
- 11. 情報システム:60点(スト生は56点)
- 12. 中小企業経営政策:64点(スト生は60点)
- 13. 沖縄再試験の問題を「リアル模試」として活用する
- 14. ちなみに
- 15. まとめ
- 16. 次回予告
7科目受験のメリット
これはストレートの受験生(初学者)にも当てはまることですが、1次試験の7科目受験には以下のようなメリットがあります。
7科目受験のメリット
- 科目間・年度間の難易度の変化の影響を相殺できる(科目ごとの難易度変化はあっても7科目トータルでは難易度は同じ)
- 出題可能性や重要度の高い論点だけやっていれば良くなる(7科目受験ならこれらの論点だけに絞っていても合格できる。そのため、7科目あるから扱う量が増えるようで、実は科目ごとに扱う量を減らせる)
- 法務の英文問題、情報の統計問題のように丸ごと捨てる論点があっても他の科目でカバーできる
- 科目間のシナジー効果が発揮できて、科目をまたいだ問題が出てきても対応できる(例えば運営管理の問題で情報システムで習った内容が問われても対応できる。近年はこういう科目またぎの問題がやや増加傾向)。
- 7科目やり通した実績面とスタミナ面に自信がついて、2次試験への弾みがつく
- 2次に必要な知識を網羅できる(意外と中小の内容も2次には出てくる)
やり直しのハードルは思ったより低い
※ここからしばらくは、2次試験に2回落ちて1次試験からやり直しになった人向けの内容になります。ストレート生(初学者)や上級1年目の方は読み飛ばしてください。
2次ベテは「2次対策経験年数が3年超の人」と定義していましたね。そのため、2次ベテの方は1次試験は2〜3回、もしくはそれ以上受けていることになります。2次試験に2回落ちて1次からやり直しとなった方もかなりいらっしゃると思います。
そうなると、避けて通れない話題が「2次試験に2回落ちて1次からやり直しになった場合」についてです。この話は当人の心境も含め、実際に体験した人でないと書けないものだと思います。
1次からやり直しになった場合、多くの方は2回目の2次試験で不合格とわかった瞬間、絶望のどん底に突き落とされる感覚を味わいます。
- あぁ、また最初からやり直しだ。またあの苦労をしないといけないのか、、、
- 1次のことは完全にやっていなかったから、1次の内容は完全に忘れているよ。どうしよう、、、
- またあの1次試験7科目の内容を暗記しないといけないのか!
- 7科目の膨大なインプットもだけど、アウトプットも量が多くて嫌だ
- 時間が取れないし、どうやって1次対策をしていけばいいんだ?
- その上にさらに2次対策!?もうどうしたらいいの?
こんなふうに思っている方が大半です。
私もそうでしたし、私の周りで1次試験からやり直しになった方のリアクションもこのようなものでした。(私の場合は、「謙虚になれ」事件のせいで、絶望中の絶望の状況でした)
しかし、2次試験に2回落ちて 1次からやり直しになったとしても、思っているよりは1次合格までのハードルは低いです。複数年のスパンの科目合格積み上げ作戦を採用する必要は一切ありません。先ほど見たような7科目受験のメリットがある上に、ここから見ていくような特徴も加わりますから、一気に7科目受けてしまいましょう!

はぁ?そんなわけあるかいな!適当なこと言うたらアカンで!
ただし、「思っているよりもハードルが低い」というのは再び1次試験に合格して初めてわかることかもしれません。今の時点ではそう言われても、この彼のように「そんなわけないだろ!」と思ってしまうかもしれません。
ところが・・・
テキストの内容はほとんどが見たことのあるもの
テキストの内容を見ていかがですか?
ほとんどの内容が、「一度見たことある」と思ったものではないでしょうか?
見たことがないものと言えば、中小企業経営政策の中小企業白書の部分(内容は毎年変わります)と一部の施策(改正や追加・新設された内容)、法務の改正論点、経営情報システムの最新IT用語くらいです。それ以外のものは一度は見たことがある内容となっています。
一度見たものがほとんどですから、再び理解や暗記をするための労力もストレート生のときと比べたら少なくなっています。つまり、ストレート生のときよりも少ない時間で理解や暗記を進めることができます。
過去問もほとんどが一度解いているもの
過去問を解いてみて、感覚はいかがですか?
真っさらな状態で受けていたストレート生のときと違って、過去問なら見たことがある問題がほとんど(直近1〜2年の問題は知らないだけ)だと思います。
もちろん、見たことがある問題を再び解いた際に間違えてしまっても大丈夫です。しかし、解説を見たときの理解のスピードがストレート生のときよりも速くなっているはずです。前にも同じような解説を見て、同じように理解していますからね。
答練や問題集にある問題も、ほとんどが前と同じもの
答練や問題集の問題にしても、前に解いたことがある感覚はありませんか?
少なくとも「見たことはあるぞ」という問題ではないでしょうか?
というより、ほとんどすべてが「見たことのある問題」です。
そして、間違えたとしても、過去問と同じく解説の内容を理解するのにそこまで時間はかからないのではないでしょうか?

あれ?テキストの内容も答練や問題集の問題も何だか見たことある、、
サトシの言うように、思ったより大変じゃないのかも?
圧倒的に有利な立場にいます!
このように、1次試験からやり直しになった方なら、実は1次試験の問題の「ネタ」はすでにつかんでいるんです。しかも、解く際に見るべきポイント(フレーズなど)も、不適切な選択肢や適切な選択肢の雰囲気(どこが間違っているかなど)も、ある程度問題を解いてくればすぐに思い出せます。
映画で例えると、どんな話になってどんな結末になるかもわかっている状態です。そんな状態ですから、初めてその映画を見る人(ストレート生)とは感覚が違って見えるのは当たり前ですよね。
そのため、このようなことがハッキリと言えます。
2次試験に2回落ちて1次からやり直しのみなさんは、ストレート生と違って明らかに有利な立場にいます。
富士山で例えると、5合目からスタートしているようなものです。麓からスタートするストレート生と比べて、頂上(1次試験合格)までの距離も時間も有利な立場にいます。
そう。1次からやり直しのみなさんは、本人的には麓(0合目)まで突き落とされたと思っているでしょうが、実は無意識のうちにバスで5合目まで連れていってもらっているのです。それが1次試験に対するアドバンテージになっています。
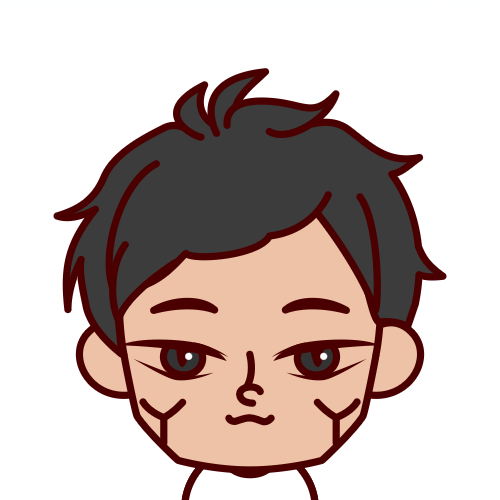
何?バスと言えば俺だろ。日本全国、どこのバスも乗っているぞ!
富士山5合目なら、河口湖駅や御殿場駅から路線バスがあるぞ
いやいや、バスってのは例えですよ。でも1次からやり直しの方は、実は無意識のうちにこのバスに乗っているんです
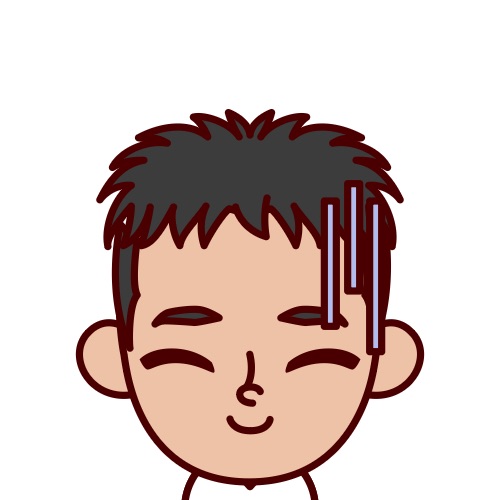
5合目からスタートというアドバンテージがあるため、1次試験に落ちることはあまり考えなくて大丈夫です。前より時間をかけず1次対策をしたとしても、過去問や答練、問題集で感覚を思い出せば、ほとんどの人が受かります。
実際、私の受験仲間で1次試験からやり直しになった方が何人かいましたが、ほぼ全員が次の1次試験は7科目を受験して420点以上を取って合格しています。
ちなみに、途中で「そんなわけあるかいな!」と言っていた彼 も、1次からやり直しになった人でした。やり直しになった瞬間は落ち込んでいましたが、結果的に1次試験に再び合格できました。そして、そのときに初めて以下のように悟りました。
も、1次からやり直しになった人でした。やり直しになった瞬間は落ち込んでいましたが、結果的に1次試験に再び合格できました。そして、そのときに初めて以下のように悟りました。

なんか、普通にやったら普通に受かったわ
なので、落ちることを不安に思わなくて大丈夫です。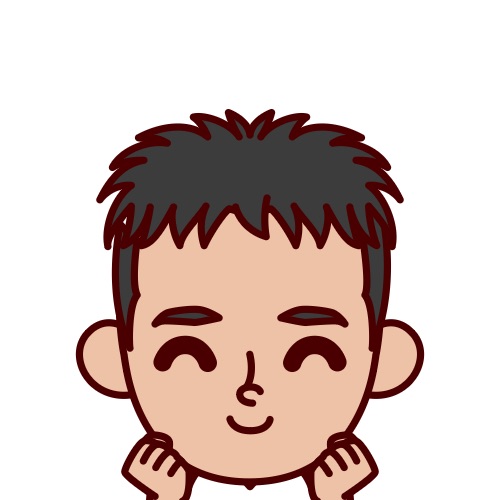
強気の姿勢で勇気と自信をもってください!
ちなみに、私は2次試験に2回落ちてやり直しになった経験を2回味わっていますが、やり直し経験が2回目になってくると、5合目ではなく6〜7合目からのスタートになります。
そのため、2回目のやり直しになった場合はさらに有利になります。

7合目からのスタートなら登山もすごくラクだよ
難易度の変化で目標点数を変動させる
※ここからしばらくは、2次ベテの方はそれほど意識しなくてもいい内容になります。逆にストレート生(初学者)や上級1年目の方に向けた内容となります。
1次試験の各科目は、年によって難易度が変動します。誰もが「今年のこの科目の難易度はどうなりそうかな」と予想したことがあるでしょう。
難易度の予想は、7科目を受けるストレート生や2次ベテの方ならあまり気にされなくてもいいと思います。何かが難しくなったら別の科目が簡単になって、7科目トータルの帳尻を合わせてくるからです。おそらく、この難易度での目標点数の変動は、7科目トータルでは±0か、若干のプラスorマイナスくらいになると思います(2次ベテの方なら経験則でわかりますよね)。
もちろん、難易度は本試験当日に受けたときに初めてわかるものですが、事前に目標点数の想定はしておいていいと思います。つまり、難しくなった場合は以下に示す各科目の目標点数から-8点、簡単になった場合は目標点数から+8点と想定しておきましょう。
このように7科目で難易度の帳尻合わせをしてくることを念頭に、当日の実際の難易度によって想定する目標点数を柔軟に変更できれば、難しい科目が来た場合でも落ち込まずに試験の最後までモチベーションを保つことができます。
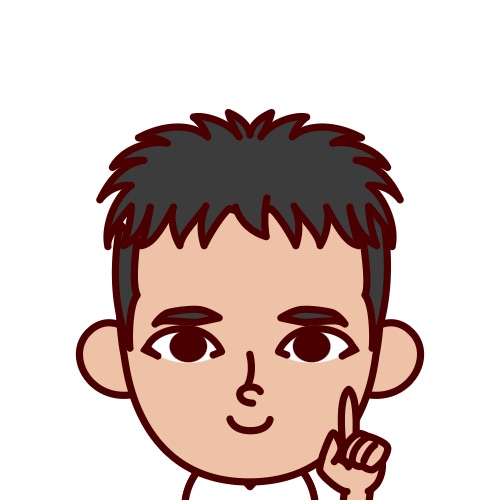
難易度予想については、6月2日公開のたいしんのこちらの記事も参考になります
得意不得意で目標点数を変動させる
また、各科目について得意不得意があります。
私なら経済、財務、中小は得意科目ですが、逆に情報システムは苦手科目です。
そのため各科目について、得意な方はこの目標点数から+8点、苦手な方はこの目標点数から-8点で考えていただけたらと思います。
例えば(以下にあるように)情報システムの目標点数は60点としていますが、得意なAZUKIと、苦手な私ではこのようになります。
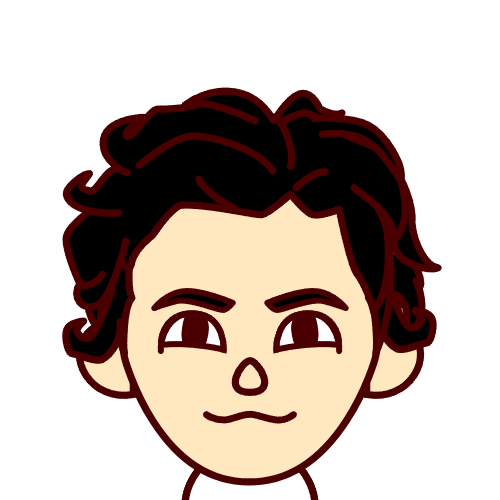
情報は大得意だから、60+8で68点が目標点ね
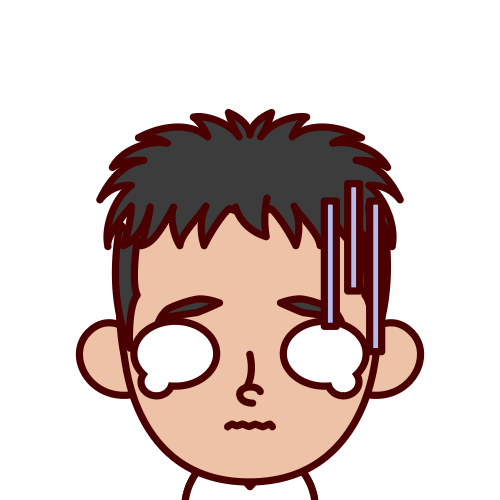
情報は大の苦手だから、60-8で52点を目標点にするね
では、1次試験からやり直しになった方は5合目からのスタートであることと、2つの目標点数変動要素がわかった上で、1次試験の得点戦略をお伝えします(各科目の勉強法も載せています)。基本的には1次試験からやり直しになった方(2次ベテの方)や上級1年目の方に向けた目標点数を提示し、そこから4点引いた点数としてストレート生に向けた目標点数も提示しています。
経済学:72点(スト生は68点)
※ここから先は、受験する科目については全員共通で読んでいただけると嬉しいです。
経済学は例年「稼げる科目」として位置づけられていて、基本的に高得点が取れます。
そのため、目標点数は72点とします。得意な方なら80点も狙えますし、数学アレルギーがあるような苦手な方でも64点は取れます。
経済が難しくなるとしたら、軽い程度になります。やりすぎると点数の底上げ(得点調整、ゲタ履かせ)が必要なレベルになってしまいますので。平成の頃は難化をやりすぎてしまって得点調整をするハメになった年がたまにありました。
軽い程度の難化なら、2次ベテの方なら経験で問題が解けます。また、グラフの問題なら導出過程など理解が以前より進んでいますから、前よりも確実性や安定感が高まっています。そのため、最近出てきている正誤の組み合わせ問題など多少の難化くらいなら正解できます。
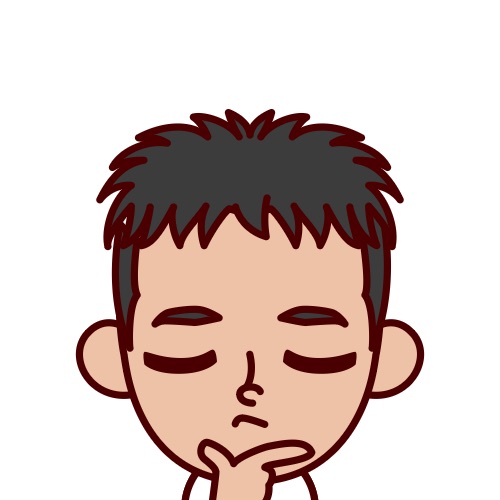
この正誤の組み合わせ問題は、問題自体の難易度は変えず正答率や平均点だけ下げることができるから、最近は他の科目でも重宝されているよ
最初2〜3問の統計問題は1問合えばよしとするくらいでOKです。それでも高得点が取れます。
グラフの問題については、苦手な方なら、見たことがない形の問題は取れなくていいです。3問くらい出てきますが、一切取れなくてもいいです。逆に経済が得意な方は、こういう問題は導出課程がわかっていれば簡単なので、取りにいけます。
ちなみに、ストレート生はグラフの導出過程の理解までは難しいのが実状です。そのため、無理なら導出過程は理解できなくてOKです。逆に経済が得意な方や上級生は、導出過程まで理解できているとそれだけでストレート生よりも有利になり、高得点が取れます。
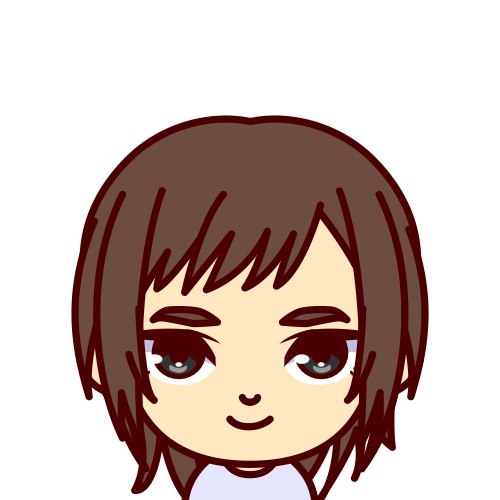
サトシさんはグラフの導出過程まで理解したら点数が伸びたって言ってたなぁ
経済理論の問題については、横串しで問題を解くこと(横串勉強法)をオススメします。例えば加速度原理なら過去問・答練・問題集にある加速度原理の問題(選択肢)だけ一気に見てしまいます。そうすると、どういう内容が問われて、どういう引っ掛けをしてくるかがわかるようになります。そうなると、案外「ネタ」は少ないことがわかります。これを理論項目ごとにやります。結果的に確実性や安定感が高まり、理論問題は半分以上の問題が取れます。
財務:68点(スト生は64点)
こちらも得点源にできます。そのため、目標点数は68点とします。
68点なら、経営分析、管理会計、典型的な会計理論・ファイナンスの問題が正解できれば届きます。これらの論点に出てくる各項目について、経済の理論のように横串勉強法でやっていけば確実に取れるようになります。例えばCVP分析ならCVP分析の問題だけを横串しで解いていきます。リース会計の理論の問題ならリース会計の理論問題だけを一気に見ていきます。
逆に簿記検定をやっていないと厳しいような簿記の計算問題や、マニアックな会計理論・ファイナンスの問題は解けなくていいです。こういうものが大好きなのはせーでんきくらいです(笑)

いやいや、サトシもこういう問題好きだろー
令和5年度の財務は、解いた瞬間は「これはかなり難化したぞ」と思っていても、自己採点をしてみたら意外と点数が伸びていました(これは情報システムも同様でした)。
今年についても、悪くてもこういう感じの出題で、実際に難化させることは避けてくると思います。
財務は得点源にしている方が多いので、ここで本当に難化させてしまうと、令和4・5年の法務並みの簡単な科目をもう1科目用意しないといけなくなります。そうなると7科目全体のバランスが崩れて合格者数や7科目の平均点が大きく下がってしまうリスクがあります。
企業経営理論:60点(スト生は56点)
企業経営理論は、意外と点数が伸びません。取れても70点強くらいです。逆に全く取れないことはなく、最悪でも50点弱で踏みとどまれます。
そのため、企業経営理論はその間の60点を目標点数とします。
2次ベテの方なら、企業経営理論の問題はかなりの数を解いたと思います。そのため、普通の受験生よりも「この文章は正しい、間違い」というのを嗅ぎ分ける嗅覚が育っています。根拠が明確にわからなくても、何となくでも「この選択肢は合っている。こっちの選択肢は間違っている」ということがわかります。
この嗅覚が働く問題だけ取れればOKです。そうすると、嗅覚が働かない問題も明らかにおかしい選択肢を削ることで3〜4割くらいはカンで取れますから、結果的に60点に届きます。
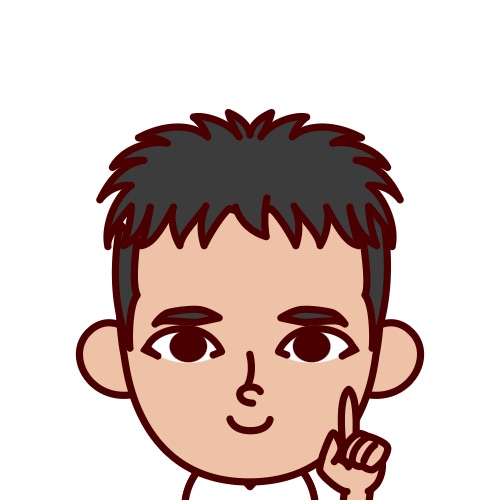
問題を解いてきた経験が暗黙知になって有利に働くのが企業経営理論だよ
また、企業経営理論も経済の理論項目や財務のように横串勉強法が使えます。例えば戦略論のドメインの問題なら、ドメインの問題ばかり見ていきます。ここで論点ごとに出題ネタや不適切な選択肢にするパターンを押さえてしまえば、さらに確実性や安定感が高まります。
なお、企業経営理論は難化はあまり考えなくていいです。戦略論、組織論、労働法規、マーケティング論の4つの分野間で難易度の帳尻を合わせるため、どこかの分野が難化しても別の分野が易化してトータルの難易度は変わらないようになっています。例えば戦略論が難しくなったとしたら、マーケティング論が簡単な問題ばかりになっています。
運営管理:60点(スト生は56点)
運営管理も企業経営理論と同じく、目標点数は60点とします。
60点なら難しいフレーズや見たことのないフレーズの問題、複雑な計算が必要な問題などは一切できなくても大丈夫です。過去問や答練、問題集にある典型的な問題さえ取れればいけますし、2次ベテの方ならそういう問題を安定して取れる力はあります。
もし安定して取れないならテキストにある典型フレーズや典型的な内容を覚えましょう。そうすると、アウトプットの経験は他の人よりありますから、すぐに安定して解けるようになります。
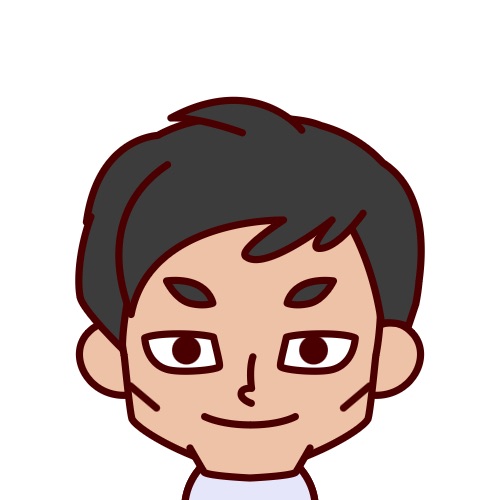
細かいJISの定義の問題とか計算問題が気になるなぁ
そういう問題は捨てても大丈夫!運営はインプットもアウトプットも難しそうなものは無視して、典型的なものだけでいいよ
.png)
法務:64点(スト生は60点)
法務は、令和4・5年とサービス期間が続いています。ここから「女心と秋の空」のように急激に難易度が変化するとは思えません。経済と同じで難化しても軽い程度と思われます。
そのため、目標点数は64点とします。どうしても苦手なら56点でもいいですが、そうでないならここで借金は作りたくないです。
法務で64点なら、英語と相続の問題はできなくても大丈夫です。景品表示法のようなマニアックな法律の問題も取れなくていいです。民法も正答率は半分以下で大丈夫です。
その代わり、会社法、知的財産権の問題と、その他の法律の問題も簡単そうな問題は取りましょう。それだけで十分届きます。
取れない問題もカンで何問かは正解しますから、その分で得点も伸びますからね。
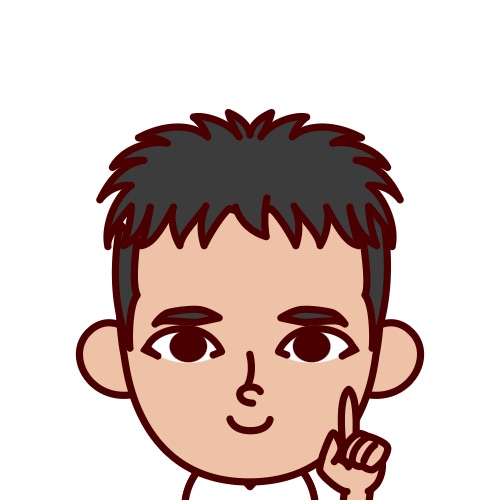
1次はこういうわからない問題での点数の伸びが重要だったりするよ
情報システム:60点(スト生は56点)
情報システムの目標点数は60点(得意な人は68点、苦手な人は52点)とします。
情報システムは、得意な人と苦手な人の差が激しい科目です。はい、先ほど見たようなAZUKIと私のようなものです(笑)私から見たら、AZUKIが話している情報システムの内容は宇宙語ですよ(笑)
そして、しんも実はSEでITの知識は豊富にあります。
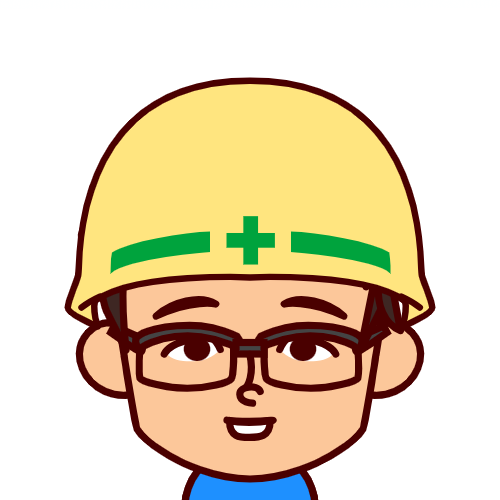
実はわたくし、SEです
情報システムについては、この知識の格差が試験側(出題者)を悩ませています。というのも、このようにITの強者がいる中で一般的なITの問題を普通に出してしまうと、SEのしん、ITに強いAZUKIのような人は平気で80点を超えてしまい、情報システムだけで1次試験が決まってしまう形になってしまいます。これだと2次試験の受験者や、2次試験の合格者、そして診断士に登録する人がSEやIT強者だらけになってしまいますよね。
そこで、試験側はSEやIT強者などが有利にならないような工夫を入れてきています。最先端のIT技術の問題やガイドラインの問題などが出題されるのは、そのような人のアドバンテージを少なくするためです。
ただし、最先端のITオタクですら知らないような問題やガイドラインの問題ばかりにすると、SEやIT強者の点数は下がりますが、普通の受験生はそれ以上にできないため平均点が大きく低下し、得点調整が必要になってしまいます。これが平成の最後あたりにありました。
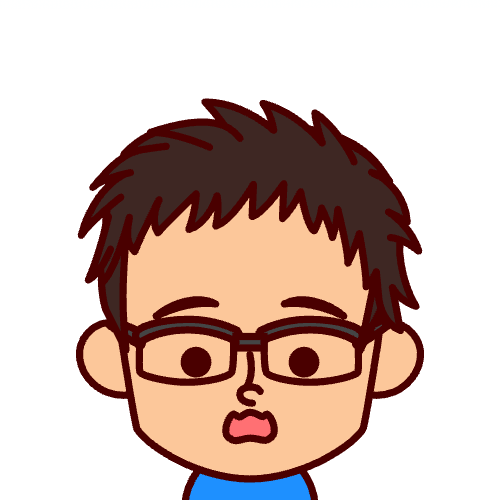
こんな細かい内容の問題やガイドラインの問題なんて、SEの私でも解けません
試験側としては、この失敗はしたくない、でもSEやIT強者などを有利にはしたくない。そこで、令和5年度は運営管理のように「その場で考える系の問題」を入れてきました。これならSEやIT強者が有利になるわけではないですし、解法さえわかれば私みたいにITが苦手な人でも点数を積み上げることができます。
今年もこの形式でいくと思います。それを入れての60点という目標点数です。
その場で考える系の問題の点数の伸びも期待できますから、テキストにある出題可能性の高い用語を押さえ、問題集を3周くらいやっておけば60点は取れます。
.jpg)
私みたいなITオンチでも合格できるから、大丈夫だよ
中小企業経営政策:64点(スト生は60点)
中小は、令和に入ってからは意外と難しくなりました。そのため、目標点数は64点とします。
平成の頃は白書の問題も政策の問題もシンプルで、「テキストで見たことのある問題なら取れる、見たことがない問題ならカンに頼るしかない」という科目でした。
しかし、令和に入ってからは、白書の問題は「テキストで見たことがあるようでない問題」が増えました。また、政策の問題もテキストに載っていない問題や、載っていても重箱の隅をつつくような問題が増えました。
ただし「増えました」と言っても、これらの問題が増えたのは中小で80点クラスを簡単に取らせないため(情報にとってのSEやIT強者と同じく1科目で勝負を決さないようにするため)であり、6〜7割の問題はテキストに載っていて、過去問(白書部分を除く)や答練、問題集でも扱ったことのある問題です。こういうところは横串勉強法が使えますので、確実性と安定感を高めることで点数を伸ばすことができます。そして、わからない問題は二択や三択まで絞ってのカン勝負にすれば、64点は届きます。
中小は他の科目と比べて、論点ごとの問題のバリエーションが少ないことが特徴です。そのため、横串勉強法で論点ごとのネタをつかんでしまえば、一気に点数が上がります。こういう部分で点数を稼いでいきましょう。
.jpg)
中小の暗記は直前にまとめてじゃなくて、早いうちからやっていこう!
沖縄再試験の問題を「リアル模試」として活用する
これは令和6年度の1次試験受験者の特権とも言えます。
ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、令和5年度は沖縄地区のみ、1次試験の日に台風が沖縄に接近していたため8月の1次試験が中止となり、12月に1次試験の再試験が行われました。
しかし、この沖縄再試験の問題は、市販の過去問題集には掲載されていません。予備校生だと予備校にて問題と解説が配布されているかもしれませんが、少なくとも独学の方は中小企業診断士試験のHPにある問題と正解しか入手できません。そのため、過去問として解くことを躊躇している(もしくは忘れている)受験生もいらっしゃるかもしれません。
そこで、沖縄再試験の問題をまだ解いていない方は、この沖縄再試験の問題を「リアル模試」として活用しましょう。通常の模試は予備校が作成しますが、これは本試験の試験委員が作成したものですからね。リアル感が違います。これを活かさない手はありません。
今年の1次試験受験生は、沖縄再試験の問題を使うことにより途中で本試験のリアルなシミュレーションができます。1次試験までのどこかのタイミングでぜひこの「リアル模試」をやってみましょう。確かに中小企業経営政策の前半部分(白書の部分)は使えませんが、それ以外の部分(政策部分+他の6科目)は使えます。本試験のリアルなシミュレーションができますし、本試験に受かるかどうかの目安にもなります。
また、本試験と同じスケジュールで受けることで、例えば1日目の4科目(経済、財務、企業経営理論、運営管理)のスタミナがもつか、2日目の最初の科目(法務)に疲れが出てこないか、7科目スタミナがもつかなど、スタミナ面のシミュレーションもできます。基本的に、過去に1次試験を突破している方なら、スタミナの心配は不要です。
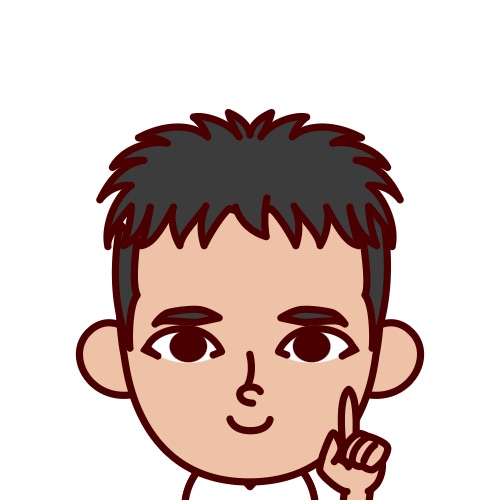
沖縄再試験については、後で「沖縄再試験特集」という記事を出します
ちなみに
これは私の経験則によるものですが、横串勉強法をしていて気づいたことがあります。

おい!またこのパターンかよ!もうちょっと工夫しろよ!
問題に対して良い意味でこういうツッコミができると、80点が見えてきます。
逆にこのツッコミができる雰囲気がしないと、良くて72点くらいです。
ということは、ここまで各科目の目標点を見てきましたが、このツッコミができるレベルになる必要はないことになります。逆に、このツッコミができる科目が1つでも出てくると、80点レベルの点数が取れることになるので、目標点を大きく超えての貯金ができ、1次試験が一気に有利になります。
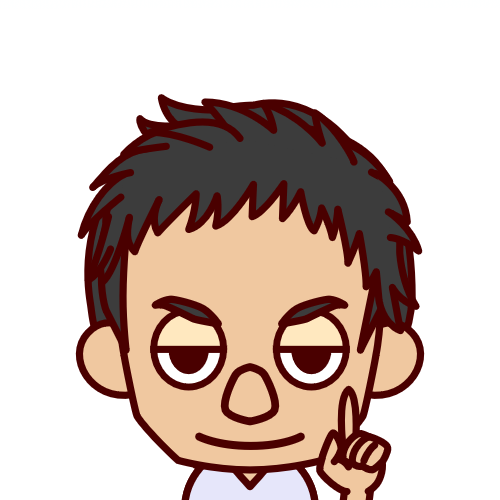
ツッコミなら任せてや~
いやいや、ツッコミのうまさは関係ないよ(笑)
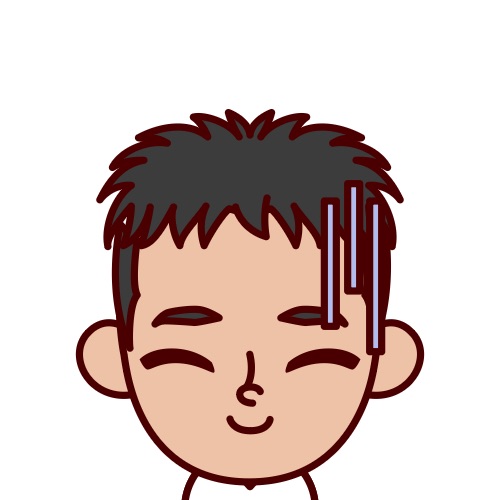
まとめ
最後に、目標点数を一覧で見てみましょう。
| 経済 | 財務 | 経営 | 運営 | 法務 | 情報 | 中小 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 68 | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | 448 |
| 68 | 64 | 56 | 56 | 60 | 56 | 60 | 420 |
どうですか?これなら28点も貯金がありますよ。もちろん、オール60点以上は理想論なので、2~3科目なら50点台でもいいです。仮に得意科目が一切なく3つ苦手科目があっても-24点(1科目あたり-8点)でまだ4点の貯金があります。
ストレート生についても、各科目から4点引いた点数を目標点数にすると、ちょうど下段のような点数になり合計420点になります。
難易度の高低での影響は7科目で相殺されますから、気にする必要はありません。
これならいけそうな気がしてきませんか?
そうです。先ほども申しましたように、特に1次試験からやり直しになった方(2次ベテの方)は、圧倒的に有利な立場にいます。自信をもっていきましょう!
2次試験の場合でも言えますが、2次ベテのみなさんならこの目標点数を取るためのノウハウはもっています。あとは実践あるのみです。頑張っていきましょう!
次回予告
ここまで、1次試験の各科目の目標点数について見ていきました。今回も前回と同じくかなり長かったですよね。1回で読み切れなくても何回かに分けて読んでいただければ大丈夫です。
ここまで私の記事にお付き合いいただき、ありがとうございました。
次回は「2次ベテの2次試験得点戦略」をご紹介します。次回もよろしくお願いします。
明日は、「ごり」の登場です。
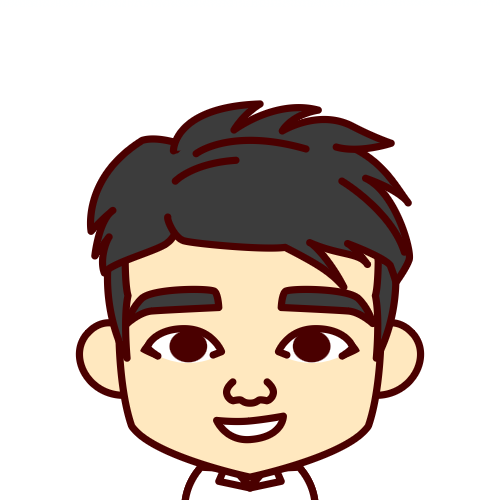
まとめシート、きちんと使っていますか?
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)