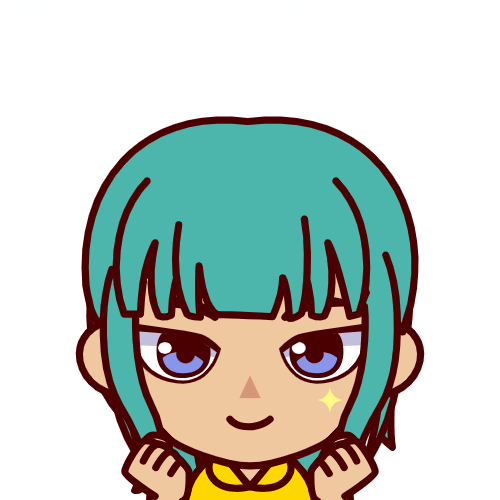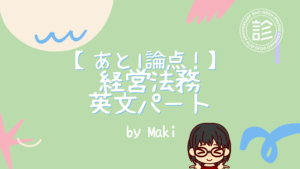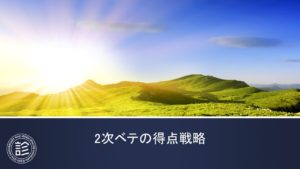2次試験開眼に至るまでの道のり(前編) by しん
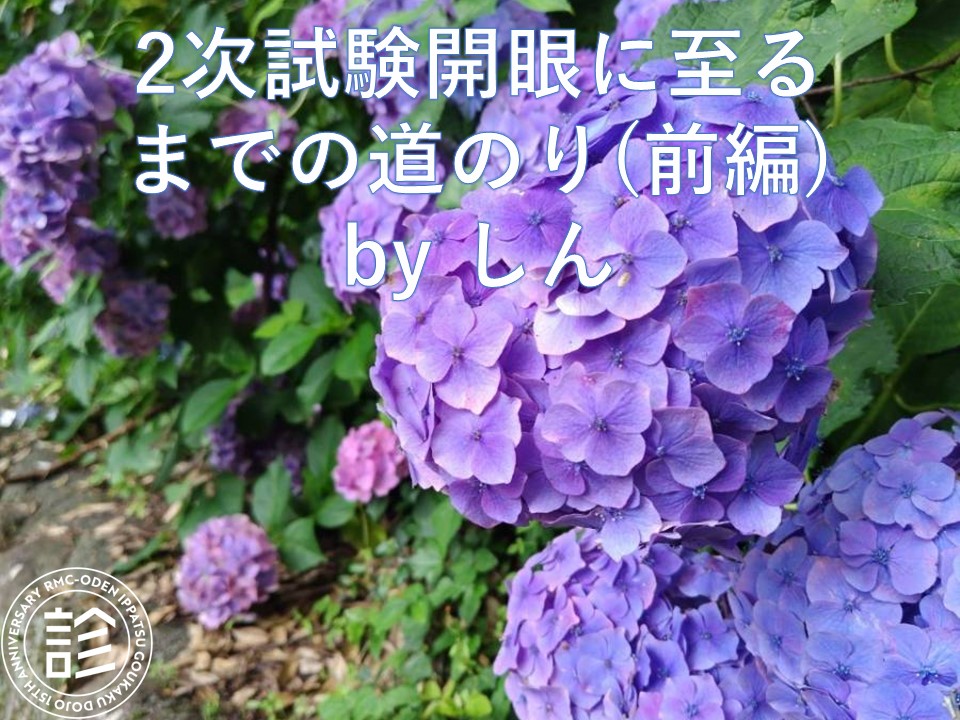
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
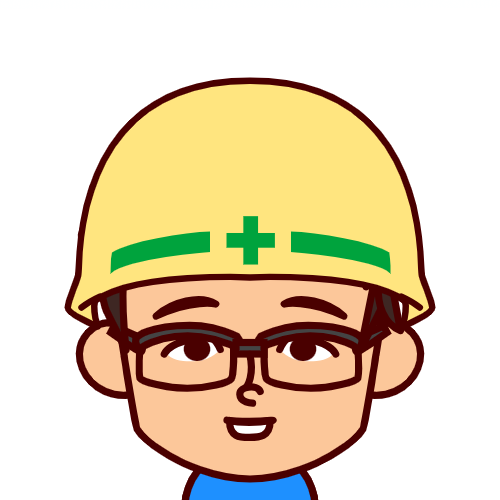
こんにちは、しんです。
5月も終わりに近づき、少しずつ汗ばむ季節となってきましたが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
季節の変わり目は体調を崩される方も多いかと思いますので、勉強しつつも身体を大事にしていただけたらと思います。
それでは本日の目次・・・の前にお知らせです!

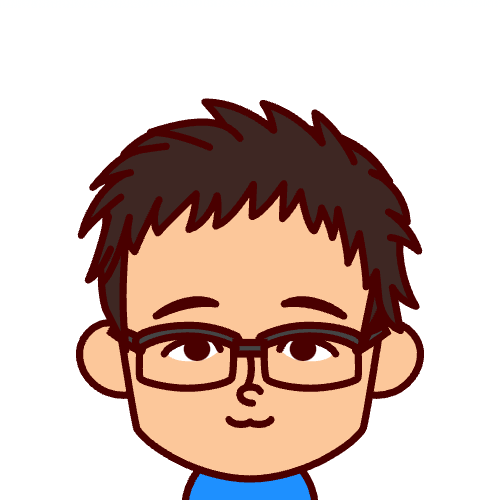
1次試験、2次試験にお悩みがある方や
モチベーションをUPしたい方!
是非ご参加ください!

それでは本編に戻り、まずは目次から。
本日の要約
本日の要約
- 概要:2次試験対策に専念されていて、「開眼」できず悩んでいる方を主なターゲットに、2次試験専念だった私がどのように「開眼」に至ったか、1年前の足跡を辿りお伝えします。
- お伝えしたいこと:「開眼」は合格に至るステップに過ぎず、「開眼」を経験せずとも合格する人も多くいます。合格するために「開眼」というステップが必要な方には、必要な学習を積み重ねることで、いつかその日が訪れます。
- キーワード:なし
上記の内容で気になる部分やフレーズがありましたら、本編に進んでいただけたらと思います。
はじめに
突然ですが、「開眼」という言葉をご存知でしょうか?
2次試験を受けたことがない方の多くは、聞いたことがない単語だと思いますが、次章で触れますのでご安心ください。
今回は、「2次試験に受かるイメージができないながらも試行錯誤していた」1年前の自身が、どのように「開眼」に至ったかを前後編に分けて、お伝えしたいと思います。
開眼について
開眼とは?
自身の体験をお伝えする前に今回の重要ワードである「開眼」とはどのような事象かについてご説明します。
様々な解釈がありますが、私は「①安定的に、②多面的で、③一貫性のある2次試験解答が書けると感じた瞬間」と捉えています。
ご参考に、私が「開眼」という言葉を知った、13代目hotmanさんの記事をご紹介します。
この記事を読み、私も2022年の2次試験までに「開眼」することを目標に励みましたが、残念ながら「開眼」には至らず、試験の結果も「不合格」でした。
こう書くと「開眼」が合格に必須のように見えてしまいますが、「開眼」を経験しなくても受かる人はたくさんいると思いますので、無理に意識しなくても大丈夫です!
自身、1年目は「開眼」を意識しすぎて、合格のための手段ではなく目的になってしまっていた気がします。
その後時は経ち、学習を再開した2023年の春頃には、「合格」をゴールとして全集中していたこともあり、「開眼」という言葉もすっかり忘れていました。
これからご紹介する様々な試行錯誤を経て、2023年8月頃に、①安定的に、多面的で、③一貫性のある2次試験解答が書けるようになり、「あ、これが開眼なのか」と思い出しことを覚えています。
一蔵アニキ風に当時の心境を表現すると、
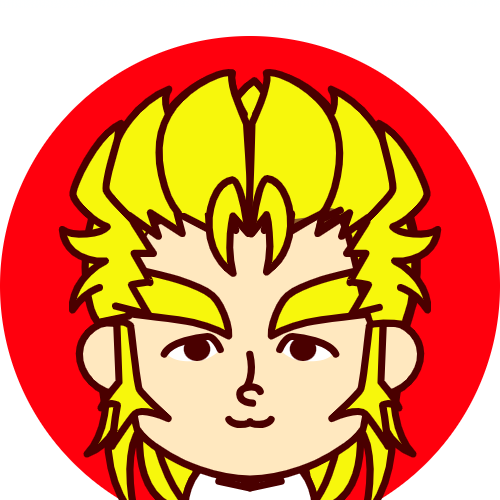
解ける!!!!!
ワクワクする!!
勉強後のご褒美スイーツがおいしい!!
という感じでした。
(実際には、2次試験受かる気がしない病も患っており、合格発表の日まで矛盾する心境に悩まされていました。。)
15代目の開眼状況
「開眼」を実際に経験した(と感じる)人がどのくらいの割合なのかが気になり、15代目メンバーにヒアリングしてみました。
結果は以下の通りです。
開眼した・・・6人
開眼しなかった・・・6人
開眼という言葉を知らなかった・・・1人
この結果からも、「開眼」は合格には必須ではないと捉えられますので、合格のためのステップの一つくらいに考えてもらえればと思います。
(せーでんきを始めとした短時間合格者は、初めから開眼を通り越して心眼で解けていたんじゃないかと勝手に思っています。)
2023年5月末までの過ごし方
それでは、ここから自身が開眼に至るまでの道のりをご紹介します。
ちょうど1年前の2023年の5月末頃までは、ギアを上げすぎないことを意識し、がっつり2次試験対策というような勉強はあまりしていませんでした。
理由は、以下の3点です。
①2次試験に確実に合格するための強固な土台(1次知識)を身につけたかったため
②2次専念といいつつ、最悪の場合の保険をかけたかったため
③1年間ギアを上げ続ける自信がなかったため(直前期~試験当日に最大のパフォーマンスを発揮するため)
ストイックさが足りない!!

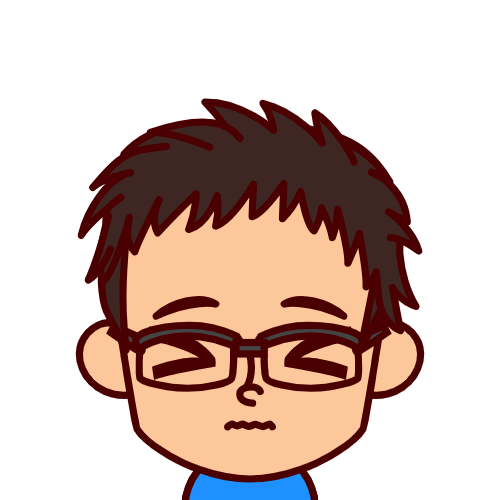
返す言葉もございません
かますからこんなツッコミを受けそうですが、がむしゃらに過去問を解いても初回受験時の二の舞いになる未来しか見えなかったので、急がば回れ作戦を取りました。
ロジカル・シンキングの習慣化
2次試験合格のための最大の課題であったロジカル・シンキングを習得すべく、書籍で概要を抑えた後は、試験勉強や仕事等のあらゆる場で意識的に思考し習慣化を図っていました。
一例として、勤め先について、この会社のあるべき姿は〇〇、現状は△△、そのgapである問題点は××、それらの情報から導きだされる課題は□□・・・等をまとめて、上司との面談で伝えてみました。
(うろ覚えですが、難しい顔をされた後に煙に巻かれました。。)
残念ながら提案を通す力が足りなかったものの、それ以降自身の業務については大きなプラスになりました。
それまではミクロな視点で目についた問題点を都度改善することが多かったのですが、会社(や所属部門)の目標というマクロな視点を常に持つことで、業務の優先付け(コア/ノンコアの見極め)ができるようになったためです。
今までそんなこともできなかったの?
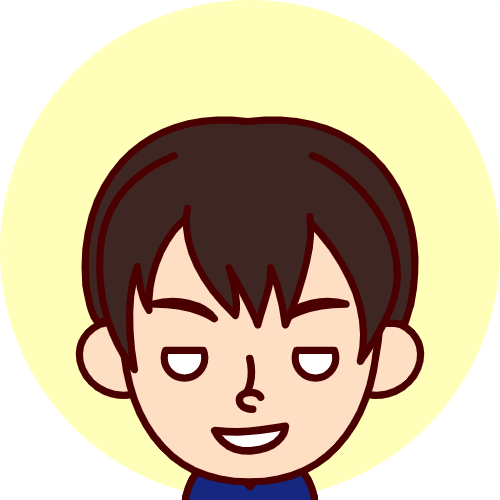
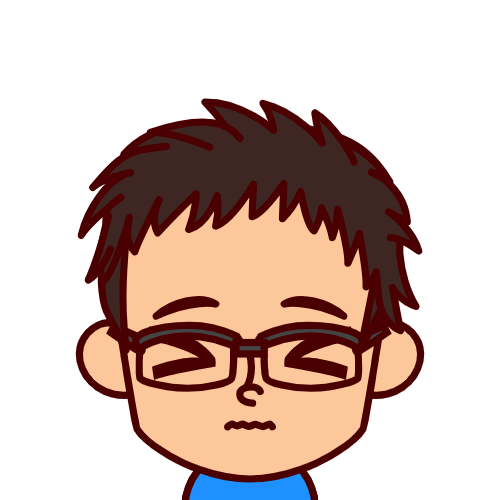
返す言葉も(以下略
今度は一蔵からこんなツッコミを受けそうですが、恥ずかしながらそれまで優先付け(コア/ノンコアの見極め)が本当に苦手でした。幸い昨年行った自己分析の結果その弱点に気づくことができ、診断士試験学習においても、この後にご紹介する学習計画の変更等がスムーズにできるようになったと感じています。
コア/ノンコアの見極めは、試験勉強のみならず様々な場面で役に立つと思うので、以下の一蔵の記事をまだご覧になっていない方はぜひご一読ください!!
読書(インプット)
以前のブログでご紹介したマンガや、その著者の書籍に加えて、診断士試験界隈で有名な岩崎邦彦先生の書籍を読み漁りました。
また、特に課題と捉えていたマクロな視点強化のため、経営戦略については、マンガ→書籍→診断士試験参考書と読み進め、暗記カードのようなものを作成しました。
ipadで暗記カード作れるよ?
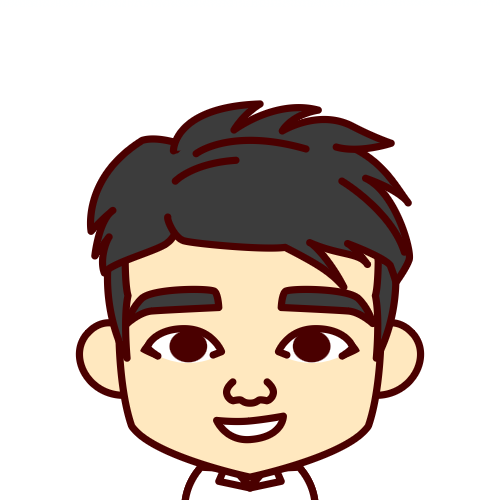
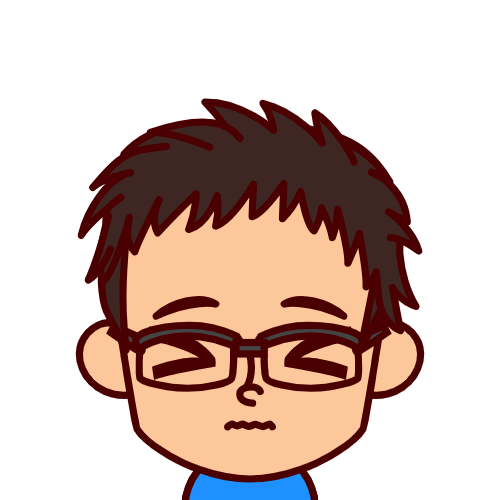
手書きには脳を活性化する効果が・・・
手書きにもメリットがあると感じるものの、時代に取り残されないよう、今更ながらipad学習法にトライしています・・・。
暗記カードを含めたipad学習法については、以下のごりの記事で紹介されていますので、興味がある方はぜひお読みください!
ごりも参考にした、先代のipad記事へのリンクもあり、道場が培ってきたipadノウハウをまとめて知ることができます。
過去問添削(アウトプット)
今回ご紹介する中で唯一診断士試験に直結する学習です。2週間に1回程のペースで、予備校へ過去問の解答を提出し添削を受けていました。この時期はあえて、自身の癖を抑えず書きたいように書いた答案を提出し、添削で厳しいコメントを多くもらうようにしていました。
その時期にいただいた血も涙もない熱いコメントは今でも覚えています。。
他資格学習
2023年1月の合格発表直後から、簿記2級と応用情報処理技術者の資格学習をしていました。
簿記2級は診断士を受かった人の多くが所持している&潰しがきく資格というのが理由だったのですが、今振り返ると理由が不明瞭でよくないですね。。
結局、簿記2級は商業簿記に興味が沸かなかった&診断士試験の事例Ⅳ毎日解くが思うようにできなかったため、1年前の5月末くらいに断念してしまいました。
診断士試験対策としてはあまり役に立たなかったと感じており、昨年の学習の中での反省点の一つです。
もう一方の応用情報処理技術者は、中小企業診断士1次試験の経営情報システムが7科目中最低点だったことがきっかけで取得を目指しました。
工場で情報システムに携わる業務をしており、得点源となることを期待していたため、強いショックを受けたことを覚えています。
この経験が一種のトラウマになり、もし2023年の2次試験に不合格となり1次試験からやり直しとなった場合に、経営情報システムは絶対に受けたくないと思い、こちらは途中で学習をやめることなく最後までやり切ることができました。
目標と現状(2023年5月末時点)のギャップ
続いて1年前に、目標と現状にどのくらいのギャップがあったかを書きます。
まず、目標については4事例で260点としていました。
なぜかというと、自身が博打を打つことなく得点することができ、かつ下振れても240点を確保できる点数だと考えたからです。
ひそかに280点に憧れる気持ちもあったのですが、回答を絞り込みすぎて大爆発するリスクが高いと判断し冷静になりました。
この目標に対して、2023年5月末時点では過去問を解いても
・多面的な解答ができない(飛びつき常習犯)
・解答要素を盛り込みすぎて字数が足りない
・新しく取り入れたプロセス(設問解釈)がうまくできない
・見直しの時間を確保できない
・事例Ⅳの計算ミスが減らない
といった具合で、ロジカル・シンキングは身に付きつつあると感じていたものの、4事例で260点には程遠い状態でした。
2023年2月初旬に立てた学習計画と比べても、量、成果共に下回っていたため、学習計画や解法を見直すことにしました。
今後(2023年6月から)の学習計画
2023年2月に立てた当初の計画から大きく見直した点として、2023年5月から7月にかけて学習する予定だった簿記2級をきっぱりと諦めました。
その分の時間を事例Ⅳの計算問題演習にあてて、計算ミスを減らすことに注力することにしました。
ただ、闇雲に計算問題を解いてもミスは減らないと痛感していたため、ミスをなくす仕組み作りもこの時期に意識し始めました。
具体的に、どのような仕組みを作ったかについては後編でご紹介します。
また、見直しの時間確保のために解法についても思い切って見直すことにしました。
それまで設問毎に色分けして使っていたカラーペンをすべて封印し、シャーペン一本足打法へとフォームチェンジすることにしたのです。
フォームチェンジした直後は、与件文のパーツを各設問へ適切に振り分けられるか不安でしたが、ロジカル・シンキングが定着すればなんとかなりそうとポジティブに捉えて、シャーペン1本での解法習得に励みました。
結果としては、開眼からさらに先の2023年の2次試験当日、シャーペン1本としたことや、いつか書ければと思っている様々な狂気的な工夫のおかげで、事例Ⅰ~Ⅲまでは70~75分程度で解き終わり、じっくりと見直しできました。
そして、計画通り高いモチベーションのまま事例Ⅳに臨んだものの・・・もちろん終わりませんでした!!ここ数年の事例Ⅳは完答させる気あるのでしょうかと作問された先生に問いたい・・・解答速度という観点での対策が足りなかったようです。
終わりに
2次試験開眼に至るまでの道のり(前編)は以上となります。
開眼するための近道や裏技はなく、自身に必要なことを地道に積み重ねた結果だということを感じていただけたら幸いです。
今回は勉強方法や過ごし方がメインとなりましたが、後編では開眼に至った具体的な手法をご紹介できればと思います。
明日はお休みで、次回は明後日となります。
私が恐れた1次再受験という大きな壁を2回も打ち破ったサトシが、1次試験の得点戦略を解説してくれるようですので、お楽しみに!!
1次試験も戦略が重要です
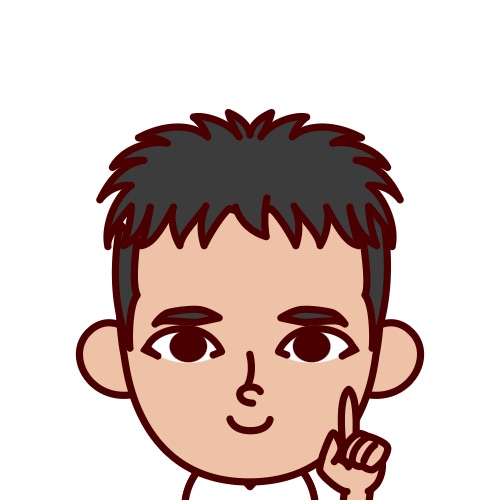
☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)