失敗談に学ぶ2次試験攻略のポイント byりいあ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
一発合格道場ブログを
あなたのPC・スマホの
「お気に入り」「ブックマーク」に
ご登録ください!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

こんにちは。りいあです。
今回は、私の2次試験対策失敗談から学んだことをご紹介しますね。
“りいあ”の2次試験対策導入記事もぜひご覧ください。
本日は、上記の記事で出てくる『レベル3』と『レベル4』の間にある壁を越え開眼に至った経緯について、具体的にご紹介します。
事例Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのシナジーに期待した1か月
いよいよ2次試験対策を本格化させる時期ですね!
2次試験は事例I〜Ⅳまでの4科目あります。
事例Ⅳが計算問題を中心とした異質な事例である一方、事例I・Ⅱ・Ⅲは文章問題のみで構成されています。
事例I・Ⅱ・Ⅲの解き方については、ある程度共通する部分が多く、対策を同じように進める方も多いのではないでしようか。

私はそうしました。
1次試験終了後から2次試験対策を開始し、時間が無かったのもあります。
勉強期間は77日間でした。
共通部分としては、マーカーの引き方や、80分の過ごし方、解答の型、制限文字数でまとめきること、などがあるかと思います。
マーカーの引き方については、以下の記事もぜひ参考にしてください。
これらについて、基本的なところは事例I・Ⅱ・Ⅲで共通して訓練できると思います。
(もちろん、必要に応じて、仕上げ段階では事例ごとにカスタマイズするのはおすすめです。)
シナジーだね~。
2次試験では、まずぶつかって慣れる!それも必要だよ。

しかし、試験科目が3つに別れているのですから、解答要素となる知識だけでなく解き方も3つそれぞれ違うはずです。
それなのに、私は、2次試験の約1ヶ月前まで相乗効果部分のみに頼ってしまいました。
事例I・Ⅱ・Ⅲ3科目の特徴の違いについてなんてあまり考えず、『ふぞろい』片手に過去問演習にぶつかり続けました。
結果として、なんだかしっくりこない答案ばかりで、解くたびに得点もブレブレでした。

とりあえず、80分で解答用紙を埋められるようにはなったけど…
しっくりこない。こんな解答で合格レベルになるのかな…?
そんな思いのまま、2次試験を約1ヶ月後に控えた頃、一発合格道場主催の勉強会に参加しました。
勉強会で恥をかく
初学者かつ独学者だったため、勉強会で初めて他の人に自分の作った答案を見せます。
ドキドキしましたが、勉強開始から約1か月を経て、なんだかんだ『ふぞろい』のキーワード採点では60点前後に届き始めていました。
勝負にもならなかった1次試験直後とは違います。
また、勉強会では事前に作った答案を持ち寄るのですが、実際には80分では解ききれなかったので、各事例につき15分ほど超過して最後まで納得いくよう解ききりました。(ちょっとズルしたということです。)
満を持しての勉強会です。
さて、そんな“りいあ”の2次試験約1か月前の答案を見てみよう。
(わかりやすい例として事例Ⅲだよ。令和2年度の過去問を温存している人は、以下ネタバレ注意。)

令和2年度 事例Ⅲ 第4問
【設問文】
C社社長は、付加価値の高いモニュメント製品事業の拡大を戦略に位置付けている。モニュメント製品事業の充実、拡大を どのように行うべきか 、中小企業診断士として120字以内で助言せよ。
モニュメント製品事業の充実・拡大に対し、①工場建屋の改修または増築により、設置高さ7m以上の製品製作へ事業拡大する②2次元CADの活用や生産計画の作成期間短縮、作業チームの技術力向上により、製作リードタイムを短縮し短納期による充実を図る。
さて、この解答を読んで皆さんはどう思いますか?ぜひ具体的に評価してみてください。
勉強開始から約1か月にしてはよく書けている?試験まであと約1か月にしてはひどい出来?どこが良くないでしょうか?
実際にいただいた道場12代目からのコメントを見てみましょう。

中小企業にとって“建屋の改修”はコストがかかるため慎重に。他に優先すべきものがあるのでは。
そもそも、“事業の充実・拡大”に対する解答になっていますか。
同じことを回りくどく言っているので、もっと文字数を節約できます。
また、事例Ⅲの設問4なら、営業力強化が定番。私なら入れます。


……はい。(涙目)
という具合で、めちゃくちゃご指摘いただきました。
(※要約しましたが、実際にはやさしく教えてくれました。)
つまり、試験まであと約1か月にしては割とひどい出来だったのです。本番じゃなくてよかった!
私の答案を見て12代目と同じ指摘を思いついていた方、素晴らしいです。合格者の視点です。
対して、私は、「え!何でもいいから解答欄に関連しそうな言葉を並べればいいんじゃないんだ…!」とその時気づきました。
ギリギリだね~。
“りいあ”はこの時点まで、事例も設問も問わず、全て同じ答え方をしていたんだね。
でも、このあと約1か月間、あることに気を付けることで、全科目を70点以上に引き上げることができたよ。

2次試験攻略のポイント~りいあの場合~
その後私は、試験まで以下の2つポイントに気を付けることで、合格へたどり着きました。
【POINT】
- 設問の要旨に答えること
- 事例ごとの特徴を把握すること
これらはすべて、勉強会での反省から得たものです。
設問の要旨に答えること
先ほどの勉強会における“12代目のき”さんの指摘は、つまり…

中小企業という相手の立場を考えていませんよ。そもそも、聞かれたことに答えていませんよ。
ということです。
いかにそれらしい単語がギュウギュウに詰まっていても、一番聞きたいことへの返事になっていなければ意味がありません。
私の解答は、書いているうちに『結局何が言いたいのか』を見失っているのです。
設問文はつまり、「事業を拡大したい。具体的にどうしたらいい?」と聞いています。
本来の解答はつまり、「より良くして、事業を拡大させる。」でなければなりません。

私の解答は「建屋を改修して、設置高さ7m以上の製品製作へ事業拡大する」です。
一見それっぽく見えるのですが(見えないかもしれません)、文章の論理展開が破綻しています。
『建屋の改修⇒7m以上の製品製作』は因果関係が成り立ちますが、
『7m以上の製品製作⇒事業拡大』は飛躍しすぎです。その方法を聞いているのです。
これでは、結局設問の要旨である『事業拡大』について答えられていません。
また、そもそも、私の答案は「7m以上の製品製作へ事業拡大する」という言い回しから、設問の「事業拡大」を「取り扱い製品分野の拡大」と同一視している節があります。
「取り扱い製品分野の拡大」は、この設問では事業充実にあたるでしょう。
事業拡大とは、事業充実したうえで、受注を増やし利益を増大させて初めて成り立つのです。
そういう意味では“12代目アヤカ”さんの指摘も重要です。
“12代目アヤカ”さんの指摘には…
営業力強化(⇒受注を増やし利益を増大させる)の視点が抜けていますよ

という内容が入っています。
この指摘に対応すると、先ほどの論理破綻も解消されます。
× 『7m以上の製品製作⇒事業拡大』
○ 『7m以上の製品製作+営業力強化⇒事業拡大』
★設問の要旨を見極め、見失わないようにする必要がある。
★解答の論理展開が破綻すると、聞かれたことに答えられない。
解決策
この論理の破綻に対しては、「つまり」を武器に使ことにしました。
★まず設問解釈時に、設問について「つまり何を聞きたいか」という要旨をメモします。
(例:「事業を拡大したい。具体的にどうしたらいい?」)
★次に解答骨子作成前に、解答について「つまりどういうことか」という要旨をメモします。
(例:「より良くして、事業を拡大させる。」)
そうすることで、設問の要旨見失うことが減り、聞かれたことに答えることができるようになりました。
事例ごとの特徴を把握すること
先ほどの勉強会での指摘では、“12代目のき”さんはロジックの面から、“12代目アヤカ”さんは事例研究の面から、結果的に答案の同じミスを指摘する形となりました。
そういう意味では、合格者は必ずしも皆が同じ知識・ノウハウを習得しているわけではなく、自分に合った方法で合格するための力を身につけているのだと再確認できますね。
さて、「設問の要旨に答えること」が“12代目のき”さん起点のロジックの話だったので、ここでは“12代目アヤカ”さん起点の事例研究の話をします。
勉強会当時、私は“12代目アヤカ”さんの発想が目から鱗でした。
事例Ⅲの設問4なら、営業力強化が定番。私なら入れます。


事例や設問の定番!?そんなのあるの??
「こう聞かれたらこれ使う」の定番には少し慣れてきたけど、聞かれる前から予測する定番は知らなかった!
この時点で私が知っていた『「こう聞かれたらこれ使う」の定番』は、以下の3つでした。この3つはとても大事です。
①解答フレーム
事例Ⅰなら「サチノヒモケブカイネコ」、事例Ⅱなら「ダナドコ」、事例Ⅲなら「生産計画と生産統制」といった定番のものがありますね。
事例Ⅰの解答フレームについては以下のリットの記事をぜひご覧ください。
②レイヤー
設問ごとに問われている内容の階層(レイヤー)を数種類に分けることができますね。
詳しくは以下のまんの記事をぜひご覧ください。
③解答の型
解答を書く際の書き出しやまとめ方の定番で、「課題は~。解決策は~。」「理由は①~、②~、③~ため」などがありますね。
詳しくは以下のまよの記事をぜひご覧ください。
しかし、これら以外にも解答するためのヒントになる『定番』や『傾向』があります。
それを知るためには、事例ごとの特徴をより深掘りする必要があります。また、同じ事例でも、設問番号ごとに特徴がある場合があります。
ここを押さえることで、事例Ⅰ・Ⅱ・Ⅲで共通の浅い内容でなく、各事例固有の目的に適う解答を作成し高得点を狙うことができます。
“りいあ”の場合、事例も設問も問わず全て同じ答え方をして、しっくりこないと感じていたところだったから、まさに救世主だね。

★事例ごとに特徴があり、解答するヒントになる。
★特徴をおさえると、しっくりくる解答で高得点が狙える。
解決策
事例ごとの特徴をつかむために、事例研究をしてFPにまとめました。
★「道場ブログ」等の事例研究記事を調べ情報収集する。
過去の道場ブログには必読の記事が多数あります。ぜひ検索して気になるものを集めてください。
※私“りいあ”からも、具体的な事例ごとの特徴について、今後のブログ記事で順次お伝えしていきますね!
★自分で過去問を解きながら傾向を分析する。
※これは時間に余裕がある、または粗々でも基本が身についてからでもいいかもしれません。
この結果、事例ごとの特徴を知り、求められる解答を想定して解くことができるようになりました。
さいごに
いかがでしたでしょうか。
今回は、2次試験の約1か月前にはこんな下手な答案を書いていました、というお話になりました。
恥ずかしいですが、この失敗談から何か参考になるところがあれば嬉しいです。
また、こんな答案でも、克服して無事合格にたどり着けたという点で、少しでも励みになれば幸いです。
今回の記事で勉強会に興味を持たれた方は、以下のhotmanの記事もぜひご覧ください。
一発合格道場主催の勉強会は、今年も2次試験1か月前にあるとかないとか…(未定です)

明日は、YOSHIHIKOよろしく!
おけまる☆
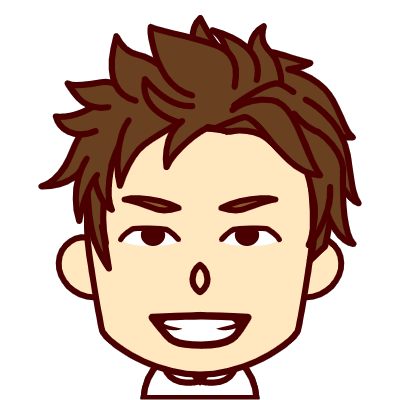
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)

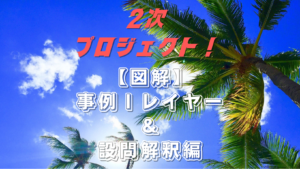
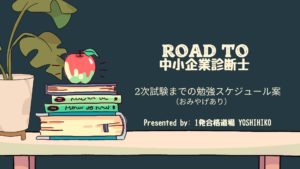
いつも読ませていただいてます。事例Ⅲの設問4なら営業力強化が定番のような、設問ごとの定番について詳しく書いてもらえると嬉しいです。
siki様
いつも道場ブログを読んでくださりありがとうございます。
設問ごとの定番や事例ごとの特徴につきましては、今後ブログで順次書いていく予定です。
現在内容を整理していますので、今しばらくお待ちくださいませ。
siki様が合格されることを心から祈っています。頑張ってください。