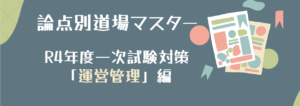モチベーションを高く保つ方法★≪マインド編≫★ byりいあ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

こんにちは!りいあです。
今回はモチベーション向上について、前回に引き続き、私なりに工夫した方法をご紹介します!2部作の後編で≪マインド編≫になります。
モチベーションが下がるときって?
みなさまは、モチベーションが下がるとき、または、もう無理だとあきらめるとき、何がそのきかっけになりますか?
私は、大きく4つのきっかけがあると思っています。
やりたいこと(挑戦)ではなく、やらなければならないこと(義務)になったとき

ブログの掲載日が迫ってきた!
まだ白紙だ…逃げたい…
待て待て

私はこれを「積み本効果」と勝手に呼んでいます。
本屋にある新しい本は買って読みたくなるのに、自宅に積んである本は読む気がしない現象です。下手をすると、すでに積んである本の存在すら忘れ、また買ってきてウキウキと読み始めることもあります。
掃除中に整理すべき本棚の本を読みはじめ、試験前におもむろに掃除を始める現象もこれです。
〈解決策①〉「やらなければならないこと(義務)」をもう一度「やりたいこと(挑戦)」のレベルに引き上げる。
前回の記事の「2.良きライバルをつくる」をご覧ください。今回の記事の「おまけ:自分にマーケティング!」もご参考に!
〈解決策②〉積まない。
私は、物理的にテキストや参考書も少しずつ買います(笑)新しい本って、それだけでやる気をあげますよね!
また、勉強計画を立てるときも、ガチガチに固めず、ざっくりのリミットだけ決めておいて、日々の自由度を高めたほうが、結果的に良い動きができると思います。
〈解決策③〉やるべきことの順番を変えて自分を騙す。
新鮮さを重視し、あえて本来のスケジュールから順番やモノを逸らします。
逸れてもいいのです。積んだ本を読むことに意味があるのではなく、何でもいいからその時やりたいことをやって、日々全力を尽くし、最終的に敵を倒す力をつけることに意味があるのですから。
掃除中に全力で勉強しておいて、試験前に全力で掃除したら、結果的にすごい集中力で勉強と掃除が進みそうじゃないですか?
単調で本当に飽きる

息子が10回連続で同じ絵本を読んでと言ってくる…
飽きる…飽きるよ…
違うのは?だめ?だめなのね…はい読みますよ
まあそれは飽きるかも

〈解決策①〉つまらないことはやらない、面白いことをやる。
やりたいことしか人は本気を出せないものです。詳しくは前回の記事の「1.面白い(≒ときめく)ことをやる」をご覧ください。
〈解決策②〉ゲーム性を加える。スリル×達成感・収集欲を活かす。
モンスターハンターというゲームがあります。
機械音痴の私ですが、学生時代にハマり800時間近く費やしていました。ちなみに孤独学を愛する私はオフラインです。
(800時間あれば診断士試験にも挑戦できるだろうに、もったいない…と今の私は思ってしまいます(笑))
モンスターハンターは、簡単に言うと、時間内にモンスターを倒してアイテムをはぎ取り、アイテムで装備を強くしていくゲームです。マップやモンスターの種類にも限りがある中、装備を作るためには何度も同じことを繰り返さなければなりません。
こんなに単調な作業を、なぜあんなに熱中してできるのか?
答えは、スリルと、達成感と、収集欲を満たす要素が絶妙に組み合わさっているからです(私の勝手な意見です。映像が美しいとか色々あるのだと思います)。
これを診断士試験の勉強に応用しない手はありません!
スリルを得よう
◆時間:制限時間と目標得点を設定し、問題演習でタイムアタック!
問題演習の復習にも制限時間を設けタイムアタック!
◆期間:制限期間を設定し、3日でテキスト1冊を終わらせるなどのタイムアタック!
◆点数:時点別の目標到達得点を設定し、模試やセルフ模試で挑む!
達成感を得よう 収集欲を満たそう
◆テキスト・問題集を進めたら、目次に今日の日付を入れる
⇒制覇を目指すゲーム
◆問題演習で、間違えたら×、あいまいな点があるものは△、完全正解したら〇をつける
⇒×を〇にしていく収集ゲーム
◆やるべきことをグラフ化して一覧にし、進捗に応じ塗りつぶす
⇒収集ゲーム
◆間違えた箇所をミスノートに集めて次に使う
⇒装備強化ゲーム
◆模試やセルフ模試で到達度を計測する
⇒レベル上げゲーム
いかがでしょうか。あまり楽しくなさそうでしょうか(笑)
実際にそう思ってやってみると、ただ漫然とやるよりは気分が盛り上がりますよ!
ちょっと孤独学者の想像力頼みな気もする


そうかな。
ちなみに、息子に同じ絵本を何度も読むときの楽しみ方は、声優になりきり、聞き手そっちのけで必死に演技することです。
息子は大ウケ。
だから同じ絵本ばかり持ってくるのでは?

何のためにやっているのか目的がわからなくなったとき
長い試験勉強期間、伸び悩んだり、仕事が忙しく時間が取れなかったり、つまずくことはたくさんあろうかと思います。
目の前の作業に追われていると、中小企業診断士を目指した当初の新鮮な気持ちがどこか遠くへ行ってしまうことがあります。
〈解決策〉夢を見る。将来のことを考える。それを書き残す。
夢を見る時間はとても大切です。ここには、時間をとる価値があります。
私は受験生時代の一時期(特に1次試験の2~3カ月前)、机に向かっていても、半日ずっと手帳に将来の活躍について書き綴り、合間に少し勉強するような日々を送りました。
試験勉強に飽きてきたゆえの現実逃避だったのか、有り余るやる気が変な方に向かったのか、今でもわかりません。
バカみたいな行動ですが、その後の1次試験と2次試験まで4カ月強の追い込み期間、記した夢が燃料となり、手帳を何度も見返しながら、最後まで熱量を持って走り抜けられました。
情報がとっ散らかって収拾がつかないとき

今日は忙しいぞ~
買い物行って、作り置き料理して、衣替えして、友人と約束…
あれ?出かけたいけど鍵がない!あれ、財布もない!
そもそも何買うんだっけ?待ち合わせ何時だっけ?
うーん……わけわかんなくなってきた…。
ま、いっか!とりあえず漫画読もう。
こらこら

診断士試験は科目数が多いので、あれもこれも、やらなければならないことが重なります。
私の場合、元々、マルチタスクや長期継続が苦手で、他の資格試験でも、こっちの科目をやっていたらあっちの科目はあれ?どこまでやってたっけ?わけわからん。なんてことが日常茶飯事でした。
教材は重くて全部を手持ちはできないし、パソコンで管理しようとすると、いつの間にかパソコンをつけるのがおっくうになり(笑)パソコンをつけたら、そのままネットサーフィンして遊んでしまったり。
そうして全体像や現状がよくわからないまま時間が経つと、試験と完全に距離ができてしまいます。そして、そのまま疎遠にしてしまいたい欲求がむくむくと湧いてきます。
そんな時は?
〈解決策〉診断士試験の目標・進捗・戦略・夢を手帳に一元管理。
具体的には今回の記事の「2.診断士試験をお手元に」をご覧ください。
診断士試験をお手元に
私が診断士試験でのモチベーション高保持に役だったと思うものの一つが、手帳です。
このペーパーレスの時代ですが、診断士試験の目標・進捗・戦略・夢を一元管理するには、紙の手帳もおススメできます。
スマホの手帳アプリやパソコンのソフトでもよいのですが、個人的には、開きたくなければ開かないでいられるものは避けています。めんどくさがりな私の場合、開かなくなってしまうからです。
参考になるかわかりませんが、私の場合、手帳を診断士試験にどのように活用したか、例としてご紹介します。
目標管理
目標は常に目に入るところに掲げておくとよいです。自宅の壁に貼るなども良いですが、外でも自宅でも確認できる手帳はとても便利でした。
汚くて恐縮ですが、私の実際に使っていた手帳の画像を載せます。

①一次試験本番の目標点数と、直近の模試の目標点数について、5月中旬頃に青ペンで書いています。
私の受験スケジュールでは、5月中旬といえば、基礎テキスト・問題集(中小企業政策除く6科目)が1周した頃です。
使用テキスト・問題集は「みんなが欲しかった中小企業診断士の教科書(上)(下)」とその問題集(上)(下)です。
薄くわかりやすいので、3月~5月の3カ月で6科目ひとまず基礎を1周することができました。
※ただ、これだけでは不十分なので、過去問メインで仕上げていく人向きです。
手帳では、基礎を1周した時点で、各科目の感触に合わせて、具体的な点数の目標を決めています。
この時点でも、最終的には各科目最低60点以上をとるという意思が固いです。
また、まずは5月末の模試で、足切り回避かつ平均60点以上を出そうとを設定しています。今思えばかなり高いハードルですね。
②5月末、模試の後に赤ペンで模試の結果を書き加えています。最初の目標は達成できていません。
経営法務の“トクイ”の記載と“44”の並びが切ないです。
③6月頭、えんぴつで試験本番の目標点数を修正しています。
模試の結果をふまえ、各科目の目標得点バランスを調整しています。
6月から本格的に過去問演習に入りましたが、その際には、日々この目標点数を確認しながら、勉強時間の振り分けをやっていました。
結果的に、試験本番ではこの目標をほぼ全て超え、総合点数も509点と目標を大きく上回ることができました。
試験本番の科目ごとの点数分布は、目標点数の分布に準じています。目標を常に見ながら、それを意識した勉強をしたことで、成果につながったと思っています。
進捗管理
進捗は常に全科目が一覧で見えるとよいです。常に俯瞰して状況をとらえることができます。
-768x1024.jpg)
↑一次試験の基礎テキスト・問題集の進捗管理です。
分かりにくいのですが、各科目を順次終わらせており、道場基本理論の橋げた理論に通ずるものがあります。
基本的には1科目ずつ確実に終わらせていく。力を分散させない。
一方で、初回の学習から時間が経ち過ぎないように既習科目の復習を組みます。
進捗管理表には事前のスケジュール要素がほぼありません。
左端の二重線で消してある「3月」「4月」等のみがざっくりとした終了目標でした。
他は、実際にやったら書き込むスタイルです。なぜかというと、事前にスケジュールを組んで縛るとやる気がなくなるからです。
大まかなやることだけわかるようにしておいて、当日やりたいことをやるのが捗りました。
-768x1024.jpg)
↑一次試験の過去問演習(上が過去問年度別、下が過去問マスター科目別)の進捗管理です。
過去問マスターの進捗管理表にふってある数字はページ数です。
過去問マスターは1週間で6科目を各1回はやるようにしていました。
1週ごとに色を変えているので、1日あたりの進捗は100ページが限界だったようです。
また、経済学・経済政策と財務・会計の2科目については、時間内に解くことも重要なため、直近5年分の過去問を年度ごとに解いています。
それ以外の科目は、過去問マスターで論点ごとに解くのみでした。
今見返してみると、手帳が原始的管理過ぎてやや恥ずかしいです。
しかし、私の場合、この手書きで作り出す狭い手帳の世界が、診断士試験を常に手元に置き、自分だけの世界にのめり込むのに大変有益でした。
戦略・夢
戦略と夢に関しては、個人的なスケジュール等と一緒に記載されているため、実際の記載をお見せできず残念です。
煽り文句が手帳のところどころ記載されており、一部抜粋してみます。
◆7月22日(1次試験30日前)~7月末の10日間
「あと1か月!ここでやり遂げなければ全てがムダになる!!」
◆8月7日(1次試験2週間前)~8月9日の3日間
「ここで全てが変わる 弱点特攻期間」
◆10月8日(2次試験30日前)~10月17日の10日間
「あと1か月ここで決まる!!やり遂げなければ全てがムダになる!!人生をかけた10日間!!1000時間をここに集結させろ!!」
※自分を煽るために盛っているようです。私は1,000時間も勉強できていません(恥)
◆2次試験の進捗管理表
「1次試験で涙を飲んだ場合を考えろ!!2次に手が届くチャンスを必ずものにしろ!」
自分だけの小さな世界である手帳の中で、自分を煽って鼓舞し続けていたようです。
おまけ:自分にマーケティング!
最後に、自分をやる気にさせる方法を「自分にマーケティング」と称してご紹介します。
マーケティングって何?
マーケティングとは何でしょう。
令和3年度中小企業診断士試験委員の岩崎邦彦先生は、著書「小が大を超えるマーケティングの法則」の中で、マーケティングとは「顧客を創造し、維持するための活動」であると定義しています。
「顧客を創造し、維持するための活動」
この「顧客」の部分を、「診断士試験を受ける自分自身」と置き換えたとき、「自分を受験生として創造し、維持するための」モチベーションの高保持について応用できる部分がありそうです。
現在、勉強をしていく中で得ている診断士としての知識も、ぜひ効率的な勉強へと役立ててください。
マーケティングについての知識は12代目masumiさんの記事がとても勉強になりますので、ぜひご覧ください。

明日は、打って変わってデジタル派のYOSHIHIKOです(*’▽’)
明日もよろしく!
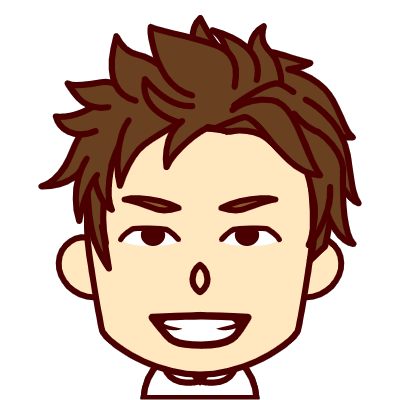
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)