【合格体験記】振り返り・復習重視と運を味方につけるスタイルで逆転合格! by sevenseaさん

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
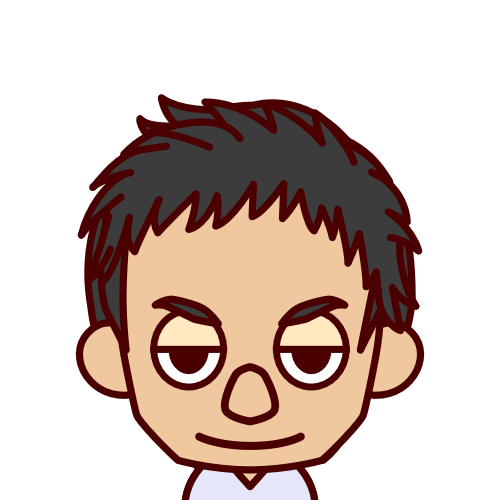
本日の合格体験記お1人目は、
sevenseaさんです!
受験生情報
- ハンドルネーム:sevensea
- 年代:20代前半
受験回数
- 1次試験:1回
- 2次試験:1回
学習時間
- 1次試験:100時間
- 2次試験:200時間
学習開始時期
2024年1月
自分の診断士受験スタイルを一言で表すと
振り返り・復習重視と運を味方につけるスタイルで逆転合格!
診断士に挑戦した理由・きっかけ
- IT一本足打法から卒業したい!
情報系の大学を卒業し、地元企業の総合職として入社。入社後もIT関連の資格を複数取得して知識をつけてはいましたが、残念ながら関わる業務のほとんどはITをそこまで必要としないものが多く、あまり知識を活かしきれていないと感じていました。そんな中、IPAの国家試験であるITストラテジスト試験の勉強をしていた際、より企業の経営にフォーカスをした資格である中小企業診断士を知り、ITに次ぐもう一つの武器になるし、自身のITの強みを仕事で活かす方法もわかるようになるのでは?と考えました。また、IT以外の武器を持っておくことでキャリア選択をする上でのリスクヘッジとしても使えるかな?と思ったことも理由の一つだと思います。
- 地元の中小企業の皆さんのサポートをして地域に貢献したい!
私が生まれ育った地域は静岡県浜松市の中にある、農業がとても盛んな地域でした。私の祖父母も農家ですし、小学校の時の同級生の家もほぼ100%が農業で所得を得ている、そんな地域です。したがって、身の回りに個人事業主や零細企業の社長として働く大人たちがたくさんいる中で育ってきました。現在は地元の大企業で働いているものの、いつか仕事を通して、自分の故郷で小さいながらも工夫を凝らして頑張っている方達に恩返しをしたい、と考えていた中で、診断士の勉強の中で得られる知識はとても魅力的であると感じていました。
職務経験・保有資格
- 職務経験:サービス業の企業で総合職として勤務する社会人3年目(受験時)
- 保有資格:基本情報技術者、応用情報技術者、ITストラテジスト、プロジェクトマネージャ
得意科目・不得意科目
- 1次試験
得意科目:企業経営理論、経営情報システム
不得意科目:経済学・経済政策、財務・会計、経営法務 - 2次試験
得意科目:事例Ⅰ・Ⅱ
不得意科目:事例Ⅳ
合格までの学習法
1次試験:独学
【本番得点(試験直後の自己採点)】
経済学・経済政策 52点
財務・会計 56点
企業経営理論 79点
運営管理 68点
経営法務 52点
経営情報システム 68点
中小企業経営・政策 54点
合計 429点(61.28%)
【学習方針】
他の資格試験で得た知識が使える企業経営理論、経営情報システム、運営管理の3科目で可能な限り高得点を取り、他の科目は50点くらいを狙って足切りだけは回避する、という方針でした。ただ、2024年は共に2度目の受験となるITストラテジスト試験とプロジェクトマネージャ試験の合格を主眼に置き、診断士についてはほぼ記念受験でOKかな、という認識でした。
【時期ごとの学習状況】
1月~2月
企業経営理論、運営管理を中心に、4月に受験するITストラテジスト試験でも流用可能な科目からインプット中心の学習を開始。ただ、本業の仕事がとても忙しかったため、片道1時間の通勤・通学のバスの中で余裕がある時だけ教科書を読む程度でした。
3月~4月
4月21日に受験したITストラテジスト試験の勉強に集中するため、診断士の勉強はほぼしませんでした。
2024年5月~7月中旬ごろまで
引っ越しに伴う手続きや準備などのため、結果として勉強はあまりできていませんでした。ただ、2日間の長丁場の試験で、前泊も含め2泊3日での受験となることから、せめて模試だけは会場で受けてみて、当日のスケジュール感を掴んでおこう、ということで6/29,30に実施されたTACの模試を受験しました。
(模試の結果)
経済学・経済政策 32点
財務・会計 36点
企業経営理論 69点
運営管理 54点
経営法務 28点
経営情報システム 52点
中小企業経営・政策 30点
合計 301点(43.00%)
正直なところ、今年の合格は難しいかなと思わざるを得ない結果でした。
7月下旬~試験当日まで
あまり試験まで当日まで時間がないため、模試で間違えた問題の復習だけは徹底的に行い、特に計算問題と暗記問題を中心に頭に叩き込みました。また、隙間の時間は一発合格道場の記事を読んでいました。当日は、どの科目もあまり手応えは無く、完全に不合格のつもりでいましたが、自己採点をしてみるとギリギリ合格ラインを超えていることに気づきました。
2次試験:独学・勉強会
8月
まさか1次試験に受かるとは思っておらず、ほとんど出題形式すら分かっていない状態だったため、一発合格道場やYouTube、野網先生の「「まとめシート」流!ゼロから始める2次対策」で2次試験の試験形式から調べ始め、各種テキストを購入しました。また、自分一人での合格は絶対に不可能だと考え、勉強会コミュニティ「ココスタ」に参加し、勉強会への出席を始めました。
9月
事例1~3については、ココスタの勉強会で指定されている過去問を解き、他の受験生や運営の皆さんにアドバイスを頂く、ということを繰り返していきました。その際、次の2点を強く意識しました。
・1次がギリギリ合格で知識が不足している状態の中でも2次試験に短期間で合格するため、なるべく早く解答の型を作ってしまい、他の方法には絶対に浮気しない。色々試すような時間は無い。
・他の受験生の解答の良いところはどんどん盗む。解答の内容はもちろん、そこに至る思考プロセスもしっかりと耳を傾けて盗んでいき、勉強会終了後に自分の解答とよく見比べて、どう直すべきかを考える。
この時点で、事例1~3については直近5年分は一通り解き終わり、隙間時間は「「まとめシート」流!ゼロから始める2次対策」の付録の100字トレーニングの問題を解くなどして知識をつけていきました。
事例4については、30日完成!を少しずつ進めていきました。
10月前半
10/13にプロジェクトマネージャ試験があるので、診断士2次試験は事例1~3の勉強会に参加するだけとしていました。事例4についてはノータッチ。
10月後半
プロジェクトマネージャ試験終了後は、事例1~3については9月に確立した型をベースに、直近5年分の過去問を解きなおし、ふぞろい採点で70点程度が取れる状態となっていたため、勉強会でアドバイスを頂いてブラッシュアップすることに注力しました。この際も復習に力を入れ、他の受験生の解答と自分の解答を見比べながら、ふぞろい採点で90点程度が取れて、かつ当日でもギリギリ書けそうな解答を作成していきました。
事例4については30日完成!を1周し、過去問5年分を解いてみましたが、ふぞろい採点で40点前後くらいしか取れなかったため、大問2と3の計算問題はほぼ諦め、大問1と4だけに絞って復習を行い、そこだけは確実に点数が取れる力をつけることに注力し、足切りを回避する戦略を取ることにしました。
なぜその学習方法を選んだのか?
1次試験
まずは一度受けてみよう、という要素が強かったため、まずはあまりお金のかからない独学を選択しました。また、基本情報や応用情報についても独学で取得できていたため、4択や5択の1次試験であれば独学でもなんとかなるだろう、と考えていました。
2次試験
明確な答えが無い試験に完全な独学で挑むことは流石に無謀だと考え、とにかくアウトプットをして他人にアドバイスを貰い、復習をする、というプロセスを繰り返すことができる方法を探した際に見つけた方法が勉強会でした。また、他の受験生の解答に対してアドバイスをすることが、自分にとっても良い勉強になるのでは?と考えたことも受験生同士の勉強会を選択した理由です。実際、アドバイスする相手を合格させよう!という気持ちでアドバイスをしようとすると、勉強会の前に相手の解答をよく読み込み、それで良いのか与件分や1次知識の振り返りをし、言葉にまとめて相手に伝えなければならず、そのプロセスには自身にとっての学びの種がたくさん落ちていたように思います。まさに、情けは人の為ならず、なんだなと痛感させられました。
学習時・受験時のエピソード
学習時
1次試験直前の7月に実家からパートナーとの同棲へと引っ越しを行なった都合や他の2つの試験と並行して勉強をしていた都合、3月頃と9月頃は本業がとても忙しかった都合などで、勉強時間の確保に大変苦労しましたし、実際1次試験直前の模試は惨憺たる結果、と言わざるを得ない状態でした。そのような状況の中で一度解いた問題の復習に力を入れて、短い時間で結果を出すことにつながったことはとても良い経験になりました。また、そのような厳しい環境の中での挑戦を支えていただいた周りの皆さんには感謝しかありません。特に、同棲を始めた瞬間から4ヶ月ほど勉強漬けの生活になってしまったにも関わらず、文句一つ言わずに支えてくれたパートナーには感謝してもしきれません。改めて、ありがとうございました。
加えて、他の2つの試験についても無事合格できたのですが、診断士の勉強の中で経営に関する知識をつけ、100字程度の論理的な文を書く力もつけたことはその合格にも大きく寄与したのではないかと感じています。この試験は専門的な知識や技能が身につくことは当然ですが、それ以前に社会人としても大きく成長できるのかもしれません。
受験時
合格は遠いだろうと思っていても会場に行き、とにかく最後まで諦めなかったことが合格の要因だと思います(すごく当たり前のことですが…)。1次試験については、全体でたった4問間違えていたら不合格の可能性もあったわけで、全問題解き終わった後の見直しをしなかったと考えると…。2次試験についても、少しでも部分点を取ってやろうと全科目時間ギリギリまで文字を書き込んでいました。自分自身は諦めの悪い性格だと思っていますが、その性格を今回以上にありがたく思ったことは無い気がします。
ちなみに、私は資格試験のような勝負事の前日には静岡で有名なさわやかのげんこつハンバーグを食べるようにしていて、一度も勝負に負けたことがありません。また、勝負事の直前(資格試験の場合は大体、問題用紙が配られてから試験開始までの微妙な時間)に、軽く目を閉じて、心の中で「できる!できる!絶対できる!」と叫ぶようにしています。これらをすると何故か本当にできる気がしてくるのです。このような弦担ぎというか、ルーティーンのようなものは案外馬鹿にできないのかもしれないですね。
これから合格を目指す方へのアドバイス
ここまでの経験を踏まえて、私からできるアドバイスがあるとすれば、以下の3つかなと思います。
- しっかりと復習をすることを意識して勉強をすること
- 2次試験は他の方に自分の解答を読んでもらい、アドバイスを貰うこと。また、他の受験生の解答を読んで、相手を合格させるつもりでアドバイスをすること。
- 合格できないと思ったとしても受験申し込みをし、当日会場へ行って試験を受け、最後の1秒まで粘り強く戦い抜くこと
特に2次試験は、決まった答えが無く、頑張って勉強をすれば絶対に合格できる、というようなタイプの試験ではありません。だからこそ、時間をかけて闇雲にたくさんの問題を解くのではなく、復習や他の受験生などとのコミュニケーションを通して、1つの問題を多面的に分析して丁寧に勉強を進めることで、勘所をおさえられるようになる必要があるのかと思います。
また、2次試験は決まった答えがないからこそ、自信がなかったとしても”ワンチャン”がある試験であるとも感じます。当日出る問題との相性や採点者が自身の解答をどう判断するかなどなど、合否を分ける重要な要素は、試験を受け、結果を見てみるまで絶対に分かりません。正直、社会人3年目で経験不足だし、勉強も不足しているし、1次も2次も合格には程遠いと思っていましたが、結果としてどちらも1回で合格ができました。自分の場合、実力1割、運9割だとは思いますが、最後の最後までもがいたからこそ9割を占める運を味方にして、”ワンチャン”を掴み、逆転合格ができたのだと思います。
この体験談を読んでおられるみなさんが、丁寧な学習で確かな力を身につけ、最後まで戦い抜くことで運まで味方につけて合格を勝ち取られることをお祈りしております。
おわりに
診断士と同時期に、ITストラテジストとプロジェクトマネージャも取得してしまうだなんて・・凄すぎます!「運」とおっしゃってますが、最後までもがいたからこそ「運」も引き寄せられたんですね!sevenseaさん、合格おめでとうございます!

コメントについて
記事へのご感想やご要望があれば、下部の入力フォームから是非コメントをお寄せください!
執筆メンバーの励みになりますので、よろしくお願いいたします。
※コメント送信後、サイトへ即時反映はされません。反映まで数日要することもあります。
※コメントの内容によっては反映を見送る場合がございますので、予めご了承ください。
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)


