【合格体験記】過去問演習を重視した学習で短期合格を目指す by まんたさん

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
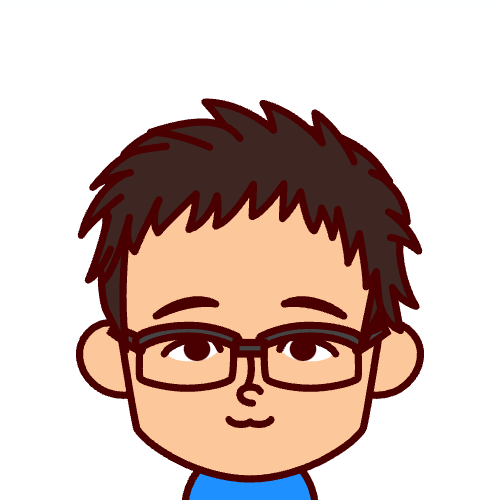
受験体験記の寄稿、ありがとうございました!
今回はまんたさんの体験記を紹介します!
受験生情報
- ハンドルネーム:まんた
- 年代:30代
受験回数
- 1次試験:1回
- 2次試験:1回
学習時間
- 1次試験:200時間
- 2次試験:250時間
学習開始時期
2024年2月
自分の診断士受験スタイルを一言で表すと
過去問演習を重視した学習で短期合格を目指す(息抜きも忘れずに。)
診断士に挑戦した理由・きっかけ
会社の経営に関する知識を身に付け、会社の経営に貢献できるようになれば、会社員として日々のタスクをこなすだけの仕事よりも提供できる価値を高めることができると思い、コンサルティング領域には以前から興味がありました。2,3年前に中小企業診断士という資格の存在を知りましたが、一般的な資格塾のサイトで、勉強期間1000時間とされていることもあり、なかなか手を出せずにいました。
そんな中、妻が簿記の勉強をするということで一緒に書店に行ったとき、偶然にも隣に中小企業診断士のテキストがおいてあり、「そういえばこの資格に興味があったな」と思い出しました。そこで、一次試験の過去問集を開いてみたところ、常識でわかる範囲の消去法で解けそうな問題もあり、意外と取っつきやすいのではないかと感じました。結局、この日は本を立ち読みしただけで、特に勉強に向けてのスタートを切ったわけではありませんでした。
それから1か月ほど経過した頃、家に転がっていた簿記のテキストを見て、「おれも簿記受けてみようかな」と言ったところ、先に資格取られたら嫌だからと妻に猛反対され、その時の会話の流れで、中小企業診断士の勉強をすることに。当時は、8月の1次試験まで約半年しかない時期だったこともあり、今から勉強を始めて半年で太刀打ちできるような試験かどうかを見極めようというくらいでした。熱い思いで勉強を始められた皆さんとは違い、一風変わったきっかけだと思いますが、これが受験勉強の始まりでした。
職務経験・保有資格
【職務経験】
研究開発(化学):9年目
【保有資格】
宅地建物取引士
基本情報技術者
危険物取扱者甲種
高圧ガス製造保安責任者乙種機械
取得宅建や情報技術者の資格は10年前に取得したもので、ほぼ記憶に残っていない状態でした。また、職務経験も中小企業診断士の試験にドンピシャで生かせるようなものはあまりありませんでしたが、知財に関する部分は比較的親しみがあったので、苦手な法令で勉強の負荷が軽減したのはよかったです。
得意科目・不得意科目
- 1次試験
得意科目:経済学・経済政策、財務・会計、企業経営理論、運営管理
不得意科目:中小企業経営・政策 - 2次試験
得意科目:事例IV
不得意科目:事例I、II、III
合格までの学習法
1次対策
使用テキスト:みんなが欲しかったシリーズ(教科書・問題集 各上下巻の計4冊)のみ
使用サイト:過去問ドットコム、その他一般のウェブサイト
2~6月:知識インプット
以下の①②をテキストの最初の教科から順に進めました。単純に①の直後に②に取り組むと、丸暗記になりそうだったので、次の教科のインプットを挟んでから復習をする方針を取りました。
①各教科の教科書を読む→例題を解く→問題集を解く→問題集を復習
②次の教科の①が終わったあとに前の教科を問題集で復習
また、問題演習中にわからないところがあればテキストやネット検索でインプット不足を補いました。わからないところをしっかり調べることによって、関連する知識をひとまとまりで覚えることができたのは良かったと思っています。
7月:過去問演習
ひたすら解いて復習です。
7月末~:直前詰め込み
試験直前の過去問演習をする中で、中小企業経営・政策の科目については、テキストの内容が非常に薄く、過去問を解いていてもわからないことばかりでした。そのため、試験直前の時期は中小企業経営・政策のインプットに時間を費やしていました。(たまに法令の知識のインプットも)
実際に、一次試験の得点でも中小企業経営・政策が明らかに低かったので、勉強不足だったのは間違いないでしょうし、最後の追い込みによって足切りを避けられたのではないかと思っています。
2次対策
使用テキスト:ふぞろいシリーズ(合格答案17、答案分析5,6,7、10年データブック)、30日完成!事例IV合格点突破計算問題集、事例IVの全知識&全ノウハウ
使用サイト:ダンシ君のサブノート(Youtube)、その他一般のウェブサイト
一日の勉強スタイル:夜は過去問演習(1事例)、翌日の朝の通勤で採点・復習、夕方の通勤で復習の続き、ダンシ君のサブノートでの知識インプット
8月上旬:情報収集~過去問着手
勉強法を調べて、道場やタキプロのブログに出会う。
同時に初めて過去問演習に挑戦したが、何を書いたらいいのか全くわからず困惑しつつも、唯一、財務関係の事例IVについては計算が多いため、なんとかなりそうな感触を得ていました。
過去問演習は、直近のものは貴重な過去問なので、2020年度のものを使用しました。
8月中旬:事例I~III過去問繰り返し
初見の過去問を残すため、2020年度の過去問の演習を3,4回繰り返しました。
演習を繰り返す中で丸暗記してしまう部分もありましたが、解答にどのようなキーワードが使われるのか、なんとなく傾向をつかんだ気になっていました。
8月下旬:事例IV着手
事例IVに未着手だったので、他の事例の勉強は中断し、事例IVの30日完成のテキストを進め始めました。
数学が得意で計算自体はスムーズにできたので、事例IVの30日完成を約10日で1周しました。
9月上旬:他年度の過去問に着手
無事一次試験合格が発表され、二次試験の勉強にも力が入り始めました。
このころの過去問演習スタイルは以下のような感じで、甘めのふぞろい採点で50点くらいでした。
・事例I~IIIは過去問(毎日1事例)、事例IVは全知全ノウ(土日とか)
・文章の接続や字数の多少のずれは許容し、キーワードを盛り込むことに注力
・早く勉強を終わらせたかったので、65分くらいで解答
9月中旬:与件重視の解答を意識、知識のインプットを強化
過去問の解答に与件文からの抜き出しが多いことに改めて気づき、与件文のキーワードを細かくチェックすることを意識するようになりました。
また、知識のインプット不足に気づき、ダンシ君のサブノートで知識のインプットを始めました。
9月下旬:10年データブックの活用
直近で初見の過去問が3年分くらいまで減ってしまったので、10年データブックに着手。
与件の抜き取り漏れの対策として、一問一答のような形で、短時間で与件を読み、キーワードを抜き出す練習を始めました。
石垣島にスキューバダイビングに行き、台風が接近中のシケた海の中でマンタに出会う。(HNの由来)
もちろん旅行中も、時間があれば過去問に触れていました。
10月上旬:事例IV過去問着手、初見の過去問での演習を開始
全知全ノウをほぼ1周し、事例IVも通しで過去問を解くようになりました。
事例I~IIIでは、与件のキーワードはほぼすべて抜き出せるようになるが、設問とキーワードの対応が不十分でした。
設問解釈の重要性に気づき、設問で聞かれたことに素直に答えるように意識するようになりました。
10月中旬:文章の改善、字数を合わせた答案作成
過去問演習で点数が伸びなくなってきたため、内容面ではなく文章のつながりや読みやすさを改善したり、本番を意識して、効率よく字数をカウントしながら答案を書く練習をしました。
何故その学習方法を選んだのか?
【一次試験】
理由①:安価で始められるものだったから。
理由➁:厚いテキストだと途中で挫折するかもしれないと思ったから。
理由③:インプットは少なくして、問題集や過去問の演習に力を入れるため。
【二次試験】
理由①:塾は解答のレベルが高すぎるというレビューを書いている方がいらっしゃったので、自分の文章で解答を書くことをゴールに考えると、適していないと感じたから。
理由②:明確に回答が示されていない以上、過去問に頼ることを最重要と判断し、過去問の分析に特化したふぞろいシリーズの演習が最適な学習法であると思ったから。(時間があれば勉強会には参加したかったが、自分で演習する時間を優先した結果、道場の夏セミナー以外は全く参加できず。)
学習時・受験時のエピソードおよびこれから合格を目指す方へのアドバイス
【試験勉強の計画】
中小企業診断士試験の勉強をする中で、私はあまりできていませんでしたので、反面教師的な話題になりますが、試験までの計画をしっかり立てておくことが重要だと感じました。というのも、私の実体験として、一次試験を4か月で合格するよりも、二次試験を3か月で合格する方がはるかに難しいと感じたからです。
日常的に文章を書いたり、難しい内容を短文に要約したりすることに慣れてる方は当てはまらないかもしれませんが、二次試験対策の3か月は非常に短い期間です。また、一次試験合格の権利は翌年度までしか持ち越せないため、たった2回のチャンスのうち1回を勉強不足で迎えてしまうのは非常にもったいないことです。長期戦で一次試験を受けられる予定の方は、ぜひ一次試験の受験前から二次試験の対策をしておいていただきたいなと思います。また、短期決戦で試験に望まれる方も、一次試験合格ラインが見えてきた段階で、二次試験の勉強にも少し触れておいていただきたいなと思います。そうすれば、きっと二次試験合格の確率も上がっていくだろうと思います。
【試験勉強のモチベーション維持】
中小企業診断士の試験勉強は、一般的に数百時間以上を要する長期戦です。365日毎日モチベーションを高く保っておく必要はないですが、ある程度継続的に勉強を続けることは必須ですので、そのためのモチベーションを維持することは非常に重要です。
私の場合、一次試験では、勉強期間が短かったこともあり、マンネリ化や中だるみといったものは、ほぼありませんでした。知識をインプットする時期には、ほぼ常に新しい知識に触れ続けていたことで、知的好奇心が刺激されていたように感じます。また、過去問演習の時期は、勉強の成果が得点という形で数値として分かるので、合格まで近づいて行っているということが明確にわかります。私の場合は勉強期間が短かったことで、結果的にモチベーションを維持ししやすかったのかもしれません。モチベーションの維持方法は人によって様々であると思いますが、もし、一次試験の勉強中にマンネリを感じたような場合は、前項の内容にも関係しますが、一時的に二次試験対策に手を付けてみるといった方法も有効かもしれません。
一方、二次試験では、せっかく一次試験に合格したのだからなんとかして二次試験も合格したい、といったプレッシャーのようなものを感じつつ勉強していました。しかし、勉強をしても前に進んでいる実感が得られず、何をすれば試験の得点に結びつくのか暗闇を手探りで探しているような状態でした。正直なところ、今でもあまり合格した実感がありません。ただ、なんとかして合格したいというおもいだけは維持し続けていたので、少しでも合格に近づくことができないのではないかと思っています。また、二次試験対策の中で、「ふぞろい」シリーズを使用した過去問演習では、ある程度得点が数値で可視化されるので、多少なりともモチベーションの維持につながっていたと感じています。
そのほか、適度なリフレッシュをしたことも、結果的に勉強のモチベーション維持につながり、集中して試験勉強に取り組むことができたのではないかと思います。趣味を我慢してしまうことよりも、ある程度割り切って楽しんでしまうというのも有効だったかなと思っています。超短期間で試験に臨まれる方は別だと思いますが、ある程度の余裕を持った勉強をしておられる方は、あまりプレッシャーをかけすぎず、オン/オフ切り替えて勉強に取り組まれるのもいいのではないかと思います。
おわりに
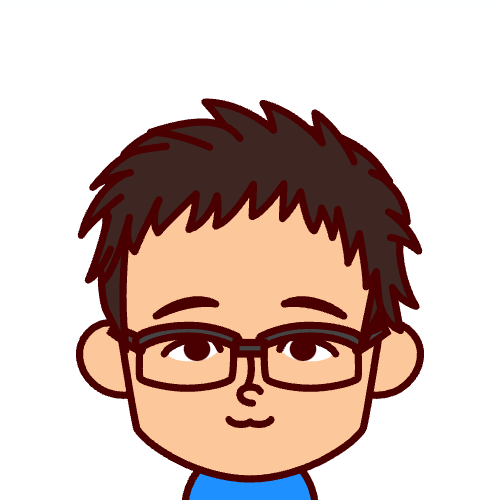
息抜きを忘れずにオンオフのメリハリをつけ、効率よく一発合格されたまんたさん。
9月下旬という絶妙に疲れるタイミングでのスキューバダイビングはとてもリフレッシュできそうです。
「計画立てが重要」という実体験からのアドバイスもありがとうございます!
まんたさんが診断士の知識を活かして、より会社の経営に貢献されることをお祈りしています!
コメントについて
記事へのご感想やご要望があれば、下部の入力フォームから是非コメントをお寄せください!
執筆メンバーの励みになりますので、よろしくお願いいたします。
※コメント送信後、サイトへ即時反映はされません。反映まで数日要することもあります。
※コメントの内容によっては反映を見送る場合がございますので、予めご了承ください。
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)

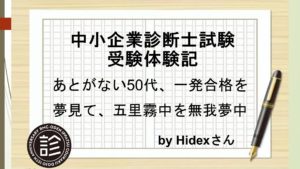
-300x169.jpg)