勉強の質を上げる勉強以外のこと 〜肩こり編 by 一蔵

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
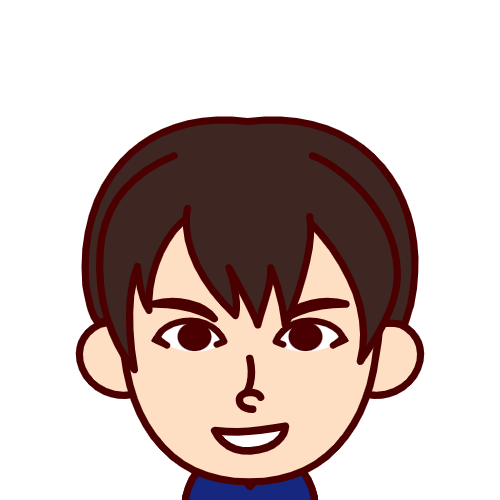
あけましておめでとうございます
みなさんこんにちは。一蔵です。
本年もどうぞよろしくお願いいたします🌈
2次試験終了後、「勉強の質を高める勉強以外のこと」をテーマとした記事を書かせてもらっていますが、今日は、「肩こり」に関する記事を書いていきたいと思います(健康経営ならぬ、「健康学習」の推進運動)。新年早々ではありますが、こういう時ほど平常運転が重要です。
- 1. はじめに
- 2. 肩こりはなぜ起こるのか
- 2.1. 長時間の同じ姿勢
- 2.2. 目の疲れ
- 2.3. ストレス
- 2.4. 運動不足
- 3. 肩こりの状態が勉強に与える影響
- 3.1. 集中力の低下
- 3.2. 記憶力の低下
- 3.3. やる気の減退
- 3.4. 睡眠の質の低下
- 4. 肩こりを解消するための有効な対策
- 4.1. 姿勢を改善する
- 4.2. 目の疲れを軽減する
- 4.3. 簡単なストレッチを取り入れる
- 4.4. 温めて血行を促進する
- 4.5. 適度な運動を取り入れる
- 4.6. マッサージや整体を利用する
- 4.7. ファイテンの「パワーテープ」を貼る
- 5. 勉強中にできる肩こり予防の工夫
- 5.1. スタンディングデスクを活用する
- 5.2. 照明を工夫する
- 6. おわりに
はじめに
肩こっていませんか?
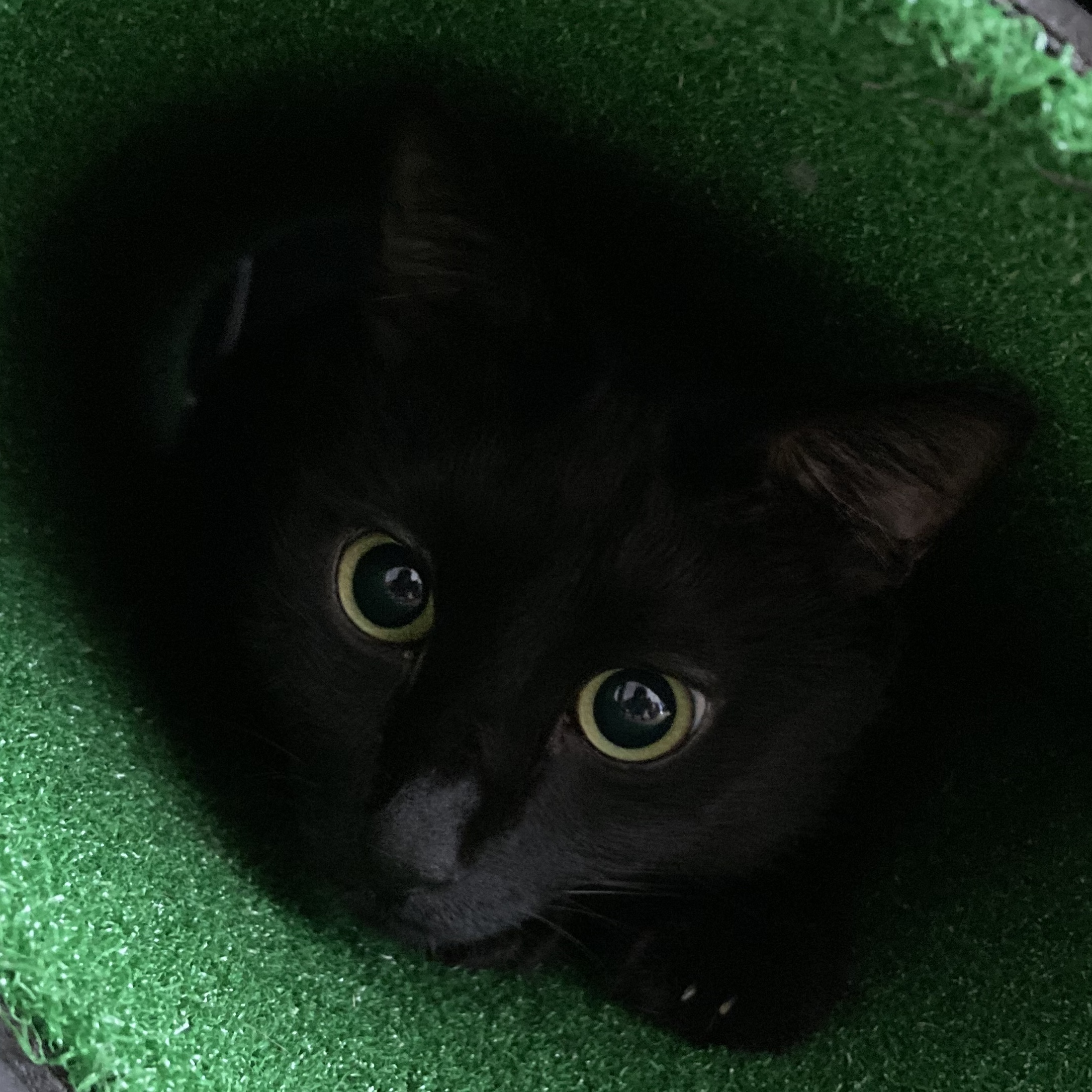
中小企業診断士試験はなかなかハードルの高い試験ですよね。
1,000時間程度の勉強時間が必要と言われていますので、長時間にわたる勉強は避けられず、体への負担が知らず知らずのうちに積み重なっていきます。
その中でも、特に多くの受験生が抱える悩みの一つが「肩こり」だと思います。
ぼくも慢性的な肩こり症ですが、受験勉強に勤しんでいた頃は、特にひどかったです。。。
今回の記事では、肩こりがなぜ起こるのか、肩こりが勉強に与える影響、そして肩こりを解消するための有効な対策についていろいろ調べてみたのでご紹介していきたいと思います。
肩こりはなぜ起こるのか
肩こりは筋肉が過剰に緊張して血流が悪くなることで起こります。
特に首から肩、背中にかけての筋肉が長時間にわたり収縮したままだと、酸素や栄養が十分に供給されず、老廃物がたまり、痛みや不快感が生じます。
肩こりが発生する主な原因には以下のようなものがあります。
長時間の同じ姿勢
勉強中、長時間同じ姿勢で机に向かっていると、首や肩の筋肉が緊張しやすくなります。
特に、前かがみになってパソコン画面や本を見続ける姿勢は肩こりを引き起こしやすいです。
目の疲れ
目の疲れは肩こりと密接に関係しています。
診断士試験の勉強では、本にしてもパソコンにしてたくさんの文章を読みこなしていく必要があるため、目に大きな負担がかかります。
目を酷使することで、周辺の筋肉が緊張し、肩や首に影響を及ぼします。
眼精疲労が気になる状態は、勉強の質を妨げますよね。
ぼくの場合、試験勉強を始めてから目薬を手放せなくなってしまいました。常に二種類の目薬を持ち歩いています。
ストレス
試験勉強のプレッシャーや不安からくる精神的なストレスも肩こりの原因になりますね。
ストレスを感じると筋肉が無意識に緊張することがあり、これが肩こりを引き起こす要因になります。
運動不足
勉強漬けの毎日では、体を動かす機会が減り、筋肉が硬くなりがちです。
特にデスクワークや座学が中心の生活では、肩周りの筋肉が凝り固まりやすくなります。
ぼくは基本的に365日(飲みの日以外)筋トレやランニングを欠かさないようにしていますが、診断士試験の勉強期間中は、運動よりも勉強の方にリソースを割いてしまっていたため、運動不足とまでいかなくとも頭や目を酷使する時間の方が多く、肩こりがひどくなっていたのを覚えています。
肩こりの状態が勉強に与える影響
肩こりは単に体の不調にとどまらず、勉強の質や効率に大きな影響を及ぼしますね。
具体的にどのような問題が生じるのかを見ていきたいと思います。
集中力の低下
肩こりがひどくなると、常に体に不快感を抱えることになり、集中力が低下します。
痛みやコリが気になると、目の前の勉強に集中できず、効率が落ちてしまいます。
記憶力の低下
肩こりが悪化することで、脳への酸素供給が減少する可能性があります。
血行不良が続くと、脳の働きが鈍くなり、情報を記憶する力が低下することがあるそうです。
これは試験勉強において致命的な影響を及ぼします。
やる気の減退
慢性的な肩こりは、勉強に対するやる気やモチベーションを奪います。
「体がだるい」「つらい」と感じることで、勉強を後回しにしたくなることも多いでしょう。
睡眠の質の低下
肩こりによる筋肉の緊張が睡眠の妨げになることもあります。
十分な睡眠が取れないと疲労が抜けず、翌日の勉強にも悪影響を及ぼします。
慢性的な睡眠不足は思考力や集中力の低下につながります。
こうして、勉強の質への悪影響を押し並べてみると、肩こりをなんとなく受け入れてしまうのではなく、しっかりと対策を取ることが試験対策的に重要なことだと感じますよね。
肩こりを解消するための有効な対策
肩こりを放置しておくと、勉強効率が下がり、試験合格への道が遠のく可能性があります。
そこで、肩こりを予防・解消するための具体的な対策をご紹介しますね。
姿勢を改善する
正しい姿勢を保つことが、肩こり予防の基本になります。
座る際には、背筋を伸ばし、肩を自然に下げた姿勢を意識しましょう。
以下のポイントに気を付けると良いようです。
ポイント
- 椅子の高さ:足が床にしっかりとつく高さに調整する。
- 机との距離:肘が90度になる位置に配置する。
- パソコン画面:画面は目の高さに合わせ、首を前に突き出さないようにする。
猫背は良くないわね🐈⬛🐈

目の疲れを軽減する
目を休めることも肩こり対策として重要です。
1時間勉強したら10分程度休憩を取り、遠くの景色を見るようにすると良いそうです。
さらに、目の周りを温めると血行が良くなり、目の疲れが和らぎます。
簡単なストレッチを取り入れる
勉強の合間に肩や首をほぐす簡単なストレッチを行うのも有効のようです。
以下のようなストレッチがおすすめされています。
ストレッチ
- 首のストレッチ:首をゆっくりと左右に倒して筋肉を伸ばす。
- 肩甲骨のストレッチ:肩を前後に回し、肩甲骨を動かす。
- 背伸び運動:両手を上に伸ばして背筋を伸ばすことで、全身の血行が良くなります。
温めて血行を促進する
肩や首を温めることで血行を改善し、筋肉の緊張をほぐす効果があります。
蒸しタオルや温熱シートを使って肩周りを温めると効果的だそうです。ぼくは、以前からあずきを使った肩を温めるやつを使っています。電子レンジで温めてから肩に置くと、じわーっと肩が温まって血行が良くなっていくのを感じます。
入浴も肩こり改善に役立つので、ぬるめのお湯にゆっくり浸かって体をリラックスさせましょう。
適度な運動を取り入れる
肩こりを予防するには、定期的な運動も重要です。
軽いウォーキングやジョギング、ヨガなどを取り入れると、体全体の血行が良くなり、肩こりが軽減されます。
特に、肩周りの筋肉を意識して動かす運動は効果的です。
(最近、運動を推奨してばかりいる気がする。。。)
マッサージや整体を利用する
肩こりがひどい場合は、プロの施術を受けるのも一つの方法でしょう。
整体やマッサージで凝り固まった筋肉をほぐしてもらうことで、劇的に肩こりが改善することもあるようです。
ただし、施術後も正しい姿勢を心がけ、再発を防ぐ努力が必要です。
(ぼくは、しょっちゅうカミさまの肩やら足裏やらふくらはぎやらをマッサージさせられ…、させていただいています。これも筋トレだと思って、必死でさせていただいています。「気持ちいい」とか、「もう少し強く」とか、一切コメントがないので大変やり甲斐を感じています。)
ファイテンの「パワーテープ」を貼る

実は、個人的に最も効果的なのがファイテンの「パワーテープ」を貼ることです。
皆さん、パワーテープご存知でしょうか?箱根駅伝とかみていると、学生たちが肩やふくらはぎ、太ももにたくさん貼っているのをみたことがあるのではないでしょうか。
ぼくも走るようになってからお世話になっているのですが、パワーテープを貼ると驚くほど肩こりが消えて無くなります。
70枚入りで500円程度、しかも数日効果が続きます(個人の感想)ので、費用対効果バリ高です。
勉強中にできる肩こり予防の工夫
肩こりを防ぐために、勉強する際のちょっとした工夫も効果的です。
スタンディングデスクを活用する
長時間座り続けることが肩こりの原因であるなら、時おりスタンディングデスクを利用して勉強するのも良いそうです。
立ちながら作業することで、筋肉の緊張が和らぎ、姿勢が改善されることがあります。
ぼくはスタンディングデスクは持っていませんが、机でやったり立ってみたり、時にはゴロゴロしながら、あらゆる姿勢を取っています(睡眠中の寝返りが非常に重要なのと同じですねw)。
照明を工夫する
照明が暗いと目が疲れやすくなり、肩こりが悪化することがあります。
十分な明るさを確保し、机の高さや椅子の座り心地を見直して、負担を軽減するようにしましょう。
おわりに

ここまでお読みいただきありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。
繰り返しになりますが、肩こりは試験勉強にとって、集中力や記憶力、やる気に悪影響を及ぼす要因となります。
長時間の勉強に取り組む際は、正しい姿勢を意識し、定期的にストレッチを行うことが重要です。
さらに、目を休めたり、体を温めたりして、肩こりを予防・解消する工夫を凝らしましょう。
肩こりの症状を軽減することで、勉強により集中でき、試験対策も効果的に進められるはずです。
肩こりに負けず、自分に合った対策を見つけて、勉強の質を高めていきましょう!

明日はかます博士です!
新年も(ストイックに)頑張りましょう♪

☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)



こんにちは!
にっくです。
肩こりの記事、ありがとうございました!
大きな目標ほど平常運転、大事ですね!
僕も勉強してないとなんだか気持ち悪くなってやるようになってきました笑(へんt・・・!)
年末年始、気を抜きがちですが、100%抜いてしまうと後で戻すのが大変になるので、60%ぐらい抜いて、やっていこうと思います。
ありがとうございました!
にっく
にっくさん、コメントありがとうございます。
勉強していないと気持ちが悪くなる・・・すごい境地に入りましたね。
目的を持って、バランスを保って、継続していきたいですね!