2次ベテの2次試験得点戦略 by サトシ
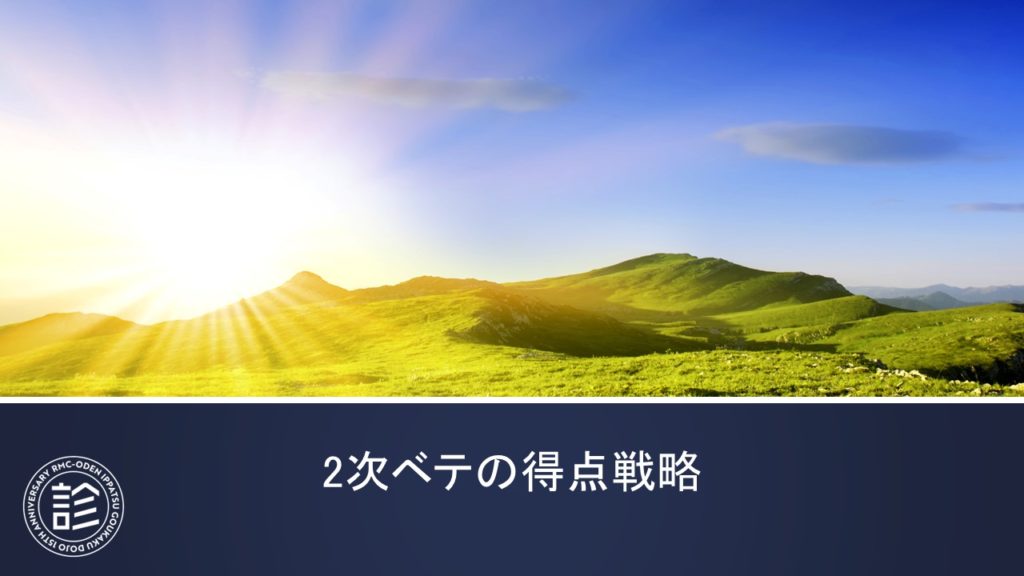
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
一発合格道場ブログを
あなたのPC・スマホの
「お気に入り」「ブックマーク」に
ご登録ください!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
みなさん、こんにちは。中1日で「サトシ」です。またお前かよ!と思わないでくださいね(笑)
今回は「2次ベテの2次試験得点戦略」として、2次試験の目標点を取るための要件と各事例の目標点数について説明していきます。
ちなみに、前回の1次試験の得点戦略の際は「2次ベテ・上級生」と「ストレート生」で目標点数を分けていましたが、今回は全員同じ目標点数にしています。
それでは、今回もよろしくお願いします。
安定感スタイル vs 特定の1事例でホームランスタイル
2次ベテが合格する場合、「3事例が60点台で1事例が50点クラス」のパターン(安定感スタイル)か、「どれか1事例だけ80点クラスで他は50点台」というパターン(特定の1事例でホームランスタイル)になりやすいです。
ちなみに、ストレート生や上級1年目の方だと他にもパターンのバリエーションはあります。この2パターンにこだわる必要はありません。

サトシは事例Ⅲが49点だったから、安定感スタイルか。でも僕はホームランスタイルだったよ
●安定感スタイル…派手さはないが、合格率は高い
私.jpg) はこちらのパターン(67、65、49、62)。
はこちらのパターン(67、65、49、62)。
2次ベテ以外の道場メンバーだと、ばん がこちらのパターン(73、60、62、47)
がこちらのパターン(73、60、62、47)
●特定の1事例でホームランスタイル…ギャンブル性はあるが、当たれば派手に決まる
上で私の事例Ⅲの点数を指摘している彼 はこちらのパターン(58、56、76、54)。
はこちらのパターン(58、56、76、54)。
2次ベテ以外の道場メンバーだと、Maki とAZUKI
とAZUKI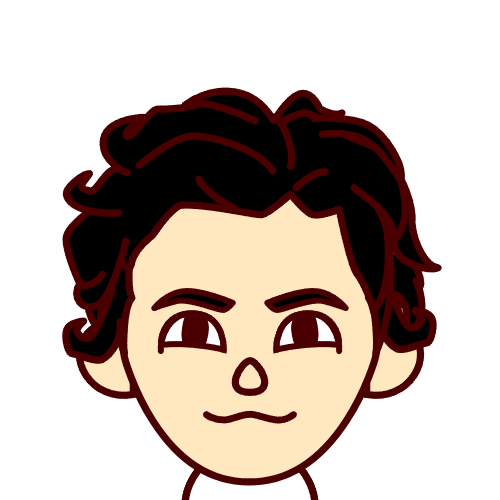 がこちらのパターン(事例Ⅲで超高得点で他3事例は50点台)
がこちらのパターン(事例Ⅲで超高得点で他3事例は50点台)
ホームランスタイルは80点クラスの事例の派手さはありますが、やはりリスクがありますし、他の受験生の出来や採点の相性など運の要素も絡んできます。
そう考えると、安定感スタイルのほうが安定性は高く、2次ベテが目指しやすいものとなっています。派手さは不要です。その代わり、安定感を高めていきましょう。2次ベテは豊富な経験がもたらす安定感が武器になります。
70点以上は取れなくても大丈夫です。60点台を3事例確保するイメージでいきましょう!

お前らは合格だけ目指せ。合格するだけでいいなら7割取る必要なんてない。6割でいいんだ。6割なら事故を起こさなければ十分取れる
.jpg)
事故を起こさなければ安定感が身につきます。そうなると派手さはなくても合格可能性は一気に高まりますよ!
事例Ⅰ~Ⅲの目標点を取るための要件
2次試験は事例Ⅰ~Ⅲと事例Ⅳで点数の取り方や目標点を取るための要件が異なります。まずは事例Ⅰ~Ⅲに関する内容を見ていきます。
事例Ⅰ〜Ⅲは、目標点を取るための要件が共通となっています。それが以下の4つです。この4つができれば、多くの受験生が解答している内容(=取るべきところ)を安定して取ることができるようになり、事例Ⅰ~Ⅲそれぞれの目標点数は十分に達成可能です。
事例Ⅰ~Ⅲ共通の要件
- 設問文の題意や制約条件に従うこと(指示に従うこと)
- 設問文に書かれているフレーズと同じ内容が書かれている(もしくは明らかにこの部分を使うとわかる)段落の与件根拠を使うこと
- 切り分けミスをしないこと(上の2つができていれば基本的にこれも満たす)
- 効果の部分に最適な知識フレーズを1〜2個入れること(乱発はNG)
なお、この4つについてはまた後の記事(7/11投稿予定です)で出てきます。その際は「取るべきところ」の4パターンとして紹介しようと思っていますが、そこでスムーズに4パターンを把握できるためにも、今の段階で上記の「事例Ⅰ~Ⅲ共通の要件」を押さえておきましょう。
事例Ⅰ:60点台後半〜70点
AAS東京が公開している再現答案を見てみると、事例Ⅰは90点近くの方もいるなど、最も点数を伸ばしやすい事例になっています。そのため、事例Ⅰは少し頑張って60点台後半から70点を目標にしましょう。
2次試験は基本的に「得意を伸ばす」より「苦手を改善する」の路線のほうが合格可能性が高まります。そして、事例Ⅰは事例Ⅱよりも点数が伸びやすいので、事例Ⅰに苦手意識があればそれをなくしていきましょう。
特に2次ベテの方は事例Ⅳの伸びしろはそれほどありません。そのため、事例Ⅳの点数を急激に高めることはできません。よって、「事例Ⅱ・Ⅳで稼いで事例Ⅰをカバーする」ではなく、「事例Ⅰで稼いで事例Ⅱ・Ⅳの借金を補う」のほうが2次ベテの方は合格しやすいです。
ストレート生や上級1年目の方にとっては、事例Ⅰは設問文も与件文も他の事例と比べると抽象的なものになっているため、事例Ⅰに対する苦手意識があるかもしれません。ですが、慣れれば要領がつかめてきますので、ストレート生も「事例Ⅰは取っつきにくいから後回し」と判断せず、むしろ積極的に事例Ⅰの対策をしていきましょう。
確かに、事例Ⅰって妙に点数が高くなるんだよな
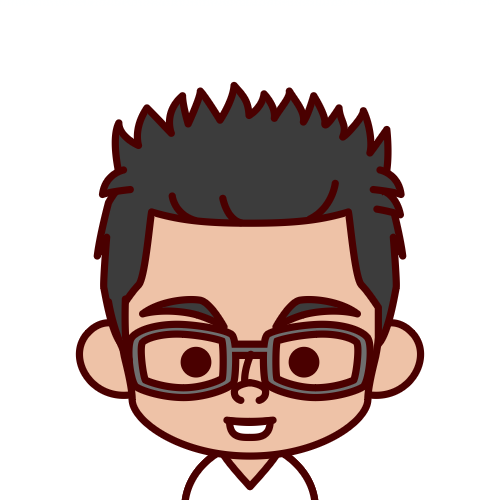
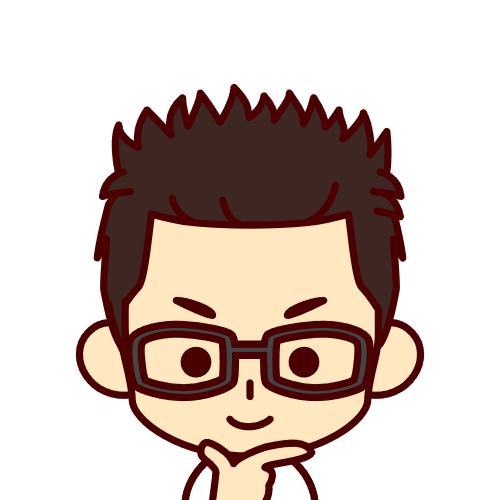
この人、似てるなぁ
事例Ⅱ:60点台前半
事例Ⅱは再現答案を見ても80点くらいが限界で、ほとんどの方が60点台前半くらいに落ち着きやすいです。そのため、60点台前半を目標にしましょう。これなら令和5年度ならサブスクを書けなくても達成可能です。
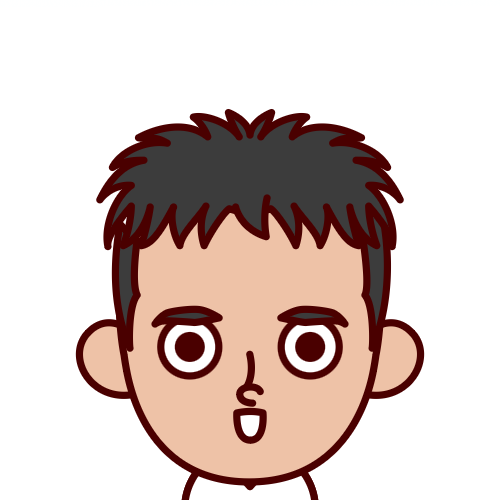
ちなみに、令和5年度合格者は「サブスク世代」と言われているらしい

そらそうよ。お~ん
事例Ⅱの点数が伸びにくい理由
事例Ⅱの点数があまり伸びず60点台前半くらいに落ち着きやすいのには理由があります。
事例Ⅱは設問文・与件文ともに4事例の中で最も具体的に書かれている上に、業種も身近で与件文の内容のイメージもしやすくなっているため、実力のない人がたまたま事例企業や設問内容、与件文の内容との相性が合って、解答内容がたまたまクリティカルヒットしてしまう可能性があります。
それだと運任せの要因での合格者を出してしまうため、公平性の求められる国家試験としては問題があります。そのため、事例Ⅱで超高得点(いわゆる事例Ⅱチート)を出さないように点数を抑えています(もちろん、あくまで個人の意見です)。
よって、事例Ⅱで点数を稼ぎにいく路線は失敗する可能性が高いです(事例Ⅳの計算でパーフェクトを狙いにいくくらい無謀です)。事例Ⅱは具体的に書いてあって取り組みやすい事例のように思えますが、意外と点数は伸びないと思っておきましょう。
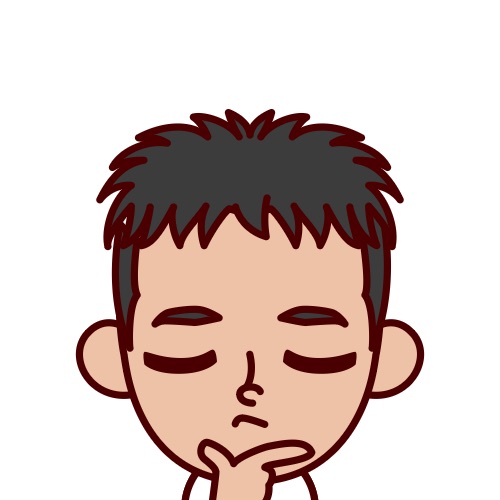
予想では75点くらいだと思っていたら実際は65点だった
こういうことが事例Ⅱではよくあります(事例Ⅰだとこの逆です)。
事例Ⅲ:60点台前半
事例Ⅲも再現答案を見ると80点くらいが限界で、多くの受験生にとっては60点台(簡単なときも70点台前半)が現実的な点数となっているため、事例Ⅱと同じく60点台前半を目標にしておくのが無難です。そして、蓋を開けてみたら実際は60点台後半が取れたということが多いです。
事例Ⅲは、簡単な年だと問題点や改善策がハッキリとわかり、切り分けミスさえ起こさなければ誰でも高品質の解答が書けます。しかし、みんな高品質の解答を書くので意外と点数は高くなりません。最大でも75~80点くらいです。逆に切り分けミスをしたら一気に大減点となり、それだけで40点台は覚悟しないといけなくなります。
逆に令和5年度のように難しい年だと、問題点や改善策がわかりにくく設計されています。切り分けミスも大量に起こしています。この場合、ある程度の点数幅に収まるように得点調整がされます。その「ある程度の点数幅」が45~75点です。余程のまずい解答なら45点以下、余程の高品質の解答なら75点以上(80点くらい)になりますが、それぞれ数%ほどの人しかいません。
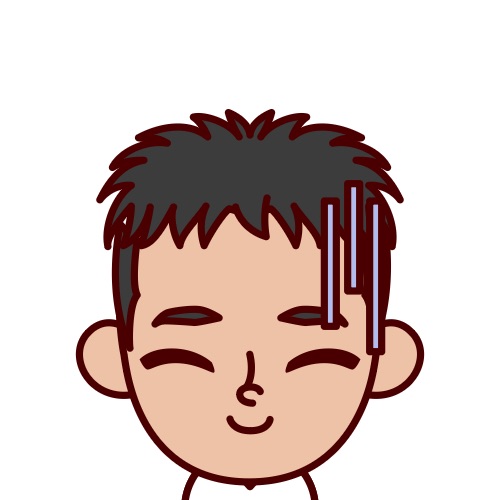
事例Ⅲは問題との相性が80分のプロセスや解答に大きく左右する事例です
事例Ⅳの目標点を取るための要件
そして、事例Ⅳの点数の取り方や目標点を取るための要件は事例Ⅰ~Ⅲとは異なります。
ここで、事例Ⅳ対策として3つのストラテジーを紹介します。この3つのストラテジーを実践できることが、事例Ⅳで目標点を取るための要件となります。なお、「2次ベテ」と書いてありますが、1つ目と2つ目のストラテジーはストレート生や上級1年目の方にも当てはまるものとなります。

この3つのストラテジーは破壊力抜群ですよ。すべてが会心の一撃レベルです
ストラテジー 21
2次ベテ勝利のストラテジー 21
事例Ⅳで超高得点を取りに行くやり方だと、計算問題がすべて合わないといけないプレッシャーがかかってしまい、メンタル面に不安のある2次ベテには厳しいです。そのため、事例Ⅳは55~60点でもいいと割り切りましょう!
事例Ⅳで55~60点なら、経営分析と最後の記述問題と基本レベルの問題だけで達成可能です。しかも、この中で1つ間違えても達成できます。
解説
こちらは多くの予備校の指導方針とは正反対になります。多くの予備校は「事例Ⅳ対策を中心に行い、事例Ⅳで70点以上の超高得点を取りに行く」という指導をされていますが、これは基本的にまだまだ伸びる余地の大きいストレート生や上級1年目の方に向けた指導になっていて、伸びる余地がそれほどない2次ベテの方は想定していません。
2次ベテの方は、事例Ⅳ対策はほどほどにしましょう。おそらく、2次ベテの方ならこれまで計算問題集を10周くらいしてきたでしょう。しかし、そこで1周増やして11周にしても点数は変わりません。費用対効果(時間対効果)が悪いです。2次ベテの方は、事例Ⅳ対策に注ぐ時間の一部を事例Ⅰ~Ⅲ対策に回しましょう。
ストレート生や上級1年目の方は事例Ⅳの伸びしろがまだまだあります。もちろん、予備校の指導に従って事例Ⅳの対策をすればするほど点数は上がります。そのため、事例Ⅳ対策を中心にやっていくのはOKです。しかし、事例Ⅳで一発逆転満塁ホームランのような超高得点を取ることは想定に入れるのはやめましょう。「事例Ⅳで80点を取れる」という考えは捨てましょう。あの公認会計士のせーでんきですら事例Ⅳは71点です。

いや、意思決定の問題とかは会計士でも無理
事例Ⅳは55~60点でもいいと割り切ってしまいましょう。これならハードルは低いです。難しい計算問題は全くできなくても大丈夫です。そういう想定で事例Ⅳを解いていくと、実際蓋を開けてみたら60点台になりやすいです。
逆に事例Ⅳで超高得点を取りに行くやり方だと、計算問題がすべて合わないといけないプレッシャーがかかってしまい、頭が働かなくなります。しかも、事例Ⅳはすでに3事例終わって頭が疲れている状態で受けるため、プレッシャーと疲労から単位ミスや端数処理ミス、電卓操作ミス、問題設定の誤認識、計算方法の勘違いなど、何かしらのミスを連発します。これは私が通っていたTAC名古屋校の津田先生(まどか先生)もよく言っていました。また、2次ベテのみなさんなら「本試験でミスなくパーフェクトでいけたことはない」というのは経験則でわかると思います。
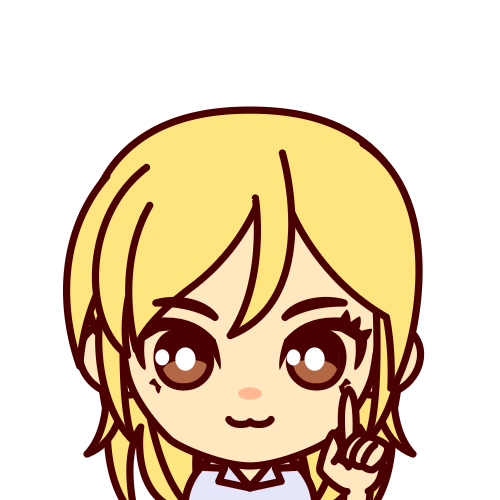
事例Ⅳは必ずどこかでミスをする。こう思っておいてちょうどいいよ
結果として、超高得点のホームラン狙いでいくとかえって点数が下がってしまいます。実際の野球でも、ホームラン狙いで打席に入るとかえってホームランを打てないですよね。それと同じです。
ストラテジー 22
2次ベテ勝利のストラテジー 22
投資の意思決定など難しい問題は一切できなくていいですし、取り組む必要すらありません。そういう難しい問題にかける時間で、確実に解ける問題の問題設定の理解や検算を厚めに行いましょう!
解説
このように指導している予備校は少ないですが、これが事例Ⅳで確実に目標点数(55点以上)を取るための方法です(2次ベテの方もストレート生も上級1年目の方も同じです)。
55~60点なら経営分析と最後の記述問題と基本レベルの問題(令和5年度ならCVP分析と貢献利益の問題)だけで達成可能です。また、投資の意思決定など難しい問題は一切スルーできます。
そういう難しい問題にかける時間で、ここまで解いた問題の検算や、解く前の問題設定の理解を厚めに行いましょう。ここがこのストラテジーのポイントです!
.png)
難しい問題は最初から手を付けない。それにかける時間を検算や理解に使おう!
そのほうがプレッシャーになりにくく、結果として力を存分に発揮できます。精神的に余裕が出てくるため、ミスの余地にも気づきやすいことから、ミスによる失点も防ぎやすくなります。
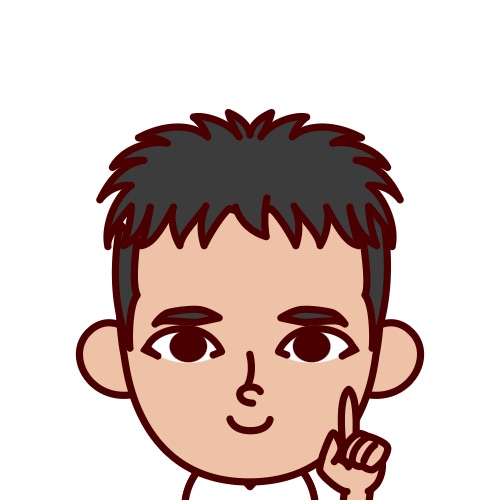
最後20分は新しく問題を解きにいかない。こう決めちゃうのもオススメだよ
ストラテジー 23
2次ベテ勝利のストラテジー 23
2次ベテは伸び代が少ないのが現状です。そのため、「できないことをできるようにする」という方針よりも、「今できることの安定感を高める」という方針にシフトさせましょう!
解説
これは2次ベテの方限定の内容になります。2次ベテの方にとっての「代替手段=加点要素の数と安定感」の1つである安定感は、事例Ⅳでも重要になってきます。
以前の記事でも言いましたが、2次ベテの方は伸び代が少ないということが特徴であるため、実力の伸びはそこまで考えないほうがいいです。
経済学の生産関数のイメージしたね。「勉強時間」という生産要素を投入しても、「実力の伸び」という生産量や限界生産物が徐々に低下(収穫逓減)していきます。
しかし、上記のストラテジーの内容など発想の転換をすることで、技術革新の非連続性のグラフで言う次のS字にジャンプし、点数が伸びていき安定感も高まります。
事例Ⅳは発想の転換が大事です。ここから難しい問題集(イ●カコや簿記1級の問題集など)をやって投資の意思決定の問題など難しい問題が解けるようになることは期待しないほうがいいです。それよりも、基本問題や難易度の低い論点(CVPやCF計算書など)の安定感を高めることを重視しましょう。
2次ベテは計算問題集や過去問、演習などで事例Ⅳの計算問題をかなり多く解いてきたことが特徴にあります。そのため、基本レベルの問題や難易度の低い論点の問題を解ける力は十分についているはずです。
また、ミスを引き起こすパターン(単位や端数処理など)もご自身なりに蓄積しているはずです。そこで、ミスを引き起こす部分に反応できるアンテナを確立し、基本問題や難易度の低い論点の問題を確実に解けることを重視して事例Ⅳ対策をしていきましょう!
診断士の試験勉強の楽しさ?
2次ベテの方の特徴として、診断士試験の面白さや問題の作り方などにこだわってしまうところがあります。私もそうでした。どこかのタイミングで変な楽しさに目覚めてしまうんですよね。
これは合格者や予備校の講師がどこかのタイミングで「勉強は楽しんでやりましょう」とか「実力がつくと勉強が楽しくなっている」などと言ってくるため、「合格するにはそれがないといけない。だから楽しさがわかるまでは実力を鍛え続けないといけない」と思ってしまうことが要因にあります。
短期間で合格されたいなら(=2次ベテになりたくないなら)、受かる人の考え方や試験の攻略法だけに集中しましょう。ここで変に他の内容を入れようとするから2次ベテになってしまうのです。1次についても、短期間で合格されている方は7科目バランス良く勉強しています。逆に特定の科目の勉強ばかりしている人はベテになりやすいです。
事例Ⅳ:50点台後半
事例Ⅳの目標点数は50点台後半としましょう。ただし、事例Ⅳも蓋を開けてみたら実際は60点台になりやすいです。
これはあくまで私の経験則による感覚ですが、上記の3つのストラテジー(ストレート生や上級1年目の方だと2つのストラテジー)ができると、55~60点なら90%くらいの確率で取れます。60~65点でも70~80%くらいの確率で取れます。
但し、どうしても事例Ⅳが苦手で数字を見ると吐き気がするくらいの人は、上記の点数から5点レンジを下げましょう。つまり、50~55点なら90%、55~60点なら70~80%の確率で取れる形です。
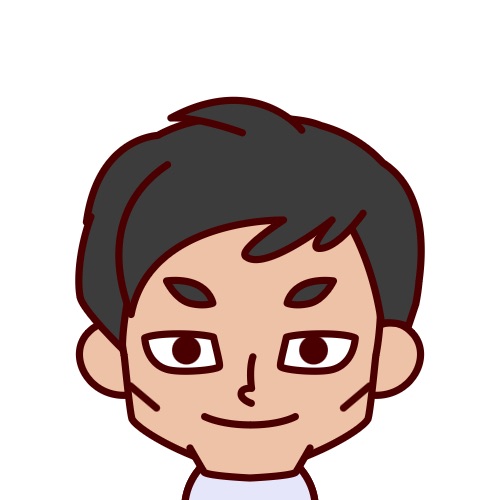
え、でもこんなに低い点数だと事例Ⅰ~Ⅲをカバーできないかも・・・
ストレート生や上級1年目の方だと、事例Ⅳ対策に多くの時間と労力を使うため、55点を目標点数にしていたら気持ち悪いかもしれません。そのため、60点以上を目標点にしてもOKです。但し、どんなに高くても70点くらいまでにしましょう。逆にストレート生や上級1年目の方でも、事例ⅠやⅢは(本人的には全く内容がわからなかったとしても)点数が伸びて65点や70点を取れています。
事例Ⅳは確かに計算問題が合えば90点近くを取ることも可能です。しかし、実際に70点以上を取っている方は意外に少なく、いてもせーでんきのような公認会計士や税理士、日商簿記1級保有者など元から会計力の高い人です。
一発逆転満塁ホームランで80点や90点を取りに行く手もありますが、それの実現率は5%くらいです。「60~65点で派手さはないけど70~80%くらいの確率で取れる」ほうにするか、「超高得点を取れるけど確率は5%」というほうにするか、確実に合格したいならどちらを選びますか?
そう!前者のほうですよね.jpg)
まとめ
ここまで見てきた点数を合計すると、4事例合計で250〜255点くらいになり、10〜15点の貯金をもてます。そうなると1次試験と同じく余裕をもって合格できます。また、(これは次回見ていくことになりますが)国語力のハンデがある人でも安定的に合格できます。
では最後にまとめとして、4事例の目標得点を提示します。
2次ベテの得点戦略
事例Ⅰ:60点台後半〜70点
事例Ⅱ:60点台前半
事例Ⅲ:60点台前半
事例Ⅳ:50点台後半
合計:250〜255点
各事例の点数は多少のミスを想定したものになっています。
蓋を開けてみてからの加点分(事例Ⅲ・Ⅳで5点ずつ)も考慮すると、私の事例Ⅲのように予備校の採点サービスの結果に対して実際の採点の相性が悪い方向(予備校の予想62点→実際49点)に作用しても相殺されるので、さらに安定して合格できます。
この目標点数は取るべきところさえ取れればいい。難しいところは取れなくていい。
事例Ⅰ~Ⅲは「共通の要件」にある4つができれば取るべきところは取れる。
事例Ⅳは発想の転換をして経営分析と最後の記述問題と基本レベルの問題だけでいい。
さらに、蓋を開けてみたらもう少し点数が高くなる。
いかがでしょうか?これならそこまでハードルは高くありません。いけそうな気がしてきませんか?
大丈夫です。みなさんならこの目標点数を取るためのノウハウはもっています。あとは実践あるのみです。頑張っていきましょう!
次回予告
ここまで、2次試験の各事例の目標点数について見ていきました。今回も私の記事にお付き合いいただき、ありがとうございました。
次回は、2次ベテの方に向けた国語力のことについてお伝えます。今のうちに言っておきますと、国語力のハンデがあっても合格できます。
では、次回もよろしくお願いします。
明日は、私の登板過多のことを心配してくれた心優しい「ごり」の登場です。
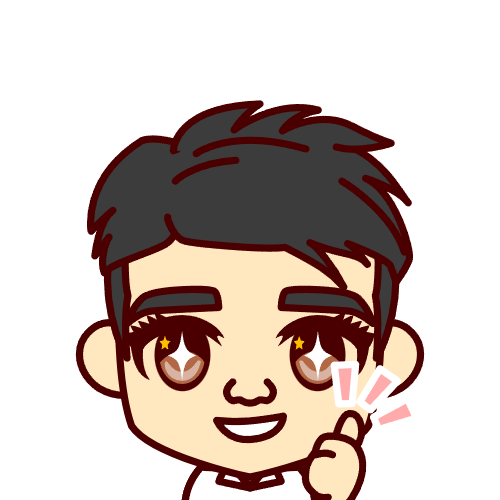
最強の勉強法をお伝えするよ
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)


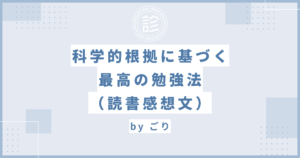
励ましのお言葉を頂きありがとうございます。
「新しい世界を創る」という言葉にぐっときました。
makiさんのような上司がいたら、もっと仕事が楽しい思えたと思います。
私の職場はやる気がある人が一人もいません。現状維持で自分のことしか考えてません。
仕事を教えてくれる人もロールモデルになる先輩もいません。
なので、診断士の勉強は業務を進める上でかなり役に立っています。
私はまだ努力することも、可能性を広げることも諦めたくないです。
志の高い方と一緒に仕事ができるように頑張ります!
引き続き宜しくお願い致します!!
もーりーさん
私の勤務先、私が入社した頃は、今で言うブラック企業でした。
(ブラックが標準な時代でした^^)
同期は1人辞め2人辞め、でも私自身は、上司と同僚に恵まれ、今は可愛い後輩達たくさんいて、
会社も、まだまだ途上ではありますが、諸々鋭意努力中です。^^
「強くなければ生きてはいけない、優しくなければ生きる資格がない」という有名な言葉がありますが、
会社も人も、強くならなければ、優しくなる段階に上がれないのかもしれないな、と思います。
会社を強くするのに必要なのが、今、まさに、もーりーさんが学ばれていることです。
1つも無駄になることはないので、ぜひ楽しんで知識を身に着けてください。
2次試験まで、まだまだ長期になりますので、気力と体力も落ちないように、
しっかり栄養を取って、運動&気晴らしに、散歩しながらの耳学も効果的ですよ。
夜はお風呂に入って、短くても質の高い睡眠を取ってくださいね。
おーちゃんが選んでくれた道場HPのエジソンの言葉のように、
継続することが合格への一番の近道です。
明日も、もーりーさんにとって、良い1日になりますように!
makiさん、サトシさん
先日の座談会では貴重なお話を頂き誠にありがとうございました。
合格までの道のりが険しいのにもかかわらず、ネット上で足の裏の米粒などと揶揄された記事を見て、報われなかったらどうしようと不安になることもありましたが、
お話を伺って、資格取得後の未来がとても楽しみになりました。
高卒の凡人ですが、皆さんのような優秀な方々といつかお仕事させていただける日を夢見て頑張りたいと思います。
もーりーさん、コメントありがとうございます。また、先日の座談会のご参加、ありがとうございました。
私の話がもーりーさんのお役に立てて良かったです。
揶揄された記事は1ミリも気にしなくて大丈夫です。我々15代目メンバーも「足の裏の・・」というのは聞いていますが、実際にそのとおりになって苦労しているメンバーは1人もいません。
また、私もここ数日、仕事の案件が急に何件も舞い込んできていて、ある意味(?)引っ張りだこです。
私の知り合いも、依頼を無計画に受けすぎて混乱しているくらいです(なので日程計画・進捗管理をしっかりしたいと言っていました)。
だから大丈夫です!診断士に合格したらすごく明るい未来が待っています。
頑張っていきましょう!
合格するまで絶対諦めません!
職場で昼休みに勉強しているのですが、先輩に陰で、はやく諦めればいいのにと噂されていたり、周囲で辞めるのではないかと噂されていて居心地が悪く精神的に疲れていたのですが、サトシさんの情報で勇気が湧きました!
逆境をバネにがんばります!
引き継ぎ、診断士としてのご活動など情報を公開いただけると嬉しいです。
今後ともブログを拝見させて頂きます。宜しくお願いします。。
もーりーさん、その意気です!
強気と勇気をもっていきましょう!
私は合格まで何年もかかった超多年度生で、最後の年は職場の所長から「サトシ君、そろそろいい加減合格しようや」と嫌味を言われていました。私はその場は笑ってごまかしていましたが、精神的にはしんどかったです。
でも精神的にしんどいときこそ、受験仲間の方を向いて強気と勇気の姿勢を出していました。そして、仲間の存在と、強気と勇気の姿勢が最後のひと押しになり、2次試験に合格できました。
職場で嫌味や陰口を言われると精神的にきつくなりますよね。でも、今のもーりーさんなら強気と勇気の姿勢で跳ねのけられると思います。15代目メンバーという「仲間」もいます。大丈夫です。絶対に逆境をバネにしていけます。
以前Makiも言っていましたが、しんどくなったらいつでもこのコメント欄に書き込んでください。いつでも我々が対応しますし、応援メッセージも送りますよ。
大丈夫ですよ。もーりーさんはひとりじゃありません。応援してくれる「仲間」がいます。
頑張っていきましょう!
もーりーさん
こちらこそ、ご参加いただきありがとうございました。^^
私の会社にも高卒の素晴らしい先輩がいますよ。
足の裏の米粒の話は、どんな資格にも言えるのではないかと思います。
何事も自分次第。もーりーさんがこの資格に挑戦しようと思って、実際に行動を起こされていることが、
もう、それだけで素晴らしいと思います。だから、不安にならなくて大丈夫。
貴重な診断士の中でも、女性はさらに少ないです。
実際に、女性限定のご依頼もありますよ。
一緒に新しい世界の扉を開いて、新しい世界を創ってきましょう。
不安になったら、またいつでもコメントください。
引き続き応援しています!