【合格体験記】父の企業の支援目的に最効率で合格されたTomoさん

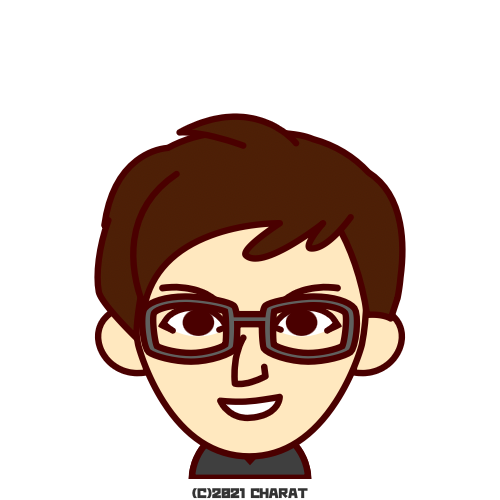
こんにちは。Ma.satoです。
本日2本目は、ご家族の企業支援を行うために体系的な知識を得るべく中小企業診断士を受験されたTomoさんです。
Tomoさんは、数多くある情報を取捨選択し、ご自身にとって最効率の勉強法を身につけた上で合格をもぎ取られました。
それでは、どうぞ!
========ここから========
受験生情報
ハンドルネーム:Tomo
年齢:20代
住まい:宮城県
職務経験:労務3年、海外営業7年、リサーチ1年、マーケティング2年
自分の診断士受験スタイルを一言で表すと
効率重視!
出来るだけ大変な思いはしたくなったので、独学で調べに調べまくってから望みました。
診断士に挑戦した理由・きっかけ
父が中小企業を経営しており、当時は会社が思わしくない状況でした。
そのため、当時勤めていた仕事をやめ「父の会社を手伝いながら会社の立て直しが出来れば」と考えていました。
経営戦略やマーケティングなど大学で軽く触ってはいたので、何とかなると思っていましたが、(そもそも認識が甘いですね。。)いざ具体的に何をやるとなっても、何から手をつけていったらいいかさっぱり分からない状況でした。
そんな中で、職場の人から中小企業診断士を受けてみたらどうかと話をいただきました。
今まで本気で資格試験というものに臨んだことはありませんでした。
教科書を読んだときに、楽しそうと思えたので、実践的な理論を身に着けてから父の会社に貢献出来れば一石二鳥になると考え、実際に行動に移し始めました。
学習開始時の知識・保有資格、得意科目・不得意科目
保有資格
なし
(大学時代経済学部で、企業経営論・経済学・財務、に関しては他の人よりも予備知識があったため取り組みやすかった様に感じています。)
得意科目
①1次
得意:財務
②2次
得意:なし
不得意科目
①1次
不得意:暗記系全般
②2次
不得意:なし
学習スタイルとそのメリット・デメリット
学習スタイル
独学
メリット
- 自由に自分のやりたいように勉強できる
- お金がかからない
- 常に自分に合った勉強方法を考えながら勉強を進めることが必要で、結果として生涯にわたって自分に最適な学習方法が見つけらる
デメリット
- 自分にあった勉強の指針を見つけるまでに時間がかかる
- モチベーションを維持するのが難しい
- きちんと前に進めているのかどうかをチェックする機会が与えられない
合格までの受験回数、学習時間とその作り方
受験回数
受験回数(1次 1回/2次 1回)
学習時間
1年
2021年5月から勉強を始めました。
一次試験は3か月、2次試験は1.5ヶ月(一次試験の合格発表まで何もしなかった)
<1次試験>
400時間
<2次試験>
150時間
学習時・受験時のエピソード及びこれから合格を目指す方へのアドバイス
最初から最後まで完全に独学だったので、同じ道を歩もうとしている方に向けて、重要なポイントをお伝えできればと思います。
一番大切なことは、「適切な方法で自分が継続できる努力の方法を見つけて頑張る」事です。
適切な方法と継続できる努力という観点で話していきたいと思います。
独学者はまずご自身で方法論を確立する必要があります。
私の場合は、youtube・Twitter・ブログ等、大体網羅したのではないかというくらい、読み漁りました。
大変です。
私が勉強方法の確立のために意識していた事は、「みんなが言っている事は大体正しい」です。
ネット上には色んな記事があり、色んな主張があります。
記事を読みすすめると、やがて「あれ、これ他の人も言ってたな」が出てきます。
この感覚が大切なんです。
「あれ、これ他の人も言ってたな」を拾い集めて自分の勉強ルールを定めていきました。
1次試験に関して、そのルールに従って頑張れば大体イケます。
あとは気合です。
2次試験はこれだけだと大体イケません。
2次試験の独学において難しい所は、
- 方法論が無限にあってどれが正しいのか分からない
- 自分がどれ位の立ち位置にいるかを認識する手段が少ない
ということです。
2次試験は1次試験よりも、独学で突破するのは苦行の道です。
私自身もう一度受けるとするならば、2次試験対策に関しては、独学よりも予備校にお金を払って受けます。
2次試験のことを詳しく話すともう1つくらい投稿出来る分量になりそうので、割愛します。
続いて努力の継続方法について話していきたいと思います。
ここでキーになる部分は、「自分がどういう環境では集中力を発揮し、どうなると集中力が切れるのかを、徹底的に分析する事」です。
成長度合いは、質×量で決まります。
質だけでなく量をどれだけ確保出来るのか、ということも大切な視点になります。
ご自身のいい部分も悪い部分も全部特徴です。それを全て踏まえた上で、
- どこで勉強するか
- どうやって勉強するか
に対する自分なりの最適解をいかに早い段階で見つけられるかも、方法論と同じくらい大切なことだと思っています。
私の場合は、家では無く、勉強スペースへ足を運び、短期集中型(30分やったら、5分休むを繰り返す)で行うことが集中力が一番持続することが分かりました。
ここは人によって違うし、早く見つけられた分だけ他の人からリードできると思います。
具体的な方法論は他の記事にも多かったので、こういう形で投稿させていただきました。
過去の記事を見て、正攻法を学ぶ。学習前にこの記事を読んでいるあなたは他の人より一歩抜きんでています!
その調子で合格まで突っ走ってください!皆さんに良い結果が訪れるよう、陰ながら応援しております!
過去の記事も含め非常に勉強させていただき、大変感謝しております。有難うございました。
========ここまで========
いかがでしたでしょうか。
Tomoさんは、ご自身に合った最適解の勉強方法を確立して合格をもぎ取られました。
勉強のモチベーションの管理や方法論について、エッセンスが詰まっている詰まっている受験体験記です!
これから中小企業診断士試験に臨む人は、ぜひ何度も読み返して受験対策を励んでみてはいかがでしょうか。
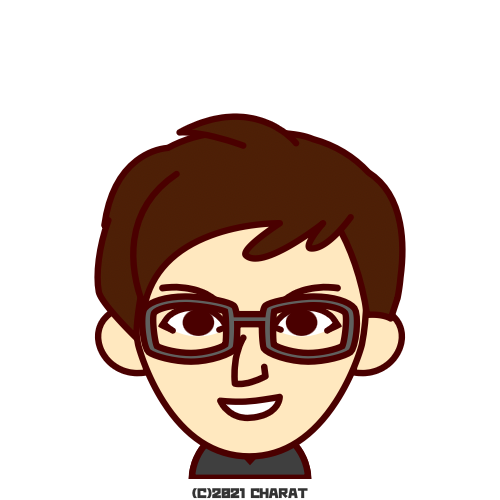
Tomoさん、合格おめでとうございます!
同じ宮城県の中小企業診断士としてこれからもよろしくお願いします。
Tomoさんのこれからのご活躍を心より祈念しております!
以上、Ma.satoでした。
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)


