「事例Ⅱ安定化マニュアル~+5点の思考法・目指せオールA」 by かます

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
一発合格道場ブログを
あなたのPC・スマホの
「お気に入り」「ブックマーク」に
ご登録ください!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
先日は「2次直前リアルセミナー」でお会いできて嬉しかったです。
来て頂いた方、ありがとうございました!
私も昨年の試験前のことを改めて思い出し、元気をもらいまして、記事で還元させて頂ければと思います。
引き続きよろしくお願いいたします!
はじめに
前回の「事例Ⅰ編」に続いて、「事例Ⅱ編」も解説させて頂きます!
事例Ⅱは得点差がつきづらく、掴みどころがないですよね。

事例Ⅱは問題数が少ない傾向にあるので、タイムマネジメントを油断しがち。
それゆえ設問毎の配点が大きいので、爆弾科目だと思っていました。
本番では「やらかしたかな~」と思いながらも63点でした。
(因みに令和5年試験といえばの○○○○世代、書けてないです)
それも、今回ご紹介する思考法が功を奏したところも大きいと思っています。
それでは、参考になるところが一つでもあればというところで、私流マニュアルをご紹介します。
2次試験合格に向けての心構え 7箇条(かます流)
前回もご紹介しましたが、まずは、こちらを念頭に!
事例Ⅱ総括~解答の方向性~
何を求められているのか、最終的に思ったところです。
コツを掴んだ(開眼?)したあとに、試験直前でまとめました。
事例Ⅱ、勢い、前に前に出る姿勢(ターゲットに訴求する姿勢)が大事だと思っています。
他の事例よりもテンション高めに、事例企業を盛り上げていくような姿勢で取り組んでいました!
余すことなく学習の軌跡と対策をご紹介出来たらと思いますので、一例として参考になりましたら幸いです。
メモの取り方
お馴染みな方も多いと思いますが、ダナドコ(誰に、何を、どうやって、その効果は?)の設問の頻度が高めです。
マーケティングの事例なので、施策を練らないと始まらないですよね。
4マスに「ダナドコ」を、当てはめていきます
制約条件多めの設問はチャンス!漏れの無いようにマスを埋めていきます
やたら設問文が長い問題などは設問自体に解答が書かれていたりすることも…
制約条件の多い設問
令和5年度 事例Ⅱ
第3問:メンバー増員のために協力することとなった。B社が取るべきプロモーションやイベントについて~
令和4年度 事例Ⅱ
第2問:X県から「地元事業者と協業し、第一次産業を再活性化させ、県の社会経済活動の促進に力を貸してほしい」という依頼を受け、B社の製造加工技術力を生かして新たな商品開発を行うことにした。商品コンセプトと販路を明確にして~
それを踏まえまして、メモは4マスのダナドコ、もしくは制約条件を書くことが多かったです。
(下記の実例は令和4年度の事例Ⅱ、本番3日前くらいにイメトレも兼ねてセルフ模試をやった時のものです)
マスに書いておくことで、抜け漏れを防ぎ、文章を組み立てていくのに役立ちました。
青の吹き出し部はⅠ~Ⅲ各事例共通、緑部は事例Ⅱならではのメモの書き方をしています。
(私は24折して枠を作っていますので、これを利用してこのような形になっています⇒詳細はこちらの記事で)

直筆令和4年度セルフ模試時のメモ&令和5年度の本番のメモ
与件文・設問文の読み方(事例Ⅱ)
続いては、与件文をどう読んでいたか、書き込みをしていたかについても解説します。
続いて、事例Ⅱ特有でやっていたこと、読む時に意識していた事です。
最終セルフ模試時の、令和4年度事例Ⅱの与件文・設問はこんな感じでマーク+走り書きをしていました。
経営資源が多めなので、解答に使えそうな表現を走り書きもしています。
令和5年度事例Ⅱの考え方はこちら!
要チェック① 長い設問文はヒントの宝庫
ここからは要チェック項目を抜粋してご紹介します。
長い設問文は制約条件が多い ⇒ その方向を示せという裏返し
令和5年度 事例Ⅱ 与件文で見る、長い設問文
第2問では、「低学年から野球を始めた子どもは、成長やより良い用品への願望によって、ユニフォーム、バット、グラブ、スパイクといった野球用品を何度か買い替えることになるため、金銭的負担を減らしたいという保護者のニーズが存在する。B社は、こうしたニーズにどのような販売方法で対応すべきか、プライシングの新しい流れを考慮して100字以内で助言せよ(ただし、割賦販売による取得は除く)。」とあります。
制約条件がガチガチです。
制約条件に色付けしてみました。
⇩開きます
「低学年から野球を始めた子どもは、成長やより良い用品への願望によって、ユニフォーム、バット、グラブ、スパイクといった野球用品を何度か買い替えることになるため、金銭的負担を減らしたいという保護者のニーズが存在する。B社は、こうしたニーズにどのような販売方法で対応すべきか、プライシングの新しい流れを考慮して100字以内で助言せよ(ただし、割賦販売による取得は除く)。
★制約条件が多すぎて、逆に解答を絞りだすのが大変なほどです。
ポイントをまとめてみます。
・金銭的負担軽減のニーズに応えらえれるものの提案がマスト
・プライシングの新しい流れに考慮した販売方法の記述が必要
設問文で解答の方向性、もはやそのまま使えるので、制約条件多めな設問は必ずヒントがある!
チャンスでもあります!
問題作成者も突拍子もない解答を書いてしまう事を阻止する、狙った解答を書いてもらえる様に、しっかり説明してくれているものと思います。
与件文のどこが引用できるかを紐づけながら、制約条件にすべて答えて外さない様にすれば大丈夫です!
要チェック② プロモーション施策の思考プロセス
双方向で!関係性強化!が1つポイント
解答の方向性を見ていきましょう!
要チェック③ 制約条件に注意「ダナドコも緩急つけながら」
ダナドコが基本!事例Ⅱを切り分ける上で欠かせないのがダナドコですね。
ただ解答を書くときには問われていることをしっかり答えることが必要です。
令和5年度 事例Ⅱ 設問で見る、問われ方
第4問では、「B社社長は、長期的売上げを高めるために、ホームページ、SNS、スマートフォンアプリ開発などによるオンライン・コミュニケーションを活用し、関係性の強化を図ろうと考えている。誰にどのような対応をとるべきか。」とのことです。
⇩開きます
問われているのは「誰に」「どのような」ですので、「何を」は聞かれていない点がポイント
私は「何を」が書きたかった、これはオンラインコミュニケーションの問題、そうそうHP、SNSと行きたかったのですが、もう答え書かれている、と一瞬焦りました。
「何を」を書きたくても問われているのは「誰に」「どのような」なので、これらに注力しなくてはなりません。
与件文にオンラインコミュニケーションに関するヒントは沢山ありますので、取りまとめて解答を書けばOK!
アイデアが湧き出てくる事例Ⅱの施策ですが、ここは抑えて、与件文と制約条件に沿って方向性を答えるのが吉。
制約条件に従いましょう!!
自分の経験上でも、これを意識して与件文と照らし合わせてしていけば良い解答も導きやすくなり、解答迷子も防ぎやすくなりました。
(明らかに必要無い時は入れませんでしたが、加点狙いで「効果」も最後に少し入れるのが自分流でした)
あと3週間ばかり、ラストスパートへ向けて
泣いても笑ってもあともう少し、辛くても楽しくてもあともう少しで今年の中小企業診断士2次試験は終わります。
当時の心境を振り返ると、今できる最大限のことをやろうともがいていました。
私は昨年の今ごろ、まだ解答の方向性が定まらない問題もあり、何度やっても上手く解答がまとまらない(加点要素が書けない)設問もありました。
与件文を読んでその問題だけ抜き出してやるなど、時短演習をやったりもしました。
上手く解答出来ない問題の傾向性を捉えることで、自分の苦手な部分と向き合ったりもしていました。
また、1週間前位の超直前になりますが、この記事でお土産として置いているファイナルペーパーも作りました。
事例Ⅰ~Ⅲの思考の方向性をまとめたものであり、自分の頭の中が整理され、スッキリさせることが出来ました。
(試験中の休憩時間はこれを見ながらチョコやラムネで栄養補給、あとは体力回復のために寝ていました。)
まだ暑い日も続きますが、朝晩の気温低下も出てくる時期かと思います。
大変な中と思いますが、体調万全に本番を迎えられることを祈っています✨健康第一!
本番エピソード(事例Ⅱ編)
本番も同じ様に解くことが出来ましたが、「プライシングの新しい流れ」と言われて与件文にヒントを見つけられず、解答をひねり出しました。思い浮かんだのは中古販売?レンタル?など、こんなもので良いのかと手が止まりました。
結果、設問が少ないからと時間ギリギリになって、第1問を5分位で終わらせ終了。(第1問は最後に解く派です)
個人的には、模試でも唯一得点が安定していた事例(高得点は取れませんが)だったので落としたくないところでしたが、出来た気がせず。
結果、事例ⅠもⅡもいまいち手応えがないままお昼休憩となりましたが、限られた時間の中で、自分の出せることは全て出し切れたという気持ちもあったので、淡々と過ごしていました。
ただ、今回ご紹介したことは問題を解くうえで念頭に置いて取り組み、目標は達成できました。
おみやげ(事例Ⅱの思考法)
私が直前に作ったFP(ファイナルペーパー的メモ)です。
解答の方向性を叩き込むために、試験1-2週間前に大事な視点を書きだしました。
本物は手書きで書いていましたが、今回はこちらを、Excelファイル&PDFにしてお届けします。
次回予告
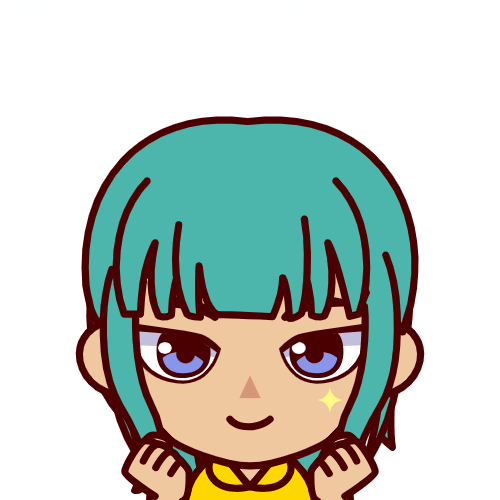
明日は、たいしんです!
10月5日(土)、6日(日)で開催した「『2次直前リアルセミナー』レポート」をお届けします!
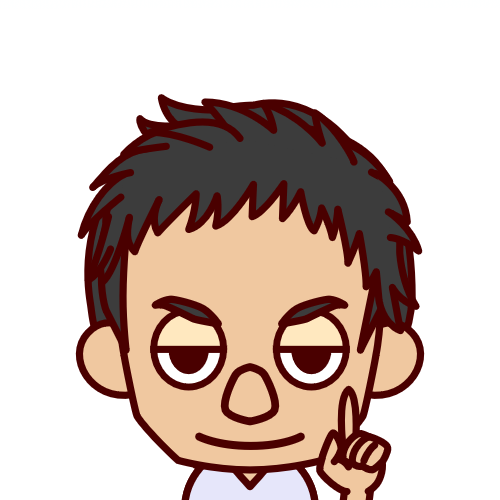
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)










こんばんは。
8/17の座談会に参加させていただきました。(同じディスカッションルームではなかったと記憶していますが)
独学なのでそろそろファイナルペーパーを制作しようかと思っていたところだったので、大変有難いです。おみやげのエクセルデータを自分なりに更新する形で活用しようと思います。
あと、メモ用紙を24分割するのは自分の中で革命的でした(笑) 早速マネしてみようと思います。
最後に質問ですが、大問1を最後に解答されていた理由を教えていただければです。大問2以降の解答の出発点になるような設問と思っていて、最後に解くという発想がなかったので、単純に気になりました。
ゆうまさん、コメントありがとうございます。
ぜひカスタマイズして頂いて、オリジナルのファイナルペーパーを作って頂けばと思います!
24分割メモですが、過去問演習をしていく中で閃いたもので、自分自身も革命的でした笑
(それまで整理するのが上手く出来ずだったので、大変助けられました)
大問1を最後に解いたのは、「①効率が良い(時短に繋がる)、②絶対外せない強み等を漏れなく書くことが出来る」ためです。
大問1はSWOT等現状分析の設問につき、大問2以降の問題を解くことで、与件文がばっちり頭に入った状態で、漏れなく書く事が出来ました。
また、2以降と一貫性を持った解答もしやすくなりますし、他の問題に時間一杯使えるという点も良かったです。
大問1は配点が低めで流れが決まっており、他の問題を解いていると、解答が頭の中に出来てくるので、最後の楽しみに取っていたところもあります!
こちらの記事でも少し触れていますので、ご参考までに載せておきます。
【渾身】「2次試験 事例Ⅰ~Ⅲ・80分で終わらない問題」克服作戦 by かます
https://rmc-oden.com/blog/archives/199610
応援しています!
こんばんは!
にっくです。
得点力を上げる記事、ありがとうございました!
あと3週間、少しでも得点を積み増したいと思っていたので、大変参考になりました!
ありがとうございました!
にっく
にっくさん、コメントありがとうございます!
わたし自身も最後の最後まで理解が進んでいく感覚があったのでこれからが更にボーナスチャンスだと思います。
1点、2点が命運を分けるところもありますし、残りの期間で得点力を上げれる様、応援しています!