だいまつが教える事例Ⅲ攻略の極意
☆☆☆☆☆☆☆
一発合格道場ブログを是非、あなたのPC・スマホの
「お気に入り」「ブックマーク」にご登録ください!
☆☆☆☆☆☆☆
<注意>
今回の記事を真剣に読むとおそらく1時間以上の時間が必要になります。
みなさん、おはこんばんにちは、だいまつです!
3回シリーズでお届けした「【永久保存版】平成29年度2次試験超高得点答案にみる2次試験合格のポイント!」の記事を読んだ読者の方から、「平成28年度もしくは平成27年度試験の事例Ⅲの解答・解説記事を読みたい」とのリクエストをいただきました。
そこで、今回は平成28年度試験の事例Ⅲを題材に、私なりの事例Ⅲに対するアプローチの仕方を解説していきたいと思います。
まず、初めに事例Ⅲを解く上で必要になる切り口やイメージしておくべきことを整理しておきます。
①私の考える事例Ⅲの基本的なパターン/切り口
~きゃっしいが「実況解説@事例Ⅲ」で示したレイヤーに「現状把握」が乗っかったイメージです。

凄くシンプルですが、事例Ⅲはこの表(4つの切り口)に基づいて考えることが極めて大切です。後で解説を読んでもらえれば分かると思いますが、平成28年度試験では、この表の上から順番に第1問、第2問、第3問、第4問と出題されています。
②事例Ⅲを解く上での基本的な認識
C社は当たり前のことができていない。だから、当たり前を目指すための解答を書く
③事例Ⅲにおける目指すべき当たり前
✔全社的な生産計画を作成され、なおかつ適切な頻度で計画が見直さ
れた上で、計画に基づいた進捗、余力、現品管理が行われている
✔作業は標準化、マニュアル化され、教育が徹底されており、効率的
である
✔作業員は多能工化が図られ、多台持ちできるなど、業務の閑散に
応じてた柔軟な対応が出来る体制が構築されている
✔情報は、DB等を用いて一元的に管理され、そして共有化され、
すぐに引き出せるようになっている
④事例Ⅲ全体に対する認識(ポポさんの言葉)
事例Ⅲは難しく考えないで、できていないこと、やらなきゃいけないことを、ただやってくださいと言うだけなのです。覚えることはかなり少ないし、解答の切り口も結構一緒のことが多いから、繰り返し練習していれば、解けるようになってきます。
事例Ⅲを解く上で必要になる切り口やイメージしておくべきことはこれくらいで十分です。
【永久保存版】シリーズのなかで何度も書きましたが、事例Ⅲで「難しく考えること」は、「絶対に禁止」です。「できていないこと、やらなきゃいけないことを、ただやってください」と書くだけでOKです。
この①~④はめちゃくちゃ大切なことなので、今年の事例Ⅲで60点以上を狙いたいと思うのなら、①~④の内容をご自身のノートに転記して、事例Ⅲの過去問を解く前に「必ず見返す」ようにしてくださいね(解いた後も)。
事例を解くたびに思い出す、そして実感する、ということを繰り返すと、「知っている・理解している」という段階から、「使いこなして事例問題が解ける」という段階(自分のものにする)へと、ステップアップすることができます。
それでは、平成28年度試験問題(事例Ⅲ)を使って解説をしていきますが、ここから先は平成28年度事例Ⅲの過去問を解いて、自分の解答や与件文を見ながら読むようにしてくださいね。でないと、効果はいつも通り10分の1以下ですからね!
過去問はLECのサイトからダウンロードできます(コチラ)。
第1問(配点20点)
カット野菜業界におけるC 社の(a) 強みと(b)弱みを、それぞれ40 字以内で述べよ。
【出題の趣旨】
X農業法人時代の事業経過、およびC社の現在の事業内容を把握し、カット野菜業界におけるC社の強みと弱みを分析する能力を問う問題です。
(a)
解答例①だいまつ
X農業法人との関係を有し、新鮮な規格外野菜の仕入れができること、である。
解答例②後輩A
X農業法人から市場に出荷できない規格外野菜を安定的に仕入れることができること。
解答例③後輩B
規格外の野菜を有効活用できる加工技術力及びカット野菜の一貫生産体制の保有である。
与件文にヒントが少なくて、強みを非常に読み取りにくい問題です。
しかしながら、冒頭で示した「4つの切り口」のうち、現状把握系の問題は、必ずヒントが与件文に埋め込まれています。
なぜなら、C社の「現状」は与件文に記載がなければ、「答案の作りよう」がないからです。
事例Ⅰなら、与件文から「類推」を求められるような現状把握(分析)系の問題が出される可能性もありますが、超シンプルな「事例Ⅲ」は、与件文の言葉を拾ってきて、整理し、答案を作るだけでOKです。
では、だいまつの解答例から見て行きましょう。
X農業法人との関係を有し、新鮮な規格外野菜の仕入れができること、である。
着目した与件文の記述は以下の通りです。
第4段落の「規格外野菜の有活用を目的として」、第7段落の「C社とX農業法人との関係に注目した新たな取引要望がある」、「新鮮さを売りものにしている中小地場スーパーマーケットなどから要望がある一般消費者向けのサラダや調理用のカット野菜パック事業であり・・・」
多くの説明は不要だと思います。なので、細かな解説は割愛しますが、「新鮮な」という言葉を入れた思考の流れだけ説明しておきます。C社とX農業法人との関係に注目した新たな取引要望があり、そして提案をしてきたのが、「新鮮さを売りものにしている中小地場スーパーマーケット」ということであれば、X農業法人の野菜は「新鮮はなず」と類推し、盛込みました。
ただし、「新鮮な」というワードは、書けても書けなくてもどちらでもいいと思います。
一方で、「X農業法人との関係に基づく、規格外野菜の仕入れ」という解答要素は、C社の唯一と言っても過言ではない長所なので、絶対に盛込みたいところですね。
次に、後輩Aの解答例です。
X農業法人から市場に出荷できない規格外野菜を安定的に仕入れることができること。
前半部分は ‘〇’ ですが、後半部分の記述が全てを台無しにしています。
与件文の着目すべき箇所はある程度分かっているにも関わらず、与件文から考えて明らかにおかしな後半部分の記述によって、0点にされかねない危険な答案を作ってしまっています。
これは、絶対に避けるべき過ちです。
与件文を確認すると、第5段落に「工場操業状況は、規格外野菜を主に原材料として利用してきた時には収穫時期から約半年間の季節創業となっていたが、市場規格品の使用や他山地からの仕入れによって向上総合期間は長くなったものの、C社に受け継がれた後でもまだ約3ヶ月の休業期間が例年生じている。販売先からは通年取引の要望がある」との記述があります。
X農業法人からの規格外野菜の仕入れだけでは、半年間しか操業できないのに、「安定的に仕入れることができること」というのは、与件文をちゃんと読めていないトンチンカンな解答です。
本試験で‘もしも’や‘仮に’はありませんが、後輩Aの答案から余計な4文字(安定的な)を取ればどうなるでしょうか。
X農業法人から市場に出荷できない規格外野菜を仕入れることができること。
見違えるような「イケてる」解答に変わりましたね。
【永久保存版】シリーズの中でも書きましたが、解答要素の抜出はできているのに、安易な修飾や余計な言葉を盛込んでしまい、開示得点がやたら低くなる「解答要素OK、開示得点低い」答案を作ってしまわないように注意しましょう。
ちなみにですが、後輩Aに「安定的な」と書いた理由を問い詰めたところ、「通年創業できないことは把握していましたが、強みを聞かれていたので、なんとなく安定的というワードがあった方が、‘強みっぽい’記載内容になると思って入れました」との返答が帰ってきました。
・・・結構やってしまいがち、ですよね!
「ひらめき」と「なんとなく」は、100%排除です。
これも、普段の練習から意識しておきたいところですね。
続いて、後輩Bの解答例です。
①規格外の野菜を有効活用できる加工技術力②カット野菜の一貫生産体制の保有である。
こちらもなかなかパンチの効いたダメ答案ですね・・・(私の教え方が悪いことが原因ですが)。
まずは、①の「規格外の野菜を有効活用できる加工技術力」という記述に関してです。規格外野菜を「有効活用」できているのは‘確か’ですが、「加工技術力」は言い過ぎです。特性要因図に目をやると「原材料(形状ふぞろい)」が、「加工不良が多い原因のひとつ」であると書かれています。「加工技術力」があるのなら、規格外野菜を上手く処理できるはずですから、「図1」のような特性要因図が示されるはずがありませんね。
平成28年度試験のC社は、事例Ⅲで登場する企業では本当に珍しい、「Q」の弱い会社でした。
続いて、②の「カット野菜の一貫生産体制の保有する」という記述に関してです。確かに事例Ⅲではたまに「一貫生産体制」が強みの企業が登場します。
ただし、今回は与件文を読む限り、C社が「一貫生産体制を有する」とは、書かれていません。「なんとなく」ではだめなのです。
事例Ⅰは「行間を読ませる」ようなところもありますが(こうした掴みどころのなさが魅力なんですけどね)、事例Ⅲは素直なので、与件文に明確に「一貫生産体制を有する」と書いていない限りは、「強み」と認識しなくてもOKです。
今回の後輩Bの答案も、強みを見つけられず「苦し紛れに過去問の知識を引っ張り出して無理やり書いた」という対応の産物です。
読者の皆さんは、初めて本問を解いたときに、「X農業法人との関係を強み」とした答案がつくれましたか?
‘何度も解いて答えを憶えている’ 今は「X農業法人との関係」を強みとして書けるでしょう。でも、大切なのは「初見」で書けるか、どうかです。きゃっしいが、先日の記事(コチラ)でやや厳しめに「振り返りの仕方に対する問題提起」をしてくれています。自分自身の過ちはもちろんのこと、今回の後輩Aや後輩Bが犯してしまった過ちもちゃんと他山の石として、初見問題への対応力向上に役立ててくださいね。
続いて(b)の解答例を見て行きましょう。
(b)
解答例①だいまつ
①通年取引不可の野菜の調達力の低さと、②組織的に生産管理できず収益性が低いこと。
解答例②後輩A
①野菜の調達力、②生産管理力、③収益力、④衛生管理力、⑤営業力。
解答例③後輩B
①生産管理が組織的にできていない②調達力が低く通年取引要望に応えられていない。
本問についても、あまり多くを説明する必要はないと思いますので、さらっといきます。
私の解答例からです。
①の「通年取引ができない野菜の調達力の低さ」は、第3段落の「カット野菜は、販売先から要望される通年納品に応えるため、常に一定量の野菜を確保する必要がある。そのため同業者の多くが野菜の調達能力が高い卸売業者や仲卸業者である」と、第5段落の「C社に受け継がれた後でもまだ約1カ月の休業期間が例年生じている。販売先からは通年取引の要望がある」を、根拠としています。
②の「生産管理が組織的にできず収益性が低い」は、第4段落の「効果的な生産管理が組織的に行われていない」や、表1、第2問の設問文「現在C社が抱えている最大の経営課題は、収益改善を早急に図ることである。生産管理面での対応策を述べよ」を踏まえたものです。
出題の趣旨に目を向けると、「X農業法人時代の事業経過、およびC社の現在の事業内容を把握し、カット野菜業界におけるC社の強みと弱みを分析する能力を問う問題」との記載がありますから、野菜の調達力の低さや生産管理力の低さはまず正解と考えて間違いなさそうです。
続いて、後輩Aの解答例です。
①野菜の調達力、②生産管理力、③収益力、④衛生管理力、⑤営業力。
究極の詰込み答案ですね。正直、私にはここまでの「詰込み型の答案」を作る能力はありません。もちろん、間違っていないため、「点数」は得られるでしょう。
ただし、「望ましい対応」ではないと考えます。
なぜなら、設問要求は40 字以内で「述べよ」だからです。
「述べよ」を国語的に考えれば、「記述せよ」というニュアンスに近いでしょう。
仮に設問要求が「挙げよ」や「列挙せよ」なら後輩Aの解答例のような答え方がぴったりだと思いますが、「述べよ」だとやや物足りない感じがしますね。
私と後輩Aの答案を並べておきます。設問要求の「述べよ」にしっくり来るのはどちらでしょうか。皆さん、評価してみてください。
解答例①だいまつ
①通年取引不可の野菜の調達力の低さと、②組織的に生産管理できず収益性が低いこと。
解答例②後輩A
①野菜の調達力、②生産管理力、③収益力、④衛生管理力、⑤営業力。
(せめて、最後に「低さ」という言葉があれば、一応述べていることにはなりますね)
続いて、後輩Bです。
①生産管理が組織的にできていない②調達力が低く通年取引要望に応えられていない。
解答要素はほぼOKです。
本番でここまで書ければ十分でしょう。
細かい話をすれば、①に関しては「生産管理が組織的にできなかった」でどうなったかの記述(収益性が低い)が欲しいですね。また、字数が少なくて苦しいのは分かりますが、②に関しては、文頭に「野菜の」という言葉が欲しかったですね。
第2問(30 点)
現在C社が抱えている最大の経営課題は、収益改善を早急に図ることである。生産管理面での対応策を160 字以内で述べよ。
【出題の趣旨】
C社が収益改善を図るために必要な生産管理面での対応策を提案する能力を問う問題である。
解答例①だいまつ
対応策は、各製造グループをまたぐ全体生産計画を作成した上で、①管理項目に限界利益を追加し作業員のコスト意識を高め加工ロスを減らすとともに、同種の原材料は低単価品を共通して使うことで原材料費を削減する、②業務の閑散に応じて作業員を移動させ労務費を削減する、③出荷を共通化して輸送費ロスを減らす。以上で収益改善を実現する。
解答例②後輩A
対応策は、各製造グループがばらばらに行っている調達から出荷までの工程について、①原材料の仕入れを一元化することで単価差異を解消する、②共同出荷による出荷作業の共通化を行う、③作業の標準化・マニュアル化し、作業員に対する教育も行うことで生産効率を高める。以上により原材料費・輸送費を削減し、収益性を改善する。
解答例③後輩B
対応策は、全社的な生産計画を策定し、統制活動を実施し、コストを削減し、収益性を改善することである。具体的には、①原材料の一括調達によって単価差異を解消することで、原材料費を削減する、②チーム間の業務の繁忙に応じて作業員を移動させ、稼働アンバランスを解消し、労務費を削減すると同時に加工ロスを減らし、原材料費も削減する。
さて、解説です。
本問の設問要求は、「生産管理面での対応策」、「収益改善を図るための(C)」です。
【永久保存版】シリーズを読んでいただいた読者の皆さんは、このド真ん中の直球ストレートの‘絶好球’を見逃すことなく、フルスイングして答案を球場の外にまで運んで、いただけたでしょう。
第1問目が「現状把握」系の問題で、第2問目は「生産管理」系の問題ですね。冒頭に申し上げた通り、4つの切り口の‘順番’で出題されていますね。
生産管理が問われ、収益改善と設問文にある訳ですから、この時点で与件文に何が書いてあるかを大体予想することができます。
恐らく、C社は「全体生産計画を作っていないか」、もしくは「計画の見直しタイミングがおかしく」、そして「統制がグダグダ」で、「コスト高になってしまっている」、そんなところでしょう。
ちなみに、事例Ⅲの現場系の問題(生産管理、生産性向上・生産効率化)で「収益改善」を問われた場合には、「コスト削減」の視点で解答を組み立てて行かなければなりません。
なぜなら、製造現場の改善と「売上UP」は直接関係ないからです。
一方で、事例Ⅱならコスト削減ではなく「売上UP」ですね。
さて、今回はせっかくですから関連する与件文の記述を丁寧に確認していきましょう。
第4段落
C社の設立当時作成された社内コスト管理資料では、予想されていた以上の原材料費と労務費の上昇によって限界利益がマイナスとなっていることが判明し、この傾向は今でも改善されていない。これは、X農業法人から独立し改善に向けて努力しているものの、いまだに効果的な生産管理が組織的に行われていないことによる。
最終行で「生産管理が組織的に行われていない」との記述があります。そして、それによって、「原材料費と労務費が上昇し限界利益がマイナス」になっていることが分かります。
そしてさらに、表1「C社作成の社内コスト管理資料」を見ると、変動費の中で「原材料費(66.8%)と労務費(28.1%)」がぶっちぎって構成比が高くなっています。一方で、荷造運賃は9.0%と両項目に比べると、構成比がかなり控えめですね。
このため、出題者は間違いなく「原材料費と労務費」の削減に資する対応策(収益改善策)を書いてほしい、そう考えていたでしょう。【永久保存版シリーズ】にも書きましたが、診断士の2次試験で難解な表の読み取りは求められません。誰が見てもちゃんと「図表が意味するところを読み取れる」ように工夫がしてあります。
第6段落
C社の組織は、X農業法人時代の加工部門責任者が社長となり、製造3グループと総務グループで構成されている。社長は、全体の経営管理のほかに営業活動も担っている。各製造グループには責任者として正社員の製造リーダー1名が配置され、合計25名のパート社員が3つの製造グループに配置されている。X農業法人時代から同じ製造グループに勤めているパート社員が多く、他の製造グループへの移動はない。
「X農業法人時代から同じ製造グループに勤めているパート社員が多く、他の製造グループへの移動はない。」という表現がなくても文章として成り立つのに、なぜこのような文章を、形式段落の「最後」に入れたのでしょうか。
皆さんならお分かりですよね。
そうです。使って‘ほしい’ のです。
使って ‘ほしい’ のなら使って ‘あげましょう’。
「移動がない」のなら、「移動させる」と、‘答案に書いて‘あげましょう’。
(事例Ⅲではひねる必要は、全くありませんからね!)
第8段落
C社社長は、まず現状の生産管理を見直し、早急に収益改善を図ることを第1の目標としているが、それが達成された後には新事業に着手してさらなる収益拡大を目指すことを考えている。
これは、設問文の記述と符合する内容ですね。
第9段落
C社のカット野菜製造工程は、顧客別に編成・グループ化され、現在3つの製造グループで製造を行っている。各製造グループでは主に素材選別、皮むき、カット、洗浄、軽量・パック・検査、出荷の各工程を持っている。各製造グループは、生産高を日常の管理項目として管理してきた。
「各製造グループは、生産高を日常の管理項目として管理してきた」どう考えてもおかしな記述ですよね。
でも、違和感を感じつつも、この与件文の記述が意味しているところを「理解しきれていない」受験生もいらっしゃるのではないでしょうか。
(私も勉強を始めた当初は全く理解できませんでした)
事例Ⅲは、「言葉通り読む」ことが大切です。あれこれ考えてはいけません。
「言葉通り」読んでください。C社は「生産高を日常の管理項目として管理」してきたのです。
原材料費と労務費がかかり過ぎて限界利益がマイナスで、作れば作るほど赤字が出る、そんな状態‘なのに’、「生産高しか日常の管理項目として管理してこなかった」のです。
普通の企業ならあり得ないですよね。
でも、診断士試験では与件文の記述が全てなのです。
事例Ⅲでは、‘特に’なのですが、「そんなバカな」という言葉を飲み込んでください。
なにせ、冒頭で申し上げた通り、C社は「当たり前のことができていない」のです。
こんな、「生産高しか日常の管理項目として管理してこなかった」C社への助言は、「赤字を垂れ流さないように限界利益も日常の管理項目として管理してください」です。
「できていないこと、やらなきゃいけないことを、ただやってくださいと言うだけ」、それが事例Ⅲなのです。
第10段落
C社の顧客からの注文は、各製造グループに直接入り、各製造グループで各々生産計画を立て、原材料調達から出荷まで行っている。製造グループごとの生産管理によって、同種類の原材料調達における単価の差異、加工ロスによる歩留まりの低下、出荷のための輸送費のロス、製造グループ間での作業員の移動の制限などが見られる。
設問要求で想定した通り、「全体生産計画を作っていない(製造グループごとにバラバラに生産計画を立てている状況)」が、‘もろ’に書かれていますね。
そして、「製造グループごとの生産管理によって」単価差異、加工ロス、輸送費ロス、移動制限(2度目の登場)が発生している状況が記述されていますね。
ここまで、設問文と与件文をひも付けできれば、後は如何に答案として上手くまとめて行くかにかかっていますね。
それでは、解答例をみていきましょう。
解答例①だいまつ
対応策は、各製造グループをまたぐ全体生産計画を作成した上で、①管理項目に限界利益を追加し作業員のコスト意識を高め加工ロスを減らすとともに、同種の原材料は低単価品を共通して使うことで原材料費を削減する、②業務の閑散に応じて作業員を移動させ労務費を削減する、③出荷を共通化して輸送費ロスを減らす。以上で収益改善を実現する。
みなさんは、どのように評価されるでしょうか。
パッと見は、完璧ですね!
全体生産計画を作る、という計画の話を起点に、①管理項目への限界利益の追加と、低単価品の共通使用、②業務の閑散に応じた作業員の異動、③出荷の共通化、という統制内容が書けています。
本番でこの答案が書ければ御の字、本当に自分をほめてあげましょう。
しかしながら、以下の問題点もあります。
(注意:ここからの解説は、答案内容を突き詰めて考えた場合における問題点なので、こだわり過ぎないでください。参考程度でOKです)
①与件文上、明らかに出題者は「原材料費と労務費」の削減に資する対応策を書いてほしいのに、輸送費ロスを解答要素として盛り込んでいる。
間違いではないため、「輸送費ロス」を解答要素として答案に盛込んでも点数はもらえると思います。ただし、「収益改善を早急に図ることが、最大の経営課題」であるC社にとっては、社内コスト資料で示されている構成比が高い項目(原材料費と労務費)を優先的に解消していくことが求められますね。
「輸送費削減」は不適切とまでは言わないまでも、解答要素としての優先順位は低いと言えるでしょう。
②「製造グループごとの生産管理によって加工ロスが発生している」という問題点に対して、「管理項目に限界利益を追加し作業員のコスト意識を高め加工ロスを減らす」という書き振りでは、言葉足らずで対応策に関する記述として不十分。
ここは、ちょっと分かりにくいところなので、理解しきれないようなら飛ばしてください。
→「製造グループごとに生産管理をしているから加工ロスが起きている」、さらに噛み砕いて言うと、「製造グループごとに‘バラバラに’生産管理をしているから加工ロスが起きている」のに、「管理項目に限界利益を追加する」という言葉(解答)だけでは、「ごとに(各チームバラバラ)」という与件分の記述への配慮が足りていません。
例えばですが、「限界利益を各チーム共通の管理項目とし」という書き方にすれば、「製造グループごとの生産管理」という問題点への対応策として、(国語的に)ばっちりだと思うのですが、皆さんいかがでしょうか。
[ before ]
製造グループごとの生産管理によって加工ロスが発生しているため、
管理項目に限界利益を追加し作業員のコスト意識を高め加工ロスを減らす
[ after ]
製造グループごとの生産管理によって加工ロスが発生しているため、
限界利益を各チーム共通の管理項目とし作業員のコスト意識を高め加工ロスを減らす
なお、「加工ロスの削減」については、後輩Bが別の観点から素晴らしい答案を作っているので後ほど解説します。
何度も言いますが、「深追いは禁物」です。あくまでも参考です。
解答例②後輩A
対応策は、各製造グループがばらばらに行っている調達から出荷までの工程について、①原材料の仕入れを一元化することで単価差異を解消する、②共同出荷による出荷作業の共通化を行う、③作業の標準化・マニュアル化し、作業員に対する教育も行うことで生産効率を高める。以上により原材料費・輸送費を削減し、収益性を改善する。
【永久保存版】シリーズを読んでいただいた皆さんならお分かりだと思いますが、後輩Aは、「生産管理」が「何者なのか」を理解していませんでした。
そのため、本問で2つもの事故が発生しています。本番でやってしまったなら、少なく見積もっても15点は吹き飛ばしてしまっているでしょう。240点付近には受験生が団子状態になっているのに、「生産管理系」のサービス問題で15点もライバルと差がついてしまう・・・、考えたくもありませんね。
【事故の内容】
①全体生産計画について触れられていない(生産管理は計画→統制なのに)
②生産効率化(標準化→マニュアル化→教育)のことを書いてしまっている
なお、後輩Aには、私が徹底的に「生産管理系の問題」に対する対応策を指導しておきましたので、今後は大丈夫でしょう。
解答例③後輩B
対応策は、全社的な生産計画を策定し、統制活動を実施し、コストを削減し、収益性を改善することである。具体的には、①原材料の一括調達によって単価差異を解消することで、原材料費を削減する、②チーム間の業務の繁忙に応じて作業員を移動させ、稼働アンバランスを解消し、労務費を削減すると同時に加工ロスを減らし、原材料費も削減する。
なんだか、「し」がやたら多いですね。日本語としてどうなんだ、と思われる方もいらっしゃると思うのですが、道場9代目のリーダー、受験生支援業界で、「ゴッド(神)」のふたつ名を持つ きゃっしい様も、「し」を多用した答案を作っておられることから、全く問題ないでしょう。
しかし、後輩Bの答案は本当に素晴らしいですね。
詳しく解説します。
まず、最初の文章ですが、本当に「生産管理」という題意を捉えつつ、QCDの「C(コスト)」を出口とした解答が書けていますね。
ここで注目すべきは、冒頭の「対応策は、全社的な生産計画を策定し、統制活動を実施し、コストを削減し、収益性を改善することである」という文章の流れです。
「生産管理」の問題であること及び「助言」の問題であることを意識して、「計画→統制→効果」という流れで文章が作られています。
分かりやすいように文中に‘( )’を追加してみました。
対応策は、(計画→)全社的な生産計画を策定し、(統制→)統制活動を実施し、(効果→)コストを削減し、収益性を改善することである。
素晴らしいですね。
加えて、「具体的に」以下の①~③の記述も本当に素晴らしいと思います。
何が素晴らしいかを解説します。
第4段落の「原材料費と労務費が上昇し限界利益がマイナス」という記述と、表1を踏まえて、ぶっちぎりでコストがかかっている上位2項目にターゲットを絞った答案になっています。
それと、さらに素晴らしいのが、②の「チーム間の業務の繁忙に応じて作業員を移動させ、稼働アンバランスを解消し、労務費を削減すると同時に加工ロスを減らし、原材料費も削減する」という記述です。
皆さんは、彼がなぜ「チーム間の業務の繁忙に応じて作業員を移動させ、稼働アンバランスを解消し、労務費を削減すると同時に加工ロスを減らし、原材料費も削減する」と、書いたと思いますか?分かりますか。
私も最初は彼がなぜそのような解答を書いたのかが分かりませんでした。
しかし、「図1 C社作成の加工不良に関する特性要因図」を見て、ハッとしました。特性要因図の赤字で囲った部分を見てください。
「製造チームごとの加工」と「製造チーム間の作業員移動がない」ことにより発生する、「製造チーム間稼働アンバランス」が、「加工不良が多い(つまり加工ロスが多い)」の原因のひとつだ、と書かれているではありませんか。
特性要因図に基づけば、全体生産計画を立て、「製造チーム間で作業員を移動させ」、「製造チームごとの加工を辞め」、「製造チーム間の稼働アンバランスを解消」すれば、「加工不良が減る」のです。
まさか第2問で特性要因図を使うとは夢にも思いませんでした。
しかし、診断士の2次試験、恐るべし、ですね。
本当に奥が深い。
ただし、私を含めてフツーの人は、気付かないので深入りはやめましょう。
生産管理ときたら「計画→統制」という着眼点を持って与件文を読みに行く、それで十分です。60点は十分に取れます。
ここまで細かく解説しておいて言うのもなんですが、診断士の2次試験は100点を狙いに行く試験ではありません。80分で現実的な対応をして60点を取に行く試験です。
第3問(配点20 点)
C社では、クレームを削減する改善活動を計画している。このクレーム改善活動を最も効果的に実施するために、着目するクレーム内容、それを解決するための具体的対応策を120 字以内で述べよ。
【出題の趣旨】
C社の生産現場の課題を把握し、クレームを削減する改善活動を最も効果的に実施する方法として、着目するクレーム内容とその解決策を提案する能力を問う問題である。
解答例①だいまつ
全体の50%を占めるカット形状不均一というクレームに着目する。対応策は、標準作業不備や教育不足による加工スキル不足が原因のため、①作業を標準化し手順書化する、②優秀な作業員を他チームへ派遣し、手順書に基づくOJTで、クレームを解消する。
解答例②後輩A
着目するクレームは、構成比の合計が80%を超える①カット形状不均一、②鮮度劣化、③異物混入である。対応策は、①カット作業の標準化で形状不均一を解消、②仕掛品削減による長時間放置の解消、③衛生管理ルール作成と教育による異物混入解消である。
解答例③後輩B
着目するクレームは、構成比の半分以上を占めるカット形状不均一である。対応策は、①標準作業の不備により人によって作業方法が違うため、作業を標準化・マニュアル化し、加工スキル不足を補うためのOJTも実施することで、最も効果的にクレームを削減する。
解答例を見て行きましょう。
まずは、私の解答例からです。
「最も効果的に実施する」という設問要求と、「表2 C社の年間クレーム件数」でぶっちぎりで構成比の高い「カット形状不均一」を着目すべきクレームとしています。
私の記事では何度も書いていますが、診断士の2次試験の図表の読み取りでは、「難しい読み取り」は求められません。誰が見てもすぐに分かるようにできています(じゃないと受験生を想定する答案へ受験生を誘導できないし、診断協会が試したいのは高度な図表の読み取り能力ではないから、です)。
そして、特性要因図に目を向けると「カット形状不均一」という「同じ言葉」が載っています。さらにカット形状不均一の原因に目をやると、「標準作業の不備」と書いてあるではないですか。
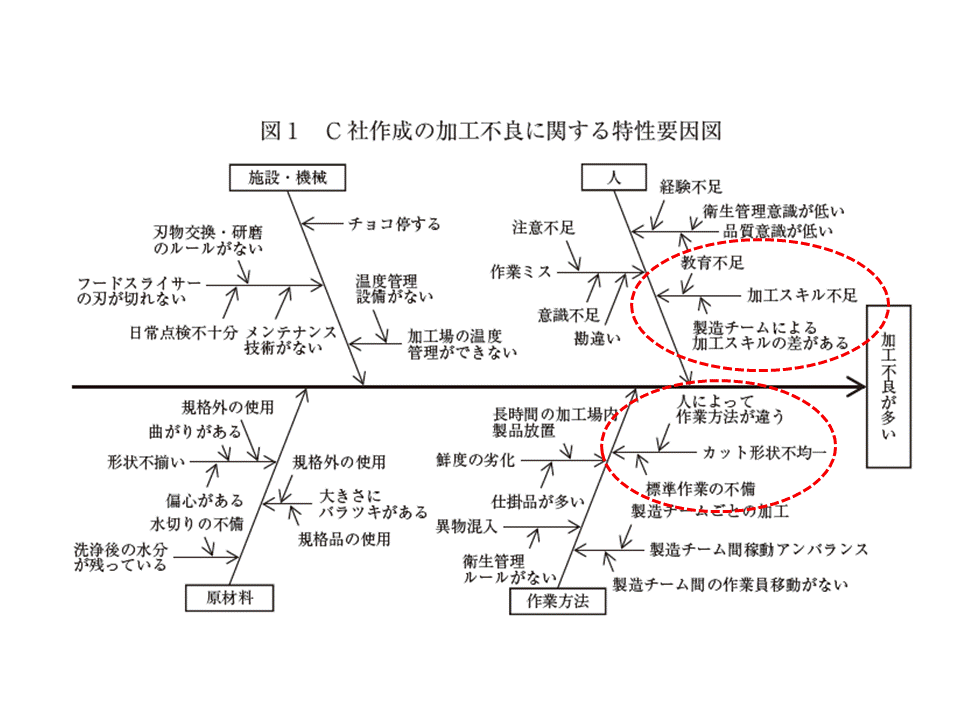
設問要求の段階では分かりませんでしたが、この時点で本問は冒頭にお示しした4つの切り口の「生産性向上・生産効率化」の問題であることが分かります。
そして、特性要因図でさらにヒントを探すと「製造チームによる加工スキルの差がある」、「教育不足」との記載があります。
ここまで与件分上のヒントが見つかれば(図表も与件)、もう大丈夫ですね。
本問は100%「生産性向上・生産効率化」の問題です。
そして、「生産性向上・生産効率化」とくれば、「標準化→マニュアル化→教育(OJT)」ですから、後はいつものパターンで解答を書いて「いっちょあり」です。
平成28年度試験は第2問が生産管理で「全体生産計画作れ」、第3問が生産性改善で「標準化→マニュアル化→OJT」です。
平成29年度試験は第1問が生産管理で「全体生産計画作れ」、第2問が生産性改善で「標準化→マニュアル化→OJT」でした。
ここまで来ると、(言葉は少し悪いですが)「解けない方がどうかしている・・・」そう言われても仕方ありませんね。
もし、私の記事に出会って、事例Ⅲに対する苦手意識を克服できた受験生の方がいらっしゃれば、本当に嬉しいですね。
事例Ⅲは、最初はマニアックで取っ付きにくいのですが、実は凄く素直で何度も同じことを聞いてくれる、受験生にとてもやさしい事例さん(Ⅲ)なのです。
ははは。
続いて、後輩Aの解答例です。
解答例②後輩A
着目するクレームは、構成比の合計が80%を超える①カット形状不均一、②鮮度劣化、③異物混入である。対応策は、①カット作業の標準化で形状不均一を解消、②仕掛品削減による長時間放置の解消、③衛生管理ルール作成と教育による異物混入解消である。
完全に「やってはいけないパターン」ですね。
設問要求が「最も効果的に」であり、「表2 C社の年間クレーム件数」を見るとぶっちぎりで「カット形状不均一」の構成比が高いにも関わらず、上位3つのクレームを挙げています。
平成29年度の事例Ⅰの第1問における「最大の要因」は、やや解答要素を絞りにくかったこともあり、リスク分散を図るスタンスで臨むことは致し方ないと思います。ですが、本問は違います。ここまで明示的に根拠が示されているのに題意(最も効果的に)に反するような答案を作ってはいけません。
何度も言いますが、診断士試験では高度な図表の読み取りは求められません。
下手なリスク分散はしない。後輩A君の失敗から学び得ましょう。
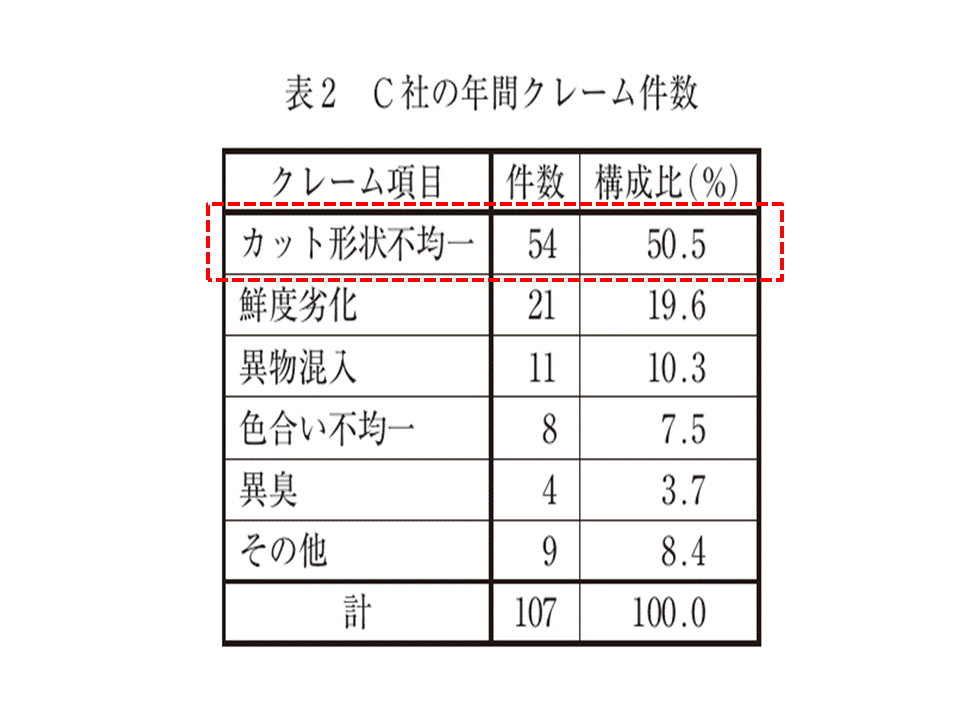
続いて、後輩Bの解答例です。
解答例③後輩B
着目するクレームは、構成比の半分以上を占めるカット形状不均一である。対応策は、①標準作業の不備により人によって作業方法が違うため、作業を標準化・マニュアル化し、加工スキル不足を補うためのOJTも実施することで、最も効果的にクレームを削減する。
注目しているところは私と同じですね。
後輩Bの答案を見て素晴らしいと思うのは、下線を引いた部分、つまり「原因」に関する記述です。
特性要因図の言葉をそのまま抜き出して解答に埋め込んでいます。素晴らしい。
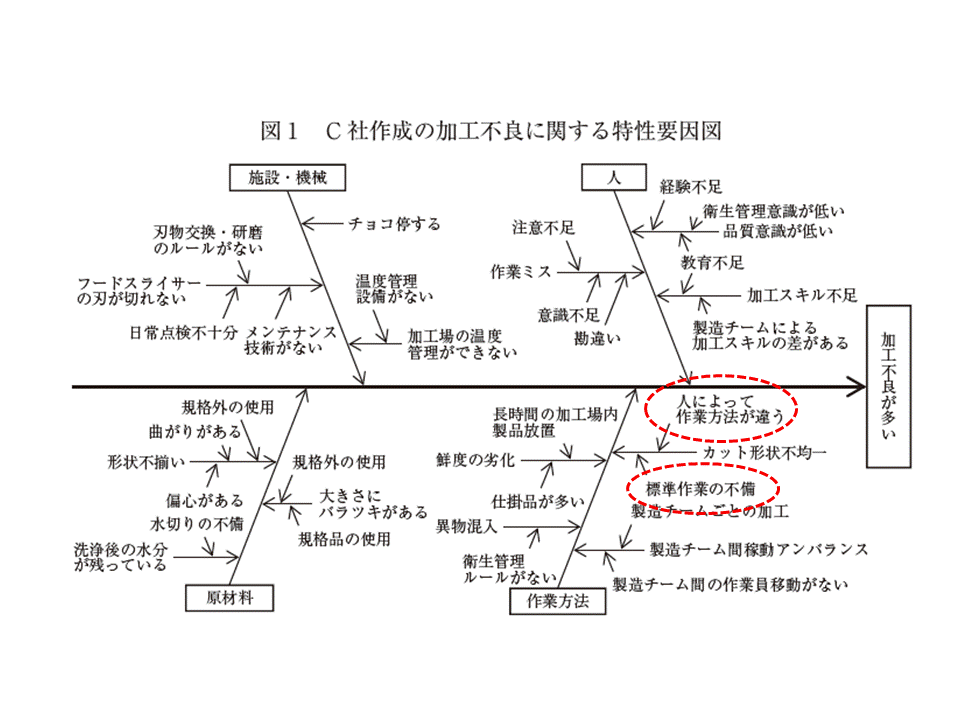
第4問(配点30 点)
C社社長は、経営体質の強化を目指し、今後カット野菜の新事業による収益拡大を狙っている。またその内容は、顧客からの新たな取引の要望、およびC社の生産管理レベルや経営資源などを勘案して計画しようとしている。この計画について、中小企業診断士としてどのような新事業を提案するか、その理由、その事業を成功に導くために必要な社内対応策とともに160 字以内で述べよ。
【出題の趣旨】
C社の顧客動向など外部環境を把握し、今後野菜の加工事業を強化して収益拡大を図るために必要な戦略について、助言する能力を問う問題である。
解答例①だいまつ
提案は、ソース等の高付加価値製品事業を提案する。理由は、①保存がきくため野菜の通年仕入れができなくても対応でき、②高付加価値製品で高い収益性が期待できる、ためである。対応策は、取引先からの改善要望に応えるため、温度管理設備を併せて導入しつつ、衛生管理ルールを策定し、従業員教育を徹底することで安全管理レベルを引上げること。
解答例②後輩A
提案は、一般消費者向けカット野菜パック事業である。理由は、①カット野菜需要の割合が年々増えている、②X農業法人の新鮮な野菜が活用できる、③現在の製造工程を利用できるから。対応策は、①仕掛品を減らし鮮度が下がる製品の長時間放置を無くす、②温度管理設備導入で鮮度低下を防ぐ、③X農業法人からの仕入強化による通年取引対応である。
解答例③後輩B
短期的には、一般消費者向けのカット野菜パック事業を提案する。理由は現在の製造工程を利用でき、新たな設備投資が不要なため。対応策は、衛生管理の徹底で鮮度を保つことである。長期的には、ソース等の高付加価値事業を提案する。理由は高い収益性が見込めるため。対応策は新設備を扱える作業員の育成を行うことである。
設問要求は、「新事業の提案」、「その理由」、「社内対応策」の3つです。制約条件として、顧客からの新たな取引の要望、C社の生産管理レベル、経営資源を勘案して答えなければなりません。
そして、第7段落を見ると、「現在取引関係にある顧客や関連する業界から、C社とX農業法人との関係に注目した新たな取引の要望」に関する記述があります。
具体的には、
①カット野菜を原料としたソースや乾燥野菜などの高付加価値製品の事業であり、設備投資を必要とする事業
②新鮮さを売りものにしている中小地場スーパーマーケットなどから要望がある一般消費者向けのサラダ用や調理用のカット野菜パックの事業であり、現在の製造工程を利用できる事業
悩まれた方も多いと思うのですが、皆さんは、どちらの事業を選んだでしょうか?
いや、どちらの事業を「選ぶべき」だったでしょうか。
・
・
・
答えは、「どっちでもいい」です。
もう少し言えば、「与件分を根拠(因)にちゃんとした理屈付け、論理展開ができているのであれば‘どっちでもいい’」です。
【永久保存版】シリーズの中で述べましたが、診断士の2次試験における‘正解(得点が得られる項目)’は1つではありません。間違いなく複数あります。
診断士試験は「当てもの」ではありませんし、実際の診断現場においても「どちらの事業を選択することが正解か」は、‘投資判断の段階’では分かりません(両方やらない限りは投資後でも分かりませんね)。
しかしながら、どちらの事業を選ぶべきか、その理由や、事業を成功させるための対応策について助言することはできるでしょう。そして、診断士として助言をする場合には、ちゃんとした裏付けに基づいて、社長が納得できる論理展開でもって、説明をする必要があります。
この「ちゃんとした裏付け」が、「与件分を根拠にする」ということにほかなりません。
これから、私と後輩Aの解答例を用いて説明していきます。解説を読んでどちらを選んでも解答が作れるようにヒントが与件文に埋め込まれていることを、しっかりと理解(腹に落とす)してくださいね。
それと、第1問で「現状把握系」の問題が出た場合には、4つの切り口の表に従えば、「経営戦略」と「セットで考える(第1問をヒントにする)」ことが大切、でしたね。
ここも、重要ポイントなので忘れないようにしましょう。
それでは、私の解答例から見ていきましょう。
解答例①だいまつ
第1問
(a)
X農業法人との関係を有し、新鮮な規格外野菜の仕入れができること、である。
(b)
①通年取引不可の野菜の調達力の低さと、②組織的に生産管理できず収益性が低いこと。
第4問
提案は、ソース等の高付加価値製品事業を提案する。理由は、①保存がきくため野菜の通年仕入れができなくても対応でき、②高付加価値製品で高い収益性が期待できる、ためである。対応策は、取引先からの改善要望に応えるため、温度管理設備を併せて導入しつつ、衛生管理ルールを策定し、従業員教育を徹底することで安全管理レベルを引上げること。
私は、「ソース等の高付加価値製品事業」を提案しました。
カット野菜パック事業は、「C社とX農業法人との関係に注目した、新鮮さを売りものにしている現在取引関係にある中小地場スーパーマーケットなどから要望」によるものですから、中小地場スーパーとしては、当然「X農業法人から仕入れている野菜」を使った「新鮮さを売りにしたカット野菜パックを提供したい」と考えているでしょう。
しかし、現状は「販売先から通年取引の要望があるにも関わらず、他産地からの仕入れによって工場操業期間は長くなったとはいえ、C社に受け継がれた後でもまだ約3カ月の休業期間が例年生じている」という大変残念な状況です。
また、今回の新事業は「現在取引関係にある顧客」からの提案である訳ですから、もちろん新鮮さを売りものにしている中小地場スーパーは現在のC社の販売先であり、通年取引を希望しているはずです。
足もとの野菜調達すらもままならないC社が、中小地場スーパーに期待されている通りに、ましてや他産地仕入れという選択肢なしで、X農業法人オンリーで通年取引ができるだけの野菜を確保することはできない、私はそう考えて(これを理由として)ソース等の高付加価値製品事業を提案しました。
また、当然に「高付加価値製品事業」なわけですから、「高い収益性が期待できる」というのも理由になるでしょう。第2問の生産管理面で対策により、投資時点においては収益性が改善されているでしょうが、収益性を上げることはC社の課題ですから、当然社長に刺さる「理由」です。ちなみに私は第1問(b)で、収益性の低さを弱みとして解答しています。
続いて、「対応策」について解説します。
第12段落には「また食品工場としての施設・設備面などの衛生管理、作業方法などの衛生管理、どちらの管理レベルにも課題があり、販売先からの改善要求もある」との記述があります。
販売先からの要望ですから、①施設・設備面などの衛生管理、②作業方法などの衛生管理の両方に対応せざるを得ない状況が見て取れます。
そして、特性要因図を見ると、食品を扱っているにも関わらず、①温度管理設備がなくて加工場の温度管理ができていない(施設・設備面)、②衛星管理ルールがない(作業方法)、③作業員の衛生管理意識が低い(人)という、‘とてもよくない状況’が読み取れます。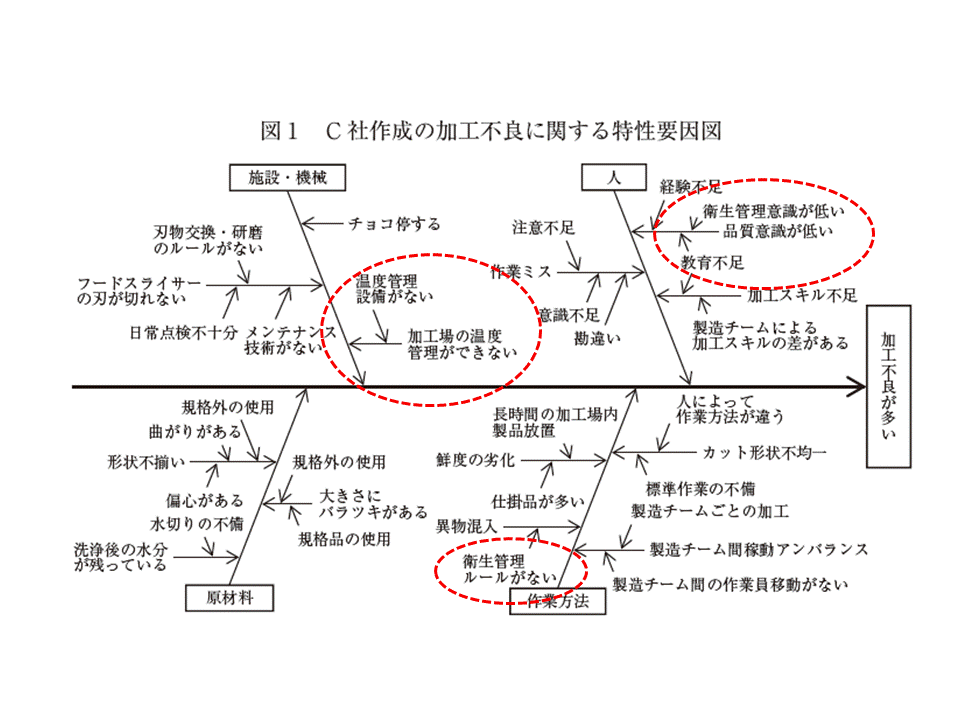 第12段落の記述から考えれば、①と②は絶対に盛り込まないといけませんし、③についても可能なら盛り込みたいところです。
第12段落の記述から考えれば、①と②は絶対に盛り込まないといけませんし、③についても可能なら盛り込みたいところです。
そうした判断から私は、「対応策は、取引先からの改善要望に応えるため、温度管理設備を併せて導入しつつ、衛生管理ルールを策定し、従業員教育を徹底することで安全管理レベルを引上げること」と書きました。
与件分の記述に基づき、ちゃんとした論理展開ができている解答内容だと思っているのですが、皆さんの評価は如何でしょうか。
続いて、後輩Aの解答例です。
解答例②後輩A
第1問
(a)
X農業法人から市場に出荷できない規格外野菜を安定的に仕入れることができること。
(b)
①野菜の調達力、②生産管理力、③収益力、④衛生管理力、⑤営業力の低さ。
第4問
提案は、一般消費者向けカット野菜パック事業である。理由は、①カット野菜需要の割合が年々増えている、②X農業法人の新鮮な野菜が活用できる、③現在の製造工程を利用できるから。対応策は、①仕掛品を減らし鮮度が下がる製品の長時間放置を無くす、②温度管理設備導入で鮮度低下を防ぐ、③X農業法人からの仕入強化による通年取引対応である。
後輩Aは「一般消費者向けカット野菜パック事業」を提案していますね。
理由の「①カット野菜需要の割合が年々増えている」は、第2段落の記述に基づいています。
「②X農業法人の新鮮な野菜が活用できる」は、「X農業法人との関係に注目した」という第7段落と、第1問(a)で答えた「X農業法人から市場に出荷できない規格外野菜を安定的に仕入れることができる」という強みを根拠としています。
「③現在の製造工程を利用できるから」は、「現在の製造工程を利用できる事業である」という第7段落の記述そのままですね。
ちゃんと与件文に基づいて書いていますから、いい感じですね。
続いて対応策です。こちらも素晴らしいですね。
①の「仕掛品を減らし鮮度が下がる製品の長時間放置を無くす」というのは、特性要因図の赤で囲った箇所の記述そのままですね。
カット野菜パック事業は、「C社とX農業法人との関係に注目した、新鮮さを売りものにしている現在取引関係にある中小地場スーパーマーケットなどから要望によるものである」わけですから、「仕掛品を減らし鮮度が下がる製品の長時間放置を無くす」ことは、当然に実施すべき対応策でしょう。
しかもこれは、第12段落に記述のある「作業方法の衛生管理」です。
②の「温度管理設備導入で鮮度低下を防ぐ」というのも、特性要因図の赤で囲った箇所の記述そのままですね。
しかもこれは、第12段落に記述のある「施設・設備面の衛生管理」です。
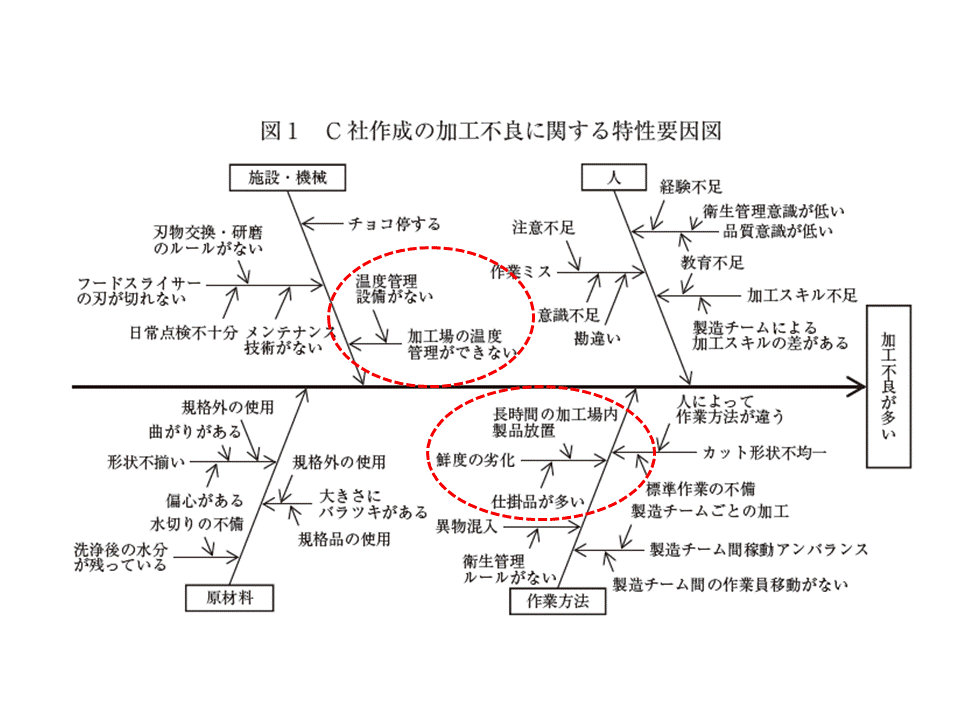
ここで、「ちょっとまて、設備投資するの?」と思った方もいらっしゃるでしょうが、第7段落には、「現在の製造工程を利用できる事業である」としか書かれていません。どこにも「設備投資不要」とは書いていないのです。
そして、「C社とX農業法人との関係に注目した、新鮮さを売りものにしている現在取引関係にある中小地場スーパーマーケットなどから要望によるものである」わけですから、「温度管理設備がない」ために起きる鮮度劣化を許してくれるとは思えません。第12段落の「食品工場としての施設・設備面などの衛生管理、作業方法などの衛生管理、どちらの管理レベルにも課題があり、販売先からの改善要求もある」という記述から考えても、対応策として設備投資することを助言すべきでしょう。
③の「X農業法人からの仕入強化による通年取引対応である」に関しては、実際は無理そうな気がします。
ですが、カット野菜パック事業は「C社とX農業法人との関係に注目した、新鮮さを売りものにしている現在取引関係にある中小地場スーパーマーケットなどからの要望」によるものです。
さらに、「取引先からの通年取引要望がある(繰り返しになりますが、今回オファーした中小地場スーパーマーケットも要望していると考えるべきでしょう)」ことを考慮すれば、後輩Aが書いたように、「X農業法人からの仕入強化による通年取引対応」を対応策として‘書かない’という選択肢はありません。
「感覚的にできなさそうだから」と二の足を踏む方もいらっしゃるでしょうが、ポポさんの言葉を思い出してください。
「事例Ⅲは難しく考えないで、できていないこと、やらなきゃいけないことを、ただやってくださいと言うだけ」なのです。与件文に基づいてできていないこと、やらなきゃいけないこと、があれば、ひっくり返して「ただ、やってください」と書けばいいのです。
どうしても、「X農業法人からの仕入強化」を書きたくない、という方は、「新鮮な野菜を年間を通じて仕入れることができる仕入先の開拓」と書けばよいでしょう。そうすると「X農業法人との関係に着目した」という与件文の記述を無視することになりますが・・・。
さて、どうでしょうか。
(まあ、どちらも「通年取引を何とかする」という話なので、点数をもらえると思います。好きな方を選んでください。)
「一般消費者向けカット野菜パック事業」も与件文の記述に基づいて、ちゃんと答案が作れましたね。
今年度の試験でもし仮に選択を求められたら、「与件文の記述に基づいて書けばOK」、そう ‘楽に’考えて 解答を作っていきましょう。
ちなみに、「いやいや限界利益がマイナスで、作れば作るだけ、赤字を垂れ流して、恐らく体力のないC社に設備投資しろなんて、そんな助言できるか。設問文にも‘経営資源などを勘案して’と書いてあるではないか。設備投資するなどありえない」と、お考えの方がいらっしゃるかもしれません。
ですが、現在の限界利益がマイナスの状況を考慮する必要はありません。
第8段落の記述を見てみましょう。「C社社長は、まず現状の生産管理を見直し、早急に収益改善を図ることを第1の目標としているが、それが達成された後には新事業に着手してさらなる収益拡大を目指すことを考えている」と、書いています。
C社社長は、最優先課題の現状の生産管理を見直し、早急に収益改善を図ることができた後に、つまり、第2問の対応が完了し、収益が改善した後に、新事業に着手してさらなる収益拡大を目指そうと考えているのです。
そうすると、足もとの収益ダメダメ具合は関係なくなります。
「どちらでもいい」これが、私の第4問における結論です。
最後に、後輩Bの解答例を見ておきましょう。
解答例③後輩B
第1問
(a)
規格外の野菜を有効活用できる加工技術力及びカット野菜の一貫生産体制の保有である。
(b)
①生産管理が組織的にできていない②調達力が低く通年取引要望に応えられていない。
第2問
短期的には、一般消費者向けのカット野菜パック事業を提案する。理由は現在の製造工程を利用でき、新たな設備投資が不要なため。対応策は、衛生管理の徹底で鮮度を保つことである。長期的には、ソース等の高付加価値事業を提案する。理由は高い収益性が見込めるため。対応策は新設備を扱える作業員の育成を行うことである。
どちらにすればよいか、判断が付かなかったのでしょう。短期的と長期的という切り口から、両方の事業を提案しています。
恐らく本試験会場で28年度試験を受けられた方の中には、後輩Aと同じように悩んだ末に、両方の事業を提案した方もおられるでしょう。
しかし、先ほどから申し上げている通り、診断士試験の「正解」は1つではありません。どちらを選んでも与件文に基づいて答えられていれば点数をもらえます。
後輩Bの答案を見ていただくと分かる通り、無理やり2つの事業に関する提案を書いたばかりに、「提案する事業名」や「理由は」、「対応策は」、「短期的には・長期的には」といった言葉が重複し、肝心の理由や対応策をまともに書くことができていません。
リスク分散する必要などないのに、リスク分散を試みた結果、書きたいことが書けなくなってしまうなんて、本当に悲しいですね。とにかく「どっちつかず」の解答を作るのはやめましょう。
(設問の切り分けが出来ずに両方に要素を盛り込む、という対応とは別の話です)
それと私が気になったのが、「理由は現在の製造工程を利用でき、新たな設備投資が不要なため」という記述です。「新たな設備投資が不要」とは、与件文のどこにも書いていません。思い込みで答案を作ってはいけませんね。
もう一度与件文の記述を確認しておきましょう。
<ソースなどの高付加価値製品事業>
カット野菜を原料としたソースや乾燥野菜などの高付加価値製品の事業であり、設備投資を必要とする事業
<カット野菜パック事業>
②新鮮さを売りものにしている中小地場スーパーマーケットなどから要望がある一般消費者向けのサラダ用や調理用のカット野菜パックの事業であり、現在の製造工程を利用できる事業
対比すると分かりやすいですね。「片方は設備投資を必要とする」と書いておきながら、「もう片方は設備投資不要」ではなく、「現在の製造工程を利用できる」という表現に止めています。受験生に「カットパック野菜事業は設備投資不要」と書いてほしいのなら、素直な事例Ⅲなら「そう書いてある」はずですが、わざわざ書いていないのです。
思い込みは禁止です。本当に気をつけましょう。
ここからは第4問に対する私なりの「思うところ」です。
設問文には「顧客からの新たな取引の要望、およびC社の生産管理レベルや経営資源などを勘案して計画しようとしている」との記述があります。
①顧客からの新たな取引の要望
与件文に記述がある通りですね。でも、わざわざ「顧客からの」と書いているのが気になりますね。「新たな取引の要望」でもいいのに‘わざわざ’「顧客からの」と書いているのです。
「これまでに取引のなかった企業」や「これまでに取引のなかったスーパー」では、「作問者が想定する受験生に答えさせたいこと」に誘導できなくなる恐れがあったのでしょうね。
②生産管理レベル
生産管理と言えば、「計画→統制→実行」ですが、第8段落の「現状の生産管理を見直した後」という記述から、ここでいう生産管理レベルとは最終段落に記載がある「衛生管理」のことを言いたかったということでしょうか。
③経営資源
ここは、まさに「第1問の強みと弱みを考慮しろ」ということだと思います。「X農業法人との関係が強み」で、「X農業法人との関係に着目した新たな取引要望」なのですから、X農業法人からの野菜をちゃんと使って新事業をしなければなりませんね。
④営業面
顧客から既に要望がある訳ですから、営業面の解答優先度は低いでしょう。
ちなみに、特性要因図は4M(man、machine、method、material)で作られています。皆さん、気付かれましたか?
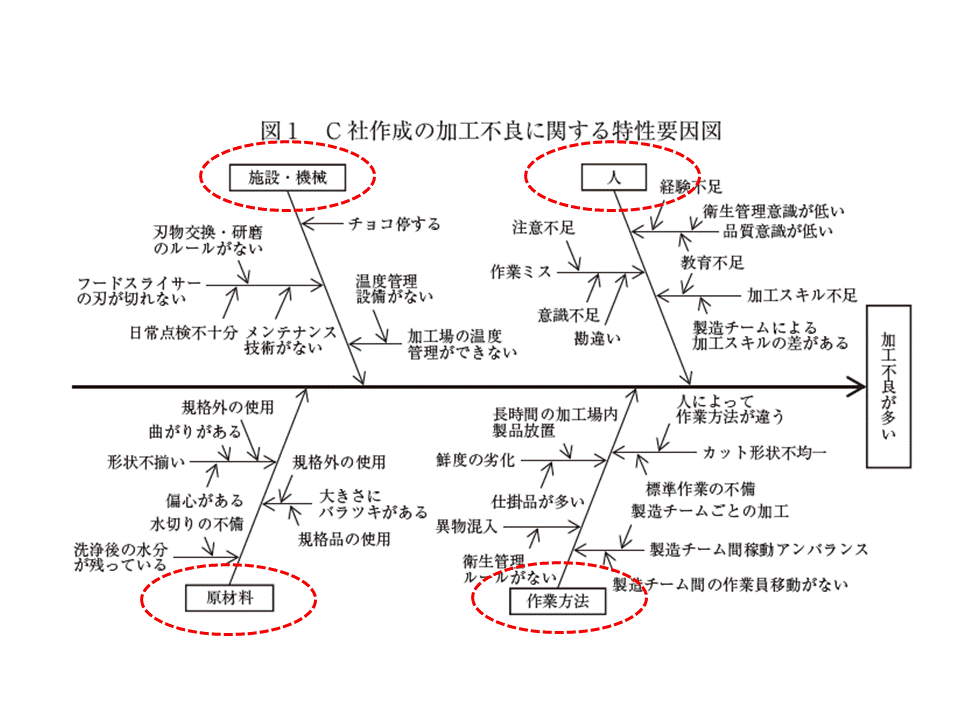 解説は以上です。
解説は以上です。
平成28年度試験は、冒頭にお示しした、4つの切り口の順番通りに出題されていますね。ちなみに平成29年度試験は、現状把握系の問題がなく、第1問が生産管理系、第2問が生産性改善、そして経営戦略の問題が2問(第3問、第4問)出題されました。
事例Ⅲは、本当にパターンが決まっているので、今年は絶対に60点以上を目指してくださいね!
長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。
以上、だいまつでした。

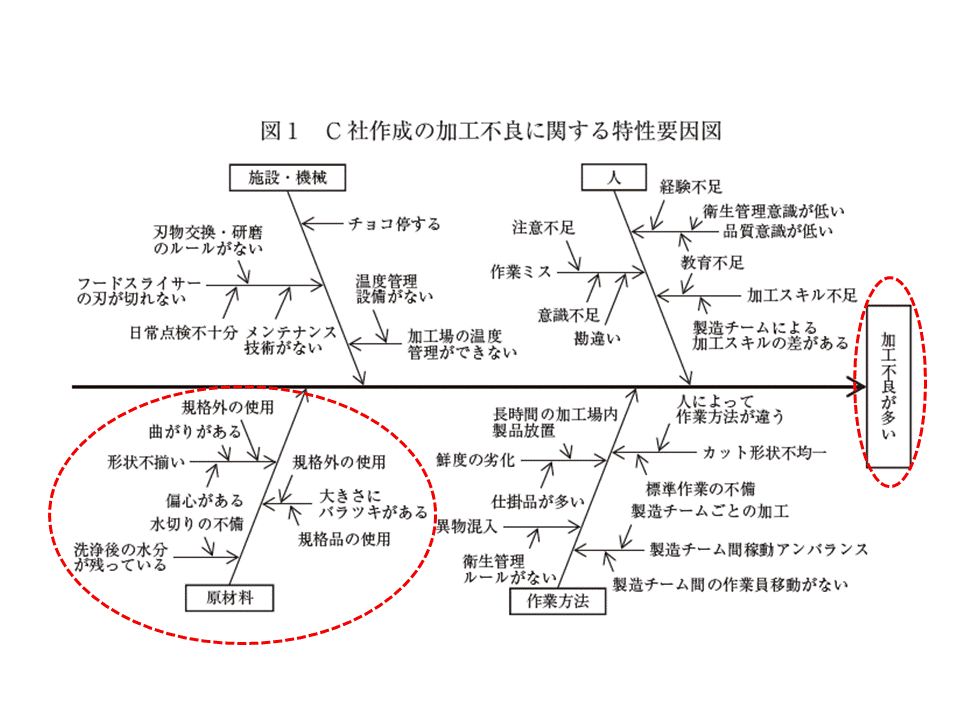
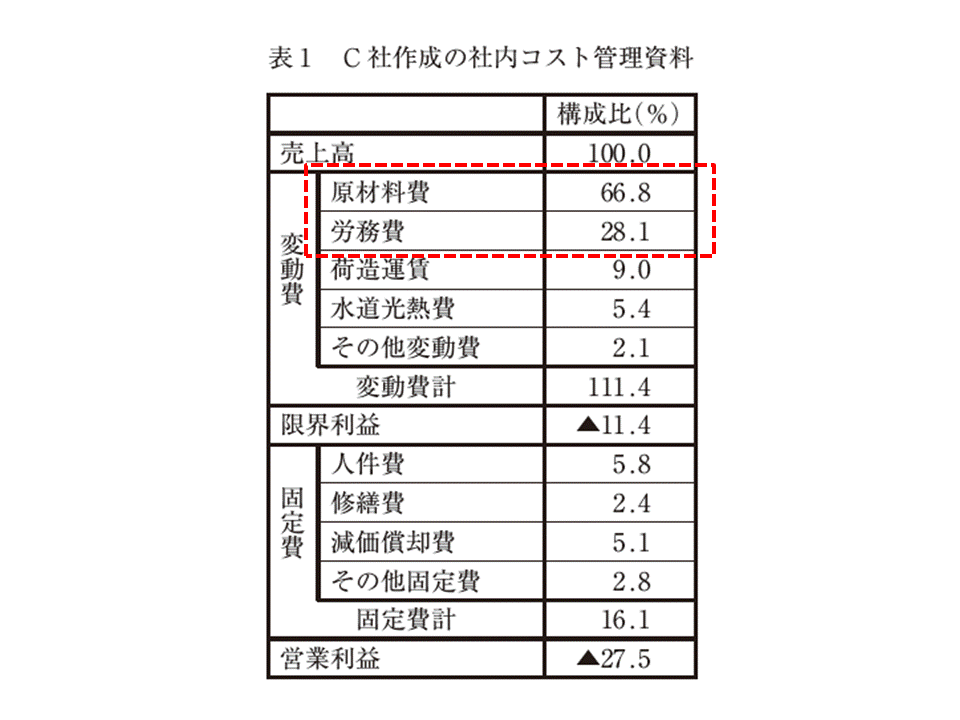
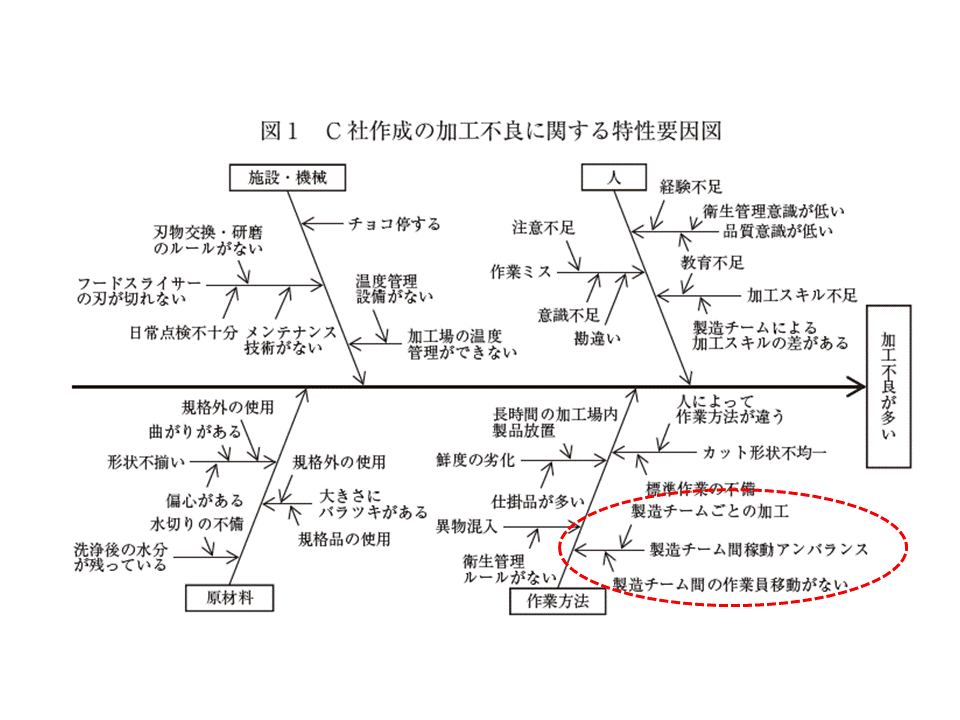

業務の閑散→業務の繁閑
ありがとうございます!
だいまつさん、はじめまして。今年の2次試験を受験する者です。現在、過去問演習に取り組んでいます。
29年度の事例Ⅲの記事に感動し、さらにダメ押しのように28年度の事例Ⅲの解説を読んで感動しました。というのもガチ文系なので生産管理に苦手意識があって、事例Ⅲについても難しく考えていました。だいまつさんが繰り返し説かれる「4つの切り口」を見て思わず「なるほど、そうか」と唸ってしまい、まさに目の前の霧が晴れた思いです。ありがとうございました。しばらく事例Ⅲを集中的にやって、得点科目にしようと取り組んでいるところです。
28年度の問題は、4つの切り口がそのまま、その順番で問われた問題でした。各設問を、現状把握、生産管理(生産計画)、生産性向上、経営戦略の順番で考えて解くということで、非常にわかりやすい構造だったと思います。
その勢いで、27年度の事例Ⅲを昨日解いたのですが、生産管理(生産計画)と生産性向上の切り分けを悩みました。具体的には、第1問の(設問3)と第2問なのですが、どちらの切り口で考えるのかということです。私は、第1問(設問3)を生産管理(生産計画)、第2問を生産性向上と考えました。
答え合わせということで、尊敬するきゃっしいさんの「解法実況」を読んだのですが、それによると、レイヤーとしては、第1問(設問3)が生産性向上、第2問が生産管理としたうえで、実際の解答ではそれぞれに生産計画と生産性改善の内容を盛り込むという形になっていました。きゃっしいさんいわく「切り分けが難しく、80分という制限時間の中では、厳密な切り分けよりも若干の重複をは仕方ない」と述べられています。
一つの問題の中に、生産管理と生産性向上という2つの切り口から解答要素を盛り込むこともありうるのかなと悩んでいます。
文章が長くなり恐縮です。だいまつさんのお考えをお聞かせください。
ぴーすけぱぱさん
返信が遅くなりました。
いまだに私の過去記事を読んでいただいているとのことで大変嬉しく思います。
さて、平成27年度の事例Ⅲですが、はっきり言って現場で切り分けするのは不可能です。私もきゃっしいの意見に賛成で、現場対応として重複して解答するのが現実的な対応だと思っています。
二次試験は合格ライン上に受験生がひしめいています。そのなかでゼロイチの賭けをするべきではありません。もし切り分けに失敗すれば(正解とアベコベに解答した場合)、40点近くを吹き飛ばすことになり合格は絶望的なものとなります。
現場で「げっ、これ本当に切り分けできない・・・、やばい。マジで分からない。どうしようどうしようどうしよう。」となったら、迷わず「2つの解答要素」を盛り込んでください。
はっきり言って「私の記事をしっかり読んで対策をしておられるぴーすけぱぱさんが切り分けできない問題」は、他の受験生も切り分けできません。最終的な調整も入るはずです。極めて難しい問題に対して、2つの解答要素を盛り込んで20点/40点、50%の得点率なら十分ではないですか!!
引続き事例Ⅲの鍛錬に取り組んでくださいね。そして合格したら診断士業界のどこかにいる私を見つけて是非声をかけてくださいね~。
だいまつでした。
匿名さん
コメント頂きありがとうございます。
この記事をアップしてから一年弱になりますが、まだ皆さんにお読みいただけているとわかり大変に嬉しいです。
拙い内容ではありますが、匿名さんの合格のお役に立てば何よりです!がんばってください!
凄い記事ですね
圧倒的に凄い
ちょっと感動するレベル
ななしさん
コメントへの返信が遅くなりました。
ななしさんのお役に立てたようでうれしいです。今回28年の事例Ⅲを分析して思ったのが、「本当に与件文に答えさせたいヒントが埋め込まれている」ということでした。4つの切り口をヒントに与件文を見る、そして変にいじらないでそのまま書く、これが本当に大切だと思います。
今年は絶対60点獲得、そして合格。キメて来てくださいね!
10月21日は朝起きたら、ななしさんが事例Ⅲで60点取れるよう、願掛けしておきます!
本当に頑張ってください。
だいまつさん、以前の記事でH28年版をリクエストしたものです。お忙しい中、対応していただきありがとうございます。
今回も素晴らしい記事ですね!
わたしは事例3については、H29年 46点/H28年 45点と苦手としており、特にH28については自分としてはできたと思っていたのに、45点という結果でかなり落ち込みました。そのトラウマとなる事例をだいまつさんの解説で理解することができました。
ご教示頂いた、4つの切り口を必ず身につけて、今年は60点を死守できるよう頑張りたいと思います。ありがとうございます。