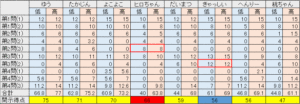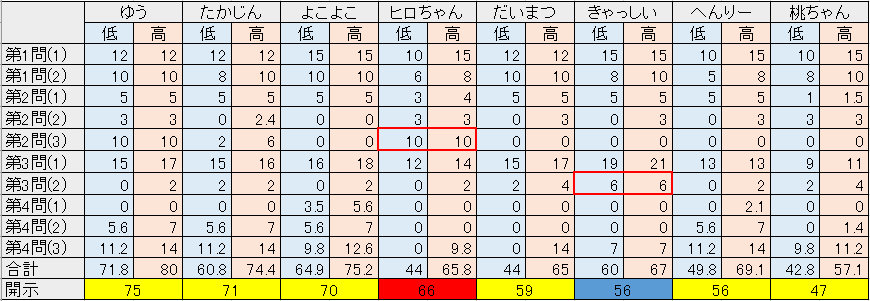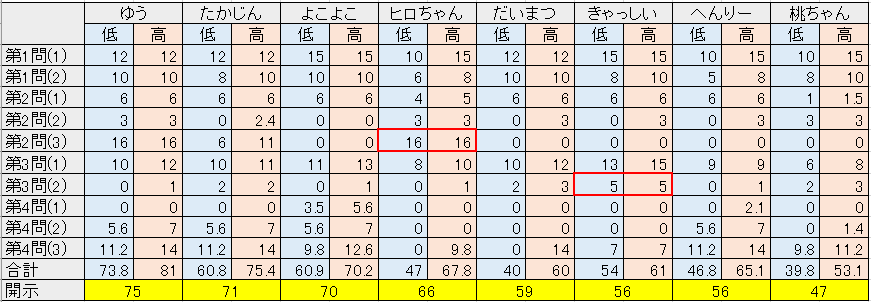【大胆仮説】再現答案の比較からの「事例Ⅳの配点操作説」
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
おはようございます。
きゃっしいです。
今日は、得点開示以降ずっとモヤモヤしていた、事例Ⅳの得点配分について、大胆な仮説を提唱させていただきたいと思います。
その仮説とは、
事例Ⅳは、問題用紙に書かれている配点すら操作された説
です。
信じるか、信じないかはあなた次第です。
仮説を唱えるだけなら、都市伝説と変わらないので、今回は多少それっぽく、道場メンバーの得点開示結果を使いながら、この仮説を検証してみたいと思います。
まずは、道場メンバーの事例Ⅳの解答をふぞろいその他予備校の解答などを参考にしながら採点してみました。
予備校やふぞろいで答えが分かれる問題や文章で書く問題などはそれぞれ低い場合と高い場合で得点に幅を持たせました。
まずは、ふぞろいの配点をベースに得点をつけたものがこちらです。(表はクリックで拡大されます)
こちらをご覧いただくと基本的にほとんどのメンバーの採点結果が得点開示の幅の中に納まっていることがわかります。
しかし、ヒロちゃんと私、きゃっしいはその幅の中に納まっていないことがわかります。
ヒロちゃんはふぞろい採点よりも得点開示結果の方が高く、私は逆にふぞろい採点より得点開示結果が低くなっています。
では、その原因はどこにあるかとデータを見たところ、他の人と比べて明らかに違うのが、ヒロちゃんは第2問が設問3まで正解できており、私は第3問が設問2まで正解できているという点でした。
そうすると最初に浮かぶのが、ふぞろいの設問ごとの配点が実情に即していないという仮説です。ふぞろいの配点を見てみると、かなり妥当そうな配点になっていますが、受験生の得点状況からそれがいじられた可能性を考えてみます。
そこで、ふぞろい採点よりも得点開示結果の方が高く出たヒロちゃんの解けた第2問の設問3の配点を大きく、逆ににふぞろい採点より得点開示結果が低くなった私の解けた第3問の設問2の配点を小さくしてみます。
その結果がこちらです。
多少得点開示結果との差が詰まりましたが、まだ得点開示結果と採点結果には開きがあります。
特に、採点結果よりも開示得点の方が低くなっている私の方は、この操作でもほとんど変わりありません。
しかし、
- これ以上調整を行うと他の設問の得点が1点未満になるなど明らかに不自然になる
- そもそもヒロちゃんは第2問は前半多少の失点はあるが最後までできており、私も第3問は前半で多少の失点はあるが最後までできており、同じ大問の設問間の配点をいじって調整できる点数にも限界がある
- もし、配点に関係なく全体に何らかのゲタを履かせる措置がなされたと考えた場合も採点結果より開示得点の高くなったヒロちゃんの方は説明がつくが、採点結果より開示得点の低くなった私の方は説明がつかない
以上から、大問の中での点数調整だけでは開示得点の説明がつかず、採点結果と開示得点の整合性が取れません。
採点結果と開示得点の整合性が取られるためには、大問ごとの得点配分が実は操作されていたと考えるのが最も自然だと思われます。
では、どう操作されたかということですが、上記で説明したような採点結果と開示得点のズレを鑑みると、第2問の配点が実は18点ではなくもっと高く、第3問の配点が29点ではなくもっと低くなるよう操作されたいう仮説が導き出されます。
そこで、この仮説を踏まえ、大問ごとの配点を少しいじってみます。
具体的には、第3問の設問2の配点を指標名・値・投資の有無を各1点にまで減らし、その分の配点を第2問の設問3に加えるという操作を行ってみたものが下記の表となります。
いかがでしょうか。
若干無理やり感がありますが、全員開示得点が採点結果の幅の中に納まりました。
これなら、ヒロちゃんと私の採点結果と得点開示結果の差に説明がつきそうです。
配点操作仮説はそれなりに説得力があるのではないでしょうか。
しかし、採点結果より開示得点が低かったというサンプルが私だけだと「実際はそそっかしいきゃっしいが解答欄を間違えてしまっただけじゃないの?」という声も聞こえてきそうです。
そのため、この配点操作仮説を裏付けるもう1つの例を挙げたいと思います。
ここで、私と同じく第3問設問2を解くことができた、Kyonさんの再現答案のお力もお借りさせていただきます。
Kyonさんとは、タキプロやマスターコースでご一緒させていただいており、得点開示の後同じモヤモヤを抱えたのがきっかけでお友達になりました。タキプロではWeb勉強会班のリーダーを務める、面倒見の良いお方です。
それでは早速、私とKyonさんの再現答案とその採点結果を以下に示します。(配点はふぞろいベース)
こちらの結果を見てわかる通り、私もKyonさんも第1問、第3問はほぼ全部解答できているため、この2つの大問の得点だけで50点前後得点できているはずです。
さらに、私の場合ですとそれに加えて第2問の設問1、第4問の設問3の一部ができています。
他の方の得点の状況を見ても、これらの部分点が合計で6点とは考えにくいです。
またKyonさんの場合、第1問、第3問に加えて第2問も最終問題以外はできています。
さらに第4問も一部できていますので、これらを全部合わせた部分点が18点しかないというのは考えにくいです。
その他にも、人づてですが、同じく第3問ができたのに開示得点が思った以上に低かったという方がいたという話も聞いています。
上記のように、道場メンバーの得点状況の比較と、私とKyonさんの得点状況の比較を踏まえると、この第3問の配点に何らかの手が加わったと考えたほうが自然ではないでしょうか。
以上、ちょっと挑戦的な仮説を唱えさせていただきました。
さて、仮説を唱えっぱなしで終わってしまうとこの直前期に無駄な混乱を招くだけになってしまいますので、最後にこの仮説から今年の試験対策にどう活かすべきかという私なりの考えを紹介したいと思います。
今回、私は運良く第3問を解くことができましたが、試験後に多くの合格者と話をしていても、第3問が最後までできたという人はかなりレアでした。
しかし、それと比較すると第2問ができたという人はそれなりに多くいました。
これはあくまでも私の肌感覚ですが、恐らく実際に採点をしていても、第2問はみんなそれなりにできていたのに対し、第3問ができた人は相当少なかったのではないかと思います。
そのため、設問をいじるだけでは得点の調整がつかず、大問間での得点調整を行うに至ったのではないかと考えられます。
このことから言えるのは、みんなが取れない難しい問題が取れたとしても、調整が行われる可能性があるということです。
以上から、確実に合格点を確保するためには、難しい問題を無理して完全に解こうとする前に、まずはみんなが取れる問題を確実に取ることが重要だといえます。
上記は、得点調整があってもなくても重要なことですが、仮に昨年大問間の得点調整が実際に入っていたとすると、もともと重要なこの鉄則がさらに重要になります。
さて、残された時間も僅かですので、この得点調整仮説からの知見を今年の試験対策に活かすとすると、
というのが私からのメッセージです。
残り時間も僅かになってきました。
残された時間を有効に使い、合格へと走り抜けていきましょう!
以上、きゃっしいでした。