ビジネス会計検定の世界 by サトシ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
一発合格道場ブログを
あなたのPC・スマホの
「お気に入り」「ブックマーク」に
ご登録ください!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
みなさん、こんばんは。レジェンド投稿シリーズ担当のサトシです。
レジェンド投稿シリーズはいかがでしたでしょうか?
今日はクリスマススペシャルとして、2本立てです。
2本目の投稿メンバーは、、私です(笑)

おい、サトシはレジェンドメンバーじゃないだろ(笑)
はい(笑)レジェンドメンバーじゃないけど、クリスマスは独り者には寂しいし、たまには私にも語らせてよ
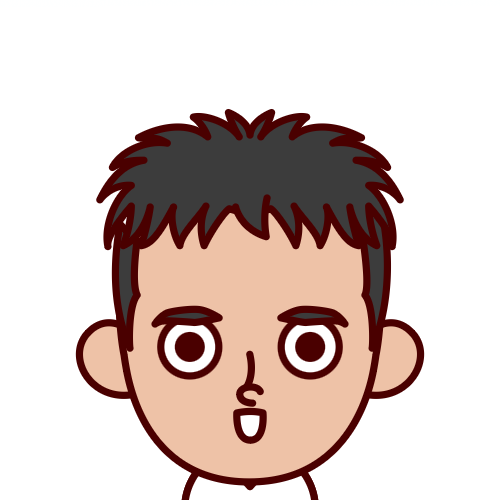

あうあ、あうう~、キャッキャ!!
(15代目で一番多く語ってるサトシは「たまには」じゃないでしょ!!)
というわけで、2本目はサトシによる「ビジネス会計検定」の紹介記事になります。
それでは、2本目もよろしくお願いします。
最近のサトシ
1.記事の執筆の締め切りに追われていました
この道場の記事ではなく、診断士の仕事としてお金をいただくものとして、雑誌や業界誌の記事を執筆させていただいております。ありがたいことに多くの記事執筆のお仕事をいただいており、毎月何かしらの記事を執筆していて、その締め切りとの戦いになっております。
それから、診断士受験生に有名な参考書である「まとめシート」。こちらは毎年、一発合格道場のメンバーも何人か関わらせていただいております。私も関わらせていただきまして、ようやくその仕事がひと段落しました。
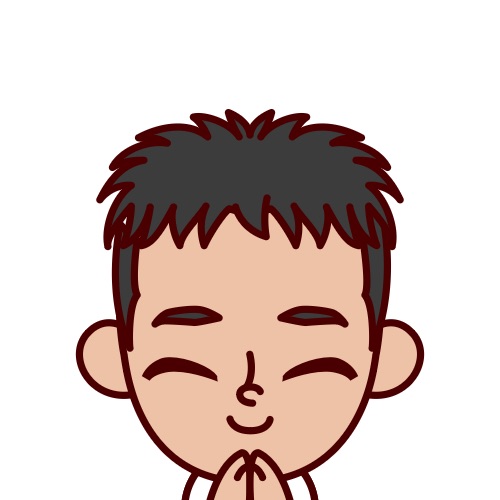
どちらも「仲間」からの紹介です。いつもありがとうございます
ちなみに、今一瞬でも「サトシはどうやって仕事をもらったんだ?」という思いが頭によぎった方、そんな方に向けて別の機会にこの秘訣を書かせていただきます。
2.実務補習先の店舗に行ってきました
私は今年の7月に実務補習を受けたのですが、小売店なので実務補習後も顧客として定期的に店舗に行っています。おかげで実務補習先の社長には大変気に入られております。はい、「長期継続顧客」ですね。LTVの要素の「頻度」と「期間」で実務補習先の収益に貢献しています。
今一瞬でも「なんでサトシはそんなことまでしてるの?する必要なくない?」と思った方、そんな方に向けても別の機会に私がそのようにする理由を書かせていただきます。

「診断士のコミュニケーション、診断士のメンタル、サトシのコミュニケーション&メンタル、伴走支援って?」という番外編記事を絶賛執筆中です
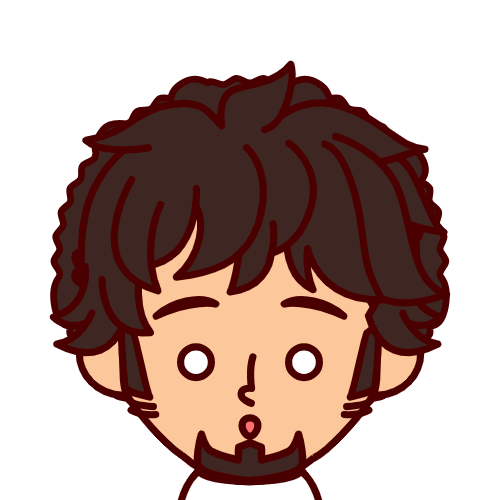
この人、どれだけ番外編の記事を書いてるんだ?(笑)
ビジネス会計検定って?
みなさん、ビジネス会計検定ってご存知ですか?
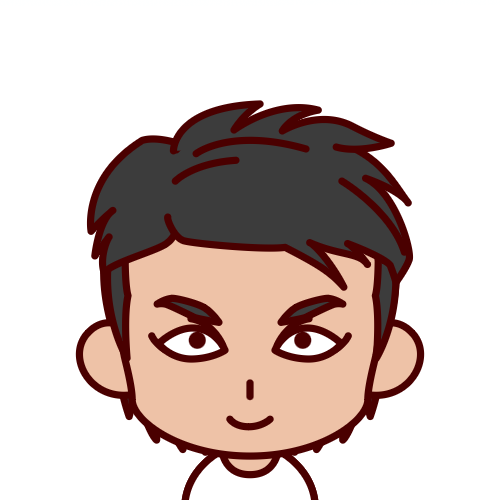
え?何それ?簿記検定と何が違うの?
そりゃそうなりますよね。
簿記検定に比べると知名度は圧倒的に低いですが、ビジネス会計検定は大阪商工会議所が主催のれっきとした検定試験です。こちらがビジネス会計検定のホームページです。
実は、予備校で簿記検定のパンフレットを入手したら、関連資格のところにチラッとだけ書いています。例えばTACのホームページの簿記検定のところをご覧ください。すみっこのほうにありますから。
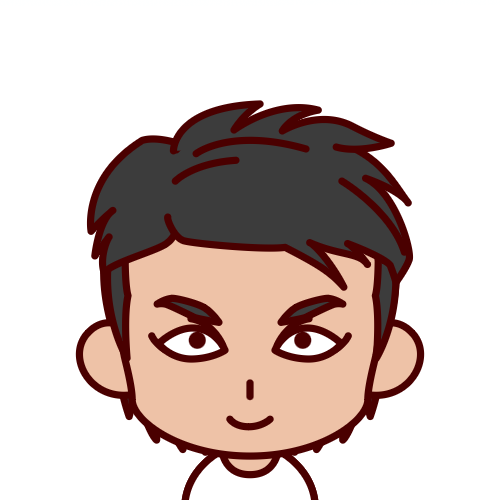
あ、確かにすみのほうに「ビジネス会計検定」ってあった!
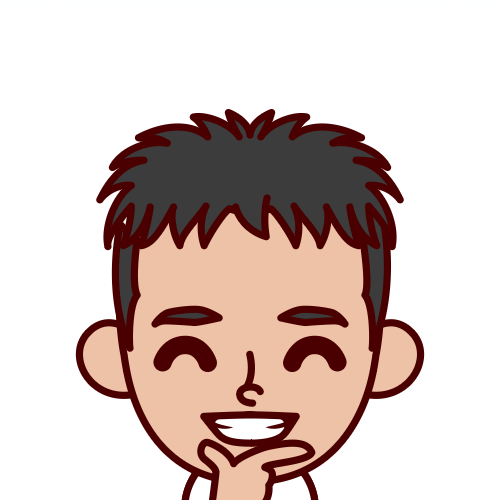
そう。まさにすみっコぐらし!(今日はクリスマスイブなので、お子さんにこちらのグッズを買った方もいらっしゃるのでは)
ちなみに、私はすみっコぐらし、ちいかわ、サンリオなどの「かわいい系のキャラクター」は大得意です!ご当地ゆるキャラもかわいいものなら大歓迎ですよ!
・・・お前の嗜好などどうでもいいから早く話を始めろ、と言われそうですね(笑)
というわけで話を戻しまして、そんなビジネス会計検定の1級を私は持っています。そこで今回は私がビジネス会計検定の内容や魅力、診断士試験に役立てる方法などについて解説していきます。
なお、この記事を書くきっかけは道場メンバーきっての財務のプロ、せーでんきの

日商簿記1級の取得者はたまにいるけど、ビジネス会計検定1級の取得者は稀だから、書いてみたら?
というニーズでした。
(せーでんきの簿記1級に関する記事はこちら)
ニーズが来たら最適なものを提案しないといけないですからね。
というわけで、私がビジネス会計検定の内容を紹介することになりました。
ビジネス会計検定で習うこと
ビジネス会計検定で扱うものは、基本的には「経営分析」と「会計原則」です。逆に簿記検定では定番の簿記の仕訳や精算表などは扱いません。
どちらかと言うと、財務諸表を作るまでの話(これは簿記検定の範囲)よりも、作った後の財務諸表の分析や見方のほうに重点が置かれています。

(TACビジネス会計検定講座ホームページより)
そのため、「決算書の数字に強くなる」というイメージですね。そのTACのビジネス会計検定のページにもこのような説明があります。
簿記検定は「記録→計算→整理→財務諸表の作成」に対する理解が問われます。一定のルールにしたがって適切な会計処理を行い、活動の情報を提供するための財務諸表を作成するまでの一連の手続きに対する理解力を問う試験です。
(TACビジネス会計検定講座ホームページより)
これに対して、ビジネス会計検定は「財務諸表の理解→情報として役立てる→企業の良否判断」に対する分析力が問われます。財務諸表に関する会計基準・関連法規・構造などの知識や分析を通じて、財務諸表が表現している企業の財政状態・経営成績・キャッシュフローの状況を判断できる能力が問われる試験です。
主催の大阪商工会議所も、このように説明しています。
ビジネス会計検定試験は、財務諸表に関する知識や分析力を問うもので、財務諸表が表す数値を理解し、ビジネスに役立てていくことに重点を置いています。簿記検定は、日々の取引を記録し、仕訳などを通して財務諸表を作成するプロセスを主な範囲としています。 これに対してビジネス会計検定は、作成時に用いられた会計基準や法令を理解し、財務諸表を分析して企業状況を把握することを目的にしています。 新しい取引先や投資案件を評価する、自社の決算内容を理解する、株式投資をする新聞記事を理解するなど、あらゆる場面で会計の知識が求められます。 経理部門の方に限らず、様々な方に会計の知識は役立ちます。 本検定試験は簿記の知識を必要とするものではなく、実社会で役立つ会計の知識を習得するのに有効です。
(大阪商工会議所ホームページより)
また、このような案内図もありました(大阪商工会議所ホームページより)

なので、簿記検定よりもビジネス会計検定のほうが診断士の「財務・会計」との相関性は高いかと思います。診断士の財務も、どちらかと言うと経営分析・CVP分析の分析系の問題や会計原則の問題が多く、仕訳の問題はあまり出ませんからね。
3級と2級ならそこまで負担ではありませんし、診断士試験の1次「財務・会計」や2次事例Ⅳに出てくる経営分析やCVP分析、会計原則を苦手とされる方は受けてみてもいいかもしれません。

簿記2級もいいよ(詳しくはこちら)
3・2級の範囲と合格率
3級と2級ではそれぞれ以下の内容を扱います。
3級の試験範囲
1.財務諸表の構造や読み方に関する基礎知識
(1)財務諸表とは 財務諸表の役割と種類 (2)貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書の構造と読み方 貸借対照表(資産、負債、純資産)・損益計算書(売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益)・キャッシュ・フロー計算書の内容
2.財務諸表の基本的な分析
(1)基本分析 (2)成長率および伸び率の分析 (3)安全性の分析 (4)キャッシュ・フロー情報の利用 (5)収益性の分析 (6)1株当たり分析 (7)1人当たり分析
3級の合格率は70%くらいです。
.jpg)
診断士の勉強をしている方なら、おそらくちょっと問題集を解くだけで受かります
2級の試験範囲
1.財務諸表の構造や読み方、財務諸表を取り巻く諸法令に関する知識
(1)企業会計の意義と制度
企業会計の役割、企業会計の制度(金融商品取引法・会社法の会計制度、金融商品取引所の開示規則)
(2)連結財務諸表の構造と読み方
財務諸表の種類、連結貸借対照表・連結損益計算書・連結包括利益計算書・連結株主資本等変動計算書・連結キャッシュ・フロー計算書の内容、連結付属明細表と注記(すべて個別財務諸表の内容も含む)
2.財務諸表の応用的な分析
(1)基本分析(2)安全性の分析(3)収益性の分析(4)キャッシュ・フローの分析(5)セグメント情報の分析(6)連単倍率(7)損益分岐点分析(8)1株当たり分析(9)1人当たり分析
2級の合格率は40〜50%くらいです。
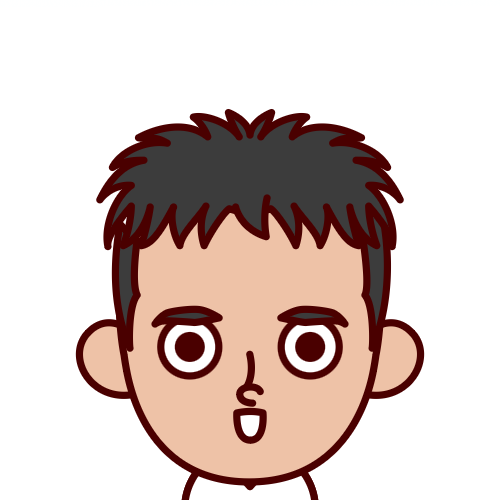
2級はちょっと真剣に勉強をやらないと合格できないかもしれません
ビジネス会計検定の試験は3月と10月にあります(1級は3月のみ)ので、3月に2級や3級を受けてみるのもいいかもしれませんね。1次の「財務・会計」も2次の事例Ⅳも、経営分析・CVP分析の分析系の問題や会計原則の問題が安定して解けるようになりますよ(少なくとも苦手意識やコンプレックスはなくなります)。
1級の範囲と合格率
さて、2級まではこのような範囲と合格率ですが、1級になると一気に難易度が上がり、合格率が下がります。
大阪商工会議所のビジネス会計検定のホームページには、1級の説明としてこのように書かれています。
会計情報に関する総合的な知識として、投資関連の各種ディスクロージャーや財務諸表と計算書類の総合的な理解を深めます。特に財務諸表をより深く読み解くためにその構成要素のうち重要なものについて、会計基準の内容を理解し注記を含む補足情報の読み方について学習します。財務諸表分析は、より深く財務諸表を分析するための方法を学習します。また、概念フレームワーク、会計基準、内部統制やマネジメントにおける事業評価などにも活用できる企業価値分析の基本的な考え方や分析方法についてもビジネス会計の応用領域として学習します。
企業の成長性や課題、経営方針・戦略などを理解・判断するため、財務諸表を含む会計情報を総合的かつ詳細に分析し企業評価できる力を身につける。
(大阪商工会議所ホームページより)
、、、はい???
各種ディスクロージャー?概念フレームワーク?内部統制?
何言ってるのかワケワカメという方もいらっしゃるかと思います。ニヤニヤと喜んでいる公認会計士のせーちゃんを除けば(笑)
1級は会計士や税理士、簿記1級などの受験生、会計専門職大学院の学生をメインターゲットにしているので、こういう「せーでんきが喜びそうなフレーズ」が多くなっています。

いやいや、サトシみたいなへんt・・・じゃないからそんなフレーズ見ても喜ばないよ(笑)
あれ?そうなの?とりあえず、バナナ食べて落ち着こう(笑)

気を取り直して、1級の試験範囲はこのようになっています。
1級の試験範囲
1.会計情報に関する総合的な知識
ディスクロージャー
ディスクロージャーとは、会社法上のディスクロージャー、金融商品取引法上のディスクロージャー、証券取引所が求めるディスクロージャー、任意開示、ディスクロージャーの電子化
財務諸表と計算書類 財務諸表と計算書類の体系、連結損益計算書・連結包括利益計算書・連結貸借対照表・連結キャッシュ・フロー計算書、連結株主資本等変動計算書の内容
財務諸表項目の要点 金融商品、棚卸資産、固定資産と減損、繰延資産と研究開発費、引当金と退職給付、純資産、収益の認識、外貨換算、リース会計、税効果、会計方針の開示および会計上の変更等、連結財務諸表注記と連結附属明細表、セグメント情報、企業結合・事業分離
財務諸表の作成原理 概念フレームワーク、会計基準、内部統制
2.財務諸表を含む会計情報のより高度な分析
財務諸表分析
分析の視点と方法、収益性の分析、生産性の分析、安全性の分析、不確実性の分析、成長性の分析
企業価値分析 企業価値評価のフレームワーク、割引キャッシュ・フロー法による企業価値評価、資本コストの概念、エコノミック・プロフィット法による企業価値評価、乗数アプローチによる企業評価、これからの企業価値評価
いかがですかね?明らかに「診断士試験より上のオーバースペック感」が漂っていますよね。
連結包括利益計算書?連結財務諸表注記と連結附属明細表?エコノミック・プロフィット法?なんじゃそれ?
そうです。1級は診断士受験生にとってはオーバースペックです。明らかに1次「財務・会計」の問題、2次事例Ⅳの問題よりレベルが上です。
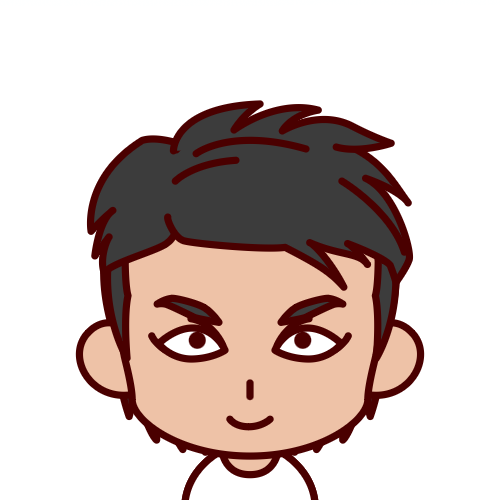
いやいや、リース会計とか診断士の試験でもやるでしょ?
範囲としては診断士試験でも扱うものでも、レベルが全く異なります。診断士試験は「入門・基礎レベル」の内容ですが、ビジネス会計検定1級は「応用レベル」の内容で、診断士のテキストに載っていないものもかなりあります。
そのため、こういう内容をこなせるのはどこかの会計士のせー●んきくらいでしょう。普通の診断士じゃ太刀打ちできません。
ということで、どうしても内容が気になる方はせーで●き宛てに質問をどうぞ(笑)

おい、こっちに振るな(笑)
バナナならなんぼでも振ってやるぞ

試験も一部マーク式、一部記述式になります(3・2級はマーク式のみです)。イメージとしては、1級のマーク式問題は診断士の1次「財務・会計」の問題、記述式問題は2次事例Ⅳの問題ですが、難易度やレベルは明らかに診断士より上です。内容的にも先ほどのワケワカメなフレーズやなんじゃそれの範囲のように、診断士試験で明らかに扱わないものもあります。
そのため、1級は診断士受験生にとってはオーバースペックです。

オーバースペックのことにこだわると、どこかのサ●シみたいに超多年度になっちゃうぞ
なお、1級の合格率は10〜25%程度です。こんなにバラつくのは1級の試験では珍しいです。おそらく診断士の2次試験や日商簿記検定1級のような相対試験ではなく、ある程度は絶対試験の性質があるのだと思います。
25%の回なら問題は簡単、逆に10%の回だと問題は難しく、最低でも10%になるように得点調整をしているものと思われます。
一応、2015年度からは1級の不合格者の得点上位者を「準1級」として認定しているそうですが、どちらにしてもオーバースペックです。
ちなみに、私は会計専門職大学院卒で、ちょうどビジネス会計検定の試験委員が私の卒業した大学院の教授だったので、教授からのゴリ押し、、もとい「教授から魅力を熱く語られて」私が受験することになり、運良く1回目で合格できました。私が受けたのは診断士試験の勉強をする2015年よりも前でしたが、その頃はまだ先ほどのワケワカメなフレーズやなんじゃそれの範囲がありませんでした。今受けたら絶対に無理です(笑)

お、サトシが一発合格とは珍しい(笑)
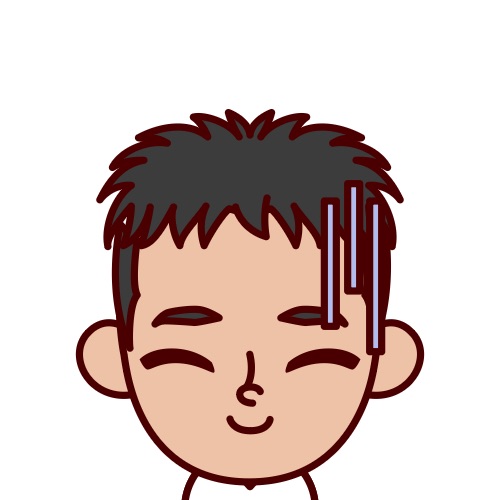
この後、まさか診断士試験に9年もかかるとはね(笑)
どうやって勉強する?
一応、3級・2級・1級ともに公式テキストが市販されています。しかし、これを見ても難しい説明がダラダラと書いてあって眠くなるだけです(笑)買うなら睡眠薬代わりにどうぞ(笑)
そのため、ビジネス会計検定の勉強をするなら公式問題集(版は違いますがサムネ画像になっているものです)、その他のビジネス会計検定用の市販問題集をやるだけでいいかと思います。2・3級なら問題集を解いて受験してもいいかもしれません。過去問で出題形式を頭の中に入れ、問題集を2周くらいさせれば合格できます。
なお、わからない問題があっても、必要な知識は診断士の「財務・会計」のテキストから補充できます。もちろん、その中では診断士の「財務・会計」のテキストに載っていない内容もあるかもしれませんが、診断士試験をメインにする限りはそのような内容を勉強する必要はありません。
また、受験しなくても診断士の試験対策として問題集だけやる手もあります。1次「財務・会計」や2次事例Ⅳの問題演習のバリエーションを増やしたい方にはオススメです。
おわりに
以上、ビジネス会計検定についてでした。いかがでしたでしょうか?
1級はオーバースペック。受けるとしても3月に2・3級だと思います。もし「財務・会計」や事例Ⅳが苦手な方がいらっしゃいましたら、ぜひビジネス会計検定の受験を検討してみてはいかがでしょうか?
今回もありがとうございました。
明日は「ばん」の登場です。

クリスマススペシャル!
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)

-300x169.jpg)

はじめまして。
記事を見させていただきました。
もしよろしければご回答いただけますと幸いです。
現在、ビジネス会計検定1級の受験を考えています。
来年の3月に受けようと思っていまして、
毎日1時間ずつ、直前2か月くらいは、毎日2時間ほど勉強可能かと思います。
難易度が高いのは十分承知しておりますが、合格は狙えそうでしょうか。
前提知識としては、
日商簿記2級、ビジネス会計検定3級はもっています。
中小企業診断士には合格していませんが、1次の財務会計は70点、
証券アナリスト1次試験の財務分析は合格できそうな水準でした。
他、財務会計や管理会計の書籍は多数読んでいます。
大変お手数ですが、もし可能でしたらご回答いただけますと嬉しく思います。
よろしくお願いいたします。
まっささん、コメントありがとうございます。
そのレベルだと、理論問題と経営分析の計算問題ならいけると思います。
逆に日商簿記1級で出る論点の計算問題が出されると厳しいと思います。
そのため、まずはまっささんご自身で過去問を見ていただいて、過去問がいけそうなら来年の3月のビジネス会計検定1級を目指してみてもいいかもしれません。
もし目指す場合は今年の2次試験が終わってから対策を始めても十分に間に合うと思います。
早速のご返事ありがとうございます。
日商簿記1級で出る論点の計算問題が出題されることもあるのですね、、
とても参考になります。
まずは過去問を一通り見てみて
目指すかどうかを考えてみようと思います。
とてもご丁寧にご返事いただきありがとうございました。
こんばんは!
にっくです。
ビジネス会計検定の記事、ありがとうございました!
丁度簿記で四苦八苦(まさに今日、2級落ちました・・・笑)していたところで、「また景色の良さそうな山が見えてしまったな・・・」という感じです。
とりあえず簿記に集中して、余力があればビジネス会計検定も受けてみたいと思います。
ありがとうございました!
にっく
にっくさん、コメントありがとうございます。
簿記検定とビジネス会計検定はまた違った景色ですね。
ぜひ、余裕があればビジネス会計検定にもチャレンジしてみてください。