設問文との付き合い方 by サトシ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
一発合格道場ブログを
あなたのPC・スマホの
「お気に入り」「ブックマーク」に
ご登録ください!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
みなさん、こんにちは。
「物事を考えるときは全体を鳥瞰的に」と言われてはいるものの、なかなか実行できない「サトシ」です。
今日は「設問文との付き合い方」という内容についてお伝えします。設問文について、「指示に従う」とか「必要な想起をする」とか「設問間の関係性を意識する」と言われてはいるものの、実際にこれらに関して正しくできている受験生は少ないです。もちろん多くの受験生からお悩み相談をいただいておりますし、2次試験の勉強会でもこれらができている人とできていない人の差が激しいです。そのため、設問文との付き合い方が2次試験の点数や合否のカギを握ってきます。
内容としては、設問1問の部分、設問1問の複数部分、設問1問全体、複数の設問というように、徐々に単位を大きくしていきます。
なお、設問文に関するプロセス(マークや線の付け方など)に関しては人によってやり方が異なりますので、対象外とさせていただきます。また、設問文から必要なプロセスを行うことや内容を想起することは「要求解釈」とか「設問分析」とか「設問解釈」と呼ばれますが、この記事では「要求解釈」に統一させていただきます。
ということで、今日の記事もとてつもなく長いですが(笑)、これ1回で設問文との付き合い方をすべて収めたほうがいいと思いましたので、お許しください(笑)
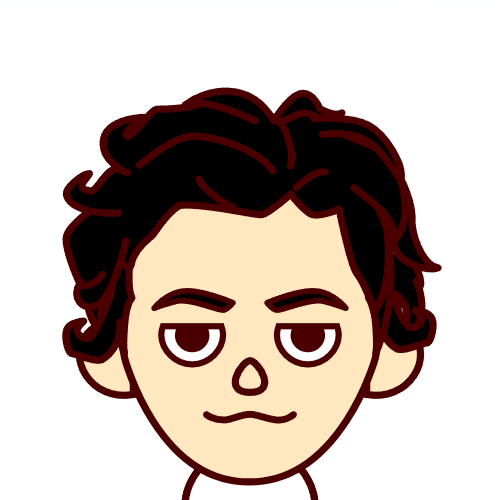
サトシは通常の記事2~3本分の長さの記事を毎回書いているへんた・・・です(笑)
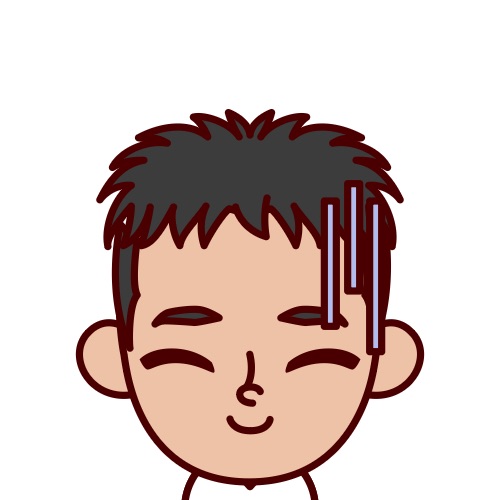
年末年始で時間もあるでしょうから、長い記事ですがお付き合いください
それでは、今回もよろしくお願いします。
- 1. 設問文に対する意識を変える
- 1.1. タイムマネジメントの意識をもつ
- 1.2. プロセスを構築し、プロセスごとに標準時間を定める
- 1.2.1. 設問文の分析(要求解釈)には10分程度かける
- 1.2.2. 設問文の分析に時間をかける決心はつきましたか?
- 1.3. 長い設問文・多い要求文字数の設問が来たらラッキーだと思う
- 1.4. 設問文にスラッシュを引く
- 2. 題意と制約条件を無視したらジ・エンド
- 3. 各部分について、①想起する、②与件文から見つけてくる
- 3.1. ①想起する
- 3.2. ②与件文から見つけてくる
- 4. トレーニング
- 4.1. 令和6年度事例Ⅰ第2問
- 4.2. 令和3年度事例Ⅰ第3問
- 4.3. 令和5年度事例Ⅲ第5問
- 4.4. 令和4年度事例Ⅱ第2問
- 5. このへんで休憩
- 6. 解答文も簡単に作れる
- 6.1. 令和4年度事例Ⅰ第4問(設問2)
- 6.2. 令和5年度事例Ⅲ第4問
- 6.3. 令和5年度事例Ⅱ第4問
- 7. ここでまた休憩
- 8. 設問間の関係性を意識する
- 8.1. 設問間の関係性のパターン
- 8.1.1. 並列
- 8.1.2. 順接(因果関係)
- 8.1.2.1. 第1問で出した強みを第2問以降の助言問題(機能別戦略の問題)で活かすパターン
- 8.1.2.2. 第1問で出した強みを(主に最後の)戦略系問題で活かすパターン
- 8.1.2.3. 第1問で出した弱みを助言問題(機能別戦略の問題)で解消していくパターン
- 8.1.2.4. 途中の設問で出てきた問題点・欠点を後の設問で解消するパターン
- 8.1.2.5. 前の設問の設問文に出てきた内容や解答内容の理論的な短所を後の設問で解消するパターン
- 8.2. 令和2年度事例Ⅰ第1問(設問1・2)
- 8.3. 令和3年度事例Ⅰ第1問・第4問
- 9. まとめ(2次ベテ勝利のストラテジー25改良版)
- 10. 今日のGRe4N BOYZ:ボクたちの電光石火
- 11. 次回予告
設問文に対する意識を変える
まずは設問文に対する意識から変えることからスタートです。
みなさんは設問文について、どのように捉えていますか?
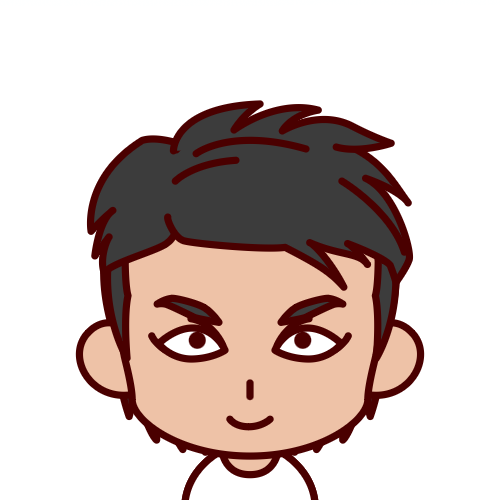
え?書いてあることを踏まえて解答すればいいんじゃないの?
また、設問文をちょちょいと片付けていませんか?設問分析をいつも10分以内に終わらせていませんか?

そらそうでしょ。設問文だけ見ていてもわからないやん!
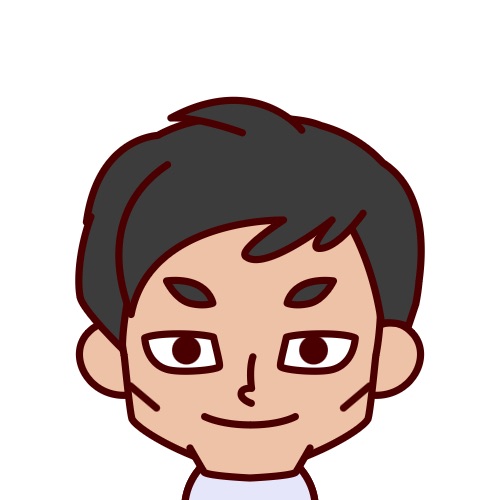
いやいや、それより与件文の内容でしょ?与件文を読まなきゃ具体的な内容がわからないでしょ!
こんなお悩みというか、ツッコミが来そうですね。
ですが、こう言っている人に限って設問文の分析(要求解釈)を軽視していて、2次試験後に「もっと鍛えておけばよかった」とか「設問文の分析が課題です」という感想を挙げています。
私がTAC名古屋校に通っていたときに、講師の津田先生(まどか先生)が演習の解説の際にクラスの受講生全体にこのようなことをよく言っていました。
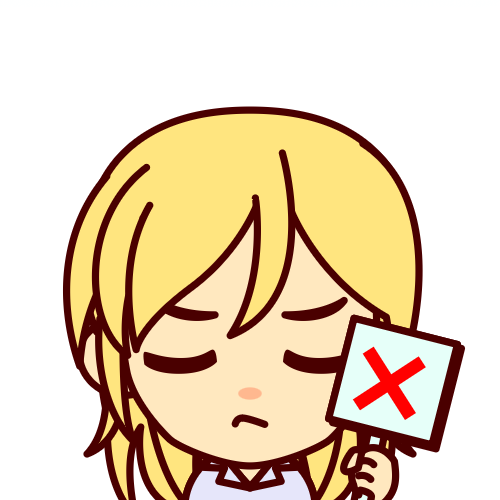
焦って先へ先へ急ごうとしすぎ!
設問文の分析(要求解釈)をしなさすぎ!
時間を余らせすぎ!
机の上に消しカスが多い!
はい、これはまさに2次試験受験生あるあるです!
先生が言うには、こういう受験生は設問文の分析(要求解釈)の時間が極端に短いそうです。要求解釈をほとんどせず、下手をすると3〜5分ほどで与件文の読解に入っているそうです。
与件文の読解も10分くらいで終わらせて、残り65分くらいは与件文の内容と解答用紙を行き来しながら、解答文を解答用紙に直接書きながら解答内容を考えているのです。
そして1割くらいの方が50〜60分、2割くらいの方が70分で解き終わっているのです。しかもあくびをしながら80分の終了時間までボケーっと待っているのです。
暇を持て余しているのか、余った時間で解答文の数文字くらいをちょくちょく直している方もいるそうですが、きちんと要求解釈をしていれば出せる肝心な内容が抜けていたり間違っていたりするため、ほとんど意味がありません。
演習が終わって休憩時間に入り、本人が席を外した机の上には大量の消しカスが残っています。解答内容を考えながら解答用紙に記入しているので、消しては直しの繰り返しで、消しカスが多いのです。
みなさんも心当たりがありませんか?
もちろん本試験でも同じ傾向があります。本試験の際に周りを見渡すと「え?早すぎない?」とか「ボケーっとしていて、時間がもったいなくない?」と思うような方がいますよね?
こういう人は「何でも短時間にできる天才」ではなく、「焦って先へ先へ急ごうしまい、いつ事故を起こしてもおかしくない人」なのです。時間切れになりたくないから、どうしても焦って先へ先へ急いでいこうとしてしまうのです。設問文をちょちょいと片付けてしまうので、制約条件や題意をいつ外してもおかしくありません。こうなるといつ事故を起こしてもおかしくないため、点数が悪くなることはあっても良くなることはありません。
タイムマネジメントの意識をもつ
ここからはそういう先へ先へ急いでしまう方に向けた対策です。まずはタイムマネジメントの意識をもつことです。
2次試験はタイムアタックをする試験ではありません。早く終わったらボーナス点が入る試験ではありません。ボケーっと待ちながらあくびをしたら5点加点されるとか、そんな試験ではありませんよね。50分で終わろうが80分ギリギリで終わろうが同じように採点されます。それなら80分をフルに使ったほうが有利ですよね。
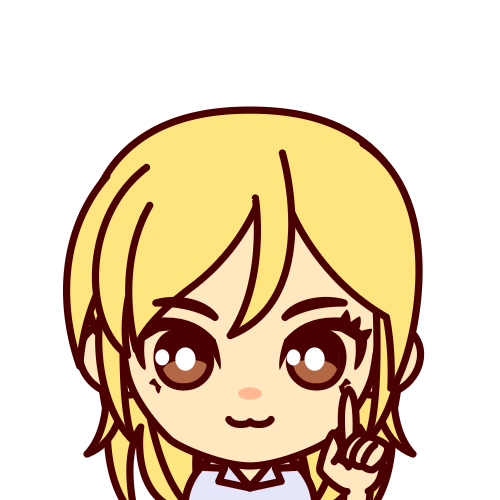
80分をフルに使う勇気をもちましょう!
プロセスを構築し、プロセスごとに標準時間を定める
次はプロセスを構築し、プロセスごとに標準時間を定めていきましょう。
80分をフルに使うためには、タイムマネジメントの意識をもち、プロセスを定め、プロセスごとに標準時間を決めることが大切です。例えば「要求解釈10分、与件文読解1回目5分、2回目10分、対応づけ10分、解答内容を考える+解答文を書く作業は残りの時間を問題数で割る」などですね。
そして、プロセスとそれぞれの標準時間を定めたら、今のうちからその時間でのプロセスに慣れておいてください。そうすると安定感が高まり、演習の際にも(もちろん本試験でも)時間切れになる心配がかなり減るので、焦って先へ先へ急ごうとする気も緩和されていきます。
もちろん演習を通じて「オレは1回目の与件文読解は3分でできそうだな」とわかれば3分に修正するなど、微調整をしていただいてOKです。
設問文の分析(要求解釈)には10分程度かける
プロセスの中で最も重要なものが設問文の解釈(要求解釈)です。要求解釈にはきちんと時間をかけましょう。要求解釈に時間をかける勇気をもちましょう。
もちろん、設問文が1行の問題ばかりなら8分くらいで終わることもありますが、基本的には10〜15分は設問文の分析(要求解釈)に使いましょう。
10〜15分ということは、5問構成なら1問2〜3分、4問構成なら1問3〜4分となります。
- 1問3分とか4分とかかけてもやることがなくて時間が余ります
-
そんなことはありません。これから見ていくスラッシュを引くこと、必要な理論をメモ書きしておくこと、強調表現やキーワードに反応すること、設問間の関係性のことを意識することなどに時間を使えば、1問3分や4分なんてあっという間です。
3分や4分かけられずに時間が余る人は、想起のための理論が定着していない+要求解釈でやることがまだわかっていないだけです。逆に言えば、設問文の分析に時間を長く使えるほど、想起のための理論や要求解釈でやることが定着している証拠になります。
- そんなに要求解釈に時間をかけていたら与件文を読む時間がなくなりませんか?
-
大丈夫です。これだけ長く設問文を見ていると、与件文の読解や対応づけの精度が上がり、対応づけまでで累計30分程度で終わります。
設問文の分析に時間を長くかければ、与件文の読解や対応づけの時間が短くなります。
逆に設問文の分析に時間を短くすると、与件文の読解や対応づけの時間が長くなります。
要はどちらにウエイトをかけるかの違いですね。ただ、後者は事故を起こす可能性が圧倒的に高いです。だから前者が勧められています。
ちなみに、EBAでは演習の際に教室受講生の要求解釈の時間を測っています。最初の演習の頃は「10分以上かけろ」と指導していても5分くらいで終らせてしまう方(やることがまだ定着していないから5分くらいで終らざるを得ない方)がかなりいて、解説講義の際に

要求解釈に10分以上かけない人は受かりたくないの?
まぁ、私としては受かる気のない人を無理に引き止める権利はないですが、、
という愛のムチ(嫌味?)が待っています。
設問文の分析に時間をかける決心はつきましたか?
さて、ここまで見てきましたが、設問文を分析する重要性と、設問文の分析に時間をかけることの必要性をご理解いただけたでしょうか?

う~ん、やっぱり早く与件文を見たいよ。設問文の題意とか制約条件も見逃さないから大丈夫だよ
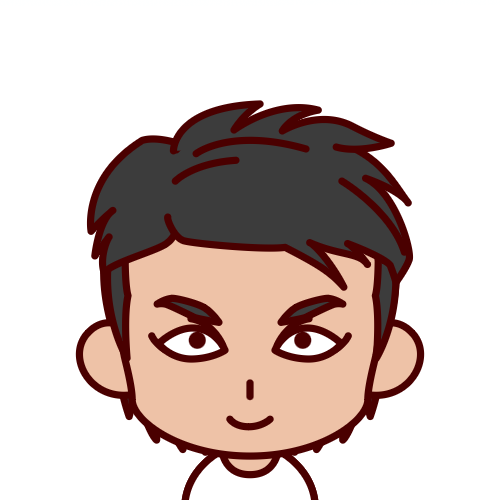
いや、理屈としてはわかるけど、時間がないんだから解答内容を考えるのに時間を使わないと!
そう言いたくなる気持ちはわかります。ただ、実は「急がば回れ」なのです。
受験生の2つのタイプ
受験生の80分のプロセスを見てみると、大きく2つのタイプに分かれています。
●タイプ①…7割くらいの受験生が該当
要求解釈と与件文読解を15〜20分で終わらせ、60〜65分かけて解答内容を考えながら解答用紙に解答文を記述する(解答内容決め・解答文記述を分けないで行う)
●タイプ②…3割くらいの受験生が該当
要求解釈と与件文読解を30〜35分かけ、50〜55分かけて「解答内容決め・解答文記述」をそれぞれ分けて行う
タイプ①は時間切れになりにくいのでその場の安心感はあるでしょうが、リスクが大きいです。一部の天才を除けば、波長が合えば高得点になりますが、事故を起こして低得点になるケースのほうが多いです。
上記の意見を言う方はこちらのタイプですよね。そして、先ほどの津田先生やEBAの先生の指摘はタイプ①の受験生が多いことを物語っています。そりゃ急いでやっていて設問文も与件文もちゃちゃっと見ている、解答内容を考えながら解答文を直接解答用紙に書いているから消しゴムを使い書き直しが多いとなれば、点数が低くなりやすいのは当然です。最初に見た設問文の題意や制約条件がいつの間にか頭の中から抜けていて、解答文に題意や制約条件が反映されていないのです。
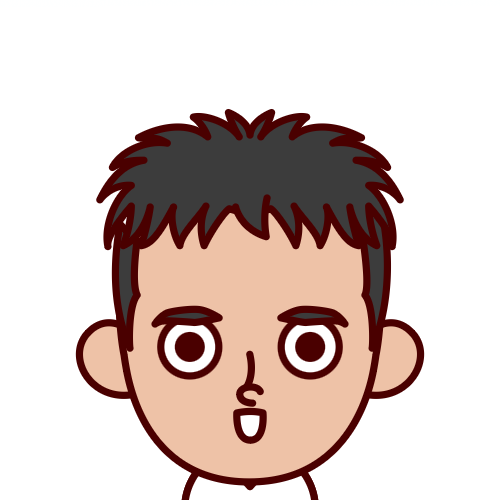
野球で言うと強振しているイメージですね。ホームランになるかもしれませんが、三振する可能性のほうが高いです
タイプ②は慣れるまでが大変ですが、慣れてしまえば安定感が出るため、リスクは小さいです。70点以上の高得点にはなりにくいですが、その分だけ55点以下にもなりにくく、安定して55〜70点を取れます。
長い時間をかけて設問文をじっくり深く分析するので、題意や制約条件が頭の中に残りやすい上に、与件文の読解や対応づけ、解答内容決めの際に何度か設問文を確認しているので、題意や制約条件が頭の中から抜けてしまうことがありません。そのため、解答文に題意や制約条件が反映され、安定した得点が取れるのです。

野球で言うとミート重視のバッティングやな。ホームランは打てなくても三振になりにくい。ヒットやツーベース量産で合格や!
タイプ①は「当たり」を3回以上引かないといけないイメージですね(高得点でハズレ1回分を賄うイメージ)。なので不合格になりやすく、仮に合格できても運の要素が大きいと思います。一方で、タイプ②は高得点の事例がなくて地味かもしれませんが、ハズレにはほぼならないので合格の確実性は高いです。
みなさんは、確率は低いけど70点以上を取って合格体験記でドヤ顔で自慢したいか、合格体験記では地味な扱いになるけど確実性高く合格したいか、どちらでいきたいでしょうか?もちろん前者がタイプ①、後者がタイプ②です。
そう考えると、タイプ②のほうがいいですよね.jpg)
ということで、タイプ②の設問文の分析に時間をかける決心がつきましたね。そして、このタイプ②を確実に実践できるために、今回の「設問文との付き合い方」のスキルが必要になるわけです。
解答内容を考えられる時間は1問あたり6〜8分
タイプ②でやることはわかりました。では、受験生が気になる「解答内容を考えられる時間」はどれくらいあるでしょうか?
タイプ②の場合は50〜55分かけて「解答内容決め・解答文記述」をそれぞれ分けて行うことになっています。そうなると、5問の場合は1問10分、4問の場合は1問13分程度の時間配分になります。その中で「解答内容決め」と「解答文記述」をするわけなので、それぞれかけられる時間は以下のようになります。
・5問の場合(1問10分):解答内容決め6分、解答文記述4分
・4問の場合(1問13分):解答内容決め8分、解答文記述5分
言い方を変えると、6分や8分で考えられる解答内容が求められているということです。だからこそ、私がこれまで散々言ってきた「取るべきところの4パターン」に該当するところだけに絞って解答内容を考える必要があるのです。それ以外のところを見ている時間はありませんし、点差がつかないので求められてもいません。無駄に探しにいくとスタミナも奪われて事例Ⅳで大きなミスをします。
なお、解答文記述の時間は4〜5分となっていて、ある程度の書き直しの時間を含めていますが、基本的には消しゴムはそこまで使えないと思ってください。ただ、ご安心ください。解答内容をきちんと決めていれば、考えながら解答文を書くわけではないので、消しゴムを使って書き直しをする回数は少なくなります。
解答内容決めや解答文記述に時間がかかっている悩みをもっている方は、まずはそれぞれの標準時間を定めましょう。それを定めずにその場任せで時間を決めていると、どうしても解答内容決めや解答文記述の時間が長くなってしまい、時間切れになりやすくなります。
長い設問文・多い要求文字数の設問が来たらラッキーだと思う
事例Ⅱや事例Ⅲだと、設問文が6行や7行ある設問や、要求文字数が100字を超える設問がありますよね。
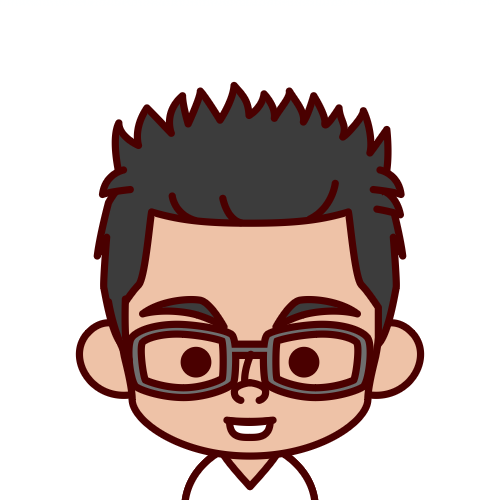
長い設問文は嫌なんだよなー

要求文字数150字って多いなぁ。自由に何でも書けそうだけど、何を書けばいいの?
こういう意見もよく出てきますね。
しかし、実は長い設問文、多い要求文字数の設問はありがたいのです。
長い設問文は、自由作文大会にならないように、解答内容の範囲を絞るためのヒントを多く入れているということです。それは設問文を細かく具体的に捉えていくと見えてきます。
近年は受験者数が増えて採点が追い付かなくなっています。そのため、自由作文大会になってしまうと別解の余地がたくさん出て採点がパンクしてしまいます。それを防ぐためにこのような制約条件を多く入れた長い設問文を作っています。
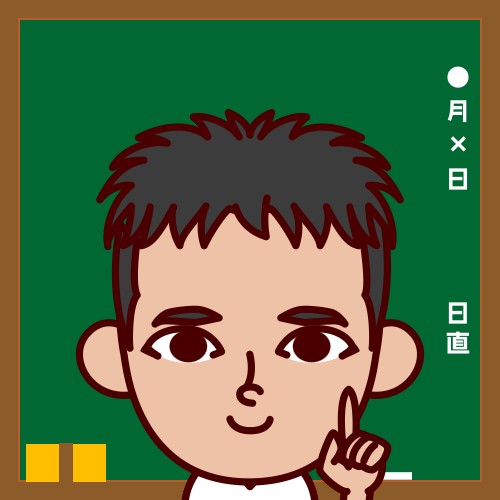
長い設問文の場合は、要求解釈の時間を多めに取りましょう。その分だけ与件文読解と対応づけが短時間で終わるようになっているので、そこで帳尻を合わせられます
また、多い要求文字数も細かく具体的に捉えた各要素を素直に入れることで自由作文大会にしないためにあります。例えば事例Ⅱの助言問題で、100字なら字数が少ないため効果の内容を解答に盛り込めないことも想定しますが、140字なら字数が多いため効果までバッチリ書かないといけない(つまり効果を書いていない解答は問答無用で減点することができる)ことが判断できます。

長い設問文、多い解答文字数の設問が来たらむしろラッキー!喜びましょう!
設問文にスラッシュを引く
次に、設問文を細かく具体的に見ていきましょう。先へ先へ急いでいる人や設問文について曖昧に捉えている人は、「指示に従う」ことが難しくなってしまいます。そのため、設問文にスラッシュを引いていきます。
これは以前の私の記事でもトレーニングメニューの1つとして述べていますね。
やってみましたか?
・・・・・やっていないですか?(笑)
やってない方や、今回初めて知った方は、ぜひやってみてください。どの問題を使っても構いません。
ミクロの単位で設問文を分析できるので、引っ掛けるポイントや出題者の意図が含まれるフレーズがわかってきます。そのため、指示を外す確率がかなり減りますし、出題者のツボを突いた解答が書きやすくなります。
設問文をいくつかの「部分」に分解する
設問文を細かく具体的に捉えていくためには、設問文をいくつかの部分に分解する必要があります。
いくつかの部分に分解、、どこかで聞いたことがありませんか?もしこれがすぐに出てくるとしたら、知識の面は何の心配もありません。
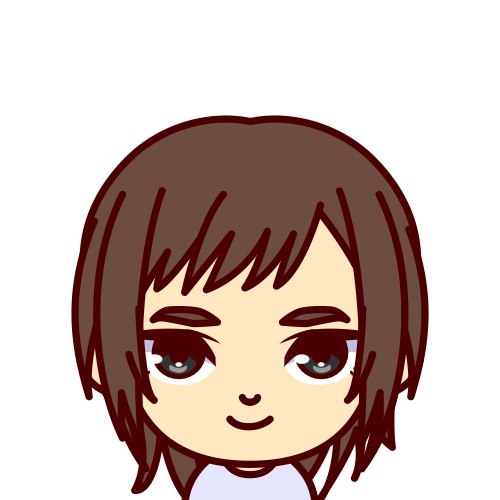
あっ!企業経営理論でやったモジュール型だ!
大正解!インテグラル型と対比で覚えるやつね
.jpg)
イメージは、「全体のまとまりの良さ」があるインテグラル型が予備校の模範解答ですね。それに対し「無駄はあるけど部分ごとに細かく管理できる」モジュール型は受験生の解答です。現実的な解答を安定的に作るなら、設問文全体から一気に最善の解答を作るより、設問文をいくつかの部分に分けて各部分の内容を想起や与件文から見つけてくることで最適の解答を作ったほうが確実です。
題意と制約条件を無視したらジ・エンド
意識は変わりましたでしょうか?そして、細かい単位で見ていくことの必要性もご理解いただけたでしょうか?
それができたら、具体的に細かい単位で要求解釈をしていけるようにステップを歩んでいきましょう!
まずは題意と制約条件に確実に従うところからです。題意と大きな制約条件は無視したらその時点で不合格確定と言えるくらい大きく点差をつけられてしまいます。
題意については、さすがに「強みを答えよ」と言われて弱みを解答する人はいないと思いますが、「問題点を述べよ」という題意なのに課題の形で書いてしまう方はよくいます。これはもちろんアウトで、点差がついてしまいますし、疲れている事例ⅢやⅣの記述問題だと意外にやってしまいがちなので注意が必要ですね。

例えば例年の阪神なら、
問題点:エラーが多い
課題:エラーの削減
だね。このように表現の仕方が異なるから注意が必要だよ。お~ん。
さすが、何でも阪神に例えてしまうAREですね(笑)
制約条件については、こちらの記事をご覧ください。この記事の最後には先ほどのスラッシュ引きを含めた要求解釈のトレーニング方法についても掲載されていますので、ぜひチェックしてみてください
制約条件には「レベル」があります。
- 大きな制約条件…事例Ⅰ~Ⅲ合計で2回無視したらアウト(1次で言うAランクレベル)
- 小さな制約条件…事例Ⅰ~Ⅲ合計で4~5回無視したらアウト(1次で言うB・Cランクレベル)
- 些細な制約条件…無視してもOK(1次で言うD・Eランクレベル)
例えば「生産面の」と設問文に書いているのに、営業面のことを答えたらダメですよね。「初代経営者の」と書いてあるのに「2代目経営者」がやったことを答えたらダメですよね。こういう「大きな制約条件」はほとんどの受験生が従うので、無視した瞬間終わりです。
しかし、「新商品の」と書いているのに新商品のことを答えていない、「どのような」と「どのように」の回答の仕方の違いを間違えたなど、「小さな制約条件」だと無視してしまう受験生は意外と多く見受けられます。こうなると「指示に従っていない」となってしまい点数が伸びません。設問文を何となく捉えている人や、焦って要求解釈を短時間で終らせている人は、小さな制約条件を無視することが多いです。
逆に、初見では誰も気づけないような「些細な制約条件」については、気づけずに無視してもOKです。こういうところまで神経質にこだわってしまうと、難しく複雑に考えるようになってしまい、2次ベテまっしぐらになります。2次ベテはこういう些細な制約条件に気づけないからなるのではなく、「小さな制約条件」を無視しているからなる傾向があります。
各部分について、①想起する、②与件文から見つけてくる
スラッシュによって設問文をいくつかの「部分」に分解したら、各部分について対応する内容を、①想起する、②与件文から見つけてくる、このどちらかを行います。
基本的に、事例Ⅰ・Ⅲは「①想起する」のほうが「②与件文から見つけてくる」よりも多いか、両者半々です。一方、事例Ⅱは「②与件文から見つけてくる」の量(割合)が多いです。そして、見つけてきた与件文の内容に合う経営資源を追加で入れていきます。
設問文をいくつかの部分に分解して、各部分について対応する内容を想起するか、与件文から見つけてくればいいだけ。実は2次試験で求められていることを突き詰めるとこれだけのシンプルなことです。
①想起する
王道の理論はもちろんですが、ちょっとした想起の内容もここには含まれます。後者については多年度生(2次ベテ)ならできることですが、ストレート生(初学者)や上級1年目の方でもトレーニングを積むことでできるようになります。以下の例に出てくるような解釈がポンポンと出てくるようになると、かなり有利になりますよ。だからこそ、日々の要求解釈トレーニング(設問文だけを見て解答内容を想起するトレーニング)が重要になってきます。
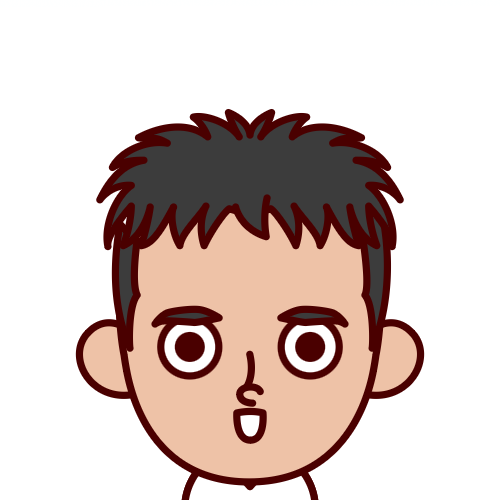
合格者は想起すべき内容がポンポンと出てくる。そうでない人はなかなか出てこないか、出てくるけど間違えている。こういう差が出ているよ

この差は要求解釈トレーニングの量の差から来ているよ。やはり、ポンポンと出てくる人は要求解釈トレーニングをサボらずきちんとやっている人だよ
②与件文から見つけてくる
これは私の過去記事で多く述べていますので、耳にタコができていますよね(笑)
そうですね。設問文中のフレーズと同じフレーズが書かれている段落にある内容や、その前後の段落の内容、同じフレーズはないけど明らかに「ここを使う」とわかる段落の内容を与件文から見つけてきます。
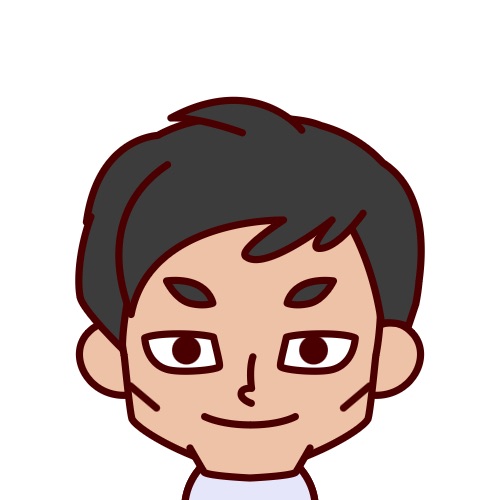
あれ?これってまとめてみると…
そうですね。私のこの記事にある「取るべきところ」のパターンですね。
今回はここに「各部分についての想起の内容」も加えました。ただし、これは「取るべきところ」になるとは限らないので、( )書きとさせていただきます。
理解するのは設問文のほう
勉強会などで受験生からのお悩みを聞いていて何回か出てきたのが、「与件文の内容を理解するスピードが遅くて、速く理解できるコツはありますか?」というものです。
しかし、80分の限られた時間の中で3ページくらいある与件文の内容を理解することは不可能です。予備校が解説で与件文の設定の話をしているのは、80分ではなく何日もかけて与件文の理解をしているからです。また、事例企業の業界のことを調べているからです。
なので、予備校の解説のような理解ができないといけないわけではありません。出題者側も受験生にそんなことは求めていません。与件文についてはせいぜい15分くらいで読んで、各設問の解答内容を考える際にもう一度確認しているくらいだと出題者側もわかって問題を作っています。
受験生が与件文の内容を現実的に理解するとしたら、大まかな流れとキーワードくらいだと思います。なので深く理解しにいく必要は全くありません。
逆に深く理解するとしたら設問文のほうです。設問文は理解を間違えたり曖昧にしたりすると指示無視につながり点数が伸びなくなります。なので、設問文こそ深く理解して指示にきちんと従うこと、これを意識していきましょう!
トレーニング
ではここから、実際の2次試験の問題を使って要求解釈をするトレーニングをやってみましょう。
令和6年度事例Ⅰ第2問
なぜ、A社は首都圏の市場を開拓するためにプロジェクトチームを組織したのか。また、長女(後の2代目)をプロジェクトリーダーに任命した狙いは何か。100字以内で答えよ。
実際にスラッシュを引いていきましょう。コツは文節ごとに引くことです。
なぜ、/A社は/首都圏の/市場を/開拓する/ために/プロジェクトチームを/組織したのか。/また、/長女/(後の/2代目)を/プロジェクトリーダーに/任命/した/狙いは/何か。100字以内で答えよ。
そして、この細分化した部分ごとに解釈をしていきます。なお、①想起する部分は緑、②与件文から見つけてくる部分は黄色のマーカーを引いています。
・なぜ
→題意の1つは理由
→理由や狙い、効果、長所の場合は「環境変化への対応、問題点の解消」が解答候補になることを想起
→また、前の設問で出た問題点や短所系の解消が来ることも想起(設問間の関係性)
・A社は
→A社がしたこと。他の会社がしたことではない
・首都圏の
→他の地方のことを解答したらNG。首都圏のことが書かれている与件文の段落を探してくる
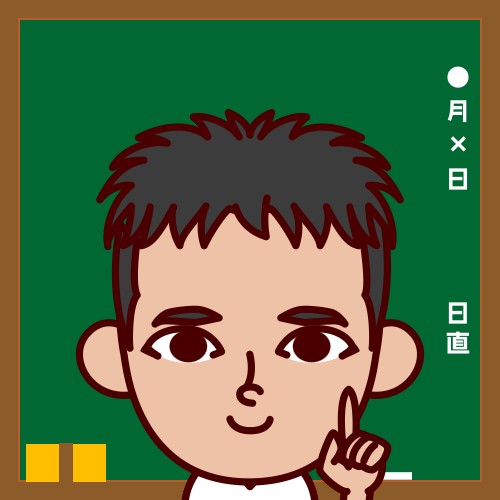
制約条件からは「このことを解答する」という以外に「これを解答したらNG」ということを想起すると大きいです
・市場を
→市場の内容が書かれている与件文の段落を見つけてくる
・開拓する
→今はまだ存在していない。すでに存在している市場のことを書いたらダメ
・プロジェクトチームを
→プロジェクトチームの長所(専門性向上、組織活性化など)を想起
→また、プロジェクトチームの短所を後の設問で解消することもここで想起(設問間の関係性)
・組織したのか
→組織論の効果の定番(専門性、効率性、柔軟性、迅速性、組織活性化、モチベUP)を想起
・長女
→長男や次女とかではない。長女のことが書かれている与件文の段落を見つけてくる
・後の
→役割を任されるのは今ではない
・2代目
→少なくとも初代がいる。初代や3代目のことを書いたらダメ。2代目のことが書かれている与件文の段落を見つけてくる
・プロジェクトリーダーに
→リーダーシップのことを想起。プロジェクトリーダーのことが書かれている与件文の段落を探してくる
・任命
→権限委譲や後継者系のことを想起
・狙い
→題意の1つは狙い

え?こんなに出せるの?
はい、出せますよ。というか、出さないといけないです。これだけ出すからこそ、確実に指示に従うことができるわけですし、だからこそ要求解釈は1問あたり3分や4分かかる(かける)のです。
大丈夫です。最初はほとんど出てこないと思いますが、要求解釈トレーニングをやっていけば徐々に出てくる量が増えて、それに比例して要求解釈の時間も長くかけられる(=与件文読解や対応づけの時間が短くなる)ようになります。
では次は、スラッシュで区切った単位を複数まとめた単位でも見ていきましょう。
令和3年度事例Ⅰ第3問
A 社は、現経営者である 3 代目が、印刷業から広告制作業へと事業ドメインを拡大させていった。これは、同社にどのような利点と欠点をもたらしたと考えられるか、100 字以内で述べよ。
まず、スラッシュで区切ってみましょう。
A 社は、/現経営者/である/3 代目が、/印刷業から/広告制作業へと/事業ドメインを/拡大させていった。/これは、/同社に/どのような/利点と/欠点を/もたらしたと/考えられるか、/100 字以内で述べよ。
そして、スラッシュで区切った部分をいくつかまとめたものとして、このように「部分」に分けることができます。
A 社は、
現経営者/である/ 3 代目が
印刷業から/広告制作業へと
事業ドメインを/拡大させていった。
これは、/同社に/どのような/利点と/欠点を/もたらしたと/考えられるか、/100 字以内で述べよ。
ここから要求解釈をしていきます。まず、題意は利点と欠点です。両方書く必要があります。これができないと即アウトです。
そして、各部分について①想起する、②与件文から見つけてくる、のどちらかを行います。
・現経営者である3代目が
→現経営者・3代目なので、初代や2代目のことを書いたらNGとなります。
→【②与件文から見つけてくる】を行います。 「3代目」というフレーズがある段落を与件文から見つけ、そこの段落にある内容(解答に使えそうなもの)を解答に入れていきます
→そうすると、第1・8・10段落に対応づけることができます。あとはこれらの段落の中から解答に使えそうな内容を見つけてくればいいのです
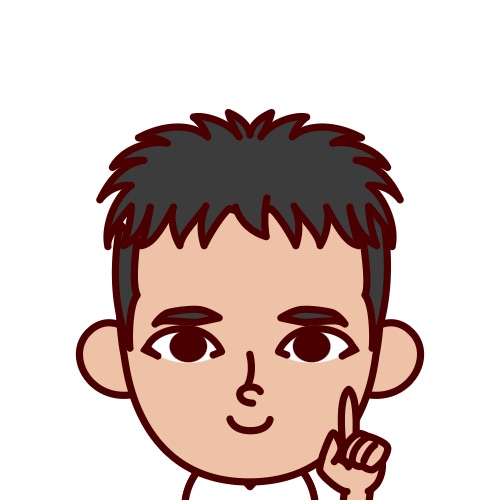
いわゆる「与件文の抜き」ってやつです!
・印刷業から広告制作業へと
→きちんと「前」と「後」を捉えていきます。設問文を適当に見ている方は後者のみ見ている方が多いですが、前者の印刷業のこともきちんと解答内容を考える際に意識していきましょう
→【②与件文から見つけてくる】を行います。このフレーズがある段落を与件文から見つけ、そこの段落にある内容(解答に使えそうなもの)を解答に入れていきます
→そうすると、第8段落に対応づけができます。そして、「紙媒体に依存しない分野」、「新たな事業の案件を獲得していくことは難しかった」、「新規の需要を創造していく」、「数多くの競合他社が存在しているため、非常に厳しい競争環境」、「新規の市場を開拓するための営業に資源を投入することも難しいために、印刷物を伴わない受注を増やしていくのに大いに苦労している」あたりが解答に使えそうだとわかります
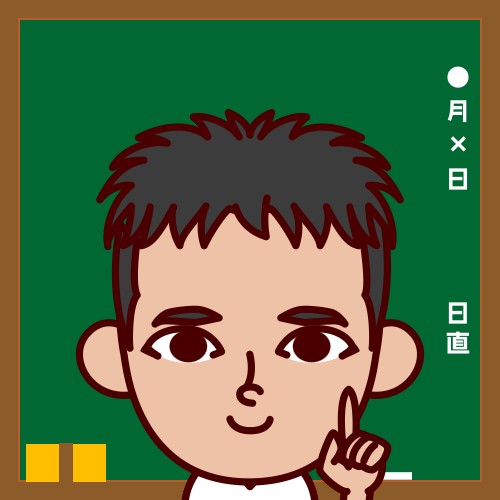
対応づけた与件文の段落内のどの内容が解答に使えるかを判断するコツは、強調表現やキーワードです
・事業ドメインを拡大
→ 【①想起する】を行います。ドメイン拡大の理論を想起すると「多角化、シナジー効果、リスク分散、経営資源の分散」が出てきます
そうすると、解答には「紙媒体に依存しない分野、リスク分散、経営資源の分散、厳しい競争環境、新たな案件を獲得するのは難しい(受注を増やせない)、営業に資源を投入できない」などのフレーズを入れることができます。
これは「ふぞろいな合格答案15」もしくは「ふぞろいな答案分析7」を見ていただくとわかるかと思いますが、多くの人が解答しているもの、つまり「取るべきところ」を網羅した解答になっています。こういう解答が高得点になります。
令和5年度事例Ⅲ第5問
食品スーパー X 社と共同で行っている総菜製品の新規事業について、C 社社長は現在の生産能力では対応が難しいと考えており、工場敷地内に工場を増築し、専用生産設備を導入し、新規採用者を中心とした生産体制の構築を目指そうとしている。この C 社社長の構想について、その妥当性とその理由、またその際の留意点をどのように助言するか、140 字以内で述べよ。
このように「部分」に分けることができます(スラッシュは省略しています)。
食品スーパー X 社と
共同で行っている総菜製品の新規事業について、
C 社社長は現在の生産能力では対応が難しいと考えており、
工場敷地内に工場を増築し、
専用生産設備を導入し、
新規採用者を中心とした
生産体制の構築を目指そうとしている。
この C 社社長の構想について、その妥当性とその理由、またその際の留意点をどのように助言するか、140 字以内で述べよ。
まず、題意3つに答える必要があります。
・食品スーパーX社
→ 【②与件文から見つけてくる】を行います。このフレーズがある段落を与件文から見つけ、そこの段落にある内容(解答に使えそうなもの)を解答に入れていきます
→そうすると、第13・14段落に対応づけができます
・共同で行っている総菜製品の新規事業
→ 【②与件文から見つけてくる】を行います
→そうすると第13段落に対応づけができます
・現在の生産能力では対応が難しい
→ 【②与件文から見つけてくる】を行います
→そうすると第15段落に対応づけができます
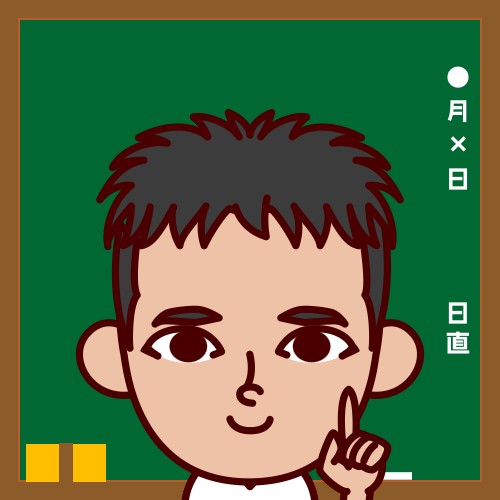
なお、設問文を読んだだけの段階では、①想起する、②与件文から見つけてくるのどちらになるかわかりにくいものもあります。そういうときは、両方必要になることを想定しておきましょう。与件文を読んだときに内容が見つからなければ「①想起する」のみになります
・工場敷地内に工場を増設
→ 【①想起する】を行います。レイアウトの理論を想起すると「5S、SLP」が出てきます
・専用生産設備を導入
→ 【①想起する】を行います。設備や標準化の理論を想起すると「育成が不要、少品種大量生産、標準化」が出てくる
・新規採用者を中心とした
→ 【①想起する】を行います。育成の理論を想起
・生産体制の構築
→ 【①想起する】を行います。効果として「生産能力向上」を想起
※事例Ⅲの最後の問題であること
→ 【①想起する】を行います。戦略系問題として、「強み、ニーズ、営業、外部、高付加価値化・差別化・競争優位、売上増」を想起
令和4年度事例Ⅱ第2問
B 社は、X 県から「地元事業者と協業し、第一次産業を再活性化させ、県の社会経済活動の促進に力を貸してほしい」という依頼を受け、B 社の製造加工技術力を生かして新たな商品開発を行うことにした。商品コンセプトと販路を明確にして、100 字以内で助言せよ。
このように「部分」に分けることができます(スラッシュは省略しています)。事例Ⅱは【②与件文から見つけてくる】の割合が高くなる上に、見つけてきた与件文の内容と合う経営資源を追加で入れる必要があります。
B 社は、
X 県から
地元事業者と協業し、第一次産業を
再活性化させ、県の社会経済活動の促進に力を貸してほしい
という依頼を受け、
B 社の製造加工技術力を生かして
新たな商品開発を行うことにした。
商品コンセプトと販路を明確にして、100 字以内で助言せよ。
・X県から
→ 【②与件文から見つけてくる】を行います。このフレーズがある段落を与件文から見つけ、そこの段落にある内容(解答に使えそうなもの)を解答に入れていきます
→そうすると、第2・7段落に対応づけができます。そして、「県内や隣接県のホテル・旅館、飲食店」、「山の幸、海の幸の特産品」あたりが解答に使えそうだとわかります
・地元事業者と協業し、第一次産業を
→ 【②与件文から見つけてくる】を行います。このフレーズがある段落を与件文から見つけ、そこの段落にある内容(解答に使えそうなもの)を解答に入れていきます
→そうすると、第7段落に対応づけができます。そして、「野菜・果物・畜産などの農業、漁業」、あたりが解答に使えそうだとわかります
・再活性化させ、県の社会経済活動の促進に
→ 【①想起する】を行います。地域活性化、地域ブランド向上を想起
・B社の製造加工技術力
→ 【②与件文から見つけてくる】を行います。このフレーズがある段落を与件文から見つけ、そこの段落にある内容(解答に使えそうなもの)を解答に入れていきます
→そうすると、全く同じフレーズではないですが「食肉加工品製造」や「高い技術力」というフレーズがある第8段落に対応づけができます。そして、「食肉加工品製造」、「高い技術力」、「良質でおいしい食肉加工品を製造できる体制」、「食肉加工品を自社ブランドで開発」、「贈答品」、「直営小売店や高速道路の土産物店、道の駅」、「相手先ブランド」あたりが解答に使えそうだとわかります
→「高い技術力」はこの与件文からもってきた内容と合う経営資源にもなっています
「新たな商品開発」なので既存商品はダメなこと(制約条件)、「商品コンセプトと販路」が題意になっていることも確認しておきましょう!
あぁ、この設問であんな大事故を起こさなければ…
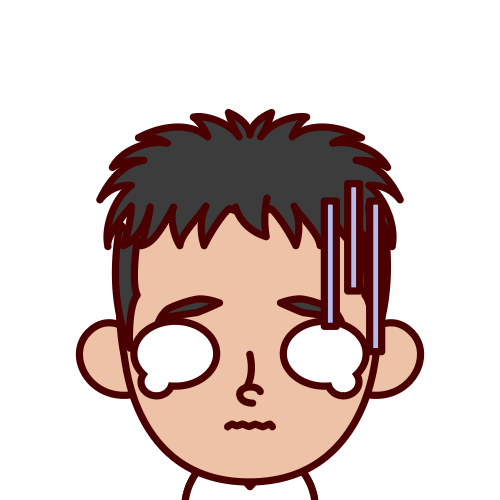
この設問には苦い思い出が、、
令和4年度に受験した私はこの設問で大事故をやらかし、事例Ⅱは42点でした。販路を「全国チェーンのスーパー」と解答してしまったのです。
令和4年度の受験の際は、私は「取るべきところ」のパターンに絞ることをしていませんでした。そのため、この設問で販路を全国チェーンのスーパーにしてしまう大事故を起こし、散々な出来(42点)になってしまいました。
この問題で言うと、販路に全国チェーンのスーパーが書かれている段落には第2問の設問文に書かれているフレーズはありませんでした。逆に正解と言われている観光エリアや道の駅などはそれぞれの段落に第2問の設問文に書かれている「X県」や「製造加工技術力」というフレーズがありました。つまり、この問題も「取るべきところ」のパターンが反映されていたことになります。設問文の「X県」や「製造加工技術力」というフレーズがある段落を与件文から見つけ、そこの段落にある内容(解答に使えそうなもの)を解答に入れることができていなかったからこその大事故でした。こういうことをしてしまうとC評価(40点台)につながってしまいます。
実はこの年は、事例ⅡでC評価ではなければ合格していました。つまり、この大事故1回で合格するものが不合格になってしまったわけです。みなさんもこういう大事故は起こさないようにしましょうね。そのためにも、設問文との付き合い方をこの機会にマスターしちゃいましょう!
このへんで休憩
はい、このあたりで休憩しましょう。
みなさん、こち亀ってご存知でしょうか?
「こちら葛飾区亀有公園前派出所」という漫画です。昔はフジテレビでアニメもやっていましたね。
この主人公の両津勘吉、実は中小企業診断士なんです。

(こちら葛飾区亀有公園前派出所 第97巻 「両さんの就職案内の巻」より引用)
こち亀を漫画かアニメでご覧になっていた方はわかると思いますが、両さんはお金が絡んだことになると、途中まではうまく進めますよね(最後には壮大なオチが待っていますが)。時流に乗るのがうまいですし、プラモなどを器用に作る技術力を活かしたビジネス展開もよくしていますし、顧客のニーズをつかんで最適なモノを提供する営業力や企画開発力もあります。
これらのスキルは、診断士の力かもしれませんね。

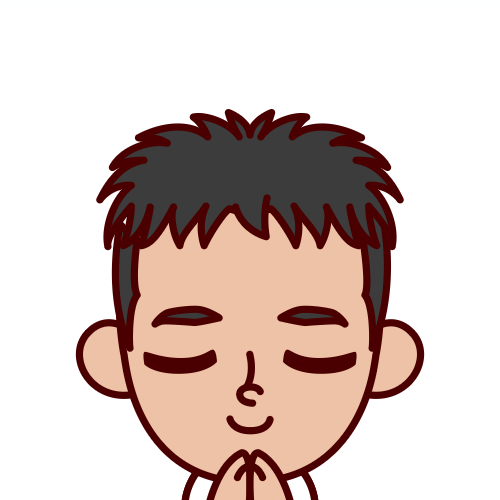
亀有駅を訪れた際は駅前に両津勘吉の銅像があるので、診断士の先輩なんだと思って敬意を示しましょう(笑)
解答文も簡単に作れる
では、設問文分解の後半戦のスタートです。次は解答文まで作ってみましょう。「あら不思議」というくらい、あっさりしたものなのに高得点になってしまう解答文が書けるようになりますよ。
ちょっとした応用テクニックも出てきます。
令和4年度事例Ⅰ第4問(設問2)
現経営者は、今後 5 年程度の期間で、後継者を中心とした組織体制にすることを検討している。その際、どのように権限委譲や人員配置を行っていくべきか、中小企業診断士として 100 字以内で助言せよ。
このように「部分」に分けることができます(スラッシュは省略しています)。
現経営者は、
今後 5 年程度の期間で、
後継者を中心とした組織体制にすることを検討している。
その際、どのように
権限委譲や
人員配置を行っていくべきか、
中小企業診断士として 100 字以内で助言せよ。
・今後5年程度の期間で
→「中長期的、段階的、計画的」などのフレーズを入れることを想起
・後継者を中心とした組織体制にする
→後継者系の内容を想起。具体的には、後継者は各部門の経験を積んで全体を俯瞰する役割、右腕的な人に権限委譲、人事施策として横断的な人事交流・定期的な配置転換・公正な評価制度、効果としてモチベ向上や組織活性化を想起
→「後継者」というフレーズがある段落を与件文から見つけ、そこの段落にある内容(解答に使えそうなもの)を解答に入れる。 そうすると、第10・11段落に対応づけができ、「常務の娘」や「店舗マネジメントや商品開発の業務」、「農業については門外漢」、「飲食サービス、直営店」、「人手不足」あたりを与件文からもってくることができる
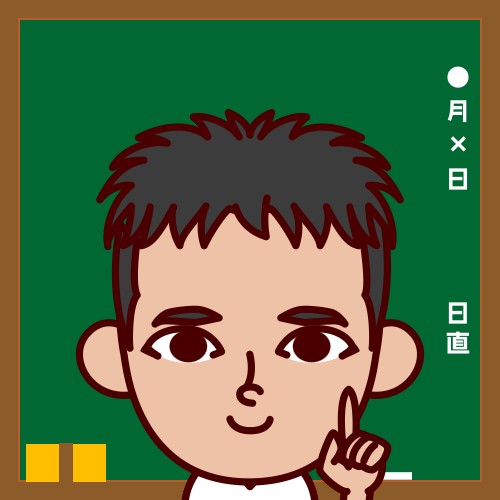
いったん「①想起する」をやってから、「②与件文から見つけてくる」もやっているよ。
このように、2つとも出てくるものも中にはあるよ
・権限委譲
→右腕的な人に権限委譲することを想起
→与件文から右腕的な人の具体的な名前を探すと、「若手従業員」が見つかる(わざわざ積極的に提案していることが2回も書かれている)
・人員配置
→人事施策に求められているのは定期的な配置転換で、効果としてモチベ向上や組織活性化を想起
すると、あら不思議。 こんな解答ができます。 これは「ふぞろいな合格答案16」もしくは「ふぞろいな答案分析7」を見ていただくとわかるかと思いますが、多くの人が解答しているもの、つまり「取るべきところ」を網羅した解答になっています。 こういう解答が高得点になります。
解答
常務の娘が農業経験豊富な従業員から農業の教育を受け店舗マネジメントや商品開発を含め全社的管理を行う。 若手従業員に直営店の権限委譲を行い、段階的・定期的な配置転換をすることで意欲向上・組織活性化を図る。
中小企業診断士として?
助言問題で「中小企業診断士として」ってフレーズをよく見かけませんか?
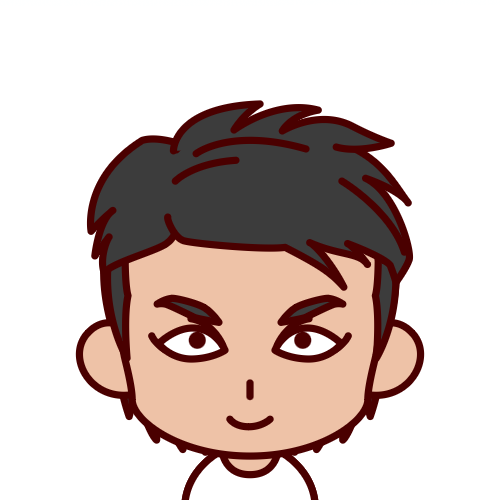
そりゃ中小企業診断士の試験なんだから付いているんじゃないの?
実は違います。このフレーズがついているのはちゃんとした理由があります。「中小企業に現実的にできることとして解答しなさい」ということを指示しているためです。つまり、「大企業の理屈をもってきた解答は×にする」という、一種の制約条件のようなものです。
中小企業経営・政策や企業経営理論で習ったと思いますが、中小企業は経営資源が乏しいです。特に「ヒト・モノ・カネ」は大企業に比べて圧倒的に不足しています。「人を大量採用する」とか「販売価格を下げる」とか「大量生産する」など、大企業なら当たり前のようにできることも中小企業には簡単にはできません。助言問題で「中小企業診断士として」というフレーズがついているときは、「経営資源が不足していることを意識して、中小企業に現実的にできることとして解答する」ということを心がけましょう。
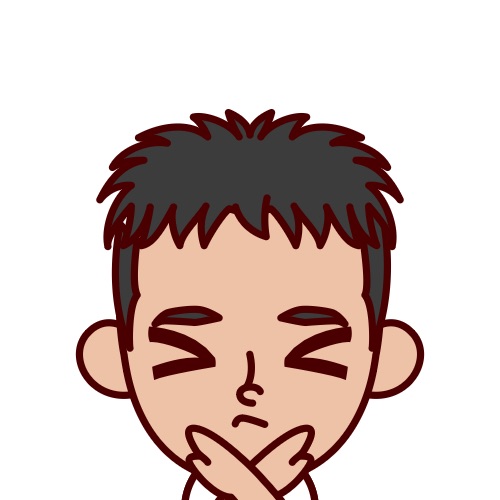
もちろん、「中小企業診断士として」がなくても大企業の理屈の解答はNGと思っていいです
ちなみに、これは実務でも同じです。合格後の実務補習のときによく指導員や補習先企業の社長から言われることが「大企業の理屈をもってくるな」です。
令和5年度事例Ⅲ第4問
C 社社長は受注量が低迷した数年前から、既存の販売先との関係を一層密接にするとともに、他のホテルや旅館への販路拡大を図るため、自社企画製品の製造販売を実現したいと思っていた。また、食品スーパー X 社との新規事業でも総菜の商品企画が必要となっている。創業から受託品の製造に特化してきた C 社は、どのように製品の企画開発を進めるべきなのか、120 字以内で述べよ。
このように「部分」に分けることができます(スラッシュは省略しています)。
C 社社長は
受注量が低迷した数年前から、
既存の販売先との関係を一層密接にするとともに、
他のホテルや旅館への
販路拡大を図るため、
自社企画製品の製造販売を実現したいと思っていた。
また、食品スーパー X 社との新規事業でも
総菜の商品企画が必要となっている。
創業から受託品の製造に特化してきた C 社は、
どのように製品の企画開発を進めるべきなのか、120 字以内で述べよ。
このように「部分」に分けることができます。
・受注量が低迷した数年前から、販路拡大
→「受注量増加、売上増加」を想起
・既存の販売先との関係を一層密接にする
→「連携、共同開発」を想起
・他のホテルや旅館、食品スーパーX社
→このフレーズがある段落を与件文から見つけ、そこの段落にある内容(解答に使えそうなもの)を解答に入れる
→そうすると、第3・13段落に対応づけができ、「地元食材を使った特色のあるメニュー」や「季節性があり高級感のある和食や洋食の総菜」、「差別化」、「外部人材」、「製品開発の実務や管理の経験」あたりを与件文からもってくることができる
・自社企画製品の製造販売を実現したい、惣菜の商品企画、製品の企画開発
→「ニーズ把握、最適な製品(商品)、高付加価値・差別化」を想起
・創業から受託品の製造に特化してきた
→「このノウハウ(強み)を活かす、需要予測、ニーズ把握、営業力の強化」を想起
すると、あら不思議。こんな解答ができます。これは「ふぞろいな合格答案17」を見ていただくとわかるかと思いますが、多くの人が解答しているもの、つまり「取るべきところ」を網羅した解答になっています。
解答
営業力強化、販売先との連携、顧客ニーズ収集を行い、外部人材の製品開発の実務や管理の経験を活かし、地元食材を使った特色のあるメニューや季節性があり高級感のある和食や洋食の総菜など高付加価値製品を共同開発し、差別化・売上増を図る。
事例Ⅲは難しい年だと何を解答したらいいかわからないと言われますが、この解答を見ていかがでしょうか?別にウルトラCのようなことではないですよね。もちろん予備校の模範解答のような難しいことでもありません。
難しいと言われる場合、「①想起する」の割合が高くなりがちです。与件文の根拠がないので、正しい想起ができないと何を書いたらいいかわからなくなり、自由作文大会(大喜利大会)になってしまいます。しかし、正しい想起ができる人はみんなが解答するような内容を安定的に解答できます。そのカギを握るのが日々の要求解釈トレーニングです。
「どのように」と「どのような」の違いを意識する
みなさん、「どのように」と「どのような」の違いを意識していますか?
「どのように製品の企画開発をするべきか」と「どのような製品の企画開発をするべきか」は、同じように見えますが解答内容はガラリと違います。
「どのように」は、「How」なので、「方法・やり方」が問われます。つまり「企画開発の方法・やり方」が解答内容になります。
一方、「どのような」は「What」なので、「モノ」が問われます。仮に今回の令和5年度事例Ⅲ第4問が「どのような製品の企画開発をするべきか」になると、「どういう製品」が解答になります。
令和に入ってからはこういう「どのような」と「どのように」の違いが注目されるようになってきているので、みなさんもこの機会に意識できるようにしていきましょう!
令和5年度事例Ⅱ第4問
B 社社長は、長期的な売上げを高めるために、ホームページ、SNS、スマートフォンアプリの開発などによるオンライン・コミュニケーションを活用し、関係性の強化を図ろうと考えている。誰にどのような対応をとるべきか、150 字以内で助言せよ。
このように「部分」に分けることができます。
B 社社長は、
長期的な売上げを高めるために、
ホームページ、SNS、スマートフォンアプリの開発などによる
オンライン・
コミュニケーションを活用し、
関係性の強化を図ろうと考えている。
誰に
どのような対応をとるべきか、150 字以内で助言せよ。
・長期的な売上を高める、関係性の強化
→効果として「固定客化」を想起
・ホームページ、SNS、スマートフォンアプリの開発など
→このフレーズがある段落を与件文から見つけ、そこの段落にある内容(解答に使えそうなもの)を解答に入れる
→そうすると、第15・16・19・21段落に対応づけができ、「各チームのデータ管理」や「メンバーや保護者の要望の情報把握、および相談を受けた際のアドバイス」あたりを与件文からもってくることができる
→さらに、この与件文からもってきた内容と合う経営資源として、提案力をもってくる
・オンライン
→ネット系のものを想起、ネット系の経営資源を与件文からもってくる
→そうすると第17段落の「ICT企業に勤めている30代の長男」が経営資源で使えそうなことがわかる
・コミュニケーション
→双方向コミュニケーション(ニーズ把握、最適なものを考える、個別提案)を想起。また、オンラインでニーズ把握となると、掲示板や質問フォームなどを想起
・誰に
→ターゲットに該当するものを与件文からもってくる
→対応づけた第19段落に「各少年野球チームの監督」と「メンバーや保護者」があるのでこれがターゲットになる
すると、こちらもあら不思議。こんな解答ができます。これは「ふぞろいな合格答案17」の事例Ⅱ第4問のほぼすべての要素を取り込んでいます。もちろん多くの人が解答しているもの、つまり「取るべきところ」を網羅した解答になっています。この解答ならほぼ満点の解答になると思われます。
解答
各少年野球チームの監督に対し、ICT企業に勤めている長男のノウハウを活かし各チームのデータ管理のアプリを開発。掲示板を設置したホームページとSNSから各チームのメンバーや保護者の要望の情報を把握し、提案力を活かして相談を受けた際のアドバイスを掲載することで双方向交流を行い、固定客化を図る。
事例Ⅱの解答は芋づる式でわかるようになっている
みなさん、事例Ⅱの解答内容っていつもスムーズに決まりますか?そんなことはないですよね?
下手をすると、事例Ⅲの難しい年のように何を書いたらいいわからないこともあると思います。切り分けが難しくてどの内容をどちらの問題に書いたらいいかわからない(ギャンブル勝負になってしまう)こともあると思います。
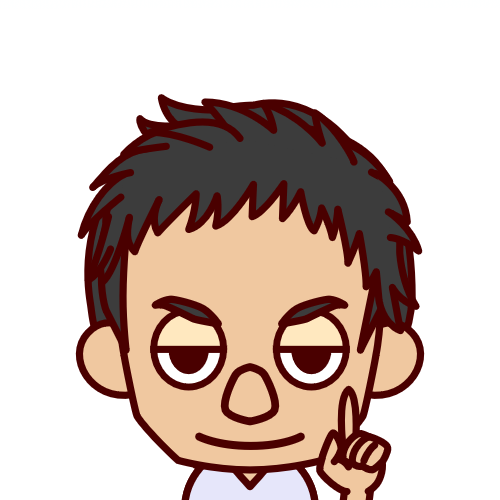
ギャンブル勝負なら任せてや!
たいしんのようにギャンブル勝負が得意ならいいのですが(笑)、なかなかそうはいきませんよね。ですが心配いりません。大丈夫です。
事例Ⅱの解答は、「誰に、何を、どのように、効果」のうち、どれか1つは必ずすぐに見つかる(明らかにわかる)ようになっています。そしてそれは「設問文に書かれているフレーズと同じフレーズがある段落」に書かれていることが多いです。まずはこれを見つけてバシッと定め、他の要素はこれと内容的に合うものを芋づる式につなげていけばいいのです。
今回の令和5年度事例Ⅱ第4問なら、設問文に書かれているフレーズと同じフレーズがある段落である第15・16・19・21段落から「各チームのデータ管理」や「メンバーや保護者の要望の情報把握、および相談を受けた際のアドバイス」をもってきます。また、ターゲットも第19段落に「各少年野球チームの監督」と「メンバーや保護者」がありますよね。なのでこれも楽勝にわかります。まずはこれらをバシッと定めます。
そしてここから他の要素を芋づる式につなげていきます。「データ管理」と内容的につながる経営資源は「長男のICTノウハウ」です。「アドバイス」と内容的につながる経営資源は「提案力」です。あとはこれに「①想起する」の内容をつなげていけばいいのです。
.jpg)
難しく考える必要はありません。簡単にわかるところから組み立てていけばいいのです
ここでまた休憩
さて、次からちょいと段階が上がりますので、ここらへんでまた休憩です。
年末年始と言うと、お酒を飲む機会も多くなると思います。診断士の受験生で「お酒」となると、令和2年度の事例Ⅰではないでしょうか?祖父が地元の有力者でA社を買収するって設定のやつです。
口述対策の際にも改めて述べますが、実は事例Ⅰ〜Ⅲの会社は実在していて、令和2年度事例Ⅰは岐阜県の高山にある「舩坂酒造」という酒蔵がモデル企業です。地元では超が付くくらい有名な酒蔵です。もちろん飛騨高山の観光ガイドにも載っています。

舩坂酒造店【公式サイト】|岐阜県・飛騨高山:古い町並みに佇む酒蔵
東海・北陸地方にお住いの方や、帰省先がこのあたりの方は訪れてみてもいいかもしれませんね。
また、ECサイトもありますので、令和2年度のA社のお酒を取り寄せてみてはいかがでしょうか?

フットワークの軽いサトシのことだから、おそらくこの会社には、、
もちろん訪れたことがあるよ。3回くらい行ってるかな。お酒だけじゃなく岐阜県の様々なお土産も取り扱っているよ
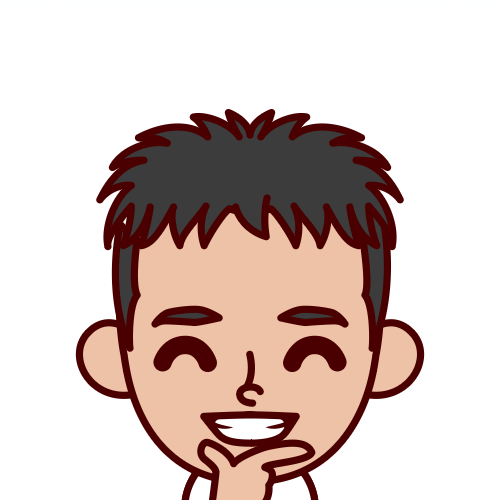
設問間の関係性を意識する
さて、先ほどまでは設問単体で見ていきましたが、ここからは複数の設問単位で見ていきます。具体的には「設問間の関係性」の話になります。
「設問間の関係性を意識しましょう」ということを、予備校の演習の添削や勉強会で他の方から指摘されたことはありませんか?
「意識しろと言っても、どうやって意識すればいいの?」と思ってしまいますよね。でも大丈夫です。設問間の関係性を意識することは意外と簡単です。なぜなら…
設問間の関係性はある程度パターンがあるから
です!
設問間の関係性を習うタイミング
設問間の関係性は応用的なスキルとなっています。やはり、知識や基本的なスキル(設問分析・与件文の読解など)をまずは身につける必要があるため、設問間の関係性についてはカリキュラムの後半で習う(演習で扱う)ことになります。
私はTACの他に、LECとEBAを受講したことがありますが、TACでは5月くらいから演習を通じて(講義では扱いません)、LECとEBAでは7月くらいから講義と演習を通じて設問間の関係性を見ていきました。
どちらにしても、設問間の関係性は応用的なスキルとなっていますので、どうしても初学者(ストレート生)には厳しいものと言えます。逆に言えば、今の時期から2次対策に取り組める上級生には有利なもの、初学者(ストレート生)と差をつけられる内容と言えます。ぜひとも、今回の記事で設問間の関係性を意識できるようにして、初学者(ストレート生)と差別化を図りましょう!
設問間の関係性のパターン
設問間の関係性は論理展開に従っています。順接とか逆接とか並列って、国語の授業でやりましたよね。

出たー、論理。現代文でやったわ
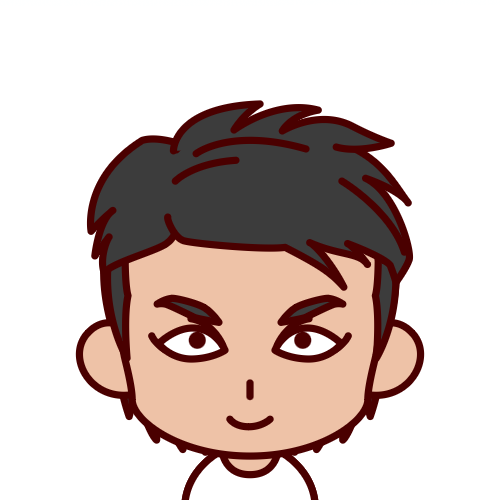
この言葉を聞くと苦手意識が・・
意外と単純なのでそんなに難しく捉えなくて大丈夫ですよ。国語が苦手な私ですらわかるのですから(笑)
以下にあるパターンを押さえてしまえば、変に設問間の関係性にビビる必要はありません。
なお、この設問間の関係性は、(設問1)・(設問2)になっている設問間はもちろん、第1問・第2問などの大問間でも適用されます。
並列
事例Ⅱ・Ⅲでよく出てきます。事例Ⅱなら第2問以降の設問、事例Ⅲなら最初と最後以外の真ん中の設問ですね。問題点や課題がいくつかあり、それを1つずつ片づけていくイメージです。
事例Ⅱなら例えば第2問で新規顧客のこと、第3問で既存顧客のこと、第4問で地域活性化のことを聞かれるパターンです。同じ「助言問題」だけどそれぞれ新規顧客、既存顧客、地域活性化の内容は並列であって因果関係でつながっているわけではありません。事例Ⅲなら例えば第2問がレイアウトのこと、第3問が生産管理のこと、第4問が営業のことを聞いている場合、並列関係になります。
切り分けで難しい場合は、この並列関係の設問間で苦労させられます。
切り分けのコツ
切り分けが難しい場合、キーワードか理論で切り分けることが王道です。
キーワードは「設問文中にあるフレーズと同じフレーズが書かれている段落の内容を書く」というやつですね。実はキーワードが段落によってきれいに分かれていることが多いです。
理論は「新規顧客と既存顧客」や「営業と生産」、「生産現場と生産管理」、「受注生産と見込生産」というパターンが多いです。新規顧客の問題なら満足度のことは書きませんし、在庫のことが問われている問題なら見込生産の内容を書きますよね。
また、3問に渡って切り分けが難しい場合は、どれか1問は簡単に解答内容が特定できるようになっています。まずはその1問の解答内容をバシッと決めて、他の2問は残りの内容からキーワードと理論で切り分けていきましょう。消去法のようなイメージですね。
令和6年度の事例Ⅲ第2・3・4問もそのような形になっていて、第4問の解答内容がすぐにわかり、そこで第4問の解答内容に使う部分を除いてしまい、残った部分について「生産現場と生産管理」の切り口を使うことで第2問と第3問の切り分けができるようになっていました。
事例Ⅱの経営資源の切り分け
事例Ⅱでは「どのように」のところで、「加工技術力を活かし」とか「品揃えを活用し」というように、マーケティング戦略に使える経営資源(3C分析の「自社」やSWOT分析の「S」で書く内容)を解答に書きますよね。
事例Ⅱの経営資源は、平成の最後あたりはたくさん(10個程度)あってどの設問に何をはてはめるかわかりにくかったですが、令和に入ってからはその傾向はなくなっています。そのため、経営資源がたくさん出てくることはありませんし、その切り分けを過剰に恐れる必要はありません。
これは、経営資源の解答のバリエーションを増やすと別解の余地がたくさん出てしまい、採点の納期に間に合わなくなる恐れがあるからです。平成最後あたりと比べ、令和に入ってからは2次試験の受験者数が増えています。その中で別解の余地をたくさん出してしまうと、ただでさえ大きい採点の負担がさらに大きくなってしまい、採点業務がパンクしてしまいます。事例Ⅲじゃないですが、診断士の採点業務も納期遅延はNGです。
なので、現在では「この経営資源はこの設問しか当てはまらない」とわかるようになっています。
なお、提案力は双方向のコミュニケーションの問題がオンライン・オフラインで求められているなど、複数の設問に使う経営資源もあります。
順接(因果関係)
並列以外はすべてこれです。前の設問の設定や解答内容が後の設問の設定や解答内容につながっていきます。具体的には、以下のようになっています。
第1問で出した強みを第2問以降の助言問題(機能別戦略の問題)で活かすパターン
事例Ⅱの第1問と助言問題の関係はこちらです。第1問と各助言問題が因果の関係になっていて、助言問題間は並列の関係です。「こんな強み(経営資源)がありますよ。じゃあこの強みは新規顧客向けに、あの強みは既存顧客向けに活かしていきましょう!」という流れです。
そのため、事例Ⅱは各助言問題で使った経営資源を第1問の3C分析やSWOT分析にも書いていると、設問間の関係性を理解していることを採点者にアピールすることができ、点数が伸びやすくなります。
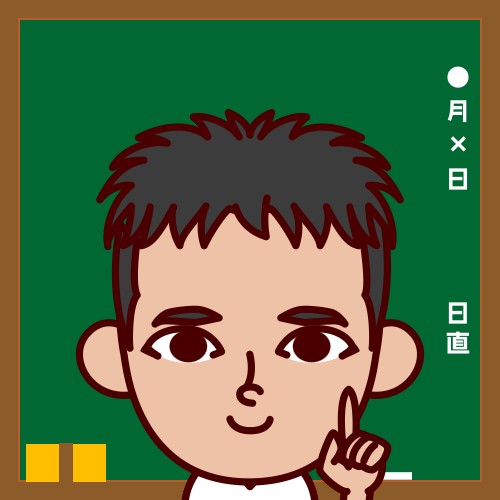
もちろんコンサルティングのやり方としても、強みをマーケティング戦略の経営資源として使うので、コンサルティングの観点からも正しいと言えます
第1問で出した強みを(主に最後の)戦略系問題で活かすパターン
これは事例Ⅲの王道で、第1問と(主に最後の設問の)戦略系問題の関係はこのパターンです。「こんな強みがありますよ。じゃあこの強みを今後の戦略でも活かしていきましょう!」という流れです。
これも先ほどの事例Ⅱと同様、第1問で強みが問われていたら、第1問と戦略系問題に同じ経営資源(技術力や一貫生産体制など)が入っていると点数が伸びやすくなります。
第1問で出した弱みを助言問題(機能別戦略の問題)で解消していくパターン
これは事例Ⅰ~Ⅲのすべてで出てくる可能性があります。例えば「定着率が悪い」とか「新規顧客が集まりにくい」とか「納期遅延が発生している」という弱みを第1問で出して、その改善策として「提案制度を設けて意欲を向上させる」とか「イベントを開催して新規顧客を獲得する」とか「段取り改善をして生産リードタイム短縮を図る」が解答になる設問を後に用意します。
途中の設問で出てきた問題点・欠点を後の設問で解消するパターン
これも事例Ⅰ~Ⅲのすべてで出てくる可能性があり、先ほどの第1問が第2問以降になっただけです。つまり、前の設問で問題点や欠点を指摘させて、その改善策として後の設問が用意されているパターンです。
問題点や欠点を指摘して終わりならコンサルティングにはなりません。指摘したなら必ず最後までに解消させる必要があります。
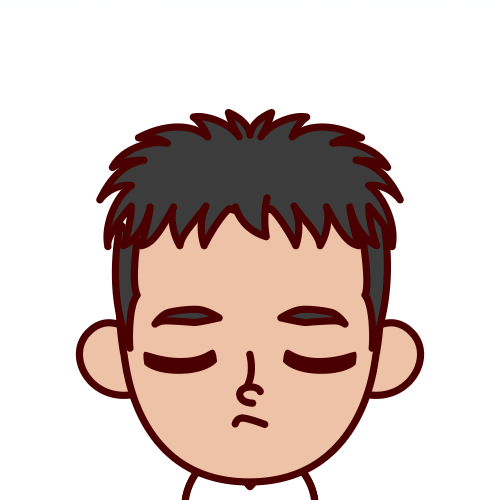
おたくは作業場のレイアウトがごちゃごちゃしていることが問題ですね
そうなんですよ。で、どうやって改善したらいいですか?

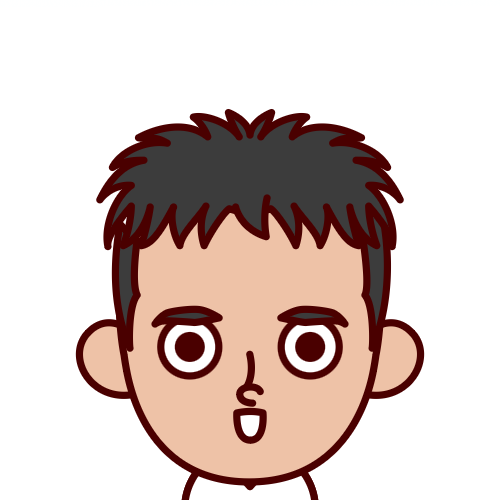
さぁ?それはご自身でお考えください
えっ?・・・(何だよコイツ!)

これじゃコンサルティングじゃないですよね(笑)
前の設問の設問文に出てきた内容や解答内容の理論的な短所を後の設問で解消するパターン
これは事例Ⅰで出てくるもので、これができるとかなり強者です。
例えば無関連多角化の設問が出た場合、無関連多角化の短所には「経営資源が分散する」がありますよね。その経営資源の分散の対策として、「職務拡大、横断的交流」が解答内容になる設問が後に用意されています。
また、外注をする設問が出た場合、外注の短所には「納期や品質の問題が出る、自社の営業力が育たない」などがありますよね。それを解消するために「外注先への管理、自社の営業力の育成」が解答内容になる設問が後に用意されています。
後の設問の設定で表面化させている場合もありますが、表面化させていない場合もあります。この場合、設問間の関係性を把握できる人は「前の設問の理論的な短所の改善の内容で書けばいい」と解答内容の範囲を絞ることができますが、把握できない人は何を解答したらいいかわからず自由作文大会のようになってしまい、点差がついてきます。
.jpg)
今後の戦略としてM&Aをしましょう!
いいですねー。わかりました

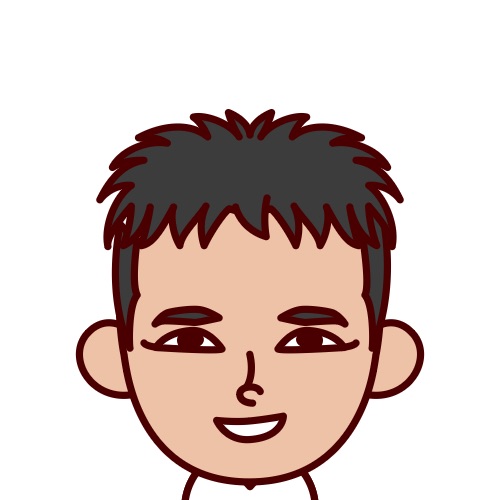
(M&Aには「組織文化や人事戦略の擦り合わせの手間とコストがかかる、ベテラン従業員のモチベが下がる」って短所があるけど、社長は気づいてなさそうだな。言うと面倒だし黙っておくか・・・)
え?何かまずいことでもあるんですか?

これもコンサルティングになりませんよね
令和2年度事例Ⅰ第1問(設問1・2)
第1問(配点 40 点)
以下は、老舗蔵元 A 社を買収する段階で、企業グループを経営する地元の有力実業家である A 社長の祖父に関する設問である。各設問に答えよ。(設問 1 )
A 社の経営権を獲得する際に、A 社長の祖父は、どのような経営ビジョンを描いていたと考えられるか。100 字以内で答えよ。(設問 2 )
A 社長の祖父が A 社の買収に当たって、前の経営者と経営顧問契約を結んだり、ベテラン従業員を引き受けたりした理由は何か。100 字以内で答えよ。
今回は大問の「第1問」として(設問1)・(設問2)の構図になっています。この場合、(設問1)の前にも文が書かれています。これは「前文」とか「リード文」と言いますが、こちらについても設問文の一部(設問1と2に共通している設問文)なので、軽く扱わないようにしましょう。
今回の設問間の関係性は、(設問1)でM&Aをやることが決まったものの、このままだと理論的な短所があるため、それを片づけるために(設問2)が用意されています。そのため、順接(因果関係)の関係性になっています。
今回はM&Aの短所への対応策が(設問2)で問われているため、「組織文化や人事戦略の擦り合わせの手間とコストがかかる、ベテラン従業員のモチベが下がる」という短所のことを意識しやすくなっています。
令和3年度事例Ⅰ第1問・第4問
第1問(配点 20 点)
2 代目経営者は、なぜ印刷工場を持たないファブレス化を行ったと考えられるか、100 字以内で述べよ。第4問(配点 20 点)
2 代目経営者は、プロジェクトごとに社内と外部の協力企業とが連携する形で事業を展開してきたが、 3 代目は、 2 代目が構築してきた外部企業との関係をいかに発展させていくことが求められるか、中小企業診断士として 100 字以内で助言せよ。
この設問は大問の間での関係性が問われています。一見すると、2つの設問は内容的につながっていないようにも思えますよね。共通するキーワードも「2代目経営者」以外ありませんしね。
しかし、「前の設問の設問文に出てきた内容や解答内容の理論的な短所を後の設問で解消するパターン」がわかっている人は、第1問のファブレス化の短所(依存度が高くなる)を後の設問で解消することを意識することができます。その結果、第4問に「依存度を下げる」という解答内容を想起することができます。
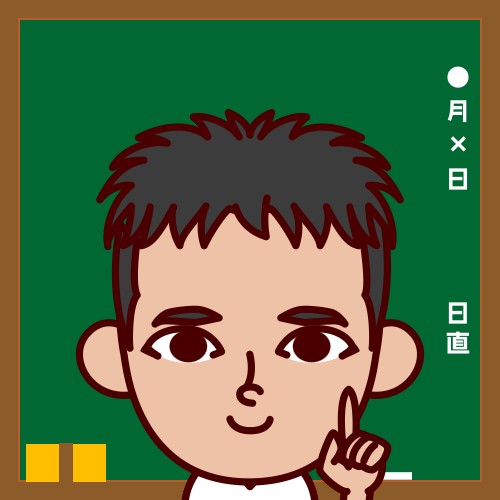
設問間の関係性がわかっていると、想起する内容が増えます
今回の第4問はかなり難しいと言われていました。ほとんどの人が何を解答したらいいかわからず自由作文大会のようになってしまっていました。「負けない戦い」狙いでキーワードが書かれている与件文の段落にある内容をもってきて逃げることが精一杯でした。しかし、設問間の関係性を把握できる人は「前の設問の理論的な短所の改善の内容で書けばいい」ということを意識できるので、「依存度の低下」という解答内容を書くことができます。もちろん、これが書けている人は大きなアドバンテージを得ることができました。
まとめ(2次ベテ勝利のストラテジー25改良版)
ここまでの「設問文との付き合い方」の内容を、以前紹介した「2次ベテ勝利のストラテジー25」に合体させてみましょう。いわゆる「グレート合体」みたいなもので、「勝利のストラテジー25」をベースに、パワーアップツール(強化パーツ)の「設問文との付き合い方」の内容を合体させた【改良版の勝利のストラテジー25】は最強のツールになりますよ。
.jpg)
以前のストラテジー25は「安定して60点以上を取れる」としていましたが、合体後の改良版では「安定して65点以上を取れる」としています。
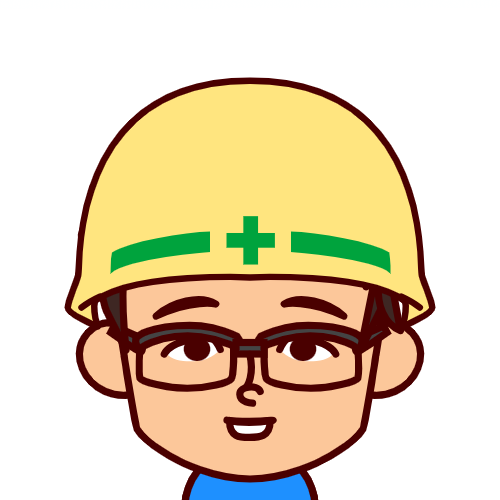
ロボットアニメでも戦隊シリーズでも、グレート合体は男のロマン!!
2次ベテ勝利のストラテジー 25(改良版)
事例Ⅰ~Ⅲで安定して65点以上を取るために、「取るべきところ」のパターンを押さえ、以下のような流れをプロセスに構築させましょう。
設問文の題意や制約条件に従うこと(指示に従うこと)
これが前提になります。ここで間違った解釈をすると、一気にチャンスがなくなります(だからこそ、日々の要求解釈トレーニングが重要になります)。
スラッシュを引いて設問文をいくつかの「部分」に分ける
要求解釈の段階では①想起する、②与件文から見つけてくる、のどちらになるか決まらない部分もあります。
各部分について対応する内容を想起する
これは要求解釈トレーニングで経験を多く積み、想起する内容がポンポンと出てくるまで繰り返し行うことが鉄板です。
前の設問との設問間の関係性を意識する
設問間の関係性を意識し、そこから解答内容になりそうなものがあれば想起しておきましょう。特に事例Ⅰでは「前の設問の設問文に出てきた内容や解答内容の理論的な短所を、後の設問で解消するパターン」の余地を意識しましょう。
各部分について対応する内容を与件文から見つけてくる=設問文に書かれているフレーズと同じ内容が書かれている段落、明らかにこの部分を使うとわかる段落(+その前後の段落)の与件根拠を使う
「取るべきところ」のパターンの、【与件文の内容】の3つのパターンです。
- 設問文中のフレーズと同じフレーズが書かれている段落にある内容
- その前後の段落(最初の接続詞など、話の流れで判断)にある内容
- 同じフレーズはないが明らかにこれは解答に使うとわかる段落にある内容
この2つのステップができていると、結果的に切り分けミスもなくなります
与件文の内容(与件根拠)を入れ、因果関係でつないでいく
因果関係の流れはどこかにメモ書きをしたほうが確実にできます。
因果関係に穴があるところや、最後の効果の部分に最適な知識フレーズを1〜2個入れる(乱発はNG)
「取るべきところ」のパターンの、【知識フレーズ】の部分です。
- 王道の知識フレーズ
※知識フレーズを適当に乱発しても(平成の頃はそれでも良かったのですが)今だと得点はほとんど伸びないと思っていてください。与件文の内容(与件根拠)がないと点数は伸びません。
あとはこの安定感を高めていきましょう!
このストラテジーのうち、青の●印で塗られているステップは、これまでのストラテジー25にあった内容です。その上で「強化パーツ」として今回新たに入ったものが、白の〇印で青の字で書かれているステップです。
通常のストラテジー25の内容でも、安定して高配点の解答要素の数を稼ぐことができ、点数が伸び、結果的に60点以上(取るべきところ7割以上が目安)を取れる可能性がグンと上がるものです。それが今回のパワーアップによってさらに強化され、安定して65点以上を取ることも可能になりました。
これができるようになったご自身を想像してみてください。強すぎてワクワクしてきませんか?
そうすると、自信がついてくると同時に精神的余裕が出てきて、難しい問題は「負けない戦い」狙いに切り替えることができるようになりますし、「取るべきところ」ではない部分には一切こだわらなくなります。
今日のGRe4N BOYZ:ボクたちの電光石火
いきなり「この四角の中を埋めなさいと問われ続けて そこには入りきらない答えを僕ら探してる」という歌詞がありますが、まさに2次試験ですよね。なので、2次の演習の前後でよく聞いていました。
また、「倒れたって何度だって立ち上がり続けよう」という歌詞も、まさに上級生なら刺さる歌詞かと思います。試験の結果もそうですが、普段の演習もそうです。課題がたくさん落ち込むこともあると思いますが、何度でも立ち上がり続ければいいのです。
次回予告
今回は設問文との付き合い方について見ていきました。2次試験の勉強時間の4〜5割は事例Ⅳに注ぐとしたら、残り5〜6割は事例Ⅰ〜Ⅲに注ぐことになります(多年度生ほど事例Ⅳの割合を減らしてOKです)。そのうちの半分は設問文の分析(要求解釈)のトレーニングに使ってもいいです。それくらい、設問文の分析は重要なものになります。
今回もありがとうございました。
次回の私の「レギュラー記事」は、2次試験の合格発表を受けてのメッセージをお送りします。次回もよろしくお願いします。
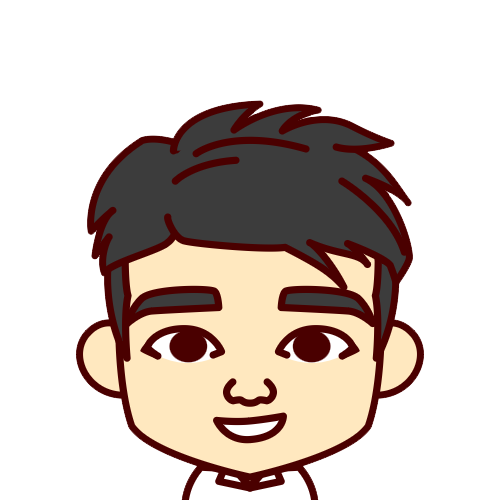
明日は私の出番・・・
.png)
いや、明日も私が連投します(笑)
ごり、その代わり年明け一発目は任せたからね!
明日は「番外編記事」として、「とっても忙しい人に向けた勉強法」を、かますとのコラボ記事としてお送りいたします。
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)



こんにちは!
にっくです。
「設問分との付き合い方」の記事、ありがとうございました!
本音を言うと、もっと早く知りたかったです。とはいえ、本来なら自分で導き出すべきもの、ありがとうございます。
来年度は1次免除受けられるので、そこで力を発揮します。
ありがとうございました!
にっく
にっくさん、コメントありがとうございます。
この記事は10月の2次試験を受けた受験仲間からのリクエストで作りました。
書いてあることはまさにその受験仲間の感想から作りましたので、共感していただけると思います。