【ゆるわだ】棚卸差異はなぜ起こるのか by しん

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
こんにちは、しんです。
2024年も残すところあと3日になりました。当ブログをリアルタイムで読んでくださっているみなさんの多くは、勉強に勉強を重ねた一年だったのではないでしょうか。
私個人としては、不安だらけの中で道場活動を始めたり、診断士の学びの場に参加したりと激動の1年でした。
激動の中心となっている道場活動については、読者のみなさんからコメントをいただいたり、リアルで交流させていただいたりしたことで、今では不安よりはるかに大きな楽しさをもって活動できるようになりました。
改めて、読者のみなさまにお礼申し上げます。
年が明けた数か月後には代替わりを予定していますが、引き続きよろしくお願いいたします。
- 1. 本日の要約
- 2. はじめに
- 3. 事前準備(2週間前~棚卸前日)
- 3.1. 棚卸伝票の用意
- 3.2. 棚卸当日に物の出入りをなくすための調整
- 3.3. 棚卸当日に仕掛品を減らすための調整(懇願)
- 4. 事前準備(棚卸前日)
- 4.1. システムの在庫情報の最新化
- 4.2. 在庫一覧の印刷
- 5. 棚卸当日
- 5.1. 午前8時
- 5.2. 正午
- 5.3. 午後3時
- 5.4. 午後5時
- 5.5. 午後10時
- 6. 後日調査
- 6.1. 原因①:システムへの入出庫登録ミス
- 6.2. 原因②:システムと現品の管理単位の不一致
- 6.3. 原因③:現品在庫に貼り付けている現品票への記入忘れ
- 7. 後日談
- 8. 診断士目線で振り返ってみると
- 9. 終わりに
本日の要約
本日の要約
- 概要:1次試験の財務会計で取り扱われる棚卸差異がなぜ起こるのかを実例を交えて紹介します。
- お伝えしたいこと:棚卸は、モノを扱う企業にとって一大イベントであり、結果から業務改善のヒントがたくさん得られます。
- キーワード:ERP、棚卸差異、権限委譲、属人化、BOM、標準原価、標準化、動機付け要因、衛生要因、他
上記の内容で気になる部分やフレーズがありましたら、引き続き本編もご覧ください!
はじめに
みなさん、棚卸というワードでどのような作業をイメージされるでしょうか?
多くの方は
「ハンディ端末でRFIDを読み取る作業」
「ハンディ端末で品目や棚の情報が登録されたQRコードを読み取って、現品を数えてその数をアプリに入力する作業」
といったハイテクなイメージをされるのではないかと思います。

ハンディ端末(引用元:unitech HT730)
そんな棚卸ももちろんありますが、以前働いていた限界町工場は初めてシステム(ERP)を導入した直後というアナログ作業が多く残る職場であり、棚卸もガチガチのアナログ作業でした。同じような規模の中小企業は少なからず、資金面や費用対効果の問題から、アナログな棚卸をしているのではないかと思います。
今回は、中小企業診断士の主な支援相手となる、中小企業のリアルな棚卸の実例を紹介できればと思い、私が町工場に勤務していた時に体験した棚卸作業のトラウマ記憶を呼び起こします。
棚卸はお金を生む業務ではありませんが、適切に行わないと意図的ではないにせよ不正会計と同様の結果となり得ます。今回紹介する残念な実例から、棚卸差異はどのように起こるかを感じてもらえると嬉しいです。
ちなみに、意図的に行うとせーでんきのような本職(公認会計士)の目が光ると思いますので、絶対に真似しないでください!絶対に・・・。
そんな本職が不正会計を解説した記事はこちら↓
また、諸事情により一部、フィクションを織り交ぜます。
それやばいと感じる部分はきっとフィクションです。
事前準備(2週間前~棚卸前日)
トラウマ記憶は、それまで工場で管理面を一手に担当していた同僚が1年くらいで雲隠れのように退職し、何も情報が残っていない状態で、担当をぶん投げられた権限委譲されたところから始まります。
それまで在庫を数える実働部隊として携わった経験や、web等で調べた情報から、事前準備が必要だということが分かったため、手探りで準備を行うことにしました。
棚卸伝票の用意
事前の準備として、まず必須だったのが棚卸伝票の発注です。
勤務先の町工場では、以下のイメージ図のような複写式の棚卸伝票を使用していました。

ちなみに、複写式というのは、宅急便の伝票のような1枚目に書くと2枚目に転記される紙のことです。1枚目をそれぞれの在庫に、転記された2枚目を管理・集計用の用紙として利用していました。
そんな必須アイテムの棚卸伝票ですが、発注業務が前任者に属人化しており、どこに頼んでいたかも不明な状況だったため、取引先からの過去の請求書を漁り、突き止めた記憶があります。
結果的に無事棚卸伝票を発注でき、最初の関門を乗り越えることができました。
棚卸当日に物の出入りをなくすための調整
続いて行ったのが、棚卸当日に製品の出荷や材料の入荷をなくすための調整です。
IT活用が進んでいる企業では、棚卸当日に物の出入りがあっても問題ないかもしれませんが、アナログな棚卸の場合、集計のずれの原因となるため避ける必要があります。
ちなみに、私が働いていた町工場では半年に1回の月末に棚卸を実施していました。
月末というタイミングで問題となるのが、中小企業あるあるかもしれませんが、材料を購入している取引先の方が強く注文した納期より前倒しして月末に滑り込み納品されることです。
取引先にとっては、月末に納品できれば営業担当者の営業成績もあがり、キャッシュインが早まるのでいいことずくめですよね。
また、製品の出荷についても、棚卸日に出荷することを防ぐため、1日早く出荷する等の調整を行いました。
材料、製品両方について調整を行い、当日に物の出入りはなくせる見通しが立ちましたが、それでも不安が残り他に何かできないかを考えに考えました。その結果、棚卸に携わる方にとっては当たり前かもしれませんが、仕掛品ってやばいのでは?という発想に至ります。
棚卸当日に仕掛品を減らすための調整(懇願)
仕掛品がやばいと感じて行ったのは、棚卸当日に仕掛品をできる限り少なくするための調整です。
1次試験の経営情報システムで出てくるBOM(Bill Of Materials)をイメージしてもらえればと思いますが、生産や在庫を管理するシステムには作りかけの仕掛品を品目として登録することは基本的にありません。もし、仕掛品が存在する場合、システム上で在庫を適切に計上できず、在庫のずれの原因となります。
身近な例として料理で説明すると、システム上に親品目としてカレーライス、子品目としてカレールー、玉ねぎ、人参、じゃがいも、豚肉、白米が登録されているとします。その場合、在庫の管理もそれらの品目単位となるのですが、カレーライスをルーを入れる直前まで仕上げた段階で止めてしまうと、システム上どの品目としても在庫として計上できなくなってしまいますよね。
(より細かい話をすると、製造オーダーに進捗率をかけて親品目として計上したりすることもあるのですが、マニアックすぎるので割愛します。)
そんなやっかいな仕掛品を減らすために行ったことは、「現場の職人さんにひたすら懇願」です。説明が長くなったわりには、行ったことはシンプルでした。。
事前準備(棚卸前日)
いよいよ翌日が棚卸となり、緊張感が増してきます。
棚卸前日まで様々な準備をしてきてましたが、前日の夜に最後の関門が立ちはだかりました。システムの在庫情報の最新化と在庫一覧の印刷です。特に、前者がハードで、日付が変わりかける時間まで作業を行っていた記憶があります。
システムの在庫情報の最新化
冒頭でも触れた通り、限界町工場はシステム(ERP)を導入したばかりであり、受け入れ作業や出荷作業は依然アナログなままでした。具体的には、ある日に発生した入出庫(物の出入り)を、翌日システムに人の手で入力するという、ITを活用しているのにアナログな作業を行っていました。
翌日入力する分にはなんともない作業であったものの、棚卸用の最新の在庫一覧を印刷するにあたって、棚卸前日の入出庫をその日のうちにシステムに入力しなければならなかったため、現場の職人さんが帰った後に、ひたすらPCとにらめっこしていた記憶があります。
つらかったからか、ハイになっていたからか、今でもその光景を鮮明に思い出すことができます。。
在庫一覧の印刷
システムの在庫さえ最新化できてしまえば、後はシステムの在庫一覧画面からエクセルを出力して少し加工するだけの簡単な作業です。
これでようやくすべての準備が終わり、ついに棚卸当日を迎えます。
棚卸当日
ついにこの日がやってきました。
工場のボスがOKを出さない限り帰れない日であり、憂鬱で仕方ありません。依然不安はあったものの、棚卸伝票と最新の在庫一覧が用意でき、棚卸自体はできる状況までたどり着いていましたので、ほっとしました。
我ながらハードルを低く設定したものです。。
午前8時
各工程の棚卸を担当いただく現場の職人さんに棚卸伝票を渡し棚卸を開始します。
作業自体はベテランだらけの現場の職人さんにとっては勝手知ったる内容であり、細かいところはお任せしてガシガシ進めてもらいました。
正午
いつも通り、集計を進めたのにもかかわらず、まったく在庫が合う気配がなく、現場の職人さんがざわざわし始めます。
今まではこのくらいの時間で一部の品目の棚卸が終わることが多かったため、嫌な予感がし始めました。
午後3時
ようやく一部の品目でシステムと現品の数量が一致し始めます。
同じタイミングで、担当工程の棚卸が終わる職人さんが出始めました。休憩して欲しいところではあるのですが、担当工程の棚卸がまだ終わっていない職人さんからクレームが出てしまうので、他の工程のヘルプに入ってもらいます。
残念ながら在庫は依然として全く合いません。
午後5時
定時になったものの、システム上の在庫と現品在庫がまだまだ合わず終わる気配がありません。
誤差が金額比で10%以上あったため、さすがに現品の棚卸漏れがあると判断しました。
現場の職人さんからは管理部門に対するクレームが飛び交いますが、ボスからも完了の許可が出ず終わらすわけにはいかないため、頭を下げて再確認を依頼します。
管理部門はちゃんと仕事しているのか!!
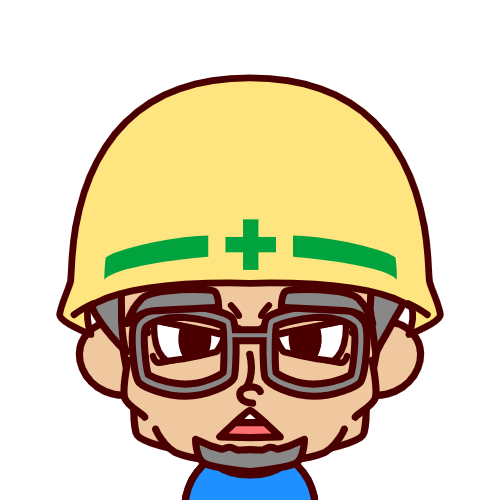

申し訳ありません・・・!!
(そんなこと言われても・・・)
ここまでデータ入力や担当者間の調整を主に担当していた私自身も、それらの作業が落ち着いたこともあり、怪しい現物を片っ端から確認しにいくことにしました。
そこで、念のためと思い、通常使用していない工場2階の物置きスペースにも突撃したところ、奥の方でほこりだらけになってはいるものの、鈍い輝きを放つ高価な材料を見つけました。棚卸漏れかなと思い、それが何かを確認しようとしましたが・・・

キメラにされてしまいそうになったので、記憶にそっと蓋をします。
簿外在庫は見なかったことにして、差異があった材料をしらみつぶしに確認し、わずかながら現品の棚卸漏れを潰すことができました。
午後10時
いくつか棚卸が漏れていた現品を発見できたものの、システム上の在庫と現品在庫には依然派手な(金額比10%以上の)差異がありました。
ただ、これ以上改善する見込みがなく、ボスより現品在庫を正として終了するお許しが出たため、ようやく長い棚卸が終了となりました。
責任問題となること間違いなしだったからだとは思いますが、何も知らないのにお怒りのボスより、どのような原因で差異が発生したのかを後日徹底調査するよう指令が下ります。
勘弁してくれ・・・と思ったのはここだけの話です。
後日調査
差異原因の徹底調査を厳命され、システムの取引履歴や現品の入出庫の記帳をしらみつぶしに確認したところ、主な原因を3つ特定することができました。
特に、システム面での原因を突き止めた時のことははっきりと覚えています。今思えば大した内容ではないですが、若かりし頃?の私にとって、人間不信になって謎の高熱で寝込んでしまうほどの衝撃でした。
原因①:システムへの入出庫登録ミス
棚卸で派手な差異が生じた最大の原因はシステムでの入出庫ミスです。
小規模な会社であるため、秤量機とシステムを連携した自動で入出庫が登録される機能や、ハンディ端末のようなハイテクな装備はなく、現場の職人さんが手で書いた入出庫伝票を基に、管理部門の担当者がシステムに手打ちでインプットする運用を行っていました。ちなみに、システムへのインプットは、退職済の前任者が専任で行っていた、属人化しまくりな作業です。
2重作業、かつ属人化しまくりと嫌な予感しかしませんが、過去の取引履歴と紙の注文書や入出庫伝票を1件1件突き合せた結果・・・
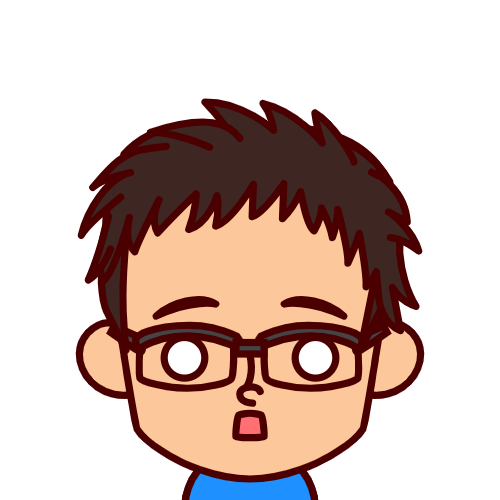
実際に購入した数量に対して、システムに登録された入庫数量のゼロが1個多い材料がいくつかある・・・!!
という衝撃の事実が判明します。
数字はざっくりですが、具体的には700円/kgの材料を1,000kgで購入したという事実に対して、システムに10,000kg入庫していました。
この処理により、
700円×(1,000kg-10,000kg)=-630万円
の棚卸差異が発生することになります。
※簡略化のため、原価や正味売却価額は考慮しません。
このような在庫データが複数あり、売上が数億円程度の町工場としてしゃれにならない事態になっていました。
原因②:システムと現品の管理単位の不一致
2つ目の原因は1つ目の原因の真因ともとれますが、システムと現品の管理単位が異なっていたことです。
どういうことかというと、注文書上kgで購入している材料を、何故かシステムではメートルで管理していました。その結果として、システムの単位に気づかずに、注文書の数量で入庫してしまっていた(と思われる)ことでした。
具体的には、700円/kgの材料を1,000kg(70万円分)購入しており、それが10mの長さだったのですが、システムでは在庫単位をmで、金額を7万円/mで管理していました。
その状況化でシステムに、注文書の数量の1,000(kg)から拾ったと思われますが、1,000(m)と入庫していました。
この処理により、
700円/kg×1,000kg-7万円×1,000m=-6,930万円
の棚卸差異が発生することになります。
単位を間違えることは、ゼロを1個間違えること以上に影響が大きくなり得ることが伝わったでしょうか。
数字を少し大げさにしましたが、このような事象が起こっていたことは紛れもない事実でした。
これらの事実を突き止めた頃、退職した同僚はなぜこんなことができたのか理解できなくなり、1週間程寝込みました。当時一人暮らしでしたが、体温が41度位まであがり、トイレで気絶したりと、いろいろ危なかったような気もします。。
復帰した後は、速やかにシステムの管理単位を実態(注文する単位)と合わせる処置を行いました。
これらの事象を診断士となった今、冷静になって思い返すと、決して担当者の問題ではなく管理や教育の体制が整っていないこと、担当者の強みや特性、スキルの確認が十分でないままアサインしてしまったこと等、組織的な要因が大きかったと思います。
このような経験からか、人事や運営面を改善する支援にゆくゆくは携わたいと思う今日この頃です。
原因③:現品在庫に貼り付けている現品票への記入忘れ
3つ目の原因は、現品に貼り付けてある現品票への記入忘れでした。
具体的には、700円/kgの材料を10kg使用したという実績を現品票には記入せず、システムには10kgを出庫する登録がされていました。
この事象により、
700円/kg×10kg=7,000円
の棚卸差異が発生することになります。
これまでの原因と比べると、頻度、影響共に微々たるものでしたが、こういった細かい積み重ねが大きな棚卸差異に繋がりますので、日頃から意識することなく手間もかけずにチェックできる仕組みを構築しておくことが重要だと思います。
後日談
私自身は深くは携わりませんでしたが、原因が判明してからしばらくの間、経理部門の方が頭を抱えていたようです。
データの登録ミスや漏れが多数確認された結果、それまでの原価計算がでたらめな数字になっていたためです。
当年度の財務諸表はもちろん、翌年度の標準原価算出にまで影響を及ぼす事態となっていました。
今振り返るとグレーというかアウトな気がしますが、経理の偉い方の指示に従い、システム上のデータを小まめにごにょごにょして、半年位かけて正常化した記憶があります。
自身、高熱で寝込んだこともあり、こんな棚卸は二度と繰り返したくないという思いから、システムや運用を徹底的に理解した上で、マニュアル作成や複数人で処理できる体制整備を進めました。
その結果、次の棚卸からは誤差が1%未満と大きく改善することができました。
泥まみれな職歴ではありますが、密かに自慢できる成果だと感じています。
診断士目線で振り返ってみると
原因のパートでも少し触れましたが、診断士として前職を振り返ると、まずは管理体制や教育の強化を提案したいと感じます。
- 作業マニュアルを作り、作業を標準化すること
- 標準化した作業を複数人、またはローテーションで行えるようにし、属人化を防ぐと共に相互チェックを行えるようにすること
- 管理者を含め、システムへのデータ登録作業の重要性を周知すること
あたりが短期的に行えることでしょうか。上の2つは在籍中に自身である程度改善できたものの、一番下の部分はほぼ手をつけられかったのが心残りではあります。
また、管理や教育の体制を改善出来次第、ハンディ端末やラベルプリンター等を導入し、入出庫の2重作業をなくす取り組みを進めたいと強く思います。
2重作業は非効率な上にミスの要因にもなり、生産性向上を妨げる作業だと感じるからです。
現場の職人さんから作業が増えるとクレームを浴びそうですが、動機付け要因や衛生要因の切り口でメリットを提示すれば了承してもらえるかなと。。
在籍していた時は余力がなく知識も足りませんでしたが、今はできることも増えましたので、お礼参りがてら?久しぶりに顔を出して悩み事を聞きにいこうかなと考えています。
終わりに
今回は、自身の記憶を振り返り、中小企業の棚卸について紹介しました。
中小企業診断士試験では、財務会計で棚卸減耗損を求める計算問題が出題される程度で大きく取り扱われませんが、モノを扱う企業にとっては重要な作業であり、悩みを抱える経営者も少なからずいるのではないかと思います。そんな棚卸に少しでも興味をもってもらえたら嬉しいです。
明日は、サトシの出番です。何やらいつもよりはるかに長い記事を用意しているようですので、お楽しみに!
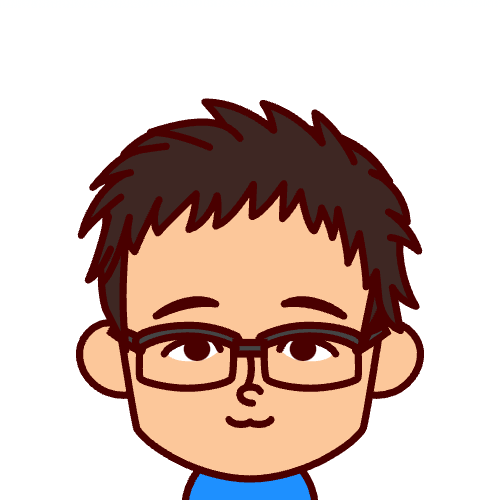
「いつも」が既に長い記事のような・・・。
ユーロビートを聴きながらノリノリになっていたら、書きすぎてしまったよ(笑)

☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)



あけましておめでとうございます!
にっくです。
棚卸しの妙、震えるほどでした・・・!
0が1個、それだけで大変な事態になるとまざまざと追体験しました。
これから電卓を打つとき、慎重に打つようになると思います。
ありがとうございました!
にっく
にっくさん、コメントありがとうございます。
0が1個増えることで大変な事態となることをお伝えできてよかったです。
電卓もついスピードを優先したくなりますが、正確性も重視してみてもらえたらと思います。
大変参考になる記事ありがとうございました。業種が異なるためとても新鮮に感じ、あっという間に読んでしまいました。原因②は想像付かない状況ですね。。。原因追及を諦めないしんさんのメンタルのすごさにびっくりです。管理体制や教育の強化は私も実施出来ることなので来年に向けて参考にします!
しまんと1号さん、コメントありがとうございます!
中小企業のリアルをお伝えしたく書いた記事でしたので、少しでも参考になったのでしたら幸いです。
高熱で寝込んで限界を知ったこともあり、当時ほどのメンタルの強さは発揮できませんが、未だにデータの不整合を見つけると許せなく、原因追及したくなります。。
管理体制や教育の強化は診断士の知識をダイレクトに活かせる分野だと感じますので、ぜひ知識のアウトプットがてらトライしてみてください!