【サトシの書籍シリーズ】④伴走支援って?

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
一発合格道場ブログを
あなたのPC・スマホの
「お気に入り」「ブックマーク」に
ご登録ください!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
みなさん、こんにちは。
もはやレジェンド投稿シリーズも含め、毎週火曜日を乗っ取ってしまった「サトシ」です(笑)
「サトシの書籍シリーズ」4回目は、「伴走支援」について解説したいと思います。これは近年の診断士のコミュニケーションの方法として国からも指示されているものなので、ぜひ今回の記事と実践によって身につけていきましょう!
内容としては、1回目の「診断士のコミュニケーション」にあった「双方向のコミュニケーション」を深掘りしていく形になります。
また、2回目の「診断士のメンタル」も必要になります。例えば謙虚さや相手への敬意などがないと伴走支援はできません。「べき思考」や優劣の意識があっても伴走支援はできません。まずは「診断士のメンタル」でメンタルのトレーニングをしましょう。
それでは、今回もよろしくお願いします。
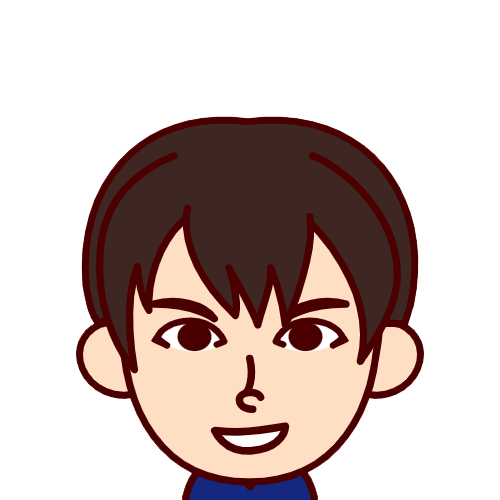
もはや聞くまでもないけど、今回の字数はどれくらいなの?
当初は50,000字あったけど、削りに削って25,000字にしたよ(笑)

- 1. 第1章:伴走支援の概要
- 1.1. 伴走支援とは
- 1.1.1. 答えはクライアント自身の中にある
- 1.1.2. 診断士と相手企業(の社長)は伴走の関係
- 1.2. 伴走支援が求められるようになった背景
- 1.2.1. 支援者(診断士)側の背景
- 1.2.2. 相手企業側の背景
- 1.3. 伴走支援でタブーの五大思考
- 2. 第2章:経営力再構築伴走支援モデルの基本的な流れ(枠組み)
- 2.1. ①事業者と接する前(契約)
- 2.2. ②事業者・支援者双方の理解
- 2.3. ③伴走支援の開始、ヒアリング(信頼関係の構築を含む)
- 2.3.1. 傾聴
- 2.3.1.1. 上から目線の聞き方はNG!
- 2.3.1.2. 知ったかぶりはNG
- 2.3.1.3. 「わかります」は危険
- 2.3.2. 信頼
- 2.3.2.1. アイスブレイクも大事
- 2.3.3. 相手の社長や従業員にネガティブなマインドが染みついていることも
- 2.3.3.1. 社長は孤独
- 2.3.3.2. 一枚岩とは限らない
- 2.4. ④気づき・腹落ちの促進
- 2.5. ⑤ヒアリング後
- 2.5.1. ヒアリング内容の整理(現状とあるべき姿の明確化)
- 2.5.2. 真因分析・ゴールイメージ&ストーリー描写
- 2.5.3. 本質的な課題へのアプローチ
- 2.5.4. 全体最適調整
- 2.5.5. 具体的な改善策を作る
- 2.5.5.1. 複数提示する
- 2.5.6. 具体的なアクションプランの設定
- 2.5.7. 経営改善提言を含む経営診断報告
- 2.5.8. 内発的動機づけ
- 2.5.8.1. 相手が動くためのハードル
- 2.6. ⑥課題解決(行動変容・スモールステップでの成功体験の蓄積)
- 2.6.1. フォローアップ(事後フォロー)
- 2.6.1.1. 時には我慢も必要
- 2.7. ⑦ゴール・卒業
- 3. オマケ:これまで受験仲間だった受験生との付き合い方
- 4. おわりに
第1章:伴走支援の概要
みなさん、「伴走支援」って聞いたことありますか?
実はチラっと出てきていますよ。2022年版のものから「伴走支援」というフレーズが中小企業白書や小規模企業白書には毎年のように出てきています。毎年最後のほうにあり、伴走支援の図と事例とともに紹介されていることが多いです。
例えば中小企業白書2023年版(令和6年度の1次試験の範囲)のⅡの333ページにも「伴走支援モデル」というものがあります。

そして、この伴走支援が診断士に求められていて、診断士にとって非常に重要なものになります。
伴走支援とは
さて、今回のテーマである伴走支援の定義を見てみましょう。
まず、中小企業庁や中小企業基盤整備機構から出ている「経営力再構築伴走支援ガイドライン」によると、伴走支援とは以下のように定義されています。
経営力再構築伴走支援は、経営者等との「対話と傾聴」を通じて、事業者の「本質的課題」に対する経営者の「気づき・腹落ち」を促すことにより「内発的動機づけ」を行い、事業者の「能動的行動・潜在力」を引き出し、事業者の「自己変革・自走化」を目指す支援方法である。
経営力再構築伴走支援ガイドライン(一部加筆)
ポイントになるのは定義の「 」の部分です。定義の全部ではなく「 」の部分だけを見た上で、続いての説明を見たらいかがでしょうか。実は、ここにあるものと似たようなスキルをみなさんも聞いたことがあると思いますよ。
そう。「コーチング」です。
伴走支援は、基本的にはコーチングです。意外かもしれませんが、コンサルティングではありません。また、カウンセリングやティーチング(教える)でもありません。

コーチング、伴走支援、双方向のコミュニケーションの3つはほぼイコールのものと思ってOKです
コーチングの定義
伴走支援が大きく影響を受けているコーチングの定義を見ていきましょう。
コーチングで有名なコーチ・エィの「新版 コーチングの基本」によると、コーチングの定義は以下のようになっています。
コーチングとは、対話を重ねることを通じて、クライアントが目標達成に必要なスキルや知識、考え方を備え、行動することを支援するプロセスである。
コーチ・エィ「新版 コーチングの基本」より
また、クライアントの能力を最大限に「引き出す」コミュニケーションスキルであることも付け足されています。
ポイントは「引き出す」です。「指示や指導によってクライアントの能力を高める」ではありません(これは「外発的動機づけ」ですね)。

「引き出す」に違和感があるなら「一緒に考える」や「一緒に探索する、発見を促す」でもOK
あくまで支援者(診断士)はコミュニケーションを通じてクライアントの内面にあるポテンシャルや可能性を「引き出す」だけの役割にすぎません。つまり、対話と関わりを通じて(傾聴や質問によって)クライアントの思いやスキルを「引き出す」ことで、クライアントのモチベーション(内発的動機づけ)を高め、目標達成に必要な知識やスキル、考え方をクライアントと一緒に考え、クライアントの自己成長や自発的行動を引き出し、目標達成までのサポート(行動の支援)をするだけです。
さて、伴走支援もそんなコーチングのスキルが基本になっております。コーチングでは提案や個人的な事情に触れることはNGとなっていますが、それが少し緩くなったようなイメージです。
答えはクライアント自身の中にある
伴走支援もコーチングも、基本的に「答えはクライアント自身の中にある」が前提です。こちら(診断士)が答えを提示することはありません。
また、目標設定も具体的な改善策の考案も具体的な行動も、行うのはクライアント自身です。こちらはあくまで「質問や共感を通じてクライアントと一緒に考える、クライアントを支援する」なので、主役はクライアントになります。そのため、クライアントにも自発的に考えてもらいます。
そして対話と関わりを通じてクライアントの本音や、当たり前すぎて気づいていないことを潜在化させ、クライアントが自分で答えを引き出せるようにサポート(支援)していきます。クライアントが自発的に考えることで、自分で解決策を見出すので、必然的に納得しやすくなり、行動にもつながりやすくなります。
「支援」と言うと難しい気がしますが、クライアントとの対話や関わりを通じて、クライアントに質問や共感をする、クライアントのモチベーションを上げる、クライアントが考えに詰まったら視点を変えるようなヒントを出すようなイメージです。
従業員も対象になる
伴走支援は相手企業の社長だけでなく、従業員も対象になります。「クライアント」と言えば会社に関わる人全員だと思っておきましょう。
経営者の自己変革力を引き出し、経営力を強化するためには、「現場で」何が起きているかを把握する必要があるため、経営者だけでなく現場の従業員とも対話することが必要です。
そのため、ヒアリングでは社長だけでなく現場の従業員の声も聴く必要がありますし、改善策を考える際も従業員の声を聴く必要があります。もちろん、社長と真逆のことが出てくることもあります。

社長から末端の従業員まで、自分で悩みを乗り越える力が湧いてくるように支援していきましょう!
診断士と相手企業(の社長)は伴走の関係
昔の診断士は「コンサルティング」として「診断士が相手企業に一方的に教える」という関係性でしたが、近年は「支援」として「診断士と相手企業(の社長)は双方向の伴走仲間」という関係性に変わってきています。
具体的には、診断士は相手企業の社長の話を聴き、相手企業の社長が自分で問題解決をできるように支援をすることや、相手企業の社長と一緒に解決策を考えることが求められています。

伴走支援では、支援者(診断士)は「先生」ではなく「パートナー」です
伴走支援が求められるようになった背景
そんな伴走支援ですが、長期間かかるし、相手の本音や気づいていないことを引き出さないといけないし、こちらが改善策を提示してはいけないなど、ちょっと面倒くさそうですよね。何ならスパッと改善策を提示したほうが効率的だし短期的に終わるようにも思えます。 しかし、国(中小企業庁や中小企業基盤整備機構)は伴走支援を勧めている。それはなぜでしょうか?
支援者(診断士)側の背景
まず、診断士側です。
環境変化が激しく変化、多様化。現代は「VUCA:変動性、不確実性、複雑性、曖昧性」の時代で予測不能な時代です。進化や変化が速く、過去の成功例も通用しなくなり、唯一無二の正解もない状況になっています
↓
不確実性向上、課題・改善策の多様化
↓
中小企業の改善策などのネタの把握が追い付かない(昔は診断士が正解や勝利の方程式を考えて相手企業に一方的に提示すればOKでした)
↓
ネタの中から当てはめる路線は限界+税理士など他の士業との競争
↓
伴走により企業の自己変革力・潜在成長力を高める路線へ=経営者自らが課題を考え、対応・実践していくよう第三者が伴走支援
相手企業側の背景
次に、相手企業側です。
普通は「コンサルティング」として「一方向のコミュニケーション」
↓
診断士が傾聴をしない、相手軸がない
↓
診断士が自分主導で進めてしまい相手が十分に話せない
↓
SWOT、課題(現状・あるべき姿を含む)・問題点、原因・真因などの現状把握が十分にできない
↓
相手企業の現状を正しく理解していない(SWOT、課題・問題点、原因・真因をイメージできていない、相手にきちんと説明できるレベルにない)
↓
改善策を自分の知識や経験から提示する、原因や真因を考えずに提示する、あるべき論や机上の空論で提示する、他社の事例をそのまま当てはめて提示する(一方的に教えるだけ、ゴリ押しされるだけになる)
↓
相手企業特有のことを反映していない
↓
相手が納得しない
↓
相手が実行しない
↓
コンサルティング(支援)失敗
多様性の拡大や環境変化の激しさから、何が正解かが簡単には見つけられなくなってきています。また、イノベーションや高次学習を求める声も高まっています。そこで出てきたのがコーチングをもとにした伴走支援です。
診断士に限らず、税理士でも「コンサルティング」をするとこのようになってしまいがちです。近年の企業を取り巻く環境は多様性を増していることからも、このような一方向での指導には限界が出てきました。
そこで、中小企業庁や中小企業基盤整備機構が考案したのが、コーチングを基にした「伴走支援」です。

経営力再構築伴走支援ガイドライン22ページより
そんな伴走支援ガイドラインでは、「伴走支援モデル」というものを用意しています。これに従ってきちんとやっていくと、以下のような効果を得ることができます。
対話と傾聴→経営者(従業員等も含む)が話しながら考える→経営者が自分で気づく→本質的課題への腹落ち・納得→内発的動機づけ→自己変革(マインドセット変化)→能動的行動→潜在力→問題解決→経営力強化・再構築→自走化
伴走支援でタブーの五大思考
伴走支援では、すべてのプロセスにおいて以下の5つの思考はNGとなっています。特にやりやすいのが当てはめ思考、べき思考、指示・指摘思考です。
×診断士がストックしたネタや経験から当てはめること(当てはめ思考)
×診断士の得意分野や得意パターンに誘導していくこと(誘導思考)
×先入観や思い込みで判断すること(べき思考)
×相手の発言を否定・批判的に捉えること(批判思考)
×一方的に教える、押し付けること(指示・指摘思考)
心身の調子が悪いなら休む
体調やメンタルがおかしいときは、パフォーマンスを十分に発揮することができません。トラブルが生じた場合、「体調がしんどくて」や「イライラしていてついカッとなってしまった」は言い訳になりません。その場合は無理せず休んでください。「心身の不調を押してでも働け。それがプロだ」という昭和の文化は診断士の世界にはありません。
不機嫌なときは特に要注意です。こういうときは運勢も悪くなり、なぜか不都合なことが連続で訪れます。このままだとますます不機嫌になり、診断士のメンタルとして超重要な「強気・ポジティブ・楽しい」や「敬意、感謝、尊重、労をねぎらう、謙虚」の気持ちが出にくくなります(詳しくは「②診断士のメンタル」を参照)。
こういうときは「負けない戦い」に切り替えます。最低限のことしかしなくていいです。後回しできることは機嫌が改善するまで待ちましょう。
不機嫌になる場合、大抵は人混みや他人からの不快なこと、スマホやパソコンへの連絡が原因です。そのため、家族と完全に信頼できる人以外はなるべく人と接しないことをオススメします。スマホは置いていき外に出ましょう。それも人がいないところがいいです。そういうところで深呼吸や運動をしてみましょう。
相手が不機嫌なときは
相手の社長や従業員が焦りや怒りからクレームや八つ当たりをしてくることもあります。その場合、相手の意見を否定するのではなく、相手の気持ちを受け止め、相手の要望をしっかりと聞きましょう。相手に寄り添った言葉をかけ、クレームや八つ当たりの奥にある相手の気持ちを読み取り、こちらができる対応策を示します。そして、要望を言ってくれたことに対する感謝の意を示しましょう。
特に社長が不安・ピリピリの状態だと、それは従業員に伝わり、組織全体に浸透します。そうすると改善策やアクションプランもうまくいきません。支援者は社長の不安やピリピリを否定したり煽ったりするのではなく、社長自身が安心できるポジティブな声かけをしていきましょう。
どうしても相手がポジティブ思考なれない状況なら、過度に干渉せず時には距離を置いて見守ることも大切です。
第2章:経営力再構築伴走支援モデルの基本的な流れ(枠組み)
では、ここからは「経営力再構築伴走支援ガイドライン」にある、経営力再構築伴走支援モデルの流れと、各段階にある内容を見ていきましょう。
①事業者と接する前(契約)
ここはクライアント(相手企業の社長や従業員)との接触、進め方の合意の段階になります。
事業者と接する前の周辺情報から事業者に成長の意欲などがなかったとしても、丁寧に対話と傾聴を行うことで経営者の本音がわかることもあります。本音がわかると自己変革に向けた取り組みにも前向きになる可能性があるため、簡単に「この会社は経営力再構築伴走支援は合わない」と判断しないことが重要です。
②事業者・支援者双方の理解
ここは主にヒアリングの前に行う下調べのようなものです。ただし、こちらが相手企業のことを調べるだけでなく、相手企業の人にもこちらが何者か、安心できる人なのかを理解してもらうことを忘れずに行いましょう。
事前準備で業界や相手企業の情報を多面的に収集・把握し、仮説をもってヒアリングに臨むことで、ヒアリングこの段階で経営者の思いやニーズを汲み取る(これらの話が出てきたら具体的に掘り下げていく)ことができます。
仕事でも取引先に関することは調べますよね。伴走支援もこれと同じで、経営者とのヒアリングの前に情報を入手して調べたり分析したりすることが重要になります。 可能な限り事前に調べてくると、ヒアリングで経営者の認識を聞いて補完できます。それによりヒアリング終了時に経営実態や経営環境についての深い理解と洞察を行うことができます。

事業内容や経営環境、経営状況、経営体制などを確認していきます。
具体的には、①内部環境分析(クライアント自身、業務や製品)、②決算書(3〜5期分)の確認と経営分析、③外部環境分析(市場・顧客・競合の分析)を行うことが基本です
なお、実務補習はここからがカリキュラムになっています。実務補習についてはせーでんきのこちらの記事など、道場の記事を検索すれば様々なものが出てきますので、ぜひご参照ください。
③伴走支援の開始、ヒアリング(信頼関係の構築を含む)
経営者へのヒアリングになります。ここでは「傾聴」と「信頼」がカギです。
もちろんヒアリングは1回に限らず、何回もやっていきます(実務補習では1回のみです)。 傾聴のスキルを使い、悩みや不安をしっかりと受け止め共感することで、相手の信頼を得て、本音を話しやすくしていきます。
③〜⑥はスモールステップ・短サイクルで何周もするイメージです。スモールステップで目標を定め、短サイクルでPDCAサイクルを回していきます。それにより、最初は「悩み・疑問・不安」だった相手企業の社長も、最初のヒアリングで「安心・信頼」を得て、何回か接しているうちに「発見・納得・満足」を得ます。そして決断をし、小さな達成をします。その成功体験がその次の目標へのモチベーションとなり、さらなる好循環を招きます。また、途中でうまくいかなくなったときでも迅速・柔軟に軌道修正ができるため、成功率が高まります。
傾聴
これは「聴く力」の本がたくさん出ているくらい、ニーズはあるものの実践できている方は少ないです。
と言っても、いきなり聴き上手になるのは無理なので、段階的にできるようにしましょう。
例えば相槌(頷き)、共感、質問、オウム返し(単語1つでもOK)だけでもやっていきましょう。話の中身は頭に入っていなくてもいいですし、「聞いているフリ」でも構いません。このスキルだけでもかなり「聴く態度」ができてきます。
余裕が出てきたら、口角や眉を上げること、相手の目を見ること、要約、言い換え、沈黙しても話しかけないこと、ミラーリング(スピードや声のトーンを相手と合わせること)ができるようにしましょう。ここまでできると、こちらは「聞いているフリ」なのに相手には「聴く姿勢」に映っています。
自分が話すことよりも相手に話をさせる環境をつくるようにしましょう。もちろん、提案やアドバイス、指摘、アイデア提示はNGです。

ミラーリングについては、声のトーンや大きさ、スピード、タイミング、顔の表情、話す量、ノリの良さも対象になります。人によってペースは異なるので、相手によってペースを柔軟に変えていく必要があります
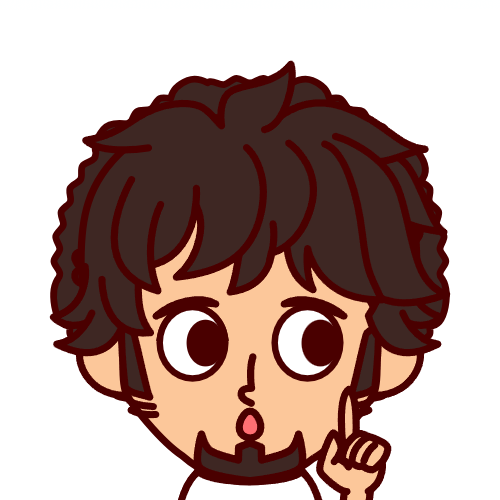
小学校でもこんな指導をしているよ


べびりんにも早速教えないと!
あ~あ~う~
(まだ早くない?)

質問のレパートリーは、究極のところこの5つのみ
- 例えば(具体的には)
- つまり
- なぜ(原因は)
- それでどうなりましたか(結果的には)
- 他には
これらに沿っているなら表現や言い方は工夫してOKです。
ここにあるような聴き方ができず、ヒアリング不足で机上の空論や一般論、知識やノウハウありきの役に立てない提案をしてしまうのが、伴走支援失敗の典型例です。そして、失敗する人ほどヒアリングを軽視しています。
上から目線の聞き方はNG!
上から目線が伝わるような聴き方はやめましょう。腕や足を組むことはもってのほかです。ヒアリングは謙虚さをオーバーに出すくらいでちょうどいいです。「あなたの話を聞かせてください」、「私に教えてください」、「教えていただきありがとうございます」くらいのイメージで聴くと、相手は安心して話すことができます。
社長にしても従業員にしても、「同じ目線」が支援者のコミュニケーションのキーワードとなります。つまり、経営者なら経営者、従業員なら従業員と、それぞれ「目線を合わせる、ペースや方向性を一致させる」ことが必要です。どんな相手でも等しく向かい合う必要があります。社長に対しては同じ目線でも、バイトの従業員には上から目線や先生のような立場では、相手と等しく向かい合っていないことになります。
この同じ目線になるためには、相手への敬意、共感、謙虚な姿勢が必要になります。社長相手だろうが従業員相手だろうが、診断士の知識やノウハウのアピール、上から目線はNGです。上にあるように「聞かせてもらう、教える」より「聴かせていただく、情報提供させていただく」態度で臨むくらいでちょうどいいです。
また、「相手に教えてもらう」というスタンスで望みましょう。「教えてくれてありがとう」と感謝をする、相手の労をねぎらうことが重要です。こちらが相手の発言内容の是非を判断したりアドバイスをしたりすることはNGです。

何でも説明したがる解説者になるのもNGです
知ったかぶりはNG
伴走支援において、知ったかぶりはNGです。プライドの高い人はどうしても「無知だ」と思われたくないからでしょうか、自分の知らないことが出てきても素直に「知りません。教えて下さい」と言えない傾向があります。
わからないことは質問をしないと、その話題の深掘りができない(真因や本質的な課題にたどりつかない)、情報収集が不十分になるなど、不都合が生じてしまいます。
確かにある程度は相手企業の内部・外部環境の知識は収集しておくべきです。しかし限界があるので、知らないことを言われたらすぐ質問しましょう。少なくとも首を傾げるなど、「知らない」とわかるリアクションはしましょう。そうすると向こうは丁寧に教えてくれます。
逆に知ったかりをしても相手企業の社長にはすぐにバレます。わからない言葉や内容があったら必ず質問をしてください。因果関係や背景がわからない場合も必ず質問しましょう。知らないことは素直に「知らないです。教えて下さい」と言いましょう。何となく過ごさないことが重要です。そうしたらすぐに具体的な情報をたくさん教えてくれます。また、素直に「知らない」と言えることは強さでもあります。

プライドが高い人ほど謙虚さがないから素直に聞けません。だからこそ、謙虚さを身につける必要があるのです
「わかります」は危険
聴く力の定番フレーズで、共感の際の「わかります」がありますよね。ですが支援の場合、安易に「わかります」と言うのは危険です。相手からすると「こっちの苦労をそう簡単にわかるわけがないだろ」や「何がわかるんだ?」という印象になります。
相手企業の社長や従業員からすると、「じゃあ今聞いたことをスラスラと説明できるのか?」と言いたいくらいだそうです(そう言われたら実際は説明できないはずです)。相手の言ったことの意味や内容を、因果関係を含めてスラスラと説明できますでしょうか。おそらくできないはずです。
下手をすると「ウチの悩みはそこらへんの企業にもある平凡な悩みと同じですって言いたいのか?」とも思われてしまい、反感を買います。どの企業も「ウチの悩みは特別」とか「そこらへんの企業とは違う特殊な事情がある」と思っています。簡単に「わかります」と言ってしまうとその思いを逆撫ですることになってしまいます。もちろん「共感」にはなりません。
また、認識のズレもありますよね。例えば「現場が混乱している」と相手が言ってきた場合、相手は当然ですが長年見てきた自社の現場のイメージを鮮明にしながら言っています。しかし、こちらは相手企業の現場を見ていたとしてもイメージは曖昧なものになってきます。他社の現場をイメージすることもあるでしょう。
このように、こちらと相手では認識が異なります。こちらが間違って認識していることもあります。簡単に「わかります」と言うのは避けましょう。
仮に「わかります」と言いたい場合でも、「そうなんですね」とか「大変ですね」などが無難です。相手の言っていることをそのまま受け止めればいいのです。
聴く力を使う際は、相手の社長や従業員の話を少し聞いただけでわかったフリをしないことや、相手の話を止めないことが重要です。
「わかります」ではなく、むしろ「すぐにわかろうとしない」ことがコツです。そうすると「なぜ?」とか「具体的に教えてください」など、話を進める質問ができるようになります。

聞き手は相手のことを100%理解することはできないとわかった上で聴くのが大前提です。わざわざ「わかります」と言って墓穴を掘らないようにしましょう!
信頼
まずは経営者や従業員との信頼関係構築を優先しましょう。特に1回目のヒアリングでは信頼関係構築が最優先です。信頼できない人に本音を話そうとは思いません。
信頼関係を構築してからでないと、相手は本音を話してくれません。つまり、「この人には相談できない」ではなく「この人には本音でも不都合な話でも何でも話せる」と思ってもらえる必要があります。そして、この本音に課題や問題点の真因があることが多いのです。
だからこそ、最初は信頼関係の構築が重要になるわけです。相手の心理的安全性を確保することで、相手が本音を話せるような環境づくりをしましょう。信頼関係を構築したら問題点やその原因・真因を探る段階に移るイメージです。

本音には「都合の悪いこと」や「認めたくないこと」も含まれます

経営力再構築伴走支援ガイドライン18ページより
相手の話を聴くときは先ほど見ました傾聴ですよね。これができることが前提です。そして、まずは「御用聞き」などをきっかけとして、経営者や従業員が求めているものを把握し、面談を重ねて信頼関係を構築していきます。
必要なら飲食を交えた対話の場の設定やリラックスした環境づくり、アイスブレイクの雑談も行い、進め方も工夫していきます。そうすることで安心感をもたらしていきます。
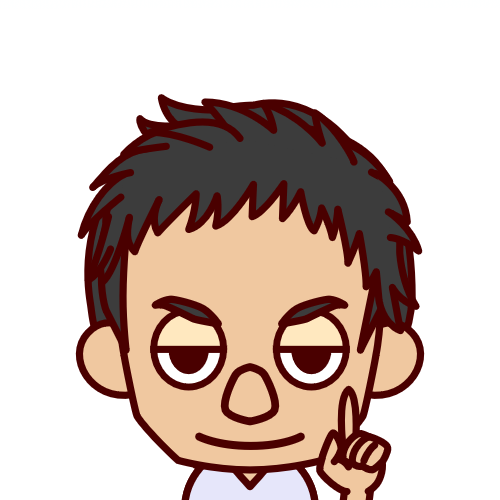
ガイドラインで公式に「飲食を交えた対話の場の設定」と書いてあるで
アイスブレイクも大事
ヒアリングにはアイスブレイクが必要です。これにより相手の安心感・信頼を勝ち取り、本音を引き出すことが可能になります。
アイスブレイクの際はこちらも自己開示をしていくことで、相手の警戒心が薄れて心理的な距離が縮まります。
また、相手に興味をもつことで、相手の安心感や信頼を得やすくなります。こちらも相手へのあくなき興味と関心をもって接していくことが重要です。

コミュニケーションでは「心理的安全性(心の距離感)」と「相手とペースとベクトルを合わせること」が大事になります
苦手なタイプのクライアントとの付き合い方
人間なら誰しも苦手なタイプの人はいます。クライアント(社長や従業員)でもそういう人にぶつかってしまうことがあります。
その場合は、以下のことをやりましょう。
- 相手への敬意などはもつ
- 聴くことに集中する(共感やミラーリングを多用する)
- こまめにほめる
- 必要最小限での関わりに止める
- 相手のことを考えない(特にネガティブな方向で)
- キツい言葉が来たら強気・ポジティブ・楽しい解釈で吹き飛ばす+適当力、背景の事情を考慮するスキルを使う
こうすることで、相手のことを気にしないようになり、相手の発言をうまく受け流せるようになります。
その他、「③サトシのコミュニケーション&メンタル」にある、怒られたときの対策をすれば苦手な人がいても乗り切れます。
相手の社長や従業員にネガティブなマインドが染みついていることも
中小企業や小規模企業の社長や従業員には、「ウチには価値がない」とか「何をやってもできるようにはならない」とか「自分の能力はそれほど高くない」といったネガティブな価値観が潜在意識まで刷り込まれていることがあります。そういう潜在意識からの価値観が余計にうまくいかない流れを作っています。そうすると改善策やアクションプランもうまくいきません。
ネガティブ思考で取り組む人とポジティブ思考で取り組む人がいたら、効率や結果が良いのはポジティブ思考の人ですよね。
そのため、支援者(診断士)は社長や従業員などに対し、ほめることやポジティブな声かけなどを通じ、相手の可能性やパフォーマンスを最大限に引き出せるポジティブな認識に変えていく必要があります。そして、社長や従業員にポジティブな価値観を染み込ませていきましょう。
中小企業や小規模企業の社長や従業員に必要なのは、自分の能力や自社の未来の可能性を信じることです。そのためには、支援者(診断士)が相手の社長や従業員の可能性やパフォーマンス、能力や未来の可能性を心から強く信じていく必要があります。支援者が信じることで、相手の社長や従業員も心から信じることができるようになるわけです。
自分の限界を決め、行動に制限をかけているとしたら、その原因は潜在意識にこびりついているネガティブな思いです。支援者の言葉がけの工夫ひとつで制限を取り払うことができ、相手のメンタルや行動の結果は劇的に変わってきます。
まずは支援者が相手の社長や従業員のパフォーマンスの高さや可能性を信じ、どんな環境下でも未来を切り開いていけると信じるようにしましょう。そして、相手が最大限のパフォーマンスを発揮できるように、ポジティブな声かけをしていきましょう。

支援者がどれだけ相手を信じているかは、言語・非言語を通じて相手の社長や従業員に伝わります
どんなときも相手のネガティブな心理を刺激する発言はNGです。ネガティブ思考を促してもいいことはありません。「④伴走支援って?」の最後で見たように、老婆心ながら価値観を否定する発言、言わなくてもいい余計なダメ出しや批判もダメです。一度否定されたら、相手は二度と心を開いてくれません。つまり本音を言ってくれません。
質問もポジティブな表現を意識しましょう。例えば「なぜできないのですか?」ではなく「どうすればできるようになると思いますか?」と聞いてみることで、相手はできるようになる方法を見つけながら前向きな気持ちになり、考えや回答を促すことができます。
最高の未来を思い描き、それに到達できると信じることができ、「実現できるに違いない」という確信になると、どんどん行動してあるべき姿に近づいていきます。仮に失敗してもポジティブに捉えて課題や学びにして成長することができ、メンタルもポジティブで楽しいものを維持できるようになります。

大切なのは、支援者も社長も従業員も「自社には価値がある、自分はできる」と信じることです!
社長は孤独
中小企業の社長は孤独と言われています。従業員や取引先など、様々な利害関係者との間で板挟みになっていて、その中で決断をしないといけないのです。決断を間違えたらたくさんの従業員を路頭に迷わすことになります。そのため、自分の考えが正しいかわからず不安に感じるときもあるし、冷静に判断できないときもあります。
経営に関するネガティブな話やセンシティブな話は社内の従業員や経営幹部には相談しにくく、1人で悩んでいることが多いのです。だからこそ、「何でも理解してくれて相談できる相手、自分と同じ目線で一緒に考えてくれるパートナー」が欲しいのです。社長の立場・責任からの孤独や不安、プレッシャーについて共感してくれる人が欲しいのです。
孤独と不安、プレッシャーに押しつぶされそうな社長は、自分の能力や意見を客観的に見ることは難しいため、支援者(診断士)が経営者の気持ちにしっかりと寄り添い、客観的な視点で経営者の話をしっかりと聴き、決断への後押しをしていく必要があります。そうすることで、対話と関わりを通じて経営者が「孤独から解放された」と感じられるようにもなります。
そして、相手の社長にとってみれば「話をしっかり聴いてくれる人=自分のことをわかってくれる人=信頼できる人」となるのです。こういう人には本音を安心して話せます。そして本音や今まで当たり前すぎて気づかなかったことなど、気づきを得ることにより、自分から改善策を出すことができ、納得して実行することができます。

本音で話せる診断士がいたらウエルカムだよ!
一枚岩とは限らない
社内の従業員には社長や上司と意見が対立している人もいます。また、「社長や上司から言われて仕方なく」と思っている従業員も多いです。このままだと内発的動機づけが得られず、目標に向かって希望をもって動くことはできません。
そういうとき、支援者はその従業員の気持ちを受け止める必要があります。心に響かない同情の言葉や、社長・上司の意見の押しつけはNGです。一方的に否定するのではなく、相手の立場に立って対話を重ね、経営者と従業員の間に生じている認識のズレなどを確認する必要があります。
支援者はあくまで中立的な立場で社長側と従業員側の気持ちや意見をしっかりと聴きましょう。どちらかの味方だと思われてしまうと、相手側は二度と心を開いてくれず、信頼関係も構築できません。
この後で改善策などを考えていくステップがありますが、その際も支援者はその従業員が安心させて動けるように、選択肢を示しながらその人が最善だと思う方法を一緒に考える必要があります。その際は、社長や上司とも相談をし、社長や上司が妥協できる許容範囲を見極めることも必要です。
従業員なら社長や上司の気持ちや意見、社長や上司なら従業員の気持ちや意見を尊重することを促しましょう。

社長だけで従業員がついていけていない状況は避けましょう
④気づき・腹落ちの促進
正しいヒアリングができると、経営者や従業員は自分で本音などに気づきます。
ヒアリングの際、相手は話しながら考えています。こちら(診断士)を信頼し、本音や当たり前のことを話すことによって、気づきを得ることができます。伴走者は「この人と話すと自分では気づけなかったことに気づかせてくれる」と思ってもらえる必要があります。
傾聴によって聴き出した内容をもとに多角的に問いかけを行うことで、自分自身を客観的に捉えることができ、それまでは感覚的だった相手の想いや考えを余すところなく言語化することができます。また、相手の頭の中を整理して気付きを促していくことができます(無意識から意識に出てくることができるので、これも言語化です)。よくあるのが、今まで潜在意識の中にあった本音が顕在化することや、今まで当たり前すぎて意識することがなかったことが顕在化することです。後者については強みが代表例です。
それにより、経営者や従業員は自ら答えにたどり着いたと実感でき、結論に対して「腹落ち・納得」ができます。そうすることで、当事者意識をもって考えや行動を変えることができ、内発的動機づけを得て、自ら能動的に行動を起こすようになります。それにより、困難や途中での変化があっても最後までやり切ることができるようになり、結果的に事業者としての「潜在力」が最大限引き出される、という流れになります。
相手が話しているうちに不満や不安が緩和され(カタルシス効果)、「この人ならありのままの自分を出して大丈夫だ」と思ってもらえて、都合の悪いことや本音を話してくれます(これを「自己開示」と言います)。そして、本音が出ることで相手の中で気づきを得て相手から提案が出てきます。そうして内発的動機づけを得て希望に変わります。だから納得するし満足しながら実行できるというわけです。
この点、一方向のコミュニケーションで診断士に言われたことを鵜呑みにするだけでは、腹落ち・納得には至らないので、このような流れにはなりません。

不安を勇気に、絶望を希望に変えていきましょう。

効果的な提言や気の利いた一言などなくて構わない。ちゃんと「聴く」だけで相手は満足し、相手の中で変化が生じ、相手が動き、相手の問題が解決します
⑤ヒアリング後
この⑤については実務補習テキストの内容も合体させています。
ヒアリング内容の整理(現状とあるべき姿の明確化)
経営者や経営幹部、後継者、従業員等へのヒアリング、現場視察等により把握した内容を整理していきます。ヒアリング前に調べたものを修正・加筆していく(ヒアリング前が下書きや仮説なのに対し、ここは清書や裏付け)イメージです。
社長の思いやニーズとともに、現場の状況も徹底的に具体化させます。内部環境や外部環境を多角的に点検し、経営者の思いやニーズ、現状とあるべき姿、課題の抽出を行っていきます。

SWOT、問題点、原因、課題、強みを明確化しましょう。また、知識やネタの当てはめよりも、「その会社だからこそのこと」を軸に考えていきます

ヒアリング報告書を作る場合もあります。他にも経営デザインシートなど、わかりやすいツールを使うこともあります
真因分析・ゴールイメージ&ストーリー描写
課題・問題点とその原因・真因をつかみ、ゴールイメージとそこに至るまでのストーリーを描写していきます。
このとき、「全体→細部」の順で整理し(ヒアリングと同じ)、「現状、あるべき姿、課題、原因、真因、ゴールイメージ、ストーリー、具体的な改善策、アクションプラン」の順で決めるとスムーズにいくことが多いです。そして、これらについてはわかりやすくまとめた図を作って報告書に入れておくといいです。
課題や問題点を把握したら終わりではなく、きちんと原因も探る必要があります。真因があれば真因まで深く掘り下げていきます。真因にメスを入れないと問題点は改善しません。

なお、強みも真因まで分析すると有利になります。真因までわかることでゴールへの路線を描け、「差別化・競争優位につながる真の強み」が把握できるからです。
ゴールイメージが描けていると、方向性を間違えなくなるし、効率的に高品質の改善策を提示できるようになります。仕事でもゴールイメージ(期待される成果のイメージ)ができていると確認不足や無駄な調整、やり直しが少なくなるが、これと同じです。なお、中小企業のネタを知っているとゴールイメージやそこに至るまでのストーリーを描きやすくなります(ただし「当てはめ思考」に注意)。
コーチングや伴走支援では、相手が向かいたい方向やあるべき姿、目標を明確にする必要があります。ここで真のあるべき姿(=本当にしたかったこと)や真の問題点、真の原因に気づくことがあります。信頼関係構築と心理的安全性確保、傾聴により、3回目くらいになるとこれらが見えてきます。

因果関係の流れがわかるように、紙に書きながらやるといいですね。社長や従業員と一緒に書いていきましょう。その図はそのまま真因までの因果関係を示す資料にもなります
本質的な課題へのアプローチ
ここでは、真因分析までした真因から本質的な課題を導き出していきます。
現状とあるべき姿の間にあるギャップ(課題)について、その原因を真因まで掘り下げます。表面的な課題の奥底には、その真因となる本質的な課題が存在しています。そして、本質的課題への気付き・腹落ちにより、内発的動機づけが行われ、経営者の能動的行動や組織の潜在力発揮につながっていきます。
伴走支援では、経営者や従業員などとの対話を重ね、信頼関係を構築することで、重要経営環境についての深い理解と洞察を行い経営課題の設定を支援することが重視されています。そのため、ヒアリングを通して真因分析の追加や修正がされることもあります。
経営者が、本当の経営課題は何かということに向き合い、気づき、自分たちが進むべき方向に腹落ちしたとき、潜在的な力が引き出されます。
支援者(診断士)は、表に見えている問題の裏に潜む真の課題に経営者が自ら気づき、その解決に主体的に取り組むように支援していく役割が期待されています。
全体最適調整
SWOTの内容と、戦略層で言う経営理念からビジョン、ミッション、企業戦略、事業戦略までが対象になります。全体のゴールを描き、方向性やストーリーを示します。
いきなり改善策を作りにいくのではなく、まずは方向性などの骨組み(構成)から作る必要があります。論理と同じで「骨組み→肉付け→皮」の順に内容を増やしていくようなイメージです。
また、2次試験の各設問の解答と同じく、整合性や一貫性が必要になります。例えば生産性を上げるために人を減らすと品質が悪くなるので顧客満足度は下がってしまいます。
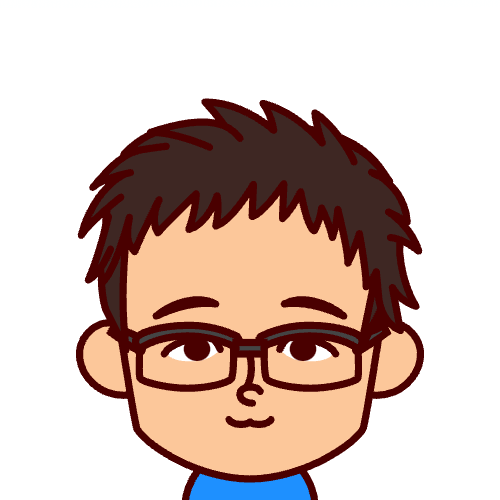
全体最適を図る過程で、ゴールイメージや方向性、ストーリーがクライアントのものと合っているか調整する必要もあります
具体的な改善策を作る
因果関係を追いながら真因レベルまで原因を探り、改善策の方向性を考え、全体戦略やゴールまでのストーリーも立てたら、具体的な改善策をいくつか出していき、提言に向けたシナリオを作成していきます。
改善策については、スモールステップ・短サイクルでPDCAサイクルを回していきます。「P」の戦略・改善策の立案はもちろん、「C」での振り返りや「A」での軌道修正・調整も一緒に行っていきます。また、「D」についてもきちんとサポートをしていきます。そして、スモールステップで経営者や従業員に「小さな成功体験」を積ませ、モチベーションを上げていきます。
課題から改善策、アクションプラン(+報告書)は、「その会社らしさ」が入っているかがポイントです。印象的な内容や具体的な内容を入れ、どこの会社にでもありそうな汎用的な内容はなるべく避けましょう。
また、すぐ取り掛かれる短期計画と、将来的に目指す中長期計画を盛り込むことで、経営者がいつ何をすればいいのかイメージできるようになり、将来に希望をもてるようになります。具体的な改善策は年ベースのもの、月ベースのもの、週・日ベースのものなど、期間のスパンに種類をもたせましょう。
さらに、改善策はハードルが低いものからのスモールステップでいくのがオススメです。ハードルが低いほど相手は納得して行動につながりやすくなります。なお、スモールステップは1つのステップ内の内容を細分化することも含みます。

義務感やノルマのような「やらなければならない」改善策はNGです。「やりたい」改善策を一緒に導き出すことで、相手の納得や満足、内発的動機づけ、自発的行動を促せます

実現可能性、経営資源のことも含めて考えていきましょう。机上の空論では意味がないです。これは大企業出身の人がやりがちですね
複数提示する
相手の社長や従業員は焦りや不安から視野が狭くなっていることが多いです。自分の意見や自分がやろうとしていることが唯一のものだと思ってしまいやすいです。「これしかダメ」が自分を追いつめてしまい、さらなる焦りや不安を招きます。 そのため、専門家である診断士は視野を広くもって別の選択肢も示す(情報提供する)必要があります。相手に「選択肢はいくつもある、自分が見ているのはたくさんある選択肢の中の1つ」と思ってもらうと、相手は安心して考えるようになり、焦りや不安が緩和されます。
選択肢をいくつか用意し、その中から相手に1つの選択肢に絞らせることで、相手は納得ができ、改善策を実行する決意に変わります。
こちらからの意見提示
意見提示を全くしないとカウンセリングになってしまいますので、相手の考えがある程度まとまってきたところで、支援者側から意見を言うこともあります。また、相手が詰まってしまったときはヒントを与えることがあります。
これらは「提案」とも言えますが、ニュアンス的には「指示・押し付け」ではなく「情報提供」です。
そのときは以下のことに注意しましょう。
- 選択権は相手にある、強要やゴリ押しをしない(一方的なものとはしない)
- 「私の意見を言ってもよろしいでしょうか?」など、相手に許可を取ってから話す
- わかりにくいものについては身近な例えを入れる
- 他社事例や一般論を言うときは相手の思考を促すように言う
- 量的には最小限にし、質的にはシンプルかつ具体的、行動可能なものにする。余計なことは言わない、ポイントをわかりやすくする。複雑なものや抽象論はダメ。
- 上から目線にならないようにする(目線を相手に合わせる=相手のレベルに合わせた説明をする)
- 伝わっているか確認する
- タイミングを誤らない
具体的なアクションプランの設定
具体的なアクションプランとは、改善策をもっと具体化したもので、「明日からできること」のイメージです。「明日からできること」がわかるようになると、相手企業の社長は納得して実行してくれます。
「いつ、誰が、どのようなことを、いつまでにやらないといけないのか」について、効果、留意点、要件なども踏まえて考えていきます。
なお、具体的なアクションプランについては相手企業の人と一緒に考えるほうがいいです。これは具体的な事情を知っている相手企業の人のほうが決めやすいからです。
経営改善提言を含む経営診断報告
診断報告書や事業計画書を作成し、実際にクライアントに提案する段階です。
この提言をする段階で、「この人は自分のことを理解しようとしてくれている、心から自分を支援しようと考えてくれている、自分を信じ続けてくれている」とか「会うことがワクワクする」と相手企業の社長に思ってもらえるのが理想です。そうすると一気に本音や深い相談も出てきて、伴走支援が一気に進みます。
なお、実務補習だとここまでになります。

相手が「?」の雰囲気を出していたら、相手にわかりやすいように説明を増やすようにしましょう。曖昧にして過ごすと納得を得られにくいです
内発的動機づけ
経営者や従業員と「一緒に考えていく」ことで、相手の気づきや腹落ちを経て、自身の考えた課題や改善策、アクションプランについて納得し、内発的動機づけを促していきます。
内発的動機づけを高めることでその達成に必要な知識やスキル、考え方、価値観などについて、経営者や従業員の「マインドセット」自体を変えることができます。
また、内発的動機づけが適切に行われれば、深い納得感と当事者意識がもてるようになり、今後経営環境に変化が生じた場合でも経営者自身が自立的かつ柔軟に経営を正しい方向に導くことができ、企業が「潜在力」を最大限に発揮できるようになります。これが「自己変革力・自走力」であり、この能力を養成していくことが伴走支援の目的です。

従業員も内発的動機づけの対象になっていることがポイント!

若い経営者や従業員ほど、ほめたりポジティブなことを言ったりしてモチベーションを上げることの効果が大きくなります
どのような場合であっても社長や従業員の揺れ動く心を支え、内発的動機づけを得て、目標に向かって希望をもって動けるように支えるのが支援者の役目です。だからこそ、信頼関係を構築できたのなら、相手のパフォーマンスの高さや可能性を最大限に認め、信じましょう。
どこかの塾のCMソングじゃないですが、支援者が社長や従業員の「やる気スイッチ」を押してあげましょう(その表現だと上から目線なので、押させていただきましょう)。支援者が「やる気スイッチ、君のはどこにあるのだろう?」と探してみてください。そのためには、相手の強みを見つけてほめる、達成した後の姿を想像させるなど、ポジティブ思考を促す声かけをすることがコツです。脅しや説教では人は動きません
成功体験がポジティブ思考を促す
先ほども見ましたが、自分の能力や未来の可能性については、捉え方や信じ方で変わってきます。限界は自分自身が作っているため、支援者はほめることやポジティブな質問を通じてこの限界を取り外すように支援していく必要があります。
ネガティブな思考の癖(ネガティブビリーフ)を取り外し、「自分は必ずできる」と信じてもらえるように支援していきましょう。「どんどんできるようになる、あるべき姿を達成できる」と信じられるようになれば、相手はパフォーマンスを最大限引き出すことができます。そして小さな成功体験を積み重ねることで、徐々にネガティブビリーフからポジティブビリーフに変わっていき、問題や課題を自ら解決できる力が身につき、自走化ができるようになります。
支援者は対話や関わりを通じてそれを支援していきます。例えば相手に不安な点、理解不足の点があったら、支援者はその都度フォローしていきます。
相手が動くためのハードル
外から言うだけなら簡単にできます。問題は「相手が動くか」です。いくら理論的に正しくても、相手企業の社長のニーズ(需要)やその背景にある思いや事情を考えずに「これをやれ」と言っても、需要と供給のベクトルが合っていないため、社長の安心感・信頼や満足、納得を得ることはできず、実行してくれません。相手のニーズを踏まえていないものや、実現可能性がないもの、相手が行動に移せないものをドヤ顔で提供したところで意味はありません。
1回目の双方向のコミュニケーションでも見てきたように、相手のニーズ(需要)に合わせた提案を供給することができてはじめて相手企業の社長の安心感・信頼や満足度向上、納得につながり、提案を実行してくれます。そしてリピート利用(長期継続利用)や口コミによる新規顧客獲得につながりやすくなります。
具体的には、以下の要件を満たせば満たすほど、「双方向のコミュニケーション」として相手企業の社長の満足度が高くなり、信頼され、改善策を実行するようになります。
- 自分のことをしっかりと理解してくれている
- 必要なときに(最適なタイミングで)知識やノウハウの提供・提案をしてくれる
- 自分と一緒に考えてくれる
- 相手の本音を引き出してくれて、相手の本音を尊重してくれる(だから内発的動機づけが高まり自主性が増す)
- 謙虚な雰囲気がある(上から目線ではない)
- 自分がしっかりとこなしていける解決策をスモールステップかつ複数提示してくれる
- 一般論ではなく自分に合ったことを言ってくれる(改善策のイメージがしやすい)
- わかりやすい説明で一歩先のイメージができワクワクできる(安心できる)
- 伴走しているような支援をしてくれると思ってもらう
- 「何でも理解してくれて相談できる」と思ってもらう
- 「何とかしてくれそう」という期待感がもてる
- 最後まで面倒を見てくれる(アフターサービス)

こういうのって最近のプロ野球でもあるよな。選手のことをしっかりと考えてくれて、選手と同じ目線に立ってくれる監督がいるチームは選手のモチベーションが上がりやすく、Aクラスになりやすい。そらそうよ
⑥課題解決(行動変容・スモールステップでの成功体験の蓄積)
ここまで定めてきた課題、改善策、アクションプランをスモールステップで1つずつクリアしていきます。
課題の解決は現状からあるべき姿(目標)までは一気にいけるわけではなく、スモールステップでいく必要があります。つまりステップごとに小さな目標を定め、それを達成することで成功体験を与え、自信と成長を促すやり方でいきます。
スモールステップで成功体験を積ませることで、相手の社長や従業員は能動的に本質的な課題の解決まで臨むことに対するモチベーションを持つことができます。そして新たな取り組みに着手する心理的ハードルを下げることができます。そうして成功し続けることが相手企業の社長や従業員の「習慣」になっていきます。
社長から末端の従業員まで含めて内発的動機づけを高め、自発的に行動し、成功体験を得ることで、さらなる内発的動機づけを得て、さらに自発的・能動的に取り組めるようになります。そうなると新たな取り組みへの心理的ハードルが下がり、環境変化にも迅速・柔軟に対応できるようになります。これが「潜在力」であり、それを引き出すことが支援者の役割です。支援者は、相手が行動を起こそうとするなら応援して行動を促すし、相手が行動できなかったら責めるのではなく手を差し伸べてていくことで、相手は支援者にサポートされている安心感をもって、行動に移すことができます。

結果だけでなくプロセスや成長を承認することも「支援」です
改善策・アクションプランを楽しんで取り組めることが理想
相手の社長や従業員が楽しみながら改善策やアクションプランに取り組めるようにすることが理想です。そのためには、改善策やアクションプランを取り組んだ先にある「ときめく未来」を想像してワクワク感をもってもらうことが必要です。また、成功体験をこまめに積み、内発的動機づけをどんどん高めることも必要です。
「悪い結果を避けるために行動する」より「良い結果を得るために行動する」のほうが、喜びやワクワク感が大きいため、前向きな気持ちで改善策やアクションプランに取り組めるようになります。もちろんこちらのほうが実際に良い結果をもたらしやすいです。
フォローアップ(事後フォロー)
変化や想定外の事態があった際の軌道修正や調整、ほめることでのモチベーションアップを行っていきます。
小さな行動と小さな結果、小さな成功体験と自信を積み重ねていきます。そして、こちらは対話やフォローを通じてフィードバックを適宜していきます。ここで相手をほめてモチベーションを上げること(成長や成功体験を実感すること)や、変化や想定外の事態があったときの軌道修正や調整も適宜していきます。
イメージは短サイクルでの生産計画立案と生産統制です。短サイクルで行えば変化や想定外の事態があったときも修正や調整がしやすいですよね。
うまくいかなかったときは?
うまくいかなかったときのフォローも必要になります。相手は後悔や自己嫌悪を抱えていてメンタルが悪化しています。このときに必要なことはアドバイスや説教ではなく、相手の気持ちをしっかりと受け止めることです。
相手のメンタルを回復させることはもちろん、「どうすればこの失敗を活かすことができるのか、どう行動につなげられるか」を社長や従業員と一緒に考え、相手が気づきを得て前向きにリスタートを切るための支援をしていきましょう。

失敗しても大丈夫!
うまくできなくても大丈夫!
なお、このままだと相手が失敗しそう、諦めそうになったら、そのまま続けさせるのではなく、計画を練り直しましょう。だからこその「短サイクルでの計画立案・統制」なのです。
時には我慢も必要
相手企業の社長や従業員はもちろんですが、部下や後輩に対しても、余計なお節介でのダメ出し、老婆心がてらの価値観の否定、ついカッとなっての説教、言わなくてもいい余計な一言を言ってしまうことなどはありませんか?
こういうものはチームプレーや伴走支援の妨げになります。
私が仕事でお世話になっている著名な診断士が、仕事のキックオフ会議のときにこう言っていました。
「診断士どうしでは上司と部下の関係性はありません。チームで作業をするなら先輩も後輩も関係ありません。チーム作業でも伴走支援でも、相手と同じ目線で接するのがプロの診断士です。後輩が先輩を頼るのは歓迎ですが、先輩が上から目線で後輩へダメ出しや否定をするのは控えましょう」
「確かに講師やコーチとして後輩の診断士に教える場面もあります。フィードバックをするときもあります。しかしその際も相手への敬意を持っていることが大前提です。言い方にも細心の注意を払っています。一時的な感情に流されて敬意を持たずにダメ出しや否定をしたら、相手は敵認定をして聞く耳持たずになってしまいます」
ダメ出しや否定などは、言った本人はスッキリするでしょうが、相手は余程の温厚な人でない限りは不快に思います。それだけでなく、せっかくそれまで築いてきた信用もなくなり、「もうこの人はない」と判断されます。
チームの他のメンバーからも変に思われるようになり、連絡も次の仕事が来ることもなくなります。謙虚さがなくなっている証拠にもなるため、周囲の人もどんどん離れていきます。
伴走支援なら相手は不快感から聞く耳持たずになり、その時点で伴走支援は失敗です。
信用というのは、構築するには長期間かかっても、失うのは一瞬です。一時的な感情の発作で自分の将来を潰してしまうのはもったいないです。ダメ出しや説教、価値観の押しつけでは人は動きません。否定や脅しは心を閉ざす結果につながるだけです。言いたくても我慢しましょう。我慢することも支援者である診断士には必要です。
どうせ声をかけるなら、ほめたりポジティブなことを言ったりしてモチベーションを上げることをしましょう。こういうものも気遣い力の1つです。人の役に立つこと、人に喜ばれ感謝されることを積極的にしていきましょう。よく「相手の期待を超える成果を出せ」と言われますが、経験やスキルが不足している支援者がいきなりこれをやることは厳しいです。しかし、経験やスキルが不足している人でも、気遣いをこまめに見せることで、期待を小さく超えることをこまめにできます。期待を大きく超えることはできなくても、小さく超えることを何回かやれば、大きく超えることと同等の効果を得られます。

ほめてモチベーションを上げることって本当に大事!
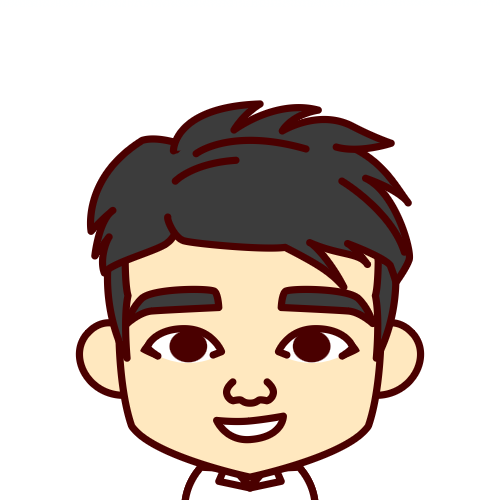
小さく超えることをこまめにするなら、1年目の診断士でもできるね
⑦ゴール・卒業
さて、ここまで見てきました伴走支援ですが、伴走支援の「ゴール」はどこにあるのでしょうか?まさかずっとお世話になるわけにはいきませんからね。どこかのタイミングでは「卒業」を迎える必要があります。
その「ゴール・卒業」のタイミングの目安は、「成果をあげ続ける思考や習慣などが身についた時点」と言われています。難しい言い方をすると「潜在力が最大限発揮できるようになった時点」となります。これで企業の体質改善が達成されます。
相手が成果をあげ続ける思考や行動を整えること、目標達成を積み重ねる習慣が身につくこと、常にパフォーマンスの向上を目出すマインドが根付くことができたら、経営課題の解決に向けて自走化ができたと判断でき、「自己変革力」を身につけた状態となります。そしてゴール・卒業を迎えることができます。
目標達成に必要な思考と行動が習慣づき、クライアントが自分でコーチング(セルフコーチング)ができるようになった時点がゴールと言えます。そんな状態になれば、「もう我々(経営者・従業員)の力だけでいけますよ」と経営者も言えるようになりますよね。強いて言うならそれを経営者だけでなく経営幹部や従業員も含めて言えるようになると、自走化・自己変革力が身についたと判断できます。
クライアントの自律性が出て、自ら解決する力が身につくと、環境変化にも迅速・柔軟に対応できるようになります。また、組織文化にも良い影響をもたらし、組織活性化を起こし、従業員を含め全員が自ら考え自ら発言し、率先して行動するようになります。結果として、パフォーマンスが上がり、目標達成や業績向上につながります。
ちなみに、「卒業したらもう知りません」ではありません。環境変化時の柔軟な対応や自立的な自己変革の継続のために、診断士の支援終了後でも定性面・定量面からのアフターフォローをしていく必要があります。そのため、経営者等との十分な信頼関係を支援終了後も維持し、良好な関係性を継続していく必要があります。
まずは支援の手順を守る
支援の手順をまとめて自分なりのオリジナルのやり方を見出したいと思ったことがあるかもしれません。その場合でも、ひとまずはオリジナルのものにアレンジするのではなく、伴走支援のやり方に従ったほうがいいかと思います。
まずは「守破離」の「守」で、そのやり方に素直に従いましょう。カウンセリングやコーチングのやり方を入れる、やり方をアレンジするなどは、伴走支援のやり方に慣れてからにしたほうがいいでしょう。
「プロは相手の期待を超える成果を出すこと」とよく言われますが、これは3年目くらいまでは気にしなくてOKです。まずは「守破離」の「守」を意識して相手の期待通りの成果を出せるようにしましょう。伴走支援のやり方が身につき、経験が一定以上になると「破・離」ができるようになり、期待を超える成果を出せるようになります。そうなるように自分への投資をして成長し続けていきましょう!
オマケ:これまで受験仲間だった受験生との付き合い方
予備校やSNSで受験仲間がいた合格者も多いかもしれません。しかし、現実的には受験仲間全員が同じタイミングで合格することはなく、必ず誰かは「受験生」として残っていると思います。
そうすると、まだ合格していない受験仲間に対し合格者としてアドバイスや情報提供、伴走支援をしたいと考えていらっしゃるかもしれません。
しかし、これはリスクが大きいです。
よかれと思って言ったことが、受験生にとって大きなプレッシャーやモヤモヤになっていることもよくあります。間違えると受験生の劣等感を刺激することになります。これまでの仲を崩壊させてしまうことにもなります。
また、相手が予備校生の場合、こちらが受験のアドバイスや情報提供をすると「余計なことを言うな」と予備校の講師からクレームが来ることもあります。クレームはないにしても、予備校の講師は受験生に「そんなアドバイスや情報は無視して私の指導に集中しなさい」と指示します。
さらに、試験直前や不合格の結果がわかった直後は非常にナーバスになりますから、こちらからのアクションで相手の怒りを買うこともあります。
もちろん、一発合格道場やタキプロで「不特定多数の受験生」に対して記事を書いたり勉強会をしたりするのはいいのですが、「かつての受験仲間の受験生」に対して個別に連絡を取ることは、細心の注意が必要です。
正直、プロの受験アドバイザーや予備校の講師以外は軽はずみでやらないほうがいいと思います。かつての受験仲間の受験生に対して「こんな記事を作ったよ」とか「今度こんな勉強会がありますよ」と情報提供するのは避けましょう。
伴走支援は相手が主体的に意思決定できるように支援していくものです。受験生においても同様で、こちらからアクションをかけると受験生が主体的に意思決定をする妨げになります。自然と受け身になってしまうため、自分自身で解決策を見出すことができず、内発的動機づけが高まりません。だから「やらされている感」が出てモヤモヤしてしまうのです。それがあなたへの不信感や劣等感になり、これまでの仲を崩壊させることにもつながります。
私も大学受験や大手予備校での受験アドバイザー、9年間の診断士受験生活の中でいろいろな受験生を見ていきましたが、やはり合格前の「受験生どうしの関係性のとき」と、合格後の「合格者と受験生の関係性のとき」では明らかに相手の受験生が抱く印象は違います。後者になると、受験生は連絡をするほど劣等感を抱きます。合格直後はこれまで通り連絡してくれたけど、徐々に反応が鈍くなってきて、やがて連絡をくれなくなります。
かつての受験仲間の受験生は放っておくのが一番です。こちらからの連絡はやめましょう。あなたも診断士に合格したら、道場やタキプロの仕事以外は前を向いて診断士の活動に専念しましょう。向こうが合格するまではかつての受験仲間は定期的連絡のリストから外し、その代わりに診断士仲間に対して定期的連絡をしていけばいいのです。
もちろん、価値観や性格が合ってとても仲の良い受験仲間もいると思います。そういう人に対してなら定期的連絡をしてもいいですが、その際は勉強の話はタブーです。基本的には優劣の意識、相対的な比較にならない話題をしましょう。
勉強のことでアドバイスや情報提供、伴走支援が必要なら、向こうから話してきます。
道場やタキプロの活動をしている場合でもこちらからアクションをかけることはありません。必要ならコメントや質問などで向こうから言ってきます。
会社の伴走支援も同じです。支援者(診断士)の側から「伴走支援しますよ」なんて営業をかけることはせず、向こうから「伴走支援をしてください」と言うのを待ちます。
精神科の医者やカウンセラーも同様です。医者やカウンセラーから話しかけることはありません。あくまで患者から話してくることを待っています。

相手を待ちましょう。それが相手を信用していることにもなります。こちらから話しかけるのは我慢です
おわりに
さて、今回は伴走支援について説明させていただきました。伴走支援は最近出てきたもので、税理士はまだ手をつけていない分野なので、差別化を図ることも可能だと思います。そのため、伴走支援は診断士のキャリアの路線にもつながると思います。
「サトシの書籍シリーズ」は今回で終わりです・・・・・としようと思ったのですが、2次筆記試験の合格発表後から毎日のように受験生(新人診断士)からの相談があったため、診断士のキャリア分析やブランド戦略についての記事も作ることにいたしました。もちろん伴走支援も診断士のキャリアやブランド戦略に活かせます。
今日の夕方公開になります。こちらが本当の最終回になります。よろしくお願いします。
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)


