スモビから学ぶ事例Ⅱ by AZUKI

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
一発合格道場ブログを
あなたのPC・スマホの
「お気に入り」「ブックマーク」に
ご登録ください!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
こんにちは、AZUKIです。
本編に入る前に、秋リアルセミナーのお知らせです!
一発合格道場からのお知らせ!

2次試験直前のセミナーになります。
お悩みや不安が尽きないそんな皆様へ向けて、座談会も含めたコンテンツも目白押しの内容でお届けする予定です!
■10/5(土)大阪 14:00-17:00 20名様の募集
■10/6(日)東京 14:00-17:00 30名様の募集
詳細内容と募集Formは、9/17(火)20:00に投稿予定のご案内をご確認下さい!
リアルセミナーはすぐに枠が埋まってしまうため、要チェック![]() です!
です!
はじめに
改めまして、AZUKIです。
1次試験の合格発表から早1か月ですね。
そろそろ、何となく好きな科目や、何となく苦手な科目が出てくる頃合いではないでしょうか。
ちなみに僕は、事例Ⅱが大の苦手でした。
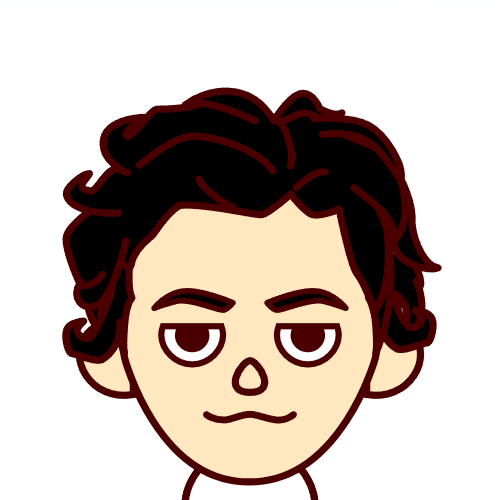
ブランド?興味ないね、服もほぼユニクロだし・・・。
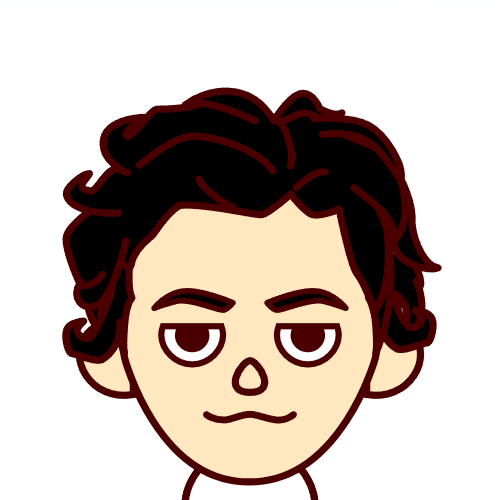
コミュニケーションの強化で顧客満足度向上?向こうから寄ってきたら鬱陶しくて逆に満足度下がらない?
↑斜に構えててめんどくせ~~~~~!!!!!
こんな感じで理解が浅いまま試験に臨んだ結果、1年目は52点というなんとも言えない点数でした。合計点が238点だったので事例Ⅱをもう少し詰めれていれば合格だったのに・・・という感じでした。(結果論ですけどね。)
そして迎えた2年目、なかなかやる気が出ず勉強をサボり続けていましたが、8月末にようやく重い腰を上げ勉強を再開しました。しかし、1年目と同じ勉強法では同じ結果になるのは目に見えています。
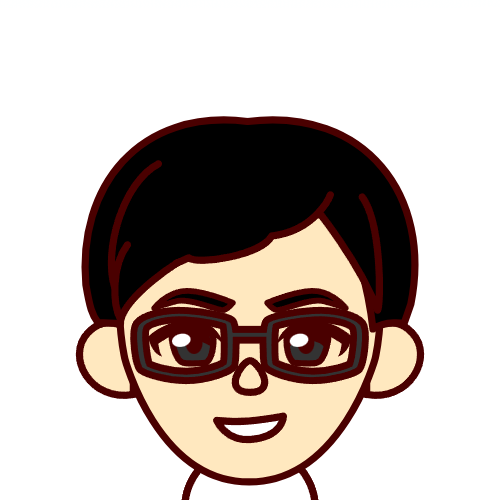
さて、どーやって勉強すべきか・・・。時間もあるし、積んでいた”スモビ”でも読んでみるか・・・。
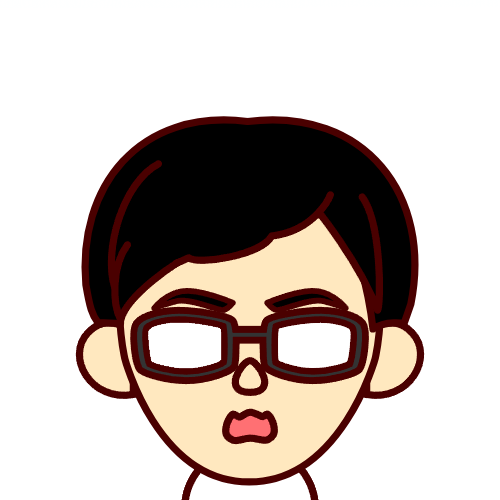
・・・事例Ⅱって「そういうこと」やったんや!
僕は”スモビ”を読んで、開眼とまではいかないものの、納得感を持って勉強を進められるようになりました。
今日はそんな”スモビ”の内容について、かいつまんで紹介したいと思います。
スモビとは?
スモビとは、2次試験の試験委員である岩﨑邦彦先生が書かれた「スモールビジネス・マーケティング」という本のことです。スモビは通称で、2次試験の副読本の中では、「ザ・ゴール」と並んでかなりメジャーな本です。
発行は2004年と、もう20年も前の本になります。しかしながら、今読んでも古臭さを感じさせるどころか、20年前にここまで現代のマーケティングに通じる内容の本が出ていたのかと、衝撃を受けました。
岩﨑先生は商学が専門で、特にマーケティング論についての研究が多いそうです。(ソースはWikipedia)
2次試験の試験委員名簿に長年名を連ねており、今年も名前が入っています。
岩﨑先生の著作には他に「小が大を超えるマーケティングの法則」「引き算する勇気 -会社を強くする逆転の発想」などがありますが、まずはこのスモビを読んでみて、気になれば他の本も読んでみるのがよいと思います。
今日はこのスモビから、個人的に大切だと思った部分を3点抜き出してお伝えします。もし、もっと深く内容を知りたければ、ぜひ購入して読んでみてください。
①”真空地帯”が発生するメカニズム

まず1つ目は、「真空地帯が発生するメカニズム」です。
前回の僕の記事でも述べましたが、中小企業は経営資源の豊富な大企業との価格競争を避けるべく、ニッチ(すきま)市場を狙う差別化集中戦略をとるのが基本です。
では、そのニッチ市場はどのようなメカニズムで生まれるのでしょうか?
下図はある大型店XとYが、自社をどのようにポジショニングするかを表した図です。

第1期は、X店とY店の初期位置を示しています。
第2期では、Y店より左側のニーズを全て獲得しようと、X店はY店のすぐ左の消費者ニーズに対応するようにポジションを変更します。
第3期では、X店に対抗しようとY店がX店の更に左側にポジションを変更します。
最終的に、X店とY店は「消費者の平均的ニーズ」に合わせたポジションから動けない、経済学でいうナッシュ均衡の状態となります。
このとき、マーケットの左右には”真空地帯”が生まれます。これがニッチ市場が現れるメカニズムです。
この”真空地帯”を狙おうとすると、店の”個性”が強くなります。
そして店の個性化が高まれば高まるほど、消費者の満足度は高くなるという結果が出ています。

スモールビジネス・マーケティング P.11より引用
ただ、個性が強くなればなるほど、それを受け入れられない消費者もいます。
大企業であれば採算が取れなくなるため過度な個性化はできませんが、“真空地帯”をターゲットとする中小企業には関係ありません。
商品や売場作りに徹底的にこだわり個性的になることで、消費者の共感を生み、顧客満足度を高めることができるのです。
+おまけ:ヴィレッジヴァンガードが大量閉店した理由
先日、”大量閉店「ヴィレヴァン」経営が犯した最大の失敗(東洋経済ONLINE)“という記事を読んだのですが、内容が今回の話とドンピシャだったので、紹介します。
皆さん、ヴィレッジヴァンガード(以下、ヴィレヴァン)はご存じでしょうか。
ヴィレヴァンは、「遊べる本屋」をキーワードに、書籍、雑貨類、CD・DVD類を所狭しと陳列して販売しています。
「サブカル感」が最大の特徴であり、「5%の方に思い切り満足してもらえるような店を目指そう。それによって95%の方に満足されなくても構わない。」という方針で運営しているようです。
※サブカルとは:本来は、「社会の正統的、伝統的な文化に対し、その社会に属するある特定の集団だけがもつ独特の文化」という意味なのですが、ここでは「独自色」くらいで捉えてもらえば大丈夫です。

しかし、このヴィレヴァンが5年間で大量に閉店(400店→300店)しています。コロナ禍の影響もあるとは思いますが、大量閉店の理由として記事内では次の2点が挙げられています。
- ショッピングモールなどへの出店を進めたことによって、「ヴィレヴァンらしさ」が普通のものになってしまった
- 人材教育が十分にされなかったことで、ヴィレヴァンを支える店員にサブカルの知識が薄く、普通の売り場しか作れなくなってしまった
ヴィレヴァンは「サブカル感」という“ありふれた店とは一線を画した独特な雰囲気”を強みとしています。
しかし、ショッピングモールを中心として出店を進める拡大路線を取った結果、ヴィレヴァンはどこにでもある“ありふれた店”になってしまいました。
また、出店の拡大に伴い、ヴィレヴァン創業者の「センス」を現場に共有するのが難しくなったり、本部の一括仕入れにより現場の裁量が少なくなったりで“個性”の希薄化が進んだようです。
先ほど、店の個性化が高まれば高まるほど、消費者の満足度は高くなることを述べました。
ヴィレヴァンは「5%の顧客」をターゲットにしていたにも関わらず、他の95%の顧客に寄せた品揃えや売場となってしまっていたら、当然5%の顧客からの満足度は下がってしまいます。そして、95%の顧客はヴィレヴァンに対するロイヤリティ(忠誠心)が元々ありません。
結果、ヴィレヴァンはターゲットに対して自社の強みを活かしきれず、せっかく拡大した店舗を縮小することになってしまいました。
ヴィレヴァンは中小企業というには大きすぎる企業ですが、ニッチ市場のマーケティングを考えるうえで良い教材になるかと思います。
②人的コミュニケーション

2つ目は、「人的コミュニケーション」です。
本書では、小規模小売業は「小さな店に惹かれる人々」をターゲットにしよう!という提案をしています。(![]() ←コイツみたいな斜に構えた面倒な奴はそもそもターゲットにしないということですね。)
←コイツみたいな斜に構えた面倒な奴はそもそもターゲットにしないということですね。)
岩﨑先生は、「小さな店に惹かれる人々」に対する適切なマーケティングを行うべく、「小さな店に惹かれる人々」の特性を調査し、最終的に下記の図のような確証的因子分析モデル(何それ?)を作成しました。
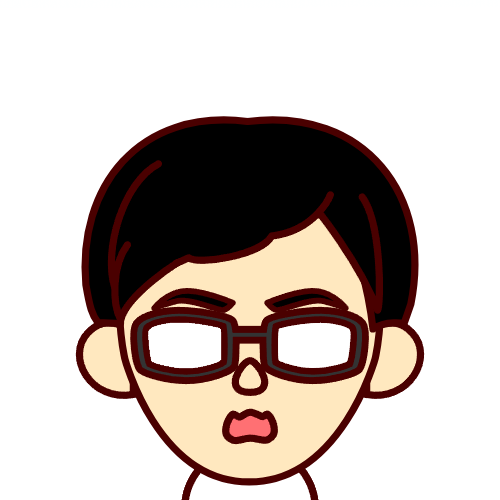
カイ2乗検定、1次試験では捨て問にしてたけどこういうところで役に立つんだなぁ・・・

そして、「小さな店に惹かれる人々」は次の3つの特性を有していると結論付けました。
「小さな店に惹かれる人々」の特性
- 「こだわり、個性、専門性」を重視する「本格志向」
- 「店員のアドバイス、店員とのコミュニケーション」を重視する「人的コミュニケーション志向」
- 「気に入った店は長く利用したい」「ここと決めた店がある」割合が顕著に高い「関係性志向」
人的コミュニケーションは、さらに「フレンドリー・サービス」と「人を通じた情報の伝達」の2つに分けることができます。
フレンドリー・サービスは、挨拶や言葉遣いなど、人的コミュニケーションのうち、接遇・接客に関する部分です。
しかしながら、岩﨑先生は、「フレンドリー・サービス」はあくまで競争の前提であって、競争優位の武器にはならないとしています。
実際僕たちも、
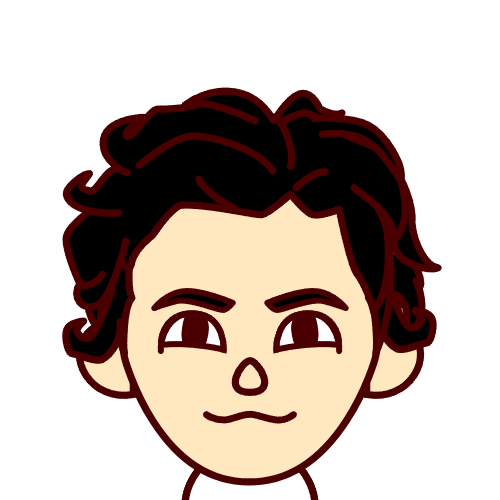
あそこの接客めっちゃええねん!!!!もう接客があまりに気持ち良すぎて、それ目当てで行ってるわ!!!!
みたいなことってないですよね。
競争優位の武器となるのは、「人を通じた情報の伝達」の方になります。顧客1人1人の状況に応じた提案や、専門知識を活用したコンサルティングなど、人を通じて情報を伝達することが競争優位の源泉となります。販売員は、取扱商品のことを熟知しており、顧客の一歩先を行かなければならないのです。
とはいえ、販売員の接客マナー自体が良くないと、いくら価値のある情報伝達ができても顧客満足度は低くなってしまうので、人的コミュニケーションは下図のようなピラミッド型で表されます。

また、岩﨑先生はコミュニケーションのポイントのひとつとして、売り手と買い手との情報のギャップの解消を述べています。そして解消の方法として効果的なのは、情報の発信と受信、すなわち双方向コミュニケーションが重要とのことです。
発信とは、お店の専門性・個性・こだわりに関する情報提供のみならず、「提案」による需要の創出も含まれています。大規模なお店はマス向けに「いまある需要を満たす」ことに長けていますが、小規模なお店はニッチ向けに「需要を創出すること」に長けているのです。
受信とは、顧客情報の収集やクレーム処理といった、顧客の声を聞く活動のことです。「不満を持った顧客の大半はクレームを入れずに黙って去っていく」という話は有名ですが、本の中でも統計データ付きでその話が出されています。顧客の声を聞く仕組みを作り、顧客の流出を防ぐことが非常に重要だと言えます。
事例Ⅱでは「コミュニケーション」というキーワードを使った解答を書く機会が多いですが、中小企業に大切なコミュニケーションとは何か、イメージができたのではないでしょうか。ただ愛想がいいだけの接客や、顧客のニーズを引き出さない単なる押し売りは、決してコミュニケーションとは言えないのです。
③関係性の構築

最後となる3つ目は、「関係性の構築」です。
モノよりコトへの消費者マインドの移行や人口減少など、顧客の絶対数が減少する世の中においては、先ほど述べたように顧客の流出を防ぐことが重要です。
岩﨑先生は、顧客の流出を防ぐための”顧客維持活動”として、下記4つの活動がロイヤリティ向上に繋がるかを研究しました。
- ロイヤリティカード・プログラム(ポイントカードなど)
- 販売員とのコミュニケーション
- 顧客との継続的接触
- 売場(売場づくり・品揃え)の変化
この研究では、「将来的な利用意向」、具体的には「3年後もその店を利用し続けている確率」によってロイヤリティを測定しています。
結論だけ言えば、どの活動も顧客維持活動として有用性があるとの結果が出ました。
しかし、この中で特に注目すべきは「販売員とのコミュニケーション」と「顧客との継続的接触」の結果です。下図に示す通り、この活動によって構築できるロイヤリティが大型店を大きく上回っていることがわかります。

事例Ⅱではよく「顧客の要望に応じた提案力」や「SNS・掲示板による双方向コミュニケーション」、「メルマガ・DMによる新製品の案内」といった解答要素が挙げられますが、これらはこの「販売員とのコミュニケーション」や「継続的接触」の強化により、顧客のロイヤリティを高めるというところに帰結するのだと思われます。
おわりに
ここまでお読みいただきありがとうございました。
スモビは事例Ⅱの考え方が詰まっている、「事例Ⅱの教科書」と言える本だと思います。発行が2004年なので、オンラインに関する内容は含まれていないですが、考え方の土台は同じです。
4代目のkatsuさんもスモビに関する記事を書いていますので、ぜひ読んでみてください。10年以上前の記事とは思えないほど、今の事例Ⅱと通ずる部分が盛りだくさんです。
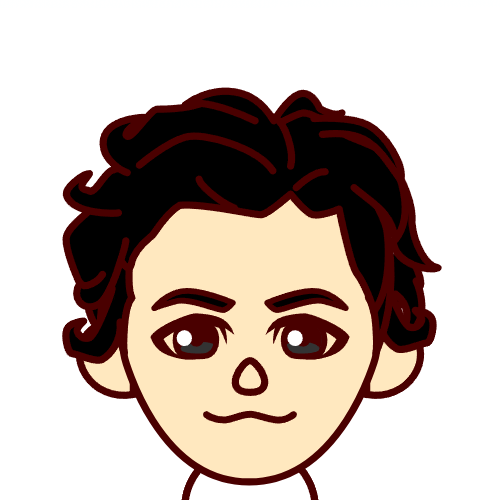
明日はレジェンド投稿の日です!診断士の働き方は本当に十人十色で、僕たちも毎回楽しみにしています!
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)


-300x169.jpg)
AZUKIさんこんにちは。
私も事例Ⅱが苦手で毎年足を引っ張っています。
スモビは以前に読みましたが、長らく本棚で眠った状態でしたので、ブログ記事にて思い返すことができました。
①個性(強み)を武器に、ニッチ市場で顧客獲得
②人的コミュニケーションによる顧客の声を聞く
③顧客との継続的接触による関係性構築
過去の事例Ⅱもだいたい、上記に沿った内容ですね。
こう書くと簡単な気がするのですが、実際の本試験では焦りからか、解答すべき要素が抜け落ちて、得点が伸びないです。
今年度はスモビ記載の①~③を忘れずに、本番に挑みたいと思います。
ヴィレバンは昔はよく行ってましたが、ショッピングモールでみるようになってからは全くいかなくなりました。強みが失われてますね。
次回、ブログも楽しみにしております。
tomiさん
コメントありがとうございます、とても励みになります。
事例Ⅱ、難しいですよね。私も1回目52点→2回目58点と、60点を超えることができませんでした。
仰るように、本質はかなりシンプルなのですが、ひねった問われ方をされると焦っちゃうんですよね。
本質の部分は理解されていると思うので、後は与件文からいかに解答要素を拾ってくるか、B社に寄り添った具体的な施策が書けるかが鍵になると思います。
頑張ってください、応援しています!