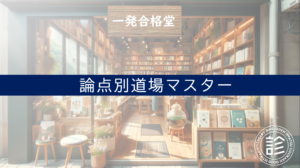【息抜き】ヒグマ入門 byぴらりん

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
今回は企業経営理論解説シリーズの途中でかつ、中小企業診断士試験とは1ミクロンも被らないですが、私の偏愛を紹介させてください!
実は私、ヒグマが大好き、です
かわいいとは思わないですし会いたいとも思わないですが、生物として人間を凌駕している存在感に対して畏怖を抱きつつ好奇心をくすぐられます
注:ぴらりんは研究者ではないですが、ヒグマに関する情報発信には細心の注意を払ってます。間違いなどがありましたらコメント欄などで教えてください
今日くらい息抜きに付き合ってあげてもいいかなという方はこのまま進んでいただき、勉強ペースを切らしたくないという方は下記リンクがおすすめです
ガチわだ・渾身記事
それでは、ヒグマについて解像度を高めていきましょう♪
ヒグマの概要
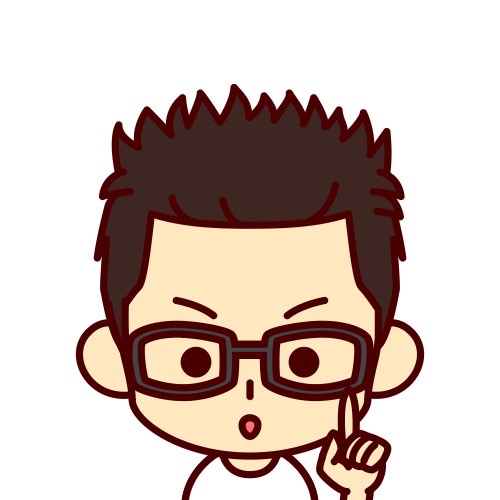
とりあえずヒグマはすごすぎる!
基本情報
ヒグマは日本では北海道にしか生息していないクマで、北海道発表の推計生息数は約1.2万頭(出典)ほど。30年ほどで約2倍程度になるなど増加傾向となっているようです
北海道の大きさは九州が2つ分入る大きさ!その中で1.2万頭というのは少ない気もしますが、北海道の山に入るとすぐにクマに出会いそうにも感じますね。笑
体長と体重はざっくり人間の2倍~4倍ほどあります
メスの成獣は体長約1.5m、体重100~200kg
オスの成獣は体長約2.0m、体重150~400kg
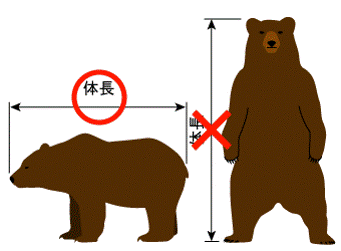
身体能力
ヒグマの研究はまだまだ進んでいないことも多いそうで、今後の研究によっては分かってくることが変わるかもしれません
| 他の動物との比較 | 備考 | 情報源 | |
| 視力 | 正確な視力数値は分かっていないようですが、人間の視力0.4~0.7程度と言われています | ・100m先の静止した人は見分けられない可能性が高い ・夜間にも普通に行動していることから、夜目は効きます ちなみに、真っ暗闇の中10mくらい離れて物を投げてもキャッチするそうです | 丸瀬布の自然を楽しむためのヒグマ対策|ヒグマの会 |
| 聴力 | 聴力は優れているが、雨音や風向きによっては聞き分けられない時もある | 高音に特に敏感なので、鈴の音や機械音を鳴らすと向こうに気付いてもらえる ヒグマは基本的に臆病な性格なため好奇心旺盛な若い個体以外は人の存在を感じると離れていく | クマの出没にご注意ください|帯広市 |
| 嗅覚 | ・非常に優れていて犬の100倍以上の嗅覚(嗅覚受容体)を持つという話もあります ・犬種によっては7倍~10倍くらいという説もある | 嗅覚受容体の密度と多様性が匂いをかぎ分けられる能力 嗅覚がいい=遠い距離の匂いを感知できる、というわけではなく、〇万分の1まで小さくなった匂い分子をかぎ分けれられるようです 風がない日は数日前の匂いも感知できるそうです | OSO(オソ)18~ある“怪物ヒグマ”の記録~|NHK |
| スピード | 時速40~50キロで走る 200kg前後の体重でこの速度です | 100m先にクマを見つけると8~9秒ほどで追いつかれます 山道でも軽自動車が走行してくる感じです | クマに注意!|環境省 |
| 消化能力 | 消化できずに、食べた形のまま出てくることも多い | 痕跡の見分け方|札幌市 |
こんな山の中の戦車みたいなスペックをしていながら、足の裏の分厚い肉球でさらに怖いことに。。

肉球によってドスンドスンという重たい音がかき消されるのです。雨の日だともっと聞こえなくなるようです
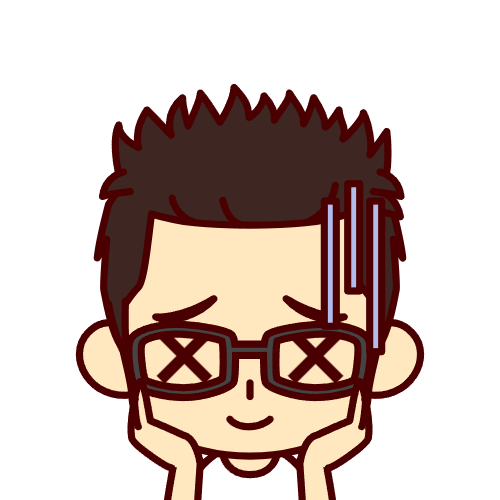
体格が大きいため、麻酔銃で撃ったとしても麻酔が効くまでに時間がかかる!?
麻酔銃は風の影響を受けるので有効射程距離は数十mまで近づく必要があります。加えて、麻酔に即効性はないので命中したら、薬が効くまで怒り狂ったヒグマの相手をしないといけない
捕獲ってものすごい難しいんです。。
鳥獣被害対策の難しさ(2 麻酔銃によるクマの捕獲)|植物医科学出版会
ヒグマのおもしろい習性や行動
ライフサイクル
基本的に単独で行動し複数で行動することはありません。ただ、子育て中や親離れしたばかりの兄弟、繁殖期、クマ同士のケンカ中、サケなどのエサが豊富にある時期は複数頭いることもあるので注意が必要です
行動範囲は意外と広く、オスの行動範囲は数百k㎡、メスは数十2k㎡の中で暮らしているようです。
ちなみにオスの行動範囲をざっくり身近な場所に例えると、「大阪市(225.2k㎡)全域」~「名古屋市(326.5k㎡)全域」くらいは歩き回るみたいです
ヒグマの一年
3~5月:冬眠あけ
冬眠から目を覚ましたヒグマが穴から出てきます。オス、子のいないメス、子グマを産んだメスの順番で出てくると言われています。5~7月:繁殖期
オスはメスを求めて広い範囲を動き回ります。
この時期は、オスを避けた子連れメスや、独り立ちしたばかりの若いオスが、市街地付近に出没しやすくなります。8~9月:端境期(はざかいき)
利用できる食べ物が少なく、ヒグマによる農作物の被害が出やすくなる時期です。10~11月:食いだめ
冬眠に向けて、食べ物をたくさん食べます。12~3月:冬眠・出産
ヒグマの生態・習性|札幌市
ヒグマは、冬になって食べ物がなくなると冬眠します。
妊娠したメスは、冬眠中に出産し、春に穴から出るまでの間、おっぱいだけで子グマを育てます。
習性
冬眠(冬ごもり)
ヒグマの冬眠って実はマストではないって知ってましたか?
冬場は食料不足になるからヒグマは冬眠を始めるのですが、これは雪の中で食料を見つけて掘り返す際の消費エネルギー>摂取できるエネルギーとなるため、ご飯を食べようとすればするほどカロリー使うわけです
つまり暖冬であったり、雪がそこまで積もらなければ冬眠をしない個体もでてきます。ちなみに秋ごろに冬眠に必要な食料を得られず、冬眠したくてもできなかった個体は「穴持たず」と言うそうで非常に凶暴らしい
止め足
積雪があり足跡が残るような状態のとき、ヒグマが自分の通った場所を分からなくするために来た道をバックして脇に跳ぶこと。途中から足跡が止まって見えるため、追跡が難しくなります
基本的には逃げるために止め足は使うようですが、個体によっては足跡を途切れさせた周辺で待ち伏せすることもあるので、注意が必要です
土饅頭(つちまんじゅう)
ヒグマは一度に食べきれない食料をゲットすると土や葉っぱを被せて隠し、少しづつ食べる習性があります
そしてこの土饅頭を掘り返されたりすると襲撃者の匂いを辿って執拗に追いかけてきた事例もあるため、森の中でもっこりしたものがあれば要注意です
掘り返さなくても近づいた動物を敵と認識することもあるそうです
生態系での役割
ヒグマは怖い面も多々ありますが、生態系の中では重要な役割を持っています。
ドングリ、サルナシ、ヤマブドウなどの木の実を食べて糞をすることで種子を広げるのに一役かっています。ヒグマは消化能力が弱く食べた木の実が完全に消化されずに出ることも多いので植物にとっては生息域を広げやすくしてくれる存在です
最新の研究によると、平均消化時間は4~6時間ほどかかるためその間に約6kmほどヒグマは移動することが分かったようです
そして、森の中にいる草食動物(シカなど)が増えすぎた際にも抑制するように草食動物を狩ることもあるそうです
最後に
いかがでしたでしょうか?今日は何のお土産もない、ヒグマだけの回でした。笑
本当は世界に8種類いるクマの比較やヒグマと人間の共生、ヒグマとアイヌ民族なども調べて書きたかったのですが、またの機会にします
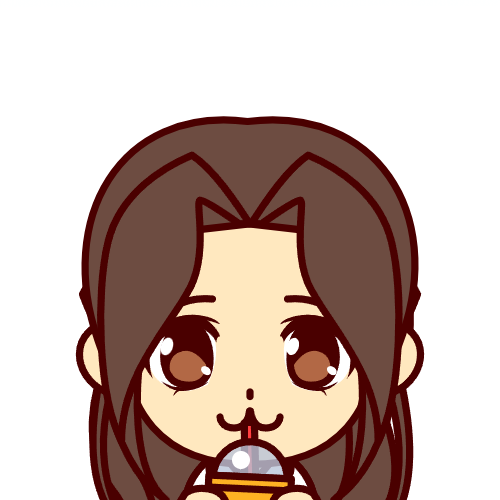
まあヒグマを見たことないけどね、普通に
情報発信を受け取る
クマに関する情報はその凶暴さと慎重さからまだまだ分かっていないことも多いです。
山や川に行くときは必ず「会わない対策」「会った時の対策」「後始末の対策を」をお忘れなく!
存在を知らせておくと人には近づいてこないと言われていますが、万が一会ってしまった時は「生きる」ことを考える!
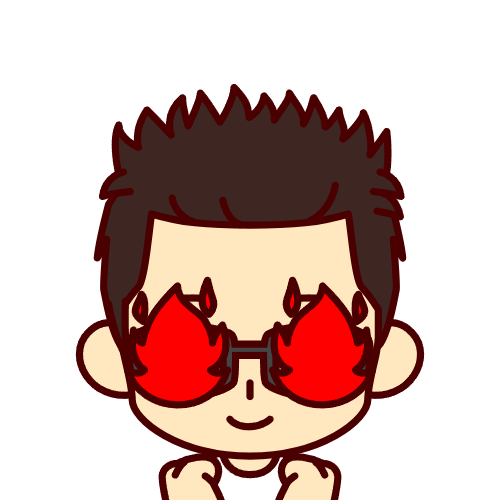
ただそんなヒグマに関心を持たれた極一部の方へ朗報です!なんとヒグマに安全に会える場所がある!!
まだ行ったことないので早くいきたいぞ!!うぉー!
明日は、『ばん』です!乞うご期待!
どうもさわやかです(クマッ)

☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)