こんなときどうする?試験当日の現場対応について!
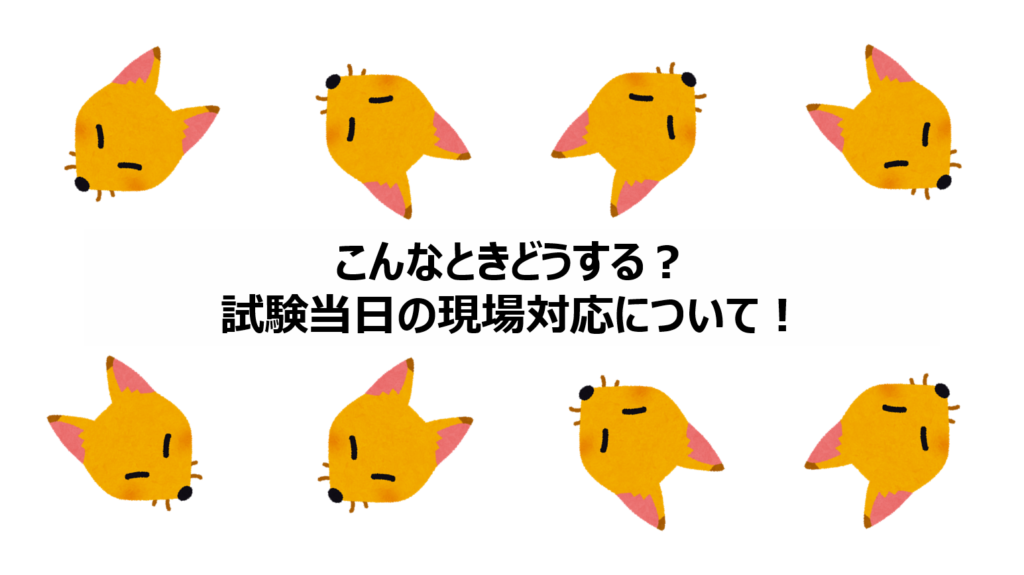

試験まであと11日!!
2次試験前のこんちゃんの記事は今回が最後となります。
少しでも役に立てるように頑張ります🔥
いよいよ試験直前ということで、
この長いトンネルも、もうすぐ終わりが見えてきました。
本番に向けて、今まで勉強してきたことを復習している人も多いと思います。
勉強時間が足りない方と感じている方もいるかと思いますが、
試験当日に全力を出せるように
本番前に1度は4事例まとめて解くセルフ模試の機会を設けるのが理想的です。
試験中の解答プロセスだけでなく、休憩時間の使い方もシミュレーションしましょう!
さて、本日は試験当日の現場対応についてです。
当然ですが、本番当日は初見の問題を解きます。
「今まで、培ってきたことが通用しない」
「計画通りに解けない!?」
などなど、試験当日のトラブルはたくさん起こります。
トラブルによって試験中にパニックになり、実力が発揮できないと、非常に悔いが残ります。
そうならないように、
試験当日のトラブルを想定して、どのように対応するかイメージしておきましょう。
私が考える対応策をまとめましたが、
皆様も自分だったらどうするか?を考えながら読み進めてみてください。
試験中:解答作成の現場対応について

まずは試験中に起こりえるトラブルについて考えてみましょう。

練習で初見問題を解くと、想定通りに解けない事ばかりです・・・

練習中の失敗は、復習して次回に活かしましょう!
おススメは対応策を解答プロセスに落とし込むことです。
試験本番のトラブルは現場対応で乗り越えましょう、
言ってしまえば「その場しのぎ」のやり方です!
*解答プロセスは人によって異なるので、該当するところを参考にしてもらえたらと思います。
あくまで、試験本番で想定通りに解けなかった場合の「その場しのぎ」ですが、
本番ではその場しのぎも大切と考えます。
-
解答骨子を作ったが、文字数が足りないときは?
-
時間があるなら、解答要素の洗い出しをしますが、
時間がないときには文字数が足りない中で書き始めることもあるかと思います。
私の場合、足りない字数は与件文の文章の抜き出し量で調整していました。
得点になるかはわかりませんが、何も書かないと点は入らないです。
ちなみに、解答欄はどこまで埋めるのか?
と聞かれることがありますが、私は95%以上は埋めるように心がけていました。
1点の重みが大切な試験なので、
「何か書けることが無いか?」と最後まで考え続けていました。
-
設問間の解答要素の切り分けができないときは?
-
特に事例Ⅲではよくあるかと思います。
解答要素をどちらの設問で使うかが判断できない場合は
リスクヘッジのため、両方に同じ内容を書いていました。
どちらかは当たると思いますし、両方正解であることもあります。
可能であれば、設問に応じて少し書き方を変えてみると良いと思います。
-
設問間の整合性が取れないときは?
-
整合性はあればよいですが、なくても致命的ではないと考えています。
私の予想ですが、いちいち整合性まで確認していたら、採点に膨大な労力がかかるため
採点するときに設問間の再現性までは確認していないと予想しています。
(恐らく採点者が見ているであろう採点基準は整合性のとれた内容だと思います)
設問間の整合性は解答を考える上では大切ですが、実際の採点時に見られているかは疑問です。
*設問間の整合性とは、例えば大問1で挙げた強みを、大問4の助言問題の施策に生かすといったことです。ここでは、例えば大問1で挙げていない強みを、助言問題で挙げた場合でも、整合性が取れていないから減点となることはないと考えています。(あくまで予想ですが)
ただ、整合性がとれた一貫性のある解答のほうが得点が伸びやすいので、そちらを目指しましょう。
-
設問文と与件文を読んでも解答要素が思いつかなかったときは?
-
聞き慣れない切り口の設問では、スムーズに解答要素を選べないこともあるかと思います。
「ん?この設問なにを言っているのだろう?」
という感想が出てくるかもしれません。
このようなときは、設問文に素直に解答することを優先的に考えます。
また、ヒントは設問文にもあると考えていて、
徹底的に設問文に関連する与件個所を探し、そこからヒントを探すこともおすすめです。
例えば:X市の夜の活気を取り込んで~(H30事例Ⅱ 第4問)の問題では、
「夜の活気ってなんやねん」とか思うのですが、
与件文の5段落目の「~活気の維持に熱心である」や「夜間の滞在人口~」といった記述から
この周辺に施策を考えるヒントがあるかも!
という風に、設問文を手掛かりに与件文から解答要素を探します。
-
40分すぎても解答骨子が完成しなかったときは?
-
とりあえず書き始めます。
私の場合、解けそうな問題から、優先順位をつけて骨子を作成するため、
最後に残った骨子が作成できなかった問題は難問である可能性が高いです。
それよりも、骨子が完成した問題で点数を稼ぐことに注力します。
骨子が作成できなかった問題は後程取り掛かるのですが、
すでにある程度、解答欄を埋めているため、
心に若干の余裕がある中で考えることができますし、
一度、他の問題の解答を記入することで、気持ちが切り替わり、
先ほどは気が付けなかったポイントを捉えることができるかもしれません。
解けない問題につかまって時間を浪費することはもったいないので、それは避けたいところです。
-
レイヤーの分類ができなかったときは?
-
先ほどの解答要素が思いつかなかったときと同じです。
設問文に素直に解答するようにしましょう。
「設問に素直に解答する」とは解答の型やレイヤーに当てはめずに、解答を考えることです。
型もレイヤーもあくまで解答の方向性を外さないための補助的なサポートと考えています。
なので、設問によってはこれらが当てはまらないことも当然あるため、
その時は設問を素直に捉えて、聞かれたことにそのまま応えることを考えます。
実際に、R2年の事例Ⅰの大問2(システム化の手順)と大問3(部下に求めた能力)では
レイヤーにこだわらずに解答を考えました。
-
解答のマス目を書き直したいときは?
-
一度書いた答案の一部を修正したいこともあるかと思います。
これは現場対応というよりもテクニックに近いですが、
私は解答骨子の「、」句点の有無や、
長い表現と短い表現の使い分け(ロイヤルティ ⇔ 愛顧 など)で文字数の調整を行っていました。
例えば「理由は、①~、②~、③、~」の句点(、)は
特になくとも問題がないと考えていたので、
初めは句点を記載して、文字数が足りない場合は句点を消して調整していました。
-
解答に必要な1次知識が思い出せなかったときには?
-
特に事例Ⅱでは直接知識を聞かれることもあるので、ビビりますよね・・・
もちろん知識を基に適切に解答できたらよいですが、
そうでない場合も与件文の内容から適切な記述をすることを考えましょう。
例えば昨年のアンゾフの問題ですが、
12代目の再現答案でも戦略名まで書けていない人も多いです。
それでも60点近く取れるので、戦略名が書けなくとも記述が適切だと得点が入ると考えています。
知識問題ができないと、かなりへこみますが、
それだけで合否が決まるわけではないので、わかる範囲で記述しましょう。
休憩中:メンタル面の現場対応について
次は休憩中のメンタルについてです。
2次試験はメンタルのコントロールが非常に重要です。
結論は
「余計なことを考えずに、目の前の事例に全力集中!」
です。
しかし、本番では様々なトラブルが起きますし、
一生懸命に勉強してきた人ほど、その思いがから回ることもあります。
ちょっとやそっとのことでは揺るがないように、
試験当日の精神状態もイメージしてみてください。
-
休憩時間中に前の事例の間違いに気づいてしまったときは?
-
少しでも失敗に気づくと、ネガティブに過大評価しがちです。
そんな時は、そのミスは実はそれほど致命的ではないと考えましょう。
先ほどの1次知識が思い出せなかったときの対策でも書きましたが、
小さなミスがあっても、それだけで大きく点数を引かれることは少ないと考えています。
終わった事例のことを考えても1点も増えませんが、
次の事例に集中して取り組むことで合格の可能性は上がります。
冷静なときに読むと「そんなの当たり前でしょ」と思うのですが、当日はかなり動揺します。
私も事例Ⅱが終わった後の休憩時間に、
アンゾフの問題の失敗を思い出してショックを受けましたが、
ファイナルペーパーを読み直して気持ちを保つことができました。
実際に事例Ⅱは70点以上あったので、
勝手にミスしたと思ってメンタルを崩す方がよっぽどもったいないです。
-
いつもに比べて緊張していると思ったときは?
-
と~しも書いていましたが、緊張や不安は期待の裏返しです。
勉強してこなかったら、そもそも合格を期待しないので緊張もしません。
合格できる力があるから、緊張するのです。
緊張したら深呼吸をしましょう。
初めの事例が終わると緊張も取れてきます。
今まで積み上げてきたことは、簡単に裏切りません。
安心して自分を信じて試験に挑んでください。
-
めっちゃ準備してきたのにまさかの体調不良になったときは?
-
これはかなり悔しいと思います。
けど、大事な勝負の時に必ずしも万全の状態で臨めるわけではない事も覚悟しておきましょう。
昔の話ですが、試験の時期になると大学受験の試験前日に緊張で寝れなかったことを思い出します。
初めての徹夜で、朝食ものどを通らず、最悪な気持で試験会場に向かいました。
3年間コツコツ頑張ってきたのに、
前日に寝れなかっただけで、全部無駄になるとか、ふざけんな!
とか思っていましたが、最後は
「この試験で自分の人生を切り開く」
と気持ちを切り替えて、試験に臨み合格することができました。
体調が悪い中でも結果をださないといけない場面は存在しますし、
それが今だと腹をくくって試験と向き合いましょう。
(ただしコロナには十分ご注意ください)
-
途中で、今まで応援してくれた人に申し訳ない、情けないと思ったときは?
-
恐らく試験に向けて様々なものを犠牲にして勉強してきたと思います。
周りの大切な人にもたくさん協力してもらったでしょう。
大変な中、周りの人のことを考えることができるのはとても立派なことです。
今年は早朝の勉強会に参加することもあったのですが、
勉強会が終わった7時ごろに、お子様が起きてきてあわただしく退席されるのを見て
家庭での役割や仕事での役割を果たしながら、試験とも向き合っていてスゴイと思っていました。
周りで応援してくれている人は
あなたの試験合格を応援してくれていますが
もう少し本質的に考えると、その試験(勉強)を通して
あなたの人生が良い方向に向かうことを期待して応援してくれてるとも考えられます。
結果にこだわり過ぎず、どのような結果を受け入れる覚悟
について書かれていました。
試験の結果はまだわかりませんが、
試験に全力で最後まで取り組むことは
人生において必ずプラスになると考えています。
応援してくれたのに、情けない・・・でなく
応援してくれたから最後まで全力で頑張れました!
と胸が張れるように取り組みましょう。
終わった後は
試験に関する愚痴は支援団体の人が聞いてくれるので、
周りの人には「ありがとう」を伝えましょう!
-
途中で「もうだめかも、、、来年かなぁ」と思ったときは?
-
今、この場で全力を尽くせないのに、来年頑張るとか考えてはいけません。
2次試験の問題を解いていると、少しずつ診断士がどんな存在かわかってきたかと思います。
コロナウイルスの苦しい経営環境の中でも、前を向く経営者に寄り添うのが診断士かと思います。
そして、皆さんが将来支援するであろう経営者の方は、
厳しい状況であっても「今年はもういいや、来年頑張ろう~」とは決して考えないでしょう。
受験生支援をしてきて、
惜しくも1次試験を突破できなかった方もたくさん見てきました。
2次試験を受験できるのは、それだけで大きなチャンスです。
最後まで決してあきらめず、目の前のチャンスを掴み取りましょう。
まとめ
今回は試験当日の現場対応について、試験中の対応とメンタルの対応について記載しました。
試験が終わった後は合格した実感がなかったという方がほとんどです。
私もそうでした。
「合格しているかはわかりませんが、できることはすべてやり切りました。」
試験終了後に、皆様にこのような心境に至ってもらうのが
私が受験生支援を始めたときに立てた目標です。
今まで積み上げてきた努力は、簡単に裏切りません、
あと11日悔いのないように全力で過ごしてください。
🦊記事のウラガワ🦊
今日の記事ではウラガワまで包み隠さず書いたので、ここで改めて書くことはないです笑
あとひとつ書き忘れたことは、
試験終了後はできるだけ速やかに再現答案を作成することをおすすめします。
私は昨年、試験が終わった後に近くのカフェで作成しました。
(事例5とかいって自分で設定してました)
そこでミスに気づきまくるので、かなりの苦痛・・・というか拷問でした笑
再現答案をつくるためにわざわざ余力を残す必要はないですが、できるだけ正確な再現答案が望ましいです。
再現答案を作る理由は、自分のためというより、
これまで先輩受験生の解答を基に勉強してきたのでそのお返しの気持ちが大きかったです。
もし結果が出なかったときの復習のためという意味もありますが、ちょっと縁起が悪いのでこの理由でおすすめしにくいです笑
本日書いた記事の最後までメンタルを崩さずというのは
あくまで試験中の話です。
なので、試験終了後はへこんだり、メンタル崩壊しても大丈夫です。
だって人間だもの。
★★★★★
いいね!と思ってもらえたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
にほんブログ村のランキングに参加しています。
クリックしても個人が特定されることはありません



いつも読ませていただいております。
貴重な情報をありがとうございます。
2次試験、3度目です。 ここにきて、いろんなことが分かってきました。
いままで全くの五里霧中でした。 何が悪いのかすらわかない状態でもありました。
ようやく、何が不足しているのか、何が弱点なのかを突き詰められるようになってきたようなきがしてます。
ここから、これまで繰り返してきた過去問を、もう一周でも回せる時間があるのならば、もっといいのにな。
という気持ちです。
あと数週間足りなかったかな。。。
ぺっぺさん
コメントありがとうございます!
成長を感じるかとが難しい2次試験において、足りないことがわかってきたのは良い兆しだと思います!
「あと数週間足りない・・・」という見方でなく、
「残りの時間でどのようにして自分を高められるか?」
と考えてみるのはいかがでしょう?
あと1週過去問を回すことで、改善の余地があるということは、
自分の解答プロセスの中で、どこを改善すべきかがある程度分かっているのではないでしょうか?
(改善点がわからなかったら、過去問解いても変わらないと考えます)
もしそうでしたら、苦手な部分(解答プロセス)のみに注力して復習することで
短時間で効率的に不足している能力を補えるかもしれません。
(例えば、80分フルで解くのでなく、骨子の作成までを集中的に行う や 設問解釈のみをトレーニングする等)
試験が終わってからは何もできませんが、試験前は対策が取れるので、
限られた時間ですが、少しでも合格の可能性を高めて試験に臨んでいただけますと幸いです。
応援しています!
ありがとうございます。
残り、頑張ってみます。
すみません、一点教えてください。
設問分析ですが、事例2.3.4は、なんとなくですが、わかります。
しかし、事例1は、与件を読む前の設問チェック段階では、設問分析まで見切れません。(聞かれていることが、組織・人事・事業戦略・知識なのか)
でも、その後、与件を読み、解答骨子を作りながら、分かってきます。(この質問は、組織だったのか。) といった具合です。
合格者の方々は、与件の読む前のチェック段階で、理解し切れているのでしょうか? 理解しきれるまで、研究を進めた方がいいのでしょうか?
それとも、与件を読む前の設問分析には限界点があるため、それは不可能なものなのでしょうか?
とにかく、事例Ⅰの設問分析が苦手です。
ぺっぺさん
そのようなとらえ方でよいと考えています。
設問の切り分けはあくまで「出来たらあとが少しだけ楽になる」くらいの認識でしたので、
与件を読む前にできていないこともありました。
たまに「なんじゃこりゃ?分けれない」といった問題に出会うこともあります。
その時は設問に今回の記事でも書いた、素直に応えることを念頭に与件を読みながら調整します。
設問の分類がうまくできないときには、分類にとらわれ過ぎないことも大切と考えています。
ありがとうございます。
こんちゃんさん、試験前の心構えの記事をありがとうございます。
こうして試験前の記事を見ていると、12代目の皆さんにお世話になった思い出に浸って、参加したセミナーのことを思い出したりしそうになりますが、ただただ今は淡々と今までの勉強ペースを継続するだけです。
そして試験本番でも、自分が積み上げてきたことを淡々とこなしたいと思います。
ただ、どうしても難問にぶち当たったりパニックに陥りそうになった時は、一次試験での試験の時のように12代目の皆さんのことを思い出して奮起したいと思います。
一次試験の時は「このまま12代目の皆さんと二次試験に挑戦できないなんて嫌だ!」でしたが、二次試験は「12代目の皆さんにたくさんお世話になったのに、途中で投げ出して後悔の残る答案にしてたまるか!」の精神でいきたいと思います。
ここまでお世話になっているので、自分の中では12代目の皆さんの存在も大きな精神的な支えになっています。
ただ、あくまで自分は淡々とこなすスタイルで、試験前の勉強も、試験中も、淡々とこなしていきます!
ロムさん
いつもありがとうございます。
我々の存在が少しでも役に立っていたらとてもうれしく思います!
実は12代目としてもロムさんのコメントが支えになっていたりします笑
今回の記事で一番伝えたかったことが伝わってよかったです。
試験前の取り組み方としては、力まずに
コツコツ淡々とやるが最強だと思っています。
アツさと冷静さのバランスを大切に、最後まで試験に全力で向き合ってください!
応援しております!