【2次試験】12代目全員全力インタビューリレー『解答骨子を作っていましたか?』

🌊🌊🌊 道場夏セミナーのお知らせ 🌊🌊🌊
一発合格道場読者のみなさま!!お待たせいたしました。大好評春セミナーに続く夏セミナー開催のご案内です。
・日程:2021年7月17日(土) 14:30~18:00、その後懇親会
・場所:オンライン(zoom開催)
・募集人数:80人
・応募期間:2021年6月24日(木)12:00~7月6日(火)23:59
・募集方法:応募期間内に以下の申し込みフォームよりお願いします
・内容:2次試験対策 (事例Ⅰ~Ⅳまで、道場メンバーによる解答のコツ、個別相談など検討中)
*今回の内容は、ある程度2次試験の問題を解いている方向けの2次試験対策セミナーです。
1次試験後、9月上旬にこれから2次対策を始める方向けのセミナーを予定しています。
(内容は今回の内容+2次試験学習の基礎知識)
🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊
2次対策セミナーの申し込みは今日までです!!!迷っている方は今すぐお申込みを!!!
今回も気合の入ったセミナーです!(笑)損はさせません!!

こんにちは!masumiです。1次試験まであと1か月と少しですね。
去年の今頃私は・・・4か月前から勉強を始めたので、まだまだ仕上げには遠いな、、というところです。
5科目を3周して残り2科目に取り組んでいたくらいですね。どんなスケジュールか知りたい方は「体がキツイよアラフォー受験生、1次試験まで4か月の軌跡」をご覧ください。今から必死でやればぐんと伸びます!!
ちなみに、体がキツイよ、、と思って受験勉強していましたが、合格後の選択によってはそれよりはるかにキツイ状況になります(笑)絶賛実務補習中の今、なんかもうよくわからないくらい疲れます。
起きている時間はずっとPCです。日中の仕事もみっちり8時間PC作業でへとへとな上に、自宅で4時間くらい作業して今深夜1時。。日中どうやって体力を温存するか、ばかり考えています(笑)
さてそんな中、今回は2次試験がテーマです。5月に開催した1次試験のお悩みに12人全員で解答するインタビューリレー、メンバーそれぞれの渾身あるあると共に好評でした!!いただいた質問に12人で解答しますので、ぜひ自分に合った対策を取り入れていただければと思います。
2次試験の12代目の試験結果はこちらです。勉強スタイルや時間、得意不得意がそれぞれありますので参考にしてみてください。黄色が最高点です。
では早速質問にいってみましょう!今日のテーマはこちらです。
「骨子」という言葉、あまり普段使わないかなと思うのですが、2次試験対策だとよく耳にします。それぞれ認識は多少違うかもしれませんが、「おおまかな下書き」というイメージです。解答用紙に記入する前の段階でどこまで解答の文章を作成していたか、ということに対する12人の回答です。ぜひ参考にしてみてください(^^)/!!

ざっくばらんに、与件文から抽出したキーワードをどこでいれるかは作成していました。
文章を作るというよりは、設問ごとに、使うキーワードを抜き出してまとめておくという程度ですね。
むしろ、回答そのものよりもしっかりと作る。文字を書くのは苦手(面倒くさい)、文章を組み立てるのは割と得意なので、本番の一か月前頃からは量をこなすために、回答分まで作らず、回答骨子までを作成する演習をしていた。

骨子を重視してしっかり作成していたんですね。文章を書くのが苦手な場合はとにかく書く練習として骨子までを訓練するとよいかもしれません。

文章を作るのが苦手なので作っていました。文字数まで数えてました。 私の場合、即興で文章を書くと、問題に答えていなかったり、主語と述語があっていなかったり、修飾語がどこにかかるかわかりにくい文章になります。
なるほどなるほど。文章を作るのが苦手だなと思う人はある程度しっかり骨子を作っておいた方が良さそうですね。
作っていました。 設問を読んで解答要素を書き出して、与件文を読んで解答要素に沿ったキーワードを入れていく程度の骨子です。

設問から解答の大枠を作り、キーワードを当てはめていくんですね。設問を読んだ時点で、というところがMa.satoのキーワード抜き出し型と違うところでしょうか。
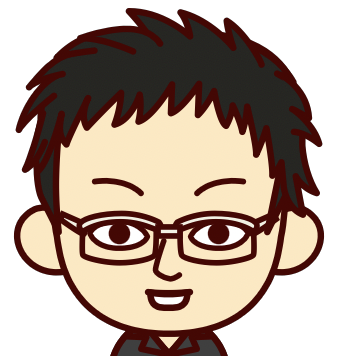
解答記入の時間は厳守していたので、それまでの時間の中で許す限り作るようにしてました。
時間がベース!時間があれば詳しく、無ければざっとと臨機応変に変えていたと。80分のタイムマネジメントが素晴らしい!
ほとんど作っていたとは言えないです。キーワードを余白に書いていた程度。後から見直してもどんな解答をしたか一言一句書けない。

私の場合は、文章を書くのは比較的得意です。書きたいことが決まっていればスラスラ書けるのですが、長くなりがちなのと、書いているうちに、ここは順番を変えた方がいいな、ということがよくあります。ただ試験では書き直しの時間がもったいないので、長い文章を書こうとせず、順番も気にせず短い文章をいくつも書くだけでいいや、と思っていました。

キーワード、解答構造を白紙にメモする程度。 (下書きまでメモ用紙で書こうとトライするも、時間不足で断念。一発で解答用紙に書く方が性に合っていた)
なゆたもキーワード抜き出し型ですね。あらかじめ抜き出したワードが入るよう構成を考えて直接解答用紙に記入、と。
1回目、2回目はつくっていましたが、時間が足りなくなるので、合格年度はつくりませんでした。

ひでさんは、なんとキーワードも書き出さず、頭に入れて直接解答用紙に書き込むという超大技です!!
ひでさんの日ごろの記事を読んでいると納得!設問解釈から与件文の読み取りがものすごく上手いです。ひでさんならでは業(ワザ)でしょう!

作っていたが、文字が汚く、書くのが遅いので、できるだけ文字を書かず番号で解答要素を表しながら作成しました。(与件文の解答要素に番号を振り、その番号を使って解答骨子を作成)ざっくりな文字数もカウントして、解答骨子に記載して、解答ボリュームの目安をつけていました。だいたい8割くらい埋まったら書き始めて、書きながら文字数を調整していました。
おお、新しい!ゴリゴリ理系のこんちゃんらしい発想!文字を書かずにキーワードに番号を振って、その番号で骨子にするとは!そのメモ書きした問題用紙がどんな風になっていたのかが気になります!
簡単なメモ書きは作っていました。骨子が決まらないと、そこに流し込む解答も決められなかったので、大まかな骨子のメモ書きは作っていました。

文章を先に作って、解答のキーワードを当てはめていくんですね!よがと近いですね。弁護士らしい、と感じるのは私だけでしょうか。日ごろ文章を作ることが多い(そうだよね??)TAKUROの方法に納得。

作っていませんでした。一時期作っていましたが、作っても結局それに従わず最終的には書いてしまっていたので、時間の無駄だと思い、削りました。
わかる!(笑)あらかじめ文章を作成していても、実際解答用紙に記入する時に見返すと書き直したりするので、だったら作成しなくてもいいんじゃないか、ということですね。にのみもキーワード抜き出し型にしましょう。
解答骨子としてほぼ全文一度下書きしてから解答用紙に書き込んでいました。 とはいっても真っ白な状態から全文を書いていたわけではなく、キーワードや文章のまとまりをいくつか作って、その後にどうやってわかりやすく論理的な文章にするか推敲するというステップを踏んで作成しました。

ラスト、のきは骨子づくりのお手本のような解答!それを80分でやっていたのが驚愕です。時間が無限にあれば私もそうしていたでしょう。解答を考えることに時間がかかるとなかなかここまでできないと思うので、いかに早く解答の方向性を決められるか、で変わってきますね。
ということで、ざっくりみんなの骨子作成方法をまとめると以下の通りです。
・キーワード抜き出し型・・・Ma.sato、masumi、なゆた、にのみ
・しっかり文章を作成型・・・と~し、アヤカ、のき
・設問から作成、キーワード後入れ型・・・・・・よが、TAKURO
・時間ベースのハイブリッド型・・・池やん
・全く書かずに頭に入れる型・・・ひでさん
・文字を書かずに番号で作成するキツネ型・・・こんちゃん

いかがでしたでしょうか。解答骨子の作成方法もいろいろありましたね。ぜひ自分に合った方法を取り入れてみてください。
明日は池やんです!「ふぞろいの使い方について」お楽しみに(*´з`)~!
ブログの感想、ご要望などあればコメントでも私のTwitterでもお気軽にどうぞ!!
※Twitterは診断士以外の話も多いですが、基本、ひとりごとが多いので毎日なにかしらつぶやいています。
★★★★★
いいね!と思ってもらえたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
にほんブログ村のランキングに参加しています。
クリックしても個人が特定されることはありません



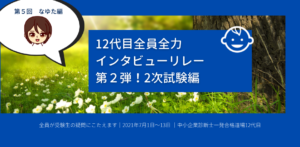

解答骨子の記事、ありがとうございます。
私も解答用紙に書く前にある程度の骨子を作ってスムーズに書けるようにと考えているのですが、どこまで骨子を固めるのかのバランスを取るのに迷っております。
過去問を解く度に、骨子を作っても解答用紙に書く時に文章の構成が崩れていったり、要素を追加しようと考えてしまったり、消しゴムが活躍してしまう機会が増えてしまいます。
自分なりのバランスのとり方や解法パターンが固まるまで、試行錯誤を続けていくしかないなぁ、と思っております……。二次試験、難しい!!
ロムさん
コメントありがとうございます。そうですね、骨子をどうするかはご覧の通り、かなりまちまちでしたね(笑)
みんないろいろ試行錯誤の末に辿り着いたやり方なので、ぜひマネしながら自分にしっくりくる方法を探していただけると良いと思います。