傾聴の勧め ~診断士×キャリアコンサルタント~ by たいしん

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
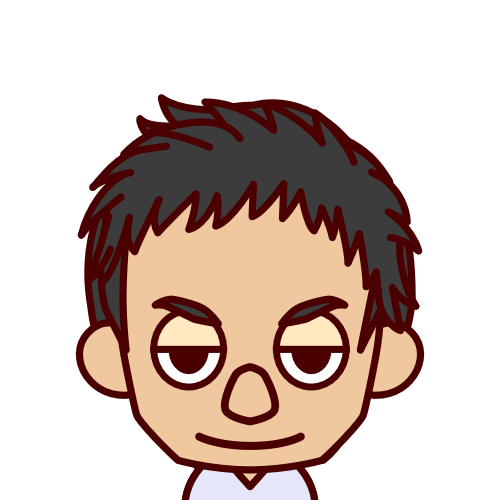
みなさん、まいど!
たいしんです。
いや~ジャパンカップのドウデュースは強かったですね~!
久しぶりに秋古馬三冠馬が見れそうなぐらい、実力が抜けてます。
ゼンノロブロイ以来の偉業を期待しましょう!
で、どうやったん?
どうせアカンかってんやろ?

グサッときますよね。あいつ。
・・有馬記念でのリベンジを誓いつつ、本日は真面目な話をしようと思います。
はい「傾聴」の話です。
今日の記事を要約するとこんな感じ
- 診断士とキャリアコンサルタントは親和性が高いと思っています
- 何故なら、経営者/相談者との関係構築には「傾聴」スキルが求められるからです
- 診断実務に活かせる「傾聴」スキルを学んでみては如何でしょうか
私たいしんは、キャリアコンサルタント(以下CC)の資格を有しています。
しかしCCで飯を食っている訳では御座いません。(というかCC1本でやっていける方は相当だと思います💦)
本業は3PL事業で人材開発の業務に従事しています。従業員の面談などで、そのスキルを活用している感じですね。
本日は診断士とCCという両方の目線で見た「傾聴」の必要性について語りたいと思います。
多少長めの記事になります。それでは宜しくお願いします!![]()
はじめに、キャリアコンサルタントとは
で、CCって言われてもね。中には「キャリアチェンジを促進させるやつ」と思っている方も多いかと。
一般的に「キャリア」って、当然仕事上のことだと認識されています。
この法律において「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。
職業能力開発促進法 第二条 5項
ただ私が思う「キャリア」って、その人の人生そのものだと思うんです。仕事以外のことも含めてね。そこに関わりあうのがCC。そんな認識です。
そして最初の方で学ぶのが「傾聴」です。クライアントとのラポール形成のためです。
信頼関係が出来ていないと、真意を話してくれませんよね。お悩みの経営者様、お悩みの相談者様、皆一緒です。
診断士とCCの親和性というより、相談される側全ての人にとって通じることかと思います。
少しはずれます
傾聴の必要性を語る前に、もう少しだけCCの技法について紹介させて下さい。
CCは先ほど見て頂いた通り「職業選択の助言」などの業務を行いますが、抽象度を上げると「クライアントの自己概念を成長させること」と言われています。*自己概念とは「自分と自分を含む世界をどう捉えるか、その見方、考え方」
・・わかりにくいですよね。こちらの図と共に、具体的に見て頂きます。
私が2回目の2次試験を落ちた時のことを例に挙げてみますね。

経験の再現
あれだけ2次試験に特化して勉強してきたのにな。何が悪かったんだろうか?はぁ、、2回目も落ちてしまった。また1次試験からやり直しか・・。気が重いな。悔しいな。周りにも顔向けできないな。でもなんで俺はこんなに悔しいんだろうか・・。
本来はこれを対話しながら時間をかけて行います。大事なのは「経験=出来事+感情」だということです。
意味の出現
なぜこんなに悔しいのか。「試験に落ちたから?」「目標をクリアできなかったから?」「周りに合格を伝えることが出来なかったから?」違うな、そんなんじゃないな。「在りたい自分になることが出来なかったから?」かな。・・ありたい自分ってなんだろう?
大体の場合、ここで「そもそも」を突き詰めるところまでいきます。
意味の実現
俺なにがしたいんだろう?突き詰めると「人の役にたって自分も成長したい」だな。診断士の資格はきっとこの思いを叶えてくれる。やっぱりチャレンジし続けなきゃな。
ようやく1歩踏み出せます。診断士試験でいう、いわゆる「社長の思い」的なやつが出てくるところです。
このプロセスが実は「内省」にあたります。
意味の実現を果たすために、CCは効果的な質問をクライアントに投げかけ、こころを解いていきます。
この際に傾聴力が必要になるというわけです。
傾聴について
眠たくなってきたでしょうか?すみません💦ここからが本題です。
まず「傾聴」とは、単に「話を聞く」ということでは無いです。
簡単にいうと「各種技法を使って、クライアントのストーリーを引き出す」ことです。
俗っぽい言い方をすれば「良い合いの手を入れる」ですかね。
そして傾聴の際に求められるカウンセラーの基本的態度を展開してきたのが、ロジャーズ(Rogers,C.R.)です。
この基本的態度は、今日のあらゆるカウンセリングの基礎として確立しています。
「受容」「共感」「自己一致」といいます。
最初に学ぶことにして、これを完璧に習得するのが非常に難しいんです。。
受容・共感・自己一致
- クライアントに対して無条件の肯定的関心を持つこと(受容的態度)
- クライアントの内的世界を共感的に理解し、それを相手に伝えること(共感的理解)
- クライアントとの関係において、心理的に安定しており、ありのままの自分を受容していること(自己一致または誠実な態度)
ここまで、傾聴の必要性・内省の方法・スキルの内容を見てきました。少し纏めてみますね。
「今日はあなた(相談者)の話を聞きたい!」と自分に暗示をかけ(実際にやってます)、相談者の心の内を丁寧に観察し・理解し、自己概念が揺らいでいることを認知させ、これまでのストーリーから導き出される「ありたい自分(≒社長の思い)」に向かって、効果的な質問を投げかけながら共に歩んでいく。
これが傾聴を活用する方法です。
傾聴を繰り返すことで、相談者との信頼関係を築くことができ、ようやく真意を話してくれる段階になります。
基本的傾聴の連鎖
最後に診断実務において注意した方がいい点をご紹介します。
この傾聴を繰り返す段階(ラポール形成の段階)を土台として、様々なカウンセリング技法を繰り出す訳ですが、この一連の図を少しみて頂きます。

上から4つめの「積極技法」というところに「自己開示」というのがあります。友人と話している時でも「自分の場合は~」とか、よく話の流れで使うじゃないですか。あれです。
これほんっとに要注意なんですよ。図をみてもわかるように、実は結構高度な技法なんです。まず信頼関係がないと、逆効果になってしまうんですね。
ちょっと極端な例をあげてみます。
良い例

〇〇っていう機械を入れたいねんな~。
どう思う?
なんで入れたいと思ったん?
導入したい思いに繋がる出来事があったん?
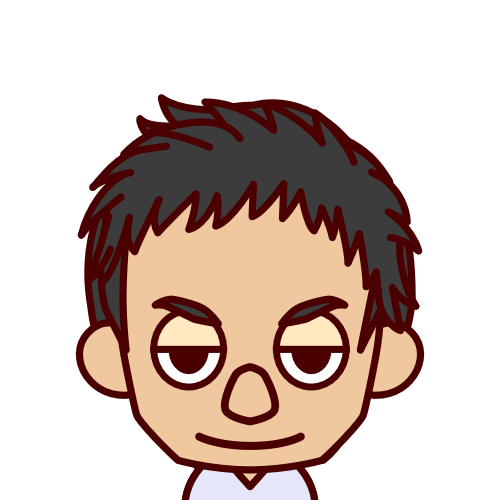

実は前にサンプル機を貸してもらってたことがあって。
苦労したけど、皆でワイワイやって楽しかったし。
出来上がった商品も、めっちゃ良かってんな~♪
NG例

〇〇っていう機械を入れたいねんな~。
どう思う?
絶対やめた方がいい!
俺も使ったけど不良品ばっかりやったわ!
納品の時なんかも、ごっつ愛想悪かったし、
~ なんやかんや・・・ ~
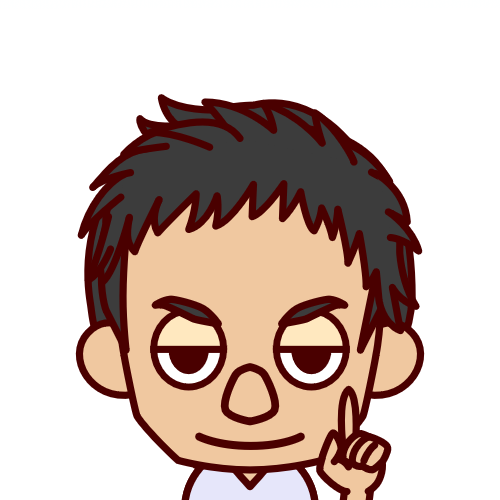
極端すぎましたかね💦
ご覧の通り、NG例の方は全然相談者に寄り添えていないですよね。
特に信頼関係がない状態で自己開示してしまうと、
「あいつ何様やねん」や
「誰もお前の話、聞きたないっちゅうねん」
っていう感じにさせちゃいます。
クライアントの「話したい」っていう気持ちが閉じてしまいます。
周りにもいないですか?すぐに自分の話に持って行く人。2次試験勉強の時に、ひたすら言われましたよね。「社長の思いに寄り添え」って。
ただの自慢話にならないように、診断実務の時にも留意したい点です。
診断業務にて
いかがでしたでしょうか。傾聴の必要性、伝わりましたでしょうか。
極論ですが、問題解決の答えは相談者の中にあります。
そりゃ具体的な施策は診断士としてアドバイスするところですが、ここでいう「答え」とは「どうありたいか」です。
このありたい姿を浮き彫りにするため、ラポール形成に必要なのが傾聴力です。

さて2次試験の事例問題。あれよくできていませんか?いや~感心するほどの出来だと思います。
ただ実際の実務では、あそこまで纏まってることなんて皆無です。私もまだ経験は浅いですが、あそこ行きつくのが大変なんですよね。
傾聴力を駆使して、あそこまでニーズや思いを収集していきたいですね。
まとめます
本日お伝えしたかったことを再掲します。
今日の記事を要約するとこんな感じ
- 診断士とキャリアコンサルタントは親和性が高いと思っています
- 何故なら、経営者/相談者との関係構築には「傾聴」スキルが求められるからです
- 診断実務に活かせる「傾聴」スキルを学んでみては如何でしょうか
よく「CCは相談者の鏡であれ」と言われます。
良い壁打ち役になって、経営者様と伴走していきたいもんですね。
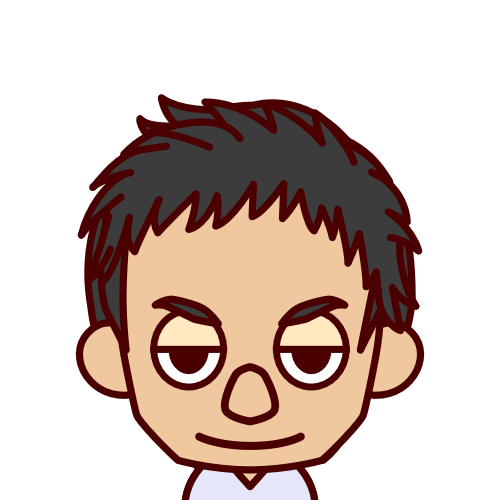
明日はせーでんきです。
せーちゃんよろしく!
簿記1級のことでも語ろうかな♪

☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)



こんばんは!
にっくです。
診断士とキャリアコンサルタントのお話、ありがとうございました!
傾聴は仕事だけでなく、日常でも身につけておきたいスキルの1つですね。
普段の生活がより充実したものになりそうです!
ありがとうございました!
にっく
にっくさん
いつもコメント頂き、ありがとうございます。
日常でも活かされるスキルなのは、仰る通りですね。
私もまだまだ勉強中で御座いますが、お互い頑張って参りましょう!
こんばんわ!
本日もありがとうございます!
私自身傾聴って大事なんだろうな〜…と思いつつも、自身の弱みとして人の話を聞くことができないことだと思っています。
よろしければ、こういう意識持つとええんやで!っていうような必須の心構えなどがあれば教えていただけると幸いです!
テセさん
いつもコメント頂き、ありがとうございます!
テセさんは弱みとして認識されているんですね。
私もどちらかというとツッコミ派なので、話の腰を折らないように注意しています。
他に傾聴する際に気を付けていること(心構え)ですが、3点あります。
1つめは、記事にも載せた「あなたの話を聞きたい!と自分に言い聞かせる」こと。
2つめは、「先入観を持たない」こと。
3つめは、「沈黙を怖がらない」こと。です。
奥が深い領域になりますが、是非取り入れてみて下さいね。