2次向け夏セミナー開催報告 〜ニジトーーク! & 懇親会でのQ&Aまとめ〜
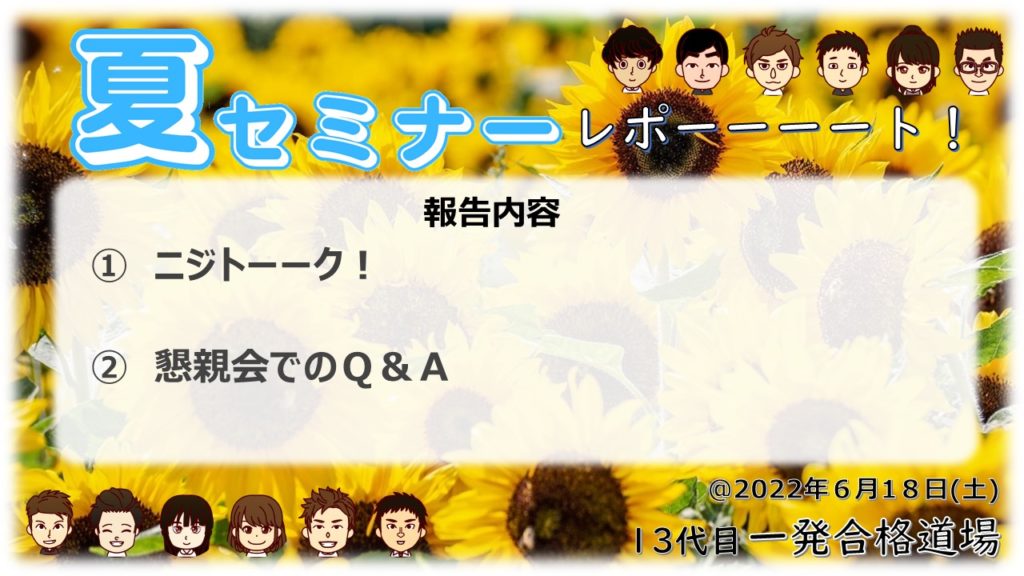
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
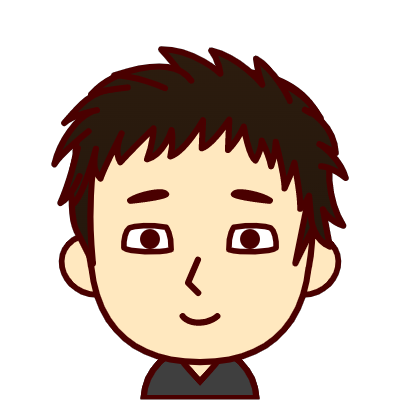
どうも、どらごんです。
今日は一年で最も昼が長い日、夏至です。
夕方、明るいうちから酒が呑めて楽しい季節です。
先日の夏セミナー(多年度受験生向け2次試験対策セミナー)にご参加いただいた方々、ありがとうございました。
私自身はあまり出番がなかったのですが、懇親会では受験生の熱意に触れ、今後の支援活動や診断士活動の励みとなりました。
昨日のくまの記事「2次向け夏セミナー開催報告 〜リット・あらきち講演〜」に続き、本記事では「ニジトーーク!」と「懇親会でのQ&Aまとめ」について記します。
それでは梅雨空が晴れて雨上がりとなるよう、元気出していきましょう!
ニジトーーク!
「ニジトーーク!」は、2次試験に関するお題に対してそれぞれ3~4人ずつ答えていく、というコーナーでした。
タイトル名の元ネタはご存じあのテレビ番組。司会はこの2人。hotちゃんとなおさこです。
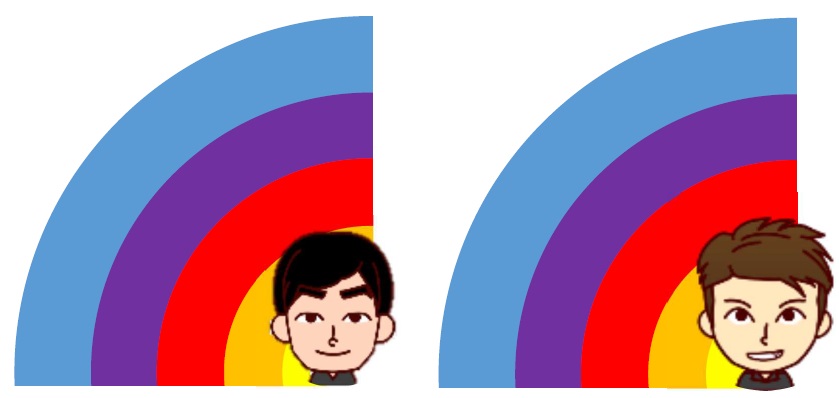
なお登場時のBGMは、ドラムのビートが印象的な「ザ・ナックのマイ・シャローナ」。
まあ、ここまで説明していてお分かりの通り、本コーナーはリットとあらきちの真面目で濃厚で熱量の高い講義の合間に、残りの10人で繰り広げた箸休め的な味変コーナーでした。
そして、そのお題はこちら。
- 2次試験の普段の勉強法、スキマ時間の勉強法は?
- 事例Ⅳの勉強方法は?(タテ解き・ヨコ解き?)
- 与件文のマーキングはどのようにしていた?
- ルーティーン(問題用紙破るとか)は?、80分間の時間配分は?
ゆるいコーナーですが、お題は真面目です。ただ、こちらのコーナーの内容に関しては、ここでは説明しません。
ではいつ説明するかというと、1次試験終了後にインタビューリレーとして取り上げます。
先日のセミナーでは、それぞれ3~4人ずつの回答でしたが、インタビューリレーでは12人全員の回答を掲載します。

上記のお題以外にも「トータルで事例いくつ解いた?」「模試受けた?」「手ごたえあった?」「テキストは何をどう使ってた?」などなど。
王道の回答もあれば、奇行種的な回答もあり、12人それぞれバラエティーに富んでいます。お楽しみに。
懇親会でのQ&Aまとめ
セミナー後の懇親会では5人前後のブレイクアウトルームに分かれて、受験生からいろいろとご質問を頂きました。
以下に道場メンバーの回答とともに掲載します。(セリフの口調がごちゃごちゃ統一していなくてすみません)
2次試験全般
-
勉強会は有効ですか?
-
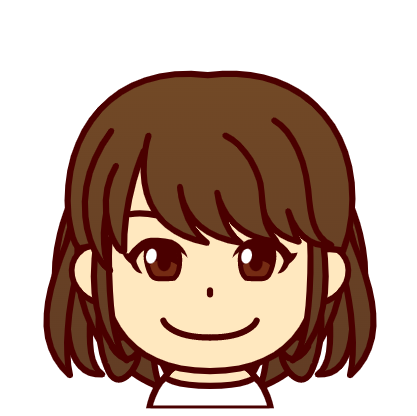 りいあ
りいあ私は1回しか参加しなかったが、そこで客観的な目線で自分の解答を評価してもらい、とても参考になった。
それまで「ふぞろい」のキーワード盛り込みでデキた気になっていたが、勉強会に参加してから考え方が変わった。
具体的には道場の勉強会(1回だけ)だが、そこで厳しい指摘をもらい、他人の視点を入れることで、大きく伸びることができた。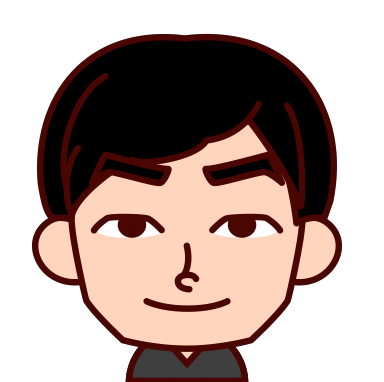 hotman
hotman有効だと思います。「ココスタ」がおすすめです。
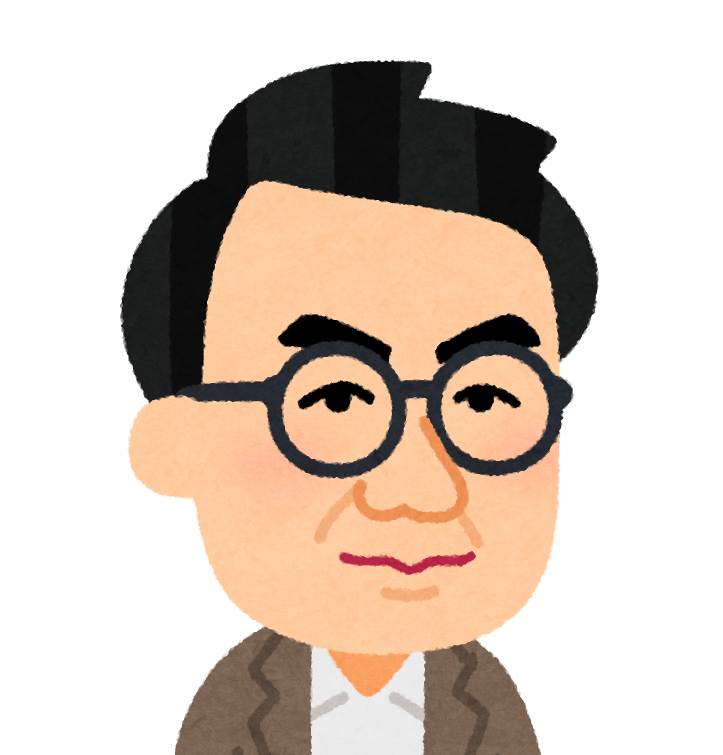 初代JC
初代JC元々TACの勉強会のメンバー4人が一発合格道場を創設しました。
当時、100人のクラスでストレート合格したのはこの4人だけでした。
勉強会はおすすめです。
-
勉強のやり方はどういうふうに確立していったのか?
-
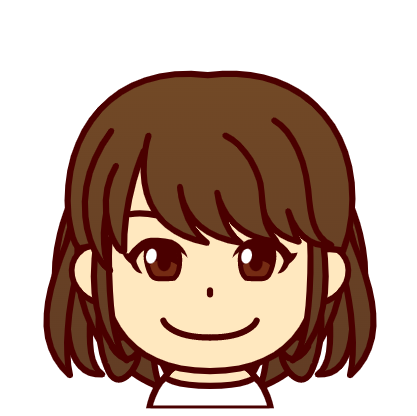 りいあ
りいあやり方をすぐに変えながら確立した。まずはブログ等で情報収集し、人が勧めるもので自分が良いなと思ったことは全部取り入れた。その上で、違うと思ったらすぐ方向転換する。(例えば、イケカコは買ったけど、自分のレベルと事例Ⅰ~Ⅳの傾向から、やらない判断、など)
-
自己採点では手ごたえがわからない、受かるという手ごたえはどう感じたか?
-
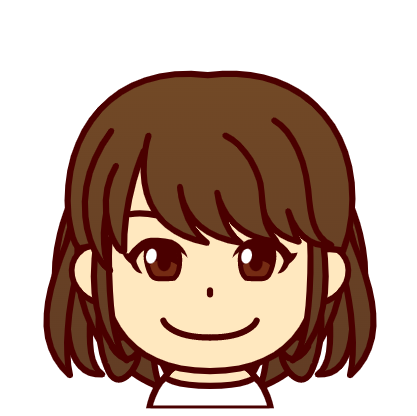 りいあ
りいあ勉強会で他人の指摘を受けた意味がわかってしっくりきたとき、受かるという手ごたえを感じた。
また、勉強会で他人の答案と並べて話をしたとき、(ここまでの伸びの速度も含め)あと残り時間で上位20パーセントに入るか?と考えると、受かるのでは、と感じた。
-
過去問を何度も解いて覚えてしまいす。
-
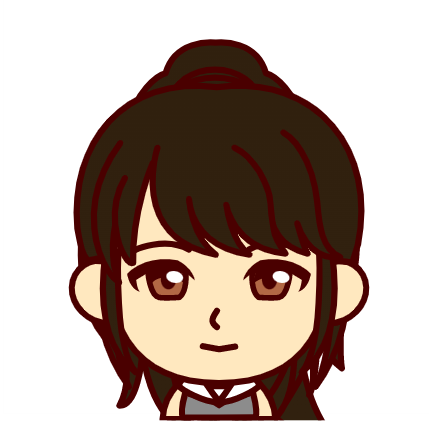 まよ
まよ直近の1年分は手を付けないようにしていた。
初見の問題に不安があるのであれば、模試を受けて対応できるか確認するとよいのでは。
事例Ⅰ~Ⅲ共通
-
合格に繋がった勉強法は?
-
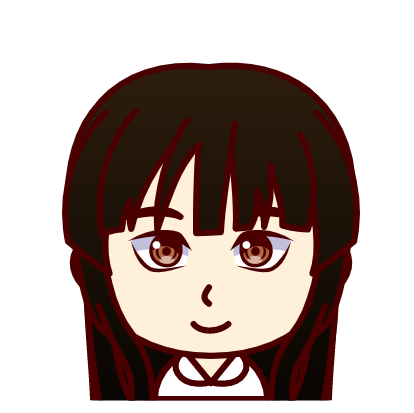 まん
まん設問解釈をしっかりやったこと。設問解釈の時点で解答の方向性を作っておくこと。
(「理由は○○」とか「○○(誰)に○○(何を)し、○○(どのように)すること。それにより○○(効果)」と、いったように)
-
設問と与件文の対応付けがうまくできない。マーカーの使い方とかが悪いのかな?
-
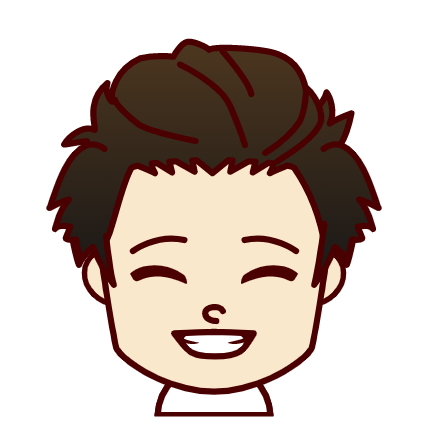 にに
にに設問文を読んだ段階である程度解答を想定できるようになると良い。それを与件文に探しに行けば、対応付けられる。
そのために、1次知識の定着と2次試験の設問に慣れることが必要では。マーカーの使い方は本質ではない。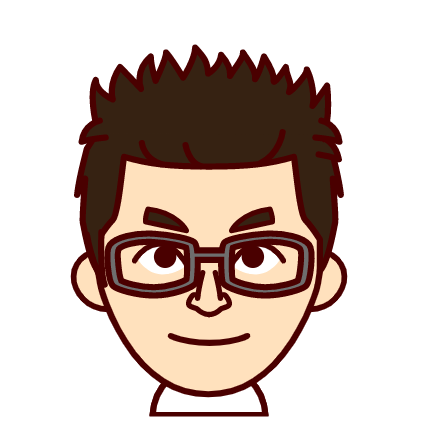 さろ
さろ与件文を設問で余すことなく使うことを意識した。段落番号を振っておき、それを設問ごとに割り振った。使われていない段落があれば、どこかの設問で使うはずと思って、その段落を中心に読み直していた。
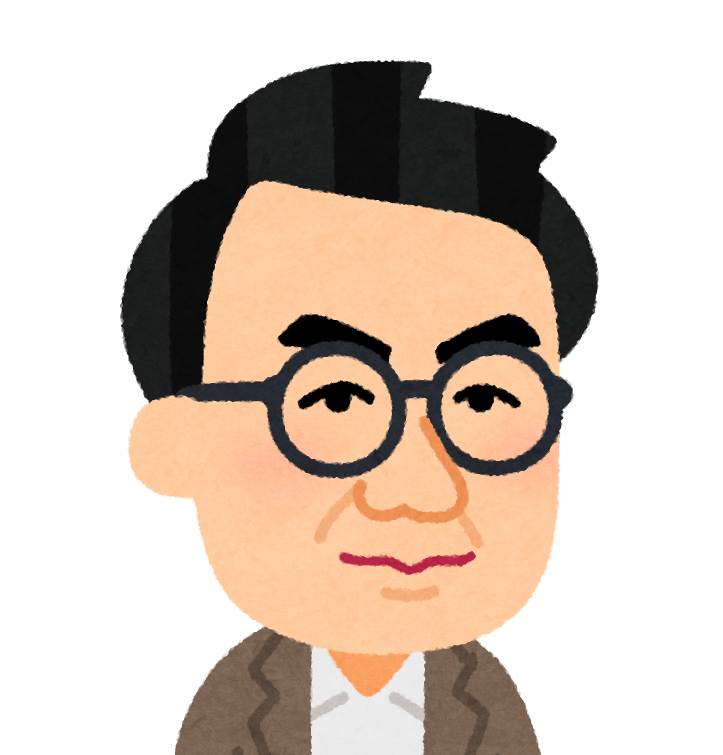 初代JC
初代JC設問文の解釈に時間をかけたほうがよい。与件文を読む前に設問を頭に叩き込むことで、与件文を読みながら設問を結び付けられるようになる。
-
解答骨子を作ったか?
-
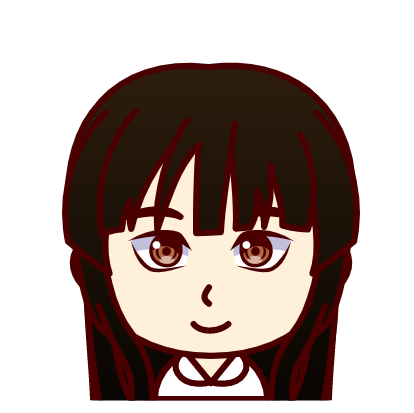 まん
まん作った。解答用紙に書くくらいのレベルの文章型の骨子を作っていた。ただし、時間が無くなるので、1事例の中ですべての設問の骨子が作れたわけではない。
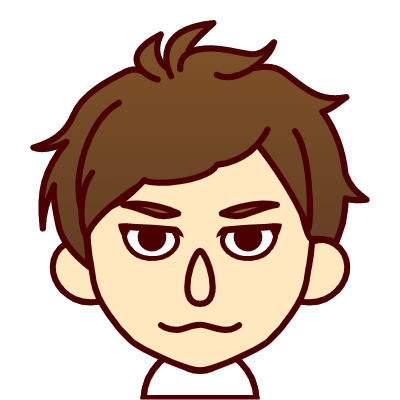 くま
くま作った。文章ではなくキーワードを書いていく形の骨子を作っていた。
-
分からない問題の取り組み方(令和3年度 事例Ⅰ第4問や事例Ⅱ第3問など)
-
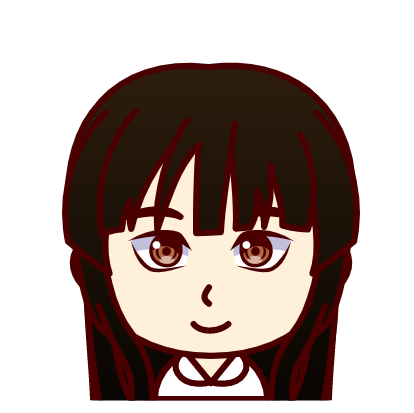 まん
まん解く順番としては一番最後に解く。与件文に書いていることを意識しつつも、どうしても浮かばない時は一般知識で書いていた。
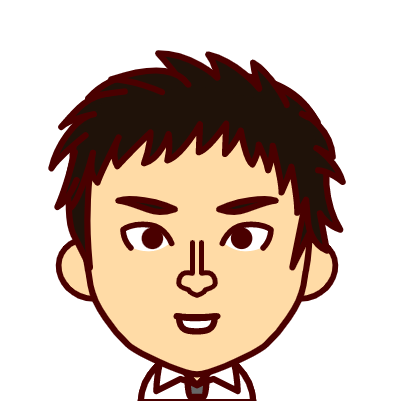 あらきち
あらきち当日どうしてもわからない問題が出た際には、パニックにならずに与件文と設問文に冷静に立ち返るというルール作りをしていたため、再度読み返し、関連する知識をもとに与件と結び付けてなんとか仕上げた。
-
SWOTの問題はいつ解く?
-
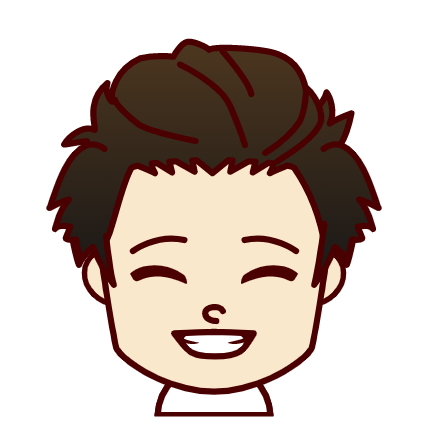 にに
にに最初に与件文読んだ段階で解答候補を拾っておいて、他の設問に行く。他を全部書いた後、解答の流れに合わせて取捨選択して最後に解答。
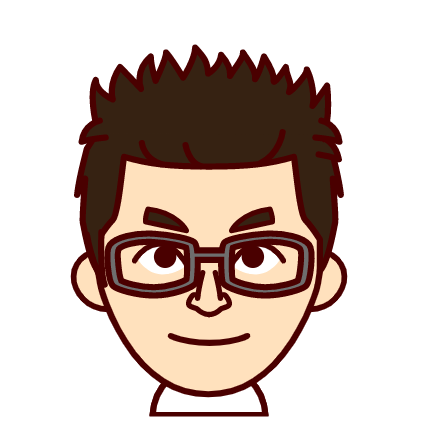 さろ
さろ最初に解く。設問1から解くことにしていたから。簡単だから、最初に確実に点を取っておく。
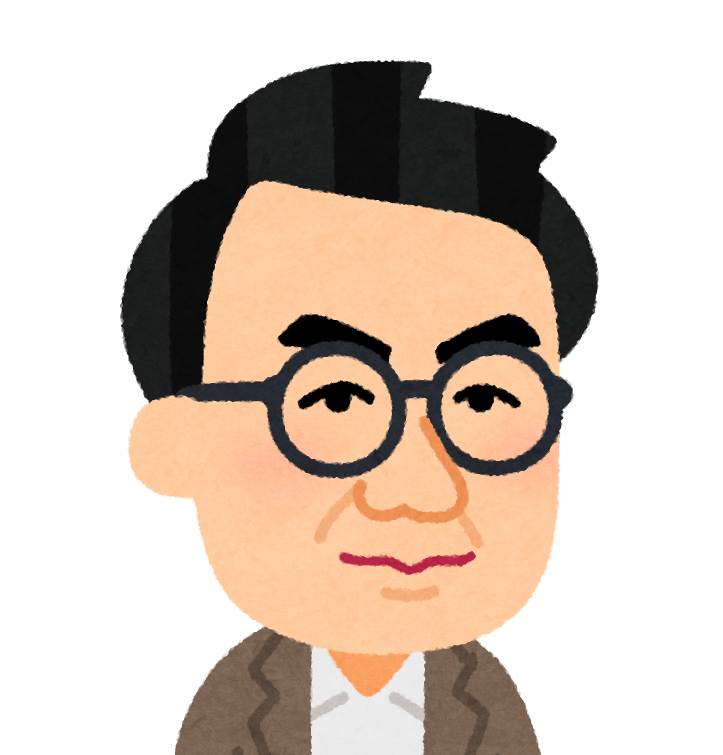 初代JC
初代JC人ぞれぞれの型を構築して、それを突き詰めればよい。
事例Ⅰ
-
事例Ⅰでどうしたら人事担当になりきれるのか?どうしてもマーケティングを考えてしまう。
-
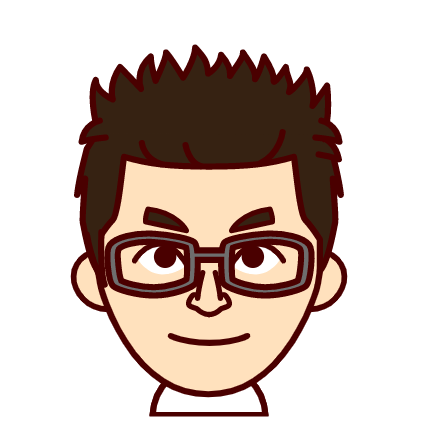 さろ
さろ私自身が事例Ⅰでマーケティング的な施策を回答し失敗した。試験が始まったらすぐに茶化などのフレームワークを書いておくことがまず一つの予防策。事例Ⅰは最初の試験なので、余裕がないと思うが、マーケティング寄りになっていないか、リットのように振り返る余裕があるとよい。
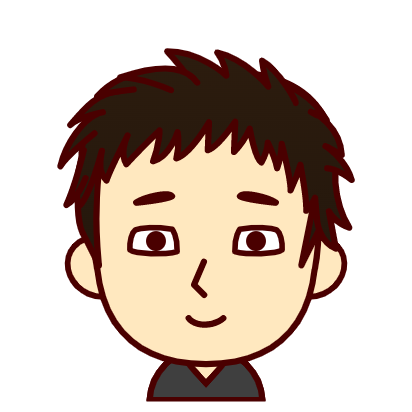 どらごん
どらごん試験が始まったらすぐ問題文の上に「人事・組織」と割と大きな文字で書いた。試験中「ああ、俺はいま人事・組織の問題を解いているのだ」と意識を高めた。
事例Ⅱ
-
令和3年度 事例Ⅱの置き配の問題で「どのように」と聞かれて何と書いて良いのか全く分からず手が出なかった。
-
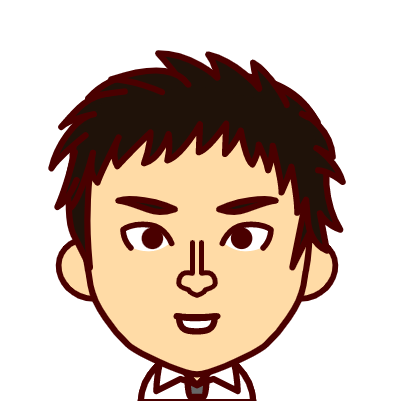 あらきち
あらきちしっかりダナドコフレームに当てはめて、高齢者にむけて⇒〇〇を⇒〇〇して⇒〇〇となる」といった手順で考えたらいいと思う。
標的顧客は何を望んでいるのか?という視点で考えた。置き配の問題では「それを利用する高齢者顧客に対して」の取組であったため、高齢者のニーズを与件から考えた際に、IMが敬遠されたことや商品説明の重要性が書かれていたため、新しい取組である置き配に関しても受け入れてもらえるように説明するための顧客向けツール(チラシ)を整備すると書いた。同じく、従来のやり取りは「来店前の電話での通話が主体」と書かれていたため、「訪問前に電話で置き配してよいか確認する」と書いた。
事例Ⅲ
-
事例Ⅲの点数が安定しません。何かメソッドはありますか?
-
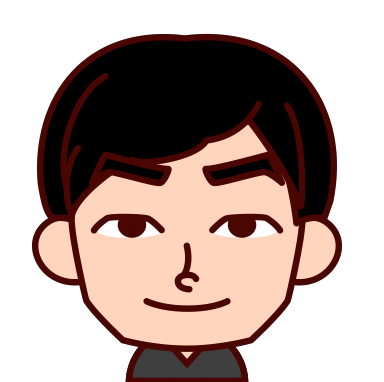 hotman
hotman「げもたこ」のフレームワークを使っていました。
げ→原因
も→問題(課題の場合もある)
た→対応
こ→効果
当たり前のことが出来ていないC社は何か問題があります。その問題を原因とセットで記載してそれに対する対応を書いて、最終的にどのような効果が得られるかを記載すると点数が安定します(少なくとも因果が崩壊することはありません)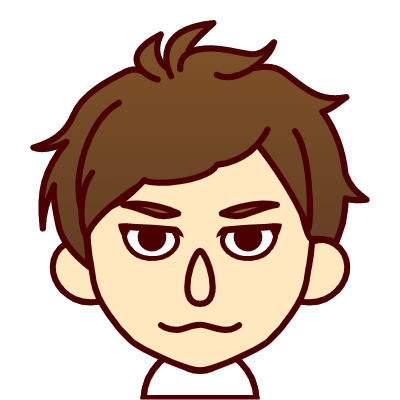 くま
くまC社は当たり前のことが出来ていないので、その出来ていないことを正してくださいと回答していました。
-
事例Ⅲが苦手。コツを教えてほしい。
-
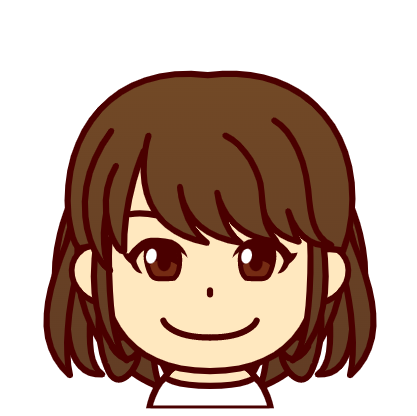 りいあ
りいあ事例Ⅲは、他の事例に比べても事例研究の意味が重いと思う。(事例・設問のパターンがある。)
私は、道場ブログをはじめ、色んなブログを調べまくり、事例Ⅲの特徴をまとめて一覧にし、FPとしていた。
道場では、13代目はこれから2次試験に向けてたくさん2次向け記事を書く。先代でいうとアヤカさんが書いた事例Ⅲの記事をよく読んだ。
事例Ⅳ
-
手ごたえ、得点戦略、単位は書いた?解答欄の書き方は?
-
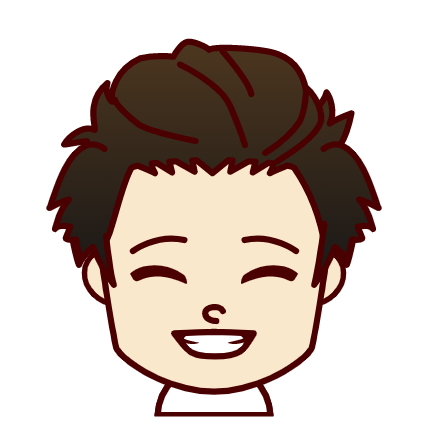 にに
にに数字があっていなくても部分点をもらうため、めっちゃ書いた。「自分はこの問題を解くのに必要な要素を理解していますよ」と採点者に伝えるために書いた。結果的に、計算が合っていなくてもどうやら点数はもらえるようだ。
手ごたえは、「部分点で半分くらいは取れているかな」くらい。
単位は、1行目に「以下、単位は百万円とする」とか書いてあとは数字だけで書いていた。
-
事例Ⅳの戦略は?
-
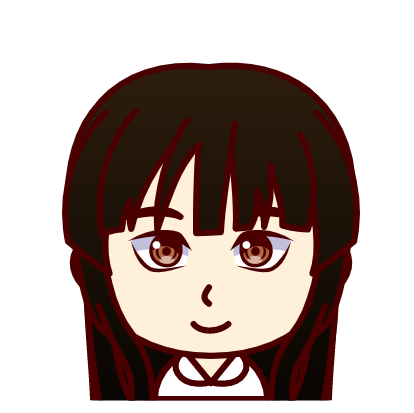 まん
まんCVPは頭真っ白になった。逆算して解くやりかたでしのいだ。何でもいいからとにかく分かっていることを書く(CVPの公式や減価償却費の計算だけでも)。パニックになったときの対応をあらかじめ考えておくこと。
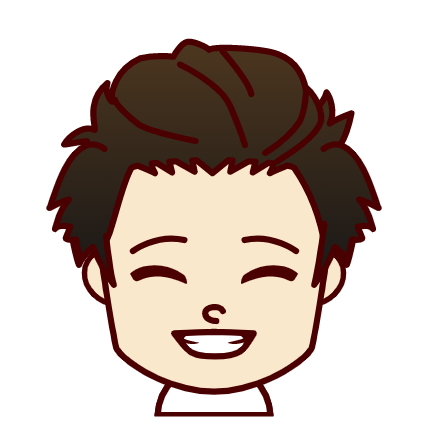 にに
にに計算結果はあっていなかったけど部分点狙いで解答書いた。採点者にわかるように書くことが重要。
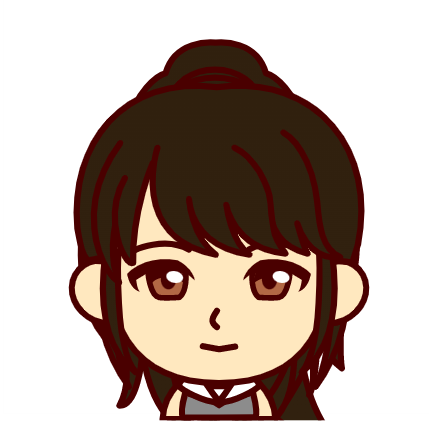 まよ
まよ文字が小さくてもいいから計算過程を全部書くこと。(こんちゃんのアドバイス:どこで加点されているかわからないため)
単位は全部書いていた。(その数字は何を示しているかわからないため)
NPVも減価償却だけは最低限書くようにしていた。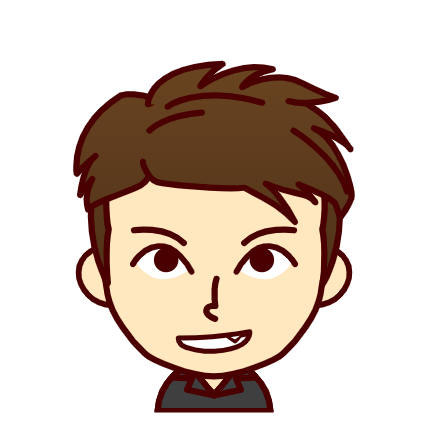 なお
なお取るべき設問の「経営分析」「最終の文章題」「CVP・NPVの(1)」と捨て問題をしっかり見極めること。そして部分点を狙うことがとっても重要です。
-
事例Ⅳの問題を解く順番は?
-
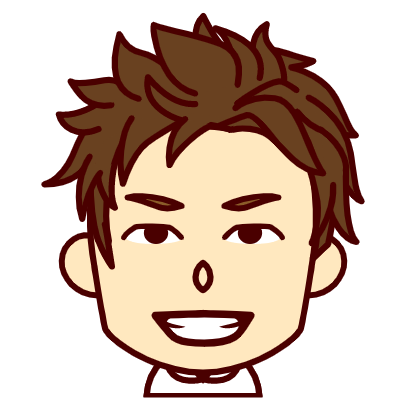 YOSHIHIKO
YOSHIHIKO経営分析→文章問題→CVP→NPVの順に解いた。事例Ⅳの方がリスクが高いと思って、事例Ⅰ~Ⅲを重視していた。当日はCVP・NPVが全然わからなかったから、部分点狙いで解答を書いた。
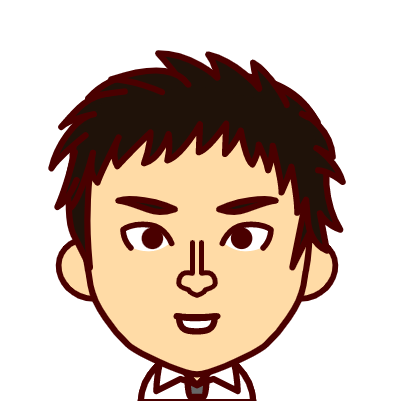 あらきち
あらきち解き方の順番で、NPVは普段冷静に家で解くと結構できるが、本番の緊張感の中で真正面から挑むとリスク高いため、簡単な⑴を解いた後は難問と判断した⑵⑶は後回しにしてCVPの計算チェックをしていた。
-
事例Ⅳの全知全ノウの手持ちが2020年度版だが、最新版は買った方がいいか?
-
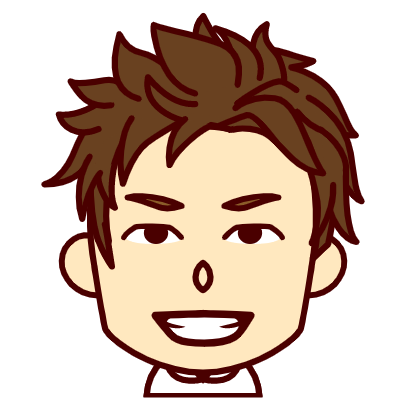 YOSHIHIKO
YOSHIHIKO買わなくて後悔するなら買う。
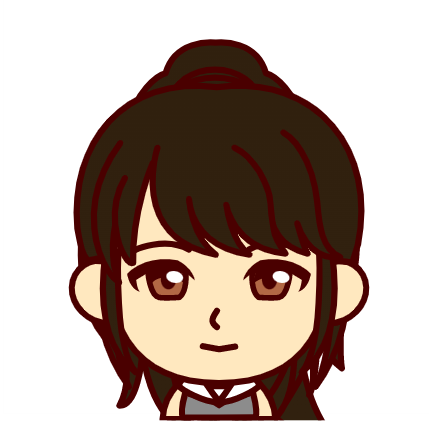 まよ
まよ直近の年(令和3年度)は反映されていないから、買わなくてもいいかも。
-
NPVが苦手です
-
 12代目と~し
12代目と~しまずはこちらの記事で基礎的知識を習得してください。
先日のセミナーの懇親会には12代目と~しさんにもご参加頂きました。ありがとうございます。
私は12代目の記事で勉強させて頂いた世代。まだまだその背中を追いかけています。
その他
-
モチベーション維持の方法は?
-
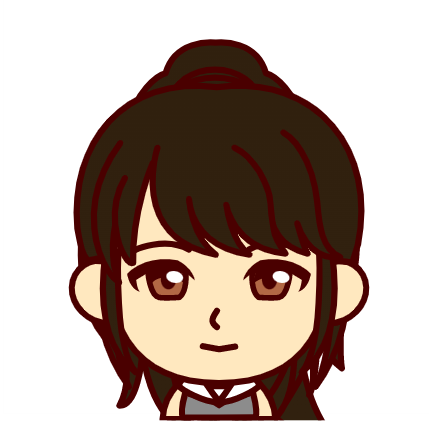 まよ
まよ出産育児で本当に時間が確保できなくなったら、一分たりとも無駄にしたくないと思うようになった。どんな短い隙間時間も活用するようになった。勉強会の予定を詰め込むなど、勉強せざるを得ない状況をつくり込むとよいのではないか。
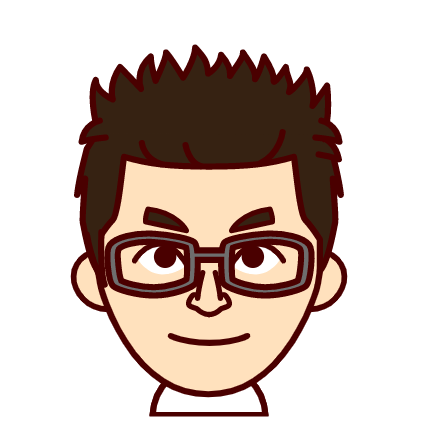 さろ
さろ周囲に診断士試験の受験を宣言して引くに引けない状況を作る。また、周りに宣言することで、意思決定会計などの相談を周りから受けるようになって、勉強した成果を実感できる機会にもなった。日々の習慣を変えてみるのが良い。
-
中小企業診断士を取ったメリットは?
-
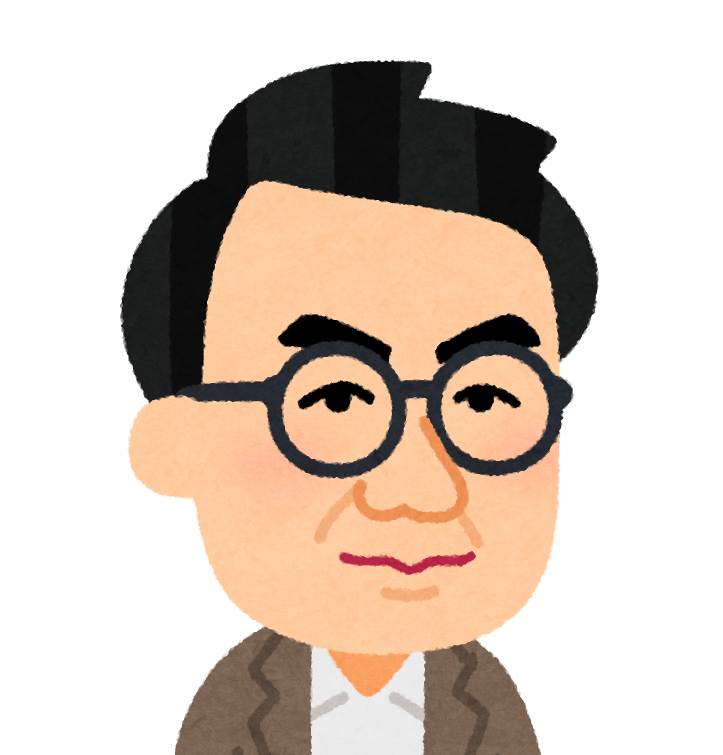 初代JC
初代JC再雇用されるより稼げそうなので、定年前に独立しました。自分から動いて何かやるにはとても強い資格です。せっかく取ったのに何もやらない人も大勢いるけど。そして、診断士を取得したことで人とのつながりができたことが大きなメリットです。
以上、いかがでしたでしょうか。最後はJCさんに締めてもらいました。
懇親会ということで(人によってはお酒を飲みながら)、ざっくばらんに話していたのでもしかしたら掲載に漏れがあったかもしれません。
もし上記にない質問があればお気軽にコメントください。答えられる範囲で誰かが答えてくれます。
明日はまよです。お楽しみに。
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)

-300x169.jpg)
