【合格体験記】受験校で基本を学んだ後は勉強会で合格!ヤマフリさん
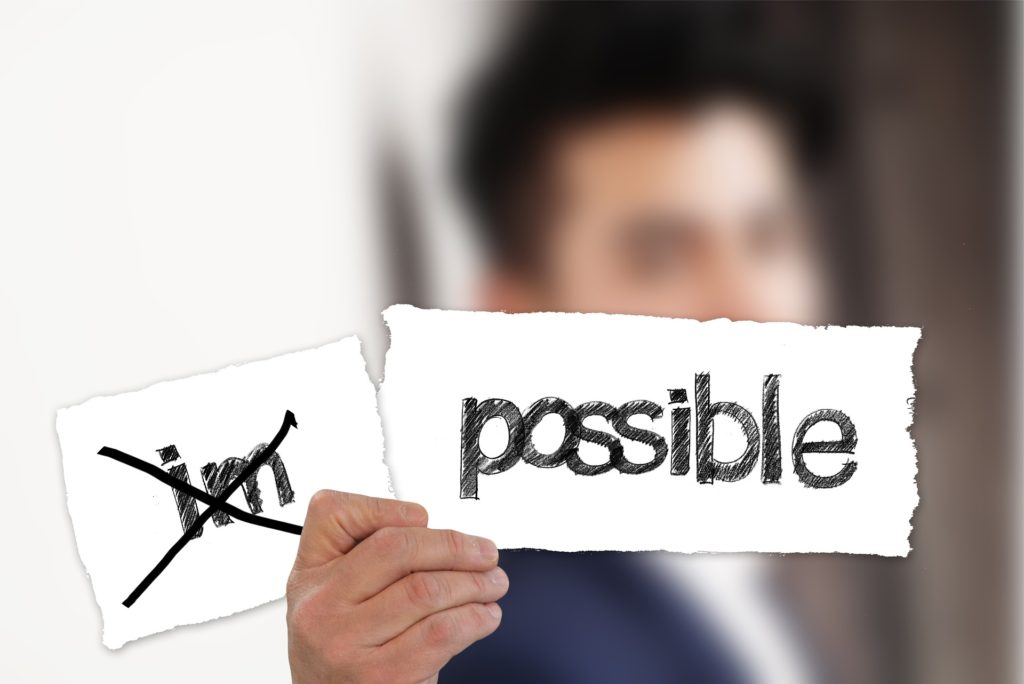

こんにちは。 と~しです。
本日3本目は、受験校で基本を学んだ後は勉強会で合格されたヤマフリさんです。
合格体験記をお送りいただきありがとうございます。
体験記の中には、勉強を進める上でのヒントでいっぱいです。
昨日、一昨日に引き続き本日も3名を紹介させていただきますので、
ぜひ読んで参考にしていただけたらと思います。
それでは、本編をどうぞ↓
contents
受験生情報
ハンドルネーム:ヤマフリ
年齢:50代半ば
性別:男
住まい:静岡県
職業:外郭団体事務
自分の診断士受験スタイルを一言で表すと
受験校で基本を学んだ後は勉強会参加
診断士に挑戦した理由・きっかけ
仕事上、中小企業事業主、個人商店店主の方とお話することが多いのですが、大多数が利益の低下に悩んでいます。
当時の自分は話を聴くことしかできませんでしたが、より積極的に支援することはできないかと調べた結果、
中小企業診断士取得を目指すに至りました。
学習開始時の知識・保有資格、得意科目・不得意科目
保有資格
診断士勉強前:特になし
診断士勉強後:情報セキュリティマネジメント、応用情報技術者
得意科目
「運営管理」「経済学・経済政策」※ 得意というか好き
不得意科目
「財務会計」「経営法務」※ 情報も苦手意識が強く、免除狙いで応用情報技術者を取得しました。
学習スタイルとそのメリットデメリット
学習スタイル
2011年~2013年 TAC本科生
2013年 2次筆記試験不合格後、勉強会に参加
2014年~2015年 勉強会
2016年 勉強会20%、独学80%
2017年~2019年 独学
2020年 TAC本科生+勉強会
2021年 勉強会
メリット
【資格校】
① ベースがゼロでもある程度の水準までレベルアップさせてくれる。
② 授業についていけば、比較的短期間で科目の概要を習得できる。
【勉強会】
① 志を同じくする仲間との勉強なので、モチベーションが維持しやすい。
② 自分では気づきにくい弱点は仲間からアドバイスしてもらえる。
【独学】
計画性があり自分を律して進めることができる方には向いている
デメリット
【資格校】
① 地方在住がゆえに通学に時間がかかる。
② 受講料がかかる。
【勉強会】
① カリキュラムはメンバー内での話し合いなので、自分がしたい勉強法が採用されない可能性がある。
② 複数年いると先輩呼ばわりされ居心地が悪くなる。
【独学】
私のような怠け癖のある方には向いていないと思います。
合格までの受験回数、学習時間とその作り方
受験回数
1次 10回、2次 6回
学習時間
合格前の1年間 1次30時間、2次600時間
(1月~8月)
勉強会8時間×33回
平日週5時間×36週
(9月~10月)
週20時間×8週
一人の職場なので、仕事の合間に時間を捻出。繁忙期には就業時間後に事務所に残って勉強していました。
合格までの学習法
週末の勉強会に参加するための下準備にそこそこ時間をかける必要があり、平日はそれに充てていました。
【1~5月】
設問分解シート(設問タイプ、問われている事、制約条件、時制、レイヤ、詳細レイヤ、使用する1次知識、
切り口、他設問とのつながり、根拠となる与件段落、回答骨子に設問を分解するもの)と回答を作成し、
それぞれについて議論しました。
事例Ⅰ~Ⅲにつき、令和2年度から平成23年度までさかのぼりつつ進めました。
加えて毎週夕方からは事例Ⅳは全知識&全ノウハウの決められた範囲について解いたものを事前共有し、勉強会当日説明しあう。
初見問題対策として4週に一回は「企業診断」の事例問題のその場解きを実施、設問から回答に至る議論をしていました。
【6月~8月】
事例Ⅰ~Ⅲにつき、令和2年から平成29年まで実際に事例を解いた際に与件文に書き込んだメモ書きを共有し、
そこから回答に至ったプロセスを説明しつつ、加点に繋がるセンテンスやキーワードについて議論しました。
事例Ⅳについては全知識&全ノウハウからイケカコに問題集を変え、継続しました。
4週に一回の「企業診断」問題対策は継続しました。
1次試験前の1か月は、企業経営理論と運営管理、財務会計の過去問(テキストインプットと過去問3年分)に取組みました。
これは1次試験の科目合格することが目的ではなく、2次試験に強く関係する3科目の知識がどれだけ身についているかを知り、
苦手分野の克服を目的としたものです。
【9月~10月】
個人的な課題の克服に取り組むため、勉強会に一区切りつけて過去問を1日2事例+翌日にふぞろいによる採点と振り返り、
合間に勉強会OBによるセミナー聴講、全知識&全ノウハウの2回転目に取り組みました。
合間時間にはyoutubeの事例に関する知識を聞き流す動画閲覧を繰り返し、基本的なことを耳で覚えるよう心がけていました。
学習時・受験時のエピソード及びこれから合格を目指す方へのアドバイス
>学習時・受験時のエピソード:
2016年度、保険のための1次試験を受けるのをやめ、退路を断って挑んだ4回目の2次筆記試験でしたが不合格でした。。
12月にその結果を知った後「もう1次試験は知識もコツも身についているんだ」と今思えば大きな勘違いをし、1次試験を軽く考え、その後2017年度~2019年度までの3年間、数科目の科目合格のみで2次筆記試験の受験資格を得ることができませんでした。
当時長い受験生活の中で最もモチベーションが下がっており、本気で資格取得を諦めることを考えました。
しかし、そこからもう一度初心に戻って取り組むことを決意したのは、今までかけたコストを埋没させたくはなかったからです。お金だけなら諦めはついたかもしれませんが、受かると信じて応援してくれた家族の気持ちや、勉強会でつながった仲間や受験を通じてお付き合いさせていただいた先輩診断士のみなさんからかけていただいた言葉、そういったものまで埋没させるわけにはいかないと思ったからです。
>これから合格を目指す方へのアドバイス:
(自分の課題に取り組む)
合格するために自分に何が足りないのか、自分ではなかなか気づくことができないかもしれません。私の場合、「お前の回答には知識が足りていない(拾ってくる根拠は間違っていない)」「回答の内容は間違っていないが、自分の言葉なので伝わりにくい」と先輩診断士から指摘されたことで、知識の習得を第一に取り組みました。それに加え、勉強会においてTBCの具体→抽象→具体の考え方を重視したことも功を奏したのかもしれません。設問文の具体的内容から知識や定義などへ抽象化し、与件文からヒントを拾い再び具体的な回答に変換する作業を行うためには、途中の知識が不足していたり、あいまいではうまく機能しません。勉強会では「この問いを回答するのに必要な知識」を常に意識していました。ぜひ自分の弱点を早めに見つけて対処してください。
(回答プロセスを作る)
80分間の回答プロセスを自分なりに試行錯誤し、2ヵ月前には最適なプロセスを確立する事です。80分の時間の使い方、設問文をどのように分解するのか、メモ書きはどのようにするのか、与件文には何を書き込むのか等々決めておくことを勧めます。
合格年から、今まで破らなかった問題用紙を破り、与件文のすぐ横に設問文を置き、問われていることを常に意識するようにしました。こういったルーティンは最大限に動揺や焦りを抑制する効果があると思います。
多くの合格された方が言う「開眼した」という感覚を私は得ることができませんでした。自分の変化に気づくことなく、落ち着きはありましたが、自信はなく試験当日を迎えました。だけど、結果として努力は裏切らなかったのかなと思います。
一発合格道場のみなさん、特に未合格体験記の執筆を勧めてくれた4代目のみなさん、私の未熟な投稿に真摯にコメントしてくださった先輩診断士のメンバーのみなさん、ようやく「次は合格体験記を寄稿します」の約束を果たせて感無量です。
これからもよろしくお願いいたします。
=====ここまで=====
いかがでしたでしょうか?
繁忙時は、職場に残ってそのまま勉強するという逆転の発想や、
勉強会などで、自分の課題を明確化して常に意識するというのは、
勉強の中で取り入れられそうな秘訣ですね。
目指すきっかけとなった中小企業事業主、個人商店店主の方々を支援すること、
取得した資格を活かしてされていきそうですね。

ヤマフリさん合格おめでとうございます!
12代目一同、ますますの活躍を応援しています。
合格・不合格問わず受験体験記、本日まで募集中!
一発合格道場の強みは「積み重ねられた数多くの体験記」です。
道場をつくるのは、あなたの体験記。あなたの貴重な経験が多くの人たちのために役立ちます。
ぜひ、体験記をおよせください。
公開先はこちらです
募集要項
- 対 象:2021年度2次試験合格者および筆記試験受験者(未合格者)
※年齢・受験年数・学習スタイル等一切不問 - 原稿量:自由。目安として2,000字(原稿用紙5枚)程度
- ファイル形式:Word(.docxまたは.doc)
- ファイル題名:合格体験記(ハンドルネーム).docx (例:合格体験記(道場くん).docx)
- 特典:「一発合格道場」ブログ上で随時公開。
- 期限:2022年2月5日(土)
- 応募方法:Googleフォームにて募集(以下のボタンより)
- 問い合わせ:shindanshi.dojyo12@gmail.com
※当ブログ運営趣旨に反しない限り、原則応募全員分を公開。
※ご提出いただいた原稿の著作権は、当「一発合格道場」に帰すものとします。
 合格体験記テンプレ
合格体験記テンプレ
- 受験生情報|ハンドルネーム・年代
- お住まい |都道府県
- 自分の診断士受験スタイルを一言で表すと(40字目安)
- 診断士に挑戦した理由・きっかけ
- 職務経験・保有資格
- 得意科目・不得意科目
①1次
②2次 - 学習スタイルとそのメリット・デメリット
①独学、通信、○○(予備校)通学
②メリット
③デメリット - 合格までの受験回数、学習時間とその作り方
①合計の学習期間(〇年〇か月)
②受験回数(1次試験〇回、2次試験〇回)
③1次学習時間
④2次学習時間 - 合格までの学習法
①1次
②2次
③再現答案の作成有無 - 学習時・受験時のエピソード及びこれから合格を目指す方へのアドバイス
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)


