3倍!!美味しい学び:目指せ運営管理マスター byと~し

🌸🌸🌸🌸一発合格道場!オンライン春セミナー2021のご案内🌸🌸🌸🌸
3月23日をもって受付を終了いたしました。
おかげさまでセミナーの部満員御礼です!!多数のお申込みありがとうございました。
4月10日(土) 15:00-17:40(1部2部)
・第1部 15:00-16:15<1次試験対策+相談会>
・第2部 16:30-17:40<2次試験対策+相談会>
・第3部 17:50-18:50<懇親会>
Web会議アプリ「zoom」を活用したオンライン開催!
一次試験・二次試験の学習ノウハウやzoomのブレイクアウトルームを活用した小グループ単位でのディスカッションで相互交流を図るセミナーです!
第3部では先代をゲストに迎えたオンライン懇親会を開催します。
道場メンバーや受験生同士で交流を深めて頂き、合格に向けモチベーションを高めて頂きたいです。
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
年度も変わろうとする今日この頃。
皆さんはいかがお過ごしでしょうか?
桜の花も津々浦々ほころび始めた今日この頃。
宴会自粛で立ち止まらない花見が推奨され、
何だか風情にかけるなぁと、思っていました。
しかし、一説では花見は歩きながらが起源という説があります。
桜を見に集った人が行き交い、地面を踏み固め強固にする。
だから土手には桜が埋まっているそうです。
(土手を踏み固めてもらって、堤防を強固にする)
そう考えると、新型肺炎による制限でなく、
時を経て、祖先と同じ花見の様式を味わえるのではないか?と、
散歩がてらの花見を嗜んでみようと思っています。
宴会を自粛する分、少し遠くの桜並木や和菓子屋さんに足を運び、
団子など春の味わいを自宅で頬張ろうと考えています。
受験生にとっても、宴会よりも散歩でサクッと終わる花見は、
勉強時間の確保に一役買ってくれるかもしれませんね。
さぁ今日は、作業服の日(さ(3)ぎょうふ(2)く(9))
メーカー勤務、食いしん坊のと~しが、
診断士試験で運営管理を学ぶコツと効果を、
美味しい飲食の事例と絡めてお届けします。
記事のココだけPoint
・言葉の奥の□□□を理解する→2.1
・JIT=ジュっと□□戦い →2.2
・全てが学びの□□□□ →2.3
1.運営管理のススメ:お得な科目
1.1.得点がお得
1.2.効率がお得
1.3.応用がお得
2.実社会から見えてくる、運営管理
2.1.ECRS:隣の企業を覗いてみれば…
2.2.トヨタ生産方式:串屋を覗いてみれば…
2.3.店舗・販売管理:お店を覗いてみれば…
1.運営管理のススメ
運営管理は、好きですか?
「メーカー勤めでないから、イメージがわかない。」
「メーカー勤めで、仕事の事情と理論で混じってしまい好きでない。」
そんな声を聴くので、運営管理3つの美味しいポイントをお伝えします。
1.1.得点がお得
運営管理、特に生産管理は診断士試験においてお得科目です。
1次試験、2次試験のどちらにも関わるので、
1次試験から学んでいる人も、この科目で学んだことは、
2次試験の勉強にもつながっていきます。
ここまでなら企業経営理論、財務・会計と同様です。
しかし、運営管理の差別化point
重要なのは試験当日の時間割です。
1次試験、2次試験ともに、午後に待ち構えるということ。
つまり。。。
>1次試験:第4科目(1日目の最終科目)
昼食を食べ終えて、90分の企業経営理論を乗り越えて、
へとへとになりながら迎える90分の最終科目。
既に疲れているし、翌日2日目の科目も気になる。
>2次試験:事例Ⅲ(昼食後、初めの科目)
事例Ⅰ,Ⅱを終えて昼食を超えた後、
程よい疲労感と、満腹感が、
うとうと気分を誘います。
ここを得意科目とすることができれば。。
>1次試験
早期に解き終えて、90分の終了時間を待たずに早期退出して帰宅。
体力を存分に回復しながら、ちょっとした達成感と共に、
2日目の暗記3兄弟との戦いに向かえる。
>2次試験
得点の安定が難しい2次試験の中で、事例Ⅳに次いで安定させやすい。
ここでは得点できる。という自信を持って二次試験当日に挑める。
疲労×食後の状態でも安心して解き、最後の事例Ⅳに向かえる。
経済学や暗記3兄弟と違い、2次試験にも直結し一石二鳥。
1・2次試験の午後で安定得点源をつくる大黒柱。
診断士試験での得点の積み重ねにも役立つ、
それが運営管理です。
1.2.効率がお得
運営管理は、学習効果を上げるための所要時間が、
比較的に少なくて済むと、推測しています。
日本は自動車産業はじめ、ものづくりで発展してきたので、
自身がメーカーで勤務している人もいれば、
親族や友人など身の回りの人が務めていることがあったり、
学生時代の社会見学や、観光で工場見学に足を運ぶ人も多いかと思います。
ものづくりを工業と絞ると、二次産業になりますが
一次産業も工業化が進み、工場野菜など都心の屋内で管理しながら生産する形態があります。
三次産業も提供するものこそ無形かもしれませんが、
在庫管理や陳列方法、生産に関わる部分が出てくるはずです。
会社での仕事も、資本金・情報、私たちの労働力などの材料をもとに、
仕事の成果物を様々な過程(行程)を経て、作り上げていきます。
また、そもそも日常生活も工業的な側面を持っています。
例えばキッチンで調理をするのは、まさに工場のようです。
材料調達・仕入: 料理に必要な食材を事前に(出来るだけ鮮度良く)準備
複数の生産工程: 包丁で切る、フライパンで焼く・煮る、など
お客様への提供: 美味しく(品質)、安く(コスト)、手早く(納期)提供するか
自分の仕事や日常生活を生産活動と捉えて、
テキストや過去問での学びと関連付けていく。
そうして学びを積み上げていける。
日々の一つ一つの行動が学びのチャンスになる可能性を秘めている、
それが運営管理です。
1.3.応用がお得
日常の事例から学ぶことも出来るというのは、
一方で、学びを自身の生活に反映して応用するのも容易です。
運営管理で学んだことを試験に向けた単なる知識や理論に終始せず、
自分の仕事や日常生活にヨコテン(横展開)してみましょう。
例えば、在庫管理を以下の通り、
私は食材の調達に応用しています。
<定期発注>
発注期間:週1(土曜日)
→・勉強期間中も買い出しから毎日の調理までやっていましたが、
・いつ・どれだけ買うか?という日々の意思決定を介さず
・週1の在庫check・仕入(買物)に、作業を集約
・買ったまま忘れる賞味期限切れを解消
<定量発注>
ダブルビン方式を調味料(醤油やごま油)に採用し、以下の様に定義。
在庫量:1つ
発注点:在庫を開封して、ストックが0になった時
(その次の買い物で1つ購入)
↓
・在庫量や買物に無駄な意思決定を介さず、
・また在庫切れや、賞味期限切れを解消
中小企業を診断させていただく前に、
我が家の食卓を診断し、大幅改善するに至りました。
理論と紐づけているだけで、やっていることは単純。
・買物を週1に集約
・在庫がなくなったら、1個ずつ補充
それに定期発注・定量発注という「ラベル」が貼るイメージです。
工場の事例は縁遠くても、買い物の頻度や、
しょうゆの買い出しタイミングなら、誰もが自分のこととして想像できると思います。
日常生活にも応用できる、それが運営管理です。
得点・効率・応用と3つもお得がそろう、運営管理。
もっと学びたくなってきましたか?
2.実社会から見えてくる、運営管理
こんなに、お得な運営管理
学びを促進するには、TAKUROが経営法務で説明してくれたように、
具体化をするのが一つのコツです。
そして嬉しいことに、法務と違って甲さん・乙さんなんて出てきません。
先述の通り一歩足を運べば、身の回りに見えてくる具体例があります。
実際の会社はもちろん、
料理や、買い物の頻度、しょうゆの買い物タイミングなどです。
今回は、3つの例を順にみていきましょう。
2.1.ECRS:隣の企業を覗いてみれば…
「PQCDSME」、「4M(+I)」、「3S」、「5S」。。。
色々出てくるアルファベットで、
改善の法則「ECRS」もこんがらがる!
そう悩む前に、それぞれの意味を考えて、
具体例と紐づけてみましょう。
題材:毎朝の洋服選び
Eliminate(排除) なくせないか?
選択肢があるから迷う→選択肢をなくす・絞る
Appleの前社長Steve Jobsの様に「黒トップス・ジーンズ・スニーカー」と決めれば、
コーディネートの悩みおろか、選ぶことなく洋服が決まります。
Combine(結合) 何かと一緒に出来ないか?
選ぶ作業と一緒にする→歯磨きしながら服を選ぶ
「服を選択」という作業を単一でするのでなく、他の作業と組み合わせます。
例えば目や頭は自由になっている歯磨きをしながら、同時進行で服を選びます。
Rearrangement(交換) 作業の順番を変えれないか?
作業順の変更→朝でなくさかのぼって、前日に済ませておく
作業自体が無くせないなら、行う順番の変更を検討します。
タンスに向かっている、前日の寝る時や、洗濯後の収納時に選んでしまう。
選ぶためにタンスに向かう/開閉する、という前後の動作を他の作業と同期できます。
Simplify(簡素化) 簡単にできないか?
都度、その時に決めて・作業する→ルール化・簡素化する
上記工程を踏まえて出来上がった手順を「標準化」して、
自動的に実施する。この棚の上から順に着るなどルールを決め、従う。
この検討の順番が大事です。
E→C→R→Sというのは、省略効果の大きさ順です。
①Eliminate(排除)・・・100%cut
作業自体をなくす=0
②Combine(結合)・・・50%cut
何かと一緒にやる=1/2
③Rearrangement(交換)・・・25%cut
作業自体は残る、前後工程の省略≒1/4
④Simplify(簡素化)
上記3工程を踏まえた作業を、実施できるようにする
順番を間違えて、簡素化で標準化から入ると、
服を選び鏡の前に行って悩んで、また選び…
ムダな循環を定着したり、問題を拡大する恐れがあります。
まずは改善効果が大きい順に検討をする。
その上で、結果を定常作業化・定着するのがECRSです。
実際の企業を見てみると、以下のような活動があります。
・日東電工・ライフネット生命: 無減代 (無くす・減らす・代える)
・トヨタ自動車やグループ企業: やめかえ運動 (やめる・かえる・続ける)
文言こそ違えど、順番は省略効果の大きさで並んでいます。
言葉の奥の「考え方」を理解しておけば、ECRSの論点を理解できるだけでなく、
実際の企業で活用される改善活動の理解も深めることができます。
更には、もっと分かりやすい言葉を生み出して、
診断先の企業に定着する新たな仕組みを開発できるかもしれません。
2.2.トヨタ生産方式:串屋を覗いてみれば…
JIT(JustInTime):必要な時に必要な分だけ用意する
日本の代表的な生産方式。
こちらは、串屋さんをイメージしましょう

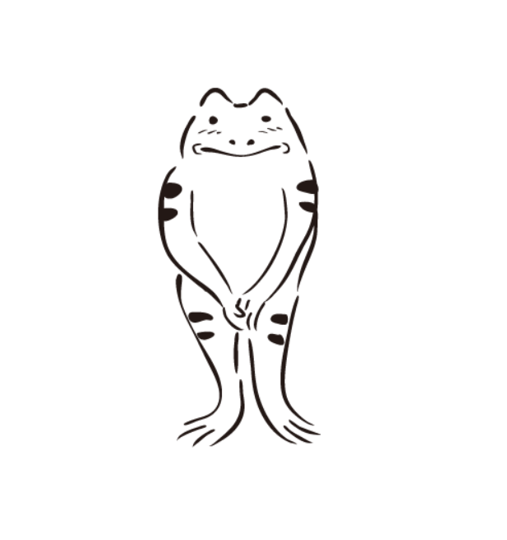
できたら焼きたてのものをカエ、買えるでしょうか。。
(同じ値段なら、焼きたてのものを買ってかえりたいな)
え、焼きたてが欲しいの?焼けるまで10分待ってもらうけど、いい?
(焼いてあるやつから買っていってほしいけど、仕方ねぇな)

焼きたての串をめぐる熱い戦い。
ハイ、このイメージで覚えましょう♪
JIT・・・「ジュっと」焼きたてちょうだい!
~供給~ 生産者(前工程)
・モモ焼き始めたから、一気にモモ焼いてしまいたい
・モモ・キモ・カワ・せせり…多品種に廃棄が出るのは避けたい
~需要~ 買い手(後工程)
・キモやカワを食べたいお客さんが来るかも?
・待たずにすぐに買いたいお客さんもいる
~回転率向上~
・全てオーダー以降に焼いていると、回転率が上がらない
→調理済を即座に買ってもらうことで、回転率を上げる
こんな想いがめぐる中で、必要とされる(需要)量を予測して、
適正な在庫を準備しておこうというのが、各種の仕組みです。
<プル方式>(後工程引き取り方式)
多くの飲食店に行った時をイメージしてください。
食べたいものを注文 → 調理される → 提供される
こちらが食べたい要望や、量と異なる料理を、
お店側から勝手に出されるお店って、嫌ですよね。。
後工程の人(顧客)が主導権をもって、必要なものを必要な分引き取る。
セルフサービスは、カウンターに商品を引き取りに行くので、
まさに「Pull」という言葉通りの動きですね。
<プッシュ方式>:参考
一方で、生産側が主導権をもって押し出していくのが「Push」型。
生産を集約して作業効率・生産性を高め、生産コストを低減したり、
在庫を持つことで、需要に応じて即座に提供することができます。
また店舗・販売管理の「ロングテール」の概念につながります。
取り敢えずそこに行けば何でも揃うという意識によって、
ネットショップや、ホームセンターの集客力につながっています。
飲食店ならスピードメニューや、時間を要する料理がこれにあたります。
一杯目のビールの横にお通しや、枝豆が一緒に出てこなかったり、
煮込み料理を、「〇時間」ください、なんて待たされたら、こんなお店は行きたくないですよね。。
すぐ出せるように事前に仕込んでおくこと、熱々の料理を提供することと別で必要です。
<かんばん>
スーパーで、残り少なくなってくると底の方に入っている注文の札や、
飲食店のバックヤードにある、発注の目印や札がかんばんです。
在庫量は減らしたいけれど、0になってから注文すると、
次に入荷するまで欲しいお客さんが来ても提供できない。
販売機会逸失の防止で、必要最低限は用意しておく。
どうしてもせせりが食べたいとき、
モモやササミを出されるのでなく、
やはり「せせり」が欲しいというのがお客さんのニーズです。
品ぞろえは供給の事情だけでなく、お客様(需要)に寄り添う必要があります。
これからは、トヨタ生産方式が出てきたら、
串やさんの場面をイメージしてください。
出来立てほかほかを食べたいお客さんと、
一気に効率的に作りたい職人さんの、せめぎ合い。
美食巡るジュっと熱い目的:JIT(Jusu In Time)
それを実現するための手段:プル方式・かんばん等
これらが織り成すハーモニーが、トヨタ生産方式です。
2.3.店舗・販売管理:お店を覗いてみれば…
店舗・販売管理は、外に出かけたら、
全てが学びのチャンスだと思って、紐づけていきましょう。
商品陳列や店舗立地/形態は、実際のお店が学ぶ宝庫です。
暗記が苦手だったので、一つ一つの用語を、
毎日の散歩やお買い物で、実店舗の現物で確認して覚えました。
<マグネット>
集客効果で客導線を長くするために、
広告の品など目玉商品は店舗奥に置いてお客さんを奥まで引き込む。
<カットケース陳列>
大量に仕入れて、そのまま陳列ができるように、
業務用スーパーなどではもちろん、スーパーの特売品でも多く活用。
一つの店舗を定点観測していくと、
ISM(InStore Murchandising):売り方や演出に気づく機会もあります。
<関連購買>
カレールーとともに具材(肉・野菜)の販売をしたり、
ワインの横に、チーズなどのつまみを陳列して、同時購入を見込む。
<衝動購買>
ノベルティ:商品におまけをつけて販売促進
→定番商品にマスコットやピンバッジ、文房具などおまけ付
サンプリング:商品のお試し
→新商品の試飲・試食
いつも同じように見えて、少しずつ変化をしている店舗。
購買の9割を非計画購買(事前に買うと決めていない)が占めるというのは、
こうした販売者の視点で見てみると、買いたく動機づけさせる仕掛けが見えます。。
売り方、「マーケティング」が浮かび上がってくると、
企業経営理論や事例Ⅱを具体例と共に学ぶチャンスかもしれません。
一つの店舗を定点観測することはもちろん、
複数店舗を横断して観察することもおススメです。
同じ要素を複数の店舗で横断して観察すると、見えるものがあります。
例えば、成城石井と最寄りスーパー、業務用スーパーで、
ゴールデンゾーン(手の届きやすい60~160㎝の領域)の比較をしてみてください。
共通点もあるかもしれませんが、異なる商品の陳列から、
今度は店舗の販売「戦略」が浮かび上がってきて、
企業経営理論や事例Ⅰを具体例と共に学ぶチャンスかもしれません。
今日のまとめ
・言葉の奥の考え方を理解する
・JIT=ジュっと熱い戦い
・全てが学びのチャンス
先日、ネットショッピングの誤発注で2kgのカレー粉が届きました。
育ち盛りの子がいるわけでもない、夫婦2人暮らしの我が家は、
途方に暮れていましたが。。。
のきが、「沼」作るといいよ笑と教えてくれました。
動画の人は、めちゃストイックでマッチョな人だし、
お世辞にも美味しさを想像できないビジュアル…
つくるのを躊躇しましたが、道場の合言葉
「パクってカスタマイズ」を、
思い出して挑戦してみました。。。
すると、想像以上に美味しい。
「やったことがないことを、やってみる」大切さを再認識しました。
出来/分からないのは、出来る/分かるまで今やっていないだけ。
これからやっていくことで、分かる・出来るに変えることができる。
つまりできない(≒やってこなかったこと)の中に、
今まで見落としていた原石が埋まっているかもしれません。
もし苦手な論点を見つけたら、
「よし、点数の伸び代を見つけた♪」と唱えてください。
自分の「穴」が明確になれば、それを埋めれば、
得点・診断士としての知見は、一つ階段を上がります。
年度も変わるので心機一転、一段と気を引き締めてまいりましょう。
あなたが決めて挑戦しているので、きっと大丈夫。
毎日、道場メンバーで届ける記事が、
少しでも学ぶ動機や、学んで得点につながる記事であれば幸いです。
明日は、ちょうど一年ぐらい前に勉強を始めたMa.satoの記事です。
合格まで短時間で駆け抜けた秘訣とは?お楽しみに。
☆☆☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたら
![]()
にほんブログ村
↑ぜひ、クリック(投票)お願いします!↑



具体化をするって、2次の事例Ⅲでも大事ですよね。
与件文の文言しか見ていないと、イメージができないまま状況を把握してしまいます。僕も与件文の文言ばかり追いかけていて、いつのまにかイメージができずに事例Ⅲを解いていました。
ECRSの適用も、納期遅延が生じていることも、単に与件文の文言だけ捉えて何の具体化もしていない(頭の中では無機質でシーンとしている製造現場のようになっている)のと、製造現場がごちゃごちゃになっていて納期が遅れて慌てている従業員や現場をイメージしながら与件文の内容を理解するのとでは、理解の質に大きな差が出てくると思います。
今回の記事がいい機会になりました。ありがとうございます。
サトシさん
コメントありがとうございます。
具体化は他科目や二次にも通ずると思います。
情景を思い浮かべることで、
ボトルネックや、一番困っていそうな工程が見えてくるかもしれません。
ぜひ、「パクってカスタマイズ」してみてくださいね。