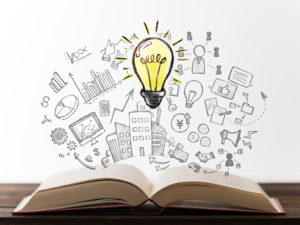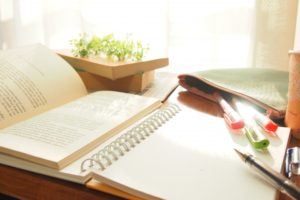【合格体験記】独学×大学生でも努力すればストレート合格できる! のりおさん
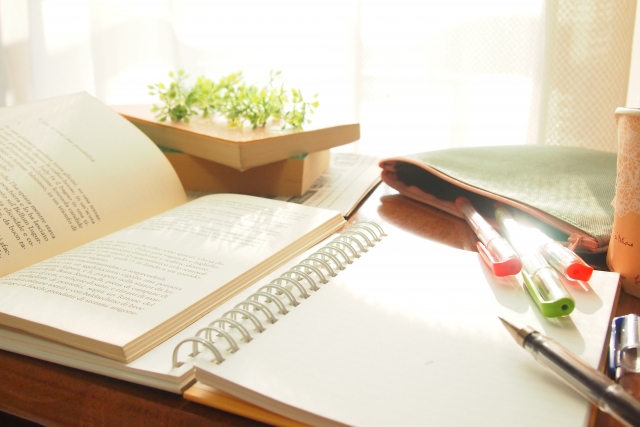
ロケットスタートセミナー @オンラインのお知らせ
【セミナー日】 2021年1月16日(土)午後予定
【募集開始日】 2021年1月5日(火)昼12時~
満員御礼となりましたこくちーずはこちら
令和2年2次試験合格者の方限定! 試験合格だけでは資格は得られない? ロケットスタートを切るにはどうしたら? 同期合格者の皆さんと繋がりたい! そんなモヤモヤをスッキリさせる 貴重な機会を活かして下さい
🚀★🚀★🚀★🚀★🚀★🚀★🚀★🚀
おはようございます! かーなです!
本日も張り切って皆様からお寄せ頂いた受験体験記をお届けします。
一人目は、のりおさんです。
のりおさんは現役大学生で、将来のキャリアを考えて診断士試験を受験されたという、かなりのしっかり者でいらっしゃいます。
それでは、どうぞ!
========ここから========
(0)受験生情報
はじめまして。「のりお」と申します。
現在、大学4年で来年からは大学院に進学し、機械関係の勉強・研究をする予定です。
2019年の4月から診断士ゼミナールと市販参考書で学習し、2020年度試験にて1次・2次試験合格しました。
私の合格体験記がお役に立てば幸いです。特に大学生で診断士を目指す人へ。
(1)自分の診断士受験スタイルを一言で表すと
きちんと学習計画を立てることと、しっかりと反復学習をすることを心がけました。
(2)診断士に挑戦した理由・きっかけ
主に2つあります。
1つ目は将来のキャリアを考えてです。
通常、エンジニアとして就職しても、ある程度の年数が経てば管理職のように人をまとめるような仕事になってきます。
そういった時に中小企業診断士の資格取得をする人が多いと聞いたので、学生のうちに取ってしまおうと思いました。
どうせやるなら早いうちにと。
2つ目は私の家系にあります。
私は100年ほど続く中小企業の社長の次男として生まれました。
生まれる前は相当に景気が良かったそうですが、近年は非常に厳しい状況です。
私は会社を継ぎませんが、この会社のおかげで私は食べ物に困らずにこれまで生きてくることができました。
診断士を取得し何か恩返しがしたいと思った次第です。
(3)学習開始時の知識・保有資格、得意科目・不得意科目
保有資格:日商簿記2級 簿記以外の知識はありませんでした。
不得意科目:経営法務など暗記系全般
(4)学習スタイルとそのメリット・デメリット
・1次試験:通信教育「診断士ゼミナール」
・2次試験:独学「TBC+ふぞそい」
①メリット
お金が本当に無かったので、予備校という選択肢は無し。
参考書学習よりは、動画でも講義を見たいと思ったので通信教育にしました。
②デメリット
勉強仲間ができず、困った時に相談する相手がいないこと。
→一発合格道場の記事で勉強方法などの疑問はほとんど解決できました。
(5)合格までの受験回数、学習時間
1次学習時間:800h
2次学習時間:250h
(6)合格までの学習法
①1次
診断士ゼミナールの講義を3.13倍速(聞こえるギリギリの速さ)で試聴し、過去問をH19からH31を4周以上しました。
間違えた問題をルーズリーフにまとめて、毎日見返すようにしました。
なお、苦手だった経営法務や中小企業経営政策はYouTubeの講義動画を電車などの移動中にずっと見ていました。
YouTubeに多くの講義動画があって、本当に環境に恵まれていると思いました。使わない手はないです。
どんな科目であっても、インターネット上には綺麗にまとめてあるサイトがあるものなので、参考書の解説がわかりにくかったらすぐに検索するのがオススメです。
②2次筆記
7月の1次試験後から8月末までは、大学院入試のため、ほとんど学習ができていません。
さらに恥ずかしながら、ペンの握り方から勉強しました。
これまで2次試験ほど文字を書く試験は経験したことが無く、模範解答を写していると手が痛くなったため正しいペンの持ち方を調べました。(本番には字の綺麗さが間に合わず、非常に汚い字で提出することになってしまいましたが。)
2次は診断士ゼミナールの講義では力がつかないと判断したため、早い段階でTBC(早稲田出版)の速修2次テキストを購入しました。
その後、ふぞろいの10年と答案分析5で合計12年分を2周しました。
私は、多色マーカー無しで解答を作成していました。
正直に言うと、短期間でマーカーを使った方法を取得できないと諦めていたからです。
シャーペンだけだと、条件の見逃しが発生しやすそうですが、マーカーだと持ち換え時間と、マーカーを塗ることに意識がいってしまいそうなので、どちらも一長一短だと思っています。
私の場合は、高校生時代の現代文を思い出して、与件文には直線と波線とキーワードに丸をつけることで強弱をつけました。
その他、SWOTと時系列に関しては与件文の横に簡単に書いていました。
それくらいで十分だったように思います。
与件文の重要な箇所と、知識を組み合わせて解答作成するため、与件文のかなり細かいところまでは拾わなくても良いのでは無いかと個人的には思っています。
③再現答案の作成有無
ブログにて公開しています。
https://kononori.hatenablog.com/entry/2020/10/25/224220
(7)学習時・受験時のエピソード及びこれから合格を目指す方へのアドバイス
資格に向けて勉強しながら、ブログ、twitter、インスタを新たに始めて勉強中の記録を残すようにしました。
診断士取得を頑張っている人のブログを参考にしたこともあったので、自分も残しておこうと思いました。
また、iPhoneのカメラのタイムラプス機能を使って勉強の様子を撮ってインスタに毎日載せるようにしていました。
勉強に関する悩み事は、その時が過ぎれば忘れてしまうので随時記録しておくといいと思います。
独学だろうが、大学生だろうが努力さえすれば合格することができます。
診断士の勉強が楽しかったこと。
日頃の生活であっても、少し違う視点で物事を捉えられるようになったこと。
これだけで挑戦した甲斐はありました。
今後の就職活動などで資格が役に立ってくれるかは不明ですが、大学生で診断士を目指しても良いっていうことは伝えておきます。
面白かったです。
いかがでしたでしょうか。
さわやかな読後感……朝から清々しい気持ちになったのは私だけではないはず。
ブログやYoutubeでの情報収集、日々の勉強の記録をSNSに投稿など、大学生ならではのITを駆使したスタイルが伺えます。
一方で、勉強への取り組み方は良い意味で地道で、反復学習の大切さを再認識させてくれます。
のりおさん、合格おめでとうございます!
診断士活動に大学院進学に就職活動と、可能性だらけですね。ご活躍ください!!!
以上、かーなでした。