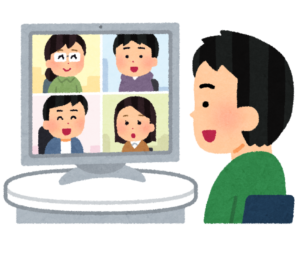【診断士2次試験】伝わる答案へ|コミュニケーションを意識する~後編~

皆さまこんにちは。ぴ。です。過去記事はコチラ。
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
私の前回記事では、2次試験におけるコミュニケーションシリーズの前編として以下の内容をお話しました。
![]() 普段の生活からコミュニケーションスキルを意識する
普段の生活からコミュニケーションスキルを意識する
![]() 設問の要求に過不足なく答えるための準備をする
設問の要求に過不足なく答えるための準備をする
前編では、2次試験で戦うための武器を身に着け、出題者の要求を理解するまでの内容でした。
後編の今回は、いよいよ出題者に伝わる解答方法と確認方法のお話です。
では、さっそく本日の記事をスタートします。宜しくお願いします。
contents
出題者の言葉を使う。
■出題者と話す時は、出題者の言葉を使え
皆さまは、解答に難しい言葉を使ってしまうクセはありませんか?
私はこのクセが最後まで抜けませんでした・・・。多年度生あるあるの「こじらせる」の特徴の一つかもしれません。
例えば、与件の言葉を深読みして一次知識のキーワードに言い換えたり、自分が普段ビジネス上でよく使っている用語や英単語等を使ってしまうなどです。予備校の講師からは「与件が使えてません」とか「唐突な印象です」などの表現で指摘されていました。
自分でも悪いクセと認識していたのですが、いざ演習になると突如閃いたかのように難しい言葉を書いてしまうのです・・・。
悪魔の囁き:「YOU、その思いついた言葉カッコイイから使っちゃいなよ」
天使の忠告:「ぴ。よ・・・難しいことは考えずいつも通りに書きなさい」
問題の傾向が変わっていたり、緊張や焦りがあると、普段通りにできず、雑念が入ってしまうのです・・・。
結果、与件の言葉を使っているつもりでも、採点する側は違う意味として受け取られるため、点数に繋がらないことが多かったです。
また、試験の出題者はその道の学者先生です。知識的にズレた言葉や知らない言葉が書いてある場合、出題者は気分を害するかもしれませんし、最悪読んでもらえないかもしれません。
ここで、前回に続きピーター・ドラッカーの名言をご紹介します。
(哲学者ソクラテス氏はかなりの頑固者であったとのウワサ。)
2次試験においては、「大工の言葉」は「出題者の言葉」と捉えることができます。
難しい言葉などを無理に使おうとせず、設問文や与件文の言葉を素直に書くことで出題者と円滑なコミュニケーションを図れます。
以下に、2次試験でよく使う2つの因果解答パターンで考えてみます。※(例)は令和1年事例Ⅰを題材にしています。
![]() 与件の言葉(因)のため、一次知識の言葉(果)となった。
与件の言葉(因)のため、一次知識の言葉(果)となった。
(例)コストカットした部分を成果に応じて支払う賞与にしたため、社員のモラールが向上した。
![]() 一次知識の言葉(因)のため、与件の言葉(果)となった。
一次知識の言葉(因)のため、与件の言葉(果)となった。
(例)顧客視点に立って潜在ニーズを引き出したため、これまでアプローチできなかったさまざまな市場との結びつきもできた。
与件の言葉はそのままの言葉で記述するほうが安全です。しかし、制限字数の中で解答をまとめるためには与件の言葉を省略することも必要です。なぜなら、そのまま与件の抜き出しだと字数が多くなってしまい多面的に複数の視点で解答することが難しいためです。
よって、与件の言葉の意味を保ったまま省略して記述する練習をしておきましょう。
(例)これまでアプローチできなかったさまざまな市場との結びつきもできた。→ アプローチできずにいた様々な市場と結びつけた。
■私の失敗例②
ここで、私の失敗例②をご紹介します。与件の言葉を素直に使えず、知識的にもズレた解答をしてしまったケースです。
※まだ令和1年度の事例Ⅰに取り組んでいないかたは、ぜひご自身で一度問題を解いた後でお読みください。
例えば、R1事例Ⅰの第1問。
✖ぴ。の再現答案(悪い例)
「YOU、最大なんだからカッコよく、つまり〇〇、と結論先出しで書いちゃいなよ」と悪魔の囁きが・・・。そして、精神的な動揺から思考が停止し、「競争劣位」という唐突で、知識的にもズレた回答になってしまいました。事例Ⅰの第1問。緊張で頭がパニックになっている中、私の知識の曖昧さを見透かされているようです。
冷静に正しい知識で設問要求を確認することができれば、「ビジネスとして成功しなかった」とあるため、収益面に問題があったのでは?と想定した状態で与件文を読みにいけたハズです。
また、最大の「理由」は何か。と問われているのにもかかわらず、最大の「要因」と書き出しています。減点されたかは分かりませんが、印象は悪いですね・・・。
与件文の4段落目に以下の記述があります。
出題者の言葉としては、売上減少と費用増大という二重苦を生み出したと言っています。また、下線の箇所にように設問文とほぼ同じ言葉がこの4段落にまとまって記載されています。この設問で合格点(6割)を確保するためには、この売上減少と費用増大という言葉を素直に結論として使い、売上減少と費用増大の両面から具体的な理由の記述をする必要があったと思います。
仮に、つまり〇〇と結論のキーワードにする場合は、「収益低下」とすると売上減少と費用増大を端的に表現でき、出題者に伝わったのではないかと思います。出題者が期待する語彙と合致していれば高得点が見込めますが、短時間で書くことは難しいですね。
私は2次の学習期間が長くなったせいか与件の言葉をそのまま使うことに拒否反応みたいなものがありました。もっと別の表現のほうが良いのではないか?など、ややもすれば明後日の方向にいってしまいがちです。ですが、そこはグッと堪えて難しく考えず自信を持って素直に与件の言葉を使うことが大事になります。
◎3chの再現答案(良い例)
出題者の言葉通り、売上低下と費用増加の両面から、それぞれの理由を与件から抜き出し、因果関係で繋いでいます。とっても分かりやすく、見栄えが良い解答ですね。
正確に伝わっているかを確認する。
最後は、自身の回答が受け手に正確に伝わっているかの確認方法のお話です。
自分の回答に対し、自己評価だけでは正確に受け手に伝わっているかを確認することは難しいです。
設問要求に正しく答えているか?
正しい一次知識を使えているか?
自分の悪いクセは出ていないか?
与件の言葉を省略したけど意味が保たれているか?
など、他にも確認すべきことがあると思います。例えば、ふぞろい等の再現答案や予備校等の模範解答で自己採点した場合、上記の設問要求と一次知識は確認できますが、自分のクセ等は確認できません。
そのため、他者のフィードバックが必要です。予備校を受講されているかたは講師等からフィードバックがあると思いますが、独学のかたはそのような機会はなかなかないですよね。
そのような場合は、勉強会をおススメします。今はオンラインの勉強会を開催している支援団体やコミュニティ等がありますので、地理的・時間的制約などの負担が少なく参加できると思います。
オンライン勉強会の情報は、いけちゃんの記事がおススメです。
私からは、勉強会に取り組む上で意識したい2つのことを以下にご紹介します。
■アサーションによる勉強会
一つ目は、「アサーション・コミュニケーション」を意識して取り組むことをおススメします。(参考:カオナビ人事用語集)
アサーションとは、相手を尊重しながらも自己主張をしっかり行うコミュニケーション方法です。
自己主張のタイプは主に以下の3類型があります。
![]() アグレッシブ(攻撃的):ジャイアンタイプ
アグレッシブ(攻撃的):ジャイアンタイプ
![]() ノン・アサーティブ(非主張タイプ):のび太君タイプ
ノン・アサーティブ(非主張タイプ):のび太君タイプ
![]() アサーティブ(バランス型):しずかちゃんタイプ
アサーティブ(バランス型):しずかちゃんタイプ
この中ではアサーティブが望ましいのですが、大事なことは、自分がどのタイプなのかを理解することに加え、自分のタイプ以外の特性も理解しておくことです。
私のタイプは自己主張が控えめのノン・アサーティブと自覚していたため、勉強会では普段の倍くらいの積極性を意識して意見をするようにしていました。
受け手に正確に伝わっているか?について、自身では大丈夫と思っていても、実際には正確ではないかもしれません。それは他者から指摘を受けることで気づくことができます。また、自身のクセをより多く洗い出すには、積極的な意見交換が必要です。
勉強会の参加者がチームとなり、積極的に意見をぶつけ合うことで勉強会の効果は最大化します。参加者の良いところは参考にすると共に、自身のクセを把握し一つずつ修正していきましょう。
勉強会に関連するおススメの過去記事をご紹介します。
■ホーソン効果を味方につける
2つ目はホーソン効果です。これは人から注目や期待をされていると意欲が高まる効果で、1次試験企業経営理論のモチベーション理論の領域で過去に出題されています。
【H30年第15問】
イ:E.メイヨーとF.レスリスバーガーのホーソン実験では、従業員が自分たちの作業条件を決定することによって内発的に動機づけられていたことを発見し、これをホーソン効果と呼んだ。(×)
【H25年第16問】
オ:作業環境を経営者が改善してくれたこと自体が、研究員に対するホーソン効果を生み出したから。(×)
2つ共に不適切な選択肢です。ホーソン効果は、作業条件を変えることで生産性が高まるのではなく、人から注目や期待をされることで意欲が高まること、つまり人間関係による作用が重要だとしています。
例えば、家で閉じこもって勉強するよりも図書館やカフェなど人がいる場所のほうが勉強が捗るというかたもいらっしゃると思います。これは人に見られているという適度な緊張感が生産性を高めていると考えられます。
勉強会のデメリットとして、参加者で経験年数や習熟度に違いがあると意見交換がスムーズにいかないといったことが挙げられます。
ですが、ホーソン効果を味方につけることでデメリットをメリットに変えることもできます。
✅自身の悪いクセを持っていない人と接する
経験者が自身の悪いクセを修正しようとするとき、初学者の素直に与件から抜き出す解答に触れることで、修正への気付きを得られる効果があります。
✅自身の目標に近い人に接する
初学者が自身の目標に近い人と積極的に接することで、教えてくれる人の期待に応えたいという気持ちが生じて、意欲が高まる効果があります。
初学者も経験者も参加者の期待に応えよう!という気持ちで勉強会に取り組むことで学習の生産性が大きく向上すると思います。
後編まとめ
✅自身の回答を確認するときは、勉強会などで他者にフィードバックしてもらおう。
2次試験におけるコミュニケーションシリーズ、いかがでしたでしょうか。
文章力に自信がなくても、普段の生活の中で文章コミュニケーションを意識することで、文章力が上達するきっかけにすることができます。
また、出題者とのコミュニケーションや学習仲間とのコミュニケーションを意識することで、受け手に伝わりやすい答案を書くことができます。
もしよろしければ、ご参考にして頂けたら幸いです。
今回は以上です。いつも長い記事を読んでいただきありがとうございます。
ぴ。でした。
☆☆☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたら
![]()
にほんブログ村
↑ぜひ、クリック(投票)お願いします!↑