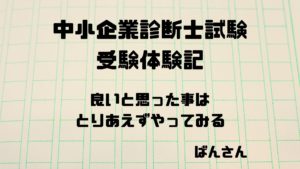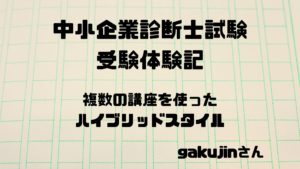【合格体験記】 ~とにかく”勉強勉強勉強勉強”!!!~ by AZUKIさん
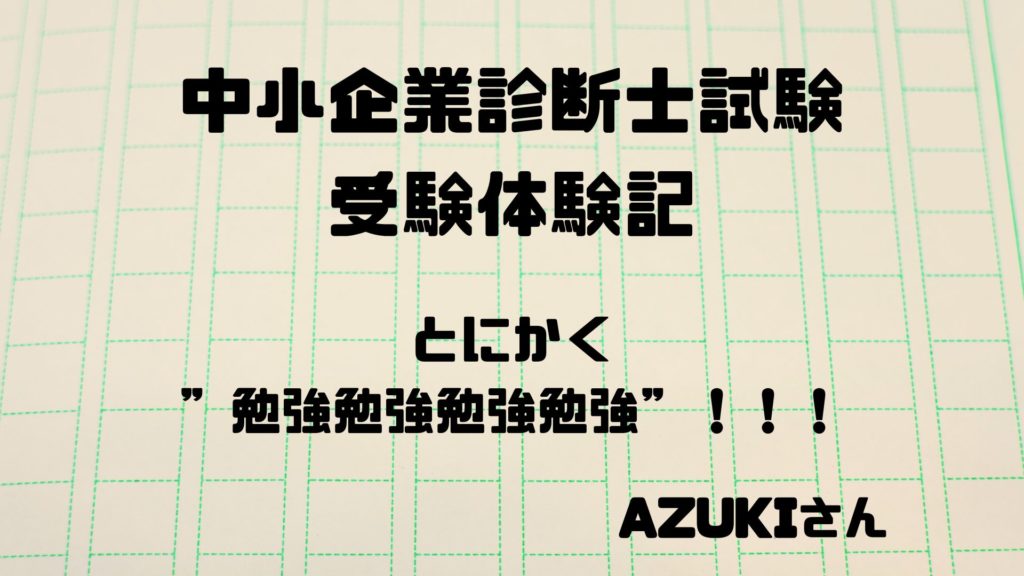
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
一発合格道場ブログを
あなたのPC・スマホの
「お気に入り」「ブックマーク」に
ご登録ください!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

こんにちは、ひろしです!
情報処理安全確保支援士を保有しているAZUKIさんの合格体験記です。情報処理の難関資格を保有していたAZUKIさんは経営のことをより深く知るために中小企業診断士に挑戦されました!
受験生情報
ハンドルネーム・年代
- HN:AZUKI
- 年代:20代
勉強スタイル
勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強
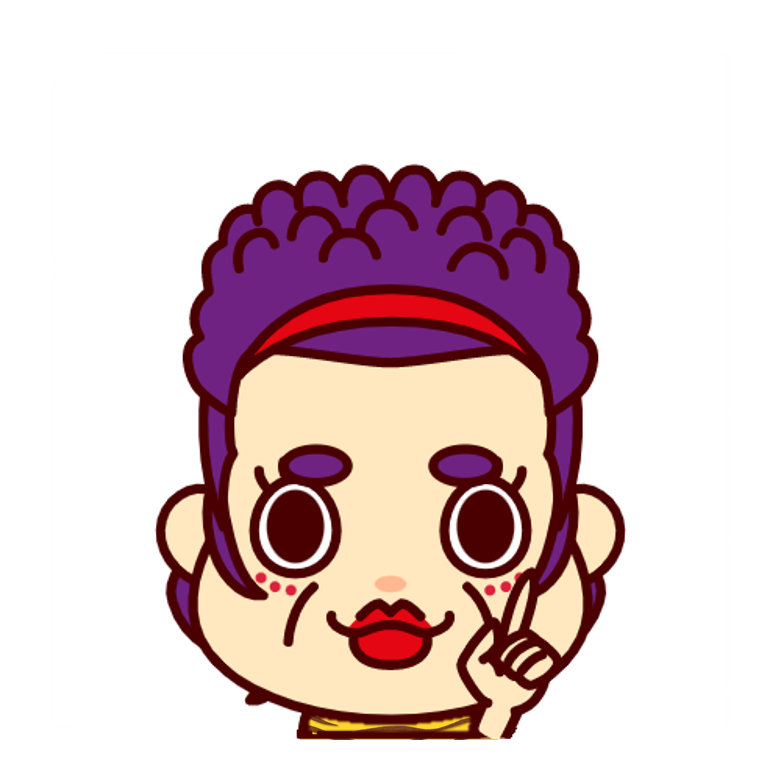
読んだ体験記の中で一番強烈なスタイルやったで
受験回数
- 1次:2回(1回目は未受験)
- 2次:2回
勉強時間
- 1次:1,100時間(簿記2・3級の取得含めて)
- 2次:400時間
学習開始時期
2021年5月~
職務経験・保有資格
職務経験:機械卸売企業のサービスエンジニア→情シス(異動)
保有資格:電気工事士2種・応用情報技術者・情報処理安全確保支援士・簿記2級
得意科目・不得意科目
【得意科目】
1次:中小以外
2次:事例Ⅰ・事例Ⅳ
【不得意科目】
1次:中小
2次:事例Ⅱ・事例Ⅲ
診断士に挑戦した理由・きっかけ
情シスとして働きはじめ数年経ったある時期、販売管理システムや会計システム更新についての打合せに同席したが、販売や財務に関する話に全くついていけず危機感を覚えました。
経営に関する知識をオールマイティに得られる資格を会社の奨励資格リストから探していたところ、中小企業診断士を発見。
前年に情報処理安全確保支援士試験に合格し、世間的にまあまあ難しい試験に合格したという勢いもあり受験を決意。(この時点ではまだ中小企業診断士試験の恐ろしさを知りませんでした・・・。)
合格までの学習法
1次試験
- 独学 (まとめシート + TACスピテキ・問題集・過去問集)
2022年初頭から100時間/月を目標とし、ひたすら演習をしました。
平日2時間、休日8時間を目安としまとめシートの演習やTACの問題集を解きました。
GWまではまとめシートやTAC問題集での演習を中心とし、GWは毎日10時間TAC過去問題集をひたすら解いていました。GWの過去問演習で大きく実力が伸びたと思います。
7月にはTACの模試を受講し、苦手論点の抽出や中小の前半(経営)部分の演習を行いました。
直前期には「不正解の選択肢はどの部分が間違っているか」で過去問をしゃぶりつくしました。この方法が追い込みにかなり役立ちました。
結果全て60点以上で危なげなく合格しました。
2次試験
- 独学(ふぞろい+事例Ⅳ全知全ノウ+TBC速修2次テキスト+TAC事例Ⅳの解き方)
1年目はふぞろいや事例Ⅳ全知全ノウ、TBC速修2次テキストの抽象化ブロックシートで過去問学習を中心に進めましたが、テクニック的な部分に走りすぎたが故に基本的な解き方が疎かだったと思います。
事例Ⅰ・Ⅳが60点以上でⅡ・Ⅲが50点代で計238点で惜敗でした。
2年目はあえて過去問を回しすぎず、2次試験に関する知識のインプットと過去問演習をバランス良く行うことで「診断士脳」を醸成しました。また事例Ⅳ対策はTAC事例Ⅳの解き方で行いました。
なぜその学習方法を選んだのか?
今まで資格を取得するのに独学で十分だったため。またネットで調べたところ独学で合格している人が多かったため。
学習時・受験時のエピソード
診断士の受験を決意して2021年5月に申し込みをし、3カ月勉強すればまあいけるだろうと思っていました。(そんなはずがないのですが、当時はまだ診断士試験の難易度を体感していませんでした。)
ネットの「1次はまとめシートだけやっとけば受かる」という書き込みを見て、とりあえずまとめシートを購入し、勉強を始めました。しかし、勉強を始めると6科目(情報は免除)を1周するのに2カ月かかったうえに、難しすぎて飛ばした論点も多々あるという有様でした。
到底合格は不可能と判断し、人生で初めて資格試験をサボりました。
特に財務会計が殆どの論点がわからず、簿記の基礎から勉強しないと話にならないと感じ、2021年末までの半年で簿記3級・2級を取得しました。
2022年の年明けからは各予備校やブログが出している勉強時間の目安である1,000時間を目標とし、100時間/月の勉強を計画しました。平日仕事から帰ってきて2時間、休日は8時間を目安とし、まとめシートの演習やTACの問題集を解きました。診断士試験は内容が面白いので勉強を続けることは全く苦ではありませんでした。(例外で、勉強初期の法務は睡眠導入剤でした・・・。)
GWまではまとめシートやTAC問題集での演習を中心とし、GWは毎日10時間TAC過去問題集をひたすら解いていました。GWの過去問演習で大きく実力が伸びたと思います。
7月にはTACの模試を受講しました。模試結果はギリギリ不合格で本番が不安になりましたが、ここで間違った論点を徹底的に復習すれば合格ラインに達すると確信しました。また、中小の前半(経営)部分の演習ができる点も良かったです。
迎えた本試験、経済の難化や財務会計も出来が悪く感じ心が折れかけるも、他の科目の感触は良く結果的に全て60点以上で危なげなく合格していました。
1次に合格してからすぐ道場の2次セミナーに申し込みをし、セミナー前に前年の過去問を解いてみてあまりの出来の悪さにまた心が折れかけましたが、2次セミナーにて「最初はみんな全然書けない」という話を聞いて安堵しました。
ふぞろいや事例Ⅳ全知全ノウ、TBC速修2次テキストの抽象化ブロックシートで学習を進めましたが、この時点では「開眼」は出来ていなかったなと思います。テクニック的な部分に走りすぎたが故に基本的な解き方を疎かにしていました。
案の定本試験では食らいつくのが精いっぱいで、試験後一カ月は2次試験のことを思い出すだけで動悸や手の震えが止まらない状態になっていました。
迎えた合格発表日、相対試験であることや、受かった人はみんな最初は落ちたと思っていた話に一縷の望みを託しながら番号を確認しましたが、番号が無くしばらく放心状態でした。
やっぱり事例Ⅳで足切りか・・・いや事例Ⅰかも・・・と思っていましたが、結果的には事例Ⅰ・Ⅳが60点以上でⅡ・Ⅲが50点代で計238点で惜敗と、2次試験の肌感と点数の乖離を実感したと同時に、合格に近い点数を取れたことが自信に繋がりました。
2次試験は勉強時間を闇雲に増やしても点数に繋がりにくい試験だと感じたので、2023年度は8月から勉強を再開しました。あえて過去問を回しすぎず、2次試験に関する知識のインプットと過去問演習をバランス良く行うことで「診断士脳」を醸成しました。テキストもふぞろいとまとめシートに絞り、思い出せなかったりうまく書けなかった論点をまとめシートで復習しました。また事例Ⅳ対策にTAC事例Ⅳの解き方を購入しましたが、事例Ⅳに必要な知識が1ステップずつ簡単な例題を通じて習得できる良書でした。2年目の事例Ⅳはこれと過去問演習しかしませんでしたが、本番でもNPV以外は躓かずに回答できました。
とはいえ、合格の自信は全くなく来年1次試験からやり直すかどうかをずっと考えていました。
しかし結果は合格で本当に得体の知れない試験だと改めて感じました。
自分は高専出身で、「文系」の勉強をあまりしてきませんでした。
しかし、診断士試験を通じて経済学や会計学、法務など社会人として必須のスキルを身に着けることができたので、「理系」の方にこそ挑戦してほしい資格だと思います。(あまり文系や理系で括るのは好きではないのですが、あえてこう表現させてもらいます。)
診断士試験に簿記2級の取得は必要かという話をたまに見ますが、1次試験でも簿記2級を持っていればすぐ解けるような問題が出たり、2次試験も簿記の考え方が土台となりCVP分析やNPV算出の理解に役立ったので、自分は取得した方が良いと感じました。
それとamazon kindleで「ドラゴン桜2」のドラマ化記念の試し読みが配信されているのですが、受験の心構えや現代文を解く際のテクニックなど診断士試験にも利用できる要素が多かったので、試し読み部分だけでもオススメです。
おわりに
情報処理安全確保支援士のネクストステップとして中小企業診断士に挑戦されたAZUKIさん。
知識のインプットと過去問演習のバランスを考慮して2次試験の勉強を進め、「診断士脳」を作られました。インプット・アウトプットのバランスは実務を行う上でも非常に重要です。
AZUKIさんがこれから中小企業診断士としてご活躍することを願っております!!!
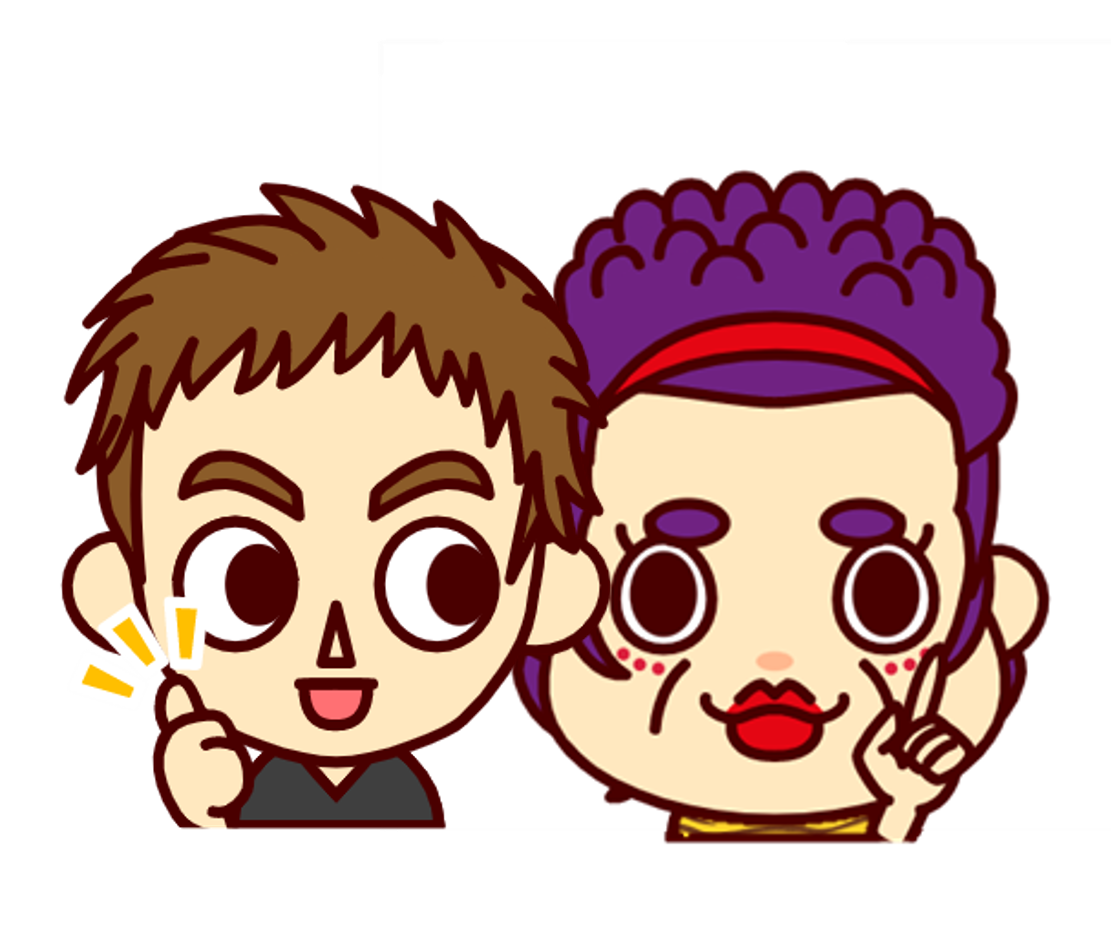
合格おめでとうございます!!
☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)