【合格体験記】田中貴金属方式のコツコツスタイルで見事合格!TKさん
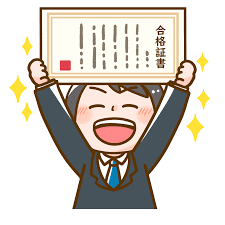
どうも、Tomatsuです。
本日の2本目はTKさんです。 TKさんは勉強習慣と勝ち癖をつけるために中小企業診断士受験の1年前から関連資格を7つも取得され、まさにコツコツスタイルで受験対策に取り組まれておりました。
2年間で勉強しなかった日は4日のみ、とイチローばりのストイックさで合格を勝ち取りました。それでは、どうぞ!
========ここから========
(0)受験生情報
HN:TK・年齢:35歳
(1)自分の診断士受験スタイルを一言で表すと
田中貴金属方式(とにかく継続してコツコツ取り組むスタイル)
(2)診断士に挑戦した理由・きっかけ
- 自分の知識不足を感じ、体系的な知識を得たいと感じたこと
- 公的な資格等で人を判断・評価をする人は今も変わらず多いと感じ、経営に関する
- 国家資格を保有する事自体にメリットがあると感じたから
- 上記他、怒り等の負の感情も挑戦の一因としてあります…
(3)学習開始時の知識・保有資格、得意科目・不得意科目
- 管理職を通じて得た拙い経営知識と経験
- FP2級
- 簿記2級
- リテールマーケティング2級
- ビジネス実務法務2級
- ビジネスマネージャー
- ビジネス会計2級
- ITパスポート
※勉強習慣と勝ち癖をつける為に診断士受験の1年前にリテールマーケティング2-3級、ビジネス実務法務2-3級、ビジネスマネージャー、ビジネス会計2-3級、ITパスポートの7つを取得
(4)学習スタイルとそのメリット・デメリット
一次・二次ともに独学
- メリット:気楽、自分のペースで進められる
- デメリット:わからないことがあった時に聞く人がいない為、質問が出来ず、調べるのに時間がかかること
(5)合格までの受験回数、学習時間とその作り方
(a) 合格までの受験回数
- 一次試験:1回
- 二次試験:1回
(b) 学習時間
- 1次試験総学習時間1,304時間
- 2時試験総学習時間622時間(筆記試験:590時間、口述試験:32時間)
(c) その作り方
・自分の為の時間を削る
受験期間はとにかく自分の為の時間を削り、例えば、飲み会をなくしたり、ダラダラとテレビを見たり、携帯をいじることをやめました。
診断士の勉強期間は1年間で、診断士の勉強の準備期間として関連資格の勉強を1年間していましたが、2年間で全く勉強しなかった日は4日のみです。
この4日は友人との夏冬の旅行で、気分転換にもなり、これがなかったらモチベーションの維持は中々に難しかったと思います。
なお、自分の時間はなくしましたが、家族との時間は削りませんでした。
これは自分の中での決め事だったのですが、家族との時間を犠牲にすることなく、診断士受験の合格を目指すと初めから決めていたからです。
具体的には当時0歳と2歳の子供(現在1歳と3歳)がいたので、平日は寝かしつけまでは勉強せず、土日も近場ですが家族で出かけたり、子供たちと遊んだりすることを優先し、診断士の勉強で迷惑や悲しい思いをさせないようにしていました。
また、ほぼ毎日のように子供たちが夜泣きをしていましたが、妻も一日子供たちの世話をして疲れていたので、基本的に私が勉強を中断して世話をしていましたね…(時間を測って過去問やっている時にこれは中々にしんどかったです…でも本番中のイレギュラーと前向きに考え、寝かしつけていました笑)
・通勤時間・休憩時間・隙間時間をフル活用
コロナの影響で4月からはほぼ自宅勤務でしたが、通勤している時はその時間を勉強にあて、通勤がなくなった時には朝の準備もいくらか短縮されたので、その時間含め勉強に充てていました。
また、会社の人には診断士を受けることを言っていなかったこともあり、出勤時の昼休憩時(1時間)は昼食をさっと食べ、残った時間は公園のベンチか駅のベンチで40-45分を勉強していました。
それは余談ですが、おかずがあると食べるのが手間だったので、勉強しながら食べられるように約2年間はおにぎり2個だけを食べ続けていました。
あとは5分でも隙間時間が生じたらすぐに勉強できるように参考書は常に持ち歩いていました。
(6)合格までの学習法
(a) 一次試験
使った教材はTACの「スピードテキスト」と「スピード問題集」、「集中特訓財務会計」、同友館の「過去問完全マスター」(中小企業経営・政策以外)、TBC「特訓問題集 中小企業経営・政策」2種です。
これらの教材を3回転させ、試験直前は過去問完全マスターを中心に取り組んでいました。
なお、中小企業経営・政策はスピ問とTBCを使用していました。
(b) 二次試験
使った教材は同友館の「ふぞろいな合格答案13」、「ふぞろいな答案分析1-5」、「全知識」、「全ノウハウ」、「事例Ⅳの全知識&全ノウハウ」、「30日完成!事例Ⅳ合格点突破計算問題集」で、全知識と全ノウハウは1回熟読した後はわからないことがあった際に調べるのに使った程度です。
それ以外の教材に関して、事例Ⅰ~Ⅲに関しては過去問をベースにふぞろいで採点し、事例Ⅳは参考書単体で4回転、別途過去問を解いてしました。
最終的に説いた事例は事例Ⅰ~Ⅲが77事例で「7年分×3回(直近4年は4回)+苦手事例2事例」、事例Ⅳが52事例で「13年分×4回」です。
なお、ふぞろいな答案分析1と2は設問形式のチェックと解答の方向性確認として使用し、「6年分×2回」で36事例分チェックをしました。
私の場合、ふぞろいはあくまでも自己採点の目安として活用していましたが、ふぞろいを教材として使う場合はその「活用方法」が重要であり、長くなってしまうので詳述は避けますが、口述試験の想定問題等を併せて活用すると良いと存じます。
※一次から口述試験を通して、模試やセミナー等には一切参加しない完全独学型、セルフ模試等も一切やらずのぶっつけ本番タイプでしたが、自分に合った勉強方法の確立と情報収集、そして本番のイメージさえできていれば結果論ですが、なんとかなります。
(7)学習時・受験時のエピソード及びこれから合格を目指す方へのアドバイス
偉そうなことを言う気は更々ありませんが、診断士の挑戦理由だけは明確にしておくのが良いかと存じます。
診断士試験は大変で何度か心が折れそうな場面があるかもしれませんが、そんな時に挑戦理由が強固であれば必ず踏ん張れることができますし、モチベーションを維持する上でも必ず役立ちます。
まだまだコロナの影響で異常な環境が続きますが、体調にはくれぐれもお気を付けいただき、勉強を継続して頑張ってください!
いかがでしたでしょうか。
TKさんもSakuさん同様子育て世代ということで、中々ご自身でコントロールできることが少ない難しい状況での勉強を強いられておりました。
しかし、お子様が夜泣きされた際にも「本番中のイレギュラー」とポジティブに捉えられるメンタリティと田中貴金属方式のコツコツスタイルで無事合格を勝ち取られました。
それにしても、ご家族との時間は犠牲にしないという受験に対するご姿勢や、二年間の中で勉強しなかった日は4日間というストイックさには頭があがりません…orz
改めましてTKさん、合格おめでとうございます!ご寄稿どうもありがとうございました。
中小企業診断士としての今後のご活躍をお祈り申し上げます!
以上、Tomatsuでした。
