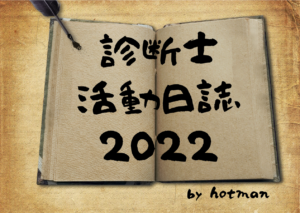二次試験不合格者(リット)の1年 byリット

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はじめに

さて、リレーブログも終わり本日から道場は通常モードです。
本日は一つ、読み物的なものをお届けできればと!
僕が二次試験に失敗してからの1年間です!
ポジティブな感じの昨日のあらきちからの落差が…💦
という訳で、今日はリットの1年間をダイジェストでお届けするよ!
受験ノウハウではないので、息抜きがてら読んでみてねー!
※少しでも雰囲気を軽くするため、ジョジョ画像多めでお送り致します

僕は二次試験はほとんど独学(事例Ⅳのみ診断士ゼミナール教材を使用)なので、落ちてからの1年はめちゃくちゃ紆余曲折がありました。
通学や勉強会仲間が居ると違ったんだろうなと思うのですが、独学の場合は二次試験後の過ごし方で迷う方もいるのではないかなと。
飲み物片手に気軽に読んでいただけると幸いです。
それでは、はじまり、はじまりー!
令和2年度 二次試験編

今回のストーリーは、僕が落ちた試験日からスタートします。
思い出しただけで胃がチクチクしてきた…
絶望の事例Ⅳ(令和2年度)
まずは二次筆記本番、つまり試験日ですね。
当時怖いもの知らずだった僕は、模試どころかセルフ模試すらしておらず、さらに80分通して事例を解いたことが無いという奇行種でした。
それでも事例Ⅰ~Ⅲまでは結構解答を埋めることは出来たんですよ。
システムエンジニア出身で、情報処理試験など試験慣れしてたのが大きいと思います。
で、どうにもならなかったのは事例Ⅳ…
これはもう無理ゲーでした。
時間もないしNPVやたら難しいし。
もう完全にこれ。

最初の経営分析と最後の文章問題(通称ポエム問題)を埋めて、あとはもう何を書いたかすら記憶に無いほどの大惨敗でした。
もうどう考えても落ちたと思ったので、帰りの電車では本もスマホも何もかも見るのすら嫌になってしまいました。
当然、自己採点すらしていません。
そうだ、本を読もう!(現実逃避)

それでも1週間もすれば少しは立ち直り、このままじゃいかんなーと。
でも、診断士の勉強はやる気がしなかったんですよね。
勉強部屋に入ることすらしなかったもんね。
気持ちは分かるけど。

そこで選んだのが趣味でもある読書でした。
診断士界隈でお薦めされている本を片っ端から読んでやろうと。
そしてAmazonポチポチ&図書館通いが始まります。
こちらは事例Ⅱの作問を担当されている(と噂されている)岩崎先生の良書です。
合格後に初めて岩崎先生のオンラインセミナーに参加しましたが、説明が簡潔ですごく分かりやすい。
この書籍もビジネス書としては異例なほど読みやすく、スッと頭に入ってきます。
製造業の立て直しを描いた小説ですが、ボトルネックなど事例Ⅲの重要用語がポンポン出てきて勉強にもなります。
道場13代目でも良く紹介されていますね。ちなみに、コミック版もありますよ。
読書期間は簿記の勉強を始める直前まで、2~3ヶ月くらい続きました。
この期間に読んだ本は30冊は超えているはずです。
またお薦め書籍も別の機会にご紹介できればいいなと思います。
二次試験(筆記)結果発表! [令和2年12月11日]

やってきました運命の日!
なんだかんだでドキドキです!
あんだけ「落ちてる」「落ちた」「無理」って言ってたのに…
少しは期待してたんだね…


ワンチャンあるかもしれないじゃん!
やっぱりさ、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけは期待するやん?
でもシラフでは怖くてとても見れないため、ちょっとだけお酒🍺で勢いを付けます。

落ちてました!
令和3年度 二次試験編

ここからはホントにきつかった。
難関資格だから落ちる人の方が当然多いんだけどね。
立ち直るまでの時間はひとそれぞれ。
諦めなければ負けじゃないよ。

やる気が出ない期 [~令和3年1月]
さて、やる気が全く出ません。
これは困った。
こんなこと言うと荒れそうですが、これまで資格試験に落ちたことが無かったんです。
難関試験には挑戦してないというのが大きな理由なのですが。
所持資格は、情報処理系を中心に大小20は超えていると思います。
で、なんか謎の自信があったんですよね。
「自分、資格試験に強いんで」みたいな。
今となっては顔から火が吹く思いです。
こういうの言っていいのは某13代目の🐻くらいのもんです。
それはされておき、試験に落ちたショックで、せっかくの年末年始、気もそぞろ。
読書はそこそこ続けるものの、あまり頭には入っていなかった様に思います。
そうだ、簿記を受けよう! [~令和3年3月]
このままじゃいかんなーと思い、ふと思いついたのが簿記!
この時、すでに日商簿記3級は既に持っていました。
でも、日商簿記2級を勉強すれば事例Ⅳの対策になるんじゃね?と唐突に思いついたのです。
令和3年度の二次も失敗したら次は一次からになるし、一次の財務対策にもなるかなと。
思いつきの割に、良い案に見えました。
一気に勉強道具を揃えて体制を整えます。

診断士の試験対策で簿記を勉強することに対しては賛否両論あると思います。
ただ、原価計算系で試験範囲が被っていたり、電卓慣れができるのでメリットは結構あるのかなと。
ストレートだと時間が無くてとても簿記まで手が回らないかなって思う。
多年度の場合は気分転換と財務分野の基礎の確認にも良いんじゃないかな?

そして約2か月の勉強の後、令和3年3月6日、日商簿記2級に無事合格します(試験日を選べるCBT方式を選択)。
簿記試験に合格できたことで少し自信を取り戻します。
そろそろ診断士試験勉強に戻ろう! [~令和3年5月]
この時点で既に3月を過ぎており、いい加減、診断士の試験に戻るべき時がやってきました。
目に見えない場所に封印していたふぞろい達を引っ張り出し、覚悟を決めます。

これまでの遅れを取り戻すべく、ふぞろい片手に過去問を回し始めます。
事例Ⅳ対策として「意思決定会計講義(イケカコ)」も導入しました。
イケカコは、簿記2級持ってるから大丈夫じゃね?くらいの軽い気持ちでやりましたが甘かったです(笑)
めっちゃ難しかったです。
ただ、事例Ⅳの難しめの過去問を解いていても「イケカコの問題よりマシ」と思えたので心に余裕はできたと思います。
保険受験するか日和る [~令和3年7月]
そんなこんなで診断士の試験勉強に戻った僕ですが、もう一つの決断を迫られます。
そう、一次試験の保険受験をするかどうか。
保険受験については、まよのこちらの記事をご確認ください。
賛否両論のこの保険受験。
迷いまくり、一発合格道場の先代へも質問をしつつ、最終的には保険受験なしで決定!
退路を断ちました。
決め手は2つです。
「一次試験は一度突破しているのでもう一回受けてもいけそう」
「勉強時間という限られたリソースを二次に集中した方が勝算があるのではないか」
結果論になりますが、これが正解でした。
二次のみに集中したことで余裕が生まれ、解答の見直しや解法の練り直しにも時間を掛けることができました。
もくもく期 [~二次筆記本番]
ここからはブレず、迷わず突き進みました。
二回目の二次試験では、事例Ⅰ~Ⅲだけでも3事例×12年分×平均3周=のべ108事例を解きました。
これは、多年度生の中でも比較的多い方ではないかと思います。
体調管理にも気を遣いつつ、試験本番までを駆け抜けます!
二次筆記試験本番
やってきました、二回目の二次試験です。
前回の令和2年の事例Ⅳ、NPVが異様に難しかったので今年はさすがに易化するだろうと読んでいました。
事例Ⅰ~Ⅲまで、残り時間と戦いながら解答のマスを埋めてきます。
そしてやってきた事例Ⅳ!
全くわからん…

当時、素数は本当に数えていました(笑)
二年連続で難問が来るとは…取換投資とか得点取れる気がしないです。
でも、そこは流石に二回目の経験が活きました。
最初の経営分析と最後の文章問題をまず埋め、残りの時間で部分点に全集中します。
綺麗に解く気など毛先ほどもありません。必要なのは部分点!
なんとか事例Ⅳも全滅だけは回避できたかに見えました。
ただ、自己採点では30点~40点…
やり切った感に包まれつつ、戦いを終えました。
ちなみに、事例Ⅳで50点無さそうだったので、今年もダメか…と凹みつつ、帰りの電車では一次の勉強を始めていました。
立ち直りは早くなりましたね(笑)
結局、事例Ⅳは得点開示で67点だったので、部分点作戦が利いたのと、相対評価なので下駄を履かせてもらったのかなと思っています。
ホントに手ごたえと点数が一致しませんね…
この後も、合格発表(筆記)で変なテンションになったり、「口述って何?」状態から慌てて準備したりと色々ありました。
口述試験については別の記事でまたご紹介できればと思います。
さいごに

いかがだったでしょうか?
多年度生の一人として、「落ちてから1年をどう過ごしたか」をお届けしました。
たまにはこんな記事もアリかなって。
人によって過ごし方は様々だよね。
「こんな人もいたんだな」くらいに思ってもらえたら嬉しいな。
さてさて、次回は🔥hotman🔥だよ!

☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)